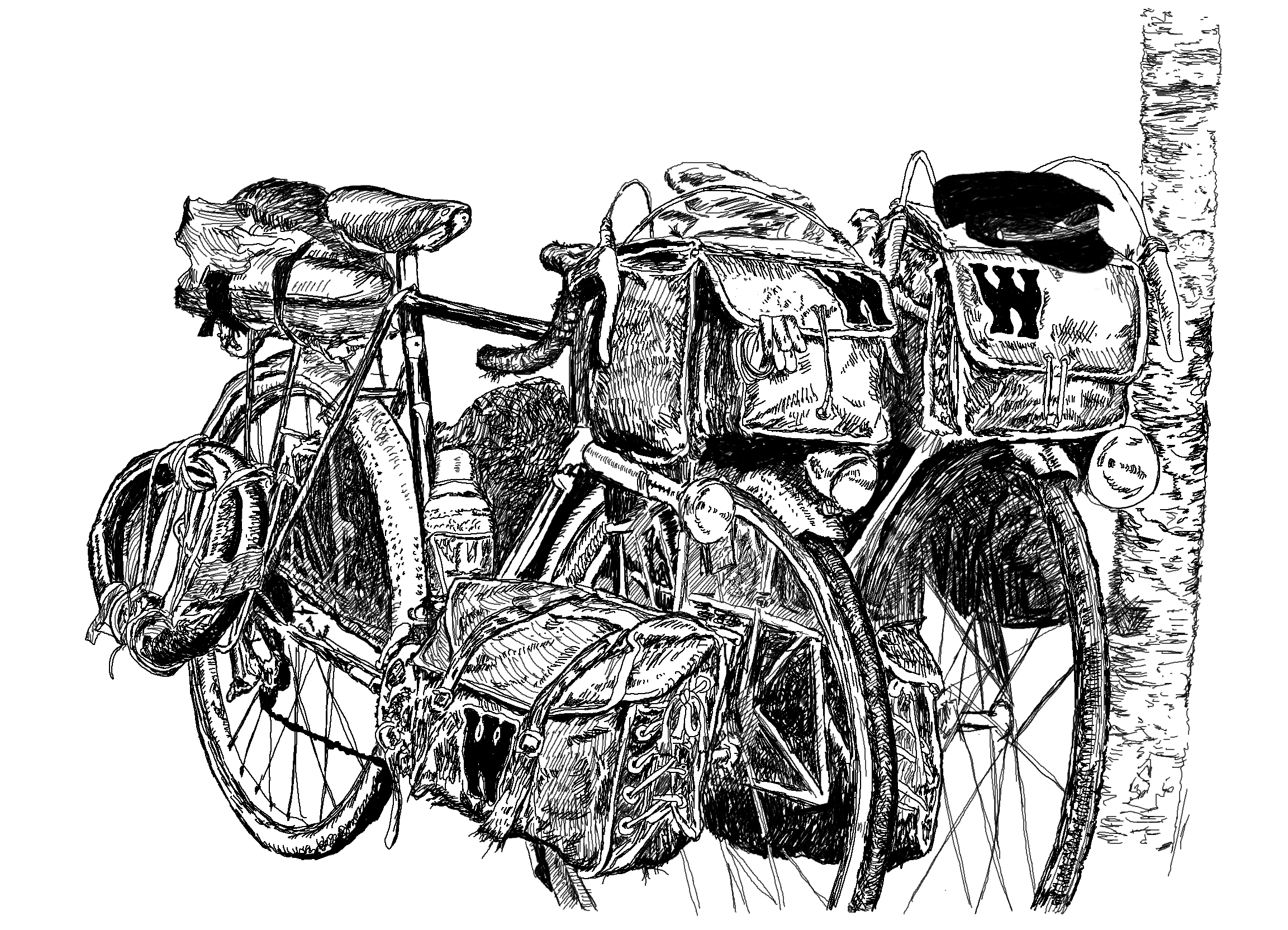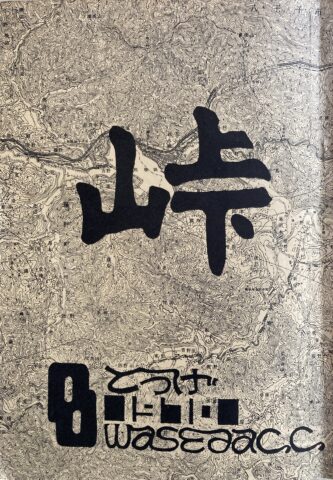
- 峠の詩
- クラブ活動における人間関係 – 上田会長
- 夏合宿A班 – 政経学部3年 宮崎
- 夏合宿B班 – 教育学部2年 丸山
- 主将としてのこの1年 – 法学部3年保泉
- 奥武蔵グリーンラインラン – 政経学部1年 梅本
- 早慶親睦ラン – 法学部1年 内田
- 第3回東京-軽井沢タイムトライアル – 政経学部1年 安田
- 第7回早同交歓会 – 商学部1年 陶山
- 同早交歓会に寄せて – 同志社大学2年 玉置
- 1970年度資料局の1年 – 政経学部3年 宮崎
- 机上的産物 – 叛乱としての異常性への飛翔 – 政経学部2年 関口
- 悲しみとは何か – 法学部3年 吉田
- 東京より木曽路を経て九州へ – 政経学部1年 平川
- 輪廻 – 法学部4年 篠原
- 眩暈(めまい) – 理工学部4年 木村
- 閉塞空間 – 法学部3年 吉田
- 70年夏の思い出 – 四国 – 商学部3年 中山
- 編集雑感 – 中山
- Editor’s Note
峠の詩
峠の詩
若者が1人峠を目指してゆく
その後に1人又1人
黒い瞳に輝く太陽
若者達が峠を目指してゆく
若者が1人峠の上に立つ
その後に1人又1人
顔は汚れて汗だらけ
若者達が峠の上に立つ
若者が1人峠をおりてゆく
その後に1人又1人
髪をなびかせ得いげに
若者達が峠をおりてゆく
クラブ活動における人間関係 – 上田会長
クラブ活動における人間関係
体育局助教授 上田会長
必要があって、クラブ活動の功罪について調査してみた。クラブ活動の積極的な効果として最も多くの人があげたのは、人間関係である。これはともすれば、現代社会が人間を個々に分離してしまうのを防いで、精神的な交流を可能にしてくれるものである。人間は元来、複数で生活するものであるから、自分が心から語り合える相手を探し得た時のよろこびはこの上もない。
しかし、1部のスポーツクラブにありがちな、上からの規制の強い人間関係には反発する人が多いようだ。クラブが自由意志によって結びあっている目的集団であれば、その構成員は、平等な立場に立って、人間として尊重されなければならない。
サイクリングクラブも、命令や強制によるのではなく、自律性をもつ個人個人の協力によって、なお一層発展することを願ってやまない。
夏合宿A班 – 政経学部3年 宮崎
夏合宿A班
政経学部3年 宮崎
8月13日(木)晴 14:00松江駅集合
合宿初日の朝が素晴しい青空とともにやってきた。(それは余りにも皮肉なオープニングであった)ここ松江青年の家には既に昨夜のうちに9人の部員が揃っていた。きょうも松江の駅には、部員が思い思いの格好で集まってくる。自転車で走って来た奴、自転車、荷夜物すべて送って手ぶらでブラりとやって来た奴、かと思えば、輪行袋を肩にかけ、手にはいっぱいの荷物を抱えてヨロヨロとやって来た奴、様々である。
歩道いっぱいに工具や部品を広げ、各人、組み立てや修理に余念がない。その間にも次々と部員が到着する。『いよいよ合宿だ』という実感の湧く時である。
一時は40人を越すのではないかと思われた参加者も35人に落着いた。しかし当初の予定通り、合宿は2班に分けて行なわれることになった。この分裂合宿の是非については今後も論議を呼ぶであろうが、我々はそのための試験的試みとして2班に分けての合宿を行なうことにしたのである。
本合宿では最初から部員の、特に1年生諸君の積極的な構えが見られた。集合地まで走って来た者が多いことである。はるばる東京から走って来たバカが5人、他に郷里から走って来た者が数人、前に例を見ない数字である。なかでも1年生が多かったのは頼もしいかぎりである。
この日は市役所の早稲田の先輩の御尽力の御陰で、市内の緑山公園にテントを張ることができた。これは毎年地方へ出て思うことだがワセダマンが各地で各分野に活躍していることに驚き、また色々とお世話になり感謝に絶えない。緑山公園は市の南部にある小高い丘の上の公園であった。市街を一望のもとにとはいかなかったが、一夜の宿としては絶好である。
ミーティングを済ませて就寝、各自の胸を去来する不安と期待。わたしの胸には言い知れぬ不安のみがつのる。企画段階での不備が事故につながることがなければいいが。無事故を祈って目を閉じる。。
8月14日(金) 曇のち雨 松江 – 米子63キロ
リーダー土肥・信田
6時起床、朝食をパンで済ませ、8時過ぎA・B班共出発。合宿の1歩が踏み出された。B班は市内で左へ折れ出雲へと向かった。我がA班は島根半島目指して右折、京都での再会を期して別れたが。(明日再会しようとは果して誰が思っただろうか)
順調に走ること1時間。そこに我が班最初のトラブルが待っていた。その栄誉を担ったのは加藤君であった。パンク、それも並みたいていのものではなかった。メカプロの及川君をして、まいったとは先輩の名言。「世の中、オレの意志とは係りなく進んでいるもんだなあ」と言わしめるものであった。修理には1時間を要した。先頭とはかなり離れてしまったろう。責任を感じてか加藤君は一心にペダルを踏み続ける。
道路から見下ろした山陰の海は深い緑に澄み、海底までをもはっきりと映していた。海岸に駐車している車は殆ど兵庫、岡山ナンバーである。海を求めてここまで来るのであろう。また海岸に点在する漁村ものどかで、某部員をしてこう言わしめた。
「しなびた感じが山陰らしくていい」
1時間の遅れを取り戻すべくひたすらペダルを踏み続けた。台風9号の接近が伝えられている今日、その影響と思われる風が海から吹きつける。むかい風でペタルが重い。晴れていれば海を隔てて大山が望めるはずだが、その姿はない。それでも予定の12時には、なんとか美保関に到着。先に着いた連中は既に食堂に散っていた。
『えびすさま』を祭った美保神社の海運の守り神に合宿の無事を祈った。ここからフェリー乗場の宇井まで戻る。ところが皮肉にも風向きは変わり、またまた向い風。
宇井からフェリーで境港へ。自転車20円也。境港から米子へは弓ヶ浜に沿って真っ直ぐに延びた産業道路を走る。正面には中国地方の最高峰、出雲富士と呼ばれる大山の雄峰を仰ぎ、松林越しに日本海を見る快適な道路。そのはずであったが現実は厳しい。大山にかかる雲は嵐の近いことを告げ、風はまたまた向い風。松林は余りに長く、大山は一向に近づこうとしない。おまけに空は今にも泣きだしそうである。
先発隊のお陰で、皆生温泉に近い松林の中の絶好のキャンプ場が見つかった。皆生は歓楽街としては山陰一という。そういう温泉街が傍にあるということはいつもなら最大の関心事であるが、今は何よりも台風の進路が気になる。ともかく各自それぞれの仕事にかかり、テントが張られ、メシが炊かれてゆく。初日はカレーライスという変なしきたりがある。雨が降り出すよりはメシが炊けるのがチョット早かった。鍋を囲んで17人が座る。「モクトー」、沈黙。「ヤメー」「ワー」「イタダキマース」一瞬の喧噪の後、再び沈黙が訪れる。
その時、ポツリ、ポツリとついに来た。食器を持って走る。鍋を抱えて走る。管視員用の大テントの下へ逃げ込み、立ったままなおも箸を持つ手は休めない。雨はますます激しくなる。食器洗いは雨にまかせて就寝。テントのまわりに漏水防止の溝を掘ってテントへ入ったが、裏もりをして、しずくが顔へポタリポタリ。テントの中で雨の音を聞いているのは忙しいものである。幸い我々のテントは新しく、寝袋を少し濡らした程度ですんだが、1号テントは見るも無惨であった。真ん中で大きく裂け、中はズブ濡れ。そこで寝ていた連中は傍の公民館の物置へ避難していた。
あすは大山へ上ると言うにこれでは一体どうなるやら、どうすべきやら。
8月15日(土) 雨のち曇
雨はとうとう朝まで続いた。予定の大山アタックは明日に延期となった。地方の方の御厚意で我々は雨を避け公民館へ入ることができた。僅かの晴れ間をみつけて、昨夜の残りのカレーを温めてみんなで佗しく食った。公民館の中には重苦しい空気が漂い、絶えまない雨の音とラジオの台風情報が無情に流れている。ラジオは台風が正午にこの米子附近を通過することを告げている。
この時B班はなんとこの風雨の中、予定のコース通り走っていたのである。我々もB班のことを気にはしていた。予定のコースを1部カットしてでも、この米子まで走って来るだろうと思ってはいたが、予定通りのコースを走って来たと聞いて驚かされた。B班が到着したのは雨も上がり我々がテントを干したり、食器を洗ったりしていた時であった。わめきながら乗り込んできた。
「ナンジャイ、こんなとこで何しとるか」
「ウルヘェー」
この雨の中を走って来たという彼らに返す言葉はない、言わせておこう。しかし大山アタックを延期したのは間違ってなかったと確信する。
その夜別々に夕飯、ミーティングを済ませ、我々A班は各自テントに潜り込み、B班は公民館へと入っていった。明日は一緒に大山にアタックすることになった。特に3年生の間にはB班には負けられないという対抗意識が強いようである。明日は台風一過の晴天を望みたい。
8月16日(日) 晴時々雨 米子 – 蒜山53キロ
リーダー田中、内田
翌朝漸く見せた青空も、出発の時には隠れていた。B班はパン食で1足先に出発。30分遅れて我々はB班を追った。ところが出てすぐトラブルである。図らずもわたしが遅れる破目になった。パンクで遅れた後の班を、わたしは大山道路へ右折する交差点で待った。ところが一向に来ないのである。雨が降り出して来た。心配させやがる。戻って見に行ったものか、否もうすぐ来るだろう。もう少し待ってみよう。雨が止んでまた降りだしてまた止んだ。どの位待ったろうか。雨の中1人立っていたわたしにとってはかなりの時間に思えた。
これ以上待ってはいられない。まだ時折雨の降る中を彼らの姿を求めて引反した。案の定、彼らの姿は何処にも見られなかった。自転車のハンドルを取って返し大山目指して走った。怒りをペダルにぶちまけながら。彼らは待っていたわたしを置いて近道をしていったものと思われる。その時には雨はすっかりあがり、真夏の太陽がカンカン照り。まったくシャクな天気だ。料金所で聞いた話では、みんな通過したようである。
道路は傾斜10度前後の裾野を真っ直ぐに上っている。遅れて走るということは精神的に非常に疲れる。追いつこう、追いつこうと気ばかりあせる。おまけに道路は何の変哲もない裾野を真っ直ぐに続いているので、地図を広げても何処を走っているのかとんと見当がつかない。傾斜は次第に急になり、道路が目の前に立塞がる。車もオーバーヒートするのか、路肩でボンネットを開けて休んでいる。車は青白い排気ガスを吐出し喘ぎ喘ぎ上っている。我々はこの排気ガスをまともに吸わされる。特にこの青白い排気ガスは油臭く、ノドや鼻を刺激し、目を攻める。涙タラタラ鼻水ドバドバでの健闘である。
わたしが漸く部員を捕えたのは、大山道路の終点大山寺にもう少しという所であった。むこうから手を振ってくれ、わたしは猛然とペダルを踏んだ。自転車を捨てるように倒して彼等の横に大の字になり、暫くは苦しさに声も出なかった。番匠君が遅れ、副将の及川君が励ましながらついていたのだった。地図を広げて言った。あと1キロとはない、頑張れ。これは自分に言い聞かせていたのかもしれない。再びペダルを踏んだ。いかにも最後であるかのように急な傾斜となる。ここまで頑張ってきたんだ、ここで降りてたまるか。
大山寺まではすぐであった。暫くは飯を食う気にもなれなかった。我々が最後かと思ったがまだ堺君と奥野君が来ていなかった。奥野君が転倒してクランクを折り、取り換える為堺君がついて米子へ下ったという。今着いた3人が2人を待つことにして後はすぐに出発。彼らが行って暫く、それまで晴れていた空が俄に暗くなり霧が立込め始めた。その変わり身の早さにはただ驚くばかり。冷たい雨までが降ってきた。じっとしていると寒さがしみる夏とは思えぬ寒さである。その霧の中から2人が現われたのは3時近かった。
彼らが飯を食うや否や出発。ここで初日以来オープン参加の木村さんと別れる。3日間を我々と過ごし、特にきのうは台風の中、1日中お付合いねがった。ありがとうございました。大山環状道路がまたまたきつい。さらにわたしと奥野君のパンクでますます遅れ、御机が6時、夕闇が迫っていた。奥野君の頑張り様には感心させられる。堺君に励まされ体力の限り、気力の限り頑張っている。わたしは彼についていくのが精一杯。刻一刻暗くなる。
鏡ヶ成から蒜山道路へ入った。蒜山まで下りである。薄暗い道を猛スピードで下る。裏大山と言われるこのあたりは車々、人々の大山寺とは違い、大いなる自然を感じさせてくれる。もっとゆっくり走りたかった。出口の料金所で加藤君をみつけた時は、全身の力が抜け疲れがどっと出た。7時であった。B班はすでに食事を済ませていたが、A班の同志は我々を待っていてくれた。鍋を囲んでの夕飯に笑いを取り戻す。
8月17日(月) 晴のち曇 蒜山 – 三朝45キロ
リーダー土肥・河野
我がA班は台風のために失った一日を、残念ながら1部のコースをカットして取り戻すことになった。蒜山 – 人形峠 – 奥津 – 津山 – 鳥取、3日のコースを蒜山 – 犬挾峠 – 倉吉 – 三朝 – 鳥取と2日で進むことになった。差当たり今日は三朝までの45キロ、比較的楽なコースである。今日は早く着いて温泉でノンビリできそうである。
出発はまたB班に先を越された。確かにB班はまとまりが取れキビキビしている。見習わなければ。我々は会う度に敵対しすぎていたようである。4年生から1度位一緒にミーティングをやって欲しかったという声もあった。
我々はB班と別れて道を左へ折れた。これでB班とは京都まで会うことはなかった。犬挾峠は蒜山三座の東の端にあり、蒜山高原が倉吉平野へ落ち込むところである。まさに落ち込んでいた。峠といっても蒜山高原からはそんなに高くなく、我々は労せずして峠に立った。小休止の後、急な下り坂を各自充分な車間距離をとって、ひとりひとり下って行った。わたしは口を酸っぱくして言った。
「車間距離を充分にとれよ」
「スピードだすなよ」
「ブレーキは早めに、スピードは控え目に」
「気を付けろ」
ところが、事故を起こしたのはわたしだった。坂の途中で急にブーキが効かなくなり転倒。体でブレーキをかけた。シャリ道に叩き付けられ、ジャリの上に数m、引摺った跡を残して溝へ落ち込んで漸く止まった。生きていた。前を走っていた奥野君が駆け寄ってきて、
「大丈夫ですか」
「あんまり大丈夫ではなさそうだ」
とは我ながら情けない。左足と腰、左手と左肩を強く打っている。手足は擦傷だらけ、腰にも血がにじみ、肩はユニフォームも破れ血に染まった。ポケットのサングラスも割れてダメ。暫くは動けず溝の中に座っていた。及川君や内田君に傷を洗って赤チンをつけてもらう。おまけに写真まで取ってくれた。なんとも情けない顔をした写真が今、手元にある。痛みの割に傷は大したことはなく、自転車もクランクを少しまげただけですんだ。ブレーキが効かなくなったのはネジのちょっとした緩みからであった。全くの整備不良が原因。
「整備などめったにしない」と変に誇りを持って言っていたことを猛省。
この後は下りのスピードを極端にセーブして落りた。他には事故もなく、12時倉吉着、昼飯。1時半3朝着、川原にテント設営。
食当の我が2班を残して三朝高原道路へポタリング。渋々行った奴もいたが、晴やかな顔をして帰って来た。適度の疲労と満足感の味わえる上りであり、快適な下りであったのだろう。きょうは川の水を使っての料理だが、後で下痢をしたという話も聞かなかった。1年生の胃袋も我がクラブに大分慣れたようだ。ところがさあ飯だという時、又々雨に見舞われた。幸いその雨は直ぐに止み及川君曰く「西の空が明るいから大丈夫だ」
食後フロへ行く。町の共同浴場で他所者の我々は20円也の入湯料を払う。ここの温泉はラジウム泉でかなりの効能があるようである。温泉を飲む治療もやっているという。その通りに濁りひとつない全く澄んだ湯で、どんな病気も治しそうな気がした。今朝の傷がしみるのを堪えて入ったが、さっぱりとしたすがすがしい気持になっに。確かに素晴しい温泉のひとつだ。これだけ湯のきれいな温泉をわたしは他には知らない。
今日は食後も充分に時間があり、茶店でダベリングをするものや、家族や友達や恋人(?)に絵葉書で無事を知らせるもの、各自忙中閑を楽しんでいた。就寝となって及川君の予報虚しく、再び雨が降りだした。今度は止みそうもない。今日もまた雨音を聞きながら寝入る。
8月18日(火) 雨のち曇 三朝 – 諸寄71キロ
リーダー上原・番匠
雨は朝まで続いた。火が起こせず朝飯抜きで出発。途中の店でパン・ソーセージで腹ごしらえをし、そこからフリーランになった。いつも何かとみんなの足を引張っているわたしとしては、事故でも起こしてはと思い、なるべく先を走ることにした。もう1つ心配があった。この峠道はわたしの道路地図には載ってないのである。果して通れたものか。
その心配は無用であった。車は殆んど通らず楽しみながら上れる道であった。時折雨が強く降り、勾配もきつい。こういう時こそ我々は強い征服欲を抱く。そして何故か嬉しくなる。投入堂のある三仏寺前を通過、見学の余裕も無し。ここまではバスが来る。この先道はますます厳しくなる。雨も強く降り、雨具をつけたいと思うが、1年生が後からビショ濡れになって追いかけてくる。休んでなどいられない。いくつかの部落を通り過ぎ、最後とおぼしき部落に入り勾配もなだらかになった。そこから峠までは直ぐだった。今日はこの雨にも拘らず事故もなく全員順調に上りついた。快い満足感を持って峠に立つ。その時には雨が上がっていた。
峠を下って直ぐに工事箇所に出喰した。さっきまでの雨もあって泥んこのヌカルミ。おまけに上から石ころや土砂が落ちてくる。プルトーザーが山肌を削っているのである。上に向かって叫んだ。
「スイマセーン、通して下さい。スイマセーン」
少しのあい間をみつけて通り抜けた。それからは地道ながら快適な下りであった。とある農協の前で休んでいると、ダンプの運ちゃん曰く。
「誰か川へ、落ちているゾ」
「えっ、誰だろうか。ケガしたんだろうか」
リーダーの上原君が様子を見に引き返した。それからまた暫く待った。落ちたのは関口君であった。いや、落ちたのは彼の自転車だけで彼は例のニヤけた顔を元気に見せた。自転車の破損もたいしたことはない。まずは一安心。鳥取目指して道を急ぐ。きょうは走行距離71キロの強行軍である。
鳥取着1時近く、ようやく昼飯。とに角今日は忙しい。食後の休憩もそこそこに鳥取大砂丘へと向かう。さらに砂丘見物もそこそこに我が2班は先発隊として出発。直ぐに国道9号線を離れ国道178号線へ入いる。海岸へ出て道路の起伏が激しくなる。海岸の部落へ下る途中、前方にその道がまた上っていくのが見えるのである。
下るのが勿体ないような、馬鹿らしいような、いやなものである。兵庫県へ入る。兵庫まで来れば京都も近い。4時過ぎ諸寄に着く。キャンプ場も直ぐに判った。1時間程待って本隊到着。今日も暗くなってからだったが全員無事に飯が食えた。当初の予定に追いついた。
8月19日(水) 晴 諸寄 – 城崎65キロ
リーダー土肥、河野
朝早く一雨あったが、その後猛烈な暑さがやってきた。晴れ渡った青空を見たのは久し振りであった。浜坂の街を過ぎ桃観峠に差掛かる。これも地図にない道である。久谷の駅を過ぎた所からフリーランとなる。立派とは言えないが、まがりなりにも舗装された道路が峠のトンネルまで続く。かなりの悪路を覚悟し、期待さえしていた我々は肩透しをくったような気持で峠を下る。下りきった所で山陰本線が余部鉄橋で交差している。非常に珍しい橋であるが、わたしは後の浜辺に寄せては返す日本海の大海原の方に目をうばわれた。
香住の駅で休んだ。歩道を占拠してズラッと並んで腰かけパンを食べ、名物なる饅頭や竹輪にかぶりつく。ここの港から海岸巡りの遊覧船が出ている。その案内嬢が2、3人駅の前で観光客に盛んに何かを説明している。それをズラッと並んで座っている我々がジッと見つめているのである。誰が手を出したのか、その1人を引張り込んで話をしている。野郎ばかり17人で旅をしているのである。どんな女でも珍らしくなる。失礼。
佐津までは青く広がる日本海を見ての快適な道。佐津で昼飯。きょうは天気にも恵まれ合宿始まって以来の単調さである。予想以上に道路は舗装され峠という峠にはトンネルが出来ていてサイクリングの楽しさの一端を奪い取っている。
その奪われた喜びを取戻してくれたのは但島海岸道路であった。名づけて日本海スカイライン。100m前後の断崖の上を走る道路であるが海岸の部落へ降りて、再び100m余り一気に上っている箇所がいくつかある。覚悟はしていたがまのあたりに見て驚いた。大山道路なんて比のうちではない。こんな急勾配みたことない。自動車でも後戻りするのではないかと思われた。呆れるやら、馬鹿らしくなるやら、笑いたくなるやら、嬉しくなるやら。快い汗をかいた。『紺碧の空』には「燃ゆる太陽」が輝き、海は遠くに青く広がり断崖の下にみる海は緑に澄み総てが夏を感じさせてくれた。この合宿が夏合宿だったことを再認識。合宿実走10日のうち全く雨を見なかったのはわずか一日のみであった。それだけに初日のあの抜けるような空の青さが皮肉に思える。
我々を楽しませてくれたスカイラインも30分余りで終わりを告げた。これだけ楽しませてもらった上に只で通ったのでは人の道にはずれる、と自転車無料の所、わざわざ金を出して自動2輪の通行券を貰っていた奴がいた。物好き。我々は物好きの集団である。このモータリゼイションの時代に自転車で旅をしようというのである。細い2つの輪っぱに総てを託し、2本の足を頼りに駆け巡る。物好きを誇りに思う。気比浜にテント設営。きょうの疲れは城崎の湯が洗い落としてくれた。
8月20日(木) 晴 城崎 – 宮津67・5キロ
リーダー田中・内田
豊岡の街並を抜け河梨峠で京都府へ入った。これは今度の合宿のコースに総じて言えることであるが予想以上に道路が良く、それがサイクリングの楽しさを半減させている。この河梨峠も然り。道路地図では未舗装であるが、すべて舗装され峠はトンネルで越える。とも角京都へ入った感慨を胸に久美浜の町へ下る。暑さがかなり我々を参らせたが次の比治山峠も難無く越え、峰山で昼食に散った。
この日先発隊である1班が遅れ、堅い結束をもって知られる我が2班が再び先発隊をひきうける。本隊より1足先に宮津へ向かって発った。道は上っていたがたいしたことはなく、先頭の仲田君は俄然張り切って飛ばす。天ノ橋立が近づいて、先ず我々が見たのは黄色い煙を青空へ向かって吐き出す煙突であった。それは今、日本三景の1つ、天の橋立を目指して走っている我々に違和感と驚きを与えた。ここも公害からのがれることが出きず、橋立によって外海から隔てられた阿蘇ノ海はヘドロの堆積が激しく、海水浴場がどんどん閉鎖されていくという。何とか美しいままで残しておきたいものである。
天ノ橋立駅に着いた我々は旅行案内所に尋ねたが、私営キャンプ場が1ヶ所あるだけで近くに公営キャンプ場はないとのこと。そこは海に面した空地で駐車場を兼ねているようである。炊事設備も悪くトイレも粗末なものであった。おまけに1張の料金が300円。我々は他の場所を求めて宮津の街まで走った。市役所の観光課を訪れた。
観光課の人は親切にパンフレットを見せてくれたりしたが、この辺1帯はキャンプ禁止区域で公営のキャンプ場も無いという。さっきのキャンプ場へ戻るより仕方がない。自然を保護する為に無法なキャンパーを閉めだすのはいい。しかし我々のように健全なる(?)若者がテント担いで旅をしているのである。設備の整ったキャンプ場を公の手で各地に整備して欲しいものである。
とも角我々はその1張300円也のキャンプ場でみんなの来るのを待った。我々は先ず会計の土肥君にこんなキャンプ場しか見つけられなかったことを謝らなければならない。1張300円、5張で1500円也の出費は貧乏旅行をしている我々にとっては莫大なものである。1週間分の食費に相当する。
ところが本隊は待っても待っても来ないのである。宮津湾で貝を取る船を見ていたり、体を焼いたりしながら待ったが、一向に彼らは姿を見せない。どれだけ待ったろうか、リーダーの田中君が1人で走って来た。あやうく通り過ぎるところであったが、呼び止めて話を聞くとみんなを橋立ユースに待たせて来たという。彼等は我々がキャンプ地を捜してユースまで来るものと思っていたのだ。リーダーと我々先発隊との打ち合わせがなかったのである。以後気をつけたい。きょうは天気にも恵まれコースも単調で全く順調に来たが、思わぬ所で時間を食ってしまった。
本隊が着いて各班それぞれの仕事に散った。我が班はテント設営後、天ノ橋立へとポタリングに出た。名物の回旋橋を越えて橋立へ入る。回旋橋が回るのは見られなかったが橋立の松林の中のサイクリングは快適であった。時間が遅いせいか人は少なく、車は勿論入って来ない。3キロあるという橋立も自転車ではすぐであった。橋立へ来たからには股のぞきをしてかにゃ、とケーブルで笠松公園へ登る。それが最後のケーブルで帰りは歩いて降りてくれとのことである。台風の近いことがニュースで知らされていたが、いかにもそれを思わせる雲が夕焼けの空に張出していた。公園には股のぞき用に石台などが置かれている。早速やってみた。奇麗に見えるものだ。逆さになると感覚が多少狂うものと思われる。諸君もガールフレンドと会う時に股のぞきを奨めたい。誤解しないでほしい。
8月21日(金) 雨 宮津 – 園部86キロ
リーダー上原・信田
朝、雨は降っていなかったもののかなりの風が吹き荒れていた。
雨は宮津の街を過ぎた所で待っていてくれた。いよいよ台風のお出ましだ。その雨の中、一団となって大江山目指して走る。鬼がでるか蛇がでるか。この日は86キロと合宿では最も長い走行距離である。これはこの日のコースがすべて舗装路であることを前提にして計算されたものなのである。ところが道路地図が舗装であることを示しているにも拘らず宮津を出てすぐに舗装がきれ地道となっていた。しかもこの雨と風である。きょうも大変な日になりそうだ。
道は次第に上りにかかる。みんなが雨具もつけずに走り続けているので、ひとり休むわけにも行かない。1年生がどんどん後から追い上げてくるのである。道端に湧水を見つけ自転車を降りる。
「峠の冷たい湧水を飲むのもサイクリングの楽しみの1つだ」
などと言って休んでしまう。1年の信田君、番匠君が忽ち追い越して行く。その後を高原君が2人を励ましながら続く。おれも1年の時はがむしゃらに上ったものだったがなあ、などと思う。それだけに峠を極めた時の喜びは新鮮なものだった。合宿も後半になって1年生の健闘が目立つ。大山ではバテた番匠君も今ではスイスイとわたしを追越して行く。自転車でかなりのハンデ!を負った奥野君は様々なマシン・トラブルを起こしながらもみんなに遅れることなくついて来た。初日にパンクの栄誉を担った加藤君は、それ以来みんなより早く起き自転車の整備に人1倍気を使っていたようだ。他の1年生も非常によくやってくれている。彼らの力は2年生にも負けない大きな推進力となっている。
とするうちに最後尾を走る副将の及川君が追いついてきた。1番後になってしまったのだ。峠からは海を望むことが出来たが生憎と橋立を見ることはできなかった。このまともに風を受ける峠にいても寒いだけである。早速下る。河守で小休止を取り綾部の駅に着いたのは昼少し前であった。この雨や風にも拘らず予定通り順調な進み具合である。もっとも大変なのはこれからであった。
昼食を終えて出発という時には、雨はさらに激しいものになっていた。わかりにくい綾部の街並を抜け山道へとはいる。勿論舗装などない。道は大きく曲がりくねって上る。雨の中出会う人も車もない。休もうともせずに上がり続ける。雨は小降りになったが横殴りの風が強くハンドルもままならぬ。峠近くでは風に倒されそうにさえなった。
この質山峠を下ってすぐ榎峠にさしかかる。雨は再び激しいものになっていた。横殴りに我々を襲う。ふらつきながらも雨や風と闘う。雨や風を楽しんでいると言った方が当たっているかも知れない。峠にはバス停の小さな小屋があり、着いたものから雨宿りに駆け込む。勿論全員入れるわけがない。峠からは班別に間隔を置いて下る。瑞穂町で国道9号線へ入る。鳥取以来である。いよいよ合宿も終わりに近い。
園部ではお寺に泊めてもらった。考えてみればきょうまで毎日テントで通してきたのだ。雨の中テントで忙しく寝た日もあった。既に雨の上がった今日、何とかテントを張りたい気もしたが、雨の中をズブ濡れになって走って来た体を休めるには畳が1番だろう。甘えることにした。
8月22日(土) 晴 園部 – 亀岡70キロ
リーダー関口・奥野
園部。目指す京都へは40キロ足らず。自転車でも2時間あればいける。しかしB班との日程を合わせるため、今日一日洛北巡りをする。これが思わぬ遠回りになってしまった。園部を出て八木町で左折、京北町へ向かう。街道からはずれたこの道は車も少なく、なかなかいいところである。ところがここで及川君が走行不能になってしまった。彼の自転車のハンドルを押えるステムが脆くも割れてしまったのだ。あれだけの重量を支えてきたのだから無理もない。彼は八木町へ下り、そこから直接亀岡へ向かうことになった。あとの責任は総べてわたしに委かされることになった。わたしはそれを軽い気持で受けた。きょう何が起こるかも知らずに。
京北町までの道は全く快適なものであった。両側の山々は北山杉に覆われ京都の近いことを教えてくれる。昨年の早同交歓会で走った洛北とあたりの景色が次第に似てくる。それが無性にわたしを嬉しくさせる。来たんだな。ついに来たんだ。いよいよ京都だ、と実感が湧いてくる。
京北の街で早目の昼食を済ませた。ここから高雄までは多少の起伏はあるが舗装されたいい道だ。京北の街を出てすぐ栗尾峠にさしかかる。パンクで2、3人が遅れる。下った所で今度は浦田君がパンク。みんなを先に行かせ、浦田君と内田君とわたしだけが残った。パンクはスポークの調子が悪くて起こったものなのだ。内田君がリムをはずしてスポークを切ったり、やすりで削ったりして修理に懸命。メカニックにうといわたしは、何の手伝いも出来ずただぼんやりと見ているだけである。かなり日差が強く、時折青空から落ちてくる雨もまさに焼石に水。修理には1時間を要した。そこからすぐの笠峠を越えて京都市に入る。ついに来たぞ。しかし喜ぶのはまだまだ早かった。高雄までは心持下っている道を快適に飛ばす。両側には北山杉の林が続き、緑がやさしい。真直ぐに伸びた北山杉は見ていて全く気持のいいものだ。
高雄到着は3時を過ぎていた。見物もそこそこに出発。清滝川沿いに下る。これが思わぬ道であった。ハイキング地図で見つけた道で、普通の地図には出ていないからして多少の悪路は覚悟していた。
ところが殆どが押しか担ぎで、乗れるのは極僅か。岩場の連続である。途中の清流ではせせらぎに足を浸して疲れを忘れる。これだけだったならどんなにきつい道でもいい思い出になったに違いない。しかし最も恐れていた事が起こった。浦田君が岩場で足を滑らし怪我をしてしまった。膝を打ち激しく血が吹き出ている。仲田君がすぐに応急処置をしてくれたが自転車に乗れる状態ではない。歩かせるのも酷な程だ。
合宿ともなると重装備で荷物もかなりの重さになる。まして1年生はあの重いテントを持たされているのである。その重い自転車を担いで岩場で足をとられるなと言うほうが無理ではなかろうか。恐れていた企画でのミスが京都を目の前にした今日ついに出てしまった。ここでは5万分の1の地形図だけでは右も左もわからない。彼の自転車を交替で持ってようやく清滝へ出た。そこで仲田君が車に頼んで浦田君と2人で京都の街へ向かった。一刻も早く医者に見せねば。
我々は保津峡へ出た。再び京都を離れて亀岡へ向かう。あたりのキャンプ場では既に夕げの仕度に煙が立ち上る。5時を過ぎている。亀岡へはまだかなりの道程がある。及川君が心配しているだろう。急がねば。わたしは高原君と少し遅れて走っていた。道を間違えたのに気づかずに走り、おかしいと思ったのはだいぶ過ぎてからであった。間違えた箇所まで戻って確かめてみると左亀岡と書かれて道
が続いていた。しかしその道は林の中の踏み分け道の如きものであり、見落したとしても不思議はない。みんなも間違えて真直ぐに行ったものと思われる。滅多に人に出会わぬ所だが道端に見つけた人に聞くとやはり真直ぐに行ったようである。我々は即、みんなを追った。既にあたりは暗くなりかけている。すごい飛ばしょうで後を追う。こんな力がどこにあったのかと感心するが、今はそれどころではない。重くなるのでライトもつけない。1刻も早く追いつかねば。
様々な思いが胸を去来する。たとえ間違った道であろうと全員が一緒にいることを願った。離れ離れになっているのでは、山の中で迷っているのでは、と心配は尽きない。この道はかなりの遠回りになってしまうが亀岡へは行きつける。したがってみんなが一緒に、無事にいることを願いながら一心にペダルを踏み続けた。高原君と走っていたが会話は殆ど交されない。みんなを案ずる気持で心はいっばいである。水ノ尾の部落を過ぎて峠も近い。警笛のラッパを鳴らしながら走った。誰かがそれに応えてくれることを期待して。
彼等に追いついたのは峠でであった。我々のラッパに応える声に安心したのか急にペダルが重くなるのを感じた。全員無事に走って来ていた。幸いにも全員が道を間違えてくれたのだった。既に真暗だから7時は過ぎている。下るのがまた1仕事だ。ライトを点検して1人ずつ充分間隔をおいて、ノロノロと下っていった。きょうのリーダー関口君のこれからの処置は適切であった。ライトを充分に点検させたがこれだけの暗闇の中を走って下るのは危険と、全員降りて歩くように指示した。空には月も星もない。早目の昼飯をとっただけで、それ以降何も食べてない。
空腹に足がもつれ、ペダルがその足に容赦なくぶつかる。稜線が次第に高くなるから谷を少しずつながら下りているのは確かである。しかし歩くのがこんなにのろく感じられたことはないだろう。無言で自転車を押して行列がゆく。陽気に振舞おうと時折声がでるが、その声も続かない。最初に見た灯は鶏小屋のものだった。峠からその灯を見るまでにどの位歩いたのか全く見当がつかない。ようやく人に出会い、亀岡の街を聞くともう近い。自転車ならすぐだとの返事がきた。全員力を取り戻す。亀岡の街や山陰本線を走る列車の灯が見えた。駅に着いた時は9時が近かった。及川君と、医者へ行ってきた浦田君と仲田君が待っていた。全く心配をかけてしまった。遅い夕飯に散る。この夜は大本教本部の庭にテントを張ることが出き、風呂にも入れてもらえた。合宿の1番長い日が、今ようやく終わろうとしている。寝つくのに時間は要しなかったろう。
8月23日(日) 晴一時雨 亀岡 – 京都21キロ
リーダー上原・加藤
朝から素晴しい青空が広がる。まさにコンパ日和。京都目指して、コンパ目指して亀岡を発つ。亀岡を出てすぐ京都との市境新峠にさしかかる。松江からの600キロを走り通し、今京都を目の前にした我々はその峠を峠とも思わずに上りきる。実際この峠は標高200mしかない。我々は再び京都市へ入ったのだ。後の方で誰かがパンクというのでこの峠で待つことになった。そこへ追いついてきたのはB班であった。威勢よくラッパを鳴らし奇声をあげて下って。蒜山で別れて以来である。みんな逞しく焼けている。ユニフォームの汚れと日焼けがこの10日間を物語る。
全員が揃うのを待って我々も峠を下る。京都へ着いた実感を味わう為に嵐山へ向かい渡月橋を渡る。わたしが1年の時、北海道合宿で札幌に着いた時は、まわりのものすべてが我々を祝福してくれているように感じたものだった。しかし今わたしが感じているのは、ただの解放感だけであった。そしてそれは虚脱感にと変わる。最後に事故を起こしてしまったが、今漸く合宿が終わろうとしている。
我がクラブ最大にしてかつ最も重要な行事である合宿、わたしが企画を引き受けて以来頭に重くのしかかっていた合宿が、不満足な結果ではあったが、今終わろうとしている。今はそれを素直に喜びたい。宇多一野ユースに部員宛の手紙を取りに寄って、いよいよ京都駅へ向かう。その足取りは軽い。京都タワーが見えてきた。11時40分京都駅着、静かな到着であった。既に昼食に散っていたB班が帰るのを待って恒例の胴上げを行なった。主将の保泉君、副将の及川君。及川君の胴上げは難物であった。自転車さえも押しつぶしたあの巨体を放り上げるのだから大変。最後は落されてしまった。折から万博でごった返す京都駅でのスナップ。
コンパまでもう1騒動があった。我々はA・B班一緒になって、同志社大から知らせて貰ったキャンプ場に行く為に鞍馬へ向かった。堀川通を真直ぐに上り鴨川を渡る。そのキャンプ場というのは同志社のサイクリング部が時々使う所だそうである。そのあたりは昨年の早同交歓会で走った所であり我々にとっても懐しい所だ。
ところがキャンプ場に着くや否や空が俄にかきくもり大粒の雨が落ちてきた。テントを張るどころではない。土砂降りになってしまった。近くの学校へ退散。ここまで雨に祟られた合宿もないだろう。何人かが今夜の宿探しに再び京都へ下りた。そして彼らが戻って来た時には雨が上がっていたが全員京都へ下りた。鴨川に面した小さな旅館の庭が今夜のねぐら。1人200円也。
漸く落ち着いた。荷物をおろし銭湯へ行って10日間の汗と疲れを落とす。コンパは近くの料亭に任せてある。6時が近くなりその料亭にみんなが集まってくる。すき焼の鍋が火にかけられコップにビールがつがれる。乾杯!!禁酒・禁欲のストイックな10日間に終止符が打たれた。この時のビールのうまさは我々だけが知るものである。疲れた体にアルコールがまわり、ドンチャン騒ぎが始まる。後は推して知るべし。翌日の鴨川は臭く濁ったとか。京都の夜空に「都の西北」が轟く。
8月24日(月) 10:00京都駅解散
夏草やつわものどもがヘドの跡。一種異様な臭いの中で目を覚す。庭に敷かれたグランドシートの上に縦に、横に、斜めになり寝袋の中に潜り込んでみんなが寝ている。2日酔か、頭が重い。次第にみんなも重い頭をもたげて起き出してくる。きょうはあの冷酷無情な「きしょう」という声を聞かずに済む。宿を払って京都駅へ向かう。クラブの器材をまとめてグンボール箱に詰め東京へ送る。自転車もまとめて東京へ送った。駅前にて解散式を行なう。御苦労さんでした。
東京へ帰るもの、それぞれの郷里に帰るもの、先輩の家へ押掛け2、3日万博を見ていこうというもの、さらにまだ懲りもせずに走って帰ろうというものと、各人各様である。様々の格好で松江に集まったように、今また思い思いの方向へ散っていく。駅前には個人の荷物の荷作りをするものと、輪行袋に詰めるために自転車をバラす奴だけが残る。彼らも2人去り、3人去りと少なくなっていく。黄昏せまる京都駅にひとり残り、合宿の終わったことを告げる為に絵ハガキにペンを走らす。
『きょう24日10時京都駅にて夏合宿が無事解散されました。合宿は終わりました』
夏合宿B班 – 教育学部2年 丸山
夏合宿B班
教育学部2年 丸山
70年夏のサイクリングの思い出は合宿である。8月13日から24日まで我らがクラブは山陰に合宿した。松江から京都までそのやまかげの道を走ったのである。私は2年生。といっても合宿は初参加である。この合宿を通して、私は1人前のサイクリストとして精神的・肉体的に大いに強化され成長したのだということと、私はやはりサイクリングが好きなのだということを確認した。
ここにまとめられた記録の記述の中では、すべてこの私が中心となっていて、記録としては形をなしていないので、はなはだ恐縮であるのだが、寛容なるクラブ員には許してもらえるであろう。すなわち、『合宿』は全クラブ員が主役であるが、いわば「合宿の内実」というものは各々のクラブ員のものだからである。
1、緑山公園で
8月13日晴 山陰本線松江駅集合
合宿初日である。みんな思い思いの方法で集合してきた。私はあのなんとも言えないロマンチックな夜行列車で朝着いた。すでに昨夜京都駅小荷物預り所で偶然会った山上君は来ていた。この山陰でも真夏の太陽は容赦なく照りつけ、これから始まる合宿がどんなによいものであるか表わしているようだ。次々と現われるクラブ員の元気そうな陽焼けした顔をみて、相当に走っているなと感じた。予定より数名欠けて34名になる。人数割りの関係で藤井君(2年)がB班に移ってきた。テント、ナベ等の器材をわけて、この日は松江市街はずれの緑山公園にてキャンプする。
夕食は外食であった。風呂と食事をいっしょにすませ帰ってくる。美しい星くずの下で夜のミーティングを行なった。主将から合宿のはじまりの宣言と全般的な注意があった。
テントにもぐり込み、私は思い出した。ちょうど1年前の東北合宿は、合宿前に伊豆へ行き、遊びすぎたため自主的に不参加にした。体力も金も底をつき、ほうほうのていで家にたどりついたのだった。今回の合宿がはじめてだ。これから先のこと思う感動で、しばし思いをめぐらし、公園の静けさにひたりながら夢路へと入っていった。
2、A・B2班にわかれる
8月14日晴のち雨 松江 – 出雲 – 松江83キロ
リーダー里見・平川
この日より京都駅で再び会うまで、A・B2班の分割走行方式をとることになる。これは我がクラブでの合宿では初めてのことで、同じコースを2班が一日ずらして走り、それぞれ独立して小人数の密度の濃い合宿をやろうというものである。この企画は早稲田にしては画期的であるといわれていた。34名をA・B半々にして、A班は先に美保関をめぐって米子に向うことになるが、私のB班は松江付近で一日遊ぶような形になる。京都での再会の時は当然、日を合わせなければならないためA班は22日には高雄、保津峡方面へ行くことになっている。
A班が緑山公園から消えてなくなると、私たちも出発することに。宍道湖をまわり出雲大社を参詣し、同じキャンプ地に戻って来るというコースである。宍道湖は濁った緑の水。しかし湖岸の道はなかなかのんびりしていい。合宿へ来ての初走行にぴったりだ。縁結びの出雲大社に到着して昼休みとなる。記念撮影などやる。我がクラブ独特の、あのすさまじい押し合いへし合いが始まる。いったん、カメラを向けるとあたかも死人に群がるハイナエのようにレンズの前に寄ってくるというのは、いつ頃から始まったのだろうか。先輩に聞くところによれば、どうもかなり前かららしい。
大鳥居をくぐり並木を奥に進んで行く。ここの巫女は事務的で愛嬌がまったく感じられない。もしニコニコ愛嬌をふりまき、参拝者のきげんなどとったら霊験あらたかにはみえず、おかしなものなのだが・・・。縁結びのお守り、交通安全のお守り、いろいろもっともらしく並べて売っている。私は記念に身体安全のお守りをいただいた。これなら交通安全にもきくし、病気も防げる。つまり合宿を無事にすごせるというわけだ。何か深いわけがあったのだろうか、縁結びの札をもらっているクラブ員もいる。
昼食をとろうと外へ向って行くと、「こんにちは」と呼ぶ人がいる。見ると女性のグループである。京都発の夜行列車で同席だった、うら若き女性3人と、他にその友人らしい女性1人がニコニコ笑っている。彼女らは岐阜にある会社に勤めていて、友人のところに遊びに行くと言っていた。夜汽車の中では私と意気投合しダベリ、食ったり飲んだりした。彼女らは途中で下車したが、おそらく友人に案内されてここ出雲大社まで来たのだろう。ここの神の力はよほど強いのだろうか、もう結ばれるきっかけができたではないか。内気な私はテレて、ちょっとあいさつをして仲間とめしを食べるために急いだ。
緑山公園に戻り夕食を食べようとする頃になって雨が降り出して。そういえば私が東京を出る時、大型台風9号が近づいているという報道をさかんにやっていたっけ。1本の木の下に17人小さくなって食事をとりミーティングをやった。雨の中、昨日行った風呂にまた行き、すぐにテントにもぐり込んだ。A班はどうしたろう。昨夜、全員で寝たが今夜はもういない。やけに淋しく感じられる。
3、台風9号=ハプニング
8月15日風雨 松江 – 美保関 – 米子63キロ
リーダー藤井・梅本
朝から雨。グランドシートの下に水がたまっている。昨夜からずっと降り続いているらしい。今日からA班の輪跡を追うことになる。雨の中を出発。いやな気分だ。走行中、山上君が私のすぐ前でパンクする。雨の中のパンクはほんとうにつらい。そばにあった建築中の家の軒下を借りて修理した。
美保関へ向う頃、雨いよいよ激しく、風いよいよ強くなる。たまたま通行中の人に台風情報をたずねてみたが、さっぱり要領を得ない。なお悪いことに、隊が前と後に大きくわかれてしまった。私と中山さんと高橋さんの3人は、かたまって美保関へ追いかけて行こうと思った。ギヤーを落としてもポンチョを着ている私は風をはらんでほとんど進まないし、進んでいるようすを調べることさえもできない状態である。海からの強風で横すべりして崖にぶつかりそうである。私は危険を感じてきた。風が弱くなるまでどこかで待機しようということになって、3人は海辺に半壊した納屋をみつけて休ませてもらうことにする。待機中も強風のため、窓枠もろともガラスがフッ飛んだ。1時間以上待っただろうか、非常に長く感じられる。
昼近く腹がへってきた。食物は3人であめ10数個である。こういう時はこんなものでも有難い。サイクリングに出る時は何か非常食をフロントバッグに突込んでおくべきだ。あめを3人で分けて食べる。これだけでかなり元気はついた。そして退屈しのぎに火をたき、衣類を乾かし、そこいらにころがっているジャガイモを焼いて食べた。他の14名の我らがクラブ員は美保関まで到達した。それはまさに、逆巻く波、荒れ狂う風雨の恐怖をのり越えてであった。フェリーで境港へ渡る頃にはもう風は弱くなりかけていた。
米子の皆生温泉に入って行くと、我々と同じユニフォームの人間がいるではないか。それは昨日別れたA班の面々であった。にぎりめしを作って迎えてくれた。私たちはありがたくそれらを頂戴した。
聞けばこの台風では大山は地形、風景の関係で走行は望ましくないと判断して、この地にとどまっていたとのことだった。私は何も理由がないのに、何故かがっかりした。このハプニングにより、今夜はここ皆生温泉のキャンプ場に同宿することになった。といってもどういうわけかA班はテントに、一日中雨に打たれていたB班は粗末な公民館に、と別々である。私は濡れたものすべてをそこにおっぴろげた。夕食は合宿2度目の外食になった。私は例によって温泉につかり、安田君に気持ちよく背中を流してもらってさっぱりしたあと玉子丼を食った。
計画に変更があり、翌日はA・B2班で同じコースを走り、17日に別れてA班は近道することになった。しかしながら、この間ずっとトレーニング、食事、出発、到着、ミーティングは別々に行なった。クラブ員の間にしらじらしい雰囲気が感じられた。
4、合宿のハイライト
8月16日朝のうち雨後晴 米子 – 大山 – 蒜山53キロ
リーダー丸山・山上
私がリーダーをやった日である。フリーランを多くとり要所々々で全員が揃ってまた出発という方法をとった。この合宿のハイライトである大山をめぐる3本の有料道路に挑戦するコースだ。すなわち大山道路・大山環状道路・そしてオープンしたばかりの蒜山有料道路を通って、蒜山国民休暇村にキャンプするというさすがに走りがいのある、スケールの大きなコースである。はるかに続くアスファルトが見える。まさにこのコースは男の早大サイクリングクラブに合っている。
最初の料金所からフリーランをとった。私は小雨にけむる、ズデーンとのびきった大山道路を泣きで走った。雨はこの苦しさを少しは和らげてくれた。私はこんな登りは初めてだった。富士スバルラインや箱根峠や確氷峠や、その他たいていの峠道は蛇行しているものだ。しかし大山道路だけは違っていた。こんな道路のダウンヒルはどうだろう。とくだらないことを考えた。おそらくアウト、イン、アウト、インとハンドリングするSカープもヘアピンカーブも楽しめないつまらないものだろう。
大山町で昼食をとり終ってみると、そこにはもう、あの真夏の強烈な陽ざしがふりそそいでいた。桝水原は大山町からすぐだった。
そこからの景色は上に大山、下に米子平野。まったくすばらしい。あっという間に休憩の10分間が過ぎた。次の大山環状道路というのは、大山町から大山の裏側へまわり込むようにしてのびている道である。そこを背中と呼ぶならば、背中は大きな手の爪でひっかかれたように険しい感じだ。色も紫色をおびている。蒜山道路はほとんど下るいっぽうだ。大きな山頂をぬって走っていく。あまりの景色の大きさに恐さを感じる。信じられない程の短時間のうちに蒜山国民休暇村に到着してしまった。一日中登り続けて苦労したのに・・・。
国民休暇村では、親切にも我がクラブに教育指導者用のきれいなキャンプ地を借してくれて、蒜山高原の牧場と樹海をながめながら寝起きした。それで大山をやったという事が報われたような気がした。
合宿のハイライトにふさわしく最初から最後までコースは超A級であった。いや、コースがすばらしかったから、ハイライトだったのだと言おう。肉体はさんざん痛めつけられたのだから。そしてここのコースリーターをした私と山上は光栄であったと思う。
5、さあ、人形峠
8月17日晴 蒜山 – 人形峠 – 奥津64キロ
リーダー名田・国友
ハイライトに続き、今合宿のホープの人形峠を越えることになる。この日もおかしな事に、朝のごたごたで遅れて後から出発した主将以下数人のグループが先に峠に着いてしまい、コースリーダーのついている本隊は後になってしまった。本隊はどうも別のコースで県道まで出たらしい。人形峠到着までリーダーの名田君は、離れたと思われる後、心配のしどうしであった。
A班とは今日で別かれることになる。A班は八束村上長田で別れて進路を北にとり、犬挾峠を越えて、1足早く鳥取県に入る。そしし倉吉市三朝にて宿泊するそうだ。次の日諸寄まで到達すれば、また元どおり一日行程がずれるわけである。我がB班は正規のコースで人形峠、津山方面へ南下した。
人形峠を通っている国道179号線に入るまで、やたらと小さな峠のようなものがある。ほとんどここで体力を消耗したようなものだ。いざ本番という時になって、全然力が入らない。おまけに日射とその照り返しの地獄である。フリーランだったので私はいつものようにとり残された。私は覚悟を決めて1人でペダルを踏んでいった。しつこい、しかも単調なカーブの連続である。店屋もないので、朝食の残りの味噌をなめた。全然、からさを感じない。清水の湧き出る所では抵抗なく愛車から降り、のどをうるおした。
峠の食堂で女連れのヒゲの外人が我々に声をかけてきた。
「自転車恐くないですか」
「今夜はどこのホテルに泊まりますか」
などとうまい日本語で話しかけてくる。この外人と奥津温泉でまた会うとは思わなかった。私たちはその快適なダウンヒルを楽しんで奥津温泉へと急いだ。メカニックトラブルで遅れていた小泉さんと、それにつき合った吉田さんもすぐ来た。ペダルのネジヤマが切れてしまい、クランクとペダルとチェーンをまとめて取り換えたということだ。テントは川西ホテル裏の駐車場に張らしてもらった。そこはマムシが出ると言う話を聞かされたが、あまり気にしなかった。私は『赤マムシ』とか『マムシゲン』とか『マムシのナニ』とか言葉は知っていたがマムシを実際見たことはない。風呂はそのホテルのきれいな温泉に入れてもらえた。
平川君が蒜山で両足首を、たちのわるい虫にさされ、それが効果的なアンクリングができない程にはれ上がってしまった。救急箱の薬ではもはや、効かないので、医者を見つけて連れてゆく。どうやら注射が効いてきたようである。この虫というのは土地の人の話によれば「ブトウ」というらしい。私は『ブヨ』のことではないかなあと思った。
夕食に小泉さんから西瓜の差し入れがあり、腹がふくれて食べ切れない程であった。食後、表通りに面した店屋の縁台でガヤガヤやっていると、あの外人が現われてきた。おそらく私たちが奥津温泉へ行くと言ったので、旅行中の彼らもここに宿をとることにしたのだろう。聞けば彼はあのカリフォルニア大学バークレー校舎で学んで、今、岡山県で英会話を高校、短大、会社で教えていて、他に個人教授もやっているそうだ。
早稲田大学というのも知っていた。さすがに世界の早稲田ではある。自転車のメカニックにも詳しい。カリフォルニアではサイクリングをやっていたと言っていた。彼らのサイクリングはこうだ。ほとんど舗装路なので、私たちのような太いタイヤは使わない。ツーリングで一日200キロも行く。そしてモテルのようなものかユースホステルに泊まる。簡素なモテルもべらぼうに高いそうだ。野宿の時はグランドシート1枚芝生の上に敷くだけである。カリフォルニアの気候が夜つゆを出さないからである。食料はスキムミルクとパンが主である。それにハム等をつけるだけのものらしい。
私はすっかりこの合宿に慣れたと思った。川の流れを耳元できき、満足して眠りに入った。
6、再び鳥取県に入る
8月18日雨降ったりやんだり 奥津 – 津山 – 智頭77キロ
リーダー里見・立石
出発前から雨が降ったりやんだりしている。
「もうエエカゲンにせいやーッ」
とどなりたくなる。ポンチョを着て出発。奥津渓谷を津山に向かって走行中、雨はさらに強く私たちに降りそそいでくる。それも津山駅につく頃までにあがってしまった。津山市は私の記憶をたどると、どこかに感じが似ているのだ。そうだ、小田原だ。一緒に昼食をとった小泉さんにたずねた。彼もうなづいた。
午後は1つ峠を越さねばならない。里見君の好リードのもと駅前を出発し、順調に峠に近づいていった。昼食後、いきなり長く走りすぎたせいか、とある神社にて休憩をとったのだが、みんな急いで愛すべき車を放置し、思い思いの方向へ散った。ある者は大木の根元に、ある者はヤブに対し、減量してまで肥やしを与えていた。ホッとして休んだ。
ここから、岡山、鳥取県境の「黒尾峠」までフリーラン。私はいつものあの調子でエッチラ、オッチラ踏んでいった。かなりの勾配である。しかも地道で石がゴロゴロしているところもあるのだが、さして苦痛にも感じなくなっていた。クロートウゲ、クロートウゲというが、これがクローかと思っている間に峠である。例によって記念撮影。今日の泊りは智頭町。地面が濡れているため、智頭小学校に宿泊をたのむ。家庭科室のタタミに寝られることになった。小学校の前の本屋のおやじさんが、息子も早稲田を出たのだと説明して、ソーメンやらジャガイモ、タマネギ、ニンジンなどの差入れをしてくれた。おまけに酒1升まで持ってくる始末である。私たちは御好意に甘え、いただいたのだが、酒は小泉さんが打ち上げコンパまで運輸管理することになった。
7、日本一、赤熱の砂丘
8月19日晴(夕だち) 智頭 – 鳥取 – 諸寄67キロ
リーダー藤井・陶山
トレーニングは校庭をフルに使って行なった。まず集まってくる子供や町の人々と音楽に合わせてラジオ体操、次にトラックを走る。次に鉄棒等の器具を使う。ちょっときつかった。1夜過ごしただけなのだが、この山に囲まれた小さな智頭の町の印象はどういうわけか、妙に頭にこびりつくような気がする。私が想像するサイクリングで町から町へと、渡り鳥のごとく放浪してゆく旅の中に出てくる町というものは、この智頭の町とぴったりなのだ。なごり惜しいがこの町を出発した。それがサイクリストの宿命であった。私は妙に感傷的になっていた。
智頭町から鳥取市まで千代川にそって北上する。またこの川にそって国鉄因美線が通っている。道はだらだら下り気味である。ペースメーカーはかなりとばしている感じだ。空は昨日とうって変わって快晴である。因美線に『駅無人化反対!』『廃駅反対!』とかの立看板がある。私はここに過疎に悩む山陰の一面を見る思いがした。ひょっと気がつくとその因美線を通る列車の窓から手を振る若い女性があるではないか。私はニッコリ笑って手を振り返した。
鳥取の砂丘はさすがである。砂山が続いているだけであると言ってしまえばそれまでなのだが、何しろふつうの砂浜とは違ってスケールが大きい。強烈な太陽はまぶしく、赤砂は熱せられてあつい。そこをみんなして、上半身はだか下半身はだしで歩いた。
変化にとんだ地形の浦富海岸を通り、今日の宿泊地諸寄のキャンプ場に到着。役割を終えたクラブ員は早速、海にとび込んでいったのだが、食当になっている私たちの班は本当にしかたがないといった感じで任務を遂行した。私は夕食と夕だちが終ってから海に入っていった。入るとき
「夜はクラゲにやられるぞ」
と言われたのだが、やはり股と脇をやられた。そのまま銭湯へ行った。
明日私はリーダーをやる。サブリーダーの梅本君と打ち合わせを終らし、寄せては返す波の音を聞きながら眠りに入っていった。
8、台風で夜間避難
8月20日晴 諸寄 – 香住 – 城崎65キロ
リーダー丸山・梅本
リーダーの任務についた私は9時に「出発」を宣した。海岸線を上下左右にふられながら城崎温泉まで行くコースである。昨日は浦富海岸へ入ってゆく道を間違え、国道9号線をかなり深く行った時点で気がつくという、大学のサイクリングクラブではちょっと困ったようなミスがあった。そしてその日のミーティングにおいて、小泉さんから
「道がおかしいと思ったらリーダーは隊を止めてもかまわない。そして地図を確認するなり、土地の人に聞くなりして絶対道だけは間違えないこと」
とアドバイスされたこともあって、私はきわめて慎重であった。出発してからすぐ桃観峠である。私はフリーランを伝えた。みんな何なくのぼる。ここで小泉さんによれば、こんなちゃちなところはフリーランにしなくてもよく、合宿はよほど大きな峠でもない限り原則としてフリーランにはしないようにと教えられた。それで以後はとても苦しかったということは誰もが承知しているであろう。ダウンヒルの後、余部鉄橋の下で休憩。記念撮影。香住町にて昼食。
再びあの海岸線をゆさぶられて行く。佐津駅前にて竹野への道を聞くと海岸線にある新道は未だ工事中とのことなので、安全な所定のコースを選んだ。これはだらだらと山の中へ入っていって、まただらだらと海岸にある竹野まで出る道である。非常に気持ちのよい田園風景である。
竹野から約10キロは但島海岸有料道路となっている。アップダウンが激しく、もうフリーランにしようかと思った。こんな時、リーダーは本当につらい。景色を楽しむ余裕さえないどころか、後続の追い上げでさらに苦しくなる。
城崎に入る手前2キロで隊を待機させ、私と梅本君は城崎町役場にキャンプ場の問い合わせに行った。そこで昨日来たというA班のうわさを聞きなつかしく思った。A班もキャンプしたという気比ヶ浜に決定、隊へ戻った。リーダーの任を終えた私はすぐ海に入り泳いだ。
夜はあの有名な温泉につかりに3キロばかりの道をぶっとばした。やはり温泉町らしい。昼間役場に来たときよりもそう感じる。温泉町は夜が色っぽくていいのだ。喫茶店に入り、お茶をのんでから帰途についた。
「起床ーッ」の声で、やっと眠ったと思ったのが起された。11時である。台風が来るらしい。駐在さんもバイクでそれを伝えに来た。どうもテントでは危険らしい。それどころか海岸にいることが危険らしい。付近の民家に主将以下数人がテレビを見に行き、情報をもってきた。それで近くのほとんどアバラヤといってもよいような海の家に避難した。シュラフを持ち、バッグをもち、テントをたたんで。
9、あらあら、砂子君が・・・
8月21日雨降ったりやんだり 城崎 – 久美浜 – 宮津68キロ
リーダー名田・平川
昨夜は大騒ぎして避難したにもかかわらず、おかしなことに台風らしきものは来なかったようだ。
きょうは2つの峠を越える。まず、昨日2度も行った町の方向へ進路をとり、そのまま川に沿って豊岡まで南下する。そこからが河梨峠である。Sカーブの続く地点で休憩がとられた。私もそうであるように、みんなの疲労はかなり蓄積している。ちょっと走っただけだと思うのだが、もう、自転車を放り投げて座り込んでいる。私も例外ではなかった。10分間の休憩ではもはや回復しなかった。サイクリングの疲労というのは、ある学者によれば1時間走った疲労は5分間の休息で解消するそうである。今の私にはこれは嘘か、あるいは、よっぽどチンタラやっているサイクリングであるように思える。
道端にボケーッとすわっていると下から、例のラッパの音が聞えてくるではないか。主将も休んでいるから、このラッパは我が隊とは関係ないと思っていたら大間違い。砂子君である。彼は今朝豊岡の駅から走り出したと言っていた。追いついてはみたものの、余りにもみんながくたびれた兵隊さんのようになっているのに、彼自身驚いているようすである。B班は砂子君を入れて18名となった。
2番目に比治山峠がある。これも何なくのぼり、峰山で昼食をとる。ここでは、町はにぎやかなのだが、何を食べるのか決めあぐねて、ずいぶん歩きまわってしまった。冷房のきいたレストランに落ちついた。映画の看板写真をみたり、トイレに入るためパチンコ屋に入ったりして戻った。雨はまた降ってきたが、雲が行く手で切れているからすぐやみそうである。
天ノ橋立はやはり美しいのだが、いわゆる観光地という感じはぬぐい切れないものがある。小さな松林にテントを張る。夜はみんなして喫茶店に行った。合宿が終ってからどう走ろうかという話に花が咲く頃になってしまったのだ。テントに戻るとまたまた雨は降り出し、昨夜と今夜と台風さんが間違えたのではないかと思うほど、風が吹きあれ、松林はうなりをあげ、砂は容赦なくテントの中に入り込んできた。ボールとテントの端をシラフの中から手をのばし、おさえなくてはならなかった。
10、気をひきしめて走る
8月22日晴 宮津 – 綾部 – 園部86キロ
リーダー砂子・安田
昨夜の風雨もそう長くは続かなかったらしい。私はいつの間にか眠ってしまっていた。
みんなと思い切り走れるのも今日で最後だろう。今日の走行を充実させようと気をひきしめて走る。昨日入った砂子君がリーダーをやる。今日のコースは最初と最後が一級国道であるが、中は砂利の地方道である。私の感じでは、峠らしきもの大小あわせて4つぐらい越したような気がする。かなりバテていたことは確かなのだが、もう、上りも下りも関係なく、苦にもならず、ペダルを踏めば自転車は前に進んでいた。フリーランもなくただただついて行った。瑞穂町へ入る前、ちょっと気をゆるした瞬間、傍の溝に私の自転車は突込んでいた。気をひきしめていたはずだったのだが・・・。こんな時に事故は起るのだろう。
園部では園部川の河原にテントを張る。大こいのは子供の頭位の石がごろごろしている。飲料水は民家からもらった。今夜は最後のミーティングである。総括が行なわれた。1年生はもうこのクラブとのくされ縁が出来てしまったわけだ。主将はクラブ員各々について合宿中に感じたことなどを述べた。このミーティング中、私は非常にうれしかった。合宿中のいろいろな場合を次々と思い出した。そしてこれが私の青春の一面だと感じられたからだ。
明日は都入りだ。私が3たびリーダーをやることになった。というのは2年生市川君が不参加のため、誰かがやらなくてはならなかったから。ミーティングにて、A班と同時に京都駅に到着するために、8時半出発を伝えた。
水の音を聞き、明日の京都の事を思いつつ寝てしまっていた。
11、京都入り – 再々会
8月23日晴夕だち 園部 – 亀岡 – 京都21キロ
リーダー丸山・中丸
きっかり8時30分に出発。今日はほとんどすべて国道9号線である。その単調な道を快調にとばす。昨夜、前のA班は亀岡にキャンプすることになっている。私は亀岡ではかなり意識して、目をキョロキョロ見回してしまった。そんなはずはないのだが、ひょっとしたらA班をみつけることができるかもしれない。そしたら何と言おう。尻にくっついて行けば、同時に京都入りだ。そんな想像をめぐらしながらペダルを踏んだ。
さて、これから京都盆地に入って行くために新峠を越えようという時、私の前にあのなつかしの及川さんと堺さん、それに連日パンクしていたという奥野君の3人が、またチューブをもんでいるではないか。それはそれは思いがけなかった。私はもうA班は京都到着を完了していると思い込んでいたからだ。
新峠には全員揃ってのぼる。峠では休憩、あるいは最低呼吸を整えるために、自転車をとめて小休止をしなくてはならない。それで私はトンネルを抜けたところで隊をとめた。数分で出発。すぐカーブをまがると、その余地にA班の人たちがズデーンと休んでいたではないか。双方びっくり。手を振って別かれ、ダウンヒルを続ける。さあ、京都だ。さあ、京都だ。私はそう心の中で言い続けた。
京都タワーの見えるところで右に曲がる。このまま突入すれば京都駅である。私はサブリーダーの中丸君に、自転車35台が置けて35人の疲労した人々が休めるよい場所を探して来るように依頼した。彼はダッシュした。そしてすぐに見つけてきた。実に10時きっかりに京都駅到着。中山さん曰く
「キョウトいう日を待っていた」
京都駅及び京都駅前は万国博のせいだろうか、この暑さにもかかわらず人でゴッタ返していた。私たちは走り終えた自信のようなもので気も大きくなっていたので、小泉さんを胴上げし、続いて主将保泉さんを胴上げした。さらに肩組んで「紺碧の空」を歌った。
同志社大学サイクリングクラブが指示してくれたキャンプ地、静原に向ったのは午後になってからであった。夕立ちのためキャンプ出来ず、コンパはすき焼き屋であり、泊まりはわけのわからない家の芝生の庭を1人200円也で借り、青空の下で寝ることになった。
「乾杯! – 」主将の音頭で、コップのビールをあける。うまい。打ち上げコンパが始まった。だんだんと例によって乱れてきてしまう。私はがなり続けた。手を打ち続けた。ああ、ついに終ってしまったんだなあ。私はそう実感した。だから私はがなり続けた。校歌を何度も歌った。
いざこぉーえそろえーて、そらもーとどろにぃー、
われらーが母校ぉーの、名をばーたたえむ
わせだわせだわせだわせだ、わせだわせだわせだぁー
主将としてのこの1年 – 法学部3年保泉
主将としてのこの1年
法学部3年保泉
この1年間は、サイクリングクラブという「名」のゾル状の流動性物質を背負って、無我夢中で突走ってきた感じだ。篠原さんから軽い気持で第8代目主将のバトンを受けたが、このクラブの最高責任者たる者の走るルートは、艱難辛苦の茨の道だった。簡単にいってしまえばゾル状を結果に於いて、ゲル化させなければならない、意義ある任務だと俺は思って、この1年間やってきたわけであるが、温度や湿度その他諸々の条件のもとでは、ゲル化は非常に難かしい仕事だった。
この操作過程のなかで、一国の首相たる心情を垣間みることが出来たり、また汚物処理の雑役夫を演じたりしてきた感じだ。この状況にある「1対55」の数字は、俺にとっては非常に虚しくもあり、またフォースでもあったが、その比例式の右辺(あるいは左辺)に浮かび上ってくるさまざまな影像を支配する「情念」というものが、いったいどのようなものであるのか、これは俺のみが知ることができたのかも知れない。
方向が定まらない運動体を、同次元に整えて、その相互関係の中においてエンジ色のアウトラインを引く行為は、俺にとっては予想をはるかに超えて厳しかったが、今振り返って見るとこれはいい勉強になったように感じている。俺がこの1年間我がクラブにおいて貫いてきた方針はこうである。
我がクラブも、同好会的存在から今や主将も8代目を数える程となり、人数からいってもクラブを構成する組織からしても「クラブ」としては非常にしっかりと固まってきたと思う。これは、今までの主将の方々をはじめとして、全クラブ員のクラブに対する積極的な働きかけがあったからこそ作り上げられたものと思う。それで、これからはこの確固たる基盤の上にたって、ただ単にこのクラブをサイクリングクラブとして終らせるのではなく、このクラブはそれぞれの個性をもった50数名によって動いているのだ、という意識を各個人個人にハッキリと認識してもらい、この我がサイクリングクラブというものを大局的な見地にたって考えて行こう、ということだった。
現在はもう、クラブ自体をどうこうしていじくり廻す時ではないのではないか、と思ったからである。このクラブを土台にして、自分自身が飛び上がるステップと考え、そして4万数千の群集のなかの心の「ふるさと」になるように、各個人個人でクラブを創り上げてもらいたかったのである。
少し具体的に言えば以下の様なことである。このクラブに於いて中心的活動となる月2回のランについて、俺はあえて「強制」してまで参加させる必要を認めなかった。これを行なって単なるサイクリングだけのクラブにしてしまっては、大学生の集まるクラブとしての存在価値が失なわれてしまうのではないかと思ったからだ。中学・高校生達のクラブ活動と同じようにある種の「強制」でもって、ハッキリと目に写るアウトラインを造ってしまっては、そのラインの外側にはみ出てしまう者は、自分の居場所を見失ってしまう。50数名の者が1つの組織を創り上げているのだから、さまざまな個性や考え方を持った人間がいる筈である。そして、その様な諸個人が同居するクラブでは、ましてや全くつかみどころのない一定した方向性も具備しない「サイクリング」というものをやっていくクラブでは、一層人間としての諸個人の行動を認めてやり、また積極的なクラブ内での活動が期待され望まれるのである。
ここで我がサイクリングクラブに於いて、クラブとサイクリングとの相関関係を考えてみると、非常に複雑多岐にわたっている。これはクラブに入部した動機につながるものであるが、決して同一ではない筈である。ある者は、クラブに入ってサイクリングを求めるだろう。また他の者は、サイクリングを求めてクラブに入ってくるだろう。それからサイクリングとは関係なく、あるサークルに入って「クラブ活動」をしてみたいという者や、とにかくクラブのなかで親しい友達をつくりたいと思って入ってきた者もいることだろう。このように様々な考えでクラブに入り、自分の求める「もの」や「こと」を追求していくのだと思うわけである。そこで各個人同志が自分のもって入ってきた考えを、このクラブの中で積極的に行動に移し、組織全体が右往左往して止まない流動体こそが、我がクラブの今後のあるべき姿ではないかと考えたのである。
ではそれらの多くの顔をもった人間をつつみ込んで、1つのクラブというものを組織するために、主将としてとるべき態度を、俺は次のように考えた。まず俺がクラブ員個人個人を1人の人間としてクラブ内での存在価値を認めてやり、それから俺とその個人個人との間に信頼関係を結ばなければならないということであった。俺がここまでくるには、絶えず50数名の顔が浮かんでくるまでは、時間もかかり苦しんだりした。そして、いつ崩れるかもわからない、この不安定な信頼関係は、絶えず俺との緊張状態を約束してくれたのだった。
特にクラブランの時は、俺のこの貫くべき態度が、多少動揺し出すことは確かだったが、たとえその日のランに参加しなかった者がいても、このラン以外の活動に自分の存在を賭けているのだろうと信じていた。ある時は、ランと重なる日にクラスの合ハイがあり、その幹事のひとりになっているためそちらの方へ行かせてくれ、といってきた者もいた。それからクラスでハイキングに行くのでクラブのキャンプ用器材を2・3日貸してくれ、と頼み込んできた部員もいた。
俺としては、これらの件について素直に許可を与えてきた。クラブのみにとどまらず、クラス等でも積極的に活動する存在になり、またリーダーとして行動してもらいたかったからだ。そこで培かわれた多くの可能性をひめた「力」は、必ずやまた我がクラブの方に帰ってくるものだと確信していたし、またそうあるべきものだと思っていたのだった。一方また、クラブの組織形態を維持する態度としては、やはりクラブのなかで大きな比重を占める合宿・対外行事等は全員参加をたてまえとして、全クラブ員が1つにまとまって盛りあげなければならない、と考えた。特に合宿は、サイクリングの醍醐味である長距離ツァーでもあり、また同じ釜の飯を食いながらの団体生活でもあるので大いに力を入れた。実際、我がクラブから合宿を除いたサイクリングは考えられない程、切っても切り離せぬ関係になってしまっている。
それからまた、普段のランに関しての必要参加条件として、年に3回以上参加しなければ我がクラブの会則第2条を誠意をもって示さない者だ、という判断をしてきた。これに該当しそうな者はノートに書いたり、個人的に直接会って、しつこく参加を促したつもりである。この数字に関しては、現在の会則第10条2項が全く空文化されてしまっており、条文を厳格に解釈することが出来ないので、この項を一応度外視して考えた結果、個人的に選んだ数字である。
これらのことは、様々なクラブ構成員が同次元において結束されるべき太い「絆」であり、またクラブの組織形態を維持する上で必要欠くべからざる不文律であるだろう。この現実原則たる不文律は組織という形態をとっている限り、必ずその構成員の個人間において問題にされ、また議論の的になるものである。今年も例にもれず、幾度かこの難題が表面に浮き上がってきたが、また必ず来年も出てくることだろう。キット出てくるに違いない。否、この問題はある1つの組織を構成する運動体には、必ず表面化されなければならない問題に違いない。
もし表面化されなければ、その運動体は全く活動していないのかもしれない。来年も大いに議論されるよう望む次第である。大分長くなってしまったが以上の様な方針で、この1年間様々な企画を行なってきたわけであるが、全部のランが全部員に満足出来たかどうか疑問である。細かなところまでは手が届かなかったが、不平・不満の点は来年のメンバーが既に気づいているかも知れない。その点は来年にまかせるとして、それでは簡単に今年の我がクラブを振り返ってみたい。
まず最初の仕事がフレッシュメンで賑わうキャンパスでの新入生勧誘であった。立看も去年までのは使えなくなり新しく作って、今年は写真もパネル板にして掲げた。囲りの他のクラブに比べて決して見劣りするものではなかった。勧誘においては、2年生に積極的に引っぱり込んでもらうようにハッパをかけた。俺としても2年生がクラブ内で、中心的活動をしてもらいたいのに、去年の活動状況からみるとちょっと不安でもあったので、とにかくどしどし仕事をしてもらって、2年生としての存在を自覚して欲しかったのであった。
今思うと、この勧誘は全て2年生がやってくれたといっても過言ではない程良く働いてくれた。あれよあれよという間にたちまち7・80名の新入生の名前が出揃った。俺もこれ程までに集まるとは予想もしなかったので、ただ驚くばかりだった。例年どうり新入生歓迎コンパには、そのうちの1/4の20数名が顔を見せてくれた。当初の頃、20名を越える新入部員が活動していたが、現在はその中の精鋭15名が元気いっぱいに走っている。我がクラブの中で1年生が最も多いので、俺としても非常にうれしく思っている。この15名が4年間ずっと我がクラブで活動してくれるのを願っている。
今年は最初のランとして、都内ランを行なった。これは新入生勧迎ランを前にして、一日も早く自転車に慣れてもらい、また集団走行に於ける走り方、車輛としての自転車に於ける交差点内の走行方法等を身につけてもらうために行なったのである。それからクラブランでは否応なしに都内を走らねばならないので、早く車の多い幹線道路の雑踏にも慣れて欲しかったためである。班を5つに分けてリーダー(2年生)の好きなコースをとらせた。初めて新入生と一緒に走ったわけだが、皆、真新しい自転車に乗ってとても楽しそうに走っていた。この企画は、演説の時に事故防止を徹底させると公約したのでその具体化であるが、この一日だけでも新入生はかなり自転車に慣れ、また親しむことが出来たのではないかと思っている。
5月に入って連休を利用して新入生歓迎ランを行なった。参加者は40名を越し、去年と同じヤビツ峠へ行った。「よし、やってやるぞ!」と前日から闘志を燃やしていたせいもあって、その晩は深く眠られぬまま目を醒ました。集合場所は大隈講堂前であった。光線にあたって目眩ゆいばかりの自転転車の側には、元気潑刺とした新入生を見ることができた。今年も例年通り第一日目のハイライトである大垂水峠アタックがあった。新入生にはちょっときついと見えて、力つきて歩き始めた者もいたが、玉の汗をかいてファイトを燃やしている1年生を見ると、非常に頼もしく感じた。
相模湖畔にキャンプして、2日目はヤビツ峠へと向かった。相変らず道が悪く、しかし舗装路の上を走るよりはましに感じるが、1年生はこのような山道の第1印象はどんなものであったのだろうか。ヤビツ峠をを一気に下り、今年は二宮の海岸まで足をのばして、そこでテントを張った。翌日は祭日と重なったため交通量が非常に多かったが、全員無事に東京へたどり着くことができた。この2泊3日のランで新入生は我がクラブのサイクリングというものをだいたい理解してくれたものと思う。下宿に帰ってから飲んだビールのうまさは、格別なものだった。
正丸峠ランは、今年も御多分に漏れず降雨に会って雨中ランになってしまった。去年は出発して間もなく降られて中止であったが、今年はテントに入って横になるや否や雨が襲ってきた。夜中からかなり雨足も強くなりビショビショのシュラフで夜をあかした。翌日は予定を変更せざるを得なくなり正丸峠をそのまま下って東京まで直行することにした。残った食料を近所の売店にやり、そのお礼としてだか何だか知らないが、とにかく貰ったカステラを各自1個づつ腹に詰め込んで雨の中を出発した。雨は依然として降り止まず、全員が濡れねずみとなり、まるでプールの中を自転車で突っ走っている感じだった。その時、濡れて重量を増したテントを運んでくれた1年生諸君には、本当に御苦労さんでしたと言いたい。
早慶戦の時は今年もクラブ員と一緒に観戦した。その頃まだ応援部員だった1年生の国友君からの折詰弁当と応援用の「日傘」のさし入れは、我々面々にとって非常にありがたかった。それから、今年は大局的見地からクラブを見つめて行こうという考えだったので、その1つとしてOBとの交流会を開きたいと思って、早慶戦の日を現役部員との合同コンパを企画した。東京近郊に在住しておられる先輩約30名に通知したわけであるが、月末でもありいろいろと忙しかったため回収率は非常に悪く「出席」と返事が来たのは5名程であった。しかし、いざ蓋をあけてみると、古川さんと中山さんの2名の先輩が見えただけであった。去年のOB会の時にこのような催しをやるからと一応話はしておいたつもりであったが、俺としてもちょっと残念であった。
月末という条件と、このような企画は過去に於いて全然行なわれていなかったため、気が揃わなかったのではないかと思われるが、今後も早慶戦の時にはOBとの交流会的な催しをやった方がいいと思う。今年は集まりが良くなかったが、来年もやってもらいたいように思う。出来れば恒例行事にしたいものだ。特に我がクラブでは、OBとの交流が全然ない(12月に開かれるのは、いやしくも「OB会」と名がついており、現役部員も限られている)ので、一緒に走らないまでも、せめてこの早慶戦の日には杯を傾け合い、当時のクラブの思い出話でも聞かせてもらいたいものである。
早慶ランでは、今年は慶応側の主催で道志渓谷へ行った。去年に次いで今年も1泊ランであった。泊まった相模湖畔の旅館では、慶応の3年生有志がビールを全員にふるまってくれた。3年間連続して、このランは雨にやられてしまった。まだ何か両校とも違和感が潜んでいる様な気もするので、やはり普段からお互い同志で接触をもつように心掛けたらどうか、と思う。サンノウへ行った帰りには、彼らの連絡場所として使っている喫茶店も近くにあるので、そこでコーヒーでも飲みながら、くだらない話の1つでもして来るようになって欲しいものである。
今年の合宿は、かねてからの念願だった2班分離制を採り入れ、山陰地方を中心にして松江から京都まで走った。例年通りの合宿ではただ突っ走るだけのツァーに陥ってしまう傾向を感じたので、今回は新しい試みとして小人数でまとまった、機動力ある弾力性に富んだ合宿をやろうと企画したわけである。2班分離性をどのような形態にするか、様々な案がでたが、結局これは最初の分離制でもあることから2班が同じコースを一日づつずらせて走ることにした。
2班に分ける際には、各個人の自由意志に委せて各班を構成させるのが妥当であるが、慶応等の班別走行を既に行なっているクラブの意見を基にして、今後のクラブ運営に支障をきたさないためと考え、こちらの方で分けさせてもらった。参加者は35名を数え、各班は17名前後の構成員だった。この2班分離の結果は、いろいろと議論の余地もまだ残っていると思うが、ただ例年に比べると各個人間に於いて、より親密さを増すことができ、厳しい団体行動のなかにもより楽しい家族的ムードで合宿ができたのではないかと、思っている。
それから、行動それ自体がスムーズに運び時間的にも十分余裕ができたことも今回の合宿の収穫であったと思う。ただ、器材の絶対数の不足からこれを補充するために運営資金の出費は、大分会計当局を悩ませ、また個人負担にも及んでしまったが、2班分離制が最初でもあったため、このやむを得ない事情を考慮して欲しいと思う。それからこの分離の結果、合宿後の運営にどのような影響があるのか懸念されていたが、現在の状況をみても思っていた程、何ら問題も起きないようなので、俺としては、自分で言うのも気がひけるが、まずは今年の分離制合宿は成功したと認めたい。
今年の合宿は何といっても、雨、雨、雨でこれには全く、開いた口もふさがらなかった。台風9号・10号に襲われ天候には全然ついていなかった。合宿には雨がつきもの、と言われるが、それにしても全行程の半分以上は完全な雨中ランになってしまった。第2日目の松江から美保関へ行くときは、台風9号をついて強風と打ち寄せる荒波のしぶきと戦いながら、飛んで来る小石や小枝から身をかわして黒雲で真暗になった視界の中をつき進んだ。この時は俺も美保関は断念しようと思ったが、合宿前に掲げたように「機動力」と「弾力性」に富んだ合宿を求めたので、思い切って強行策に踏みきった。
とにかく今までと違った2班分離制を採ったからこそ、決行できたと言えるかも知れない。案の定、下級生から批判を受けるに至ったがポタリング程度のサイクリングのイメージしか持ち合わせていない1年生には酷であったろうと思う。しかし、その時は冒険の連続であったが、今から思えば各人楽しい「思い出」になっているようだ。それからまた海岸でキャンプをした時、台風襲来の情報が入り、真暗闇のなかをテントをたたんで近くの小屋に全員避難する1コマもあった。ともあれ、毎日雨を気にしながら、次々とまき起る爆笑の渦を背にして全員が大きな事故もなく無事に、あの万博客でごったがえす京都駅まで完走することができた。これは、各人の規律ある行動・責任ある態度によって各班が一致団結してくれた結果だと思う。1年生も最初の合宿とは思えない程、元気一杯だった。特に大部分の1年生が、集合地の松江まで走ってきたという意気込みは、今後の我がクラブに於いて少なからず影響を与えるものと思う。
オープンサイクリングは、JCAに自転車のストックがなく、借りることが不可能だったため、クラブとして公的には行なえなかったが、2年生が結束してこの意義ある催しを実行してくれた。人数こそ少なかったが、成功のうちに無事終ったことは、まさに1・2年生の努力の結果であり、この積極的な態度は高く評価されるべきである。
恒例の早同交歓会は、第7回目を迎えて今年は10月30日から11月3日まで伊豆半島を中心にして行なわれた。参加総数は、両校合わせて70名にも達しようという大勢を集めて挙行された。前日から雨が心配されたが、4日間とも快晴に恵まれて、晩秋の伊豆半島は絶好のサイクリング日和りだった。大仁に集合して、各班ごとの自由行動形式で下田まで走った。ヒルクライムでの両校の激しいデッドヒートでは、同志社側に軍配が上った様だった。また呼び物の演芸大会では、毎年同じような相も変らぬ出し物が演じられ、爆笑の渦が幾重にも広がり、夜ふけの谷間にこだまして絶えることがなかった。最後のコンパでも両校の醜態ぶりが、まざまざと見せつけられ、はたしてこれはどちらに軍配が上ったのだろうか。この両校の親睦を深めるへ祭りとしての交歓会は、末長く続けられることを祈る。
東京 – 軽井沢間タイム・トライアルも例年通り早稲田祭の期間中行なわれた。早同交歓会が終ると間もなく早稲田祭に入ってしまい連絡の徹底を欠いてはいたが、それでも参加者が28名も集まったのは非常にうれしかった。(但し、実走者は23名)今年で3回目だが、年々レース熱を帯びてきており、誰がメダルを獲得するか、興味の的になってきたようである。レース展開としては、去年の木村さんのタイムはとても破られそうにないと思えたが、いざ蓋を開けてみると小泉さんが彼の記録を27分も短縮して、5時間11分という素晴らしい記録を出して優勝した。また新記録が上位4人まで飛びだすという熱戦だった。特に1年生の強さには目を見張るものがある。2位から5位までを独占し、しかも5時間台で走った10位までのうちで6人も顔を揃えているのである。今年は事故も無かったが、年々ハイペースで記録が更新されていくのは結構だが、くれぐれも交通事故だけは起こさないでもらいたい。
翌日は、半日ポタリングの後、今まで伸び伸びになっていた待望のソフトボールを行なった。都内では場所捜しで四苦八苦の状態で、も「話」だけで終っていたので、大学の広い私有地で皆元気いっぱいに初めてのソフトボールを楽しんだ。俺としても、今年こそは絶対にやるぞと思っていたので、この時公約を果たせて肩の荷が降りた様な気がした。
今年度の最後のランは、2年生の企画で御岳山へ自転車をかつぎあげた。去年の早同以来の「かつぎあげ」だったので、かなり苦しかったが、こんな企画も1度ぐらいは面白いものである。4年生も最後のランとして御老体にムチ打って多くの人が参加してくれた。
俺も帰路の青梅街道を走りながら、さまざまな事があったこの1年間の我がクラブもこのランを最後に終りかと思うと、何だかペダルも重く感じてしまった。解散のとき、全員で胴上げをされた瞬間、今までの苦労がいっぺんに吹きとんでしまった様だった。今年度も大きな事故もなく、全員が無事に走り通せたのも、クラブ員全員の協力と規律ある行動の御蔭だと思う。それから3年生を中心とした各役員諸氏の奮闘を心から感謝したい。特に企画を担当してくれた宮崎、「峠」の編集やランのたびにパンフを刷ってくれた編集担当の中山、会計を担当してクラブの運営資金の徴収に奔走してくれた高橋の3君、どうも御苦労様でした。
これからのクラブの発展と後輩の活躍を祈る。
奥武蔵グリーンラインラン – 政経学部1年 梅本
奥武蔵グリーンラインラン
政経学部1年 梅本
薫風吹き抜ける5月。ああなんとスバラシイ天気なのだろう。青梅街道の雑踏も何のその、黄色いユニフォームは真青な空と、緑に包まれ、白く浮かんだマシュマロ雲を供として一路正丸峠へと向かっていったのだ・・・ガシャーン!!!不気味な機械音とともに私の体は宙に舞っているではないか、自動車にひっかけられてしまったのだ。5m間隔で走っている時に急に横合いから、強制うんち吸い上げ装置付高級自動車が飛び出してきたのだ。うんちくしょう。私は道路に一回転してたたきつけられたが、運よくケガはなかった。ただ私がはいていたナイロンパンツ(これは股ずれができやすいのだが)がさけてしまったのだ。Gパンをはいていたら車にまきこまれてしまっていたかもしれない。正解であった。もう1つ正解なことは、ナイロンパンツの下にこん色の海水パンツをはいていたということだ。ああ、これをはいていず、真白の(私のはいつも真白である)普通のパンツをはいていたりしていたら・・・ましてや下着などをつけていなかったとしたら、ああ考えてもみて下さい。
我がかわいらしい青春のつぼみが、ちらちら風にゆられて顔を出すあり様を。いやであります。私は絶対にハダ色反対なのであります。
自転車は、と見るとハンドルが曲がっているだけである。これを直そうと、ハンドルのイクスパンダーボルト(というそうである)をしめすぎたのが悪かった。ねじを切ってしまったのである。『ポキーン』あの音の鮮烈なことよ、飯能まではどうにかもったが、とうとう走行不可能になってしまった。修理のため本隊から離れ、メカの及川さんとともに自転車屋を捜し回った。やっと我が愛車『みどり』号を直し、本隊に追いつこうと、名栗溪谷をぶっ飛ばした。快適である。にっくき自動車はやってこない。溪谷では、子供たちが無邪気に遊んでいる。
東京で生まれ育った私には考えられない程の別天地だ。緑が目にしみる、青空が手のとどくようなところにある。そしてシューシューといって通りすぎていく風..まてよ、風はシューシューといって通り過ぎていくのだろうか。5月の風である。せめて「そよそよ」ではないだろうか、やっぱりそうだ。シューシューといっているのは、愛車『みどり』のタイヤとガードがこすれている音ではないか。こんちくしょうと思って、ガンガンガンとにっくきガードを1蹴り2蹴り3蹴りしてやったら、やっぱり物理学的にいっても、たたかれたらそっちへハンドルが向くのは必至である。「ウアー!」という私の悲鳴とともに、「みどり」はドブに落ちてしまったのだ。私はまたもや投げ出された。自転車はと、またまたみると、リムがぐしゃぐしゃに曲がってしまっていた。それも両輪である。及川先輩のうらめしそうな顔、2人ともあっけにとられて、そこにすわりこんでしまった。
気をとり直して修理にかかったが大変なことである。タイヤをはずし、リムだけをとりだし、丸たん棒でたたき、石でたたき、どうにかこうにか円形に直してから組み立て、スポークの張りぐ合いを直すといったように、筆で書けば簡単だが、まったくいやになる程時間がかかった。どうにかこうにか直してすぐ出発した。日が暮れてしまってはもうどうにもならなくなってしまうからだ。
これ以後の難関は山伏峠だ。私にとっては始めての峠らしい峠だ。及川先輩はどんどん先へ行ってしまう。あの、すべてを抱摂してくれるような大きなオシリがみえないということは淋しい。
何度か降りようと思ったが、必死で頑張った。あの峠を征服した気持は、何にましても痛快だ。私は、何も利益があるわけではないのに頑張ること、峠を征服したって誰に自慢するものでもないのに、それでも必至に峠にいどむ姿が大好きだ。やっと峠をこえて本隊へ、皆心配してくれていた。夕食は例によってカレーライス。うまくてうまくて、自分だけが多く食べるのはいけないと思って半分以上残しておいた。皆の皿にもそれ位づつ残っていた。
夜になると雨が降り出した。そうとう強い雨である。さっそくテントに入ったのだが、そのテントも年期がきてしまっていて、ポタポタもってくる。ミスタータチマン(これはなんのことかいまもって分らないのだが)とあだ名される吉田先輩の赤裸々な、衝撃の告白が絶頂に達する頃には、私の下半身はしっとりと濡れてしまっていた。そして疲れて眠りについた。
翌朝目をさましてみると、まだ強い雨が振り続いている。予定を変更して正丸峠から、飯能へ出ることになった。『みどり』をいたわりつつ山道を降りる。ブレーキのききが悪い。前を走るは、快ケツイエローマントの丸山先輩、黄色のポンチョの影からは、キャリアにつけたメシたき用のおかまがちらちらと見えてくる。関口先輩から、ケツを貸すか(この言葉は、私の辞書には出ていないので解しかねる。)と言われたことが、頭をかすめた。後を走るは砂子先輩、東北弁の英語で愛の讃歌を唄っている。雨の中のサイクリングだが、楽しい旅ができた。飯能から所沢へ出て解散した。びしょ濡れになって帰ったときの家族のおどろき顔を見るのは、楽しいものであった。
このランで、2つの大きな事故を起こし、サイクリングのキビしさ、危険ということを身をもって体得した。高校時代の体育クラブのキビじさから逃避し、浪人時代からの自分の価値観の崩解からくる恐怖に少しでも目をつぶっていようと、サイクリングの世界へ飛びこんだのだが、そんなあまっちょろさはどこかへふっ飛んでしまった。あの峠での苦しさは何なのだ。立てなくなる程の苦しさは何なのだ。それに自分の価値観の問題は、どこへ行ってもついてまわるもので、目をつぶっていられるものではない。これからは、サイクリングその他を一生懸命やることで、自分の価値観・世界観を追求していかなければならないであろう。
最後にこのランで様々のことを心配して下さった諸先輩、同輩諸君、特に、及川先輩、里見先輩に厚く感謝し、筆をおくことにします。
早慶親睦ラン – 法学部1年 内田
早慶親睦ラン
法学部1年 内田
早稲田の勝利に終った早慶戦の興奮も冷めやらぬ6月13日、14日、今後は早慶サイクリングが神奈川県の道志溪谷、山伏峠において行なわれた。
このランは、僕にとって入部以来初めてのもので、前の晩は今月に入ってやっと完成を見た愛車を磨いたり、油をさしたり、専用のキャリアが未完成の為、古いやつを引張り出してくっつけたり、ネジ類をしめ直したりしていたものだから、1通りカタがついたと思ったら外はもう白んで来てしまっていた。こうなったらもう寝るわけにはゆかず、愛車を室から出して、ねむい目をこすりながら中原街道を一路早稲田へと向かった。家から早稲田まで約30キロ、2時間ほどで早稲田についた。ところが家を出たのが5時半頃だったから、当然7時半に着いてしまった。大隈講堂前には12時半に集合とのことであったから、それまで5時間はある。はて、どうしようと迷ったものの地下で寝ようにも開門前だし・・・そうだ保泉さんの下宿がそばにあったと思いだし、行ったものの、管理人のバアさんに
「保泉さん、まだ寝てらっしゃいますよ。何ならあんた行って起して来なさいよ」
などと言われ、それも保泉さんに悪いのではないだろうかと思い結局、大隈講堂の石段で横になることにした。すると、変なオッサンがそばに来て、
「よう、兄さん、その自転車高いのかい」
と僕の愛車を指して言った。僕は愛車が注目されたので、
「アッタリメェダアナ、トーエイだもん」
と言ってやりたかったが、早稲田サイクリングクラブの一員としては、
「マア、そんなに高くはないですね、ざっと10万くらいかなあ」などと答えた。
当のオッサンは目を丸くして
「ヘェー、自転車みたいなモンが10万もするのかい」
と世間が自転車に対して持っている最大公約数的な感想を残して行ってしまった。僕は機嫌が悪くなった。
6月13日、午後12時30分。大隈講堂前集合、ここから調布警察署で待つ慶応サイクリングクラブの人達と合流する為、甲州街道を下る。天気は大変良い、暑いくらいだ。アスファルトがまぶしい。不思議なことに、しばらく走っているうちに涙が出てくる。原因は車の排気ガスだ。排気ガスの恐さをこんなに身近に感じたことはなかった。
警察署の前には慶応の人達と我クラブ員も何人か待っていた。先ず、気になっていたテキの自転車はと見ると、やはりサンノウが主流のようだ。その他、マスプロ車やゼファーもあり、これにはシクロ・ランドネェル・ギアが装備されていた。聞くところによると慶応にはユニフォームがなく、僕もまだユニフォームをもらってなかったので、慶応のクラブ員と間違われやしないかと思ったりした。
今回は慶応側の主催ということで、慶応の主将挨拶の後、パンフレットが配られ、グループ編成も済み、いよいよ相模湖へ向けて出発。グループ編成は1班から8班までで早慶各半分ずつの割合。僕は1班で堺さん、丸山さんらと一緒。調布から府中、八王子をぬけて、いよいよ大垂水にさしかかった。ジワリジワリと勾配が増してきて段々と峠に至る、あの感じはいやらしいったらない。
僕達1班のトップは慶応の人だが、自転車がボロいにもかかわらず良く走り、飛ばすこと飛ばすこと、こちらは、はじめてのランでおまけに前日の徹夜がたたり、さんざんたるもので、途中まで何とかついていったものの、遂に見放され、後からヨタヨタくっついてゆく始末、まったく情ない。陶山君や平川君はさすがに強く、どんどん先に行ってしまう、僕の方は顔から汗、口からはヨダレを出して必死の形相でギアなども、チェンホイル30枚、マルティホイル24枚と全部落してこれなのに、後で聞いたら砂子さんなどはトップギアで登り切ったというのだからまったく信じられなかった。何の為に多段ギアをつけているのか分らなくもないけど、その脚力は大変なものだ。峠で記念撮影が行なわれたが、僕など無理して笑うのに苦労した。ここで欲んだコーラはウマイと思った。
上りの辛さに比べて下りの何と快適なことか。苦しい峠を歯を喰い縛って上がっているとき、ふと
『俺はなんでこんな所で苦しい思いをしなければならないのか』
などと自問したくなる。しかし峠を上り切って下りに向うときの、何んとも言えないうれしさは、こんな問を吹飛ばしてくれるだけの価値がある。
快適に飛ばして下り切ると、相模湖にゴール・イン。湖畔の大正館に落着くと、どっと疲れが出て室の中に座り込んでしまった。風呂で誰かが(我クラブの某先輩だと思ったが)女中さんをつかまえて、
「一緒に入りませんか」
などと、僕など赤面するようなことを言うと、この女中さん、
「入りましょうか」ときた。
風呂の後、2階の大広間で夕食。早慶各々交り合っての交換会である。各々、自己紹介などをやり、ドーイウワケか出て来たビールで、乾杯!!コップ一杯のビールで不思議に良い気持となり、応援歌の交換の時など、慶應の応援歌の時には、どうしたことか替歌しか浮かんでこなかった。食後、室割りもすんだので慶應の1年生と氷屋に出かけ色々と話をする。彼も相当自転車が頭に来ている様子で話が合う。彼のシクロ・ランドネェルは余り調子が良くないそうだが、ダブルワイヤー式ディレイラーは引きは軽いが、泥などにはデリケート過ぎるとの結論が出た。所詮、舗装率80パーセント以上の国で作ったものでは、それも仕方がないと言える。しかし話はそれるが、この辺の氷イチゴ、舌が真っ赤になって100円は高いんだなぁ。天気は余り良くない。
翌朝、6時半起床。案の定、空はどんより曇って雨もパラついている。8時40分出発。今日のコースは解散地、山中湖まで、途中全コース、フリー・ランとの事である。
小さなパン屋のショーケースをカラにしていざ出発、途中までは快適な舗装道路だったが、すぐに恐ろしい地道の登場となった。おまけに、バラスがバラまいてあるのでホイールが空転してしょうがない、ウォルベのタイアも減るだろうしイヤダ、イヤダ。そうは言ってもフリーラン、昨夜の友好ムードもどこえやら、両校負けてはならじと頑張っている。僕も腋野あたりまでは、慶應の3年生の後にピッタリコンとくっついていたのだが、情なや、メカニックトラブルに見舞われてしまった。カンパのグランスポルトは本来ダブル用に出来ているのに、トリプルにくっつけたものだからBBのシャフトの短さも手伝って、チェーンがインナーギアにデレイルしてくれない。結局、前48枚で走り続けた為に、こっちも足がメカニックトラブルを起こして遂にダウン。こうなると愛車もへったくれもあったものじゃない、
「コノヤロー!!肝心な時にぶっこわれやがってー!」
などと罵詈雑言を吐いていると、慶應の人が追いついてきて、
「だいじょうぶですか」
と声をかける。本当は、だいじょうぶどころではないのだが、ここで弱音は吐けない。
「ダイジョブ、ダイジョブ。何でもないんです」
などと手を振って答えた。どうにも直らないのでチェーンを手でインナーギアに固定して走ることにする。それにしても、メカニックトラブルというのは厭なものだ。
昼食は各自、自由にとのことだったので、通りすがりのパン屋に駆け込んで一休みすることにした。僕のそばには誰もおらず、ひとりその店先でパンをかじっていると、その店の子らしい5つくらいのジャリが出て来て、盛んに、
「牛乳買え、牛乳買え」
と言う。僕もちょうど喉がかわいていたので御要望どおり買って飲んでいると、さっきのジャリが、7つくらいの姉さんらしき女のしきりに僕の方を見ながら話をしている。僕も気になったので耳を澄ますと、どうやら関心は僕の牛乳にあるらしい。男の子が、
「あの兄チャン、牛乳残すかな」
と言えば、女の子は、
「ここで飲む人、皆、残すョ」
などと言いながらこちらを見ている。この子たちは、どうやら牛乳を飲みたいらしいのだが、商売物の牛乳は父ちゃん、母ちゃんから飲んじゃいけないと言われているのだろう。そこで、牛乳を買った人の、お余りを頂戴しているらしいのだ。
僕はそう考えると、何となく全部飲んじまうのはかわいそうな気もしたが、やっぱり全部飲んでしまった。それを見ていた2人は、がっかりした様子で、
「あれ!飲んじまいやがった」
僕は、何となく後めたさを感じてその店を出た。
日が出てきてホコリっぽくなった道を懸命に走っていると、突然後ろからこの世のものとは思えない異様な音が響いた。強いて、擬音語で表現すれば、『ホンゲー、ホンゲー』とでも言おうか、僕は背筋が寒くなるのを抑えながらこわごわ振り向くと…そこには何と、砂子さんが笑っていたのです。そしてあの奇怪な音は、砂子さんの自転車にくっついている、ラッパから発せられたものだったのだ。砂子さんはなおも笑いながら(少々サディスティックな笑いであったかもしれない)
「ヨォ!内田どうした。抜くゾ」
と言いながら僕の背後にせまって来た。ここで抜かれては男がすたるとばかり、足の回転を早めては見たものの、所詮、僕は砂子さんの敵ではなかったようだ。あのラッパの音と共に僕はあっさり追い越されてしまった。不思議なことに、抜かれたとたん全身の力がへナヘナと抜けてしまい、後は抜かれ放題に抜かれてしまった。憶えているだけでも、平川君や慶應の人など5人はいた。ああ、情ない。
だいぶ抜かれはしたものの、無事に山伏峠も上り切り、60キロ余りのフリー・ランも終りに近づいた。峠で皆と合流し、一路山中湖へと向かう。湖に近づくにつれ、また雨が降って来たが舗装道路で助かった。今日は日曜の為か、サイクリングをしてる人も多い。通り過ぎるとき手ぐらいはお互いに振りたいものだ。ミニスカートでミニサイクルに乗っている勇敢な女の子もいた。こういうのと出会うと事故の発生率も違ってくるのじゃないかな。
午後3時ちょっと過ぎに、全員無事山中湖に到着。中に、大分遅れた者もいたが事故がなくて本当に良かった。解散まで少し時間があったので、陶山君や中丸君と湖をバックに写真を撮っていると、突然砂子さんが、着ているものを脱ぎ始めた。僕はただ啞然として、コンパでもないのにどうしたのだろうと思いながら見ていると、
「ボクチャン、泳いでくる」
というなり雨の山中湖に、ザンブとばかり飛び込んだと思うと、
「ちょっと、山中湖、横断してくる」
と言い残すなりスイスイと沖に向かって泳ぎ出した。聞くところによると、砂子さんは、水と見れば、雨後の水溜りでも泳ぐそうだが、いくら何でも、あれだけ走った後では、心臓麻痺か何か起こして溺れ死ぬのではないかと思い、皆で、
「止めた方がいいですよー」
とどなったが、本人は手を振って余裕たっぷり。この分では本当に向こう岸まで行ってしまうのではないかと思っていると、100メートルぐらい行ったところで、急にこちらに向かって帰ってくる様子だ。
「あれっ、どうしたのかな、帰ってくるぞ」
等と話していると、途中で会った、水上自転車の子供達と何か話している。どうやら競争しようということらしい。皆で、
「砂子さん、やーり過ぎ」
時間は、途中まで5分と5分であったが、最後は、やはり機械力の方が強かった。まあ2対1だったからしょうがないが。砂子さんが湖から上がって来たので、
「どうして途中で止めたんですか」
と聞くと
「ああ、疲れちまった」
と言う。僕は安心した。やはり砂子さんも人間だったのだ。
そうこうしているうち、全員が到着したので、解散式が開かれ、両校クラブ員の健闘を称え、来年の再会を約束した。この早慶ランは、僕にとって入部後初めてのものであったせいか、かなり強烈だった。特に、慶應との合同ランということで、少々緊張気味ではあったが、来て良かったと思う、学校は違うが、同じくサイクリングが好きな連中と話し合うことができたし、ある程度、自分の脚力も分ったような気がする。と、ここまで書けば、もう終りと思うでしょう。確かに早慶親睦ランのレポートは終りですが、もう少し書かせて下さい。
解散式も終り、あとは各自、家に帰るだけとなったのですが、何を間違えたのか、僕は陶山、中丸両君と自転車で帰ろうということになってしまったのです。今思えば、若気の至りとでも言いましょうか、止めておけば良かったと思います。
とにかく、御殿場までは皆と一緒に行くことにしたのですが、途中、雨はザアザア降るし、御殿場特有のガスで、まるで雲の中を走っているようでした。御殿場についても雨は上がらず、いよいよ勢いを増すばかりでした。大部分の人は輪行袋に自転車を蹴り込んで、スマートに電車で帰って行ったのですが、僕はそんな気のきいたものを持っていないし、一旦行くと言ったものを引込める訳にもいかないので、覚悟を決めて出発することにしたのです。ポンチョがなかったので、立石君に借りたのですが、これが後に、僕の生命を危くするなどとは夢にも思いませんでした。
とにかく、国道246号線を一路東京に向けて、皆の声援を背に受け出発した時には既に5時を回っていました。
雨は増々ひどくなり、ポンチョに音を立てて降り注いだ。そして魔の一瞬は刻一刻と近づいていた。トップを中丸君、2番目を陶山君、シンガリを僕という順に走っていた時、御殿場を出てから1時間くらい経っただろうか、小山あたりの下りで快適にとばしているとき、それは起こった。
一瞬、僕は誰かに首を締められたのではないかと思った。何しろ猛烈な勢いで頭が後に引張られ、上体がのけぞり、ちょうど、脳天逆落しをくらった形になったのだ。危うく転倒だけはまぬがれたが、愛車もろとも横倒しになった所へ鋭いクラクションと共に、車がすり抜けた時にはもうオダブツかと思った。やっと気を取り直して、一体全体、何が僕をこうさせたのかと見ると、何と、ポンチョの紐がマルティホイールに引っかかってダンゴみたいに巻きついているではないか。これでは、もし僕が沈着冷静に急ブレーキをかけて、愛車を倒していなかったら、モロ脳天逆落しを決められて、クラブに50万円の特別収入が計上されていただろう。陶山と中丸両君は、何せ下りのことでもあるし、姿が見えるうちに声を張り上げて、
「オーイ!!待ってくれえ」
と怒鳴ったが、あっという間に見えなくなってしまった。雨の中、やっとのことでホイルから、からみついた紐を取って2人を追いかけた。
教訓、ポンチョの端はヒラヒラさせないこと。しばらく行くと、2人が心配顔で道端に立っているのが見えた時は、ホッとした。中丸君が、
「お前、あんまりこないから道にでも迷ったのかと思ったよ」
と言う、通りがかりの車に僕を見なかったか尋ねてくれたらしい。本当に申し訳ない。山北を過ぎて松田に入るころには、もうまっくらになっていた。松田でメシを食い30分ばかり休む。茶がうまい。店で一緒になった人が、
「オートバイかい」
と聞いて来たので、
「いや、自転車です」
と答えると、
「ホウ、若い人はいいねえ」
と言う。確かにこんな事は、若いうちしか出来ないかもしれない。
雨は既に、降るという状態を通り越して、まるで泳いでいるようだ。フロントバッグにかけたポンチョの上は見る間に水溜りとなり、こぼすと、ジャーといってこぼれる。目はとびこんでくる雨でほとんど開いていられない。盲運転に近い。車が脇を通るたびに、バシャーと水をぶっかけてゆく、こうなると雨具など有って無きがごとしだ。それにつけても国道246号線は、上り下りが激しい、これが1番こたえる。ヒイヒイ言って上った分だけ下るのはホントにもったいない、泣けてくる。
やっと厚木にたどりつき、ここで中丸と別れる。中丸君、ごくろうさんでした。
このあたりになると、大分家が近づいた感じがする。幸い雨も小降りになり、ポンチョを脱ぎ棄てて、陶山君と快調に走る。まったく雨が降ると降らないのでば、こうも違うものかと思った。ところが快調に来たのは良いのだが、どこかで道を間違えたらしく、いつの間にか国道246号線から外れてしまった。幸い大和市のあたりで、以前通ったことがある道だった為、再び国道246号線に出ることができた。もしこれがまったく見知らぬ土地で、こんな夜中に迷ったとしたら(おまけに地図もなく)目も当てられないところだ。
既に出発してから6時間余、80キロばかり走った。そろそろ横浜に入る。この旅も終りに近づいた。市ヶ尾に、0時着、陶山君とはここで別れる。彼は川崎だから僕よりもう少し走らねばならないだろう。陶山君ごくろうさん。
陶山君と別れて僕は家へ向かう、足は既に、僕の意志とは関係なく動いている。雨はまだ降り続く。0時30分、家に着く。御殿場から約90キロ。
翌日、愛車をバラして、フレームを逆さにするとパイプから水が出て来た。
第3回東京-軽井沢タイムトライアル – 政経学部1年 安田
第3回東京-軽井沢タイムトライアル
政経学部1年 安田
今年の軽井沢タイム・トライアルは早稲田祭期間中の最後の3日間を使って行なわれた。
第1日目<11月9日>
パンフレットには、7時30分集合、8時スタートと予定ではなっていたのだが、今朝も集まりが悪く8時30分スタートとなってしまった。出発間際に主将が、「お前は3番候補だ」と言われたので、「よし」と思って出発した。僕と立石君が最初に、2番目が岡田君と加藤君、3番目が平川君と陶山君と1年から2人ずつ、2分置きに出発することになった。僕が家から戸田橋の方へ下ってきた時には、車はかなり混雑していたが、逆に高崎の方に向かって行く時には、あまり混んでいなかったように思われた。僕と立石君とは互いに、信号にひっかかる度に先頭を入れ換わるようにして走った。それでも立石君はかなり速く、僕などは付いて行けない位の速度で走っていた。
大宮あたりでは本当に疲れて「これで軽井沢まで行けるのから」と思った。しかし、僕が中学時代に長距離の伴走をした時に「マラソン選手は最初にくたびれる程走って、あとはその疲れにまかせて無意識のようにして走る」ということを言われたのを思い出し、このまま平均した速度で走ろうと思った。大宮市街を少し過ぎた所で、立石君が後ろについているのだろうと思って後ろを見ると、なんと岡田君であった。彼は今日、非常に張切っているように見えた。身をすこし丸めてネズミを狙う猫のような格好で走ってきた。
しばらくすると今度は平川君が後ろについてきた。平川君と僕との差は4分もあったのに。4分といえば少なくとも1キロは離れていたと思われるが、余程飛ばして来たのだろう。平川君の後ろから付いて行くと、あの力強い、グィグィとこぐ様子がよくわかる。道理で強いはずである。
しばらくして僕たちの横に1台のバイクが付いて来た。『誰だろうな』と思って見ると及川さんであった。僕たちの前後を行き来していたが、「あまり飛ばすと峠でバテるぞ」と言ってくださった。
うれしい助言であった。そのままだんだん行くと、何だか落ち着かなくなってきた。そう生理現象である。だが小便が出来そうな場所はなかった。あたりはほとんど田んぼである。まさか自転車を置いて2、30mも駆けて行く訳にはゆくまい。ここら辺で、ここら辺でと思ってもなかなか決心がつかず、困ったなと思っていたら、平川君が、「安田、この辺で休まんか」と言ってくれたので助かった。ドライブインに入って7分位、休みを取った。用たしや準備体操などをやっている間に岡田君が通って行った。平川君の言うのには陶山君も立石君も先に行ったそうである。さて出ようかなとした時に中丸君がやって来た。中丸君はしきりに「疲れた、疲れた」を連発して走っていた。休もうかと言っても、「ああ」と言うだけで一向に休もうともしない。なかなタフである。熊谷の交差点で、
「安田、何か食うもの持っていないか。俺、今日、何も食ってないんだよォー」
「リンゴならあるぜ」
と言ってリンゴを分けてやった。僕のとなりに止ったダンプの運ちゃんが、「速いなあ」などと言って首を傾げた。僕はドライブインで買ったチョコを頬張りながら走った。2、3分差だというのに先に行った者の姿は全然見えない。30キロ近く走ってやっと陶山君の姿を見た。すると中丸君は俄然スパートし出した。僕はタイツを脱ぐためにちょっと休んだ。しばらく走って、県境のあたりにくるとお巡りさんがたくさん立っていた。大宮かどこかその辺でもたくさんいたが、『何か捕物をしているのかなあ』などと思ったりした。
さていよいよ埼玉県に別れを告げ、群馬県に入る。県境を1つ越えただけで、あたりで作られている作物が変っていたのはおもしろかった。10キロ位走ると、高崎市内と市外との分れ道にぶつかった。地図を広げて見たが、あまりはっきりしなかったので、こっちだろうと思って市外へ向っている道を行った。すると、「オーイ、安田」と声がしたので、河原の方を見ると立石君が河原から出てきた。随分休んだらしく、昼飯を済ませていた。なかなかよい所だったので、僕もここで昼飯をとることにした。おにぎりを半分位、食べた時、中丸君と薄青いタイツをはいた人が走って行った。続いて立石君、それから加藤君。(これは僕にとって意外というしか仕方がなかった)がベルを鳴らして通って行った。これは負けちゃいられないと、おにぎりの2つ目をやめて僕も出発することにした。すると先程と同じ様なお巡りさんがあちこちに立っていた。
僕の計算では高崎・松井田間16キロを1時間と見積ったが、40分前後で走れたのは意外であった。ここら辺が、急に緩やかな上りとなっていたので大宮あたりと同じく苦しかった。でも誰でも苦しいのだと自分に言いきかせて頑張った。安中と松井田との中間地点あたりで加藤君に松井田市街で立石君に追いつた。ここで先に行ったのが中丸君と小泉さんであるということを知った。さすがは小泉さん!しばらく行くと中丸君がドライブインのところで腰を下ろして、
「休んでけよォー!」と声をかけた。
「先に行くぞォー」と返した。
だが小泉さんの姿は全然見えなかった。
さていよいよきつい上り坂。もうとっくに確氷峠に入ったのだろうと思って上って行ったら、「これより確氷峠―8000曲り」という看板を見て急に力が抜けた。ここら辺が今日3回目の苦しい折だった。20カーブあたりのドライブインで立石君と一緒に休もうとしたとき、後ろから小泉さんが上ってきた。「あれ?僕より後だったのかな」と思って聞いてみると、
「中丸とドライブインで休んでいたよ」
と言われた。牛乳を飲みたかったのだが、牛乳だけでは僕の体が受けつけない。それでジュースをグイと飲んだ。この坂で小泉さんに勝てれば他の人よりは速く登れると思った。6、70あたりのカーブで小泉さんに勝った。これでひょっとしたら1番でゴールに入れるのではないかと思った。130から140あたりのカーブは内側が急で非常に上りずらく、胸がやけて気持ちが悪かった。140を過ぎたあたりから、40、39、38と逆に数えて登った。話の中で皆んなもこのような数え方をしたと言っていた。やはり心理状態は誰も変わらないものである。あとカーブが10位になると急に元気が出て、3、2、1ときた時には何とも言えないような気分だった。
峠からゴールまでかなりあると思っていたのに、すぐに着いてしまってあっけなかった。しかし、帰り自転車に乗って帰る時には都合が良いだろうと思った。ゴールでは吉田さんがタイムを取っていた。しかし、記録では小泉さん。私。中丸君。立石君、、となった。ミーティングの時、記念のメダルを貰った。小学校以来このかた、駆け足ではいつもびりだったので、それだけよけい気持がよかった。
第2日目<11月10日>
今日は、峰の茶屋 – 分去茶屋 – 鬼押出しと行って午後ソフトボールをする予定である。朝9時に友愛荘を出て、チンタラチンタラと峰の茶屋まで上って行った。それから分去茶屋までのダウンヒル。ここは非常にすばらしく、ひさしぶりにそう快な気分を味わった。こういうものがサイクリングの醍醐味というものであろう。ここで内田君の愛車がこのラン2度目のパンクをしたのは、内田君にとっては残念であったろうと思われる。このパンクですこし時間がかかったので、鬼押出しに行かずに、このまま帰ってソフトをやることになった。僕はソフトをやりながら、もしこういったことが1年生が入ってきた時に持たれていたら、もっと早く先輩の名前などを覚えることができ、もっと早くクラブに溶込み、もっと気軽に(良い意味で)話しができるようになったのではないかなあなどと思った。皆んなこのように考えたり、思ったりしたのではないか。鬼押出し、浅間牧場の方も行ってみたかったが、身体は1つなのであるから、やはりオールタナティブな行動をとるより仕方あるまい。一応今日でこのランは終った。あとは帰るだけである。
第3日目<11月11日>
この日はこのトライアルが始まる前から乗って帰ると決めていたので、1人で帰る予定だったのだが、砂子さん、陶山君、岡田君それに加藤君が乗って帰るというので僕も加えてもらった。立石君も輪行袋で帰ると言っていたのだが、結局は僕たちと一緒に帰ることになった。朝9時友愛荘を出発。出発してからちょっとたって雪がチラチラ降ってきた。さすがは軽井沢だ、11月半ばにして初雪が見られるとは。かなり寒かった。峠を下るときに強風が吹きつけ、木の葉や木の枝が飛んできて顔などにあたって痛かった。僕などは前から車がきた時、両目にごみが入って「危うく遭難地獄行き」という破目に合うところだった。でも強風のおかげで、木の葉が風に舞って、あたかも蝶々が飛んでいるかのようで、とてもきれいだった。山の景色は昨夜の雨に洗われたせいか、紅葉、それに紅葉と常緑樹との対照が実にすばらしいものであった。妙義山の姿も紺一色でなかなかいいものであった。左右に山河を、上下に天地を見ながら、一路東京へと向かったのであった。
僕は1度通った道をもう1度通ってみて「こんなところあったかなあ?」などと思うのが好きなのであるが、来る時にまわりの景色をあまり見ずに走って来たので、見たこともないような景色がたくさんあって結構楽しかった。やはり走る方にばかり気が取られてしまうと、まわりの景色は見られないらしい。
帰りは道もやや下りで、強い風が吹いていたので、あまり疲れも感じずに家に帰ることができた。浦和着5時。所要時間8時間。県庁の前で皆んなと別れた。無事故(パンクはしたが)で帰ってこられたのは何よりもうれしいことである。
最後に一言。出発時に及川さんが、同志社を見習えよと言っておられましたが、まさにその通りであると思う。集合時間にちょっとルーズなような気がすると思います。時間をもう少し守るようにしましょうよ。
第7回早同交歓会 – 商学部1年 陶山
第7回早同交歓会
商学部1年 陶山
プロローグ
僕は生まれてからこの方、文章といえる様な物を書いたことがない。せいぜい私用ノートに書く戯言程度である。小中学校の時、作文の宿題などは、いつでも母に代役をつとめてもらっていた。僕はそれを原稿用紙に、
「この字何て読むの?楷書で分り易く書いてよ」
などとブツブツ言いながら写し、自分の名前を平気で書いて先生に提出した。その文章がよく作文集やPTAの会報などに載ったものである。だから僕が文章を書いても支離滅裂なつまらない物になってしまう。がしかし、この『早同交歓会』なる文章は、1ヶ所たりとも母の手は加わっていない。僕が1人で書いたものである。言わば僕の童貞作である。つまらないだろうが最後まで読んで下さい。
僕達5人(保泉さん、吉田さん、関口さん、立石君、僕)は東京から、今回の集合地、伊豆の大仁まで、ペダルを踏んで行くことにした。それだけなら別にとりたてて書く程のことでもないが、その途中、思いもよらない滑稽な、いや不幸な事故があったのである。この事故の真相は僕達5人が、心の隅の深い深い所にしまっておく筈だったのであるが、この童貞作を少しでも面白くする為に、保泉さんには気の毒だが犠牲になってもらうことに決定した。
それは僕達5人が小田原市内に入った頃でした。あたりはもう日も落ちて、すっかり暗くなっていました。5匹の腹ペコ狼達は(中にはゴリラも何匹かおりました)早いとこ吉田さんの家に辿り着いて御馳走にありつこうと、あせってペダルを踏んでおりました。吉田さん、関口さん、僕、立石君、保泉さんの順に走っていました。僕の前で、2匹のゴリラが、
「今夜の夜食に、好物のバナナでも買っていくか」
などと言って果物屋さんの前に止った時です。後で「アッ」という声がしました。振り向くと保泉さんが口をポカンとあけて、びっくりした様な顔をして立っているのです。そして暫くしてから何かわめき始めました。しかし僕達には、保泉さんが何を言っているのかさっぱり聞きとれません。ただ口をモグモグさせているだけなのです。よく見ると前歯が2本ばかり欠けている様子でした。そして口のあけ具合とジェスチャーから推測すると、前のブレーキを急にかけた為に、前輪を支点として、自転車が半回転した時、地面と強烈なキッスをしたらしいのです。僕達は困ったことになったと保泉さんに同情しました。しかし、どこからともなく笑いがこみ上げてくるのです。その笑いを必死にこらえながら、歯医者に行きました。保泉さんが治療をしている間、僕達はスーパーマーケットの前に腰をおろし、カッパえびせんをパリパリやりながら、
「おなかがすいたなあ」
とうらめしそうに歯医者の門の中を覗き込んでいました。暫らくして保泉さんが、前歯がきれいになくなった顔で出て来ました。とても複雑な表情をしていました。そしてやっと晩飯、いや吉田さんの家に到着です。台所では吉田さんによく似た(?)綺麗な妹さんがお母さんの手伝いをして料理をしていました。僕は適当に遠慮などしながら、おなかがパンクする程食べました。保泉さんは、と見ると、吉田さんの妹さんの方を気にしながら、とてもやりにくそうに食べていました。
さて次の日の夕刻、僕達一行は急な坂を登って、伊豆臼井ユースホステルに着いた。そこではもう、両校の人達が親しそうに話していた。薄暗い部屋の中で最初に同志社の人達を見た時、脛にはもじゃもじゃの毛、顔にももじゃもじゃの毛、
『こんな人達と一緒に何日も走ったり、寝たりするのか、恐ろしいな』
と思った。しかし、自己紹介をしたり、話をしたりしていると、みんな関西弁でおもしろいし、ピーターに似ている人とか、妹さんが岡崎友紀だという人などがいて、おもしろい人ばかりだ、ということが分った。
11月1日
朝、自転車を点検していると、同志社の塩出さんが、どう勘違いしたか、1回もパンク修理をしたことのない僕に向かって、パンクを修してくれ、と言った。兎に角ものはためしだ、1回やってみることにした。チューブをやすりで擦っていると、横から誰かが、
「そんな、女の子を撫ぜるようなやり方じゃ駄目だよ。もっとゴシゴシやらなくちゃ」
などと、いろいろうるさい。やっとパッチを貼り、一応チューブを収めてさあ、出発。参考までに付け加えておくが、塩出さんは出発したすぐ後で新しいチューブを買ったようだ。
この日は、峠を2つ越えた。国士越と天城峠である。同志社の人達の脚力の強さには、びっくりした。やはりよく食べるだけのことはある。
今晩は、かの悪名高き『芸能大会』が催される。民宿に着き、夕食が済むと、みんな、いくつかのグループに別れて、出し物の打ち合わせの為、部屋に入って練習だ。時間は30分しかない。何をやろうか、と僕達早稲田の1年生が、額をあつめて考えぬいた結果、結局落ち着く処に落ち着いた。
いよいよ蓋を開けてみると、前々から先輩達に聞いていたとおり、それこそもう、エロ、グロ、ナンセンスのエッセンスである。僕達もこのエログロなんとかをやった。炬燵の足やごみ箱なども持ち出して、それが壊れる程の大熱演だった。よくもまあ素面で、あれだけやれたと我ながら感心している次第です。しかし僕達の中には、かなりの演技派もいて、この後度々話題にのぼった。
11月2日
この日は、朝から心臓はドキドキ、胸はワクワクだった。午前中にヒルクライムがあるからだ。僕は幼い頃から、およそ競争と名のつくものは苦手だった。運動会の徒競走などは、ビリにはならなかったが、賞品などもらったことがなかった。この日もやはり駄目だろうと思った。そう思ってみても、やはり競争を意識している。やたらにソワソワして、準備運動をしたり、何回もオシッコをしてみたりした。(僕は緊張するとオシッコが近くなるたちなんです)
スタートは班別に5分間隔である。僕の班は後の方である。前の方の班が次々に出て行く。いよいよ僕達の班がスタートラインに並ぶ番だ。そしてスタートの合図を待つだけであるが、この間が1番いやだ。心臓はいまにも破裂しそうである。
「ヨーイ、ドン!」
がむしゃらに飛び出した。他人と並んで走っている間は、無我夢中である。しかし、みんなと離れて、独りぼっちになると、競争意識も消えて、『紺碧の空』など歌っている。時々、この道でいいのかな、なんて思ってラッパをプカプカやりながら走って行った。もう賞品をもらおう、などという野心は消えていた。暫く行くと、4年生の斉藤さんに会った。僕も降りて、斉藤さんと一緒に歩きだした。
「おい陶山、お前ガンバレば、けっこういい線いくかもしれないぞ」
「そうですか、そんなことないですよ」
と精いっぱい謙遜した。
「いや、ひょっとしたら、何かもらえるかもしれないぞ。ガンバレよ」
この一言がきいた。
「ひょっとしたら」
と思いつつ、素直な僕は、再び自転車にまたがって俄然ハッスル。少し走ると向いの山の中腹からラッパの音がプカプカ聞こえ、みんな手を振って、何かわめいている。
『何だもうゴールか、これじゃひょっとしてもひょっとしないな』などとわけのわからぬことを、独りブツブツいいながらゴールを目指して走った。だがなかなか着かない。あのカーブの向こうかな?などと何回思ったかしれない。峠の上り道特有の、あの胸をワクワクさせるカーブの連続である。やっとゴールである諸坪峠が見えた。
僕の前を走っていた2人が、
「おい、同時にゴールインしようぜ」
「よし」
「絶対に裏切るなよ」
などといいながら、ノロノロノロ、その横を風のように(?)通り過ぎて僕はゴールイン。ゴールに入ると、もう大勢集っている。
ああ、やっぱりひょっとしなかったなあ、とガッカリ。しかし僕達の班は終りの方に出発したので思ったより、成績は良かった。嬉しいことに宿に着いてから賞品まで戴いた。賞品はスパナのセットであるが、なまじ英国製の為、ペダルを廻すことしかできないしろ物だ。
遠くに富士を見ながら、碧い海を目指してほこりっぽい地道のダウンヒル。僕達の班が民宿に1番のりをした。日あたりの良い砂浜で、野球をしたり、泳いだりした。(11月だというのに海の水はとても暖かだった。おまけにきれいだった)
みんなが集ってから、船で波勝崎のサルを見に行った。オサルさん達はみんな(といっても雄だけ)股間に大きな、郵便ポストのような色をした袋をぶら下げて、ガニ股でクロウロしている。あんなに大きなものをぶらさげていたんじゃ、木登りをしたり、森を走りまわったりする時、ぶつけたり、すりむいたりして不便じゃないのかな。などと余計な心配をしていると、猿と仲の良さそうな説明係が、走りまわる時には、中の玉がヒョイと体の中に避難するんですと言った。僕はよくできているもんだな、とつくづく感心した。
参考までに、以前小耳にはさんだ話だが、人間のものも咄嗟の場合は、ひっこむのだそうである。君は以前、キャッチボールなどをしていて、タマがタマに当りそうになると、その瞬間、タマの方がタマをよけて、当ってタマるかと、ひっこんじゃったのを、タマタマ経験したことない?
宿では夕食後、学年別のミーティングをした。クラブの話や、パチンコはどこそこがよく出るとか、早稲田にすべって、仕方なく同志社に入学したとか、いろいろな話に花が咲いた。同志社の1年生とも親しくなり、1年後に再会するのがとても楽しみになった。その後みんな風呂に行ったり、雑談などをして時を過ごした。寝る前に外の風呂から帰ってきた人に聞くと、何でも男女混浴だったとか、若い女の子がいたとか、見えたとか、見えなかったとか言うのである。僕も行けば良かったとくやしくて、もったいなくてその夜は熟睡できた。
11月3日
この日の午前中は、海岸の崖っぷちの幅が1mそこそこの道を通って行った。目の下は、波が岩にあたって白くくだけているが、もし落ちても途中の木にひっかかって、助かるだろうと思うと気が楽だった。しかしこの道からの風景はとても良く、リーダーの里見さんが、
「ここで写真をとりまーす」
と言った。
石廊崎をまわり下田の旅館についた。僕と塩出さんが1番に風呂に飛込む。いい気持ちでつかっていると、中で塩出さんが、
「1番風呂で小便したら、気持ちええやろなー」
と言ったので、あわてて風呂から上った。落ちついてから下田の町をぶらぶら歩くことにした。先輩の後にくっついてゆくと、「了仙寺」というお寺の前まできた。入口に風呂屋の番台みたいなものがあり、そこには「18才未満入場お断り」と書いてある。何だかわけがわからなかったが、僕も18になったことだし、入場料を払ってとにかく中へ入ってみる。中には、ためになるもの、面白いもの、わけのわからない気持ちの悪くなるものが、たくさんウィンドーに入っている。このお寺を見物しなかった人は、ぜひとも下田に来た際には、立ち寄ることを勧める。とにかく何かの役には立つかもしれない。
そして夜、コンパである。今日で予定の全コースを走り終え、全員無事に到着したことを祝い、又早稲田と同志社の交歓会をいつまでも続けていくことを誓って乾杯した。ビール、清酒からトリキン、焼酎までありとあらゆるアルコールが用意され、次第にみんなは酔いが回り、歌ったり、踊ったり、走り廻ったり、それはそれは大変な騒動である。しまいには旅館のタヌキおやじが、食器をこわされては1大事と、ものすごいけんまくで女中に命令してかたずけさせている。みんなは酔っているので、一向に構わず騒いでいる。そしてそのまま、夜の下田の町へと出て行った。道路を走り廻る者、通る車を止めて、8つ当りしている者、歩きながら、大声を張り上げて歌をうたう者、下田の町は早稲田と同志社の若き自転車乗り達に、ひっかきまわされていた。
11月4日
1夜明け、赤い目をこすりこすり起きて、あたりを見まわすと、みんなはものすごい格好で寝ている。天井には醤油に染ったパンツが1枚ぶら下がっている。(何だアリャ?)
朝食が終るとみんな身仕度をして荷物をまとめ、自転車にそれをとりつける。そして、東へ西へと、手を振り大声をあげながら別れてゆく。
「気をつけてなー」
「来年も元気で会おうぜー」
たった4日か5日の間で全く知らない者同志、こんなに親しくなれたのは、サイクリングというスポーツを通して、一緒に寝泊まりしたからだと思う。そしてそれは若者であればこそできたのだと思う。
最後に、早同交歓会がいつまでも続くことを祈って筆を置きたいと思います。
同早交歓会に寄せて – 同志社大学2年 玉置
同早交歓会に寄せて
同志社大学2年 玉置
伊豆!これ程夢とロマンをそそる地名があろうか。「伊豆の踊子」という国際的な物語をも生み、また大衆に親しまれる流行歌にも数限りなく歌い込まれて来た伊豆。この伊豆で第7回同早交歓会が開催されるという。我々同志社のロマンチスト達は、果てしない期待を胸に、大仁駅前に三々五々結集した。この期待が同志社サイクリストの面々に如実に出ていたのを見てもらえたと思う。
喜びが隠し切れずに、そのままさっそうと臼井YHへ。早速その夜の自己紹介。この場の打ち解けたムードはとても尋常のものとは思えない。この交歓会を全然知らないはずの1年生でさえ、またたく間に豪笑の渦の藻屑と化したのは、やはり伝統のなせる業か。改めて、伝統の偉大さとそれを生むべき日常性の重要さが身にしみる。尽きない話題と笑いのうちに交歓会の幕は切って落とされた。
翌日からのツーリングは「伊豆」に胸ときめかす我々に優しく応えてくれた。国士越から仰ぎ見た駿河湾の彼方に霞む富士の山。恋に身を焼いた乙女が女郎脚妹となって住むという浄蓮の滝。もみじ葉のトンネルを額に汗して登り切った天城峠。束の間の夢とは言え、想いを寄せたあの娘が踊子の姿で俺に微笑みかけたのも、天城にまつわる忘れ得ぬ思い出。
この夜は例によって例の如く、並の破廉恥を数倍した程の破廉恥で両校の馬鹿さ加減を競い合う。湯浅氏の流し目や関口氏の露出癖は今なお健在であり、人を食った様な吉田氏の話し振りにも我々は素直に脱帽した次第。
翌日のハイライトは何と言っても、急坂に脚力を競ったヒルクライム。芸能大会での汚名を挽回すべく我々は奮起して、実力の程をまざまざと見せつけた。こと脚力に関しては日頃のトレーニングが物を言い、平均レベルは早稲田を圧倒していた様である。
そして最終日。雲見から奥石廊への崖っ縁、石廊崎からへいげいした風に荒れ狂う太平洋等々を胸にたたんで最終地・下田へと輪を進めた。真夏の昼寝に見る夢の如き交歓会の短さを恨みつつ、しかし早くもこの夜の大コンパを思い描いたのは親譲りの酒好きのせいか。尽きない名残りをこのコンパにぶつけ、ほとんどの者がしたたか酔っていたのは、不快というよりは壮観とさえ映じたものである。
今、目を閉じても鮮かに甦る秋の伊豆の山々。熟練した織子が織りなす反物の様に、山の中ばかりを走っても決して我々を飽きさせない魅力を持っていた。こうした大自然の中で素晴しき交歓会を準備してくれた、及川氏を中心とする早稲田サイクリングクラブの方方に心からのお礼を言いたいと思う。
1970年度資料局の1年 – 政経学部3年 宮崎
1970年度資料局の1年
政経学部3年 宮崎
資料局としてのバトンを渡された当初、わたしなりに資料局の意義等について考えてみた。その結果、資料の保管は勿論のこと、その活用を推進することが重要な任務と考えた。分散して保管されていた資料が続々とわたしの部屋に集められた。かなりの量である。それを本棚に並べ、訪れる者の目に止まるようにした。
しかし、1年たった今、何人かには資料を貸出したものの、全般的に低調であった。企画を兼任したわたしとしては、クラブランの企画の際、昨年・1昨年等の資料を充分活用させていただいた。今後もこれらの貴重な資料を充分に活用していくことが重要な課題であると思う。
以下資料局の1年をクラブランを中心に振り返ってみたい。
5月3日 – 5日 新入生歓迎ラン<丹沢方面>
参加者33名 日帰り参加者11名
いよいよ本格的クラブ活動が始まった。我々3年生が中心となって行う最初のランである。非常なる不安がつきまとう。コースは1部の希望もあり、昨年とほぼ同じく相模湖からヤビツ峠へ至るコースである。
3日リーダー上原 早大 – 相模湖
日帰り組を含めて44名の大集団、勿論これは我がクラブ始まって以来の数字である。これだけの大部隊が、あの悪名高き甲州街道を走るのであるからして、その危険性は計り知れない。しかもその殆どが初心者である1年生を多数連れているのである。3年生の重みを感じる。甲州街道の混雑状態は昨年よりもさらに深刻であり、これからのサイクリングに問題を投掛けるものである。その甲州街道を、思いの外順調に走ること2時間、1年生が全く遅れることなく12時には全員八王子駅に着いていた。
しかし1年生諸君の健脚に驚かされるのはこれからであった。飯を食って1時、八王子駅を発つ。京王線高尾駅を過ぎて、いよいよ大垂水峠へと差掛かる。上りがきつくなると、1年生にみるみるうちに差をつけられてしまった。わたしは主将の保泉君と、遅れている2年生を励ましながら上ることとなった。したがって残念ながら1年生の快走振りは拝見できなかった。
峠での小休止の後、相模湖まで一気に下る。黄金週間とあって相模湖はハイカー、家族連れ、ドライブ族等で飽和状態、人人人…の相模湖である。なんのことはない、我々もその混雑を促進しにやって来たようなものだ。ここから日帰り組は帰路につく。土肥君の先導で津久井湖・野猿街道経由で府中へ向かう。既に3時、府中解散は6時近くなるであろう。御苦労さん。彼らと別れてわたし達は弁天島キャンプ場へ向かった。ところがキャンプ場にはテントを張る余地など全く無い。弁当をひろげた家族連れに占拠されてしまっている。結局、テントは彼らが帰った後に張ることになった。忙中閑有。暫く河原に水と戯れる。
弁天河原に夕暗迫り、飯の炊ける匂いが漂う。メニューは毎年恒例のカレーライス、2・3年の愛情こもったカレーである。幸い下痢を起こした1年生はいなかった。頼もしい限りである。飯の後はファイアー囲んで交観会。各地の民謡も飛び出て格調高く、終始白けっぱなし。コンパのようにはいかぬものだ。
4日リーダー砂子 相模湖 – 二宮
歓迎ランのコースをほぼ昨年と同じにしたのは、わたし達が始めてサイクリングをしてバテバテになり、先輩に励まされて上った道を今、もう1度、上ってみることにそれなりの意義があるとみたからであるが、実はもう1つ、1度上った道なれば、余裕を持って上ることができ、新入生に対して上級生としての面目を保てると考えたからであった。ところがこの策略は全く無駄であった。
峠へ着いた先頭集団は2年の田中君を除いて全て1年生で占められていたのである。同じ頃、わたし達は道を間違えた3年生を待って途中の橋の上で休んでいた。何度も車を止めて彼のことを聞いてみた。バイクの兄チャンが、すぐ下にいたよ、と教えてくれてから彼が来るまで暫くあった。右へ行く道を左折して下ってしまったという。気がついてまた上り直して追いつこうと必死になって走ってきたようだ。今度は気をつけような高原君。そこからヤビツ峠まではさらに1時間、わたし達が着いたのは先頭が着いてからかなりたってからであった。
空の青い部分が次第に隠されていき、先に着いた連中は体も冷え、寒さに震えている、しばらく休んだだけですぐに下り始めた。ここの下りは雄大である。ハンドリングを間違えれば谷底へ真っ逆さまというところである。先日も車が落ちたというニュースを聞いた。それだけにスリル満点、途中からは舗装もされ、かなりのスピードが楽しめる。少なくとも60キロは出る。それだけにひとつ間違えれば地獄行き。幸いその志願者もなく秦野の街へ着いた。二宮は更に渋谷陵を越えた所である。相模湾に面した砂浜はまだ夏には遠く、トレーニングをしているどこかの女子バレー部の女の子達の声も冷たい波の音に消される。ところがである。ここにひとり馬鹿が現われた。まだ冷たい海に飛び込んだのだ。奇人揃いの我がクラブにおいても特筆すべき奇人である。それにしては風邪をひかなくてよかったなあ砂子君。合宿2日目の夜もなごやかなる交歓のうちに暮れていった。
5日リーダー藤井 二宮 – 二子橋
3年としてのわたし達の最初のランもなんとか終わろうとしている。二宮を出て大磯から国道134号線に入った。7年前の修学旅行が思い出される。江ノ島までは相模湾に沿った海岸道である。ここでまた道を間違える者が出た。今度は1班がそっくり行方不明になった。直ぐに気付いて戻ってきてくれたものの連日のミス。リーダーや班長は勿論、これからは1・2年生もコースを熟知しておいて欲しいものである。もっと主体的なサイクリングをやろうな。
江ノ島もまた人人人。早々に江ノ島を後にして国道246号線を目指して、真っ直ぐ北上、途中の大和で昼飯。わざわざ国道1号線を避け、国道246号線をコースに組み入れたのは、多摩丘陵を真っ直ぐに貫いたこの道の楽しさを新入生諸君に教えたかったからなのだが、健脚揃いの彼らの前には、この上り下りの連続である国道246号線も何の変哲もないつまらない道路でしかなかったようだ。
汗をかいて必死に上っていたのは、2年生と3年生のみか。いやはや今年の新入生は頼もしいやら、末恐ろしいやら、いずれにせよ先が思いやられる。3日に帰った連中が青葉台辺りまで向かえにきてくれていた。
2時半、二子橋で全員無事に解散。わたしは帰路を急ぎながら、3年としての責任の重さを再認識せずにはいられなかった。
5月16日・17日 奥武蔵グリーンラインラン
参加者18名
大家族だった前回のランとは打って変わった小人数のノンビリとしたランではあったが、雨の為コースは大幅にカットされた。
16日リーダー砂子 早大 – 山伏口
9時に出発した本隊に遅れ、わたしは陶山・奥野両君と10時に早稲田を出た。順調に走ること1時間半、所沢の手前で本隊に追い付いた。飯能までの道はこれで何度目であろうか。この間の行程を輪行袋などの使用によって、短縮することができれば、わたし達の活動範囲は大きく広がるであろう。
飯能での昼飯をすませて、わたし達は名栗川に沿って上る。この道はわたしにとって初めてであるが、名栗川のせせらぎの音を聞く静かないい道である。人数も18人、この位が1番いいのかも知れない。のどかなサイクリングが楽しめる。きょうの野営予定地の山伏口では食料の買い出しができないので、途中の部落で買い込んでいった。米を担ぐ人は御苦労である。
名郷までは快適でなだらかな上りが続いた。名郷から山伏峠までは5キロ、これからが本格的な上りだ。フリーランにするために全員揃うのを待ったが2人が来ない。梅本君が道路脇の溝に突込みリムを曲げてしまったのだ。如何に強いリムであろうとも、我がクラブ屈指の巨体を誇る梅本君を支えるには充分ではなかったであろう。取り敢えず及川君に応急処置をしてもらい、曲がったリムで走ることになった。
フリーランになって先ず飛び出すのは、やはり1年生である。3年ともなるとずるくなっていけない。後からいけば追い越される心配もなく、ゆっくり走ることができる。いつも最後尾ばかりを走っていたわたしも、きょうは思いきり前へ飛び出してみた。1人抜き、2人抜きと力の限りがんばってみたが、今さらながら苦しいものである。山の中腹に道路らしきものが見えるが、まさかあそこまで上るわけではあるまいなどと思いながら結局そこまで上ってしまった。予想以上にきつい上りである。それでも先頭を走る河野君に何とか追い付いた。ところが追い越してからは、彼はわたしにぴったりとくっついて離れない。そしてわたしがバテたころをみはからって、
「お先に」などと言って追い越して行く。もう追い付くことはできない。峠に着いた時には、全く余力なくブッ倒れてしまった。苦しかったが、久し振りにさわやかな気持になった。サイクリングはこうでなくてはいけない。
キャンプ場はこの山伏峠からすぐである。キャンプ場といっても唯の川辺であり、炊事は全てその川の水でする。川の水で炊事をすることは我がクラブにおいて珍しくないが、未だに食中毒患者を出してはいない。みんな鍛えられた胃袋を持つ。我がクラブの大きな誇りである。夕飯はシチューの予定であったが、材料の関係でカレーライスに早変り。1番手っ取り早いのがカレーライスである。
飯を終えてテントに潜り込む。そろそろ寝つこうかという時、パラ、パラ、ザーときた。雨はテントを通し、次第に中へ入り込む。テントの中にいてもビショ濡れになってしまう。この付近には雨宿りの場所などない。朝まで待つしかない。やけくその罵声が飛ぶ。明日はどうなることやら。
17日リーダー名田 山伏口 – 田無
雨は朝まで続いた。予定を変え、奥武蔵グリーンラインはカットし、正丸峠から飯能へ下ることになった。朝飯など作っている暇はない。朝飯用の米などは近くの店にとってもらい、その御礼としてカステラパンを貰った。全員に1個ずつ渡ったが、残ったパンを巡って冷たい戦争が始まる。それはジャンケンでけりがついた。濡れたテントをたたんで早々に出発、すぐ正丸峠に上り、下りにかかる。雨の中では上りよりも下りが恐い。全くブレーキが効かない。リーダー名田君の指示の下に、かなりの車間距離をとって下って行く。
これが結構疲れる。手がしびれ、肩が痛くなる。雨というのは全くサイクリスト泣かせだ。体はびしょ濡れになり、それでも汗はかくものだ。なめてみてわかった。なんといってもブレーキの効かないのが恐い。わたしもある雨の日、ブレーキが効かず開いたタクシーのドアにぶつかりそうになったことがある。タクシーの中へ飛び込んだ先輩もいると聞いている。今日は全員無事に飯能の街に着くことができた。
早速、腹ごしらえに街の中に散った。が日曜の朝もまだ9時、あいている店もそんなにあるわけはない。それにしても食堂の少ない街だ。かなり歩いて、ようやく見つけた店で準備中だったのを無理をいってあけてもらった。温かい味噌汁に生きかえる思いがした。飯を食って満足したのも束の間、再び雨の中へ飛び出す。所沢で解散。所沢街道・川越街道へと散って行く。この企画は昨年、雨で流れたものであるが、今年また、雨の為中止の憂き目をみた。今度は絶対に晴れるという日にもう1度走りたいものだ。雨の中ほんとうに御苦労でした。下宿に着いた時には青空が出ていた。
5月24日 中津溪谷ラン
リーダー猪又 参加者31名
5月晴れの青空が広がるダービー日和。府中の東京競馬場目指して走る車・車・車。その車をかきわけ、かきわけ走る31台の自転車。今日がダービーだということも知らなかったくそ真面目な企画者のおかげでコミコミの甲州街道を走らされるはめになった。関戸橋を渡るまでが大変であった。関戸橋からは多摩川をはさんで甲州街道と平行に八王子街道まで走り、そこから七国峠へ向かう。ところがこの道が全くの山路で、右へ行ったものか左へ行ったものか全然見当がつかない。さんざん考えたあげく、まちがった方へ行った。結局峠へは止らずに下ってしまったようだ。城山の街へ出て、ここで昼飯にしようとしたが、食堂が全く無いのである。弁当を持って来れば最高なのであろうが、わびしい下宿住まいのわたしなどには弁当を作ってくれる人などいるわけがない。この日も結局何個かのアンパンですませた。
昼飯後は上ったり下ったりの道が続く。愛川町の手前で右に折れ中津川に沿って上る。これからが中津渓谷である。この道はハイキング地図で見つけたもので道路地図には出ていない。ところがこの道にも車がどんどん入ってきている。すりかえもできないこの狭い道に車が入ってきて石小屋付近にはずらっと並ぶ。中津溪谷は水もぬるみ、結構いいところであった。しかしなんと言っても車と人が多い。最近この道が全面舗装されたという。また車がふえることだろう。中津渓谷を抜け落合へでる。この辺りにも河原で遊ぶ人が多い。ここからは5月の歓迎ランで通った道であるが、今日は宮ヶ瀬から左へ折れて土山峠へ上る。ここは1年の時、伊勢原側から上り、バテてしまい中山君と自転車を押して上ったところである。
東京周辺のみならず全国に、サイクリングが作ってくれたこうした思い出の地がある。いつの日かまたその地を訪れることがあるだろう。その時はその地が、そしてわたしがどう変わっているか、それを見るのもまた旅の楽しさの1つである。土山峠を下って厚木の街へ出る。今日は国道246号線を避け、座間米軍キャンプ前を通り、町田へ抜け、多摩水道橋で解散。リーダーについて先頭を走っていたわたしは予定通りの6時に水道橋に着いたが、最後尾はパンクの為遅れること30分。日帰りランにはどうしても無理が伴う。トラブルを見込んだ余裕あるプランの作成が望ましい。この日も下宿に着いたのは8時近かった。走行距離も140キロを越えている。4年生の御老体にはきつかったでしょうか?
6月7日 <マップリーディングへ多摩丘陵>
参加者9名
1年生会から地図の読み方について教えて欲しいとの申し出があり、何としたものかと戸惑ったが、百聞は一見に如かず、否、百聞は1走に如かず、地図を片手に走らせることにした。渡辺君、関口君、土肥君が手伝ってくれることになった。しかし1年生からの申し出にも拘らず、その1年生の参加が僅か5名というのは情けない。それでもマップリーディングは少人数のせいか和やかなうちに進められた。
関戸橋を渡った所で1班3人の3班に分け、マッブリーディングに入った。もっともここへ来る途中、道に迷い、マップリーディングをしながら来た者も何人かいた。3班がそれぞれ充分間隔をおいて出発、1年生を先頭に、地図の上の線を追った。多摩動物公園前までは順調に行った。ここからハイキングコースへ入ったが、そこに最初のトラブルが待っていた。パンク。
この道は平山城跡公園から野猿峠へ抜けるポピュラーなハイキングコースであった。しかしいまやそれは過去形でしか言えない。宅地造成のブルドーザーに寸断され、新興住宅地の真ん中を通る道になってしまっている。しかも思わぬ所まで車が入り込んでくる。埃をかぶってのサイクリング。
城跡公園に着いたのは12時少し過ぎであった。ここにはまだ多摩丘陵のたたずまいが残っている。一軒屋の古いみやげ物屋にあがり込み昼飯を食う。眼下には浅川の流れ、とくに八王子の街が広がる。野猿峠でハイキングコースを抜け、戦車道路へ向かう。戦車道路とは、戦時中は戦車の訓練とかに使ったそうで、この名もそこに由来するものらしい。今は滅多に車が通らず、舗装こそしてはないが、広い道路を我が物顔に走ることができる。そのほぼ中間にある小さな神社で小休止。相模原の街と米軍基地が眼下に重くひろがる。そこには2年前同じ所から見た同じ景色という懐しさもある。
ここから少し行った所で前を走っていた1年生2人が、期待に応えて道を間違えてくれた。しかも全く気付かずにどんどん行ってしまった。わたしは2人が気付いて戻ってくるのを待ったが一向に帰ってこない。急いで追いかけると2人で地図を広げて首を傾けあっている。このまま行って途中から正規のコースへ戻ることにした。すると前方から他の班の3人がこっちへ向かって走ってくるではないか。彼等もやはり道を間違えてこの道へ入り込んでしまったのだ。
一緒に正規のコースへ戻ったが、こんどは残りの班がこない。奥野君が下り坂で転倒したのだ。かなりすりむいて赤チンの洗礼をうけたが、肩も強く打っており、無理は禁物だ。こんな時、彼は実に真剣な顔をして我々を心配させる。1部コースをカットして帰路についた。多摩水道橋5時解散。
サイクリストたるもの、自分がどこを走っているのか、それを地図の上で示せるようでなくてはいけない。1人でツアーをする時には、それが役に立つ。今日は事故を起こしてしまったが、こうした企画はやっぱり必要だろう。
6月13・14日 早慶ラン<道志溪谷>
参加者20名
3回目を数える早慶親睦ランが慶応の企画で行なわれた。早稲田側の参加者は当初30名を予定したが、20名の参加者しかなかったことを慶応さんにお詫びしなければならない。実は、わたしも参加できなかったので、これについては内田君の記録を参考にして欲しい。
8月13日 – 24日 合宿<山陰>
なんと言っても我がクラブ最大の行事である。今年も35名の部員を集めて山陰を駆巡った。13日に松江駅集合、24日京都解散。雨の降らない日を数えた方が早く、まさに波乱万丈の合宿であった。尚、今年は試験的試みとして、2班に分けて合宿を行なった。
詳しくは別掲の合宿の記録を参考にして欲しい。
10月18日 山王峠ラン
リーダー湯浅 参加者17名
後期の活動は、紛争そして各学部バラバラの前期試験等のため、大きく狂い、これが後期の最初のランとなった。早同交歓会の前に是非1度ランを、ということでこのランが企画された。年間計画にはない、にわかプランであり、その作成には苦労した。既に東京近郊は走り尽した感があり、日帰りプランの作成はかえって困難である。
そこで以前から名前を聞いていたがまだ行ったことのない山王峠へのアタックが決定した。なんでも慶応が歓迎ランで走ったところだそうだ。
飯能への道に変化を持たせるため、途中平林寺に寄った。入山料50円。さすがに中は広く、雑木林の散策は格別。野郎が集団でぞろぞろ来るところではない。アベックが迷惑しているではないか。ここから飯能までは4班の班別行動である。時間までに飯能に着くことを申しあわせ、各班思い思いのコースへ散っていく。といっても時間が限られており、そのコースもおのずと限定されてくる。それでも平林寺前の店で優雅におしるこなど所望していた班もあった。
1時50分、再び全員そろって飯能を出発。名栗川に沿って上る。コスモスが美しい。舗装道を離れ峠に差掛かる。途中工事中の箇所があり、勾配もきつく、容易には進めない。ところが峠はそこから直ぐであった。あまりに近く肩透かしを食わされた感じである。みんなの物足りなさそうな顔がわたしに向けられた。実際あとはただ帰路を急ぐだけ、物足りないのはわたしとて同じこと。これから青梅の鉄道公園へ向かう。ここが今日のコースに組み入れられたのは、多分にわたしの個人的嗜好からである。わたしは往々にして公私混同してしまう。このような公の文章を書かせても、つい私事にふれてしまう。利己的なのかも知れない。自己顕示欲が強いのかも知れない。
その鉄道公園は小高い丘の上にあり、そこまでの道が結構きつい。しきりとボヤク者あり。しかし鉄道公園はおもしろかった。小さな子供達と一緒になって機関車に駆け上り、釜の中へ顔を突込んだり、客車の屋根の上を飛び跳ねたり、久し振りに奔放に振舞うことが出来て嬉しかった。
鉄道公園を後に、帰路に着く。10月ともなれば暮れるのが早い。5時にはライト無しでは走れなくなる。7月は7時過ぎまで走れるというに。5時半、田無解散。珍らしく予定前に解散ができた。それだけ内容が乏しかったともいえる。反省。
10月25日 オープンサイクリング
参加者19名
当初予定されていたオープンサイクリングは、貸自転車が集まらず、中止と決定されたが、この決定に2年生が発奮してオープンサイクリング実行委員会を結成、その努力が報われる日が来た。一般から多数の参加申し込みがあり、自転車集めに奔走したが、その大半は使わないまま帰すことになってしまった。当日集合地の三鷹駅には雨の為9名の参加者しか集まらなかったからだ。それでもこの雨の中9名の人が集まってくれたのだ。雨も小止みになり、公園へ向けて出ることになった。参加者が少ないことは却って幸いした。9名の参加者に対して部員が19名、ひとりに対して2人のボディガード、これは参加者の安全をまもるにまず充分な数であろう。玉川上水をはさんで五日市街道に沿った道を3班に分かれて進んだ。
時折強い雨が通り過ぎる中、全員無事に小金井公園に到着。ちょっと湿った芝生の上に腰をおろして円をつくる。例によっての自己紹介が始まる。全員の紹介が終わって班別にちょっと早い昼食会にうつった。勿論我々は弁当など持ってはこない。たかり専門である。こっちの女の子から、あっちの女の子からと餌をせしめる。これが楽しみなのだ。彼女達もそれが嬉しいのだ。次第に和んで行き、バレーボールを追って1つの輪ができた。その時には空は晴れ、朝の雨はお前の記憶違いだろう、と言わんばかりに青空が広がっていた。そしてその空は、夕方もう1度土砂降りになるとは全く考えもさせなかった。バレーボールをやっていて汗ばむ暑さである。和れた頃、丸山君の指導でいろんなゲームが、笑いのうちに進められた。
午後は多摩湖までの予定を大きくカットし、小平から水道道路へ入った。この道路は自動車通行止になっているので、絶好のサイクリングコースになっている。ところがこの道へ出てすぐ女の子の車がパンク。篠原さんが修理を買って出る。やっぱりこの体重には耐えられなかったか、などと冗談を言いながらも修理は手早く行なわれた。三鷹にもあと少しと言う時、再び雨が我々を襲った。浄水場の前で雨具をつける為に止まったが、その用意のなかった女の子には、部員が我先にと雨具を貸している。そこから解散地の三鷹駅までは直ぐである。
雨に始まり、雨に終わったが、事故もなくよかった。参加者を見送って後、我々にはまだ自転車の返済という仕事が残っている。これは1・2年でやってくれたが、その為に月曜がまる一日費されたようであった。オープンサイクリングは準備、後始末において普段のランの数倍の労力を費し、安全を守る為に数十倍の神経を使う。来年また行なわれるものならば、今年の経験を生かして充分な準備のもとで、充分気をつけてやって欲しいものだ。
10月31日 – 11月4日 第7回早同交歓会<伊豆>
参加者35名
恒例の早同交歓会も7回を数えるに至った。この日の為の準備が夏休み前から、実行委員長の及川君を中心に、主に2年生により進められた。そして今日ここ大仁には、1年振りの顔が続々と集まる。早稲田35名、同志社30名の出席を得て、幕が切って落とされた。例によって早稲田側の集合が散慢であったのは反省したい。
幸いに4日間晴天に恵まれ、天城旧街道・西海岸から望む富士・猿の波勝崎・伊豆最南端石廊崎と、伊豆の秋を満喫。下田でのコンパも例の如し。盛況のうちに第8回のバトンが同志社に渡された。
はるばる京都より来られた同志社の諸君、並びにこの交歓会を成功に導いた及川君に感謝の意を表したい。尚、詳細は陶山君の記録を参考にしてほしい。
11月9日 – 11日 軽井沢タイム・トライアル
参加者27名
早同交歓会を終えて数日の後、タイム・トライアルが行なわれた。部員諸君には金銭的に多大なる負担をかけてしまったが、それをものともせず、好記録続出。トップは小泉さん、時間5時間11分。
昨年の記録を30分近く更新。毎年30分づつ速くなっているが、10年後は如何に?更にもまして驚ろかされたのは、10位まですべて6時間を切り、その中には、1年生が6人もいることであった。このコース3度目の小泉さんの記録はともかくとしても、初めてで昨年の最高記録を破った1年生諸君には驚異よりも、恐怖を感ぜずにはいられない。来年、わたしなど出ようものならそのスピードに着いていけず殺されるのではないだろうか。彼らが再度このトライアルに挑戦する時、新たな記録が生まれるのは明らかだろう。大いなる期待が持たれる。
今回のトライアルの詳細については、安田君の記録を参照にして欲しい。
11月22・23日 4年生追い出しラン<2年生企画>
参加者26名
早大 – 御岳山頂
22日
1970年もいよいよ最終ランを迎えるに至った。集合地の四面道には寒さに震える27名が集まった。さて出発とペダルを踏み出した時、最初のトラブルが起こった。内田君のパンク。かなりのパンクでチューブを取り換えなければ、だめなようである。わたしにはわからないが彼の自転車はそんじょそこらにあるのとはわけが違ううのだ。したがってそのチューブもそこにある、ここにあるというものではないのだ。直し次第追いかけるという彼を置いて出発した。彼は結局来られなかった。あまりいい自転車を持つのも考え物だ。
五日市街道を西へ西へと進む我々の頭上を頻繁にジェット機が往来する。この辺には立川基地、横田基地や米軍キャンプが点在する。何の為か今日も多数の機動隊員が出動している。
昼過ぎ、武蔵五日市駅に到着。ところが先に出た班がまた着いていないのだ。どこで追い越したのか我々が先に着いてしまった。五日市からは秋川に沿って上る快適なサイクリングである。秋川と別れいよいよ本格的上りにかかる。裏から御岳山へ上るコースである。御岳山から下って来るハイカーが多い。我々は彼等の、特に彼女達の目を意識してどんどんとばす。苦しい時も実際には向けられていない彼女達の視線を意識して、休みたいのも堪えて重いペダルを踏み続ける。美しく色づいた紅葉が鮮かだった。
全くの山道となる。乗って上れるものではない。押して上れるものでもない。かついで上る。自転車をかついで上ることは、我々にとって珍しいことではない。かついで下ることもある。現に次の日はかついで下ることになった。現代版畠山重忠。しかしこの日ほどかつがされたことはなかった。乗れるところなど全くない。えんえんと階段が続く。軽合金で出きてるとはいえ重いものである。まして鉄製のわたしの自転車はずっしりと肩に食い込む。それでも前を歩く女性のミニスカートに励まされ、遅れまいとついて行った。おかげで比較的早く頂上に到達できた。
かなり早く着いたな、などと思いながら宿の国民宿舎へ入ると、何人かがもう風呂から上がってさっぱりした顔で待ちうけていた。国民宿舎を宿にするなど、我がクラブでは最上級の贅沢である。というのもきょうは4年生から酒の差入れがあるのだ。毎年追い出しランはその性質上、他のランとは違った非常に和やかな性格を持つ。きょうも和やかなうちに夜が更けようとしている。アルコールがちょっと少なく寒さが身にしみる。
23日 御岳山 – 奥多摩湖 – 東京
標高900米の山頂はさすがに冷えこむ。昨夜も雪でも降りそうな冷え込みであった。まだ朝もやの立込める外へ飛びだす。山荘から青梅街道へ下る道は、最初は乗って下りられる決適なものであったが、途中からはぐっと険しくなってかついで下りる破目になった。
おかげで1時間で下る予定が倍以上かかった。これが今日の計画を大きく変えてしまった。青梅街道へ出てからの小河内ダムへの上りは、きのうの御岳山の上りに比べれば屁の河童。難無く上り着いた。上っている途中は体も暖まるが、奥多摩湖は風も冷たく、寒くて立っていられたものではない。飯を食ってそうそうに立ち去ることになった。
午後は数馬峠を越え、秋川渓谷を下る予定であったが、既に時間も遅く、青梅街道を下ることになった。ここからの下りは快適であった。道は狭いが飛ばしに飛ばし、車を寄せつけない。青梅を抜けて、多摩湖から水道道路に入った。この道は今の4年生が新入生の時の歓迎ランで通った道なのだそうだ。この道路も周辺の宅地化に伴い変わりつつある。和やかなサイクリングも東京が近くなるにつれて終わりに近づく。三鷹に近く、この道路が五日市街道にぶつかる所で恒例の胴上げだ。嬉しさの中で、逃げまわる4年生をひとりずつつかまえて大きく空へ放り上げる。そのまま落とされることもある。我々3年生が最もお世話になった先輩を今送る。大きな礎を失うようであり、またこれからは我々が後輩の礎とならなければならないのだ。
11月27日 総会(8号館201教室)
役員改選の季節。我々の執行部も発足して既に1年がたってしまったのだ。部員数も増え、ランの参加者も増えた。かといってこの1年、盛況だったとは言いきれない。数字で単純に示されるものではないだろう。
総会で砂子主将、立石副将以下新しい執行部の顔振れが決まった。この1年の活動を踏み台に、さらに大きく飛躍してもらいたい。同じ1年を繰り返してはいけない。失敗に終わってもいい、それを恐れずに新しいなにかに挑む、その気力が欲しい。わたしはこの新執行部が期待を裏ぎらないことを信じてやまない。
机上的産物 – 叛乱としての異常性への飛翔 – 政経学部2年 関口
机上的産物 – 叛乱としての異常性への飛翔
政経学部2年 関口
人間は、感性的・理性的認識に基づく目的意識的行動を志向する故に、ホモ・サピエンスとして、生物界における特権的地位を独占しているのであろう。
私がこれを書く理由は、自己主張あるいは、自慰的欲求を充足させようという内的要因以上に、クラブ員として、他のクラブ員対象に自己をコミュニケートする最も有効な手段として、提供されたものと理解するところの幻想によるものと、機関誌上で、意志表示することも一種の「義務」と独善的解釈することによる外的要因に、見い出される。それ故、私は、記録的紀行文を避けるのである。
異常性に対置させられる日常性に関しては、ルフェーベルの『日常性批判』などがあるが、それに依拠せず、私なりの批判を、サロン風に、集約させたいと思う。
しかし、実際には、私の社会観、それを構成しているところのイデオロギーは、私の社会的存在基盤である、社会という客観的対象から醸造された以上に、自己の実体験の産物ではなく、書物という観念的世界において獲得した知識、それも極めて限定的に摂取した知識に他ならないのである。それ故、教条的複数的エピゴーネンとしての私は、不可避的必然的結果として、矛盾せざるを得ない。しかし、私は、矛盾した存在としての人間は、人間の普遍的本質と観る故に、逆に居直るのではないが、承諾していただきたい。社会と自己との、自己内部における矛盾との葛藤が、エゴイズムと共に、人間の行動の原動力として、歴史を創造してきた二大要因と思う。
高橋知巳的「人間が矛盾した存在であって、自己の中に色々な考え方が混沌としてある」思想観によれば、まさに、私自身、本来的人間的存在であり、それ故に、正当化しようとは意識的に避けるが、人間は自己の矛盾・社会の矛盾から訣別できないであろう。
毛沢東流に言えば、主要矛盾を摘出することによって、自己の問題を発展させることが重要なのであり、歴史は、その露出過程であり、矛盾の究極的止揚は、人間そのものの否定であり、歴史を停止することになるから。ただ、私自身について言えば、まだ、エピゴーネン的イデオロギーから脱却し、自己の思想観を打ち築く段階に達していない故に、1人称で語ってみても、読者には、3人称的に響くかもしれないだろう。それ故、私の精神的楔を読者の心に打ち込めないかも知れないが、出来るだけ自己の考え「イデオロギーとは異なる、初歩的·流動的·直観的・未熟的なもの」を発露させる意図の下に書いた。舞台裏を暴露したのは、それだけ、功罪を減じることが出来ると思ったからである。
前置が長くなったが、このテーマに即して、自己の考えを拡大で散させよう。
過去の自己を、思考的観念的世界から把えてみると、少なくと大学生活に踏み込むまでは、日常性という一本の太い糸に操られ来たという被害妄想に駆られるのである。実際、私は、大学というものを、常識的に、経済的・身分的パスポートを発行する職業訓練と見なし、学問を第2義的付帯物と規定し、産学共同路線の崇拝者だったのである。今でも、この考えは私の心底の一部に沈殿しており、私の決断力を鈍らせる魔物である。大学入学後も日常的、常識的なものが、精神的・物質的生活の主要部分を占有し、日常的行動と異常的行動の境界線に立つ時、常に、私をして、逡巡させるのである。
この糸を切断する機会は度あるごとに訪ずれるが、私は対処しえず黙過してきた。これを実行に移すことは、現在までの自已を否定することになり、社会的・経済的基盤の崩壊を必然的に供い、日常的安住性を固執する人間にとっては、それだけの決断力を有するのである。
秩序という1本の固定された軸を中心に、回転する日常性的領域にひたることを自己目的的活動の基盤としながらも、日常性からの1時的脱却を渇望し、試みるのは、人間の本能的衝動的なものであろう。そして、日常性という1本の糸にすがりつつ行動できる領域は、法·慣習·地域的因習·国家的伝統等の諸々の幾重もの鉄条網で限定されているのであり、この鉄条網を切断して領域外に出ようとする行為が、国家によって反体制的性格を帯びると主観的に判断される場合、国家権力の番犬に噛みつかれ、破防法・公務執行妨害・公安条例違反・騒乱罪等の罪状で、合法的に処分されるのであり、このような既制事実の積み重ねにより、この領域をより神聖化し、新たな日常性を付与することにより、この厳正なる領域で生活することを強要するのである。
自らは、領域外に通じる秘密の地下道を構築し、自由に出入りし、「国益」なる大義名分の下に、新植民地主義的経済進出を遂行し、私有財産の増殖に没頭する一方、野党は、これも同じく、議会において合法的に、新たな取締法というスコップで、この地下道を埋めようとするが、政府は、パワージャペル・ブルドーザ等の近代機械の大量導入で、いとも簡単に、土砂を取り除き、このどさくさに乗じて、新たな地下道建設に着手している。
1時期には、この糸が、ある社会情勢に照応した外的要因によって、切れそうになったこともあるが、その都度、国家は、色々な金具等を用いて、この糸を補強し、ナイロン製に交換し、恒久的なものとして来た。そして、私を含めて、多くの国民は、この処置に対して、無関心を装い、黙認し、1部の者は、当世流行の事大主義的に迎合し、自ら裸踊りの役割を果たした。そして、朝鮮戦争・勤評闘争・警職法闘争を経て、60年新安保条約を契機として、このナイロン製糸は、鉄のロープによって替えられ、その番人としての宿命を担った自衛隊・機動隊「政府が父親であり、その母親である無関心的国民及び去勢的野党は、酒に酔った勢いによる強姦行為に為す術もなく、はかない抵抗を試みたが、結局は、身を任せざるを得なくなり、私生児として、この双生児を生んだのである」は、税金という甘いミルクによって養育されて、現在では離乳期を迎えつつある。
中華人民共和国は、この2人をすでに、とりわけ、長男の方を、不良少年として、盛んに日本国民に警鐘乱打している。そして、この子を、抹殺することを希望しているのである。過保護故に、独立自尊心を持たない長男「自衛隊」に、業を煮やした三島氏は、養子として、長男を引き取り、スパルタ教育をするために、『楯の会』という実子を、数名引き連れて、市ヶ谷の自衛隊本部に談判しに行ったが、世間体を憚ってか、父親から、仕送りを絶たれることを恐れてか、この子は拒み、三島氏を死に至らしめたのである。三島氏は、自分の実子と、この子とで、清水1家ならぬ、三島1家として旗揚げし、人間性を超越したカリスマ的存在としての天皇を神格化し、「昭和維新」を起こそうとしたが、極度の現状認識の欠如故に、夢の饗宴として徒労に帰した事は、世間一般の知るところである。そして、かの有名な「マラッカ海峡防衛論」を唱えた実兄―仲曾根は、国会答弁として、三島氏のこの行為をたしなめたが、それは、時期尚早故に否定したのであり、政治責任を回避するためにすぎないのである。
我々が、精神的・物質的に、常識的・日常的なものを、至上目的的素直さで、無意識的にせよ、遵守することは、国家そのものを、容認することに相等しい。
マルクス・エンゲルスは、その著『ドイッチェ・イデオロギー』で、「いかなる時代においても、支配的な考え方とは、支配階級の考え方のことである。すなわち、社会を支配する物質的権力を代表する階級は、同時にまた社会を支配する精神的権力でもある」と言っているが、まさに、これは普遍的理論として、現在でも、効力を有しているだろう。政府は、マスコミ・ブルジョアジャーナリズム等の情報網を精神的権力手段として、駆使しているのであり、我々の支配的な考え方―「マスコミは常に中立的立場で報道する」―は幻想にすぎないのであり、下層階級と同一平面上の存在ではなく、政党的色彩を帯びている世論の統制機関なのである。
確かに、現在では、現体制を非難する新聞もあるが、それは、現在の支配者的疑似平和を、根底的に揺るがすには程遠い微力しか持ち得ないからであり、過去の「アカハタ」発行停止事件や、「田英男」事件のよう言論の自由とは、政府と国民の力学的表現なのである―すなわち、一方には、支配者階級側の無限定的自由があり、もう一方には、国民の合法的限定的自由があるのである。
そして、我々が、義務教育・マスコミから得る知識の大部分―義務教育においては、教科書検定という濾過装置によって、体制批判的なものは、除外され、日本の建国と直接結びつけた神話が、歴史的実証性を加味し、復活されようとしている。それは、天皇制を神秘化し、擁立し、超歴史的に恒久化しようとする政府の国家統制的教育の1現象なのである―は、体制の支配的イデオロギーの具現的産物に他ならないことを、銘記する必要があるであろう。そして、このような教育から得た知識を、常識として、自己の価値基準とさせることが、政府の教育上の意図することなのである。そして、政府は、大学まで干渉せんがために、国庫補助金というアメと引き換えに、ムチを加え、大学の帝国主義的再編を弄しており、大学立法を契機として、高圧的姿勢で大学の御用化を策している。
自称革命的前衛党指導下の一部民主的学生は、1連の大学紛争における主導的役割を演じた学生を、大学の自治・民主主義を破壊する「トロツキスト暴力集団」・「トロイの木馬」・「ファシスト集団」等、様々なレッテルを貼りつけるが、それは提起された問題を恣意的に隠ぺいし、政治技術主義的に、本質と現象をすり替える片手落評価ではないだろうか?そして、彼等の唱える大学の民主主義の擁護の究極的目的は、大学から国家権力を排除し、トロツキスト追放による民主的学生と民主的教職員とが一体となって、大学を一元支配下に置くことなのである。
彼等が信奉するレーニンは、『国家と革命』の中で、「民主主義は、多数者への少数者の服従を承認する国家である。すなわち、一階級の他階級にたいする、住民の1部分の他の部分にたいする、系統的な暴力行使のための組織である」と定義しているが、すなわち、民主主義とは、国家の本質であり、敵対関係の力学的表現に他ならず、一方にとっての民主主義は、他方に対する独裁を意味する故に、彼等が民主主義の立場に立つ場合、彼等も本質的には、暴力学生なのである。そして、民主主義も国家と同じく、支配・抑圧・暴力の根源として、究極的には、死滅される対象なのであり、過度的要求として容認される対象なのである。我々が、口にする「民主主義」とは、資本主義体制―日本においては、支配者階級によって規定―すなわち、ブルジョア民主主義―されているのである。要は、民主主義の階級的本質を見極めることが、必要なのである。
自主独立・平和を唱える彼等の党が、1956年のフルシチョフ報告を契機としたスターリン批判の衝撃によるハンガリー動乱を反革命と評価し、ソ連邦の労働者・市民虐殺行為を正当化した事大主霧的迎合処置は、彼等の体質を見抜く1つの足掛りである。
確かに、「大学を安保粉砕・日帝打倒の砦に」というスローガンを掲げて、大学を革命の拠点とパラノイア的に願望する1部学生集団を擁護するつもりは、毛頭ないし、それは、主体と客体を取り違えた労働者蔑視の思想にすぎないだろう。現実には、日本の労働運動は、労働戦線統一「革新再編成の名の下に、労使協調を主軸とした賃金獲得経済闘争至上主義的反共御用労働組合化」問題の抬頭に見られるごとく、その右傾化の道を歩みつつあるが、即自的反発によって、街頭に出るのではなく、労働戦線深部において、右傾化に抗し、この日常的現象を逆流させ、職場という生産点を原点として、ストライキという武器で以って、最も有効な経済的打撃を支配者に与えるのは、革命のイロハであるが、過去の大学の自治・民主主義とは、実際には、教職員の経済的日常的安定性を容認する制度的基盤に他ならなかったという疑問が強く私の心を支配する。
それは様々の条件―とりわけ、各個人の崇高な人間的水準の必要性―を前提とするが、教授連の単位認定権という権力を放棄させ、大学を労働者・一般市民に解放し、彼等自らが管理し、自主講座等で、我々が大学教育を相互的に規定できることを現実化し、この異常性を日常性に転化させた時点において、初めて、真の大学の民主主義なるものが、確立できると、ユートピア的に私は「大学像」を描いている。
現在、政府は、「繊維の自主規制」問題で頭を悩めている一方、産業界は、「国益擁護」の大義名分の下に、労使協調一体となって、反対しているが、「国益」なるものは、支配者階級が、公益を私物化し、国民の労働生産による剰余価値を合法的に窃盗した私有財産にすぎないのである。ブルジョアジーの代弁者である政府が、企業優先的政策を打ち出すのは、何も不思議なことではなく、大企業ほど政治献金が多いのはその事実を実証している。
「大東亜共栄圏」を夢想する我国家は、後進国の経済援助の名の下に、東南アジアに経済進出しているが、労働力の豊富と低賃金故に、それだけ私腹を肥やせるからである。最近では、自衛隊の国連軍派遣などの声も、上がっているが、国連軍が資本主義国より構成されている点に気付けば、その意図は、明確に理解されるであろう。
国家に対する暴力を否定した平和的愛国心によって、支配者階級の一定の秩序を保ち、社会福祉政策を導入し、高度経済成長によって「豊かな社会」を築くことができるかのように吹聴されてきたが、そのような幻想を国民に植えつけることによって、主従関係に基づく下僕的存在としての我々を常識化し、一定の枠にはめ込んだ観念行動をステレオタイプ化するのである。
彼等が言う「期待される人間像」とは、国家に奉仕し従順な没主体的、没個性的、常識的・ロボット的存在としての人間なのであろう。全体的規模での「自主防衛」が盛んに強調されているが、我々が「国のために戦い、国を守る」ということは、我々を守ることには、結び付かず、国家というピラミッド的階級社会の頂点に立つ支配者階級の利益擁護なのであり、支配者階級の利益と被支配者階級の利益は、対立関係にある故に、我々が新たな社会体制を望む場合レーニンが1917年のロシア革命の時に、帝制ロシアに反対し、「戦争を内乱に転化せよ」という革命的敗北主義の立場に立ったように、戦争責任者である国家を打倒することが必要である。
マルクス主義的観点に立脚すれば、「国家は階級対立の非和解性の産物であり、階級支配の機関であり、1階級による他階級の抑圧機関であり、階級の衝突を緩和しつつ、この抑圧を合法化し、強固なものにする秩序を創出するものである」。まさに、これが、国家の本質であり、我々は国家に対する共同幻想を払拭しなければならない。
歴史は常に、諸階級の権力奪取の闘争、すなわち、階級闘争の物質的表現なのである。国家は、諸階級を内包している合法的組織的暴力形態であり、暴力の根源―階級による階級の支配・抑圧―は、この国家にある故、本質的に暴力を否定するならば、無階級的非搾取のない社会を志向せざるを得ないであろう。すなわち、国家・民主主義が死滅し、高度の生産力を前提とし、労働が生活の第1欲求となり、「各人は、能力に応じて働き、欲望(必要)に応じて消費する」という真の平等が確立されている共産主義社会である。
生産手段は国有化されているが、1部の特権的官僚が権力を掌握して、ブルジァ的に生産物を分配している現在のソ連邦は、まさに、修正主義的社会主義国の典型に他ならない。
弁証法的唯物論に依れば、元来、国家とは、共産主義社会に移行するための過渡的形態なのであり、歴史の発展と共に、消滅するものであり、トロッキーが言うように「国家はそれ自体が目的ではなく、権力の座にある社会的勢力の手中に握られた作業機械にすぎない」のである。
義務教育は、ある一定の時期における最低限の精神的価値形成の基礎的材料としてあるが、国家の思想統制の手段化しているのが、現実であろう。そして、現在、まさに再上程されようとしている靖国神社法案―「国家」のために戦死を余儀なくされた犠牲者を手段化し、太平洋戦争を居直り的に肯定し、美化するための合法的根拠を得んがための、さらに、「愛国心」を鼓舞せんがための軍国主義的政策―によって、さらに、思想的攻勢に拍車をかけようとしている。
脱政治的、無関心的と一般に言われる人間であっても、決して、政治―経済の集中的表現―から逃れることはできない。政治は、国家において、常に我々が神聖視している日常生活の領域をも浸食しているからである。
俗に言う「公害」を例に取ってみても、それは、何も人間を超越した自然的現象ではなく、企業と癒着した為政者の利潤追求という目的意識的所産である政治的人為的現象であり、資本主義体制下においては、利潤追求が、至上主義的目的化される故に、必然的結果に他ならないだろう。
人間は、ある価値体系を、自己の精神的基盤とし、日常生活の行動の指針として、己れの人生を消化する。
この価値体系は、理論であったり、支配的な常識であったり、実体験から得た独創的観念であったり、それらを組み合わせたものであったりするが、大方の人間は、安易に、既制の価値基準、すなわち、常識を、客体的に、運命的に受け入れるのである。そして、この価値基準を絶対的なものとして神聖視し、諸々の社会事象を、これで以って、その外面的結果―現象だけを、短絡的に評価し、内面的な本質を把えることを放棄しがちである。
しかし、この「常識」こそ、支配階級の考え方―換言すれば支配的な物質的関係が表現されたもの―に他ならず、一時的な性格しか帯びず、その運命は、権力を掌握している支配者階級の双肩にかかっているのであり、それ故、支配者権力の崩壊と共に、一般市民の奥底に、長く余韻を残しつつ、消滅し、かっての非常識にその座を譲るのである。この非常識が、前体制下において、日常的地位を占める時、これは、体制変革の兆候となる一大転機を迎えるのであり、階級闘争の激化が表面化するのである。
しかし、この逆もありうる。すなわち、体制が1つの壁に突き当たり、彼等の築き上げた日常性・常識が、この壁を爆破するだけの効力を失う時、異常性・非常識が、その解決策として抬頭し、現在的な日常性・常識に包含され、総体的に日常化・常識化され、増々、促進されるのである。現体制と対立する思想を持つ人間は、この常識・日常性という束縛から逃れることにより、自己に内なる精神的権力を樹立し、彼の思想を行動に転化せしめ、物質化することは、彼の自己の解放を勝ちとるための精神的・物質的根拠である。それ故、体制変革を志向する人間が、支配者的日常性に対峙するものとしての異常性を内臓することは、彼という主体者にとっては、正常であり、日常性は阻害物であり、体制という客体者から、見る場合のみ、異常なのであり、彼が権力を掌握した場合、彼の異常性は合法的に正当化され、日常性として蔓延されるのである。
彼が、自らの異常性を行動として表現する時、体制は国家暴力装置である警察・軍隊・法律を用いて、秩序破壊者として、合法的に暴力を行使しうるのである。法の拡大解釈によって、自らの暴力を行使しうる合法的範囲をおし拡げることは、秩序強化による体制の強化のための処世術である。よくブルジョア新聞は、平和な秩序を乱す過激派学生を槍玉にあげるが、このような被害者側の現象的暴力を、「暴力の本質」とすりかえる本末転倒的な報道は、国家権力の代弁者としての機能を果たし、支配者階級が、自己の権力を維持せんがためのマヌーバーに他ならないのである。暴力を巨視的本質的に把握するなら、支配的な秩序を合法的に強要化しうるための法そのものが、暴力の一形態であることに、必然的に気付く筈である。
すなわち、法とは、支配者階級の経済的利益を合法的に擁護せんがための集約的表現であり、法律的・政治的上部構造は、社会の土台である下部構造―生産諸関係(物質的生産諸力の一定の発展段階に対応する)の総体という経済的機構―に規定されるのであり、一定の社会的意識諸形態も、この現実の土台に対応しているのであり、法は、何も人間の良心によって形作られるのではなく、社会発展の産物であり、個々の権力が、個々の法を持つように、独自の固有の歴史を持たないのである。要するに、法の土台は、物質的生産様式であり、社会の支配者意志なのである。
近代国家においては、一般的経済状態の反映が法なのである。それ故、経済発展につれて、法も発展し―修正され、法原理の反作用が、ある限度において、経済的土台を修正するのである。そして、結果的に見れば、法の至上的遵守は、体制の側につくことを意味する。
現在の我国は、国家独占資本主義という「資本主義の最高段階」に達し、死滅しつつある資本主義と定義されるが、その腹には、すでに、社会主義という胎児を宿しており、この胎児が、流産させられるか、無事に、1個の生命として、この世に生まれるかは、その母親である国家が生む意志を持たない故に、父親兼産婆である被抑圧階級としての労働者階級の主体に、その運命が、かけられている。
社会主義の前夜を生きている私にとって、夜明けを迎えることが、私の希望である。私は、現在でこそ、このような考えを持っているが、マルクスの言うように「社会的存在が意識を規定する」故に、大学生というプチ・ブル的存在である私が、ミイラ取りになるかミイラになるかを決定する、生産点という社会的存在基盤に立つ就職が、1大転機となるだろう。現在の私は、常に日常生活に逃避し、社会を決定する主体とは、無縁な常に何かを期待する客体者的傍観者的立場の人間であることは、私の自己嫌悪であるが、この嫌悪が日常化せず、常に脳裏を支配しているのでない故に、日常性に押し流され、この意識が麻痺される可能性が濃い。
生産社会に出て、ある状況を変革せざるを得ない時に、初めて、日常的な自己から脱皮し、精神的・物質的人間としての自己を統一できるだろう―主体的存在としての自己を。
この文章を終わりまで読んだ方は、「机上的産物」の意味を納得してくれることと思う。クラブ員としての私が、サイクリングと言う活動から得た体験を、表現したものではない故に、私と他のクラプ員の共通性を持たない内容と、感じるかも知れないが、我々にとってより本質的なもの―「日常性」―に焦点を合わせて、社会的人間としての自分の日常的なものを、もう1度、考察して貰いたいとの意図に基づいて、急拠、内容を変更して―私が最初に予定していたテーマは「個人的クラブ観」―書いたのである。初めは、一種の「義務感」から、書いたのであるが、書いているうちに、ある目的を持った「欲」が出て、予定の枚数をオーバーしてしまった。
私は、自己主張の場として、機関誌をあいまいに理解してきたが、先輩はこの機関識を発行する際、当然、共通の目的を持っていたと思うが、現在、我々は、先輩に対する体裁を憚ってか、安易に、伝統至上主義的に、後向きの姿勢をとって、惰性的に、発行しているように思う。つまり、クラブ員全員のための機関誌が、一部の常連に私物化されている―むしろ、我々が、その私物化を許しているのだ―と思う。
1部の指定された者を除くと、大体、『峠』に載せる者が決まっている。それは、編集局が「義務」として、1部の者を指名せざるを得ない現状―つまり、自発的に・積極的に載せようとする者が少ない故に、いつも自発的に載せる者の文章は、選考の必要なく、無批判的に受け入れられるという否定的現状―にあるのであり、1部の者を指定して、紙面を埋めなければ、発行できないからであり、その負担を編集局に、流れ弾として、広告を集める渉外局に、負わせているのである。
私の内容は枚数に見合った価値を持たないかも知れないし、場違いかも知れないし、一定の政治色を帯びている故に反感を買うかも知れないが、それでも紙面を埋めるという貢献により、私の文章は載せられるだろう。
確かに『峠』を配布されて読むことは、全員の権利であるが、「義務」として指名されて受身的に書く以前に、各部員が、もっと積極的に・主体的に・個性的に・独創的に書く「権利」として、どしどし応募し、編集局がやむを得ず選考しなければならないような状況に変革しようではないか!
確かに文章として、意志表示をする故、限界性を持ち、一方通行的な文章かも知れないが、少なくとも、何らかの形で、反応を得られ、それによって、書く意義が見い出されると確信する。
まず、機関誌をより豊かにし、「書く」ことを「義務」とすることからはじめ、共有化する時点で、この「義務」はすでに「権利」化しているのである。内容を限定することなく、活動記録だけでなく、社会に対する不満等の日常なものであってもいいと思う。
『峠』の内容が先輩の当初の内容と、多少、趣を異にしても、クラブ員の所産であることに変わらず、ある程度、社会の発展、具体的には、クラブの発展、究極的には、各クラブ員の意識の変遷に、照応するからである。
機関誌『峠』を、全部員の共有財産とし、我々全員の所産とすることは、本来的義務であると思うし、『峠』発行という形式的な行為ではなく、我々自身の汗や考え、意志を文章として、結晶するという行為が、「峠』という伝統を、真に継承することだと思う。
悲しみとは何か – 法学部3年 吉田
悲しみとは何か
法学部3年 吉田
「1」
週3回、夜の数時間をアルバイトのため王子で過ごし、ゴトゴトと早稲田行の都電に搖られながら下宿へたどり着く生活が、もう1年以上になる。王子から飛鳥山を経て雑司ヶ谷・鬼子母神・早稲田と来る頃には、10時も半を回っている。夏のうちはまだいいが、冬に、押し黙った夜空を仰ぎながら1人下宿へ帰る、凍えた夜路はひどくひっそりとしている。そこでは、妖しい位の寂寥感に人知れず埋ずもれてしまいそうだ。ふと立ち止まれば、裸電球の光は1人のぼくを張りつめた静けさの中に浮かびあがらせ、心細いその影は、身をすりつけるようにしてついて来ようとする。暗く閉ざされた商店街の低い家並は、まるでその闇を歩いていく1個の人間に感知しないかのように、ただ眠り続けるだけだ。
恐らく、<ぼく>という存在と<○○商店街>という存在は、豊島区高田の路上に同時に存在していた。にも拘らず、その間には何の<連帯感>も見い出せなかった。その間には、何の義務もなければ何の必然性もなかった。寒さでうずくまり飢えで歩けなくなったとしても、差しのべようとする<手>そのものが暗闇に呑みこまれてしまっていた。やがては朝になり、太陽が昇り再び商店街が活気を帯びていく最中に、確かにぼくは威勢のいい魚屋のアンちゃんと顔を合わせることが出来るし、愛想笑いをしてインスタントラーメンを手渡してくれた食料品店のオバさんとも、細いが一筋の人絆で結ばれているような気がする。だのに、今閉じられてしまった低い商店街の家並は、何故あのようにかたくなにく沈黙し続けるのだろうか。
ぼくにとって、父や母や兄妹は確かに現存しているし、掛替のない存在だ、といえる。が、やがては失なわれていく関係でもある。
そう思えば、殊更<残酷>な存在に思える。友人は居る。けれど、もし太平洋の真中に2人だけで漂流した時、食料も水も何もなくなれば、ぼくは彼を殺してその肉を食って命をつなぐことを企てるだろう。セックスを経験しない異性との関係は、歯の浮くような虚構に充ちている。夫婦は、殆んど<罪>をなすり合うようにして生きているし、それは1種の惰性のように思える。このようにして、1皮べロリと人間を剥げば、本質的には誰とでも<連帯>していないことに気づいてしまう。
どうみても1人だ。結局、1人の自己の内面に向けられた微かな愛情や確信をほのぼのと育てていくより仕方がない。押し黙った商店街の暗闇に瞳を凝らしてぼくが見たものは、この恐ろしく厳粛な<結論>に他ならなかった。恐ろしく厳粛なこの困惑に気づいた時、すぐ死ねたらどんなに幸福か知れなかった。けれど、何の因果か、ぼくらは生き続けようとする本能を持ち合わせてしまった。内面に蓄蔵された<苦しみ>を乗り越えていく形で、いやそうではない、大きく食出してしまった脱腸を引きずるようにして歩いていこうとしてしまった。大事なことは、1人きりのぼくらが生き、歩き続けていくということ自体が、即ち<死ぬ>ことである、ということだ。死に向かって確実に進んでいくことに他ならない。生き続けることは、死に至る行進を続けていくことなのだ。そして、泣き言を並べずく笑っていろ>ということだ。そう思い知った時、たまらなくはかない生の<悲しさ>を感じて、ただ絶句狼狽してしまう。
「2」
三里塚闘争というものがある。新東京国際空港予定地内の強制代執行を目前にして、地下に縦横の横穴を掘り続ける人々がいる。小学校に押しかけ、全校討論集会の前に校長・教頭を引き出す少年行動隊がある。機動隊に糞尿をふりまき、かなわないとみるや自分の体にそれをかけて機動隊員に抱きつき抵抗を続けていく婦人行動隊がある。
今、炬燵の中でじっと凍えた手を暖めようとうずくまっているぼくがいる。そのぼくはひどく幸福だ。どうして、千葉の局地で、少数の農民たちが国家のありとあらゆる総権力の動員の前でたじろがないでいられるのか、ブルドーザーで潰そうと思えば2時間で潰されてしまうような地下要塞を作り、その中で彼らは何をしようとしているのか、そんなことを考えている。ほくがもう少し「頭が良ければ」、そこで思考を止めているはずだ。それらは、あくまで内面に押しとどめておき、自分はといえば、再び炬燵の中で暖をとりながら、何か得体の知れない幸福感に浸ることを続けるべきだったろう。それを、愚かにも思考の深みに自らはまろうとしているのは何故だろうか。
どうせ散ってしまう<命>なら、何故、三里塚の農民たちのような行動をとることが賢明であったろう。1坪何十万かで売り渡してしまい、残りの人生を気楽におもしろおかしく暮らしたほうがどんなに楽しいことか。それを彼らは否定してこう言うのだ。
―損得の問題でやってるんじゃねえ。百姓の命はツヂ(土)だ。そのツヂを離れて生活していくことは、不甲斐ないことなんですよネ。それに、闘いを通じて新しい人間関係もできたしヨ、今まで全然関心がなかった政治のことが見えてきた。ステレオ買ったり自動車買って、テレビ見て寝っちゃうような生活が本当なのかつうことを考えると、それはほんとうじゃネエ。怨念だよナ。絶対土地は明渡さネエ。
怨念。恐らくそれは空港公団や政府に対するような<1部世界>の怨念をいっているのではないだろう。そのような怨念なら、札ビラを前にしてもうとっくに挫折しているはずだ。単なるツヂ(土)への執着だけでもない。目の前に迫ってくる国家という<怪獣>を意識した時の、自己の生という<全体世界>に対する執着であるはずだ。そしてそれが重大な<裏切り>を内包しているということへの<絶望>であったに違いない。
国家という怪獣の血走った目に恐怖させられた彼らが、唯一確認しようとした自己の生は、<死>という裏切りを孕んでいた。そう思い知らされた時、最早彼らにとっては直面した<現実>のみが、唯一<感触>せられるものだったのだ。だから彼らは、圧倒されるような滑走路という既成事実を前にして、その困惑を自らの<苦しみ>の形のままに放置してはおけなかった。唯一感触せられた現実というものに必死ですがりつこうとした。その苦しみを乗り越え突き破って、<それでも>生きていこうとした。彼らにとっては、地下要塞を掘っているということが彼らを<守っている>と同時に、相手を<攻撃している>ことにつながっていったのだ。<壊死>しようとして、その中で自己の生を確認していこうとする彼らの闘争の中に、打ちのめされてしまいそうな偉大さを感ずる。
<悲しみ>は、<苦しみ>を乗り越えて生きようとするところに、真摯な意味の光彩を放っているはずだ。そのようにして、<悲しみ>というものを理解してきた。現代にとっても過去にとっても、悲しみは内面に<秘められた>ものではなかった。ぼくらが、安易にそう思い違いをしていたにすぎない。苦しみを確認し、それを克服して生きていかなければならないという過程に、悲しみは厳然と立ちはだかっていたのだ。そして、それはぼくらが死ぬまでつきまとってくる。だからこそ、その悲しみに震撼され続けてしまうのであっては、ぼくらはまるで生きながら既に死んでいるようなものになってしまう。
「3」
最近、ビンセント・ヴァン・ゴッホの生涯を読む機会をもった。ゴッホの絵は、余りにも有名だけれど、彼の芸術家としての生涯の苦しみと孤独を知っている人間は少ないだろう。せいぜい、発狂して耳を切ったとか、ひまわりの絵が傑作だ、という位にとどまってしまう。ぼくらは、彼が耳を切った時、ゴーギャンと同棲していたことさえ知らない。そして、非常に重要なことなのだが、彼を精神的にも経済的にも支えてくれたのは弟のテオドルである、ということなども。
ゴッホは印象派の画家として出発した。それが、次第に画風が変化していき、やがて「ひまわり」などの強烈な絵を描くようになる。
「これは気狂いの目だ」と批判したのは、当時一緒に住んでいたゴーギャンだった。ゴッホはピストルで彼を殺そうとする。それが失敗した後で、あの「耳切り事件」が起るのだ。血まみれになった耳を女に送ったりする。そんな風だから、その後数回精神病院行きとなる。そして精神の病は、無気味で鬼気迫る絵を描かしめる。退院してガッシェという医師のもとで療養を続けるため、オーヴェールに向かう。それも弟のテオドルの計らいだ。ゴッホはテオドルを自分の犠牲にしていると思い、暗い気持ちに突き落とされてしまう。発作の恐ろしさを思うと気持ちも不安になる。再び、眠れない夜が続き、極度に疲れ始めた。発作的に、ガッシェを殺そうと企てるが失敗する。
1890年の夏、ゴッホは誰もいない丘の中腹で心臓にピストルの銃口を当てひきがねを引いた。弾丸は心臓をはずれて体の中に止まっている。血を流しながら自力で部屋に帰りベッドに横たわる。かけつけたガッシェとテオドル。ゴッホは弟に向かって言う。「悲しみは、生きている限り続くね」そして、翌日早朝に死ぬのだ。
ゴッホの病気について、多くの学者はてんかんであろうと言っている。そして芸術家にとっては、狂気がしばしば傑作を生む。ゴッホはオランダのグロート・ツンデルという小さな村に、牧師を父として生まれた。小さい頃から変わり者であったらしい。勤めもだからうまくいくはずがない。結婚も断わられる。女ともすぐ別れてしまう。
貧困と孤独と体内の悪魔と闘い続けた彼の生涯は、苦しみと悲しみに充ちていた。初期の作品は農民主体の力強い筆致で描かれ、パリに移ると印象派の影響で想像も出来ないような優しい作品に変わる。バリからアルルへ移るまでの間に、有名な作品が殆んど描かれている。そして、死ぬ間際の発作に追い立てられるようにして描いた数々の作品。「星月夜」「オーヴェールの教会」「糸杉と星の道」「麦畑の上を飛ぶ鳥」・・。
これらは身の毛もよだつような死の予告を表現している。ゴッホは精神の病魔と闘っていた。けれど、彼の作品の変遷は普遍的に人間の内面とつながっていた。あの<死>というものを本気で意識した時の、今にも喉もとから内臓がとび出してきそうな恐怖と。そして、人間の内面が苦しみの垢で塗れている以上、それを掻き落とそうと絵筆をとり続けたゴッホは<悲しみ>に読まれなければならなかった。奇しくも父の死の床で「死ぬのはつらい、しかし生きることはもっとつらい」と述べた彼にとって、正に生涯はその嘆息を裏づける形で進行していき、「悲しみは生きている限り続くね」という理解をもって終わらねばならなかった。
ゴッホにとって、世界は不安と孤独と非連体と無理解というような<悪意>に充ちていた。その世界から、しかし彼はなかなか逃避しえなかった。むしろ、鬼気の様相を呈して立ち向かって行った。だから、彼の絵を描くという行動は三里塚の農民たちと全く同質のものだったろう。一方は<絵画>であり、他方は<地下要塞>であっただけの違いにすぎない。目指したところは、自己の内面に巣くう<苦しみ>を克服することだった。そして、そうすることが結局、彼らを疑いもなく死という断固たる事実に向かわせていた。<それでも>、彼らは闘い続けようとした。そこに生というもののもつ、果てしなく切ない<悲しみ>の深みが存在したのだった。
「4」
三里塚の人たちにとっては、20数年前の戦争体験や機動隊を前面に押し出してくる<反動国家>の体験が鼻先に存在していた。ゴッホにとっては、自分の内面を蝕ばんでいく狂気と闘うための<カンバス>という体験があった。そして、彼らが後を振り返った時には<人生>の裏切りがあった。同時に、彼らは攻撃しつつ逃げている、という<悲壮>さがあった。そしてそれがどっちみち<籠の中の鳥>の出来事である、ということをも彼らは知っていた。やがて<籠>から放たれた時、その<劇>は終らねばならなかった。
18世紀フランスの博物学者ビッフォンは、”世界とは、私にほかならない”と言った。ヌーボー・ロマンの作家たちなら、”世界は意味もなければ不条理でもない。ただ単に、そこにあるだけだ”と、吐き捨てるように言うだろう。現代世界は、結局、そのような意味をもっているにすぎない。サルトルは、恐らく初めから政治・社会に対して<絶望>を抱いていたろう。つまり、彼が理想とする日―革命の日が来る確率は少なかった。
今や経済と物質の時代がやってきて、宣伝・広告だけが氾濫してしまった。一体、どこに理性があるだろう。どこに真実があるだろう?ミニスカートや、トップレスやはたまたホットパンツ、銀座の酒落たレストランや帝国劇場や文化勲章の授与式・・・など、反動政府とその連邦世界は、巧みに「流行」や「性」や「自由」や「教養」を安売りして、ぼくらの目をそらそうとしている。そうして、三里塚の農民の苦しみやゴッホの悲しみや<世界>のもつ真の意味を、低級な酒で朦朧とさせようと企てている。例えば、京浜安保共闘の銃砲争奪を「犯罪だ!犯罪だ!!」と耳もとでわめきちらし、その陰で自分たちのもっと重大な<犯罪>と<暴力>を闇に潜ませてしまう。
こんな目眩(めまぐる)しい繁栄の時代だ。ぼくらの目はとかくそれらに目移りがして、イヤなことを忘れようと努力しているかのようだ。日常よくある心のわだかまりを、心理学者は”認知的不協和”と呼ぶ。”認知的不協和”は、残しておくと不安が高まり、しまいにはノイローゼになってしまう。ぼくらの生存は、やはり無限の空間や永遠の沈黙を恐怖するところの、頼りなくこわれやすい1本の葦であることに疑いはない。
そうならば、ゴッホがカンバスに残した悲しみの傷跡<認知的不協和>を、ぼくらは本当に理解できるだろうか。三里塚の闘争は、帝国劇場でオッにすまして松本幸四郎を観劇している御婦人たちにとっては、全く歯クソも出ぬつまらないものだったに違いない。サルトルが、毛沢東派組織の機関紙「ラ・コーズ・デュ・プープル(人民の主張)」の編集長を引き受けたことを、年寄の冷水とみなす人間も多いだろう。ぼくらが生きている<現代>というものは、かくも風化してしまい、ぼくらが生の悲しみから派生させる<ひたむきさ>を茶化すことに才たけている。
日常生活が、或る意味ではすべて<苦しみ>の連続であり、それを乗り越えて生きようとする<生>そのものが<死>に向かって確実に時を刻んでいくだけなら、ぼくらの<悲しみ>はそこで最少限に食い止められるはずだ。ところが、ぼくらは親子関係をもち、友人関係をもち、大学の共同体におり、そして肝心なことは<国家>と係わっている。その国家は、月面にまで星条旗を打ち立てるような、そんな国家の類型だ。ベトナムから「名誉ある撤退」をするためにインドシナ全域を戦争にまき込む、そういう国家の類型だ。そういう国家の類型に生きようとしているぼくらの<人生>は、だから益々<悲しみ>を深くしている。そして、その深い<悲しみ>から逃れようと、より良い社会を目指そうとすれば、国家という怪獣は、<ガァウォーツ>とぼくらを呑みこもうと震撼させるのだ。そういう<敵>を、軽井沢の駅で見たあの大男・小田実は、”リクツじゃなく、<直感>でわかる”と言っている。
ぼくらの日常生活は、巨大な怪獣の支配に治められてしまっている。殺されてしまうかも知れないし、どっちみち死ぬ運命にある。けれど、1番大事なことは、現在ぼくらは生きている、ということだ。正に、生きていることに重点を置いている。そして、紛れもなくこれからも生きようとしている。だから、ぼくらの存在そのものが<悲しみ>であるとしても、その悲しみを更に倍加させるような<敵>に対しては、抵抗し続けていくという決意をもっている。そして、ぼくらが理解しなければならないことは、そうした国家・社会の矛盾と対決した時にこそ、初めてぼくらの悲しみは<正当化>されるということだ。<運命的>悲しみは、文学や哲学の仕事に任せておけばいいのだ。或るいは、それに耐えられなければ死んでしまうがいい。ただ、かの右翼作家のように「オカマのヒステリー」などと言われるのを覚悟の上なら。
「5」
<正当化>される悲しみというものは、ぼくらを<ガマンならない状態>に置いている。<運命的>悲しみが、口もとや目もとでわだかまるだけで終ってしまうのに比べて、正当化される悲しみはぼくらに義憤を与え、行動を提起している。その行動も、何々のため、という大義名分があるのではない。いや、あってはならないはずだ。ただ生きているから、生きていくから―、それだけのことだ。そこから<変革>が生まれる。
理想は抱かない。現在のこと、たまたまそこへ割込んできた<ガマンならない>問題とひたすら取組んでいく。それは勿論、個人的趣味の問題であってもいい。人間の根源にふれるような普遍的な問題なら、尚更望ましい。そういう問題意識をぼくらに植えつけるものこそ、ぼくらにとって<真の悲しみ>と言わなければならないだろう。
再び問う。ぼくらにとって、悲しみとは何か?ほくらにとって<悲しみ>とは、涙を流して立ち止まり、そして寂しげに立ち去っていくメロドラマみたいなものであろうか?と。
東京より木曽路を経て九州へ – 政経学部1年 平川
東京より木曽路を経て九州へ
政経学部1年 平川
07/17
7月17日は東京はまだ梅雨であった。我ら3人はこの煙雨の中を出発し、五日市街道に入った。未だ武蔵野の面影を残す五日市街道も白くくすぶり視界はきかず、周囲の木々さえ、この煙雨で掻き消されボーッとかすんで見える程度であった。ただ萱草(かんぞう)の鮮かな色のみ目に入ってきた。だが、我らの自転車は、こんな天候でも河口湖目指して快調に走った。と言うとウソであった。
実は、出発直前に某氏の自転車のパンクが発見され、大幅な時間的変更を余儀なくされた。快調なんてものでなかった。その上、私の自転車、早くも国立市役所付近で故障して呉れた。トップにもっていったらチェーンがはずれてしまったのである。出発時刻が遅れていたから、この様な事態は非常に遺憾な事であった。腹もたったし、ディレイラーの調節も面倒くさかったから、今後トップを使わず走る事にした。
最早この時、我らは国道20号線に入っていた。大垂水峠を上って下って相模湖へ出て、大月へ向かった。これ以後の道は全て、私には初めてであった。途中、日本3奇橋の1つ猿橋で記念撮影。大月からは国道139号線に入った。この道は全て上りで、富士吉田に着いた時、我らは疲れきっていた。時計は6時を過ぎていた。
「よし、今日は富士までだ」
と同時に宮崎さん得意とするマップリーディングが始まった。宮崎さんの指図に従って角を左に曲がった。すると、自動車から声がした。有難い。皆と相談して泊まらせて頂くことにした。結局この日は、その人の好意によって、晩飯を御馳走になり、畳の上で寝かせてもらうことになった。
07/18
朝起きたら足がきしんだ。腹に力を入れて足に負担がかからぬようにして立って、窓の外を見た。『オッ!!富士が見える』。富士は考えていたより低かった。天気にも好転の兆しが見えた。
お礼を言って此所を発ち、河口湖によって御坂峠を上った。絶景かな絶景かな。宮崎さんと私は、横目で富士と河口湖を睨みながら上った。ようやく上った峠だったが、何もなかった。天下茶屋は崩れ落ちんとし、太宰治の「富士には月見草がよく似合う」を偲ぶには時期尚早であった。せめて放屁でもと思ったが、出なかった。残念無念。
新道を通って行った信田は、下で待っているだろう。急ごう。
ハンドルにしがみついて坂を下った。が、石ころの待ち伏せにあい、あえなくパンク。その後で、またミサカイもなく転倒した。流石、名に負う峠、アッパレだ。これで事故が終わればよかったのだが、舗装道路に出てキャリアがずれるという大失態をやらかした。キャリアがずれた時の衝撃は大きく、私に、『死んだ』という感を与えるものであった。
今日も、私の事故のため予定が大幅に遅れた。これに対処するためのスピードアップは私に苦痛を与えた。私の自転車はトップに入らないから、富士見町に着いた時、モーローとしていた。
07/19
昨日、トップがはいらなかったのはこたえた。早速、点検すると、問題はディレイラーになく、ワッシャーにあった。とるに足らぬ修繕だったが、これを直した事でメカに強くなった気がした。
私達は茅野駅に荷物を預けて、蓼科有料道路を息をはずませながら上った。スズラン峠(約1,760m)を頂点として白樺湖までは下りである。下りきると目の前にビーナスラインがうねっているのが見えた。一息ついて霧ヶ峰目指してアタックを開始した。山の端を3、4度ぬけて車山肩(約1,810m)にやっとの思いで達した。高原の涼風に吹かれているうちに、2人も到着。しかし、両氏が着くと同時に黒雲が覆い、天候があやしくなった。あわてて霧ヶ峰までのダウンヒルを遂行。霧ヶ峰は平穏そのものであった。私達は高原をゆっくり堪能したかったが、時間に追われて直ぐ下山した。そして、茅野に戻り、荷物を受け取り諏訪で宿をつくる事にした。
諏訪の一角に野営地を見つけた。蚊の多い所だったが、日も暮れた事だし渋々荷を降ろしだした。私は明日からの事を考え、しんみりとした気持になっていた。
「先にテントを張る。いいなア」
宮崎さんの声が聞こえた。3人でテントを張り始めた。
「平川はテントを調べてみたか」
「いいえ、調べてませんけど・・」
「調べてみた方がいいよ。ペグが足りなかったり、綱がない事があるから」
早速テントを点検してみた。ナイ。ナイ。いやペグが4つしかないのである。クソッ!一瞬当惑して保泉氏をうらめしく思った。しかし、明らかに保泉氏をしてテントを選ばせしめた私が悪い。困った。困った。
後になるが、この事に保泉氏に問うた。保泉氏微笑をもって、淡々として曰く、我平川をして練習せしめたのであると。
07/20
もう陽が昇ってテントの中は明るく、暑苦しくさえなった。我らはテントをたたみ、今日も旅立った。先ず、塩尻峠とやらを一気に上り1休み。下に、諏訪湖を中心としてそれを囲むように屋根が競いあっていた。そして遙か遠くに、うっすりと八ヶ岳がそびゆるを臨みながら、手足を伸ばして深呼吸した。
下界を見降ろすのも束の間、私達は車の排気ガスをかき分け下った。また、この頃から天候も安定しだし、以後、背中の”WASEDA”は真夏の太陽を真面に受ける事になった。
塩尻で、宮崎さんと信田と別れた。塩尻を出た時、時計は、既に12時を回っていた。果たして、中津川へ着けるだろうか。早くも心配が募ってきた。
少し道を間違えたが、まず無難に、国道19号線に出る事が出来た。19号線は、アスファルト舗装を仕返たばかりであり、また、交通量も上々であった。景色にしても、マアマアであり、私の前途には、洋々の観があった。
右手に、雲に頂上を隠された北アルプスの連峰が、「来年は、俺を窮めてくれ」と言わんがばかりに、そびえていた。しかし、その北アルプス連峰も、まもなく、姿を消した。
ところで、私は、「是れより木曾路」の碑の前で、絶対写真を撮ろうと考えていたから、常に道路の両側を注意して走った。その甲斐あって、無事に、その碑を写真におさめる事に成功した。しかし、実は、どうやって写真を撮ろうかと苦慮し、随分、その当りを捜し回ったのである。大きな石を運んできて、その上にカメラを固定したり、地面に腹ばいになって、カメラの角度を定めたりした。とに角、色々な事をやった後、ガードレールの支柱に固定する事で、事が足りることに気が付き、今後の写真撮影を楽観した。撮影後、ひたすら、木會福島目指して走った。
「苦しい!」
またもや、排気ガスの洗礼である。峠にさしかかると、いつも、ダンプが勢揃いして、しかも安全運転をして呉れる。サッサッと、通っちまえ。畜生!それでも、私は頑張った。鳥居トンネル(1,045m)が見える。後は下りと思いきや、さにあらず。長い。長くて真っ暗。自転車のライトも定まらず、本当にお先真っ暗。右に寄っては、対向車のライトに驚いて左に寄り、左に寄っては、壁にぶつかりそうになり、また右に寄る。後から来るトラックや自動車が、通り過ぎては自分の身を確かめた。一体、こんなトンネルを如何なる理由で、「トーリイー」と名付けたのであろうか。通過後、一息ついて水をグイと飲み、木曾福島までの下り道をとばした。
強行軍であったから、此所の「養老の滝」という店で昼飯を食べ、そして、寝覚の床を見ただけという状態で、南木曾から旧中仙道に入ることとなった。この街道には、最近クローズアップされてきた妻籠宿、馬籠峠(801m)、馬籠宿が並んでいる。
実は、昨日まで、私はこの道を省略するつもりであったが、宮崎さんの「行く可し」の言葉に励まされて行ったような次第であった。黄肌をむき出した山道を上りつめると茶屋が1軒あった。空は、夕映えを見せ、森閑とした情趣に包まれていた。程なく自転車をこぐと馬籠宿に着いた。陽の落ちた馬籠宿は青白い灯がともり、左方彼方に、広い雄大な裾を持つ恵那山がそびえたっていた。子供が、2、3人、私を見つめていた。もう暗い。一瞬、私の胸の中で、焦燥感と恐悸が交錯した。涙が出そうになった。しかし、私は足を進めた。宿場の石畳の道を少し下ったら、右手に藤村記念堂があった。
「もう閉まっているようだ。急ぎ足で暇もない」
下り道で、リュックサックを背負った4、5人の女学生とすれ違った。
「多分、馬籠に泊まるのだろう」
一帯は、蜩(ひぐらし)が鳴き叫んでいた。時折、枝がガサッと搖れた。そのたびに、背筋に寒気が走った。
夜7時20分、中津川に着いて、肩の荷を降ろした。しかし、夜の町は、様子がわからない。心細い思いでさまよったあげく、町はずれの或る崖の下にテントを張った。今考えるに、無理をせず、妻籠宿でゆっくり体を休め、その代わり、夜明け前にそこを発てばよかったように思う。
07/21
今日は、彦根までだが、体力が持つだろうか。6時間も寝ただろうか。
昨夜、暗闇の中で、塩尻で購入したばかりのペグを使って、テントを張ったが、朝起きて改めて驚いた。そばの橋を自動車が通るたびに細かい石が落ちてくるのだ。妙な感慨に浸っている暇はない。早いうちに沢山行って6時までにテントを張ろう。
土岐市で国道19号線にサヨナラして、美濃加茂経由で日本ラインを下り、犬山に到着。但し、私は、船の転覆を恐れて、乗るのをやめた。日本ラインは景色が良い上、水しぶきをあげる船があったから一層良く見えた。余談になるが、この船は、名鉄の支配下にあり、一旦下ってしまうと、再び上ろうとせず、トラックで美濃加まで輸送してもらう。そしてまた、乗客を運ぶのである。
この頃から、かなり疲れを覚えたが、岐阜、大垣、関ヶ原を経て、無事に米原にテントを張った。岐阜から関ヶ原までは平坦直線路、景色最悪、しかも向かい風と、悪因子が揃っていたから苦戦した。
07/22
琵琶湖でも、公害と言わずとも汚れている。浮遊物も漂っていた。しかし、魚が泳いでいたから、抵抗力の強い人間が泳げない事はないと考え、朝の一時を水泳して、楽しんだ。水も心持ちヌルッとした感じで、必ずしも快感を与えるものでなかった。水も濁っていた。でも魚に習って、勇気を出して目をあけてみた。何も見えなかった。
水泳をした後、彦根城を周囲から隈なく見学して、琵琶湖岸サイクリング道路に出た。左方には青田が連なり、右手には時折湖面が顔を出す。道路は、舗装したてとお見受けした。
ところが、出発が遅れた上、途中で道に迷うというアクシデントが起こったので、大橋通過時刻も2時10分となっていた。あせっても始まらないと1休みして、近江神宮前から峠越えして、京都の北白川に出た。そして、京大、同大の前を通って御所より駅に下り、西国街道を通って豊中の親戚の家へ走った。
大阪で、3日間休養をとった。万博に行ったり、会食に出席したり、全て、あちらさんの金で遊ばせてもらった。
07/26
サイクリングも飽きたが、ここでやめると尻切れとんぼになってしまう。幸い、叔母の実家が牛窓(岡山)にある。そこでまた考え直せばよい。この日は、6時前に出発して、海岸沿いのコースを選んで走った。姫路に着くまでは、快調そのものだったが、姫路城見学に時間を費やしすぎた。そのため、後の行程にしわよせがきて、赤穂御崎には行けなかった。
私が赤穂市内の某店前でアイスキャンデーを食べていたら、或るオッサンがやって来て、
「どこから来たか」と聞く。
それで私は、
「東京から来ましたけど」と答えた。
するとその人、
「ゴッツイ。ゴッツイ」を連発する。
私は初め、自分の顔がゴッツイかと、真面目に考えた。しかし、どうやらそうでないとわかり、おかしくなった。そして、その次に、
「何日かかった。ここまで何日かかった?」と聞く。
「実際に走っている日は、今日が7日目です」と答えると、再び
「ゴッツイ。ゴッツイ」
を連発するので、ばつが悪くなって、そこを逃げだした。
その後、海岸沿いの道から(備前町から)、一旦国道2号線に出て牛窓へ入って行った。牛窓到着は7時半、日暮れ寸前で、ライトなしでやっとセーフという状態だった。
07/28
牛窓で一日また休養した。ここで、ライトをつけてもらったし、私自身も自転車の点検をやっておいた。出発に当たり、途中まで伴走して呉れた。
岡山市内に出て、後楽園を見学した後、鷲羽山に向かった。瀬戸内海第1の眺望と聞き、そのパノラマを期待していたが、曇っていたため、眺望はさえなかった。
この日は、予定通り笠岡に着き、某神社境内にテントを張った。笠岡には、駅を中心として半径1キロ以内に、3つの神社がある。
初め、最も見晴らしのよい神社にテントを張ろうとしたが、しかしながら、まだ陽が落ちてなかったため、境内には2、3人の人が遊んでいて、私をいぶかしそうにみつめ、暗黙のうちに私を好ましくない人物として立ち退かせようとした。私も負けじと見かえした。が、いざこざを起こす気はなかったから、潔く退散し、別の神社を選んだ。
テントを張った後、飯と風呂を捜して、市街へのり出した。笠岡の市街は、道路が極端に狭く、商店街の裏側は、軒の低い昔風の家でつまっていた。人の身なりも決してよくなく、どこか暴力団でもいそうな町だった。私は、先ず風呂を捜した。ところが、町の人の話によると、一日おきだから今日はあるかどうかわからないというものだった。幸い風呂屋は営業中で、旅の汗を流す事ができた。
飯を食べて、急いでテントの所へ戻った。直ぐテントの中に入って寝たが、暑苦しくて眠れなかった。それに私は無断でテントを張っていたから、首かにたたき起こされるのではないだろうかと、とビクビクしていた。夜10時頃、
「オーイ、オーイ」
という声がした。私はそ知らぬ顔をして、聞き流しておいた。向こうは続けて何度も呼んだが、それでも強情に寝ていた。とうとう向こうさん、
「もう寝たのかな」
などと、ブッブッ言いながら退いた。しかし、今度は、2人位の人が私を呼び出したから観念して、
「はい」
と返事して首を出した。観念して首を出したのだが、彼らには、私を立ち退かせる意志は全くなく、かえって、宴会に招かれる事となった。この好意にあまえて、眠たい目をこすりこすり、旅の話をしながら、ビール、刺身、肉を頂載した。
07/29
今日は、YHに予約をとっていたから、自然に、距離が限定され、尾道までしか走らなかった。尾道も笠岡に続いて、かなりこせこせした町であった。但し、道路は幾分広かった。ここは、寺の数が多く、そのうちの1つの西国寺へ行った。
尾道から目的地の生口島に向かった。生口島には、西日光耕三寺があり、日光や平等院鳳凰堂等に似せた建築物が、どぎつく色塗られていた。100円の入場料を払って、1時間も見なかったのは失策だった。
07/30
予定通りならば、広島市内某所にテントを張るはずだったが、家恋しさのため、一気に岩国まで足をのばした。
午前9時発の船で、50分間の乗船の後、三原に上陸。そこから呉経由で、広島へ向かった。瀬戸内海には飽き飽きしていたから、三原から呉までの77キロを、全く休みをとらず走った。呉に入って、うれしい事があった。それは、下関221Kmの表示だった。これに勇気づけられて、広島市内を見物して国道2号線を岩国へ走った。岩国市内の地図を持っていなかったので、テントを張らずに、YHを利用した。
07/31
家へ急ごう。最後の宿泊地岩国半月庵YHのペアレントさんから、御守りとしてのヤツデを戴き、錦帯橋を後にした。ヤツデの御利益あってか、たび重なるパンクにめげず関門海峡を、くぐり抜ける事に成功した。(関門海峡は非常に狭く、対岸の人が見える所さえある。この下に関門国道トンネルが通っていて、自転車は30円払う事によって、人道を通れる)
以上のような経過をたどって、九州の地に入り、勇んで小倉へ走った。が、またもやバンク。家までニキロという所から、自転車を押す事になってしまった。しかし、無事家へ着き、東京から自転車で帰る事を果たした。時恰も7月31日。夏も盛りであった。
輪廻 – 法学部4年 篠原
輪廻
法学部4年 篠原
暇な人はどうぞ最後まで読んで下さい
そうでない人は途中までで結構です
【河】
河を1本の大木が流れていく。静止した世界の中で、河だけがあたかも自分が世界の中心であるかのごとく生きている。その流水に身を任せ大木が流れている。
「世の中なんと静かなんだろう。毎日毎日相も変らず静かなものだ」
大木は大きな胸の中に、空気を一杯吸い込み溜息をついた。もう1度空気を胸一杯吸い込もうとした時、腹の方から声が聞えた。最初は鳥でも乗っているのかと思ったが、すぐに人間である事に気がついた。
「あーあ、随分眠ったな、どれ程眠ったかな」と人間は木の上に立ち背のびした。
「おいおい、おまえは何者だ。人の上に無断で乗るなんて失礼じゃないか!」
木はこの小さな生き者をからかうように言った。
「いや俺だって何故今ここにいるのかわからないんだ。何しろ長い間眠っていたもんでねえ」
彼は木の上から海のように広々とした河を眺めながら言った。
「眠っていたもないだろう。おまえさん、一体どこへ行くつもりなんだ。俺はこの流れに乗っていくしかないんだぞ。俺には足もなければ手もない達磨同様なんだ。自由に動けないんだ。だが、おまえは別だな。人間だろ。自分で歩けよ」
大木は相変らず、この小さな存在をからかい続ける。
「ちょっと待ってくれよ。歩けもくそもないぜ。一体ここはどこなんだ」
「どこでもいいじゃないか、それを知ってどうするというのだい。俺は陸では案山子みたいにただ立っているだけなんだぜ。こうして河にいると動けるんだよ。考えてみろよ、足のない俺が動けるんだぜ。おまえたち、人間どもにはわけのない事だろうが。とにかく俺はこの流れに乗って流れていくだけだな」
「この河はどこまで行くのかな」
「それもどうでもいいことなんだよ。俺にとってはね」
「しかしだな。どこへ行くかもわからずにただ流れているだけとは、ちと能がなさすぎるぜ」
「おまえさん達人間共はすぐ頭で考える。考えるだけじゃないか。どうだっていいんだよ、そんな事は。いやなら下りろよ、その方が俺だってすっきりするしな」
「下りると言ったって、この海のような河の真中じゃ無理だぜ、泳ぐにしてもどこへ泳げばいいのかわからないよ」
大木は幾分にこの人間を煩わしく思い、皮肉を込めて言った。
「だからこそその御立派な頭を使って考えてみろよ、人間さん」
「状況を冷静に判断して現在は君の上にいるのが、最上だと思う。しばらく御厄介になるよ」
大木はそれには答えず、また何もなかったように流れに身を任せた。人間は今どうしてここに在るのか考え始めた。
【暗黒の世界】
彼は暗黒の中で生まれ、しばしの間、眠っていた。いや眠っていたというよりも外界へ脱出する機会をねらっていたのである。目は勿論不必要であったが、手探りでその暗黒の世界を探ってみた。やがて自分1人に与えられたスペースの狭さに気づき、それ以上動いてみた処で無駄だと悟った。しばらく眠ることにした。
どれ程眠ったのだろうか、急に世界が動き出した。
『地震だ』
彼はとび起き身を隠そうと思ったが、そうすべき場所もない事を思い出し、暗黒の世界を右往左往するだけであった。と急に頭上にひびがわれ、その隙から1抹の光がさし込んだ。細く強烈な光だ。彼は思わず目を閉じた。目が焼けつくように痛む。
彼はその苦痛を通じてどうして自分に目がついているのか知らされた。やはり世界は暗黒だけじゃなかった、そう思うといても、立ってもいられず、未知の世界に対する好奇心が沸き起り、光に目を慣れせながら序々に目を開いた。先程に比べると割れ目は幾分大きくなっていた。その割れ目に手をつっ込み、押し広げてみた。意外と柔かく、2、3度広げると体が出入りできる程に広がった。そして勢いをつけて体を押し出し外界に脱出した。
【純白の世界】
外界は雪におおわれて真白だった。それでなくても今まで暗黒の世界にいたのである。彼はあまりの明るさに眩惑を起し、雪の中に体をうずめたまましばし動けなかった。
雪はかなり積っているが、さほど冷たく感じなかったのは太陽が強く照りつけているからだ。強烈な太陽の光線にも目が慣れ、彼はようやく身を起した。
初めて見た世界は、音もなく静かな山の上であった。大きな木々が雪の重さに耐えかねているようだ。
彼は本能的に歩きだした。雪に足をとられて歩きにくいが、1歩1歩、力強く歩いた。少し歩くと体中汗をかいた。遠くでゴーゴーという音が聞える。彼は何とはなく、その音のする方向に歩き出した。
音は序々に大きくなる。どうやら何かがあるらしい。近づくにつれてそれが河であることがわかった。強烈な太陽に照らされて雪が溶け、高い所から低い所へと群れを成して集まり、河となり土砂や木々まで運ぶ。
彼は重い足を引きずりながら、やっとの思いで河までたどりついた。
【滝】
河の水は雪の白さと比べ、ひどく汚ないものだった。
彼は雪の中を河まで歩いてきたため、疲労を感じ、河岸で雪のない所を選び、身を横たえた。彼はほんの少し眠ったように思ったが、身をきる冷たさに驚き、とび起きた。気がつくともう河が自分のすぐそばまできていた。土砂が少しずつ削りとられ、彼の横たわっていた場所まで水がきていたのである。
彼はとび起き、安全な場所まで逃げようとした瞬間、地盤がくずれ足をとられて水の中に吸い込まれた。彼は1度は浮き上がり岸へ泳ごうとするが、そうすればするほど岸から遠ざかり、流れにどんどん押し流された。彼は冷たい水のために体中の感覚を失いかけていたが、すっと伸ばした手に何か大きなものが触れたので、それを握り、すばやくその上に乗り意識を失った。
彼はやっと自分がどうして大木の上にいるのかわかった。あの時に無意識でとび乗ったのが、この大木だったのである。彼はまたしても木の上に立ち、河を見渡した。大きな河だ。海かと見間違う程である。
彼は大木に話しかけた。
「おい、とてつもなく大きな河だな」
大木は又、睡眠を邪魔されたので少し不機嫌になりながら答えた。
「ああでかいよ。しかしこの河も上流は雪溶けの水が流れてできた小川のようなものだった。それが合流してこんなにでかくなったんだ。これからまだ大きくなるんじゃないかな」
「これ以上大きくなるとは信じられないな。陸が見えてもよさそうじゃないか。畜生!陸さえ見えれば何とかなりそうなものだがな」彼はあたかも一時も早く陸に上がりたい気持であるかのようにつぶやいた。すると大木は悟すようにいった。
「おいおい、おまえさんが陸へ上がっても、所詮は自分の小さな足で歩かねばならんのだぞ。それよりも俺の上で寝ながら動けるのだから、このままの方がいいぞ」
彼は自分の意思に関係なく流れに押し流されるというのが、やりきれなく、少しでもいい、自分の足で自分の好きなように歩いてみたいと思った。
「相変らず静かだな」
という大木の声に彼は我にかえり、耳をすました。彼は成程静かだわいと思ったが、何故か遠くで音がするような気がした。彼がかって聞いたことのあるなつかしい水の音のように思われた。いやそんなはずはないと思いつつも、耳をすますとやはり聞える。
「おい、起きろよ、何か音が聞えるぞ」
彼は大木の上で足を鳴らした。大木は小馬鹿にしたように、
「そんなはずはない。相変らず静かだよ」
と言った。しかし、彼はそういわれるとかえってその音がはっきりと聞えるように思えた。
「おい、やっぱり聞こえる。あれは確かに水の音だ。何かあるぞ。」
彼の真剣な声に、大木も耳をすましてみた。心なしか何か聞こえるようである。いや大木も確かに聞えたのである。
『水の音だ』
その音は序々に大きくなってくる。いや音は変らないのだが、彼等がその音に近づいているのだ。
「おい、確かにあれは水の音だ。しかし水があんなに音をたてるとは、こいつは何かあるぞ。もしかすると滝でもあるんじゃないか」と大木は自分の思惑がはずれていることを願いたい気持でいってみた。
「滝があると一体どうなるのだ。このままだと一緒に滝から落ちてしまうぜ。そうすれば…」
彼はそれ以上は考えたくなかった。音からすれば相当大きな滝に違いない。かといって今さら流れにさからう事もできないし、泳ぐこともできない。どう考えてみても何もなすすべがない。自分の微力さを嘆いた。もはや事態は明白である。彼はこの大木と共に滝から落下するほか道がないのである。まさに死刑囚の心境で近づきつつある滝に身を任すほかないのである。
心なしか流れが早くなった。滝は耳を裂くような大きな音をたてている。少しずつ、しかも確実に滝が近づいてくる。滝が目前に迫った時、彼は大木から河の中に飛び込んだ。
そしてそのまま流れにのまれ滝を落下した。彼は滝壺に落ちる瞬間、大木の割れる音が聞えたように思った。
【分裂】
彼はまた以前のように大木の上で目をさました。彼は自分がかってこのような状態を経験した事があるような気がした。それは記憶の先行によるものかと思った。がよく考えてみると確かにこのように大木の上に乗っていた。いやその大木と共に滝から落下した事を思い出した。また無意識のうちにこの木に乗ったのだと思った。滝から落ちたことを除けば以前とまったく変わりないかのように思えた。まわりの景色も以前と変化なく、もはや滝も激しく落下する水の音も聞えなかった。彼はようやく冷静さを取り戻し、改めてまわりを見た。
そして初めて、もう1人、いやもう2人の自分が同じように木に乗って流れているのを発見した。彼は左右両方の鏡に自分の姿が写っているのかと思ったがすぐに、馬鹿げた仮想だと知らされた。
もう2人の彼等はまったく彼に無関心のように大木の上に横たわっている。滝から落ちた時に肉体が何らかの衝撃を受け、大木が割れたように彼の肉体も3つに分裂したのだ。と同時に彼自身の肉体は以前と比べて、わずかに縮少していた。そしてこの時から彼、いや彼等は定期的に分裂を繰り返し、そのつど肉体が縮少していくという羽目に陥った。
彼等3人はそれぞれの木に乗り、お互いに1定の距離を保ちつつ河を下った。流れているのが3人であるという点を除いては、以前とまったく変わりなかった。静かな、まったく静かな状態が続いた。彼等は一言も口を聞かなかった。まるで口をきかなくてもすべてを理解し合っているようであった。
【独立】
3人は相変わらず無言のまま流れに身を任せていたが、その河が少しづつ変化し始めた。直線的だったのが少しではあるが蛇行し始めたのだ。河はいよいよ中流にさしかかったのだ。そして彼等3人を別れさせる決定的な時期がやってきた。河が2つに分かれたのである。
3人は木が流れるに任せた。もとよりそうする以外になすすべがなかったのだ。右に流れたのが1つで、後の2つは左の方へ流れた。
(右の1人)
彼は2人と分かれてすぐさま母体に変調をきたし始めた。そろそろ分裂する時期だったのだ。彼は苦痛も感じずに、まるで蟬が孵るように口からもう1人の自分を吐き出した。細胞が分裂する時は、普通2分の1に分裂するものであるが、滝から落ちた時は、そのショックにより3つに分裂したのだった。
彼はもう1人の自分に対しては母性愛のようなものなどまったく感じなかった。ただ生理的に排泄物を吐き出したにすぎなかった。
これから順列的に自分が増えるということが、果たしてどのような結果を招くかということにまったく無関心であるかのように、彼らは無言のまま木の上に立っていた。河自体も序々に変化をきたし河口が近くなってきた。
彼はもう1人の自分を吐き出してからというものは、急速に分裂の期間が短くなった。しかも吐き出された者も加速度的に自己分裂を速めた。彼の大きさは序々に縮少していくが、増殖する速さには追いつけず、見る見るうちに流木は彼自身であふれんばかりになった。が、それでもなお彼等は分裂を続けた。ついには限りある木には収容しきれず、自然淘汰の法則が働き、本能的に1人を吐き出した者は自ら河の中に身を投げた。
少し経つと、どちらが産んだものか、生まれたものか区別がつかなくなり、木の上で自分の場を確保するために押し合いが始まり、そのためついに木が1回転した。と同時に木の上に乗っていた全員が河の中へほうり出された。長い間の自己分裂により体は丁度、めだか程に小さくなっていたので、あたかも大海原のど真中で船が転覆したように、誰もどこへも泳ぎつけなかった。
木はいままで黙って彼らの愚行を見守っていたが、
「人間というのは何故こんなに愚かなんだろう」
と一言いって、また何もなかったように河の流れに身を任せた。
(左の2人)
もう1人の自分と分れた彼等2人は「右」のそれと同じように自己分裂を繰りかえした。彼等も「右の彼」と同様に木の上で自分の場を確保するための醜い争いが始まるかと思われた時、彼等の中の1人が大声で叫んだ。
「向こうの木を奪おう。そうすりゃまだ十分余裕ができるぜ」
そして彼等はためらいなく河に飛び込み、あたかもブール・サイドで初心者がするようなバタ足で木を移動させた。それと同時にもう一方の木に乗っている連中も同じ事を考え、同じ方法で互いの距離を縮めた。
木と木は遅々としてではあるが、着実にその差を縮めていった。やっと木と木がくっついた時には、大半の者が疲労により木によじ登ることさえできず、ついには河に沈んでいった。強靱な者だけがやっとの思いで木の上にはい上ったが、もはや戦う目的は充分達せられ、その必要もなくなった。生き延びた者はただ疲労感だけが満身しその場で深い眠りに落ちた。
眠りながらも彼は自己分裂を繰りかえし、それに比例して体は小さくなる一方だった。彼が深い眠りから醒めた時には、河はすでに河口に近かった。
彼にとってもはや、河も海も同じであった。彼にはどんなに小さな河でも海にみえたことであろう。彼はそれ程までに小さくなっていた。河口に近いせいか、木は異常な搖れを繰り返えした。その度、彼等の1部が水中へ振り落とされ、ついには必死にしがみついている1人を残して全員が木から落とされた。彼等は盛んにもがいたが、鯨以上にも大きな魚(単なるダボハゼにすぎなかったが、彼等には鯨以上にも見えた事であらう)がやってきた。彼等は思い思いの方向へ全速力で散らばった。
ダボハゼは小さな彼の口をゆっくりとあけ、そして彼等すべてを飲み込んだ。
木はやっかいな荷物がなくなったので、気持よさそうにゆっくりと海へと流れていった。
【河】
河を1本の大木が流れていく。静止した世界の中で、河だけがあたかも自分が世界の中心であるかのごとく生きている。その流れに身を任せ大木が流れている。
「世の中なんと静かなんだろう、毎日毎日相も変らず静かなものだ」
大木は大きな胸の中に、空気を一杯吸い込み溜息をついた。もう1度空気を胸一杯吸い込もうとした時、腹の方から声が聞えた。最初は鳥でも乗っているのかと思ったが、すぐに人間である事に気がついた。
「あーあ、随分眠ったな。どれ程眠ったかな」
と人間は木の上に立ち背のびした。
(筆者注)
これからこの話がどうなるか知りたい人はどうぞ最初のページへ戻ってください。
眩暈(めまい) – 理工学部4年 木村
眩暈(めまい)
理工学部4年 木村
(1)
背中に太陽が落ちるのを感じる頃には、妙な形に引伸ばされて、道案内者の様に逃げもせず戻りもせずに、私と同じ速さで前を行く自分の影にどうしても視線を奪われてしまう。血と肉の疲労によって帰された意識が平性の分別をあやふやにして、こうも容易く単純な物に心惑わされてしまうものなのか。
がんぜぬ子供の様に、眠むたげな私の瞳は前を行く平面に凝縮された私の分身を追っている。やつはすこぶる忠実で真正直に動いて行く。しかし、時々悪戯けて径業師の様に振舞う。目の前に石ころや道路脇に止められた自動車があれば、私は衝突を避けるために、神経を苛立たせねばならないのに、やつときたらおかまいもなく、ずかずかとその上を通っては平気な顔をしているのだから。樹に駆け登ったり、石屏にへばりついたり、かと思うと、川の水面を水澄しの様にいとも簡単に泳いでしまう。それでも周りにやつの見せ場となる舞台に事欠くと、黙って元に還っては、こんなの朝飯前さと言いたげにすましてしまう。そして、そんな変幻自在に動きまわれるやつが羨ましいと思う処まで、私の血と肉は、疲労の餌食になってしまってるのだ。
2日前、まだ東の空が白らむ前に寝静まったまへの家をとび出し、軽装な自転車を駆って、漸く水温み、小動物が蠡き始めた初春の武蔵野から秩父山魂に続くなだらかな丘陵地帯に気まゝな1人旅をして、今その帰途にあるのだ。行程に充分な余裕をみてコースを選んでいたのにもかわらず、そこは気まな1人旅、昨日のこと、体にうっすらと汗を感じる位の、小さな峠を上り切った処で、柔らかな草布団の上に寝ころんだのがいけなかった。丁度うまい具合に冷たい風が木立ちに遮られ、陽だまりになっているのを幸いとばかり、激しく緊張してた全身の筋肉が、心地良い痺れと共に解きほぐされて行く快感に現をぬかし、いつしか、微風に揺する梢の音が妖精の歌声に、瞼に映る和らかな春の陽が乙女の頬の赤ら味に、耳許で打つ心臓の鼓動が舞踊会に流れるワーグナーの円舞曲に変わってしまった。車のクラクションに起こされてすっかり眠ってしまった事に気付いた時、すでに時計は、短針が文字盤の上を2度半回ってるのを示していた。取り立てて気に病むこともないが、この風流じみたひと時が、結局今日の強行軍にまで影響してしまったことになるのだ。
今うんざりする車の洪水の中、青梅街道を走るこのあたりで、親切にも昨夜の仮りの宿を与えてくれた農家を発ってからざっと120余キロ走っている計算になる。それに家に帰り着くためには、この窒息しそうなガソリンの匂いの中をくぐってまだ30キロ近く走らねばならない。そして、今日は私にしてみれば、やつに翻弄されながらも、かなりのピッチでペダルを回している。今になってじわりじわりと、腰から脚にかけて厄介な手合いがのさばり出して来たのだ。視神経といわず、私の体を支配しているありとあらゆる神経にそれらの尋常さを失なわせている。眠気すら感じている。こんな危険な状態にあるというのが経験的にも判断がつくにもかかわらず、相変らずのスピードで突走っている。何故か。それは私に約束されに帰宅の時限があるからだ。その時限とは、今晩ラジオの音楽番組で放送される現代音楽の電子音楽曲の初演のものをテープに録音したいという、他人からみれば実に笑止を莫迦々々しい、たわいない事に間に合わんが為に足掻いているのだ。しかし、私にしてみれば、それは莫迦々々しいとして片付けられない意味がある。他人と私の意識は別だし、旅とこれとも又意識は別である。
『危険に身をさらしてまで、あるいは運が悪ければ肉体を犠牲になると予測されても』と他の誰かが私を嘆くかも知れない。しかし、この愚問に対し叱咤すべく意識は、疲労に暈された今の私にでも綽然としている。
「危険?」どうやら君は被害妄想とやらの詐欺師に弱味を握られてしまっている。危険こそ、裏を返せば我々が口を糊するに必要に近い十分な糧さ。危険に身を晒さずして何如に己の生を知る。これ以上の言及には及ぶまい。もしそれでも確然としない輩があれば、君の心は被害妄想色に塗りたくられてることになりそうだ。聞くところによると、勇気色との混和によってそれは無色になるらしい。
1つ試したらどうだい兄弟。「犠牲?」厭な言葉だ。血生匂くて厭になる。犠牲には血は付き物だ。神の供物になった羊の血、最後の晩餐に基督が葡萄酒を指して宣った血、その紅い血だ。肉の片割れたる血が破滅することは、とりもなおさず肉の死だ。すなわち、生物が静物となる事さ。犠牲とはそういうこと、というよりそれだけさ。ほう、今度の君は察しがいいぞ、その通り、見のがしてならないのは今君が指摘しようと躍起になっている魂、それを忘れないで欲しい。魂に永遠の犠牲などありゃしない。君も知っての通り人間てやつは便利なもので、ずる賢い形而上的手段によって思うまゝに処理してしまう。それだけと言ったのは将にこの事であって、物質形態に滅亡があるにせよ、意識形態に於いては変化こそすれ、脈々と息づいているという事さ。でも、正直言って我々は、血に対する本能的恐怖感念から瞬間的に理性的行動を見失なってしまいがちで、後になって自分の不条理な行動を膝を叩いて悔恨する。しかし、そこに愚かな人間たるを愛すべく所以がある。そうは思わんか兄弟。
「予測?」予測、予想、予見、先見、可能性、確率、とこの種の言葉は多々ある。そして、これらは皆我々の思考行為に於いて何んとなく歯がゆい、遊離しがちなあるいは、首枷となる概念であり、反面、最も興味のある事に異議はあるまい。まやかしでない本物の予見者の登場を焦れる執念は古代ローマに於いても、20世紀の現代に於いても同じに人間の心の中に渡らされている。科学という名札を下げた妖怪に、より完璧な予見者たるを期待、信仰するのが好例だろう。しかし残念ながら、よりという首枷は当分合鍵を見つけ得ないだろう。少なくとも、過去から未来に突走る時空座標系、畢竟、地球生活空間系で物を語る場合、絶対将軍の抬頭は許されず、全て相対将軍の采配に委ねられている分だから、絶対将軍の采配を受ける時空座標系に普延された生活が体験されなければ所詮、本物の予見者の降誕は茶番でしかない。
ぞくぞくする様な霊感があったのでと、囁きながらギャンブルに身を弄した経験は君にもあるだろう。確かに1刻先を期待する時の官能的ともいえるあの緊張は何んとも言えない。そこで考えて欲しい、その時我々は常に自分の都合のいい様に、その期待値を10割に見積っているから愉快だ。それで順当なのさ、自分の期待値を0にしてギャンブルする半可通もおるまい。そして、それは生きる事にも当てはまる。何故かって、そこまで私に言わせるのかい。後生だから兄弟、それに必要なエネルギーは家に帰るまでの力に代えさせてくれ。ただ、「人生は賭け」という俗物的なこの言葉を君の明晰な頭脳を持ってハイブロウな尺度で解析して欲しい。えっ?何が心配だって。もし将来に於いて、未来を容易に見通せる時空間に生活する様になったら人生なんて味気なくなり、ギャンブルだなんて患の骨長だろうって。心配するなって、その時はその時で、愚かなる人間の英智は新しい未知のカテゴリーを捜し出してくれるさ。
ずい分君と話し込んでしまったな。もう君と別れてペダルを回すのに専念しなければ。おやっ、これはまずい。だいぶ視力が弱って来てる、数m手前の車のナンバーが暈けてしまって判読しかねる。脚力の方も危ういもんだぜ。スピードがまるっきり落ちてしまってる。
田無の市街地に入る頃すっかり陽は落ちていた。軽業師のやつもいつの間にかどこかへ消えてしまっている。ヘッドライトの波が疲労した角膜を刺激し苛立たせる。風を切ってすぐ傍を掠めて行く車に比較された自分の速度に、一層もどかしさを与える。陽が落ちてしまっては春といえども肩口から衝っかってくる冷気が疲憊した筋肉を萎縮させる。
ジャンバーを着るため適当な菓子屋の前に停って一息入れた。1気に飲み干した冷たい牛乳が熱くほてった臓腑に気持良く浸み渡る。幸い体の内外から冷やされて、鈍った神経が活を入れられたため、先程来の眠気に対する危機が一応解除された。自転車の震動で狂うのを防ぐため尻のポケットに入れておいた腕時計を見ると、やっと時間的余裕が出て来たのが分った。約束の時限まで小1時間はある。ここまで来てしまえば残された距離は知れたもの。普通の速度で20分もすれば、私の暖かい自由奔放な空間に戻る事が出来るはずだ。
小さな菓子パンを口に頬張って気休め程にも飢えを凌いで、再び自転車に股がった。畜生、胸が痛み出した。踵の筋が前に刺されたみたいにチクチクする。ちょっと甘い汁飲まさすとこれだから!酷使され続けてきた脚の脆弱な筋肉達が、僅かではあるが労働から解放されたことによって彼等の性状に相応した抵抗の砦を構築したのである。
悲しいかな其等は余りにも脆弱であり、私の神経に張り巡らされた捜査網の外界へ離脱するだけの力を保持するには余りにも飼い慣らされている。かわいいやつよ!赤信号が青に変るうちにはもう立派な奴隷になって苛立たしい神経に操られてしまってる。ひよっ!あいつは気違いか!すんでのところであの忌々しい瓦斯食動物の餌食になるところだったぜ。何んという破廉恥漢なんだあいつは、人を虫けらだと思ってやがる。警笛も鳴らさずに、突然後から来たかと思うと私の前を横切って小路の方へ消えてしまうなんて法があるか。くわばらくわばら、気違いに凶器。注意が肝心。今度その気のあるやつが来たら大形に手でも振って宣誓功撃をかけてやろうか。それとも君子危うきに近寄らず流でいこうか。それじゃ左団扇的厭世隠居風で腹ごなしが悪い。
いっそのこと激流の中へ諸肌脱いで躍び込んで、儘よ!わっちもしがねい人間様よぁ、てな具合に歌舞技のさわりの様なみえを切って試したらどうだろう。いくら鬼でも蛇でも慈悲の涙ぐらいは持ってるだろう。何を命知らずな!五体が繋がってれば上等。それでも挙句にゃ、官憲が記章を光らせてやって来て、道路交通法第某条交通妨害罪により科料に処する、と撮み出されるか、おおいそこの白痴者め!罵声一擲ぶいってことか。
青梅街道が、今までより倍近く広がった処を私は走っている。時間の余裕をみて、相変らず愚にもつかない事を考えながら、春の冷気の感触を楽しんでいた。道幅が広まったことで車の煩わしさや圧迫感から大分緊張が解け、軽快な脚さばきが敏感にそれに反応を示した。周囲が1段と明るくなった。そして、その不夜城の如くに輝く街並の灯が、あたかも私の帰還を出迎える宝石を散りばめた歓迎の花束の様に見えた。もうその光の中を潜ってしまえばそれでいいのだ・・・かにみえた。
将に不意は音もなくやって来た。丁度路上に止められた10トンもあろう大型のトラックを避けて通り過ぎようとした時である。影から赤い塊がふいっと飛び出して来たのが目に入った。闇夜に不意打を喰って息を飲んだ私は、本能的というか咄嗟にブレーキレバーを握った。間に合わなかった。赤い塊が自転車のどこかに接触したかすかな手答えがあった。赤い塊がもんどりうって地面にうずくまるのが目に入った次の瞬間、私の方はバランスを失った自転車に乗ったままコンクリートの電柱に。強烈な衝撃が私を宙に放り出した。濃紺の夜空の中に街路燈の光が不規則な弧を描いた。円孤が上隈から下隈まで来た瞬間、私は右脚に一筋の鋭利な刃物で切られような鈍い感触と、次に右肘に激痛を感じた。自転車からころげ落ちた私の体は、ガードレールと堅いコンクリートの地面にしたたか打ちつけられたのだ。何んてこった!私は仰天したま、唇をかんだ。
「どうしよう」
赤いコートを着た女性着た女性が私の頭上に立っていた。両手を頬に当て、眉をひそめて私を覗き込んでいる。今にも泣き出しそうな顔を見かねて、たいした事はないと跳ね起きた。威勢良く立ち上ったものへ右肘がずきずき痛んで、真直に伸ばすと余計具合が悪い。案の定、ガードレールに衝けた右脚は、大腿部の外側が斜めに刀傷のように裂けて夥しい血が流れている。神経が麻痺して私には痛さはそれ程でなかったが、彼女は夥しい血を見て絶句したま、茫然としている。
「困るなあ、突然飛び出して来られちゃあ。道路には自転車だって走ってるんだ。貴女の方は怪我が無かった様だからいいものの私にとっちゃいい迷惑だ。何んだってまた…」
勘忍袋の緒が切れそうになったのを、悲しげに俯いている彼女を見て押し停めた。
「ごめん、つい感情走りしてしまって。大した事はないけど近くに適当な病院はないかな」
「家のすぐ傍に外科医があるわ」
「家の?」
「すぐそこ。通りの向う側なの」
電柱に無惨にも叩きつけられた自転車は、とても乗れる状態にはなかった。前輪を支持している双方のフォークが美事に後方にのめり込み、チェーンは無雑作に歯車から外れ、ペダルはクランクと鋭角をなして曲がっている。ベアリングの良く効いた後輪だけが音静かに空転を続けている。自転車は歩道に寝かせたままにして、まず治療を受けに道路を横切った。皮肉にも、めずらしく自転車が少なかった。
「ごめんなさい。私の不注意からこんなことになってしまって」
彼女は謙虚に謝った。
「もういい。運が悪かったのさ。過去はいいからこれから先の事を考えよう。病院はまだかい」
「あそこ」指を差して云った。
「あの角にある白い建物よ。痛むの?」
右脚を地面に着ける時に目配せする私を見て、心配そうに彼女は言った。ショックから立ち直り始めた神経どもが本来の任務を使行し出したのだ。打撲した部分が一斉に苦痛を呈し始めた。
「心配には及ばない。こんな傷には慣れっ子になってるからね」痛みを堪え大丈夫然と歩いてみせた。
「それに、今は貴女が付いていてくれるしね」
私は軽く笑って彼女を覗くと、彼女は初めて笑顔を見せた。その時初めて、彼女の胸のボタンが千切れて1つ無くなっているのに気付いた。それで、私の体が宙に浮く前に感じた触覚の意味が分った。病院に着くと、他の待ち患者は居なかった。無愛想な若い看護婦に促がされて診察室に入ると、白髪まじりの太った男が私を迎えた。効きすぎの暖房のためむっとした空気が気分を損ねた。金儲けばかり気にしている町の開業医の藪医者ほど、患者の無知を幸いに必要以上に薬を塗りたくり、薬を売りつける。この白髪頭の太っちょ医者もどうやらその一族の未席に座る資格がありそうだ。脚の切り傷は出血の夥しさの割りには傷口は浅く、縫う必要はなかった。しかし、無器用につける消毒液の痛さといったらなかった。
その上、化膿止めの軟膏をその痛さも構わずずきずきする傷口に塗り込まれ、何んと大袈裟に包帯を巻かれたことよ。まるで白い半ずぼんを履かされた見たいだ。肘はレントゲンの結果幸い骨には異状がなかった。しかしかなり腫れ上がっていた。痛みを訴えると無愛想な看護婦に腕を取られて、痛み止めの注射をぶすりとやられてしまった。最後に内腹薬の痛み止めをもらい、かくも患者を労った丁重さに礼を言って診察室を出た。
「どんな具合い?」
「心配いらない。見てくれ程でもないさ。どうやらかすり傷で済んだようだ」
大腿部にかくも大袈裟に巻かれて痛々しそうな負傷兵の如く診察室を出て来た私を見て、彼女は駆け寄って来た。
「よかった」胸をなで下ろす様に言った。
病院を出ると、効き過ぎのために火照った顔が夜の冷気に気持良かった。この辺にはまだ夜がある。外燈のない処では彼女の顔も定かに見えない暗闇が確保されている。秩父の山中で見た程を期待するのは無理だが、久遠の夜空から降る星明りが向こうの雑木の繁みの上の黒々とした一画に幾つも見えた。気のせいかその中の並んだ2つの星が輝きを増したかに見えた。
「あの自転車は修理が要るなぁ・・・」
「自転車だったら」彼女が口をはさんだ。
「弟に頼んで家に持って来てもらってあるので心配なく」
「いつの間に」
「貴方が痛い注射をうたれてる時頼んどいたの。元はといえば私の責任から出たものですもの出来るだけお役に立ちたいの。家の方に置いといて構いませんから、傷が直った時にでも取りにいらしたら何如かしら」
「それは有難い。でも、ここからなら押して行っても分からないだろうから・・」
「そんな体で強がりは止めて。そんな事私が許せて!」
彼女はだだをこねる少女の様に言った。
『この位いの傷だったらこの先4、50キロでも走れる勇気を持ち合わせてるけど、ここは貴女に妥協しよう。愛する友を他人に預けるのは忍びないけど』
「まあ、見えすいた勇ましいことを言うんですこと。せいぜい貴方の愛する友を大事に預けさせて頂きます」
初めて見せた悪戯っぽい彼女の笑いが私の心を和ませた。目を見張る様な美女とは言いかねるが、スキー焼けでもしたのだろうか。健康そうな小麦色の滑らかな肌が赤いコートに良く似合った。知性的な額の形良い丸み、子供の様に清らな澄んだ瞳、目立たない位うっすらと口紅をつけた桜草の花弁の様な唇。私はそれらにすっかり魅了され、暫し彼女に見とれてしまった。異性を物色する眼が畑々と首をもたげていた。
彼女の家は病院から50歩も行かない処にあった。好奇心が門の表札に視線を向わした。「宇津野猛」父親の名だろう。門を入ると、構え込みの向うに玄関が見えた。手入れの行届いた庭に囲まれた小ざっぱりした平屋造りの家だった。とりわけ玄関の白壁に和らかなオレンジ色の光で辺りを照らしているブラケットライトが印象的だ。弟が運んでくれたという私の自転車は、彼女に案内されたガレージの中に、主人よりも痛々しげな格好で壁を枕に立てかけてあった。
「中に入つて母に会って下さらない。私以上に心配してるの。安心させてやりたいの」
その時、ふと約束の時限の事を思い出した。今更急いで帰っても時間的にみて無駄なことは明然であった。しかし面倒な応接を回避するための口実とするには好都合な材料となった。そのためには、もっともらしい演技が必要だった。
「大変だ!今何時かな」
「8時を回った位だと思うけど。正確な時刻を見て来ましょうか」
「いや、それには及ばないけど、私は急いで帰らねば。ああ、すっかり忘れていた。今ならまだ間に合いそうだ」
役者顔まけの演技をやってのけた。彼女も、すっかり信じ込んでいる。おまえってやつは何んと罪作りなやつだ。
「生憎車が出はらってるのでタクシーを見つけなければね」
と彼女は先に通りに出て懸命に車を呼び寄せた。献身的な彼女の態度が愈々心を苦しめた。別れぎわに、よっぽど本当は口実だったと告白しようとしたが、その言葉は咽喉の辺で止って、それより上に出てこようとしないのだ。私のエゴイズムから出た行為の真実の方がもっと彼女の心を痛めると信じたからである。
<神よ、偽善者たる邪まな私をお許し下さい>おいおい「神」だって、そんな言葉がまえの口から出たのを見いたためしがなんぞ。
一体どうしたというのだ。熱にうかされ出したのか。それとも、あの東の空に浮んだ白い月の光に打たれて気でも狂ったか。まてよ、はーん、さてはあの女にぞっこんいかれっちまったな。どうだ図星だろう。
<そんなに心苦しい今の私を責めんでくれ。軽卒にも、おまえの1番嫌いな神頼みをしたのは悪かった。許してくれ。健気な彼女に対する邪まな私の報報を後悔してるのだ。確かに、私は好意が有るにせよ無いにせよ、初体面の人に通り1辺の挨拶をする、あの時の計算ずくめの緊張がいたたまれない程嫌いなのだ。いくら自分の方がそれを避けようとしても、相手が計算ずくめであれば何の意味もない。だから回避するのが策と心得てる。仮面を覆った者同志の応接談議ほど糞面白くないものはない。エゴイズム?そういわれてもしかたない。自分でさえ、エゴイズムと納得してるのだから。何処かに葡萄を喰うと尋麻疹が出来るという妙ちきりんな性状の男がいたが、彼が葡萄を肉体的に拒むのと同様、私にとってそれは肉体的にアレルギー反応を起こさせるのだから仕方あるまい。今私が心苦しんでるのはその事じゃない。何故あてこすりな口実を持ち出す前に、その真相を彼女に告白することが出来なかったのだろうか。これだけ言えばおまえも分ってくれるだろう>
そんなに自分の心を苦しめる事はないさ大将。あの女に対してそれ程心苦しめる裏には、少なからずもあの女の心の中におまえの心が入り込もうとしている証拠さ。しかしだよ大将良く聞きな。あそこで貴女のお母様にお会いするのは性理的嫌悪感からどうしても出来ません、と言えなかったのは、詰るところおまえはあの女にまだ心許す境地に入っていないってことさ。無理もない話しだよ。それ程まで潔癖漢になるこたあないもんだぜ大将。
<有難度、私の愛すべき飲んだくれ。時にはおまえもまともな事言うぜ。少しは気が晴れたというもんさ>
いっその位のこたあいくらでも説教できるこの老ぼれでも、無駄飯食らっちゃいねい。大将とあの女のことはこれからだ、今が丁度幕が上った処よ、この先を見ないって法はないもんだ。
<おまえさんも、この先見たかったら酒をいい加減にして目の玉磨いとくんだな>
何を言うんだ、口の減らねいやつだ、この老ぼれ、例え酒樽につかる程飲んだって目玉はいたって達者なもんよ。
<そう向きになって怒るなよ、私の飲んだくれ。悪酔いしなさんな>
流石に家の者は私の格好を見て唖然としていた。そして次の瞬間、矢継早に質問が私を攻撃して来た。私は早く横になりたい一心で手短かに事の経緯を話して、空腹を満し、室に篭った。
ベッドの上に大の字に寝ころんで煙草をふかしながら過去を辿った。この怪我のおかげで、2日前に出発してからの秩父の山を旅した事が、ずっと昔の事に思えて、容易に歯車が噛み合わない。何処の山道を走っていても、突然、赤い塊がもんどり打つシーンが割り込んで来て手順ある映写を妨げるのだ。もはや回想するのを止めて、今夕、聞き損ねた音楽番組を確認するため新聞を取りに行った。少なくとも赤い塊の遠因でもあるのでと。この約束の時限を意識してなかったら、とうてい赤い塊と出食わす事もなかったろう。私は見立たらしい新聞記事にさっと目を通しながら、夕刊の頁を追い、蜜柑を剥きながら番組表に目を据えた。
「無い」
私は思わず叫んでしまった。有るべき筈の物が無い。眠気が一編に飛んでしまった。代りに「バロック音楽への招待」となっている。
一気に体内の血液が逆流しているのを感じた。脚の痛さも忘れて、急いで室に戻った。月間番組表を手にしてその訳が分った。私の求めていた番組は確かにある。しかしそれは明日なのだ。一日感違いしてしまっていた。
この感違いを知らずに苦痛をこらえ、疲身に鞭打って齷齦していたのだ…この感違いも知らずにあの赤い塊に出合ってしまったのだ…この感違いも知らずに彼女に嘘の口実を作ったのだ…何もかもがこの感違いのために!
意外な展開に対する屈辱感が、次第次第に真空の中に虚脱し、笑いに転換されていった。とうとう、それは堰を切って流れ出した。私は大声で笑ってしまった。真剣な形相で必死になってペダルを回している姿を思い浮べては、腹をかえてベッドの上を笑い転げてしまった。
<私の飲んだくれ!まだ起きてるかい>
棒め!これから本腰入れて飲むところよ。何をそんなに笑ってるんだ。
<これが笑わずにいられないぜ。人生なんて喜劇だよ。大真面目に考えてた事が、実はとんだ食わせものよ。人生なんてこれだから愉快だよ>
ワシには何の事ゃら分らんが、大将がうれしそうにやってるなら、ワシの方も歌でも聞かせてやるか。
<あの調子ばずれな歌かい>
まあ一杯やらんゃ大将。
若者は、
木陰に咲いた白菊1輪、
無骨なその手に、
手折りて泣いた。
2羽の小雀、
それみて笑う。
(2)
「さようなら!」
道子は手を振りながら通りの向う側に停ったバスの方へ駆けて行った。亜麻色の髪が白い太陽の光の中で縺れ、街路樹の淡い縁に踊るのを私はずっと見送ったままでいた。
僅か5,6歩でバスに乗れる距離の処まで行って、彼女はもう1度振返った。何か大声で叫んでいた。しかし、車の騒音に掻き消された声には、私の鼓膜に届くだけの力は無かった。ところが、私の視線が彼女の視線と丁度びたりと合った瞬間、全てが変った。時の流れを止めたのだ。不思議にも、彼女と私の間に作られた時間を超越した空間は、鼓動と鼓動との間の僅かな時間を何万倍にも引伸ばし、網膜にコマ落しの様な逆戻りの映像が映し出された。そして最後に赤い塊がもんどりうつと映像が白んで太陽の中へ消えていった
すでに道子の乗ったバスは遠くの方へ行ってしまった。私はすっかり輝きを増した太陽に眩暈を感じ、大きく息を吸った。
まだ少しばかり地面の所々に雪が残った。何を間違えたか4月も半ばというのに前夜東京地方に記録的な雪が降った。
競技場や体育館等の施設が建ち並ぶ公園に近い駅で私は道子を待った。何故この駅を待ち合わせに選んだかは、道子と最初に待ち合せた場所であるというにすぎない。あの日道子はホッケーの試合が見たいと言った。例の傷が癒えて自転車を取りに彼女の家を訪ねた日だ。怪我をした日、家の住所も電話番号も聞かずに帰ってしまったため、「宇津野猛」という表札と、白壁の玄関という不確な記憶だけを頼りに家を捜し当てるには随分時間を食った。病院を目当てにやっと見つけて、玄関に行く前にガレージを窺いてみると、修理を終えて元通りの姿になった愛する友がいた。
私の知らぬ間に勝手に弄られた嫉妬に似た依怙地を玄人気質の憂恨と、彼女の手極良い配慮に対しての深謝の念とが相剋するまま、ベルを鳴らした。出て来たのは彼女の母であった。初め怪訝そうだった顔が、私の正体を知るや満面に笑顔露わにして、私を居間に捉した。全く予想された通りに、彼女は私に話の暇を与えずに、詫び辞令を読み上げた。私はただ彼女の期待通りの相槌を打ってやれば良かった。道子が現れて場が白けずに済んだ。(道子という名は母親の話で知ったのだが。尤も名前なんてどうでもいい事で、寧ろ名前によって個物化してしまう意識の方が情緒を殺ぐ)道子は、長い髪を巻いて束ねて結ってるせいもあってか、薄暗い街路灯の下で見た時よりずっと大人っぽく見えた。体の線を露わにしたワンピースに包まれた姿体は、成熟した女の楚々とした官能的意識さえ起させた。
道子の語るところによれば、目下絵の勉強中で将来画家のはしくれにでも成れたらということで、彼女の力作とおぼしき額縁の油絵が三角棚の傍の壁に掛けてあった。私には絵に対する高級な情操など持ち合わせがなく、絵の話は不燃のまゝ終った。その内、私の方も正体を証さねばならない形成になったため、私に関する簡単な形容辞句を並べて談を絡いだ。自転車乗りの段になって、彼女は興味を示した。弟が加わって話がより沸騰した。私は、種尽きない過去のヒロイックな武勇伝を披露するたびに、彼は熱っぽい目を輝かせて私に聞き入っていた。一般通念から自転車の機動性を過小評価していた彼等にとって、それは将に疑惑でさえあった。私は口の停止まるを知らずに自転車が与える貴重な人間への影響力 – 飢え、乾き、疲労からくる原始的視点で学ぶ脆弱な肉体と堅固な意志力との絡み、そしてその側面。育まれる自由、自律、創造、智恵の幾何 – にまで普延して話しまくった。しかし、それは一方的に顕示する話しでしかなかった。
西に太陽が傾く頃になって私は暇乞いをした。完全に復調した自転車に股がって、門まで出て来た道子に別れを言うと、彼女は突然に、ホッケーの試合を見に行かないかともちかけたのだ。
もどかしそうに言う道子の眼には、はっきりと物恋うるものがあった。私は出来るだけ素気無く承知の返事をした。何故なら、私こそ道子に接近したい欲望がすでにあったからだ。というのは時は自由に選べる。ただ闇雲に時を競く程の浪費癖は無い。裏を返して言えば、刹那的な感情でこの問題を処理したくなかったからである。そしてその日、この駅で待ち合わせをしたのである。
その一日は、道子にとって見れば退屈だろうと思える程、私は終始、貪欲な観察者の眼で彼女を追った。彼女は絵かきという1つの芸術環境に生活しているだけに、一種独得な美学意識を持っていた。
ホッケーの試合を見ている時、私は道子にホッケーの試合に興味があるのは何故か尋ねてみた。
「好き嫌いというのじゃないけど、ホッケーにはダダイズムがあるわ」
「例の意識の世界と無意識の世界がどうのこうのってやつかい」
「そう。否定と破壊と逆説があるわ」
「難解なこと言うんだね」
「あの目まぐるしい選手の交替、ボディアクションに備えた行々しいいでたち、あれは一般のスポーツ通念を否定し、破壊しかかってるわ。そしてあの罰則者のためにあるボックス、あれは美事な逆説よ」
私は、この彼女の鋭い難解な美学に唸った。そして、不思議に気障に聞えないのが、私を魅了した。
予想に反して、あんな退屈そうにしていた彼女から、後日ふたび誘いの電話が入った。そして、3日前その様にして道子からの電話で一日を供に過した。その日で彼女に対する皮相の見は頂点に達した。そこで止まるはずはなかった。皮相下にある姿を発見するため、より以上の接近が必要となった。私はその夜彼女を家まで送っていった時、別れ際に握った手をそっと引き唇を寄せると、彼女は拒むことなくそれに答えた。
オレンジライトに浮き出た、道子のシルエットは、その後の私の行動を加速した。帰宅するなり私は、初めて私の方から受話器を取った。彼女に断わる理由は無かった。
(3)
昨夜来の雪は、公園の茂みの下の陽の当らない芝生の上に、真綿の様なふくらみを残していた。梢の粉雪を飛翔させて駆けて来る風は鼻の先を凍らせた。寒い。太陽は鉛色の雲に顔を見せる構えは無い。
私は公園の石壁が低くなったところに腰掛けて夢想した・・・水と冷気が美事に完成した幾何学的ホルム、氷の傑作小品は、いつか互いに肩を寄せ合い雪となって、その果敢無い命をこの汚れた大地に預ける。この大地に人間が居るからこそ、雪は妖艶な姿体を美化され、浄化 – 主観的に醜悪な物に対象して象徴化される。私は雪が好きだ。その柔軟な形態と、雪の持つ冷やかな光沢との絡合いが心的に好きだ。そして雪は魔術師だ。雪はその稀少な特異現象を操って、それに纏る過去の記憶を容易に甦えらせるからだ。私にとって、とりわけ友人の涙を忘れることが出来ない。
八年を逆上る冬の日、銀世界の中で、友人は合格者の掲示板の前で泣きじゃくった。当時、学校の門を潜る迄、彼は試験の結果から合格への皮算用を悲観視していた。いじらしい程気落ちした自分を慰めていた。ところが、彼の背負った2桁の番号が雪の中に黒々と記されるのを見つけた時、たった2桁の数字が彼を奈落の底から、上昇気流に乗った粉雪の様に引き上げた。コウモリ傘を握ったま、肩を振わせていた。私が彼の肩を叩くと、彼は雀躍して私の手を取った。
彼は泣いていた。その時私は、初めて間近にした喜びに泣く男の涙のはっとする様な美意識の衝撃に息を飲んだ。頬のなだらかな曲線を這う、まろやかな滴涙の中に、きらきらと輝く5色の光を見た。
それは恰も、2つ折りにされた暗空間が行成左右にひらかれて、その割れ目から洩れ出た太陽の閃光の如くであった。その眩耀に眼が眩んだ。その現世のものとは思われない光を私は今も鮮明に憶えている。我に返って私達は手に手に握った雪玉を衝け合っては、当時なりに歓びを分ち合ったものだ。その日の主役は雪をおいて何があろうか。雪があったからこそ、その日の1部始終を、愚にもつかない細かなことまで克明に憶えている。体験的連想記憶法とでもいうのだろうか。より最近の大学の時を考え起してみれば、受験番号が3桁だったか4桁だったかという不確かさは兎に角、雪が降ってなかったということ位しか速出の記憶にはない。それとも、心の純粋さの為せる業であろうか、、、?しかし、専ら雪は事実をより雄弁にしてくれることは否定されそうにない。初めて女を知ったのも雪の降る日だった。
<おい!私の愛する飲んだくれ!今日はさっぱり元気が無いじゃないか。ここで酔いつぶれるのはちと早くはないか。お前の待っていた第2幕がすぐにも始まるというのに。おい!どうした、聞いてるのかい>
あ、聞いてるとも大将。でもな大将、今日という今日はいけねい。いつもなら、こんな瓶空けちまっても、女のケツを追い回す位のこたぁ出来るんだが、今日まるっきしよ。ちぇっ!体の方が言う事聞いちゃくれねい。なさけねい話よ大将。眼だって1ヶ所に止まっちゃいねい。ほうら、お前さんの顔が3つに見えるよ。こうなっちゃおしめえだ。
<おいおい、いつものお前らしくないぞ。やけに臆病風に取りつかれたもんだ。元気を出せよ。苦コーヒーでも飲んでバケツ一杯水を浴びりゃ酔いも醒めるだろうよ>
大将、それには及ばねえ。大将の気持はありがてえが、もういい、ワシには分ってるんだ。お迎えさんだよ♪これには流石のワシにもお手上げだ。いくら逃げ回ったところで、元のもくあみよ。頼むから大将このまゝ酔いを醒さずにしておいてくれ。
<分った。いつもの調子ばずれのお前のおはこが聞けないのは寂しいけど、もう言わん>
すまんな大将。眼はいかれっちまっても、話は出来る。耳だってまだまだ。ほら聞こえるぞ。あれは開幕を告げる喇叭の音に違げえねえ。
<その通りだ。もう行かなけりゃ。いや待てよ、何故行かなけりゃならないんだ。行くのを止めて私の飲んだくれの傍に居ることだって出来るんだ。こんな眼のおぼつかない老人を1人きりに放っておくなんて。何んたることだろう、俺っていうやつは!>
否、大将、お前さんは行くべきなんだ。そして堂々と舞台で演じるんだ。死神がすぐ近くまで寄って来てる様な者のシリ拭いなどするべきじゃない。今のお前にはもっと新鮮な生々とした物を求めるべきなんだ。
木乃伊(ミイラ)取りになっちゃおしめいだ。<でも>言うな!速く消え失せろ!だが1つ言っておく、物事は是か否だ。その眼を失うなよ。宙ぶらりんはいけねい、、、宙ぶらりんはな、、、
<分った、忠告ありがとう。ぢゃ又会う!愛する私の飲んだくれ!>
(4)
改札口を通って来る10人位の人塊りの中に道子の姿があった。道子は、すぐに私を見つけると駆け寄って来た。そして、行成、私の胸の中に飛び込んできて、思いがけなくも感情を露わにした。人目を憚からない彼女の積極さに私は途惑ってしまった。形の良い額に唇を寄せると、ジャスミンに似た香りがぶんと鼻をついた。道子の温りが私を抱きしめた。彼女の顔に東洋的な退屈な微笑は無かった。気持を圧えない表現が私に寒さを忘れさせていた。
「大分待たされたぞ」彼女の顎をつまんで言った。
「ごめんなさい。来る途中で・・・」
「おっと」人差し指を彼女の唇に当てた。
「言分けは嫌いだ」
「ごめんなさい」顔を私の胸に押しつけて言った。
それでもう1度顎をつまんで顔を上げさせた。
「多分、僕の時計が君の分だけ進んでいたんだろう」
口紅を感じさせないうっすらと赤味のさした唇が、純白のオーバーコートと生鮮な対照を配っている。それに、紫色のメッシュのストッキングと同系色のネッカチーフが、オーバーに配色されその採色のアンサンブルが雪景色と絶妙に会合する。そういった繊細な気使いが私は気に入った。そして、純白のコートの下のコォディネイトを見たい衝動を覚えた。
私達はそのま、地下鉄で銀座へ向った。道子に案内されて街の中心部から少し離れた人目につかない小さな画廊に入った。道子の絵の先生の個展が開かれていた。10米4方ほどの内部に入るとしんと音が途絶えた。受付けの2人を入れて4人の観覧者がいるだけでひっそりしていた。受付けの2人が顔見知りらしく何やら話していた。私はそのまま壁づたいに絵を見て回った。時折り道子達の笑いが静かな画廊に響いた。
幸いにして、絵の主の画作風は、当人でも分らない様な抽象画や、最近の超現実主義派が描きなぐった類のものでなく、私の様な絵画には疎遠な人間でも一応は楽しめるものだった。私の少ない知識からして、印象派のそれと似た作風であると思った。中でも、「夕日の港」という題名の付いた風景画 – 多分スペインかイタリヤの様なラテン系の国の港だろう – に圧倒された。構図からいっても、作者が鳥の目となっているのが新奇を思わせるが、何んといっても、西の方へ半分沈みかけた夕日が素晴らしい。配色といい配置といい、雄大で叙情的で作者の熱意が伝わって来る。そして今にも自分の顔が夕日に染まりそうな錯覚さえ感じる。
裸婦画が1つあった。膝をだらしなく半ば開いて、両手も所在の定まらない様に無難作に下らし、ねむそうな顔でベッドに腰掛けた若い女の裸体だ。この絵は私を引きつけるものは無かった。私は拙作だと思った。その時私は後に気配を感じ振り返った。
「こんな絵どう?」道子だった。
「どうって?」
「こういうのに興味あって?」
「興味?この絵に関する限りでは余り興味ない。今もそう思ってたところ」
「意味深ね」きれいな歯並びを見せて言った。
すでに彼女はオーバーを脱いでいた。濃いカーマインのベルペットのワンピースに身を包んでいた。腰の処に結んだベルトのリボンがアクセントになっていて、ベルベットの持つ濡れた様なしっとりとした光沢が均整のとれた体線をより女らしく見せた。
「裸体、実際に見たことあって」
「無いとは言わない」
「モデルが全裸になって、赤いスクリーンをバックにして立つと、まるで彫刻の様に美しくなるのよ。クロッキーなんかやっていると時々見とれちゃうの。人間の体ってこんなに美しいものかってね」
「赤じゃなければ駄目?」
「やっぱり赤がいいわ」
「どうしてかな?」
こんな会話が私に彼女を大人として自覚させた。と同時に気の置けない女だ、とも思った。
午后になるとやっと春らしい太陽が顔を見せた。冷気が序々に温められ雪は次々に果敢無い命を断って元の姿に還っていく。高層ビルに囲まれた、猫の額程の森林を通ると、小鳥の声も聞えた。照照たる春霞の中空に小鳥囀り、、なんて情緒は無いが、冬の軍勢は一挙に退陣を始め、春の小妖精達が飛翔を始めた。
私は、今日こそ、宇津野道子という女、人間に対する皮相の見の裏付けを確証するためなら、いかなる穿鑿の努力をも惜しまぬ覚悟があった。ところが、図らずも、駅頭でのむき出しの振る舞いや、面廊でのこと等から、その容易なるを暗示した。そして、更に彼女の次の言葉がこれを絶対的なものとした。
「今晩、友達の家に泊まるって言って来たの」
「橋」という小ぎれいな仏蘭西風レストランで食事をしている時、道子はこう言った。道子の視線は私の方に据えたまま動かなかった。私は水の入ったグラスを口許に近ずけたままで灼かれてしまいそうなその熱い視線を受けた。しばらく人形の様に見つめ合った。沈黙が流れた。その間に、視線が活発に言葉を交し、不思議な空間で道子と私は語り合っていた。そして、私は何物にも邪魔されることなく、道子と私の過去をさまよった2つの動線がその空間で、今1つになろうとしているのを垣間見た。
「こんな事言うべきじゃないのかしら」
道子はかすかに頬を染めて言った。緊張の空気が緩んだ。
「そうは思わないさ。婉曲さはあるけど、自分の求めるものを臆せずロに出す方が立派だし、今の僕達にはそれが必要になって来てるのさ。むしろ君から先手を取られてしまって僕の方こそいい面の皮さ。」
「でも内心どきどき、ほらまだ心臓がこんなに」
道子は豊かな胸のふくらみの下あたりを両手でおさえ、少女の様に恥かしがった。
「家の人どんな顔してた?」
私は、そう聞いてみてつまらん事言ったなと咄嗟に思った。
「友達って貴方の事じゃないわよ。いくらなんでもそこまで、、」口をすぼめて彼女は言った。
「もちろんそうだろうとは思うけど。やはり口実が必要となるか」私は以前の事故当夜のことを思い出し笑いした。
「そうでもしなかったら干渉されちゃうばかりよ」
「でも、そういう風に嘘偽りを弁護してしまうのも危なくはないかな。そうやって嘘偽りのポテンシャルを高揚させてしまうと、いつか身動き取れなくなって、露現した時の瓦解のエネルギーは強大だし、影響も熾烈だろう」
「そうね」道子はそういうと何か考えてる面持ちで口を噤んだ。
この辛辣な言葉は私自身に対する告白でもあった。そして、その先截然と事を運ぶのに必要な箴言ともなった。
「もし、その人から道子さんいますか、なんて家に電話でもかかったらどうする」私は煙草に火を点けながら言った。
「その時はその時よ。どうにでもなれ、ケセラセラね」
こういった道子の寛容な性格は以前からたびたび現れていた。
(5)
つい先程まで、林立する樹永に幾筋もの冷例な光を通して、向いに聳え立つ純白の山肌を異様までも赤く染めていた太陽が、静かに消えた。暗み始める東の空から冬の星々が冴え出すと、山は再び光を生んだ。大鳥居から玉砂利の敷きつめられた神社の境内までの400段余りもの長い石段の両側には松明が置かれた。そして闇の中に長い光の回廊が浮かび出た。山は4年に1度の神秘な儀式を行なおうとしている。遠くから風の音に紛ぎれて2つの太鼓の鈍い音が聞こえてくる。方角はいずれも異なる。そして互いに大鳥居を目指して近づいて来る。ドーン、ドーンと互いに呼応しながら近づいて来る。近づくに従って音の間隔が次第に狭ばまってゆく。人のざわめきが境内まで伝わり始める。太鼓を乗せた御輿の後から手に手にかがり火を持った人の波が続いた。
太鼓を打つ音を、より速くより高らかに響かせながら長い石段を1歩1歩上り詰める。とうとう社の前まで着くと、正面に通ずる敷石の両側に据えられ、音は佳境を告げるかの様いよいよ激しく山々に谺した。
2人の晒帯を巻いた逞しい若者に伝かれた巫女の登場によって儀式は頂点に達しようとしていた。女人禁制のこの山は4年に1度その入山をゆるした古式に儀式は由来する。新月の夜を選んだ。山の頂上から運ばれた真新しい雪を融かした神聖なる水で肌を清められた巫女は、白装束に身をかため、社に入る。2人の若者はそれぞれ運ばれた太鼓の抱を執り乱打する。諸肌脱いだ上半身からその激しい動きにつれて湯気が立つ。傍の男がその肌に水を叩きつける。水は合気にかかわらず、一辺に湯気となって男の裸身を包んだ。
儀式は頂点を迎えた。巫女は社中に入り、神座の前に装束を捨て平伏す、と同時に雨時雨の様に連打された2つの太鼓がびたりと止んだ。
私は道子の中に身を任せたままで静かに息をした。道子は声にならない溜息を洩すと、顔をのけぞらせて体を小刻みに痙攣させていた。
(6)
私達は今1つの性的本能を満足した。しかしこのことが、私にとって、あるいは道子にとって何の意味があるのだろうか。男女が互いの人間を理解するという大義名分で性器性愛が擁護されうるのだろうか。勿論それは1つの手段にすぎない。性愛は感情でなくして本能である。本能に大義名分などの理性が頭を入れる余地は無い。本能 – ジグムント・フロイトの言う様に、生の本能(エロス)と死の本能(タナトス)とに分けられるのかも知れないが – と、理性と感情という二律背反のものとは肩を比べうるものではない。
本能は自制しうるものでは無い。エロスもタナトスもすなわち自制しうるものではない。我々は環境にうまく飼い慣らされてしまっているから、往々にその錯覚に陥入ってしまうのだ。そして、この本能と心理との上に超本能(こんな言葉があるのかどうか知らないが)が介在していると思える。すなわち私が言いたいのは、超本能をエロスとタナトスと混同して考えてしまうことが錯覚をひき起す事に思われるのだ。換言すれば、超本能こそが永遠性を持ち得るものであって、それに包括される本能や心理は有限を持っということだ。
性愛 – 母性愛、父性愛、兄弟愛等といった言葉もこの類いだろう – にも有限性がある。性器性愛が刹那的有限を持つのと同じ様に。話が筋を逸れそうだが、男女愛、父性愛又は母性愛といった性愛が永遠だと力説するのは環境を忘れてしまっている。種の保存、家督の秩序といった様なことで来られてしまって、環境の為せる業だということを忘れ去っている。そうあるべきだと思うのは当人の勝手だ。人間と人間の間には道徳心理によって維持される社会系があるのだから。だが何故に血族愛だけが社会的に肯定されなければならないで、そこに矛盾を感じながらも。脱皮を計ろうとしないのだろか。血族者に不快を感じながらも社会的に阿諛追従せねばならない運命を背負わねばならないのだろうか。
世間の世知辛さに不満紛々たる人間でさえ、当世のマイホーム主義などという迷信に囚われて、一族郎党を閉鎖的な狭間に閉込めて、一層助長しているから憤慨に耐えない。
「人間よ自分の穀を保って野に出ずれ!」
これは私の持論である。自分の穀すなわち自分の住空間である。安息の空間が確保されたなら野、すなわち外空間に飛び出せ、という意味である。決して一族郎党の血縁空間と外空間の対比を考えてるのではない。そして、外空間から個空間へ生活行動の主流を置くのではなく、全く逆なのである。訳の分らぬ、知智や教養がだらしなく社会通念に屈するものだから、いよいよ縺れてしまうのだ。
愛すべく豆腐屋のおやじに、君は親子の契を結ぶ勇気はあるか!
話を戻そう。エロスとタナトスこれは、相反して拮抗する、秤の上の分銅の様なものだ。我々はこれを水平に保たねばならない。生の本能すなわち創造する本能が増大すればする程、死の本能すなわち破壊の本能も同様に増大する。一旦いずれかが均衡を失なえば、その相棒も失なう。有限性を前述した通り、それはいつかやって来る。それは、感性と理性によって感受する。しかし、超本能によって建直しを計り、再びバランスを保つ。
又、本能と心理との関係で、本能は心理によって侵されないと述べたが、その可逆性はないように思われる。心理は時々本能 – 深層心理なんていう言葉もあるが – に侵かされそうになることが良くある。例えば、自転車を転がして、ある峻険な峠に登ろうとする時、目の前に峠が口を開けているにも拘らず、1歩手前で止まってしまいたい、あるいはこのま、下に逆戻りしてしまいたい衝動が起る。何故にそんな衝動が起るのか分らない事がある。意識の領域には無い。
それがタナトスの侵入兆候に思える。生への本能がうすれて例の秤がバランスを失ないかけるのではなかろうか。もし、バランスを失ってしまえば、理性が目醒めるまで、そこに留まってしまうだろう。もっと強大なもの、あるいは重大なものであったなら、ハンドルを180度回転してしまうかもしれない。
今私は、本能と心理、それを包括する超本能を上げた。そして、本能の中のエロスとタナトス(断っておくが、これはフロイトの言葉を借りたまでのことであって、彼は実際にどう解釈しているのか知らない)は秤の上の分銅の様なものであると述べた。超本能がエロスとタナトスを平衡に保とうとする、それに、心理は本能に対して不可侵的存在であるが、その可逆性は無いように思われる、とも述べた。しかし、ここに問題が残る。では一体、本能を有限なものとするもの、換言すれば、エロスとタナトスのバランスを崩そうとするのは何物なのか。それは知らない。すなわち、第6番目に考えられる感覚の様なもの。解析学的に言えば、4次元の世界、その影響を知れる様な気もするが自体は曖昧模糊としている。あるいは5次元、6次元、更にそれ以上の次元かも知れない。しかし、それは知らない。その知らないものがエロスとタナトスのバランスを失なわせるものと思う。
コスミックなエーテルを絶対者に見たてたニュートンカ学は、科学がその矛盾を現出させ、かのアインシュタイン理論の予言によって、以前の力学に修正を加えなければならなくなった。古典力学によれば、横、縦、高さで済んだ、しかしそこに時の軸を加えねばならなくなった。すなわち、その時空軸をもとに、4次元の世界を解き明したのだ。かくして光が絶対者となった。我々が物に長さや大きを求めたのは実は相対的なものである。いくら目の前の煙草1本の長さが、8・0cmであるといっても実は相対的な長さであって、煙草にスピードが加われば7・8cmに、減れば8・4cmになるのである。しかし、我々が相対的生活次元にいる以上それは感知出来ない。分かりやすくいえば、今我々の住む宇宙は増大の途にある。
しかし、我々には何らの影響もない。眼を醒して見たら、煙草が1mに増大していたかも知れない。しかし、自分自身も同じ様に増大している。マッチだって鉛筆だってそれだけ増大しているのだから、我々の生活には何ら不便を感じないのである。ところが、科学はそれに甘じる訳にはゆかない。常に絶対的なものを求めて行かねばならないのである。
物事を思考するにおいて、自分に絶対者を求めて考える。ある人は、否、自分を否定して考えなければならないのだ、と主張するかもしれない。それも1つの考え方だろう。しかし、私は少なくとも前者である。常に自分が超越した絶対的立場に一度立って思考し、相対的な自分を見い出して行くのである。
飛躍的に言うと、我々が思考するのは、全て脳細胞の中である。ところがそれは、ミクロ視すれば原子の集積体にすぎない。ミクロがマクロに移行して、思考という結果が生まれる。その移行過程に於いて、科学的法則性があってしかるべきなのである。現代の科学がその難解な法則性に頭を悩ませているのだ。難解なことを、その難解な頭脳で考えているのだから、しかたあるまい。しかし、我々は真理の積重ねという強力な武器を持っている。アインシュタインが従来の科学に新風を吹き込んだ様に、将来X氏がその魂を明かす期待を持てるだろう。
(アインシュタインが一般相体性理論を1916年に、場の統一理論を1929年に発表している。マルクス、エンゲルスの資本論はその最終刊を1894年に出版している)
相対性理論が我々に4次元の世界を知らせた様に、X氏の理論が第6番目の感性を我々に知らせてくれるであろう。もし、そのX氏の理論が感性の法則を発見したら、人間は生きる価値がなくなってしまうと激情して言うかも知れない。しかし、例えそれを知っても、前述した通り、相対的空間に生活している限り、4次元の世界は我々の生活に何の支障も来たさないのと同じ様に、X氏が人を殺すことはない。ビクトル・ユーゴーが「ああ、無情」の冒頭で述べる様に、「我々は昨日に勝ち、今日に闘かい、毎日に死ね」ば良いのだ。前に、それも1つの考え方だと言ったのは将にそのことである。
(7)
道子と私は、官能の世界で性本能を激く求め合い来るべく頂点によって、秤は平衡を失った。しかし、何か知らないものがその平衡を保ち、暈された理性が復調し出した。
手を延して、置机の上の煙火を取った。火を点けようとしたライターが、取ったはずみに手を滑べらせた。床に落ちたその音で道子は目を開けた。
「いや、いや、いやぁ!」突然道子は叫んだ。両手で顔を覆って体を震わせた。
「おい、おいどうしたんだ一体!」
私は彼女の腕を取って揺すると、夢から醒めた様に眼を大きく開けて、上半身をベッドに起した。
「鳴呼!夢だったのね」
「驚かせないでくれよ、1時はどうなることやらとびっくりしたよ」
床に落ちたライターを拾い上げながら言った。
「莫迦みたい、私ったら叫び声上げちゃったりして」
乱れた亜麻色の長い髪を手で撫でた。血管が透徹る程白い乳房が、腕を動かすたびに形を変えた。
「厭な夢でも見たの。だいぶ怯えていたようだけど」
「想像もつかない様な変な夢だったわ」
ベッドに俯せになった。私は滑らかなその曲面に人差し指を滑らせた。
「それで?」私は話を促した。
「突然目の前がぼおっとしたかと思うと、体がいつのまにか飛んでるの。ふわふわっていうんじゃなくて、まるでジェット機の様に乗ってる様な凄い速さでよ。あたりの風景は眼が回りそうで何も見えなかったわ。そしたら急に目の前に真白な壁の様なのが現われたの。上にも横にも限りなく大きな壁だったわ。それにどんどん近づいて行くの」
「雪じゃないのその白い壁って」
私は言葉をはさんだ。
「そうかも知れないけど何がなんやら分らないで、兎角その広い白い壁に吸い込まれて行くの。そのまま、その壁に叩きつけられて、ガラスの様にこなごなになってしまうと思って目を覆って息を飲んだわ。ところが、壁に衝突した気配もなく、急に動きがびたりと止ったわ。それで恐い物見たさにそおっと目を開けたの」
「そしたら海が見えた?」
煙草の煙を勢い良く天井めがけて吐き出した。
「ちがうの。何も見えないの、ただあたり一面真白。私の手も足も見えないの。咄嗟に体を触ってみたら手応えはあったわ。でも見えない。そのうち寒さを感じて来たわ。それがどんどん寒くなる。体は冷さでガタガタ震え出したわ。私は恐くなり足を動かすと、地面を蹴る感触があったので、歩き出した。でも相変らず真白で何も見えないし、何処に向って歩いてるのかも分らない。駆けようとするけど駄目。いくら歩いても切りが無いので歩くのを止めた。すると今度は体が変に重くなったわ。強い力で圧えつけられる様に。とうとうそこにしゃがみ込んでうずくまってしまうの」
「今度は何が出て来るの」
私は、道子の夢を分析しようとした。夢には時々ある過去の体験がきっかけとなって、錯誤しながら夢を作っていくからだ。しかし、この夢物語には、感覚的なものばかりで、実体が無い。白い壁や周りが真白というのは雪かもしくは彼女の着ていたコートを意味するのか知れないが、それ以上は余りにも感覚的で少しの判断も出来ない。
「今度は、背中にじりじりする様な太陽を感じたので顔を上げると砂漠の中にいるのが分ったわ。咄嗟にぐるりを見回したわ。でも見えるものは、染りそうな青空と太陽、それに波を打って続く砂丘群。私は生まれたまへの格好」
「砂漠に行ったことは?」
「無いわ」
「砂漠を絵に書いたことは?」
「見たことは?」
「覚えてない」
具体的なものが出て来たのでその動機になる様なことを尋ねたが駄目であった。
「続けて。」
「それで私は太陽の反対側。自分の影の方向に歩いたわ」
「ええ?不思議だなあ」
「どうして」
「だって普通だったら、そんな何んにも無い処にほうり出されたら、本能的に焦点にもなる太陽に向うと思えるけどなあ」
「何故だか分らないわ。でも確かにそうしたわ。多分太陽が眩しかったからか、自分があんな姿でいたからかしら」
私はその意味が分る様な気もした。煙草の火をもみ消しながら、その先を知りたいと思った。
「しばらく行って高々とした砂山に登って前方を見渡すとぽつんと黒い影が見えた。そしてその影が私の方に歩いて行くのが分ったので、私もそれに向って歩き始めたの。まもなく、というより時間はすぐ経ったみたいだったわ、その影は1人の髭を生した老人だと分った。不思議なことに、その老人ネクタイも締めたちゃんとした洋服を着てたわ。でもおかしいのは、あんな砂漠をのに、コウモリ傘を持ち長靴を履いていたわ」
「それは愉快だ。で自分が裸だっていう差恥心は?」
「別に無かったみたい、忘れていたのね」
コウモリ傘と長靴、多分今日どこかでそんな格好の老人を見たんあろう、と私は判断した。
「プェルラ!」
「何んだって!」
「プェルラ!確かそういったわ。その老人は私の傍まで来るとそう呼ぶの」
「それでそれがどういう意味か分かるのかい?」
私は身を乗り出して言った。
「分らないわ。私の知らない国の言葉ね。英語でも仏語でもないようだし。というのはその老人が鞄の中から取り出して私に差し出した本が聖書なの」
「ちょっと待ってくれよ。信じられないよ。「プェルラ」ってのはラテン語だよ」
私は大声で言った。こんなことがあるのか。私は以前にラテン語を興味半分に独習したことがあるので、しばらく考えてそれがラテン語であり「puella」とは「少女」という意味も分った。しかし、夢の中に自分の知らない言葉が出現しうるものなのか。私は信じられなかった。
「どういう意味?」
「少女っていう意味だよ」
「へえそうなの。ところでその老人がくれた聖書、読もうとすると不思議なことに意味が分るのよ。創世記なの。でも、実際のとだいぶ違ってるわ。初めに出来たのがイブで、彼女のあばら骨でアダムが生まれたとも書いてあったわ」
「逆じゃないか。それで?」
「それで、レモンを1つ私にくれたわ」
「リンゴじゃなくてレモンか」私は笑った。
「そうレモンよ。それでレモンを丸ごと噛じるの。酸っぱかったわ。ところが、怖しいことが起ったの」
「毒でも入ってたのかい」
「いや、前を見るとその老人がピストルを持ってその銃口を私に向けたの。そして言ったわ。日本語で『お前は何故に私の前にいる。何故そうやって太陽を遮るのだ。私の前に人がいてはならないのだ。お前は死ななければならない。今お前は聖書を読んで、全てでたらめな解釈をした。アダムはイブから生まれたのだ。そして、私の渡したのはレモンじゃなくてリンゴだ。お前の体は情欲に燃えすぎている。私を狂わせてこれ以上人間を増されては困る。私以外に人間は必要ないのだ。だからお前も死んでもらう』というと、私は泣いて『殺すのだけは許して下さい。あなたの居ない処へすぐに消えます。願いです』と叫んだ。でも『許さん!』といってその老人は引金を引いたの。バァーン!そこで貴方に起された訳よ」
「ライターの落ちる音がピストルの音だという訳か。不思議な夢だなあ。でも、よくもそんなにはっきり憶えていられるよ」
私は夢の話を聞いている内、その信憑性に疑いを持たざるを得なかった。
(8)
道子はラジオのスイッチを捻った。ラジオが午前0時を告げた。闇を知らない街もこの頃になると静けさを作っていた。それでも、深夜を往きかう車のクラクションが下の道路から聞こえて来る。窓のカーテンの隙間から広告塔のネオンサインや高速道路の規則正しく並んだオレンジライトが濃紺の夜景に見える。東京タワーのイルミネーションがその鉄骨塔の輪郭をひときわ高く浮き彫りにしている。
上半身を裸けたまっでいた道子は、「寒い」と言って、毛布を顎の辺まで引き上げては、私の胸に冷えた体を寄せてきた。私は、弾力性のある柔肌を抱きながら、道子の夢の話しを考えた。漠然としていたのが、終りに従って、余りにも具体的になって来たのが腑に落ちない。そして彼女のこれまでの言動から察して、それが何かを暗に謎掛けしているのかも知れないと思う様になった。彼女ならやりそうな事だ。そこで私はある罠をかける事を思いついた。
「連想ゲームってのやらないか」
「あ、あの心理学者が良くやるやつね」
道子は毛布の中から顔を半分出して、上眼使いに言った。
「それで私の性格を判断しよって魂胆ね」
「君の様な人はどんな反応を示すか知りたくてね」
「結構よ」
彼女は眼を瞑って質問を待った。私は思い当るままに言おうとする単語を頭に用意した。
「じゃ行くよ。ライター」
「ピストルじゃどう」
「素直に逃げたな。それじゃ、夜」「歴史」
「ほぉ。じゃ太陽」「歌声」
「乙女」「処女」
「ピアノ」「黒と白」
「男」「農夫」
「棒きれ」「骸骨」
「海」「油」
「山」「石炭」
「酒」「薔薇」
「じゃがいも」「お春」
次第に質問のスピードを上げていった。彼女らしい発想の片鱗を見せ始めていた。
「唇」「花壇」
「東京」「学生」
「映画」「禁煙」
「詩歌」「会話」
「物語」「ペンネーム」
「夢」「-」
一瞬返事がテンポを乱した。敵もさるもの何か感づいた様である。
「夢」「囮」
「血」「白鳥」
「愛」「ぼろ布」
「老人」「長靴」
「聖書」「リンゴ」
「レモン」「紅茶」
道子が動揺を見せ始めた。
「空」「太陽」
「雲」「太陽」
「女」「男」
「雪」「白」
「夢」「う、、」
「夢!」
「分ったわよ。嘘よ。貴方は私にそう言わせたかったんでしょう」とうとう道子は罠に落ちた。
頭の中が空転するのを感じるついでに、彼女の意識によって偽作された夢物語の意味する事、すなわち彼女ならやりそうな私に対する謎掛だという推察を偲った。先程まで、宙ぶらりんだった思考行動が、その確証を得ることによって、水を得た魚の様に生々と動き始めた。
「全部が全部嘘じゃないのよ。信じちゃくれないと思うけど、初めと1番最后のピストルの音は本当よ。話してゆくうち、砂漠が出てくるところから、あまり貴方が興味を持ち始めて来たので、私は貴方が夢を分析してるって察したの。それで、最后の音にうまく合せる為に工夫を凝らしながら、私は貴方に分析してもらいたい作り話しをしたわ。話が終わって貴方に何んの反応がなかったので失敗かなって思ったら、やはり貴方は反応を示したわ。でもその材料まで見透されちゃったわ。ゲームで最初に「夢」といわれて、それが分った。貴方は私の夢に疑いを持ってるってね。それから貴方に見破ぶられない様にと気を配ったわ。でも、もう駄目ね、余計に心がじれてしまって。とうとう貴方に敗けたわ」
道子は以前に見せたことのない顔でいった。眼の輝きは屈服のそれではなく、むしろ挑戦を思わせた。
「髭のある老人は僕を意味する為かい」
「そう、貴方はどこかに俊髦を耆宿を思わせるの。私の実感よ。でも一方には自然人として、周囲に容易く屈服しない力があるわ」
「砂漠にコウモリと長靴か」
「そう、貴方はいつか私に言ったわ。自転車を動かしていると、人間の強さと弱さを強烈に見つける。そして、生活の中での自分が時には強さを、時には弱さを偏見的に見ていることに気ずく、って」
「勿論、自転車至上を唱えてる訳ではないんで、それも1手段にすぎない。その1手段が大切なのであって、一時的に何物かに自分自身を没入する必要がある。まやかしでない没入を」
「まやかしでない没入って?」
「人間個々の問題であって別に基準などありはしないが、行為の過程で自分を評価してしまったら、それはまやかしの没入になるな。その没入によって拾った材料も、来たるべき自分の空間 – 孤独といってもいいかも知れない – に持ち帰える。そこでは、何もかもが自由自在だ、待ち帰った材料で思うがまいの形を造り、評価を下して否定すれば壊して又造れは良い。それからだ、自分の最高作品を背負って外の世界に出て行くのは」
「でも、没入してる人間だって個人を失なってはいないわ。いつもついて回ってるはずよ」道子は容喙した。
「そんなこと当然じゃないか。あ、君が言いたいのはその過程で否定する心も起るはずだということかい。起っているかも知れない。しかし、それを評価してるかどうかは別問題だ。ついでに言えば、我々の行動で主観行動は連続だが、客観行動は不連続だ。没入するのは、その主観行動と客観行動とが1つの方向を定めた時だ。しかし客観行動は不連続を起す。すなわちその空白が問題となってくる。もし、それを主観行動で埋めて繋いでしまったらどうだ。決して没入から抜け出なくなるだろう。
今ここにF(x,y)という2次平面にグラフを考えてみよう。そして、このグラフが主客行動の方向を定めた1つのグラフと考える。そして(x,y)=(a,b)の点で不連続とする。今言った様にその定まった線をなぞって行く(客観行動)うちその(a,b)点にさしかかる。その先のグラフは見えている(主観行動)。しかし、その先をなぞっては行けない。客観的に不連続を起したのだから。ところが、主観行動が、ただとび越えてしまえばまだまだ先に続いていると助力したら、その行動は又F(x.y)のまゝで動いて行く。しかし僕はそう望まない。その不連続から新しいグラフG(x・y)をつけたいからだ」
「それはどうするの?」
「その平面のようなものかな。主観も客観も見度たせる様を次元が必要なんだ。主観主義も客観主義も一方に偏見視してはおかしくなってしまう訳だ。どうしてもそうなると、今に言った意味で主観主義的だ、なんて人に思われちゃうけどね」
「仏教の空の思想ね」
「一概にそうもいえない似てるけど。でも仏教のように自分を晒け出すことは出来ないなあ」
「それは貴方に接してると感じるわ。貴方に入ろう入ろうとしても気がついてみたら、実はまだまだ遠くにいる。何か堅い殻の中に閉じ込ってる様で」
「僕の分身が何億もの中から1匹だけ、他の分身に飛び込んだ時から始まってるんだろう」
道子は笑った。そして、私は夢の中で言った老人の言葉の意味が分った。私は、誰れにも侵されない個人の堅い殻が必要であるという信念がある。だから、他人からエゴイストとか、ニヒリストとか言われてもしかたがないのだ。しかし、自分の殻を守るかわりに、他人のそれをも仮定して行動をとる。その点で老人の行動は間違っていた。そう彼女に言うと。
「しかたなかったのよ。音にむすびつけるための手よ」
(9)
そして、私達は話し続けた。しかし、私は彼女にあまりにも共通点を見つけ過ぎたのだ。彼女にも又、がんとして侵入を許さない壁があった。男と女という性の違いだけで、知る限りでは余りにも共通している。そしてそれらが妙に反駁し合うだけである。
「私達って余り似すぎるわ」
道子は天井をながめながら言い切った。その言葉が全てを結論ずけていた。私流の貪欲な経験主義さえ彼女にはあった。結局、互いに補填すべき処が余りにも少なすぎるのだ。これでは、相手を理解するのは容易いだろうが、相手を批判することは、とりもなおさず自分を批判していることになり、鏡と対話している様なものである。
矛盾と拮抗しながら止揚を求めて行くには絶好の相手ではあろうが、始終それを繰返していたら息が詰ってしまうだろう。
「僕達は今日で終りになるべきだな」
私は、道子の少し充血した眼を見て言った。彼女は、その眼を離さずに、ゆっくり首を下に下げた。
「後悔なんかしていないわ。そういわれて、さっぱりしたわ」
道子は、そう言って微笑した。その微笑が私の気持を楽にしてくれた。その微笑する眼の光は確かに偽らざるものであったからだ。そして、亦その微笑は私の微笑でもあった。
その時、ふと夢のクライマックスを思った。道子は確か、最初と最後は本当だといった。ライターが床に落ちる音がピストルの音としたら、私が揺り起した時の恐怖に怯えた叫び声からすれば偽りはないであろうが、一体何んなんであろう。その訳が知りたかった。
「夢の最后の処を聞かせてくれない」
「駄目よ」はっきり答えた。
「どうして?そんな恐ろしい事でもあるの。ピストルの音だったのは本当だろう?」
「それは本当よ。でも駄目、とても言えないわ。恐しくって」
「僕に関することなの?」
「それも言えないわ」
道子を激しく左右に振っても言おうとしなかった。私はそれ以上の詰問は止めた。しかし、果して何なのであろう、それ程までに厭がるピストルの音は。夢であるにも拘らず、なんとしても教えてくれないことには何か重大な意味があるのだろう。それは何なのか?私は心の苛立ちを感じるのだった。その前に、私が『今日で終りだ』と言ってしまったから、言おうとしないのか。それともそれに関係があることなのか。その前に聞いておけば良かったのかも知れない。しかし、その意味が明らかになってしまっては、もり道子から別れられなくなってしまいそうな重大なことであったのかも知れない。私は胸騒ぎを感じながら、その事を一言聞いてみようとした。
「もう1度抱いて欲しい」
突然、彼女は毛布を剥いで言った。喉まで出かかった言葉がその言葉で一蹴されてしまった。
(10)
「人間万事塞翁が馬」 – 幼少の頃書道の手本にあるのを意味も解せず書いたこの8文字が反対側の白壁に黒々と浮き出た。そのうち8文字は飴の様に融けて一塊に変ると、いつのまにか馬に変った。そして馬は鬣を振り乱して高々と前脚を蹴上げると、甲高く嘶いては駛走を始めた。夜陰を馳駆する麒麟の様でもあった。ふと見ると、
私がその背に跨っている。手にした顔をハシっと知くと、馬は白い壁の中に消えていった。
<私の飲んだくれ!何処にいるんだ!今戻ったぞ!何処にいるんだ。頼むから返事をしてくれ。この酒瓶は少しも変ってないぞ。おや、何んだこりゃ、やつの字だ>
『愛する大将へ。 – 大将、このおいぼれ最后の舞台を聞いていた。お前さんはこのおいぼれの忠告忘れんでくれた、ありがとう。これで良いか悪いかワシには言えん、これからの大将自身の問題だからな。ワシはもう大将には会えないが、嘆かんでくれ。大将との別れに涙なんかとんでもねえ。笑って別れるぜI』
へ、、、こんな風にしてお前がいなくなっちゃうなんて、悲しい。お前の好きな酒も充分飲まずにいっちゃうなんて。涙を流すのも許してもらえないのか、、、分った分った泣かんよ。私の飲んだくれ!もうお前はいなくなったのか!お前らしくもない、まだ宵の口だというのに酒も飲まずにかノ、、、忘れんよ。お前の墓には、大理石の上にいつも楽しそうに歌ってたあの歌を刻んでやる。
若者は、
木陰に咲いた白菊一輪、
無骨なその手に、
手折りて涙いた。
二羽の小雀
それを見て笑う。
ってな。今日はいやに煙草が目に染みるぜ。そして、お前の相棒を頭の上から浴びる程かけてやる。多分、いまごろそっちへ行っても酒場の女を追い回してるんだろうよ>
(11)
翌朝、目を醒すと白い太陽の光がこの空にも一杯に洩れていた。その光の中に道子の姿があった。逆光線の中で道子の体は黒々とした彫刻の様に動かない。眩しさで彼女の表情がすぐには見分けられなかった。目が光に慣れて初めて彼女の美しい笑顔を見た。その顔は美しい程美しかった。
雪はすっかり街から消えていた。
閉塞空間 – 法学部3年 吉田
閉塞空間
法学部3年 吉田
まるで、それ以外に方法がないかのように、また1つの季節が何1つ新しいところがない土地の上にやって来た。遠くのケヤキの梢が、カサカサと鳴り出した。物憂げな平べったい日差が、郊外の開静な住宅街にさし込んでいた。見上げると、薄青い空の下にクリーム色の高層アパートが林立している。広いアスファルトの道路には、車もまばらだ。それらの光景は心苦しくはなかった。ただ、相変わらず物悲しいだけだった。
いつものように、汚れたサンダルを引っかけ、底の破れてしまったポケットに先細った夢をつめこみ、どうかすると伏し目勝ちに肩をおとして、駅へ向かって歩いていた。住まいといえば、安下宿の1階の一日中一滴の陽も差しこまない三畳風穴の部屋だ。ドス黒く固まり吐き気する部屋の窓から見えるのが、その新興アパートのピルの群れ。ロクに歯も磨かず顔も洗わないで、ソイジャサイナラとそそくさ飛び出してしまう。絹雨あがりの舗道の水溜りに、クリーム色の長方形モザイクは忽然姿をあらわし、微風が吹けば細かくちぎれ、シャボン玉ように消え失せてしまった。
また、いつかのように埃に塗れ、おし黙った停留所の前に来てしまった。いつもなら、舌たらずな1人ごとを言い、大人が決して理解できない深さや夢を蓄えた不思議な子が、ポツネンと遊んでいた。それは妙にオットリし、楽しさに充ちあふれた光景だった。だから、毎日何のあてもなく空き腹をかかえた僕は、その子と暫らく遊び、白い歯、暖かな手の平、めくるめくような鼓動を少しでも分けてもらうのだった。別に恵んでもらうつもりはなかった。ただ、ちょっと休ませてもらいたかっただけなのだ。駅へ向かい、とある電車に乗り込み、気安めに破れたポケットの中のゴミを煎じ、バラまきながら夢を空想するはずだった。その不思議な子との出会いで、幾回となくその計画は潰れてしまい、乗り遅れてしまうはめになった。その子に出会ってから、その子が僕の涙腺を捩じ登って眼集の裏からとび出し、白眼を占領して虹彩や瞳孔さえ奪いかねなかった。
可愛い子だった。この子の母親を、僕は柄にもなく、奥さんと呼んだ。まだ30を越えてはいなくて、化粧も集積回路のように端念にしているから、とてもキレイだと思った。だから僕は狭苦しい牢獄の下宿を出て、せいせいした広い住宅街のアスファルト道路に1歩でも足を踏み入れると、まるで、ふいにモホロビチッチの不連続面に出会ったように、目に染み入るクリーム色の建物と、この母子の姿が浮かんできてしまう。
(1)
いつかのようにバス停の前に来た。あの子の姿は見えなかった。ただ、クリーム色の摩天楼の1角のその子の家のドアの前に、まるで黒山の蟻が群れていて、何故か寡黙しているのが見えた。その時、咄嗟に子供の頃のあの、大袈裟で不吉な予感めいたものを感じた。
そして、それは、今度こそ裏切りの仮面をはがして、素顔で立ち表われるかと思われた。
<人可哀そうにねえ・・・>
そういう囁きを聞いた。僕は胸の中の蝶番がはずれた、と思った。と同時に、大きな音を立てて陥落したのだ。
<あんな可愛い子がねえ、あなた。だからこの川には柵でも作ってもらいたい、そう幾度もあの人にお願いしたんですのよ。すると、まあ、どう?何て言ったとお思い?束縛の安全よりか保護の外に置かれた危険な豊富を選ぶことが人間の特権でしょう?そう言ってすましているんですからねえ。全く人を馬鹿にしているじゃございませんか。今度の事故の責任は、あの人にあるっていってもいい位なんですのよ。本当にひどい人だわ>
バス停のすぐ下を、ドス黒い川が流れていた。川幅は2mもなく、深さも大したことはなかった。しかし流れは急で、おまけに高い土手の斜面はきっぱりと90度に聳えていた。3歳の子が誤って落ちてしまえば、すぐ流され、ドロドロに溶けた腐敗物で息絶えてしまうだろうと思われた。事件は、ついに僕の140億の神経細胞の小部屋から逃れられなかった。毎日遊んだホッペタのふくらんだあの子は、断崖絶壁の土手から川の中へ転落してしまったのだ。あの手首のふっくらした伸び切らない幼ない腕で、懸命にドブ川の水をかいた。恐らく泣き声をあげ助けを求めたのだろう。ドブはその子の口から強引に侵入し、抵抗し続けた小さな心臓を凍結させてしまった。何も知らない澄んだ瞳は、ドス黒い文明の反吐に塗りたくられ、ネコ柳のように柔らかくて茶色がかった頭髪は、グッショリ濡れネズミになって息絶えてしまったことだろう。
人をかきわけドアの中に入ると、奥さんが遺体にすがりついて泣き伏していた。白衣を着た医者らしい男は、いかにも慣れきって、屁でもないといった顔つきで帰り仕度をしていた。その他に数人、警察関係らしいのが、何やらメモをとったりしている。奥さんは髪が乱れ、とめどなく流れる涙で化粧も何もあったものじゃない。ただ泣き叫ぶだけだ。ふと見ると毛布の下からは、あの子の白い柔らかそうな手が、何やら黒く汚れてはみ出ている。その手を何回か繋いで、その子の秘密やその子だけのもつ奇跡や様々な変化を僕は感じていて、どれほど心が暖かくなり励まされたことだろう。1時、こちらが何かの物真似をしたら、それが面白いといってキャッキャ笑い転げた。その子はドブ川にはまって死んでしまった。もう、僕の腰にからみついてくるその子はいないのだ。そう思うと、熱いものがドッと目頭にこみあげてくるのを禁じえなかった。同時に、声をあげそうになったので懸命にこらえようとした。けれど、駄目だった。故障した楽器のような不恰好な嗚咽が喉仏を震わせた。奥さんの後に立ったまま、僕は拳を目にあて思いもかけず泣いてしまった。
49日も済んで、その事件も1応人々の記憶の陳列棚に落ち着いてしまうと、ふうと、もう赤トンボの群れが山の方から飛んでくるようになった。その子の父親とは葬式のとき顔を合わせた。といっても後姿を見たきりだから、まるで会わないのと同じだった。奥さんとは、その後2、3回顔を合わせている。その事件以来めっきり痩せてしまい、益々無口になってしまった。顔を合わせるたびに
<あの川に柵さえあったら・・。何度も皆さんでお願いしたのですが・・。あの人が憎い>
と、目を伏せる。あの人、とは誰だかわからない。ただ、その時、奥さんは僕の顔をじっと見つめた。
あの子が哀れな死に方をして、僕や奥さんの前から永遠に去ってしまったことは、口惜しくてたまらない。そして腹が立つのは、何事もなかったかのように、傲慢な態度を崩さない真黒なドブ川の流れだ。相も変わらず透き通る青空の下でワルツを踊っているようなクリーム色のアパートの群れだ。僕自身の存在がそうであるように、世の中の動きにとって1個の生命の死生ほど意味のないことはないのだろう。きっと、死ぬということと生きていくということは、同じくらいつまらないことなのだ。それなのに、死も生も僕らを脅かし続け、そのことのために誰しも心の1番深いところで啞になってしまう。
(2)
或る日、何のあてもなく空き腹をかかえた僕は、ブラブラと駅のほうへ向かって歩いていた。空は暗く、雲が今にも地上に触れんばかりに覆っていた。けれど、それとは対照的にアパートは生々と映え、相変らずティルオイレンシュピーゲルの愉快ないたずらを繰り返していた。いつかのようにバス停の前まで来た。すると、ちょうど奥さんがアパートのベランダに出て洗濯物を干しているのが見えた。
<今日は>
僕は、余り快活にならないように低く、しかしはっきりした口調でそう声をかけた。
<アラ、これからお出かけ?>
奥さんは僕のほうを向くと、白い歯を見せてニッコリ笑った。目の下の隈もとれたようだ。水色の柄のはいったブラウスに緑色のスカートをはいていて、少し膝小僧が見える位だからふだんより若々しく見えた。
<急がないんだったら、あがってお茶でも飲んでいって下さらない?>
その声には馬鹿に艶があった。僕は驚いた。無口で滅多に御愛想を言わない奥さんが、今日に限ってこんな心境になったのも、きっと寂しさに耐えかねたのに違いないと思った。配偶者は出張で帰ってくるのはたまにしかない、と聞いている。勿論、唯一の慰めだったあの子はいない。隣近所とも奥さんの性格上、いま1歩親しくなれないというところだろう。毎日毎日、1人ぼっちで物言わない能面のような壁を見て暮らしているのじゃ、誰でも頭が変になってしまう。時々、僕と路上で会い、2言3言ことばを交わすことがあったくらいだ。あとは殆んど隔離された生活みたいなものだったろう。
部屋にはいるのはこれで3度目だ。1度目はあの子が溺死した日、2度目は葬式の日、そして3度目は今日。下宿と変わらない位狭苦しい感じがするのに、家具が立派で新しいからとても豪華に見える。経済的には、きっと不自由はしていないのだ。居間に通され、スポンジの効いた座布団にすわると、何か香水のいい匂いがする。女性女性した甘ずっぱさに、下宿の埃っぽい万年床に飽き飽きしている僕は、一瞬目が眩むかと思われた。そして、妙に落ち着かないのは、尻の下のスポンジがいつまでも震動し、僕を空中にはじき出してお手玉代りにしようと企んでいるからに違いなかった。そのうち、青々した香ばしいお茶とパラフィンに包まれた最中が運ばれてきた。明るい部屋の中央のお膳をはさんで、僕と奥さんは相対することになった。あの子がいなかったなら、奥さんとこうして話をする機会もなかったろう。そして、今ではその子がいなくなってしまっているのだから、何とも奇妙な感じだった。
ものの10分とたたないうちに変な気持ちになってしまった。というのは、奥さんは、ふだん話をする時、伏し目勝ちで滅多に人の顔を見もしないのに、今日に限って(自分の家ということもあるのだろうけれど)、こっちの目をじっと見つめている。こっちは照れてしまい、適当に視線を部屋の中の新品の家具や調度品に向ける。そういう時でも、どうやらこっちの方をじっと見つめて楽しんでいるふうなのだ。いつまでもソッポを向いているわけにもいかないから、益々途切れ勝ちになる会話の合間にチラッと奥さんの目を盗む。すると、すくんでしまうくらい大きな目でこっちを見ている。もう、何か逃れられないような気持ちになって苦し紛れにニッコリ笑う。
すると、相手はそれに輪をかけたように徐ろに白い歯を見せる。そうしているうちに、会話は完全に途絶えてしまった。明るい静かな部屋の中央での出来事だ。色白で器量良しの奥さんと、毎日何のあてもない空き腹をかかえた薄汚ない僕とが、黙りこくってじっと相手を見つめ合っている。誰かに見られたら、気狂病院にでも通報されかねない。
奥さんは髪を赤く染めてアップしている。首が細くて、頂に乱れた髪がはみ出ている。肌は艶があり、顔は卵型で目がキレイだ。色白だから鼻の周囲に薄いソバカスがあるのがわかる。唇は薄いけれど、下唇は少しめくれて形が良かった。細い腕は意外と毛深くて、差し込んだ光の加減で柔らかな草はらを思わせる。僕は苦し紛れに、もう冷めてしまった茶をグッと一杯呑み込みながら、奥さんの顔を見た。すると、
<フフフ・・・>
と、微笑んだ。咄嗟に、自分が馬鹿にされていると思い、言葉を言いかけようとすると、
<あなたって、純情ネ?女の扱い方を知らないのね>
と、真剣な顔つきになった。
<女というものはね。優しい目で見ていさえすりゃ他になんにも要らない、というようなものじゃないのよ>
僕とていい年をした男だ。その言葉の意味がわからないわけじゃない。けれど、奥さんの豹変する意外な面に次々に参れるたびに、もう頭が混乱してしまってそれどころじゃない。僕はもともと臆病なのだ。
その結果どうしたかというと、そそくさ逃げ出すより仕方がなかった。迎え入れてくれた時とうって変わって、ドアの所で見送りに来てもくれなかった奥さんに、むしろ感謝した位だった。
外に出ると、いつの間にか空は晴れて、昨日のしゅう雨の名残りの水溜りが四方で光っていた。クリーム色の建物の群れがその1つ1つに雪の6方結晶を巣くってユタユタと揺れた。通り過ぎようとすると、またしても微かな波紋を起こして消え失せてしまった。見ると、広くて人通りのないアスファルトの通りを、むこうから子供が駆けてくる。元気のいい子だ。まだ3、4歳位だろう。こっちの姿に気がついたらしい。手を振った。そして、
<ママアーッ!>と叫んだ。
僕はギョッとなって立ち止まってしまった。僕の横を走り抜けクリーム色の摩天楼の中へ消えていこうとしたその子。はっきりとは判らない。けれど、その子は紛れもなくあの子だった。(死んでしまった、あの子だ!)アパートのベランダからは、奥さんがニコニコしてその子の走っている姿を迎え、手を振っている。それは、僕は、慄然と眺めている。やがて、何か勘違いでもしていたかのように首をかしげてしまう。その光景に、何で殊更驚いたのだろう。第1、僕は薄汚ない下宿を出て、ただこうして駅へむかって歩いているだけなのだ。憂うつな昼下りに目覚めた僕は、ただあてもなくこうして歩いていく。不思議なのは、その僕が瞬間に何度も何度もこのアスファルトの通りを往復している感覚だ。
何のあてもなく空き腹をかかえた僕は、再び広いアスファルトの通りを駅へ向かって歩いている。人通りはない。まるで、真夜中の工事現場を歩いているみたいに淋しい。確かに、今の僕に威張れるものは何もない。金もなければ、恋人もいない、健康でもなければ、皮肉の1つも言えないのだから。頭の中には、常にきらびやかな瞬きに停まらない酔いがある。ふと我に帰れば、益々鉛で肥大た後頭部が痛み出す。眼球は、いっそポトリと道端にでも落ちてしまえば随分楽になるだろう。そう思わせるほど視界を奇妙に変形させた。反吐はいつも喉もとまでこみあげてきている。
何か言おうとすると、激しくわめき立て、僕を万力で固く押し込めてしまう。今の僕の歩き方。はめ込みゲーム式の歩道の、牌のような敷石。その筋目を見失うまいと着実に踏んでいく。もし、1歩でもその歩調が狂えば、心臓の鼓動はすぐさま顎の下まで這い上ってくるだろうし、小刻みな尿をたれ流してしまうだろう。足のふくらはぎは恐怖のため、沢山の筋糸を露出させてしまうだろう。そして、重心を失なわせ僕の全体を確実にコンクリートに叩きつけてしまうだろう。まつわりつく建物の圧迫。気にとめないようにしよう。でないと、毛穴から、水銀は760ミリバールを破ってとび出してしまうから。僕の首は、アポロやソユーズでなければ引き上げられないくらいに萎れうなだれてしまうだろうから。
そんな姿勢で世間に注視されたいとは思わない。ラムネじゃあるまいし、歯痒いビー玉を気管支の中でゴロゴロ鳴らし続けるのは御面だ。息をつめて、ひっそりと歩きたい。だから、誰も声をかけないでほしい。
いつの間にか駅へ着いてしまったらしい。電車が走り抜けるらしい轟音がする。目的地に着こうと、徒らに神経を苛立せているアメーバ様の群れがいる。それが目の前でうごめいている。確かに、それはアメーバと呼ぶのに相応しかった。そして、ここへ来た以上切符とやらを買わなくちゃいけない。でないと、状況は何1つ進展しないという寸法だ。それが、駅というもののもつ特徴なのだ。だから僕は、片道切符を買いに窓口へ行った。すると、開口1番、
<自動販売機でお願いします〉ときた。
先程から気にはなっていたのだが、僕のほうをじっと見つめている奴がいる。この暑いのに背広など着込み、それに馬鹿に目つきの悪い奇妙な奴だ。そういえば、あの目つき、何処かでいつか見たことがある。いや、何度も見ている。薄気味悪い奴だ。こうしてはいられない!すぐ電車に乗っちまおう。そして、姿をくらませちまおう!だけれど、どうして改札口に人が居ないんだ。もう電車の音がすぐそこに近づいているじゃないか。早くしろ。いい加減にしやがれ。
奇妙な電車がやってきた。1両目の行先札には、
《われらにとって≫と書かれてあった。続く2両目には《希望とは》と書かれてあった。3両目には、《何》と記されてあった。目の前に止まった車両には《か?》とあった。何のことはない、僕は勇気づけられているような妙な気持ちになった。この電車に乗ればすべてが解決されてしまうに違いない、と思えた。けれど、真黒な車体は気になってしまう。恐ろしく真黒な車体なのだ。
ドアが開かれた。降りる人間は誰もいなかった。真黒な車体の電車が、真黒な口を開けた。そこに、真黒な空間があった。僕は後も振り向かず乗り込んだ。車内はいつかのようにスシ詰めだった。ただ、真暗な車内がそこにあった。さっきの男の姿はプラットホームには見えなかった。奴め、乗り遅れたに違いない。それともこの真黒な車体の電車が、あの薄気味悪い男を薄気味悪くさせたのだ。第1、例え乗り込んだとしてもここじゃ手も足も出まい。そんなことを気にするより、窓の外の風景でも見やったほうがよっぽどましだ。
小さな、重なり合いへし合って、しかし妥協しているバラックの醜悪な群れが見える。ミートソースを猫の死体にかけ、人肉をまぶして悪口を思いっきり言い放ったような臭いのする黒色の河が流れている。逞しく落ちぶれたスモッグ色の息絶えた空も見える。殺意を滲ませた道路上の騒音の排泄物。ただ、パクパクと口を開け、へラヘラと負け惜しみの笑いを浮かべる人間たちの溺死体が引き上げられた。
この電車の意味する言葉と色彩。僕は思わず《一員だ》と呟いた。それは、思いのほか気分を安らかにしてくれた。僕はその一員だ。けれど希望をもっている。ただ、《あて》がないだけだ。何のあてがあるわけじゃない。それで、この電車に乗ってしまった。この奇妙な真黒な電車に。なまじ《あて》がないだけ、僕の《希望》は果てしなく広がっている。だから思うに《颯爽》としているはずだ。
それにしても、先程の男の目。あの男は一体、何者なのだろう。(シッ!ほら…)、やはり、あの男はこの電車に乗り込んでいるじゃないか!1番後ろの「疑問符」の車両。そう、ドアのそばに立ってこちらを監視している男。紛れもなく、あの男だ。薄気味悪い。真暗な車両で目だけ光らせている。
そう言えば、電車はさっきからもの凄いスピードで突走っている。窓外の風景が、形をなさず擦り切れ後方に流されてしまった。勿論、駅などに止まろうはずもない。第1、駅らしい駅など見つからない。車内の人間達は、例のウンザリするほどニコやかな調子で語らっている。まるで、ミニスカートやビキニやマッカーサー風サングラスを、不平も言わず鵜呑みにしてしまっている。そして、笑いが止まらぬふうなのだ。(冗談じゃない!)。判らないのか、今がどういう事態なのか。この電車は車体だけじゃなく、車内まで真黒じゃないか。(クソッ!)俺のほうを見ろ、そして俺の言うことに耳を傾けろ。
(とてもじゃないが)、誰も僕に気がつかない。まるで、お前は気違いだとでもいうように無視してやがる。1番奥のドアの側にもたれかかりながらじっとこちらを見ているあの男だけが敏感に反応している。胸に片手を入れているのは、恐らく、逃亡し抵抗しそうになったら撃ち殺そうと拳銃をひそませているからに違いない。暑いのに背広を着込んでいるのは、その拳銃を隠すためだ。腰のポケットからはみ出ている紙切れは何だ。まさか、逮捕令状でもあるまい。あのギラギラ光る冷酷な手錠もあるに違いない。胸の残りのポケットには、何やら僕に関する詳しい様子が記された手帳がほうりこまれている?(確かなことは)、僕を狙っているのは1人や2人じゃないということだ。きっと3人も4人もいる。常にそ知らぬ顔をして、機会があれば捕まえるつもりなのだ。(けれど?)
一体何の罪でこの僕は追われ、そして逮捕されなければいけないのか?そこを明白にしてほしい。でなければ、ナンビトも僕の生命若シクハ自由ヲ奪ヒ又ハソノ他ノ刑罰ヲ科スことなどできやしない、、、。
(4)
その男の動きを逆に観察していた。すると、<トーン、トーン〉と肩を叩く奴がいる。誰だい? <今日わ、どちらへお出かけ?>
白い歯が見える。女だ。奥さんだ。珍しく着物など着ている。それも、白いカスリの気持ちのいい柄のヤツを。答えそびれていると
-無理もない、僕を狙っているヤツが同じ電車に乗り込んでいるのだから-
<もし急がないのだったら、お茶でも御一緒にいかが?>
僕は驚いた。今の情況もさることながら、ふだん大人しくて滅多に笑顔も見せなければ話しかけることもしない奥さんが、こうして話しかけてくるなんて。(そして、この会話はいつか聞いたふうなのだ)
<あの子がいなくなって以来、毎日毎日が深い溝に埋もれていくような気がして恐ろしいのよ。夫は、月に3度と帰ってこないんです。あのクリーム色の建物の群れの、またその1室に押し込められた生活なんて、まるで目覚めたまま死んでいるようなものだわ。意味のない日常性に支配されるのは、まるで虚空に色を塗っているみたい。>
そう言うと、奥さんはその美しい顔を両手で覆い、華奢な肩を心なしか震わせた。(そして、このしぐさもいつか見たようなのだ)僕にはその気持ちがよくわかった。誰もそういうことに対して、真底慣れっこにはなれない、と知っていたから。そうして、そういう別離をキッカケとして初めて、《愛》は充実し、《愛》の心は深く内面へ沈んでいくのだということを。そして、孤独というやつ。僕らのいる孤独の心境と群集の動き。群集の熱狂と僕らの中にある深いものとの間の距離を知っていたから。
けれど、僕は《希望》という棘が刺さっていると感じている。だから外見は《颯爽》としているはずだ。《あて》がないだけだ。そして、決して細心というわけじゃない。臆病なだけだ。未来からしめ出されるのが恐ろしくて、《希望》をもとうとしている。奥さんの慰めになってやろうとするのも、励ましの言葉をかけてやりたいと思うのも、そういう利己的な思惑があるからだ。別に野卑な望みがあるわけじゃない。第1、ずっと追われ続けていて、慈善家肌を身につける暇もなかった。
<次の駅でおりません?>
それは結構です。けれど、この奇妙な電車は止まってくれないでしょう。それに止まるべき駅の姿も見えないようだ。停車するには、早すぎる。それより、人混みに紛れて手でも握り合っていたほうがよっぽど楽しいと思うのだけれど。(ところが)、そうもしていられなくなってしまった。この疑問符を黒く塗りたくった全く奇妙な電車は、やがて、速度を緩め始めたのだ。と思う間に、ゴキブリみたいなのがサワサワと群がりこぼれ落ちそうなホームへ、停車する構えを見せた。しめた、あの得体の知れない男をまく絶好のチャンスかも知れない。そして、奥さんとゆっくりお茶でも飲めたらー。と、思っている間もなかった。ドアはふいに開かれてしまった。それは、かなり急な出来事だった。次には人の波がドッと、まるで巨大な下痢みたいに吐き出され、音をがなりたて排泄されてしまった。
僕は勿論、その必然性に逆らうことなど出来やしない。もともと気の弱い質なのだから。しかし、どうして奥さんは急に、刃物にでもつき刺されたように冷たい顔になり、吊り皮に掴まって動こうとしないのだろう。ホラ、早くしないと降りられなくなってしまう。ホラ!
僕は慌てふためいて手をさしのべた。けれども、もうホームの混沌とした溜池へ押し出されてしまった。見ると、ドアの周辺は乗り込む客で、まるでバリケードみたいに固められてしまっている。見ると、あの目つきの悪い奇妙な男は、もうホームに降り立ち、飢えたコヨーテのようにじっとこちらを窺っている。(捕まるかも知れない)今度こそ本当に捕ってしまうかも知れない。そんな予感が僕の脳裏の毛細管をグルッと1周するかしないうちに、僕はもうひたすらホームを走っていった。邪魔だ・邪魔だ、人混みどいてくれ、俺の行手を《ポッカリ》開けてしまえ。
逃げた。敵は拳銃をいつ発射するか知れない。だから、無理にジグザグと人混みをぬって逃げた。階段にかけ降り、改札口にむかって逃げた。クチャクチャになり、早くも消耗してしまいそうな安っぽい切符をポケットから振り出した。そいつは顔を歪めて、頓馬な顔の駅員に手渡された。と、そこで意外な人物に出会った。
奥さんだ。(あの子を抱いている!)デパートに買い物にでも出かけたのだろうか。大きな袋をあの子と一緒に抱きかかえている。あの子は、毛沢東がかぶるような形の、合成皮の帽子を小さな頭にのせて、キョトンとこっちを見ている。それが存外可愛いい。奥さんはこっちに軽く会釈した。けれど僕は、それに目をやるのが得一杯だった。後から3人にふくれあがった敵が追いかけてきたからだ。どうしても捕まりたくなかったからだ。
第1、まだ何も始めていないじゃないか。この世界が、僕のものだという確信を何1つ得ていないじゃないか。だから、ここでしくじっては全てが灰燼に帰してしまう・・・、けれど、一体、目を血走らせ心臓を早鐘のように鳴らし続けて逃げまわっているこの僕は、何の罪を犯したというのだろう。(ただ、確かなことは)、僕はまるで、手ごたえのない大気の中をふわりふわりと駆けていった・・・。
(5)
走りまどううちに、元来心臓の強くない僕は呼吸が苦しくなり、今にも倒れそうになってしまった。恐らく、顔は水気を失い真青だったろう。ペッと吐いた唾液が粘着して、ベタリと頬についた。喉がカラカラする。唇が乾く。全身の力が抜けていく。もう駄目だ。足が動かない。無理もなかった。考えてみれば、こうしてもう22年間以上追われ続けたような気がするから。
気がつくと、うまい具合に材木置場の陰に隠れる恰好で倒れていた。材木置場の下には川が流れている。そこには、材木が無数に浮かんでいた。古い木橋がかかっている。その苔むした影が、どんよりした川の水面に映っている。柳が古い町の面影をしのばせた。僕は、ぼんやりとそれらの風情を見やった。空は曇っていて風もない。いつかのように、人通りはなかった。いつかのように静かで、憂うつな午後だった。川のむかいには、古びた瓦屋根の家が並んでいる。一体、どこへ来てしまったのだろう。そして、この静けさは一体どうしたことなのだろう。このけだるさ。この頭の底に響く重苦しい吐息は一体何だ。絶えず唸り続ける低い顫音。そして、熱くなろうとしている目頭の痛みは。
突然、バタバタという音が橋の上を通り過ぎた。あの3人だ。僕を狙っている。僕を逮捕しようとしているあの3人だ。
<ヤツめ、どこへ逃げやがった>
1人がそう言うと、他の2人は相槌をうちながらその後を駆けていった。足音がだんだん遠のいた。まるで、凍てつく夜中のようだ。3人の足音は、いつまでも耳の奥にはっきりと響いていた。それはいつまでも止もうとしなかった。僕は苦しんだ。何故、こんな目をして逃げまわらなくちゃならないのかと。なるほど、僕は何の《あて》ももち合わせていない。毎日毎日不安でたまらないし、そのために何の取得もなくなってしまった男だ。けれど、依然として希望をもっている。そして、希望というヤツは永遠に回避することなどできやしない。だから、ショウコリもなく、颯爽としているはずだ。それで、他人にとやかく言われる筋合はないのだ。僕のことはどうか構わないでくれ。そっとしておいてほしい。これ以上追いかけないでほしいのだ。
その時だ。肩をグイッと掴んだ奴がいる。材木が心なしかグラッと搖れた。誰だ?
<ふん、とうとう捕まえたな>
恐怖の余り、心臓の鼓動が危うく止まるところだった。3人のうちの1人 -恐らく僕が気がついていた、あの目つきの悪い男に違いない- が、ニヤリと笑みを浮かべながらいつの間にか背後にまわっていた。(もう駄目だ!)もう逃げられない、と思った。けれど、一体何を、この僕がしたというのだ。
<何を?それはこっちが言うセリフじゃないのか。おマエこそ、どういうわけで俺から逃げだすのだ。俺はオマエに他ならないじゃないか。おマエは俺なのだ。何故、オマエはオマエである俺から逃げようとするのだ?それとも、あの子供が死んだ責任をオレにとれというのか?そして、オレであるオマエは責任を免れようとするのか、あの子を川へ突き落としておいて->
僕は、確かに誰かに追いかけられていた。けれど、別に悪いことをした憶えはない。憶えはないけれど、追いかけられたから逃げた。ただ、それだけだ。特に、あの子を殺すなんてことをするわけがない。それに、目の前の男など見たこともない。どこの誰かも知ろうはずがない。その僕がどうして、この男であるのだ。そんなことがあってたまるか。何を言っているのだ、この男は。いきなり手錠をかけてくるに違いない。そんな手に乗らせようとしている。油断するな。そんな策略で捕まるオレか。(逃げ出さなくちゃいけない…)
僕は目の前の男を、ジッと見つめた。恐ろしく歪んだ顔をしている。濁った目。臭い息を吐き散らす。僕がニラむと、その男もまるで僕自身が鏡に映っているかのようにこっちを二ラむ。ほくが少し後ずさりすると、その男は同じ距離だけ進んでくる。気持ちの悪い奴だ。こっちが黙っていると、相手も黙っている。暫らく緊張した時間が続いた。すると、目の前で材木を小山のように固定していた鎖が、グッと張りつめた。と、その瞬間、鎖は音もなくちぎれた! 広い大気の中へ、それらははじけ飛んでいってしまったのだ。その男は、木端微塵になった鎖とともにハエみたいな喘ぎをみせて、ナイアガラの爆風に霧散してしまった・・・。
だけれど、その男はどうも僕の影であったみたいな気がしてしようがない。何故なら、一声の悲鳴もあげずに僕の足もとで死んでしまったから。とにかく、追いかけ続けてきた敵のうち、少なくとも1人は死んだ、そう思った。だから、再び逃亡し続けることができる…。もう、こんな古ぼけた《過去》なんぞには来まい。少なくとも僕は《現在》なんだ。そして、同時に《未来》へとつながっていくはずなのだ。
そんなことばが、クルクルと脳裡を旋回していた。よくよく見れば、僕の前では何も起らなかったような気がする。第1、僕は汗ひとつかいていない。
(6)
ネオンが華やかだ。何故か、ひといきでムンムンする街へ来てしまった。確かに、もう誰も追いかけてこないようだ。勿論、あの男は既にいない。僕の前後や左や右の足もとにまつわりついていたあいつの影はない。それもそうだ。今は、夜なのだから。
厚化粧した女たちや、手持ちぶさたの連中がたむろする街の1角だ。そしてたまらなく寂しい街だ。それらの光景は、永い間タブーであったばかりではない。恐怖でさえあった。しかし、今はこう言い切ることができる。それらの光景は全く身内のものになってしまった、と。今では、闇に浮かぶ毛むくじゃらの女性自身も、ぼんやりとでなく、はっきりと見分けることができる。恐らく、怖いものは他にある。あらゆる事柄を利潤で売買する財貨に変えてしまうこと、それである。少なくとも、薄暗がりの女性を見捨てるほど僕は卑怯じゃない。ホラ、ああして声をかけてくる。それを聞かないふりをする、それほど臆病者じゃない。だから、そのうちの1人の誘いに同意することが、今の僕の勇気を示すことに他ならなかった。
手を握られ、狭いバーの中にイソイソと連れ込まれてしまう。所謂、個室バーというやつだ。ドアの鍵がしめられる音を聞くと、もう僕は下腹部の辺がミミズみたいにうごめていいるのを制止できやしない。
<何にする、坊や?コーク・ハイでも飲む?>
坊や?コーク・ハイ?冗談じゃない。オレをなめなさんな。(だけれど)そう言ったところで事態はまずくなるばかりだ。この際、ただ笑っているのが利口というものだ。けれど、女の肩に手をのせ、歯の浮くようなことを囁くと、僕の眼の隅に、果てしなく広い、暗黒の大海が広がったのに気づいた。それが恐かったから、唇を重ねた。胸から手を差し入れると、女は、まあエッチねといって、手を更に奥に押し入れた。固いブラジャーの下に、冷たい乳房があった。眼の隅で、黒い大海は徐々に押し寄せてきた・・・。それが恐かったから、夢中で背中のホックをはずそうとした。すると、大きいの1枚じゃなければダメ、と女は言う。毎日、何のあてもなく暮らし、物騒な連中に追われ続けて辟易している僕に、そんな大金あるはずがない。拒もうとするのを強引に抱き寄せると、やせぎすの女は、いきなり立ち上り、やにわにスイッチに手をやった。狭い個室バーはいっぺんに明るくなってしまい、うねりをうった暗黒の大海は音もなく引いてしまった。けれど、その後では、顔を硬直させた女が威丈高にこっちをにらんでいるのが理解できた。
<ふざけんじゃないわよ。あんた、わたしをオチョクルつもり?>
そうたんかを切った女の顔を見て、思わず口を塞いでしまった。女も一瞬アッと声をあげた。(奥さんじゃないか!)あのクリーム色の摩天楼の1角に軟禁されているはずの奥さんじゃないか。
<まあ!あなただったの>
そう言うと、信じられないことだが、奥さんはニヤリと笑った。それは、とても奇妙で恐ろしい微笑だった。驚きの余り、頭の中の《カニ星雲》が強力な宇宙線を発し始めた。そして、もの凄いエネルギーの解放で爆発している反粒子の世界へ、僕を放り込んでしまった。僕は、口もきけなかった。
<御免なさい。あなただったの・・・。驚いたでしょう。でも、わたしって、最初からこういう素性の女だったのよ。昔から、この水商売やっていたんだね。夫が出張で、いつも家をあけていたなんて、真赤な嘘。わたしを囲っているパトロンにすぎないのよ。彼との間に生まれたのが、あの死んでしまった子だわ。誰かに殺されてしまった、あの子だわ。けれど、わたしをこの正につなぎ止める唯一の絆が、あの子のふっくらした手の平だとは思わない。わたしにとって、何よりも大事なことは、多分、お酒とセックスよ。お金なんぞも、大してほしくない。そういう、1切のわたしたちの願望は、実は巧みに体をかわすことでしかないわ。なぜって、わたしたちは、毎日毎日死の方へ向かって走らされているのだし、時は確実に、その証明を行なってくれている。そうした中で、虚しさしか残らないというのは、むしろ当然なことじゃないかしら。ホラ、そんな真剣で泣きそうな顔をすることないわ。こっちへいらっしゃいな。わたしが、いいことしてあげるから>
奥さんは、僕を狭いソファーの上に倒した。そうして速やかにシャツのボタンをはずしてしまう。ズボンのチャックをおろし、パンツを下げてしまった。自分はといえば、ワンピースを脱ぎ、胸をあらわにし、下半身を生まれたままにしてしまう。目の隅に・・・、再び、暗黒の大海が押し寄せてきた。しかも、レールに乗って真黒な車体の真黒な電車が、奇妙な緩やかさで迫ってきた・・・。奥さんは、不思議な振動を起こして、僕の下腹部にヒタヒタと押し寄せてきた。その1部分は、掌握されてしまうと、もうそのとりこになってしまった。そうして、ついに血液が足の爪先から頭のテッペンまで、秒速30万キロで往復しようとした瞬間、目の隅から波をかきわけ、真黒な車体の電車がまってきた…。下腹部は、異様に高まり始めた。それを、奥さんは巧みに自分の秘密の場所にもっていった。と、思う間に、全身の力は、まるで核融合を起こしたみたいに巨大なエネルギーになって、その袋小路へなだれ込んだ。やがて、僕の叫び声である銀色の液体が白目をむいて腹の上を濡らした。
目の隅で・・暗黒の大海は静けさを取り戻し始めた。真黒な車体の電車は、走り抜けていってしまった・・・。奥さんは、まるで友禅を染めるような手つきで、僕の体に銀の液体をなすりつけている。それに、いつまでも頬ずりを繰り返していた。僕は、色褪せた天井の光に、拡散してしまっていた・・・。
<終ってしまった…。もう、あなたにとってわたしは、赤の他人ではないわ。奥さんでも、子供を失った母親でも、なくなってしまった。離れようとしても、結局、あなたは、わたしを忘れることなんか、できやしない。一切の力を消尽してしまった時、あなたは、その本質的過去へと帰ったのよ。所謂、《胎内回帰》というものへ。あなたの未来、唯一の、恐ろしい未来をあなたは見わけ、その中へと身を投じていくのだわ。わたしへ、わたしの内側の骨盤の中へよ。そこに漏斗状の《希望》という臓器を盛る骨があるの。他に求めても駄目で、ここにしか見い出せやしない。なぜって、まだ死刑の宣告を受けていない哺乳類の幼体は、この中でしか生活ができないから。その幼体は、未来を呑みこむか、それとも、嘔吐してしまうか、その選択権を握っているの。そして、本当に重要なことは、そのへその緒へ、酸素や栄養物を送っているのは、他でもない、このわたしだっていうことよ〉
何のあてもなく、空き腹をかかえた僕だった。確かに《希望》はもっていた。けれど、それは、中味のない幽霊みたいなものだった。毎日毎日、あてどなく駅へ向かって、トボトボと歩いていた。
そして、黒塗りの奇妙な電車に乗ろうとした。けれど、いつまでたっても、何も始まらなかった。《希望をもつこと、そして、その虚空に色を塗りたくろうと思うことは、結局、運命その頑迷な怪物から、僕自身の権利を回復しようと志すことなんかじゃなかったのだ。悪どい冗談にすぎなかった。悪足掻は、もうこの辺でやめにしよう。形の整った立派な住所をもち、トイレットもキッチンもバスも、それにコーヒーの備わった《希望》をもとう。奥さんー。
奥さんは僕にとって、ずっと以前から陽なたぼっこしていた、陳腐な希望だった。けれど、それでいいじゃないか。どうして、アレルギー反応など示していたのだ。
<いいのよ。済んでしまったことは。そうと決まったら、ここから1時も早く逃げ出さなくちゃ。目つきの悪い、頭のヘンな連中が、あなたを狙っているわ。最悪の場合は、撃ち殺されるかも知れない。ホラ、足音が聞こえるわ!>
本当だ・・・。死んだはずの男が、またやってきた。でも、大丈夫。僕には奥さんがいる。けれど、冗談じゃない。何度も言うように、どうして追われなくちゃいけないのだ。この僕が、一体何をしたというのだ。どういう罪を犯したのか。罪?本当に笑わしちゃいけない。(けれど)やはり足音が聞こえてくる。どこからともなく、あの男たちが迫っている。迫ってくる以上、兎に角、逃げ出さなくちゃいけない。さもなければ相手を倒すかだが、相手は数人だ。僕は、もともと臆病なのだ。だから、逃げるより術がない。
(7)
狭い山道のむせかえるような草いきれと、浜辺のコーラを胸一杯吸いこんで、僕は柄にもなく、ネクタイ背広に磨いた皮靴をはき、手には《刑事政策》という名の奇妙な本を携え、正面の階段をのぼっている。ヤツら、ここまでは追いかけて来ないだろう、という安堵感を抱いて。ホラ・・、聞こえてくるじゃないか・・、あの快い音楽が・・・。だから、僕は久し振りに浮き浮きしているのだ。
<戦線を共にするぅ、すべての戦士諸君!亡霊はぁ、ここに再びよみがえった。学園斗争はぁ、決して終りはしない。69年第2次斗争の、大衆的昂揚を克ち取った戦線の主体はぁ、斗争の圧殺ともども葬り去られたかのように見える。しかしながらぁ・・・>
そっと、来た遙かな道を振り返ってみる。そこには、沢山の笑顔や大きな叫び声。そして原爆を散りばめた街の騒音・曇りガラスを張りつめた暗い空の下で、アルジェのじりじり灼き尽された荒廃した家並。ヤケッパチの超価利潤、すなわち、ミニやマッカーサー・サングラスや血のしたたるネオン。それらが、扮飾され、泣きべそをかきそうに笑っていた。
<学友諸君!我々の怒りの論理が偽物でないのならぁ、そして、今なお抑圧の中に生き続けているものなら、叛逆こそ、我らの生活の始源ではないか。今こそ、再度の偉大な斗争に決起せよ!そして,,,>
まわりを囲む、僕らの分身は表情もなく、まるで村はずれの風化した地蔵のように伏し目がちに排泄され、轟音の混った水とともに暗闇の中へと呑みこまれてしまった。広場は、血のついたアスファルトの蒼白なあばたを見せている。こみあげてくる血の匂いを胸一杯吸いあげる。と、やがて、この広場と建物にひっそりと寄生していたドブネズミの一員であった自分が懐しく思い出されてくる。
耳をすませば、遺水の脅しめいたはね音も、懐しいざわめきの混迷も、僕の胸を滑らかに沈めてくれる。あのように背を屈め、痩せこけ、足もとフラついてしまった広場の物言わない群衆を、許すことができる。そして、許すも許さないもない。1番責められるべきは誰だ。ずっと逃亡していた。《希望》にしがみつき、その館に忍びこもうと追われてしまっていたのは誰だ。
ふと、手に持っている本の表紙をめくってみる。《犯罪者の処遇に関して》わけもわからず建物の中へ進んでいった。すると、1番初めの入口のドアに《じゅぎょう》と書かれてあった。何故か、息をハァハァさせながら1番後ろの席に座った。やがて、壇上に1人の男が、スタスタと歩み寄り、マイク片手に本を開いて講義を始めた。改めて、その男を見たとき、僕は早くも顔じゅう凍結した緑色の血液で覆われてしまった。唇は木枯しみたいにカタカタと震え、足は鉛色の桎造を受けてしまった。
<ええ、皆さん。今日は《犯罪の概念》ということについてお話しせねばならない。アー・マイク聞こえますか?聞こえますね?そうです。そこの席に座っている学生>
と、僕の方をぼんやりと指さし、
<君のことから始めようと思うんです。君は次のような事実に気がついていますか?他でもない。わたくしは即ち、君である。そして君を追っていたのは、他でもない君自身である。えっ?わかりますか? 君は、即ちわたくしは、今までさんざん、いかにも意味のありそうなポーズをとり続けてきました。そして、何が始まるのかと思っていたら、何のことはない。何も始まらなかった。ただ、人殺しという罪を犯した。そうですね?あの可愛い子供を殺した。間違いないでしょう?それだけのことだった。それだけなら、大目に見ることもできましょう。何故なら、人間一生の間に他人を殺さないで生き抜くことなど不可能にちかい。嘘だと思うなら、これからずっと生きてみるがいい。生き延びるためには、直接的にも間接的にも、必ず他人を殺していくのだ。
考えてみますればぁ、生きること、つまり生まれたということ自体がもう1種の罪である。だから、オギァと(うっかり)叫んでしまった者には、《死刑の宣告》という、素晴しい運命が与えられるのです。君も、既にその刑を受けていたのだし、その罪に対する刑罰というものを更に絶対化する立派な殺人を実行した。せめて、そこで止めとけばよかった。それをです、なまじ《希望》などと、口にしたのがいけない。どうして、《死刑の宣告》と《希望》というものが矛盾しないでいられよう?そのことに気づかなかった君は、あの日常性、すなわち、毎日何のあてもなく下宿を出て、クリーム色のアパートの群れを見やりながら、人通りのない大通りを歩き、駅まで通う《日常性》さえも放棄しようとした。すなわち、わずか3歳の罪のない(いや、まだ自意識をもたないという意味で)予供を川に突き落として溺死させ、あの奇妙な黒塗りの電車に乗ってしまったのだ。
あの子供が死んだ時、アパートの主婦たちが囁いていた<あの人>とは、君に他ならない。君は、殺人者なのだ。それというのも、あのアパートのベランダに見かける美しい御婦人に、1種の恋をしたからに他ならない。その御婦人には、子供がいた。だから、その子は君にとって邪魔な存在だった。だから川へ突き落としたのだ。そして、その犯罪から逃れようと黒塗りの電車に乗った。そこでは、すべてが清算されると思えた。追手は来ないだろう、と思えた。けれど、追手はやって来た。追手は、君自身に他ならなかったのだ。
けれど、あの御婦人は、君のものになるはずだった。君の最大の誤ちは、あの御婦人を《希望》とすりかえようとしたことだ。そうして、罪を逃れようとした。しかし、そうすればそうするほど、希望は意味のないものになっていったのだ。
よせばいいのに、《希望》が何か無限の可能性を秘めているものだと信じ、それを探そうとした、あてどもなく・・。電車を降りて、君は何を見たか。結局、何も見なかった。見たといえば、あの黒塗りの奇妙な電車に乗る前以上の《絶望》を見た。つまり、その結果として君は今ここにいて、君自身であるわたくしから、そのことを確認させられている。
子供を殺したことは罪ではなかった。何故なら、先程も言ったように、人間一生のうちに他人を殺傷しないで生きていくことなど不可能なのだから。そして、あの子供は君に比べて、遙かに豊かな希望をもっていたからだ。そこで君の嫉妬が燃えたというのは、当然だといえる。だから、せめてそこまでにしておけばよかったのだ。それを君は、日常性を打破しようとあの奇妙な電車に乗ってしまった。そして、《希望》の中味をあれやこれやと詮索してしまった。それがいけないのだ。希望のカラクリを見てしまった君は、一生、うちひしがれて生きていくより仕方がない。だから、その行為は、《加重的自己逃走罪》並びに《秘密漏泄罪》にあたるのである。
いつの時代も、未来は幻想を一杯にはらんでふくれあがり、新奇なもの、意外なものやスピードに満ち満ちて深呼吸しているように思える。けれど、それらに対して、君らは何1つ真実の声を発しえない、去勢された群衆の世代になりつつあるのだ。つまり、様々な可能性に魅せられ、やがて疲労困憊してしまった。もう、何も捉えることはできない。その背後に、もう世界はないように思われる。そういう新しい凡庸の時代を形造っている。だから、そういう体制の中で、必然的に深化され、死んでいくのだろう。《希望》のカラクリを破ろうとして、その体制を崩そうなどと、また夢想しないほうがいい。同じことなのだ。また、同じ問いに悩まされるだけだ。だから、火炎ビンを投げ、バリケードを築くことは重罪である。見せかけの歪み顔や、見せかけの問いは無意味であるばかりでなく、傍で見ていて吐き気をもよおさせるほどである。だから、そういうポーズの一切の総体こそ、結論とするところの《犯罪》の概念の典型的なものである>
まわりを注意深く見回した。僕の分身みたいな栄養失調の長髪の連中が、わなわな肩を震わせ、声も出せないで教壇の男に脅えている。僕は、そっと立ち上る。すると、ドアの所に《きんえん》と書かれてあった。それをメチャクチャに破り捨て、一目散に出口まで駆けていった。そして、広場を通り抜け、正面の階段をかけ降りようとした。途中で、フワッと体が浮き、随分高い所から落ちたような気がした。幸い、外傷はなく、ただ痒いような痛みが背筋を通り抜けたから、思わず≪寝返り》をうった。
すると、ヒマラヤ杉に囲まれた蔦はう建物の一角に、ポリネシアに注ぐような希望に満ちた夕陽が差し込み、その影が長く尾を引いて、ちょうど僕の顔をさえぎったのだ。その時は、とても幸福だったように思う。そのすぐ後だった。振り返ると、もう機動隊がずらりと並び、ガス弾をやたらメッタに発射してきた。後ずさりすると、背中のほうから、ワァーッという声とコーラと炎が飛んだ。ヘルメット角材の連中が、スローモーション映画みたいに機動隊と衝突した。もともと、臆病な僕は、サッと身を翻し横道からずる賢い蝙蝠の如く逃げてしまおうとしていた。逃げざま、ふと見れば、ヘルメット・角材の連中はもう地に叩き伏せられ、真赤な反吐を吐いて苦しそうにのたうちまわっているではないか・・・。
(8)
いつの間にか、駅に来ている。ずっと以前から、どこかへ逃げたいと思っていた。けれど、ずっと以前からこの土地にいた。そして恐らく、これからもずっとここにいるだろう。遠くのケヤキの梢が、カサカサと鳴り出した。物憂げな平べったい日差が、郊外の閑静な住宅街にさし込んでいた。広いアスファルトの道路には、車もまばらだ。それらの光景は心苦しくはなかった。ただ、相変わらず物悲しいだけだった。
ちょうど、ほくは気が滅入っていた。駅まで来て煙草を買うと、またそこから下宿まで戻ろうとしていた。漠たる空想の世界は、貧困な現在を高めてくれた。それだけで、買い物がてらの散歩は目的を達していた。今、帰ろうとして、駅前広場を見渡すと、妙なことだが、僕のほかに誰も居なかった。郊外の新興住宅地だ。朝晩の混雑に比べ、午後の今は、ただ建物だけがシーンとなった白日に晒されている。熱帯魚のように群れをなした赤トンボが、そこを通り過ぎた。例の、クリーム色の高層アパートとその間をぬう広いアスファルトの通りが右手に見える。
僕は、そこをトボトボと伏し目がちに歩き出した。真青に染まった山々が遠くに見える。その上を遙かな大空が広がっている。どうやら、いままでと逆の方向にむかって歩いているらしかった。見慣れた下宿の建物が、次第に大きく見えてきたから。駅やクリーム色の建物や真黒な車体の電車、古い町、ネオンサインや広場の群衆が・・・、だんだん視界から失せていこうとしていたから。つまり、僕は空想から、1つの<結論>を得て、そこから出発しようとしていた。
誰もいないアスファルトの大通りだ。そこを暫く歩いていった。すると、急に自分がたまらなく可笑しくなった。
けれど―、またほんの暫らくいくと、何故だか急に哀しくなってしまい、立ち止まってしまった。ふと見ると、僕の影が行手に長く伸びている。その影を追いかけるようにして歩いていく。そして、決して踏み潰せはしないのに、微かな期待を抱いた。影を踏み潰してしまいたかった。それは、不吉な影だから。そして、無限の希望の中で生きたかった。けれど実際は、やがて年老いて膝まずき、その影の上に重なるようにして、生は終ってしまうだろう。だから、今こうして歩いていて、いこうとする僕は哀しかった。そして、それは、まるで滑稽であることがそのまま悲劇的である、僕たちの生の奇妙に憂愁にみちた総体的な姿みたいだった。
70年夏の思い出 – 四国 – 商学部3年 中山
70年夏の思い出 – 四国
商学部3年 中山
四国でのサイクリングは、今年の春、計画をたてたのだが、いろいろなことで断念しなければならなかった。今年の夏合宿が山陰地方と決定し、松江に集合と決まった時、私はこの計画を実行に移すことができた。四国は私にとって未知の土地である。生まれて此の方あちこち渡り歩いたが、四国にだけは足を踏入れたことはなかった。観光センターへ行き、資料などを集めコースを考えたが、徳島県出身の高原君から東京から走るのでつき合わないかとの誘いがきた。私は四国まで走ってゆくつもりは無かった。というのは、松江への集合日が決まっているので日数が制限されてしまい、四国でのコースが短縮されてしまうからだ。しかし、彼も1人で走ったのではつまらないだろうし、又誰もが大体、東京・大阪間を走っているし、コースの魅力は乏しいが、のちになって自分だけ走っていないということになるのも、しゃくだしと思い彼の提案を受入れることになった。
かくして1970年の夏は、横浜から出発して大阪を経て四国に渡り、四国を巡った後広島に渡り、中国山地を横切り松江にて合宿に参加し、そして解散地である京都まで走るというかなりの長期ツアーになってしまった。
私はこのツアーの四国におけるサイクリングの出来事を書いてみたい。
8月1日
大阪で高原君の自転車は、その機能を全く果さない単なる物体となってしまったため、徳島へは別々に入ることに決まった。大阪では篠原さんの家に御厄介になり、高原君は大阪から徳島へ、私は1日遅れて和歌山まで走り、そこからフェリーで徳島に渡ることになった。大阪で自転車を完全に整備して、なにしろ後のタイヤのスポークが9本も折れていたのだから。篠原さんは深酒がたたってか、身体の調子を悪くしていた。母上曰く
「あんた、酒はやめて女にせい」
一理ある。しかし篠原さんは、女がだめだから酒にはしったのではなかろうか。
篠原さんと母上に1宿1飯以上のお礼を述べて和歌山へと向かった。ひどい雨で、堺までは車道は水びたしで、歩道を遠慮しながら走った。深日港についた時には雨はあがっていたが、運の悪いことにフェリーは出ていったばかりであった。港を出たばかりの船をうらめしく思いながら時刻表を見ると、あと3時間待たないとならない。もう10分も早くついていたらなあ、と思いながらしばし茫然と海を見つめていた。雨あがりのせいか海はなんとなく精彩を欠き、さらに気が重くなった。徳島に帰っている高原君に、そちらに着くのが遅れることを電話で知らして、ゆっくりと昼食をとり、時間をつぶしたが港の囲りには何もなく、待時間がとても長く感じられた。しかもそのうち、再び雨が降り始め、待合所で1人寂しく煙草をふかしていた。そばに旅行者でもいれば、話をして時間をつぶすこともできるが誰1人いない。じゃりが敷きつめられた広場には、雨が小止みなく降っている。
フェリーの着く1時間くらい前から、フェリーに乗るための車が集まり始め、待合所も活気を帯びてきた。やっとフェリーに乗り込むことができたが、天候は悪く船は大きく揺れて、客の中には吐く者がいた。寝ていても畳の上をすべってしまうのである。私も余り乗り物に強い方ではなく、回りで吐かれるとこっちまでもよおしてしまう。なんとかこらえて徳島に着いた時は、日はとっくに暮れていた。高原君が港まで迎えに来てくれていて、そのまますぐ彼の家まで走った。御両親に丁重な出迎えを受け、はなはだ恐縮して家にあがらせてもらった。
8月2日 徳島 – 大歩危
徳島といえば、誰もが御存知の阿波踊りがあるが、いや阿波踊りしかないのでは、こんなことを言うと地元の人に怒られるかな、私が行った時は、その練習とかで市内の広場のあちこちで人々が踊っていた。うまいもんだ。旧盆の頃には、徳島の人口は何倍にもふくれあがるという。徳島県にとっては、阿波踊り様々であろう。
朝起きたのは8時頃であった。眠い目をこすりながら御両親に別れを告げ、高原君は途中までついて行くと言い出発した。池田町まで国道192号線は吉野川に沿って、少しずつながら上っている。
途中、高原君の親戚の家とやらに寄り、冷たいものを御馳走になり、銭別としてロングピースを3箱もらった。タバコ屋なのである。東京から2人で走ってきたと話すと、信じられないような顔つきで見られた。それからしばらく走って高原君と別れることになった。不思議なもので何となく寂しい気がする。彼とは松江で再び会えるだろう。「さあ、これからは1人」と心に告げ、ペダルを踏み出す。太陽は青空を背景に我が物顔でそのエネルギーを発散している。途中、むしょうに喉が乾き川の堤の上で小休止して水を飲んでいると、川で泳ぐのであろうか、小さな女の子が水着に着替えている。そのとたん彼女と目が合ってしまい、何とも気まずかった。その時は無意識だったのだが、こんな時は男は弱いものだ。いくら相手が歳が若すぎるといっても女性であるからして、私としては何と言っていいやら、すっとぼけたものやら、困ってしまった。結局は、そうそうに自転車にまたがり、口笛を吹きながら、さも平然と走ってゆく他はなかった。
さて、この国道192号線だが、この道路に立っている距離指示は全くのでたらめで、走れば走る程、目的地まで遠くなってゆくのである。かと思うと、いっぺんに目的地に近くなり、又だんだんと遠くなってゆく、こんな精神的に疲れる道もない。
池田町についたのは4時半頃である。ここから国道33号線へ入り、大歩危へと向かう。左に渓谷を見ながら進む。川の流れは、山の木々が映っているのか緑色をしており、岩肌は白く、みごとなコントラストを見せている。山の中であるため、日は早く沈み、夕暮迫る道をとばした。大歩危にはキャンプ場があると聞いていたので、今日の泊りはそこに決めていた。
徳島本線はトンネルを出たり入ったりしている。大歩危についたのは5時45分。キャンプ場は川まで降りなければならない。自転車を上に置いておくのは心配であるから下まで降ろさねばならない。ちょっと一苦労だ。
食堂で氷を食べていると、1人の女性が私の前に座り話しかけてきた。リュックをしょっている。山歩きが好きで、黒滝山を上り、今おりてきたのだと言う。
「それは大変ですねぇ」と大げさに答える。
「あなたは何をしているのですか?」
と聞いてくる。その時の私の姿は、ブルージーンの半ズボンに、上は紺のランニング、遠くから見ると、1世紀前の水着みたいな格好をしていたのであるから、この質問もうなづける。
「自転車に乗ってるんです」と答えると、
「そうですか、それは大変ですね」と彼女。つづけて、
「この辺は、旅館が高くて困っているんです」
「テントは持っていないんですか?」と私。
「テントは母から禁止されているんです」と彼女。私はここで危く、
「それじゃ、私のテントへ来ませんか」
と言ってしまおうとした。だが、私は立派な青年であるから、ぐっとこの言葉を飲み込み、結局でてきた言葉は、
「旅館なんてものは、交渉しだいでまけてくれますよ」
であった。彼女は私の言葉により、再び旅館の主人と交渉しにいった。しばらくして戻ってきて、
「まけてくれましたわ」と言い、
「よかった。よかった」
を連発していた。私は心の中で、
「惜しかった。惜しかった」
を連発した。5人用のテントの中に1人で、大の字になって寝たのは何とも気持ち良かった。
8月3日 大歩危 – 須崎
朝はどうも眠い。国道32号線は上り気味の道である。9時を過ぎると日差がきつくなる。道は舗装されており、ペダルもそれ程重くない。相変らず左手には渓谷が続き、太陽の光を受けて水はきらきらと輝き、その美しさを一層素晴しいものにしている。途中、大阪府立大学のサイクリストと会う。西サ連、エスカなどの堅い話をしたが、私はエスカ無関心派の部類であるから余り話は進まない。
「友達と会わなかったか?」
と尋ねられたが、私は昨日からサイクリストには会っていない。そのことを述べると、彼はおかしいなというような顔をして、
「高知の方へゆくなら、竜河洞へ回って行ったら面白いだろう」
と教えてくれた。国道32号線は相変らずだらだらと上っている。別れ際に彼が、
「この先に峠がある」
と教えてくれたので心して進んで行った。しかし、道は急な坂にならず峠まで私を導いてくれた。こちらから走ると、峠と名をつけるのには、ちょっとぎょうぎょうしい。しかし反対側からくれば、こいつはちょっと大変だ。ブレーキを鳴らしながらヘアピンカーブを何度も経て下っていった。高知まであと10キロちょっとという所で、竜河洞へ向う道路標識があった。そちらへ回ると20キロ程遠回りになるが、時間に余裕があったため回ってみることにした。竜河洞までの道は田んぼの中を通り、山の中へ入ってゆくのだが、ついてみると、附近の静かな景色から浮き出たような大繁いを呈していた。竜河洞は鍾乳洞の1つで入口から出口までは約1キロあり、中はまるで別天地で半ズボン・ランニングではちょっと寒すぎた。中を流れている水は、身を切るように冷たい。又所々には急な階段があり、期待したが、電灯は上の方についていて期待は裏切られた。
私は生まれて初めて鍾乳洞なるものを見たので、中に立っている案内係にいろいろと質問してみた。しかし、1人として私の質問に答えてくれる者はいなけった。
「ちょっとわかりかねます」
「さあ、どうですかね」
「そういうことは聞いてないんですけど」
こんな答ばっかりだ。彼等はパンフレットを読んでいるだけなのである。
南国市を通って高知へついたのは3時45分であった。初めの予定ではここで泊るつもりであったし、ついたときもそうするつもりであったが、それをやめさせる事件が起った。それは、私が駅前のターミナルの真中の芝生の上で煙草をふかして、
『桂浜までどのくらいあるかな』
と考えていると、髪をきれいになでつけた40くらいのおじさんが、こっちの方へやってきたのである。私は今までサイクリングをやって、その度その土地の人から浴びせられた質問がくるのではないかと少々うんざりして待ち構えた。
「あなた、学生さん」
「はい、そうです」
「自転車で旅行しているの」
「はい、そうです」
「高知は初めてなの」
「はい、そうです」
「今日は高知で泊るんでしょう」
「ええ、そのつもりです」
変なおやじである。妙にていねいな言葉を使い、なんかなよなよしていて、気味悪い。
「それじゃね、私、1人でマンションにいるの、よかったら泊っていかない。なんの気がねもいらないから」
「ええ、でも悪いですから」
「そんなことないのよ、今まで何人か学生さんを泊めてあげているの。学生さんはこれから国のために尽くす人でしょ。だから、そのちょっとのお役に立ちたいと思ってとめてあげるんだから」
「ええ、でも」
「それに、学生さんて余りお金ないんでしょ。私ね、旅館の番頭をやっていてそんなに多くはないけど、学生さんに比べればゆとりがあるから。だから、そうおこづかいあげましょ。これからも旅行を続けて、どんなことがあるかもしれないから。いくらぐらいがいい?」
なんじゃ!このおやじ。もしかしたら、いや、本当に親切で言ってくれているのかな。いや、違うな。大体こづかいをくれて、マンションにとめてくれるというような話をそう簡単に受けるわけにはいかない。うまい話にゃ気をつけろと昔からの言葉もある。この場合は、これからの旅を無事に進めるためにも、サドルに苦痛なく乗るためにも、この話にはのるべきではないと私は判断した。
「私はこれから仕事があってね、8時になると終るの。だから8時に駅で待っていて頂だい。必ず迎えに行きますから、きっとよ。お願いよ」
「はい分りました。どうもありがとうございます」
「じゃあね」
私はその男が人ごみの中に消えたと同時に、自転車に飛び乗ってペダルを踏んだ。一刻も早く高知を出よう。そう心に決めていた。この男のおかげで、私はついに桂浜を見ることはできなかった。
国道55線から国道56線へと入り、南下する。土佐市を通り、須崎市へ入る。時間は6時45分。今日はここで泊ろうと決める。コーラを飲みながら、テントを張るような所はないかと聞いてみる。浜まで出ればいくらでも張れるとのこと。海辺に出たときには、日は沈んでいて、テントを張る頃には暗くなり、ペグの代用の石を見つけるのに苦労した。
風呂から帰りそろそろ寝ようかという頃、テントの外に人の気配がする。だんだんと近ずいてくる。話声から判断すると、男女のカップルでしかも高校生のようである。私のテントに気付かないのか、近くで座って話しだした。
「俺、まだ童貞や」
「あたしもバージンよ」
なに!私はぱっちりと目があいてしまった。冗談じゃない。おれはこれから寝なきゃならないんだ。そばでごちゃごちゃ気になる話をしてくれては明日に差しつかえるのである。私はよっぽど、
「おれもだ!」
と怒鳴ってやろうとしたが、前にも書いたように、私は立派な青年だから、軽くせきばらいをしたにとどまった。それでも彼等は、びっくりしたように、
「こんな所にテントがある!」
と言って、どこかへ走って行ってしまった。これで私はようやく寝ることができた。
8月4日 須崎 – 中村
海では太陽の隠れるところがないとみえて、まぶしくて朝早く眼が覚めてしまった。なぜか喉がからからである。7時前に出発する。須崎を出てしばらくすると久礼坂峠にさしかかる。今ちょうど新しい道路を建設中で、舗装はされていないがほとんど開通しているようである。通行禁止の看板が立っていたが自転車ぐらいどうにかなるのではないかと思った。が、途中で拒絶されたらこんな馬鹿な話もない。
それで安全策を取り、将来は旧道になるであろう道へと入っていった。この道はいわゆる山道で、上は木々でおおわれて、地面は心なし湿っている。所々、清水も湧いているといった感じのよい道である。しかし時々、大きなトラックが2・3台連なって通ってゆく。その度に自転車から降りてトラックが行き過ぎるまでよけていなければならない。しかしそれを除けば、気持ちの良い道である。上りはちょっときついが、これはしかたないだろう。峠の付近は工事中で一方通行になっており相当待たされてしまった。しかもこの辺には木が1本もなく、日にまともにさらされて、暑いの暑くないの、おまけにほこりがひどく、早く通してくれることを祈った。
峠の上のドライブ・インで朝食を済ませる。このところ、朝は食事をする気にはなれず、峠を1つ越えたところで朝食をとる格好になっている。ドライブ・インの女の子達が、私をなにか変なものでも見るような目つきで見ている。よくみると、髪の毛はほこりで白くなっていて、紺のランニングも白っぽくなっていてなんとも薄汚ない。下りは道幅も広く舗装されていて快適である。
若く明るい歌声に雪崩も消える花も咲く…
私は下りになると歌がでる、上りでは絶対にでてこない。
窪川町までは、このような快適な下りが続くが、そこを過ぎるとひどい道となる。工事中でバラスがまいてあり、がたごとがたごととサドルの上をはねながら進む。このような道は早く抜け出したいと、あせってペダルを踏むが、その割にはスピードが出ない。あきらめてゆっくりと進むことにする。この先に素晴しい峠があった。
といっても景観が良いのではなく、こちらから進んでゆくと急に道がすとんと下に落ちているのである。なんの気なしに道を曲ると、道はずうっと下り出すのである。名づけて「片坂峠」いい名だ。逆から来た者は、つばでも吐きかけたい名前だろう。細い道で、それ程車は通らずサイクリングコースといった感じがぴったりの道である。土佐佐賀で再び海に出て、そこから中村までは、ひたすらペダルを踏み、かなりとばした。中村では大平寺というユースホステルをやっている寺の境内にテントを張らしてもらった。
8月5日 中村 – 足摺岬 – 宿毛
中村を出てしばらくすると伊豆田峠にさしかかる。地道の上をゆっくりとしたペースで上る。山の木々の間からに鳥の声がして、朝早いせいか車も時折通るくらいで、回りの景色を楽しみながら進んでゆく。峠にはトンネルがあり、トンネルを抜けると舗走道路が下に向かって伸びている。一気に下ると海へ出るといった具合である。ここから土佐清水までの道は、岬では上り、入江では下るといった海岸線特有の道が続く。
相変らず空には太陽が輝いている。土佐清水から半島の西側を通って足摺岬へと入ってゆく。道幅はそれ程広くなく、木洩れ日の下を清水のしぶきを浴びながら必要以上にゆっくりとしたペースで進んでゆく。右手には時折、すばらしい色をした海が顔を出す。足摺岬は有名な観光地であるから、人がたくさんいるであろうと予期していたが、真夏でもあるせいかそれ程でもなく、ちょっとしたハイキングコースを1人でぶらぶらと歩いてみた。四国最南端と書かれた展望台から下をのぞくと、海に吸い込まれてゆきそうな気になってくる。自殺の名所だそうで、そばの立看板には「相談承ります。某」と書いてあった。
青い空がお日さまにとける
白い波が青い海にとける
青い空は私の恋のいろ
青い海はあなたの愛のいろ
恋はみずいろ空と海のいろ
歌おうと思ったが、そばには人もいたし歌えなかった。しかし、こんな歌がでてきそうになる程、海は澄んでいた。
同じ道を土佐清水まで戻り、昼食をとり先へ進んだ。途中、ちょっとした下りでブレーキをかけたとたんにパチッという音が聞こえて、後ブレーキが効かなくなった。調べてみると、片側のブレーキゴムが飛んでしまっているのである。引き返して捜してみると、ゴムは見つかったが、ナットはどうしても見つからない。
これは私のミスで、昨日パンクをしたとき、片側のブレーキゴムをはずして修理を行い、工具をしまった後、ブレーキゴムをとりつけるのを忘れていて、なんとスパナで締めず手で締めただけにしておいたのである。読んでおられる皆さんは、なんと馬鹿なことをとお思いであろうが、そのときは、なぜかそうしたのである。今考えるになんと馬鹿なことをしたのだろうと思っている。大事に至らずに済んだことを神に感謝しなければならない。うまくいっているときは、神の存在などは気にもかけないのだが、ひゃーとしたその瞬間には、この人が頭に浮んでくるのは不思議なものだ。途中、自転車屋でナットを求めたら、
「代金はいらないから、気をつけて走ってください」
といわれ、すなおに、
「どうも、すいません」と答えた。
しばらくして私は、自分で計画したコースとは違ったコースを走っているのに気が付いた。海岸線を走っているはずなのに、山へ山へと道は続いているのである。左手には川が流れている。地図を拡げてみると、本日の予定宿泊地である宿毛にはゆけることが分かったので、そのまま進むことにする。しかし、越えなくてもよい峠を1つ越すことになってしまった。蝉の合唱隊でもあるのであろうか、うるさい程に鳴いている。車が通り過ぎる度に、ほこりが舞いあがり喉がざらざらする、途中、川までおりて体を拭いていたが、上のほこりのたっている道には、仲々戻る気はせず、私は思い切ってこの川で泳いでみることにした。何故、思い切ったかといえば、自転車は上の道に置いてきており、水着はそこにあるのであるから、このまま泳ごうとすれば、私は何も着ないで泳がなければならない。
さいわいにも、川は大きなものでなく、しかも木におおわれていて上の道からは見えない。そしてあたりには人影はない。それで私は思い切ったのである。水着なしで泳ぐのがこんなに気持ち良いものだとは知らなかった。
宿毛の手前で大きなパンクをやらかしてしまった。それは、あっと思った瞬間、タイヤの空気がいっぺんになくなった程だから、察しがつくだろう。水で調べる必要もない程大きな穴があいていた。
宿毛はそれ程活気のある町ではない。夕食を食べながら店の主人にテントを張るような場所はないか聞いてみる。
「そばに川があるから、その河原で張ったらどうですか」
と言われ行ってみる。石がごろごろしてはいるが、犬きな石ををどければ張れないことはなく、ここを今夜の仮の宿にすることに決めた。
テントを張り、日記を書き終え、ほっとしてウトウトしていると、テントのそばで舟を漕ぐ音が聞こえる。すると、
「テントの人。テントの人」
と呼ぶ声が聞こえる。何だろうと思い出てみるとびっくりした。テントのすぐそばまで川の水がきているのである。舟の人は、
「もうすぐこの辺は、川の水につかってしまいますよ」
と言う。私はあわてた。荷物はすべてどての上にほうりあげ、テントは引きづり倒し、両手にかかえてどてに上った。真暗である。
『どうすりゃいいんだ』
しばらくの間、ちらばった荷物とめちゃくちゃのテントを見て、その場に立っていた。どこかテントを張るところを見つけなければと思っていると、近くに人の気配がする。女の子が犬を散歩させているのである。彼女に聞いてみる。
「川の上流に公園の予定地がありますから、そこにいらしたらいかがです」
「そうします。どうもありがとう」
と礼を述べて、荷物を自転車に付け、テントはごわごわにまるめたまんま自転車にくくりつけた。道は細いうえに暗くてよく分からないため、自転車を押して進むことにする。あった、あった。ブラソコが1台完成しているが、まだ公園といえるものではない。しかし公園であるからには、公の土地であるから断りなしにテントを張ってもだいじょうぶだろうかと心配になった。又寝ていて起されるのはいやだ。もう水の心配もないことだし、近所の人にこの旨を尋ねてみると、「だいじょうぶですよ」とのこと。やっと眠りにつくことができた。
8月6日 宿毛 – 宇和町
朝起きると不思議なことに腹が空いている。昨日と同じ店にゆき、朝食をとる。この店で高校生のサイクリスト2名と会うが、こちらが話しかけても余り乗ってこない。白けた気分で出発した。単々とした道が続くが、松尾峠は圧巻であった。上りでは汗がアスファルトの上にしたたりおちてゆく。距離はそれ程長いものではないが、傾斜はかなりきつく、しかも空には南国の太陽がギラギラと光っている。しかし、いったん下りに入ると汗はいっぺんにひき、一瞬身振りした程である。
宇和島についたのは2時を回っていた。別に見るべき所はないのでそのまま進む。吉田町をすぎてから法華津峠にさしかかるが、この道はひどい。地面に大きな石が埋まっていて、まるでロデオ大会のごとく私は自転車の上で踊っていた。しかも道は上ってゆくのだから仕末が悪い。しかしそれもしばらくすると普通の地道になってくれて、峠の近くになると景観は素晴しく左手には入り組んだ海岸線をしたがえた海がキラキラと光って見え、右手の山は一面のみかん畑である。そうこうしているうちにトンネルが見えてきた。しかしトンネルの中へ入ってもペダルは重く、苦しい。おかしいと思いながら進み、トンネルを出るとまたトンネルがある。今度は下るかなと思って進むが、一向にペダルは軽くならない。そんなこんなで、遂に9個のトンネルを上ってしまった。いい加減頭にきた。10個目のトンネルを抜けてやっと峠が終った。この下りは、ほんのお情程度のものであった。ここで宇和町についた。
予定より早くつき、ゆっくりと風呂に入ったが、なんとも奇妙な焼け方をしている。足は短パンであるから、中途半端な所から焼けて、上はランニングであるから焼け方は想像がつくだろう。風呂に入っている人は、まだ時間に早いせいか余り多くはなかったが、その人達は私を注目していた。私は彼等が私をどのように判断しているかが非常に知りたかったが、まさか聞くわけにもいくまい。テントは児童公園わきのテニスコート予定地に張ることにした。ここはちょっと町から離れていて、ちょっと寂しいような気もする。近くにある高等学校で水を貸してもらい、ランニングとくつ下を洗濯させてもらった。夜になると風が出てきて、風で回りの木が、ざわざわと揺れると熊でも出てくるんじゃないかと馬鹿なことを考えたりした。
8月7日 宇和町 – 松山…広島
舗装された上り気味の道がつづく、朝早いためか霧が濃く、サングラスがくもってかけられない。上りが急になるところで舗装が切れてじゃり道となる。しかし体調は良く快調に上ってゆく。峠も近いだろうと思われる頃、タイヤの調子がおかしい。パンクにしては空気が抜けているとは思えないが、サドルに伝わるショックはちょっと異常だ。しかたなく調べてみるが、近くに水はなく、どうしても穴は見つからない。どのくらい時間がたったろうか。しばらくすると宿毛であった高校生2人が自転車を押して上ってくる。彼等も昨日は宇和町で泊ったのだそうだ。それぐらいの話で彼等は自転車を押して上ってゆく。しばらくして遂に、空気もれの原因を発見した。それは古いパッキンが2枚並べてはってある中心からぬけていたのである。2枚ともはがし、大きなパッキンを1枚はり、勇躍出発した。すぐに2人を抜き、快調に上ってゆく。大州までの下りは途中から舗装になり、あっという間に大州についてしまった。
大州で朝食をとり、町中を進んだが道が入り組んでいて方向がはっきりしない。しかたなく近くを歩いていたおばさんに松山への道を尋ねた。ところが、そのおばさんは私の姿を見るや
「まさか松山まで自転車でゆくのではないでしょ」
「いえ、行きますよ」
「そんな馬鹿なことはおやめなさい。汽車があるんだから、汽車でゆきなさい。まあ、自転車だなんて」
私は今までちゃんと自転車で走ったことを告げ大丈夫であるからと言ったが、そんな言葉には耳も貸さないで、「汽車でゆけ、汽車でゆけ」と言う。私は遂にこのおばさんから、松山へ行く道を聞くのをあきらめた。高校生に道を尋ねて、やっと大州の町から出ることができた。
大州を出ると道は徐々に上りだす。地図には榎峠、犬寄峠と2つの峠が載っている。ゆるやかな上りがずっとつづく。中山町までずっと同じ調子だ。このあとに2つの峠があるのだが坂は急にならない。ふと見ると前にトンネルがある。トンネルの上には、犬寄遂道と書いてある。まさかこれで峠がおわりでは、ちょっと信じられない。トンネルを出るまで信じられなかったが、トンネルをぬけると下るは下るは、ものすごいダウンヒルである。四国で最高だ。言うことなし。ついた町は伊予市である。
松山まではあと10キロ程だ。快調にとばす、あっというまに松山についてしまった。松山では見たい所がいっぱいあるのだが、今日中に広島へ渡ってしまいたいため、松山港へと急ぐ。徳島へ渡るときのようにフェリーの時間にづれなければよいが、と思いながらペダルを踏んだ。港についたとき、フェリーはすでについていて、もうすぐ出るとのこと、あわてて切符を買い船に乗り込んだ。船の上から四国の山々を見つめた。いよいよこれで四国ともお別れだ。又新しい1つの思い出を、この地に残すことになった。船がゆっくり岸壁を離れてゆく。
畳の上に寝ころがり、今度はいつ来るだろうと考えていた。近くに外人の家族連れがいる。だんならしき男が英語を話しかけてくる。早くしゃべるので意味が分からない、すると一緒に旅行しているという日本人が、
「何をしているのか?」
と聞いていますよと教えてくれた。
「自転車旅行をしていると言って下さい」
この時、なぜかサイクリングと言わなかったのは後で不思議な気がした。
「1人で?」
これには私も分かった。
「イエース」
「オオ、、、」
何を言ったのか分らない。この後、外人だんなはそばで麻雀をやっているのを後からのぞきこんで、さかんにうなづいている。
「あの人、麻雀分かるんですか?」
「いえ、少しは知ってしますがね。教えろ、教えろとうるさいんですよ。」
「へえ」
ちょっと疲れたようだ、このへんで少し眠るとしようか。これからもまだ旅はつづくんだ。フェリーは、白波をけたてて広島へと向かっていた。
編集雑感 – 中山
編集雑感
蝉の声はいつしか聞こえなくなり、夜には虫の音が、涼しさを漂よわせる季節となった。
今回は例年になく、原稿の集まりの悪かったことが非常に残念だ。今年になって「峠」是非論なるものが、クラブの中で論ぜられるようになったのは、ある意味で大きな集穫ではなかったろうか。クラプ会計の中で「峠」の発行のための費用が大きなウェイトを占め、各社の援助金なしでは、到底、製作できないものとなっていることも確かだが、クラブ員の「峠」に対する認識の欠如というものが、大きな問題としてあげられるだろう。これは、クラブを運営する上級生に、大きな責任があると思われる。
現在、クラブ・ランの原稿は新入生に書いてもらうという立前になっているが、「峠」の性質、役割等を説明する機会ももたず、単に「書いておけ」では、新入生も面喰うのが当然だ。このことが何年も続けば、結果は明らかであろう。このことは、編集に直接携わっている私に大きな責任があると深く反省している。
次に「峠」の性質が変化してきていることが、第8号を読んでみて、おわかりになるだろう。2・3年前までは、クラブの活動の年間記録の集成としての役割が強かったが、近頃は、記録というよりも、クラブ員の主張の場といった感じが強くなってきている。しかし、これも限られたクラブ員によっているというのが現状である。
これから「峠」が、どのように変化してゆくかは、私には判断しかねるが、「峠」を製作するのは編集局である、という考え方は、すぐにでも捨てなければならないだろう。「与えられる機関誌」から「参加する機関誌」への変化が、行なわれなければならない。
第8号では、各自の提出した原稿枚数が多く、ページ数が重んだため、又第7号における、それが秀逸であったため、「切捨御免」は休むことにした。OB会員・現役クラブ員の名簿も載せないことにした。第9号が、すぐに発行されるであろうから、その点で御容赦願いたい。最後に広告集めに努力してくれた関口君にお礼を申し上げる。
そして「峠」に対して暖かい援助をさしのべて下さった高橋、東、中村、藤田、サンノー、アルプスの各社に対して深く感謝いたします。
(中山)
第8号峠
1971年10月1日発行
編集責任者
早稲田大学サイクリングクラブ
中山
Editor’s Note
1970年の出来事。昭和45年。
第12回日本レコード大賞 1970年 今日でお別れ 菅原洋一
3月。 日本万国博覧会(大阪万博)開幕(-9月)
日本航空機よど号ハイジャック事件発生。
4月。アポロ13号に事故発生。
6月。日米安全保障条約自動延長。
米軍、カンボジアから撤退完了。
7月。アスワンハイダム完成。
10月。ソルジェニーツィンのノーベル文学賞受賞
WCC夏合宿は、「 山陰地方 : 松江から – 京都まで」でした。
=====
こんにちは。WCC OB IT局藤原です。
峠8号には他にない特色があります。篠原先輩著「輪廻」、木村先輩著「眩暈」、吉田先輩著「閉鎖空間」。この3作はサイクリング紀行文ではなく、一種の小説であって、文字起こしは非常に困難でした。何とか完成したので公開いたします。
当時の文章をWEB化するにあたり、できるだけ当時の「雰囲気」を尊重するよう心掛けたつもりです。
文章と挿絵はPDF版より抜粋しました。レイアウト変更の都合で、半角英数字、漢数字表記等を変換していますが、全ての誤字脱字の責任は、編集担当の当方にあります。もし誤りありましたら、ご指摘をお願いします。
2025年2月、藤原
Copyright © 2025, WCCOB会