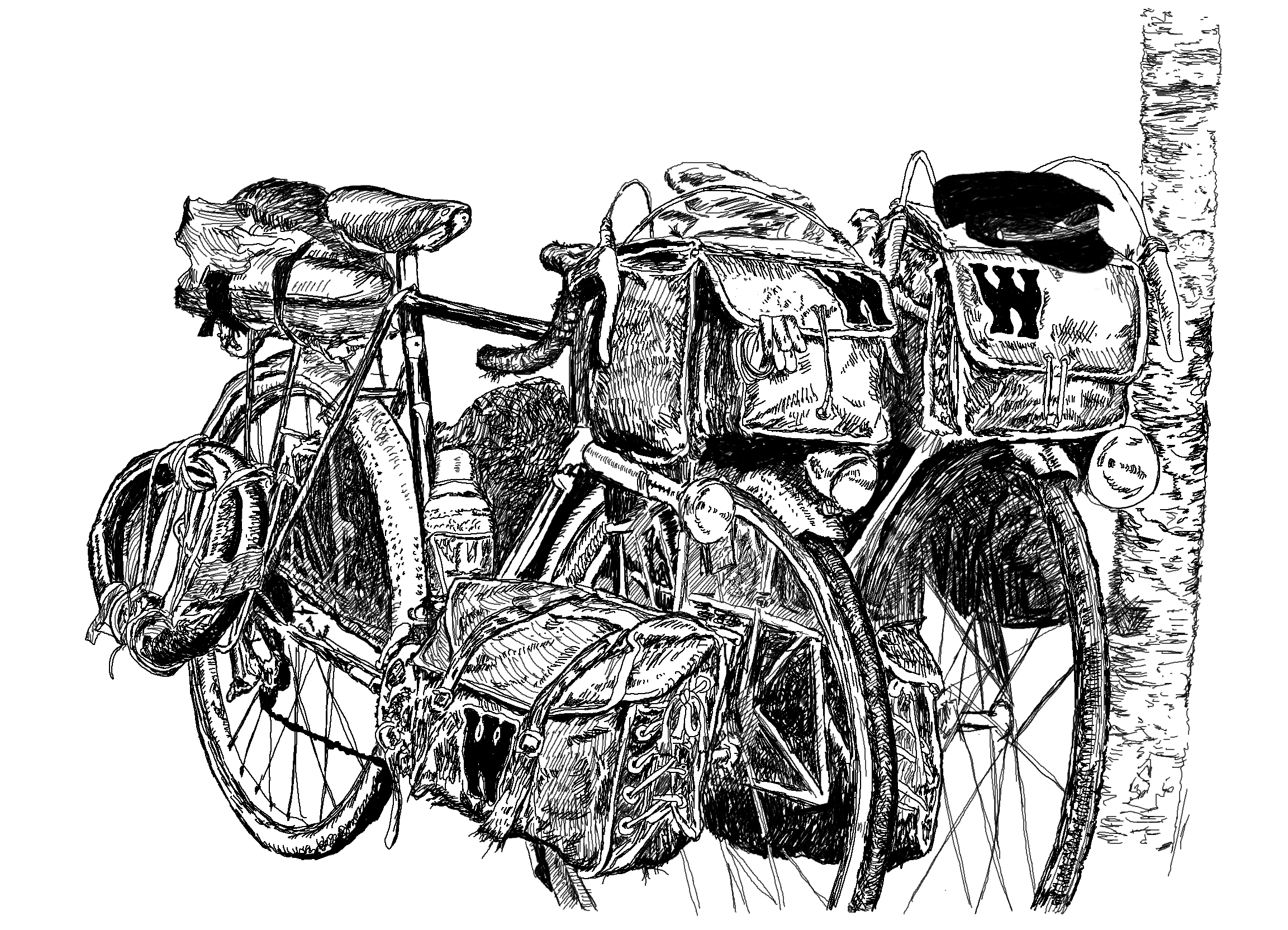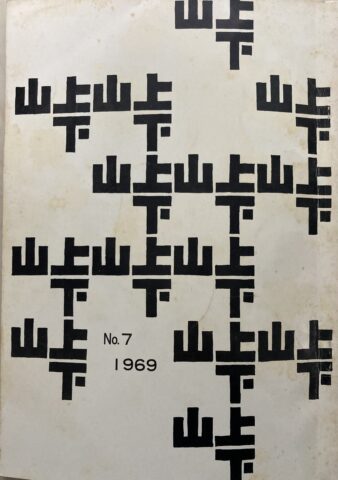
- 峠の詩
- 多目的のクラブ – 体育局助教授 上田会長
- 1969年度 夏合宿記録 東北 – 商学部3年 滝野
- 回顧録 – 法学部3年 篠原
- 1969年活動記録 – 法学部2年 保泉
- 新入生歓迎ラン – 政治経済学部1年 上原
- 山伏峠・正丸峠下見行 – 政治経済学部2年 仲田
- 早慶親睦サイクリング座談会 – 法学部2年 保泉
- 富士スバルライン・トライアル – 理工学部1年 土肥
- C140のこと – 法学部2年 堺
- 鎌北湖顔振峠 二年生企画ラン – 政経学部2年 宮崎
- 四年生追い出し 1年生企画ラン – 教育学部1年 砂子
- ドンキホーテ的主観主義 – 法学部2年 吉田
- さすらいの青春 – 教育学部3年 星
- 雨の七夕 東京-青森ひとり旅 – 政経学部2年 宮崎
- ハプニング – 法学部3年 小泉
- 地獄谷峠 – 法学部3年 篠原
- 京都レポート – 法学部2年 吉田
- 編集後記 – 滝野
- Editor’s Note
峠の詩
未知のものへの憧れと
ひとつの思い出のために
旅に出よう
若い命から吹き出る炎が
すべてを包みこむ
峠に立とう
人生喜劇の道化師に
あわれを感じたら
旅に出よう
太陽が大きく燃え
青空がまぶしく見える
峠に立とう
多目的のクラブ – 体育局助教授 上田会長
多目的のクラブ 新会長になって
体育局助教授 上田会長
縁あってサイクリング・クラブに関係することになってしまった。会長の役がつとまるかどうか不安ではあったが、幸い私の研究がスポーツ心理学であるので、クラブの世話をするというより、実践的な研究の1部だと思って引き受けることにした。
早稲田大学には、スポーツ関係の組織としては2つの系統がある。1つは、運動部として登録され、体育局が管掌しているものであり、他の1つは、クラブとして学生部に登録されているものである。この2つの関係についてみれば、部とは全く無関係にクラブが新設される場合もあるが、部員として活動していた人達が分離してクラブを設立した場合も少なくない。聞くところによると、わがサイクリング・クラブも後者に属するらしい。
それではなぜ新しいクラブを設立する必要があったのか。クラブを創立した先輩たちも、自転車に乗るという行為自体が嫌いであったはずはない。おそらく何のために自転車に乗るのか、その目的が既存の部と相入れなかったのではなかろうか。
ところが、今年の新入生歓迎会で学生諸君と話し合っている中で、わがクラブにも目的というか、好みがいくつかに分かれているように感じられた。もし好みを異にする人がごく少数であれば、クラブから脱落するという形で個人活動に移行するだろうし、ある人数に達すれば新しいクラブを設立することになるかも知れない。しかし私は、そのいずれも好きではない。できることならば、このクラブは、多目的の、毛色の変った人間を幅広く包含できるような、大きなクラブであって欲しいと思っている。
1969年度 夏合宿記録 東北 – 商学部3年 滝野
1969年度 夏合宿記録 東北
商学部3年 滝野
8月12日(火)晴れのち雨 2時青森駅集合
あたかも乙女の微笑みに引き寄せられるかのように、午後2時という時刻を目指して総勢35名の男たちが青森駅前に集合した。青森までのプライベートランで既に黒々と日焼けした者、人目を憚らず自転車を組み立てる者、整備する者、そういった者たちが、周囲の人々の目を引きつけずにおかなかったことは確かである。それほど異様な雰囲気をこの男たち、即ち早稲田大学サイクリングクラブの面々は持っていた。もしかすると、乙女の微笑は、いつしか苦笑に変わっていたかも知れない。
去年にひき続き、本年も35名という大所帯。これは、昨年同様クラブ員の合宿強制参加という措置によるものだが、こうした多人数のランは、それなりにプライベートランとは違った意味、意義をもつものと思われる。
1年生を除く大部分の者が、去年この青森の地を踏んでいる。各人がそれぞれの感慨を胸に秘めてキャンプ予定地、合浦公園へ向って予定よりやや遅れて出発した。合浦公園到着前に、ついにこらえ切れなくなったか雨が降り出した。ふと1昨年の合宿第一日目が想い出される。あの時も雨に祟られ、不安に心が重く沈んだものだった。その後は比較的晴天に恵まれ、いつしか不安はどこかに消し飛んでいたのだったが・・・やはりサイクリングは、快晴のもとで爽やかな汗をかくのがよい。
合浦公園では生憎とテント設営が許されず、雨足も激しくなってきたので、合浦スポーツハウスでお世話になることになり、そこの体育館を借用させていただいた。しかし、悪条件が重なったとはいえ、合宿初日から屋根の下で寝るというのは、嬉しいような寂しいような複雑な心境である。
ミーティングの時、主将より亜細亜大学の不幸な事故が報告された。サイクリングの最大の敵の1つは交通事故である。主将は、合宿中しつこいほど事故の恐ろしさを強調、そのおかげか、合宿中はたいした事故もなく無事終了、ほっと安堵の胸をなでおろした次第である。亜大の方々に対しては心からのお悔みを申し上げるが、故松本さんへの最高の供養は、私たちサイクリストが彼女の轍を踏まないことであろう。亜大の事故や雨などでずいぶんと湿っぽい初日となってしまったが、各人の気を引き締めたという意味においては、むしろよかったのかも知れない、と今にして思うのである。
8月13日(水)曇り時々晴れ
青森 – 蔦温泉46・5キロ
リーダー渡辺・砂子
雨は止んだが、爽快な青空というわけにはいかなかった。しかし約1ヶ月ぶりの本格的ツァーは、そんな憂鬱さを吹きとばしてあまりあるほど清々しい気分を与えてくれた。雲谷峠までは徐々に上ってはいたが、舗装路であったため快調に飛ばすことができた。しかし、雲谷峠を過ぎてから道が地道になると、急に1ヶ月のブランクが大きな重荷となって現われてきた。
前日の雨のため土が柔かすぎ、実に走りにくい。それに加えて何度も繰り返されるアップダウン。時々雨もパラついた。こんなにも容易く人間の心境とは変化するものであろうか。今朝のサイクリングへの讃美は、とっくにどこかへ失せてしまっていた。泥道といってもいいすぎではない地面をただ黙々と眺めながらペダルをものに憑かれたように踏むだけであった。距離に対しも時間に対しも全く感覚が無くなっていた。予定通り3時に蔦温泉に着いたのが不思議なくらいである。
蔦温泉付近はキャンプ禁止なので、1泊200円(風呂代込み)の宿らしきところに泊まった。合宿中は畳が懐かしくなるのであるが、ここの擦り切れた古い畳はかえって嫌悪感を、もよおす程であった。しかしさすがに温泉地、風呂だけは良かった。この風呂に加藤さんが時計を落としてしまうというハプニングが起った。加藤さんご自慢の防水時計であるが、その時計を誇らし気に自慢しているうちに、温泉の中に落として失くしてしまうといういかにも加藤さんらしい(?)失態であった。
8月14日(木)雨のち晴れ
蔦温泉 – 宇樽部キャンプ場24・6キロ
リーダー仲田・湯浅
出発間際になってまたもや雨がパラつき暗雲が胸を過ったが、信じられないほどの青空になり不安は消し飛んだ。その空の青さはなにもかも青く染めてしまうのではないかと思われるほどであった。
奥入瀬を写生する場合、青い絵の具を多く用意したほうがよいかもしれない。奥入瀬渓流に沿った雨上りの舗装路を走った時は、澄みきった爽やかな心の静けさと、変化に富んだ動いて止まぬ渓流の激しさが交りあって混沌として、一種の陶酔感にめまいを覚えるほどであった。
走行距離が最も少ない今日は、午後、各班毎にポタリングでゆったりと十和田湖、奥入瀬の景観を楽しんだ、各班の行動は次の如くである。
A班 奥入瀬渓流をハイキング&ハンティング
B班 宇樽部(船)→休屋→瞰湖台→宇樽部
C班 B班と同じ
D班 宇樽部→瞰湖台→休屋(船)→宇樽部
瞰湖台から見た十和田湖は素晴しかった。濃い藍色の静かな湖面は、一種の神秘さを持っているようで去年見た摩周湖を想わせた。だが、湖岸まで降りて見た十和田湖は、展望台からの神秘さは消え失せ、ただ、だだっ広いだけで岸に寄せる波もまるで海のそれのように激しかった。人も多すぎた。観光シーズンに、観光地に、観光客が多いのは当然かも知れない。しかし観光客のもつ雰囲気といったものは、その土地の自然にそぐわないものであることは確かである。こうした矛盾はいかんともし難いものであろうか。
ここ宇樽部キャンプ場で偶然出会った理科大サイクリングクラブと、交歓会を持つ。彼らは10数名と小じんまりとしており、僕たちと明確な対比をなしていた。
8月15日(金)晴れ
宇樽部 – 八幡平64·7キロ
リーダー中山・猪又
合宿3日目、まだ疲れはほとんど感じられず、爽やかな目覚めであった。昨日に続いて十和田の空は青く澄んでいた。
出発直後の瞰湖台までの上りは、昨日のポタリングで経験していたのでペース配分がうまくでき、きびしい上りの割には比較的楽に上れた。1度の経験がこんなにも2度目を楽にしてくれるとは思わなかった。休屋から十和田湖岸に沿った路を左に折れ、湖に背を向けた。十和田湖に後ろ髪を引かれながらも次の目的、発荷峠を目指して新たな気概に皆が燃えた。だが燃える必要はなかった。ほとんどトップで上れるほどの楽な上りで、まさに期待はずれといってよかった。自己の精神的、肉体的限界に挑もうと気を引き締めてかかる時は、実際にその行程が苦しければ苦しい程良い。その耐えられない程の苦しさが、挑戦後の充実感をより大きなものにしてくれるのだ。
十和田湖4大展望台の1つである発荷峠から十和田湖に最後の別れを告げ、峠をあとにした。発荷峠の下りは、今合宿中最高の素晴しさであったように思える。完全舗装、距離も長く、またまわりの風景を楽しめる余裕を持てるほど緩やかで、サイクリングの醍醐味ここに極まった感がした。
八幡平にはおかげで予定より1時間程早く着くことができた。今夜は風呂に入らなかった者はいなかったのではないだろうか。誰からともなく混浴だと言い伝えられると、1時はキャンプ地には誰も居なくなった程である。僕も早速風呂に行ったが、実際には混浴ではなかった。しかし、男湯と女湯とをしきる衝立は申し訳程度にあるだけで期待に違わなかった。某ホテルでトイレを借りたあと、町をぶらつくと盆踊りの練習をやっていた。大きな太鼓の拍子はなかなか力強くて雄大なものであったが、踊りは単調なので人々に加って一緒に踊ることができ、楽しい一時を過せた。
8月16日(土)曇りのち晴れ
八幡平 – 田沢湖65キロ
リーダー及川・土肥
炊事班のミスで前日買い入れておいた味噌汁用の豆腐を変質させてしまい、ほとんどの者は万一の場合を考えて味噌汁に手をつけなかった。そのせいか、全行程が地道である今日の疲労はかなりのものだった。地道を走ることはそれなりに楽しいものである。それどころか舗装路を走るより数段と面白いかも知れない。しかし、それにも程度というものがある。今日のように行けども行けども薄茶色のほこりっぽい細い道が帯のように眼前から遙かかなたにまで延びているような時は、いい加減舗装路が恋しくなるものである。
玉川温泉へは丁度正午頃着いたが、800mという高度と山中ということのためか、とても夏とは思えないほど涼しすぎた。この玉川温泉は、合宿前に仕入れた知識どおり一種の異様な雰囲気をかもし出していた。
玉川温泉から田沢湖までは再び地道の繰り返し、食傷気味のところへ舗装路が現われた時は感激で全身がうち震えた程であった。
キャンプ予定地の田沢湖国鉄キャンプ場が満員で他のキャンプ地を捜すのに時間がかかった。おまけに水道がないので、炊事には川の水を使うなど手間を要した。その結果、食事時は暗闇の中、ローソクや懐中電灯の光を頼りに食事を取った。また食事中、自動車の襲来(食事場所として道路を占領していた)に皆は、各自の食器を持って逃げまわるというおまけまでついた。
尚、主将は出発早々方向を間違えてしまい、岩手県に入るまで気付かなかったという失態を演じた。勿論、主将である篠原君に言わせれば「岩手に足を踏み入れたのは俺1人だけだ」という奇妙な自慢話になってしまうのだが・・・。
8月17日(日)晴れ
田沢湖 – 横手62・6キロ
リーダー堺・藤井
湖底からの湧水が主だという田沢湖の水は、清楚なルリ色を保っておりさすがに美しかった。が、惜しむらくは、湖畔の風景が変化に乏しく単調で、ハッと思わせるようなアクセントとなるポインが見当らず、それが故に湖の魅力を半減していることであった。
昨日の延々と続いた地道のせいで疲労が思ったより残ったのか、今日は景色を楽しむ余裕もなく、国道105号線、13号線を単に走ったという感じしか残らなかった。
しかし、横手公園の1部で冬はスキー場になるこのキャンプ地に、秋田にお勤めのOBである菅原さんがわざわざ訪ねて来て下さり、楽しい一時を過ごすことができた。
夜、そろそろ眠りに落ちんとする時、「テントが燃えている!」との大声で驚愕と共に目を覚ましてしまった。幸い大事に至らずに済んだが、どうやら明りのローソクの炎が原因らしい。気が緩んできた証拠か。
8月18日(月)曇りのち晴れ
横手 – 鷹ノ湯温泉
リーダー丸山
炊事班の皆さん、ご苦労さんでした。炊事に欠かすことのできない水がでなくなってしまって、さぞ苦心されたことと思います。僕たちがいつもと変らぬ朝食をとれたことに対して、心からの感謝の意を表します。
昨晩のようなハプニングを起こす程ダレてきた部員の気持を引き締めるのに、このキャンプ地は最適であった。トレ・マネの渡辺君は、心の中で秘かにほくそ笑んだに違いない。まさに山あり谷あり、おまけに池まであった。それらの間を縦横無尽のランニングは、僕に全精力を使い果たさせてしまった。厳しいトレーニングは気持を引き締めるのに役立つとは思うが、ある限界を越えるとかえって、注意力を散漫にしてしまい、逆効果だと思うのだが・・・どうだろう、渡辺君?
朝食後出発までの間、精力の使い道に困っている者が数人、キャンプ地脇の小高い山の征服への可能性の追究を試みたが、さすがにその急勾配を走破できるものはいなかった。
曇り空の隙間からこぼれていた日の光が、やがて雲を追い散らしてしまった。舗装路は快適であった。湧き出る汗が快い。車量も少くピッチは上がる。雄勝峠までの距離を示す道路標識は完全に無視、何故なら峠の手前で進路を左に折ることを知っていたから。ピッチはますます上がる。だが、班毎の隊列は1糸も乱れず、後部から見ると30数名のサイクリストの整然と走る様は壮大(早大と掛けた洒落)であった。
途中、小野小町塚に寄る。絶世の美女と謳われた彼女だが、僕の可愛い子チャンと比較してみた。結論は言わずもがな、である。
キャンプ予定地鷹ノ湯では、運良くホテルを経営されている早稲田出身の方が、そのホテルの傍の素晴しいキャンプ地を提供して下さった。また、そこには早大法学部某教授が宿泊されており、法学部の諸君はその教授のお話を承まわった。また、キャンプ地の傍に泳げるところがあり、皆勇んで泳ぎに行ったが、水が冷たすぎ、ほうほうの体で逃げ帰ってきた。ラジオでは、例の太田投手の活躍を知らせる高校野球の決勝戦を放送していた。
明日はいよいよ鬼首峠にアタックである。静かな虫の声を聞きながら、いつしか眠りに落ちた。
8月19日(火)晴れ
鷹ノ湯温泉 – 鳴子41・5キロ
リーダー高橋・名田
東京を離れて旅行する場合、最も強く残る印象の1つに空の青さがあるのではなかろうか。ここ鷹ノ湯の空も東京では見ることのできないほどの青さを湛えていた。
ホテルのご主人、早大教授を囲んで記念写真を撮ったあと、鬼首峠へと1歩を踏み出した。東北とは言え夏なのでさすがに暑い。木陰に入った時の心に広がる安堵感は言い知れぬものがある。
舗装が切れてからはなお一層、前の自転車の後輪を見つめ、1歩1歩確実に踏みしめながら進む。心はいつしか峠への不安で占領されている。
赤倉橋からは合宿初めてのフリーランになった。峠まで距離にして4 – 5キロなので、たいしたことはない、と心に言い聞かせようとするが、延々と続く上り坂を見るとやはり不安感は増すばかりであった。だが、一旦上り始めるとそんなことは言っていられない。
「絶対に降りるもんか、休むもんか」という負けん気が、むらむらと心に湧き起こる。峠へは、この負けん気で遮二無二挑戦するようなものである。この負けん気に対する強敵は坐折感である。期待に反するような事態が生じた場合、忽ちにして坐折憾が負けん気を凌駕してしまうことになる。この鬼首峠もそうであった。元来、トンネルの存在は峠の頂上を示すものと思っていた。しかしこの峠の場合、トンネルは頂上に至るまでの単なる道程の1つでしかなかった。
そのことを思い知らされた時の気持は筆舌に尽くし難い。また、ある程度進むと、道の勾配度がだいたい見当つくものであるが、この峠の頂上直前の想像を絶する急勾配は、車に乗った女の子からの声援を受け入れるどころではなかった。しかし、幸いにして僕は、こういった坐折感に打ち勝って頂上に立つことができた。その時の満足感、充実感は、ファンタ1本70円をも大した高額とは思わせなかったのである。
尚、頂上へは小川君とほとんど同時にゴールインしたが、彼は自分の勝利を主張して譲らない。僕は、僕が先にゴールインしたことを信じて疑わないが、彼が僕に勝ったと思うことによって少しでも優越感を味わいたいのならば、小川よ、僕は喜んでおまえに勝ちを譲ろう。
峠から鳴子までの下りは、舗装路のあい間にちょくちょく地道が顔を出したが、仙秋サンラインという名が生みだすイメージに違わず快適なものであった。しかし、このたいして走りにくいとも思われぬ下りで、吉田君が転倒してしまった。日頃の彼の悟りきったような顔を知っている僕は、いまにも泣き出しそうな顔をしながら、僕の治療を受けている彼を見ては、笑いのこみあげてくるのをおさえることができなかった。下り切ったところで突如として眼前に開けた鳴子の町並は、いかにも温泉地といった風貌を湛えていた。けばけばしい装飾にむせかえるような鳴子の細い街路を通り抜け「尿前の関跡」を右手後に見過ごしながらキャンプ地に到着、町とは対照的に静かな落ち着いた場所であった。
ここ鳴子のキャンプでは、「ホテル鳴子峡」が、そこの支配人の息子が早稲田に在学中という好誼から風呂を借して下さるというご好意を示してくれた。しゃれたホテルでの清潔な風呂は旅の疲れを癒してくれるのに充分だった。夕食後、全員で分担してOB諸氏に残暑御見舞を書く。
昨晩にも増した静けさに、なにか物寂しいせつない想いに浸る。
8月20日(水)晴れ
鳴子 – 天童72キロ
リーダー吉田・関口
人間とは旅にでると必要以上に感傷的になるのであろうか。僕なんぞ、なんでもない野辺に咲く花や澄んだ湧水に、無闇やたらと胸を打たれることが多いのである。しかし、朝のトレーニングの合間に、川底近くまで降りてみた温泉の15mぐらい吹き上げている様に感嘆したのは単なる旅先の感傷ではなかった。
山刀伐峠までは、またもや地道であったが昨日の鬼首峠に比べると格段の差があった。勿論、山刀伐峠のほうが楽なのである。なにしろ6キロで170mの登りしかないのであるから。峠では芭蕉の歌碑を見に行く。しかし何と詠んでいるのか皆目見当がつかない。クラブ員諸氏、しきりに感心していたが、それはその俳句に詠まれている心にではなく、その句を記した達筆に対してであったに違いない。
峠を下った尾花沢から天童までは、何の変哲もない国道13号線をまっしぐら、脇目も振らずにペダルを踏むだけであったが、天童市内に入るとさすがに将棋の駒の町、駒を形どった看板や飾りがいたる所に目立ち、つい目がそちらへと奪われてしまった。
夕食に遅れた者に打ち上げコンパのあとの食器洗いを命じた。合宿もはや後半に入り、中だるみの感じが現われており、全員の気を締める意味からである。
夕食後の自由時間に近くの旅館へ風呂に行く。なんでもこの旅館は、かって心中がありそれ以来客が寄りつかなくなったという噂であったが、噂どおり寂れた暗い旅館であった。そこのおばさんの愛想のよさもかえって不気味さを増すだけであった。またこの自由時間に、例の小屋へ直行し、かぶりつきで涎を垂らしてきた者もいたそうである。10日弱の禁欲生活を強いられて、無理もないとは思うが…明日は大丈夫だろうか?尚、保泉君が軽い食あたりを起こし、明日のリーダーを堺君と代わることになった。
8月21日(木)晴れ
天童 – 小野川77・3キロ
リーダー堺・田中
今日まで奮闘してきた田添君が、都合により合宿を終えることになった。どうもご苦労さんでした。
この旅は合宿であり観光地巡りではないので、ほとんど名所、旧跡などは訪れてこなかったが、今日は、芭蕉の「閑けさや岩にしみ入る蝉の声」で有名な立石寺に寄った。そこでまず感じたことは、この寺もやはり俗化されてしまっていて昔の面影など偲ぶ余地がなかったということだった。派手に品物を揃えた土産屋が多くの軒を並らべ、寺には何の関心もない、ただ他人が行くからといった理由だけでここを訪れた観光客に眼を光らせていた。そんな雰囲気に反撥を感じながらも、店員につられて土産を買ってしまった僕は、土産屋から見れば他の観光客と何ら変わるところのない単なる獲物でしかなかったのであろう。
山形からは再び国道13号線に戻って米沢まで直行、山形市はこれまで通ってきたどの町よりも活気に溢れており東北から浮かぶイメージとは裏腹に明かるかった。
米沢で適当なキャンプ地が見つからずまごまごしている所へ、米沢日報社の記者が媚びを売るように我々に接近してきて、副将である小泉君を引っぱっていってしまった。後日、クラブに送られてきた米沢日報を読んだところ、小泉君は「ダーウィンの進化論云々」と大見栄を切ったらしく皆で苦笑した。それにしても、米沢では集団サイクリングですら記事になるとは・・・でも考えようによっては、こんなことが記事になるくらいが良いのかも知れない。
キャンプ地は米沢より更に7キロほども行った小野川に決定。
8月22日(金)晴れ
小野川 – 檜原湖キャンプ場46キロ
リーダー宮崎・里見
いよいよ本合宿のクライマックスである西吾妻スカイバレーへの挑戦である。ここで保泉君が天童での食当りが原因でリタイアしたのは残念であった。
フリーランを始める白布温泉までは、班毎に隊列を組んで進んだが、もう峠にさしかかっているのではないかと思われる程厳しい上りであった。白布温泉では、連絡場所となっている「あづまユースホステル」へ手紙を受け取りに行く。手紙を受け取ったクラブ員にとって、それは峠挑戦への力強き心の支えとなったことであろう。
各人それぞれ水や食料を充分に補給し、いよいよ大自然への精一杯の抵抗に向かった。僕は2番目にスタート。初めから相当の厳しさ、初めの気負いはどこへやら、肉体的疲労に先んじて精神的疲労が襲ってくる。忽ちにして小泉君に抜かれ、落海さん、田中君に追いつかれる。暫く3人でグループを作って走る。否、これが走るといえようか?歩く方がよっぽど速そうである。細かい砂利が、ペダルにかけた力を吸い取ってしまう。車輪がスリップして思うように前に進まない。
観光案内書にこう書いてあったのを想い出す。この西吾妻スカイバレーは昭和34年、難工事の末、4年の歳月を費して完成したと。完成?冗談じゃない。これが完成だなんて。ただ山を切り崩して砂利をバラまいただけではないか。流れる汗を拭う余裕もない。苦しさを紛らわそうと女の子の事でも考えようと思うがとしも無理。今疑問と思うに、走っている時はどんなことを考えていたのであろうか?一体何回ぐらい休憩をしただろう。峠から降りてきた車に、頂上までどれくらいかと尋ねる。尋ねなければよかった。まだ半分しかきていないと知ってショックで失神しそう。
後を振り返ると吉田君が僕たちに迫ってくる。彼だけには負けてはならぬと気を取り直して再び前進。足よりも胸が苦しい。ゼイゼイと口で激しく呼吸しながらペダルに全体重をかける。いつの間にか、田中君が遅れはじめ落海さんに離され始める。1人で走ることの苦しさよ!汗がサングラスにかかり前が見えなくなる。それを口実に自転車を投げ出す。時たま、フッと自転車が軽くなる時がある。確かに昇っているのだが、そう感じるのは、それまでの勾配に比べると楽だからであろう。それほどこのスカイバレーは、激しい勾配が続くのである。フト顔を上げて前方を見る。道は急角度で左に折れており、あたかもそこで行き止まりの感じ。その背景には紺碧の空以外なにものも視界に入らない。素晴しい光景。まさに一服の清涼剤を飲む思いであった。
峠までタップリ1時間半はかかった。峠に立った時の感激は改めて書くまでもないだろう。サイクリストなら誰でも1度ぐらい経験しているはずであろうから。
檜原湖キャンプ場は、峠への激しい挑戦をまるで夢の如く甘い思い出にしてしまうほど広々とした静かな美しい場所であった。しかし、夏とは思えぬほど寒く、空には雲が激しく流れている。台風が接近しているという。合宿もあと一日、これまで大過なく経てきたが、明日が心配される。無事に終わってくれることを祈りながら眠りに落ちた。
8月23日(土)曇りのち豪雨
檜原湖キャンプ場 – 会津若松50キロ
リーダー三輪・石川
予期したとおり厚い雲の垂れ下がる空の下で冷たい強風に身を晒さねばならなかった。台風が予定進路を忠実に守っていることが解る。疲労した身体に勝手なことを言わせている暇はなかった。皆てきぱきと自己の義務を果し、一路会津若松へ。幸い猪苗代へ到着するまでは、雨は時々パラついただけ、小野川湖、五色沼、秋元湖巡りをカットした甲斐はあった。
しかし、野口英世記念館を出た時、雨はもう待っていてはくれなかった。雨のシャワーを浴びながら目的地を目指す。猪苗代湖の水は、灰色と緑色を混ぜ合わせたような不気味な色相を呈していた。強風に引き起こされた激しい波のしぶきも白くはなかった。湖岸の道路は、湖岸であるが故になお一層風が強かった。時折右手前方より突風に襲われる。平衡を保とうと重心を右にかけたとたん、突風は過ぎ去り、自転車と共に勢い余って大きくセンターライン近くまでよろける。
幸い車量が少なく、事故を起こすことはなかったが、その前進する様は、酔払ったカニの如く、よたよたとS字型であったに違いない。湖を背中越しに見はるかすころから道路は下り始め、それが会津若松まで続いた。晴天ならば、否、少なくとも風雨がなければ快適であろうと思われるこのダウンヒルも、今日のような日には恐怖心が胸に吹き込むだけであった。ほとんど役目を果たさなくなったブレーキの代わりに、片足を道路につけなければならなかった。そうしなければ、加速度でスピードはどんどん増していき、その結果、僕は天国(地獄?)へ直行していたに違いなかった。
幸いにして、事故もなく全員無事に会津若松に到着した。時間にして僅か3時間足らずの行程だったとは信じられないほど疲労を感じた。最終目的地に着いたという感激が少しも湧いてこない。恒例の主将、副将の胴上げも行なう雰囲気ではなかった。キャンプは不可能なので、駅に近い旅館兼予備校に泊まることになった。余談ではあるが、ここ会津若松では高校進学のための中学浪人がいるという。アッと驚くタメゴーロォー。
旅館に落ち着いてから総合ミーティングが行なわれた。なにはともかく、マクロ的視野に立てば、今合宿は成功裡に終了したと言えよう。であるのに、活発な意見が出ず沈んだムードになってしまったのは、強風、豪雨をついて強行したことを思い起こし、それに対して各人が、自己満足に酔っていたのか、それとも改めて恐怖に震えていたのか、のどちらかであったのだろう。そんな憂を晴らすが如く、打ち上げコンパは乱れに乱れ、深夜まで狂宴は繰りひろげられた。その異様ともいえる光景は、いかなフォークナーでも適確に描写することはできなかったであろう。
8月24日(日)晴れ 10時会津若松解散
雨上りの街は、2日酔いの眼にはまぶしすぎた。全員で前夜の狂態の証拠を葬りさるため、しつこいほど掃除を繰り返した。
器材を送り終わり、公務を終えたところで会津若松駅前で記念写真を撮ったが、今、その写真を見てみると、皆空虚な顔をしている。やはり依然として、頭はもうろうとしていたのであろう。合宿終了に対する何らの感想も感じられなかったのは当然だったのかも知れない。しかし、そんな精神状態ではあったが、別れにつきまとう一種の寂しさはやはり感じてしまった。汽車に乗り込む者、東京まで走る者。だんだんと消えて行く仲間を見ていると空虚な沈んだ気持に落ち込んでいくのをどうすることもできなかった。
皆さん。どうもご苦労さん。今度は学校で元気な日乗けした顔を見せ合おう!
回顧録 – 法学部3年 篠原
回顧録
法学部3年 篠原
昨年の2年生会で、その年の反省と今年度の方針等を話し合い、主将をやることに内定して以来、きょうに至るまで、私の頭の中にはいつもクラブがあり、何をするにつけてもクラブの主将という気持があった。時にはそれを誇りに思い、ある時にはそれが非常なる束縛であると感じつつも、1年間がまたたく間に過ぎてしまった。
来年度の運営委員が決定した今、この1年間を振り返り、自分の足跡を思い出してみて、当初の方針とその結果がいささか違うのを否めないのが、非常に残念である。
まず、今年は従来クラブ・ランを毎週行なっていたのを改め、原則として隔週ごとにすることにし、それと共に1回ごとのランを充実させるために、1泊ないし2泊でこれを行ない、クラブ員全員が参加するという方針を立てた。これにより、毎週日帰りランをやるよりも、企画面で充実したランができたことは確かである。また、昨年はあまりにも対話が少なかったというので、特別なグループ・ミーティングを設け、クラブ各員の意志の疎通を計るつもりであった。今は「であった」としか言えない。なぜならば、実質的にこのG・Mが行なわれたのは、最初の1、2回だけであったからである
また、役員の負担が大きすぎるということで、規約通りに局長の下に数名の局員をおき、各局ごとに有機的な活動ができるようにしたが、この点、局員がよくその責務を果たしてくれ、クラブ運営方法のひとつの型を、曲がりなりにも形成したように思う。しかし、やっぱり1部の者には、全て役員任せきりという傍観者的態度が見られ残念であった。
ともあれ、私自身としては、全ての局長の上に立つというよりも、むしろ各局の和の中心的存在として自分を位置づけ、その態度を年間通じて持続したつもりでいる。それは、即ち、私の人となりであり、歴代主将のように先頭に立ち、クラブを引っ張って行くには、肉体的、精神的未熟さがあり、力量不足なので、自分をそのように位置づけざるを得なかったのである。この点、諸先輩に対して大いにお詫びしなければならないと思う。しかし、私は自分なりにベストを尽したつもりである。多少、弁解めいてきたが、年間活動を主将としての立場から振り返ってみよう。
まず、私がぶつかった最初の、実に面倒な問題は、女性問題だった。女性問題といっても、そこらの週刊誌にある妖艶な話ではなく、まさに男性と女性の違いという人間関係の根元的、かつ単純にみえて最も複雑な問題であった。というのは、ある女性がサイクリングをやりたいという理由で―これは、我がクラブに入部するには必要かつ十分な理由であるが―入部を希望してきた。我々は年間活動予定表を見せて、女性には無理だと説明し、例え、あなたが入部してもこの計画は変更するつもりはないし、特別にあなたのためにクラブ・ランを設けるつもりはないと断言するに至って、彼女は泣き出してしまった。この時、私は彼女がどの程度クラブ活動をできるかということよりも、女性が1人入って従来の男だけの良さを壊されることを恐れた。はっきり言って、サイクリングをやりたいという女性を入部させない正当性を我々は持たない。なぜ女性を拒否しなければならないのか?単にそれが伝統であってもだ。
しかしながら、私は断固として女性の入部を拒否した。のみならず、規約を改正し、「男子学生に限る」と付け加えた。なぜならば、私は「男だけの世界」を守りたかったからである。合宿、早同交歓会、コンパ等を筆頭にして、我がクラブの活動はすべて男だけという前提に立っている。いや、これはどうにでもなる問題かも知れない。エスカや西サ連を見ても、女性のいないクラブは少なくなっている。今や女性を拒否するということは、時代錯誤かも知れない。しかしながら、私は女性を1人入部させることにより、クラブ運営上に被る損失の方が大きいように思えた。これは、損得といった利害関係で考える問題ではないかも知れない。少なくとも、今年は女性を入れないことにしたが、これが最上の策だとは決して思っていない。
新入生歓迎ランは、2泊3日で相模湖、ヤビツ峠方面へ行った。参加者が40名にも及び、また、4年生にはほぼ全員に近く参加していただき、ランの雰囲気を盛り上げてもらった。しかも、これは年間のクラブ・ランを通じて言えることで、この点、4年生諸兄には大いに感謝すべきであろう。私個人としては、この歓迎ランが待ち遠しくてたまらなかった。3月のプライベート・ラン以後、自転車に乗っていなかったことと、サイクリング日和というのがあれば、多分そのせいであろう。とにかく、この歓迎ランは楽しかった。
前期の活動は、この後、秩父山岳ラン(途中大雨で中止)、第3回早慶親睦ラン(柳沢峠)、富士スバルライン・トライアルと私自身にとってもかなり厳しいランをやり、合宿に臨んだつもりである。
合宿は、東北地方縦走に決定していたが、大学紛争の影響で、コースが全く逆になり、青森集合ということになった。今合宿は、私にとって楽しみのない、その意味では、最もつまらない苦しいツァーであったが、まずは大した事故もなく終えたことを素直に喜びたい。ただひとつ気になったのは、肉体的に事故を起こす者が多かったことである。食あたりをしたり、下痢をしたりで、個人の摂生の悪さが目立った。来年からは、是非とも合宿の前に、参加者の健康診断を義務づけるようにする必要があると思う。また、今合宿では意識的にいわゆる「対話」を充実させたつもりである。夕食後のミーティングは、毎日平均1時間前後を費した。単にその日の反省、翌日の予定を述べるだけにとどまらず、各自のサイクリング観、人生観といったものまで出て、非常に有意義であったと思う。
後期になってからも、紛争が尾をひき、クラブの統制がとりにくかったのは事実だが、とにかく、昨年より始められた戸田橋 – 軽井沢タイム・トライアル、第6回早同交歓会だけは絶対に行なおうと思っていた。前者については、木村(淳)さんが空前絶後の記録を出し、後者においても、晩秋の京都に両校の参加者65名を集め、まことに盛大に行なわれた。この後、多分に同志社大学の影響を受けたクラブ・ランをやり、4年生追い出しランで本年度のクラブ・ランを締めくくった。
総括的な意味でこの1年間を振り返ると、歴代の主将が何か新しいことを始めたのに対し、私は新しいことをやるどころか、それまで毎年行なわれてきたオープン・サイクリングを中止さえした。これは大学が紛争中であり、かつエスカ構成一員のあるクラブが死亡事故を起こしたので、新聞で募るなどという大々的に行なうことに一種の後ろめたさを感じたからである。また、クラブ・ランに関しては、年間を通じて1泊ないしは2泊で行なってきたが、この際問題になるのが、土曜日に授業のある者への配慮であろう。クラブ・ランに出ることは、即ち、授業をさぼるということになり、ひいては、クラブか授業かといった個人的な問題になるわけではあるが、クラブとしては、積極的にその者達への配慮をする必要があったのではないかと思う。
なお、我がクラブの会長として、長い間ご助力いただいた清原先生が、他クラブとの兼ね合いから、会長の座をご辞退され、代わりに良き会長として、上田先生をご紹介して下さった。清原先生に深く感謝すると共に、上田先生には、これから何卒よろしくお願いする次第であります。
最後に、未熟な私が無事に主将という大任を果たせたのも、副将の小泉、保泉両君をはじめ、諸役員の協力のおかげだと深謝し、筆を置くことにする。
1969年活動記録 – 法学部2年 保泉
1969年活動記録
法学部2年 保泉
4月18日
今年度の活動状況を振返って、資料局の方から報告したいと思う。今年は、全国的に学園紛争が吹き荒れ、休火山といわれていた早稲田も、前期半ば頃から各学部に紛争のきざしが見え始め、7月に入ると学校当局によるロックアウトまでエスカレートするに至った。
以上の様な状態を経過したために、一部連絡の困難が生じ、徹底さを欠く面もあったが、前期3回、後期5回のクラブ・ランを企画できた。前年と比べて月2回とランは減りこそしたが、この8回のランはより充実していて、有意義なものになったと思う。恒例行事である早同交歓会も、両校共に紛争状態にあったが、同志社の熱意と早稲田側の協力のもとに、無事終ることができた。合宿も大きな事故もなく、無事、東北縦走を成し遂げることができた。
今年、残念なことは、亜細亜大学の女性サイクリストが坂を下る途中バスと接触し、一命を落したことである。今後、観光ブームの波に乗って、観光地に押し寄せるパスやマイカーが増えることだろうが、このような波をぬって走るサイクリストには一層高度な技術、敏速な判断が要求されてくるであろう。我々の連盟から1人死者を出したことは、後で検討の余地があろう。
では、わがクラスのこの1年間の活動を振り返ってみよう。
4月18日 新入生歓迎コンパ、参加者37名
初めのうちは、新入生はキョトンとして、暴れ回る先輩達を尊敬の眼差しで見つめていたが、酒もそろそろ頭の方へ上るにつれて、やがて、本性を現わし始めた。酒の美味さを初めて知ったのか、涙を流す者や喉の奥の方からうがいでもするように酒以外のものを「やぶき」に吐き捨てていく者もいた。頼もしいやからである。最後に全員肩を組み「都の西北」を合唱し、夜の巷に消えて行った。コンパの初めに、去年の北海道合宿のカラーフィルム『ドキュメンタリー、早稲田の男―北海道を行く銀輪隊』というたいへん長い題の映画を見せた。これは恐らく新入生諸君のサイクリングへの興味、醍醐味、爽快さを一層、奮い起たせたことだろう。新入生諸君!さあついてきてくれ、一緒にペダルを踏もう。
5月3,4,5日 新入生歓迎ラン(相模湖、ヤビツ峠方面)、参加者39名
大隈講堂前に9時半集合。空は絶好のサイクリング日和。新入生の真新しい自転車が非常に印象的である。どの顔も楽しさであふれている。トレーニングの後、10時ちょうどに相模湖へ向けて出発した。小生がこの日のリーダーに指名されて先頭を走ることになった。新宿より既に何回も走ったことのある、あの悪名高い排気ガスのトンネル – 甲州街道を一路西へ西へと向った。去年の自分を顧みると、この日の新入生の気持ちが非常によくわかるような気がする。
八王子を過ぎてガードをくぐるとすぐ左へカーブしながら、だらだらと上る坂があるが、これが今日の最初の肉体的爆発力、測定自己判断基準ポイントである。この地点は誰しも体の1部に克明なメモをとっていることだろう。あなたは如何かな?高尾の駅から大垂水峠の頂上までフリーランになっていたため、全員鋭気を養うために、高尾駅で休みをとった。各自適当に腹に食べ物をつめ込み、先輩達はこれからの峠の様子を触れて回っていた。この峠は毎年新入生歓迎ランに組み込まれているとのこと。恐らく来年もまた通ることだろう。
1時間近く休んだ後、1年生を先頭にして初日のメインエベントに向かった。休日のため車が非常に多くて、光輝なるサイクリストを排気ガスと共に路肩へ追いやってしまうのには、今さらながら閉口した。
2年生以上は、ここぞとばかり軽快に上って行き「どうだ、先輩とはこんなもんだ」といわんばかりだった。対照的に1年生は顔を真赤に染め、玉のような汗を背負ってアタックを試みた。かなり差はついたが全員上り切ることができた。今度は一気にダウンヒルを楽しみながら、湖畔キャンプ場へ向って下っていった。
3時頃第一日目の目的地に到着した。2年生以上は、食料買い出しや、テント張り、飯つくりに奔走し、新入生を「一日だけ」の暇人にさせておいた。テントに寝るのは初めての連中もいるとか、まあそのうちゆっくりと、懇切丁寧にテントの張り方、たたみ方を教えてやるから楽しみに待っててくれよ。
飯を口いっぱいにほうばり皆楽しそうだった。ミーティングでは、大垂水峠のことが例年どうり話題になった。5月初旬とはいいながら、夜ともなると寒さが俺達のテント村を包囲した。各自テントに入りエロエロな話に花を咲かせた。
目が覚めた。2日目も快晴で、早朝の湖水に霧が重たく、ゆったりと浮かび、太陽の光が霧のわずかな隙間から先を争って我々に対話を申し込んでいた。さあ今日も張り切って行こう。
朝食を済ませ、装備を整える頃には真夏とも思われるような光が俺達の出発を促した。途中の新宿という所から3人1組になりヤビツ峠に挑んだ。道は狭くなり、勾配も激しくなってきた。中津川には都会の騒音をのがれて、車でやってくる夢も希望もない(一見そのように見える)エコノミックアニマル達が大勢繰出していた。木々の緑も目にしみるようだ。札掛あたりから隘路も著しく、車とすれ違う度にヒヤヒヤした。急にぞろぞろ人影が現われ、誰の声だとはっきり解る地点まで来たとき急に足が軽くなった。案の上、黄色のユニフォームがチラチラ見えだした。峠でのサイダーの味は格別だ。1年生も落伍することなく皆よく頑張った。写真機に群らがり、醜い顔をさらすことは、相も変らず我がクラブの光景である。全員揃ってから峠を後にして、ガタガタ道を下った。途中の舗装路の快適さは、また抜群であった。
2日目のキャンプ地である秦野には5時頃着いた。中学校の御厚意により、水道を使わせて貰い飯の準備にとりかかった。河原にテントを張った。近くに銭湯があったので2日間の汗を流した。わざわざ風呂まで食器を持ち込んで洗った者もいたが、余り感心できない。その夜は皆ぐっすりと眠れたことだろう。加藤さんは8時頃、東京まで帰るといって懐中電灯を片手に厚木街道を暗闇の中へ消えていった。
3日目は、少し疲れた様子も、1年生の中には見うけられたが、しかしサイクリングの楽しみというものを身をもって感じているようにもとれた。班ごとにまとまって、凸凹の激しい厚木街道を一路、二子橋までペダルを踏んだ。まったくこの道は何とも言いようがない…?ともかく3時には全員無事到着した。
3日間とも快晴に恵まれ歓迎ランとしては、非常に楽しめるコースであった。
1年生はサイクリングの醍醐味がおわかりになりましたかな?
二子橋で解散し、各自思い思いの記録をフロントバッグにつめ、3日間のランのアルバムを閉じようと家路へ向かった。
5月31日 エスカ新入生歓迎会(於・立教大) 参加者16名
今年は、立教大学がエスカの理事校なので、加盟校は池袋に集まった。1年生がたったの6名とはどうしたことであろう。各校の年間の活動予定を挨拶がてら話した後、例によって何某氏の大変、大変面白いお話をうけたまわった。それから、コーラを飲みながら北海道ツァーの映画を見た。この映画の主人公が、途中日本1周をしている青年に会ったが、数日後の新聞で、彼が死亡した記事を読んでびっくりした。彼は、帯広で酪農の研修を受けて帰路についた時この事故に会ってしまったそうである。諸兄達も事故にはくれぐれも注意しようではないか。サイクリングをしていて死ぬのは本望だという族もいるだろうが、死んでしまっては身も蓋もない。
6時頃、今日の行事は終った。1年生が6名とは残念な気がする。エスカ自体もより改革の必要がせまられてはいるが…。
6月7・8日 早慶親睦ラン 参加者26名
今年は、早稲田が主体となって企画し、柳沢峠をアタックすることになった。またしても去年同様に雨にたたられ、さんざんだった。
2日目は、快晴になり、両校とも闘志を燃やして峠を征服した。宿舎となっている思源荘に全員が到着したのは、5時頃になった。
夕食後は、両校全員がミーティング室に集まってエールの交換や自己紹介を行なった。芸能大会でもやろうという話が出たが、やらずじまいになった。来年は、このような企画をたてたなら、もっと面白くなるだろう。
宿舎の前で記念写真を撮り、班ごとに出発した。奥多摩湖で少し休みをとった。初夏の日差が湖面いっぱいに降注いでいるこの湖を左手に見ながら、一団となって快適な舗装路をすべるように走っていった。途中には昼飯を食べる所が無いということで茶店でパンを買い入れた。しだいに道もせばまり、やがて舗装も切れて柳沢峠入口にさしかかった。多くのサイクリスト達が通ったというこの青梅街道は、凸凹の激しい、また大きな石がごろごろしていて、乗っていても楽でない道であった。徐々に勾配が急になるにつれて班もばらばらになり、皆それぞれマイペースで上り始めた。
深い渓谷に沿っていて景観は良かったが、路肩に寄り過ぎて転落でもしたら大変なことになるだろう。このコースは、普通塩山の方から上り、奥多摩へ抜けるのが常道らしい。東京側から行くと、上り坂の距離が長いとのことだ。2・3人づつのグループになって、昼飯を取る地点まで上りつめた。ここで立教大学の同志3人に会った。彼らは今日、塩山からやってきたとのことだった。
昼食を取ってからフリーランとなり、また石のごろごろした山道を上り出した。慶応の人にはガムシャラタイプはいないと聞いていたが、なかなかどうして、なかには闘志満々の者もいた。頂上には、2時間ぐらいで大半はたどりついたが、既に到着した者が汗が引っ込んでしまっても、まだ着かない者も何人かいた。慶応のメンバーも非常にファイトを出したようだった。
峠の茶屋の人が、親切にも熱いお茶をサービスしてくれた。頂上からの富士山はくっきり見えた。写真に撮ったが、かろうじて写っていたようだ。2・30分休んだ後、セーターやジャンバーを着込んで立教大学のメンバーが上ってきたという道を一気に下った。下りも、ガタガタ道でハンドルを握る手が苦痛を覚えるくらいだった。1時間半ぐらいで解散地塩山駅に着いた。
その日に、東京まで自転車で帰るという猛者が慶応に2人、早稲田に2人いた。ここで名を記しておこう。早稲田の2人とは、高橋と高原の両君である。聞くところによると夜中の1時頃、東京へ着いたそうである。ごくろう様でした。慶応のお2人さまも。
この4人を拍手で送った後、慶応は自転車を分解してレーサー・バッグにつめこみ、早稲田は次回の富士スバルライン・トライアルのため、塩山から河口湖まで自転車を輸送した。
両校とも皆、無事に楽しい早慶ランが終ったことを喜び合い、来年の慶応主催による親睦ランの再会を約束して、電車で一路東京へと向った。小生にとっては、2回目の早慶ランではあったが、このような企画はぜひ続けるべきだと思う。
6月14・15日 富士スバルライン・トライアル 参加者23名
このランには、小生は参加しなかったので、土肥の記録をもって報告とする。
8月12日 – 23日 夏季合宿<東北> 参加者35名
これについては、滝野さんの記録にかえさせていただく。
8月27日 – 29日 エスカ夏ラリー<鎌倉> 参加者15名
合宿後、間が3日しかなかったので早稲田にとっては非常に苦しい、肉体的にも厳しいラリーであった。そのためか、参加人数も少なく、このラリーの主体となる企画(ヒル・クライム及びマップ・リーディング)を担当する早稲田としては容易でなかった。
27日の午後1時に、鎌倉の日本学生会館に集合した。それからすぐ、理科大の企画による班別ポタリングに出発した。小生の走ったコースはかなりきつく、合宿の疲れがいまだにとれていないようだった。
これには賞品も出るので、上位をねらっている者は真剣になっていた。結果はやはり、早稲田で脚力を誇っている小泉さんが1位になった。
翌日は朝9時に宿舎を出て、大楠山へのヒル・クライムに向った。急勾配の坂を各校とも覇を競った。大楠山で昼食をとったが、ここでは上品で純真無垢な早稲田の学生さんらしい態度に振舞ったので、そこにいた中学生(小学生?)の女の子を驚かせた。覚えのある御仁も多かろう。
昼食後、自転車をかついで山を下り、マップリーディングに移った。結果は、皆よくできたが、2・3人ポイントを間違えた者もいた。5時頃には全員宿舎に戻ることができた。
夕食後は、ホールに集まり歌を歌ったり、ゲームに興じた。この時は、各校ごとにかたまってしまうことなく、連盟と呼ばれるにふさわしかったと思う。早稲田の森進一と自他共に認めている美声の持主、三輪さんの歌も非常に良かった。最後に各校の校歌でしめくくり、今年の夏ラリーの幕を閉じた。
このラリーでもやはり、主体は早稲田であったような気がした。エスカの早稲田役員の方々、どうも御苦労様でした。このラリーが成功に終ったのも、ひとえに堺君をはじめとする役員諸兄の奮闘によるものと感謝いたします。
10月7日 総会及びコンパ 参加者32名
大学のロックアウトもまだ解かれず、講義も行なわれていないので、クラブ員の連絡が思うようにいかないため、各クラブ員に手紙を出し、コンパを兼ねて後期活動の連絡を行なった。
主な内容としては、対同志社との交歓会の日程、内容が決定したのでその旨を伝達した。次に、第2回東京 – 軽井沢間タイム・トライアル及び秋期合宿の件について詳しく連絡した。
やがて皆の前にビール、酒が並べられ、いつもの調子でコンパが始まった。小生が、1年生の頃は非常に楽しいテーマソングが次から次へと歌われたと記憶するが、最近はどうも静か過ぎるようだ。これでは、我がサイクリングクラブの名がすたるというもの、各自それぞれ持ち歌でもって大いに歌って欲しいと思う。特に今年の1年生は、まだ基礎ができていないようである。歌唱指導もあまり行なわれなかったが、これくらいは自分で仕入れてきてもらいたい。この日も酒に大分、可愛いがられた御仁もいたようだった。とにかくコンパは楽しいもの!
10月14日 – 16日 秋期合宿及び東京 – 軽井沢間タイム・トライアル 参加者27名
去年から始まったこの合宿形態をとる軽井沢タイム・トライアルは、今年で2回目である。紅葉の美しい時期なので、毎年美しいカラー写真が思い出を残してくれる。
宿舎は軽井沢友愛山荘を利用しているが、今年は去年に比べて、早稲田サイクリングらしい行動をとれたと思う。なにせ人数が多いものだから統制をとるのも楽ではないが、毎年使用するのであるから、ユースホステル内での団体行動は、各自自重する点があると思う。
今年は、ポタリングとして碓氷峠見晴台へ上った。細い山道を木木の間をぬってペダルを踏むサイクリングは、普段のランでは味わうことのできないものである。これぞ本当のサイクリングだ、と感じた。
歩いて上るコースではあったが、難なく頂上までたどりつけた。途中で小学生の遠足に出会ったが、快く道を開けてくれたのは有難かった。見晴台で昼食を取り、抜かしてきた小学生達で狭い場所が、埋まってくる頃、下り始めた。軽井沢の駅までは、軽快なダウンヒルが楽しめた。
余った時間は、各自のプライベート・ランに当てられた。小生は4・5人で峠の茶屋まで行った。途中の上りは非常にきびしく、汗でびっしょりだった。しかし、また下りは格別で、1時間半もかかった上りを20分で滑りおりた。帰りの旧街道は、車も少なくサイクリングには絶好の場所だった。
しかし、ここで気にかかるのは、軽井沢ランもまだ終っていないのに、このプライベート・ランをしないで自転車を送ってしまった者がいたことだ。解散は翌日の10時となっているのである。走りたくなくても自転車を輸送してしまうのは、ちょっと軽率ではなかったか?自転車を手離すのは、その者にとってランの終りを意味するのである。このような行動は、クラブの統制を乱す行為である。今後は絶対に慎しんでもらいたい。
タイム・トライアルについては、今年も戸田橋より軽井沢駅前まで140キロのコースで行なわれた。8時にスタートし2人1組になって脚力を競った。出発点に着いた時、伊藤さんや木村(淳)さんの姿が見えたので、ちょっと内心やる気をなくした。
皆、今年こそはと意気込んでいた。1年生より車のラッシュの中を一路軽井沢へと国道17号線に飛び込んでいった。(途中高崎より国道18号線に入る)先に出発した者に追いつき、横目でニヤリとしながら抜かす時の気分は何ともいえない。小生も去年のことがあるから、必死になってペダルを踏んだ。高崎の観音様のあたりから堺、渡辺君と並んで走り続けた。やがて安中の精練所が左手に見えてくると、小生は腹が急に減ってきたので、店でパンを買った。
パンを抱えて出てきた時、先を走っていた堺・渡辺君も自転車から降りて休んでいるようだった。小生もそこで休もうと思い行ってみると、渡辺君はフロントバッグを抱え込んで、こちらへ歩いてくるではないか。車も2・3台止まっているので、これはひょっとすると車に彼が喧嘩を申し込んだのではないかと思い、急いで走りよった。
「どうした渡辺!」
「俺の通る道をガードレールが邪魔しゃがって」
車にぶつかったのではなく、ガードレールにぶつかったというのでほっとした。彼は、しきりに肩に手をやって、
「骨がどうかしちゃったんじゃねえか、手が上がらねえよ」と連発した。
そこで止めてあった車で医者へ行ったが、どうしたわけか、どこかで見たような奴が、同じ車に乗っている。何と、高校の同級生ではないか。そんなこともあって、親切に病院へ連れて行ってくれた。大きな外科病院で直ぐみてくれた。
「大したことはない」と言って、医者は看護婦達に治療方法と注射を命じて立ち去った。何と診察室には、若い(高校生ぐらい)看護婦がウヨウヨいた。こんな田舎町に来ると、白い制服の魅力もまだ残っていると見える。
渡辺君は丁寧に足の傷口を治療してもらい、小生は端で見ていて思わず、
「俺も怪我をしてみたくなった」と口に出してしまった。
諸君も来年あたり行ってみたまえ、きれいな子がいるよ。そんなことはどうでもよいが、渡辺君も元気を取りもどして、看護婦に手配してもらったタクシーに乗り、渡辺君は安中へ、俺は事故現場へ行った。
タクシーを降りた時、店の前で黄色いユニフォームが動いているのを見つけた。
「あれ!新間さんまだ走っているのですか」
この調子で走ると事故も起きないのではないかと、つくづく新聞さんの顔を眺めた。
小生の自転車は、中山君が番をしてくれていた。中山君もここで1時間くらい待ったとのこと。事故を起こすと皆に迷惑がかかってしまうし、また自分もひどい目に会うので、くれぐれも注意して事故は絶対に起こさぬようにしてもらいたい。渡辺君は、電車で下宿まで帰ったとのことだった。もう2時間も休んでしまったので、足に力が入らずマイペースで碓氷峠を越えていった。日もとっぷり暮れて山荘に着いた時は、だいぶ遅くなってしまった。
また来年もこのタイム・トライアルの企画はあると思うが、事故だけは絶対に起こさないで欲しい。もし疲れたなら適当に休んでもいいじゃないか。5分ぐらいのロスは、直ぐ取りかえせる。
今年のベスト記録は守谷さんのそれを破り、木村(淳)さんの6時間台を割ったすばらしいレコードにぬりかえられた。この記録を破るのは、ちょっと難しいのではないか。今年は全般的に、自転車から離れた者が少なかったせいか、皆良い記録だった。戸田橋から乗りっぱなしで来れば、6時間台の記録は出せるのではないかと思う。来年は、事故もなく全員が良い記録を出せるようにしよう。
11月1日 – 4日 第6回早同交歓会<京都> 参加者34名
第6回早稲田・同志社交歓会は、両校60数名に達する部員が参加して、京都北山方面を中心にして盛大に行なわれた。
我がクラブに於いては、経験したこともない自転車をかついで山越えするというとても素晴らしい経験をし、また京都の山々の更けゆく秋を存分に楽しんで帰ってきた。
両校のクラブの相違を目のあたりに見て、西と東の差というものが良くわかった。
それにしても、東京と違って京都は近くに山あり、川ありでサイクリングをするには、非常に環境が良いというのは全くうらやましいことだ。京都を初めて走る者も多かったと思うが、これは誰しも感じたことだろう。
演芸大会もコンパもこの交歓会の楽しみだが、今年も例年にもれず爆笑が絶えなかった。小生の出し物が馬鹿に受けて、この交歓会の会言葉になってしまった。これを聞いて、行きたい行きたいと寝言を言う者も出るしまつ。あーあ、もう来年はよそう。
コンパも余ったエネルギーを全部出しきった感じで、期待通りのコンパだった。同志社のクラブ員が団結して、この交歓会を盛り上げてくれて、楽しい4日間を過ごさせてもらいとても感謝している。本当に御苦労さまでした。
最後に反省しなければならないのは、早稲田が集合時間に全員揃わなかったことである。ある少数の者達であるが、このような大勢が参加するラリーにおいては、特に各自が自覚をもって守るべきことは厳守するべきである。前から言われていることだが、この際また認識をあらたにしょう。
来年は早稲田の主催である。クラブ員1人1人の力を合わせて、第7回大会を成功させよう。
11月16日 2年生企画ラン<鎌北湖・顔振峠> 参加者11名
小生は参加することができなかったので、これについては、宮崎君の記録報告に替えさせてもらう。
11月28・29日 4年生サヨナラ・ラン≪和田峠≫ 参加者16名
前回のランを最終とする予定だったが、4年生の方から、もう1度全員でサヨナラ・ランをやりたいとの希望があったので、このランを企画した。全員参加がたてまえであったが集まりが悪かった。特に1年生が3人とは情ない。1年生の反省を望む。
時期的にちょっとはずれているような感がしないでもなかったが、その点は企画の良さでカバーでき非常に楽しかった。最終ランとしては、すばらしいコースだったと思う。
和田峠へ向う途中の八王子から入った陣馬街道は、サイクリングコースとしてとても良かった。車も少ないし、移りゆく囲りの景色も見ごたえがあった。舗装もされているのでこのコースをサイクリング専用道路にしたら、多くの人が楽しめることだろう。
和田峠の上りは、ちょっときびしかった。上っている時は汗をかいて暑かったが、頂上に着く頃には太陽も沈みかけて、急に寒くなった。皆で焚火をして煖をとる仕末だ。
下りはジャり道だが快適そのものだった。途中で、村が観光用に水車を回し米をついている光景に出会った。下校途中の小学生に尋ねると、村で管理しているとのことだった。小生も本当に米を入れてついているのは初めて見た。水車を後にして坂道を上り、国道20号線に出て、相模湖ユース・ホステルまで暗くなった道をとばした。途中マシントラブルを起し遅れた者もいたが、全員6時半頃にはユース・ホステルに無事到着した。夜は、駅前の喫茶店に出かけて行った者もいた。
翌日は大垂水峠の頂上まで一気に上り、それから山道を押して高尾山まで出た。山道でも快適に乗れる所もあり気持良かった。しかし、高尾山の見晴台の近くで、自転車をかついだのはちょっと苦しかった。でも同志社との交歓会で慣れていることもあって、皆ぶつぶつ言いながらも楽しそうだった。頂上で、相模湖町で仕入れてきたパンを、昼食がわりに食べた。
下りは薬王院を通り参道に出て、石のゴロゴロしている急な坂道を一気に下った。途中で女の子の集団に会い「みんな、こういう道でも慣れているのね」とささやかれて、ハンドルをしっかと握りしめた者もいたということだが。高尾駅前で名物のトロロソバを口にした。ほとんどの者が舌つづみを打ったようだった。
帰りは、企画担当者が5万分の1の地図を持ち出して、退屈させない良いコースを選んでくれた。何という川だか忘れたが、その川べりの小道は楽しかった。1列に整列して走る姿は後から見ていると、雑誌のグラビアそのものだった。名カメラマンがいて、その場所をうまく写真に納めてくれた。途中、突然道が消えてしまい、小川を自転車をかついで渡ったのも面白かった。
関戸橋のところで、主将の篠原さんや4年生をこの1年間の労をねぎらって胴上げして解散した。4年生のサヨナラ・ランとして、このランは皆から良いコースだと絶賛された。企画を担当した宮崎・砂子両君に感謝したい。御苦労様でした。
12月5日 総会 法学部203教室 参加者33名
1年と2年のミーティングの報告並びに会計報告が行なわれ、来年度の新役員が選出された。また来年は、早稲田がエスカの理事校に立候補することが決定した。
この1年を振り返ってみると、各自それぞれの『思い出』がアルバムに整理されていることだろう。4年生は汗のしみこんでいるあの黄色のユニフォームをタンスの片隅にきっと大切にしまって置くに違いない。ランの数こそ減ったが、有意義で楽しいサイクリングだった。
それではこのへんで40数名の手垢のついた、ずっしり重い走行日誌の最後のページを閉じることにする。
新入生歓迎ラン – 政治経済学部1年 上原
新入生歓迎ラン
政治経済学部1年 上原
5月3日、午前9時30分、学校に集合した。他のクラブ員は、元気が有り余っている様子であった。僕は、これからのサイクリングを考えると、胸は騒ぎ、心は踊ってきた。僕たち新入生にとっては、最初のクラブ・ランである。きょうは、相模湖まで約60キロを走ることになっている。点呼を取って10時に出発した。
新宿を抜けて甲州街道を走った。車の波が続き、衝突するところを想像すると恐ろしくなってくる。高尾付近までは快調に走ったが、それから先は、だらだらと上り始めてとても苦しい。心臓は高鳴り、息は切れ、先輩にはスイスイと抜かれて行き、当然とは思ってみても情なくなってくる。頂上はまだか、まだかと思いながら、ヒイコラ、ヒイコラ、ペダルを踏みながら上って行った。
僕の一生もここで終りか、あ、神様、仏様、○○ちゃんと思った時、ようやく頂上が見えた。「バンザーイ!」後は快調を下り坂である。ハイカーが非常に多く、どうしてこんなにも人が多いのかと考えながら進んだ。途中、かわいい女の子から「カッコイー」と声をかけられ、少々いや非常に気を良くした。その日は奥相模の静かな所でキャンプをすることになる。テントを張り、よってたかって飯を炊き、おかずはシチュ―と野菜サラダを作った。腹がへっているせいか、意外とうまかった。
2日目、きょうは秦野まで行く予定である。朝6時に起床し、7時半に出発した。例によって、最初は快調である。しかし、しばらくして山道に入ると、上り坂が続き、しかも道には砂利が転がっている。おまけにマイカー族がやたらと多い。こっちは、太陽の照りつく中を、ハァハァ言いながら上って行く。こんな山の中の細い道を車に通られては、危険この上ない。レジャーだ、なんだといって、山の静けさが破られることは、非常に嘆かわしいことだ。
しかし、さすが中津川渓谷の眺めはすばらしかった。ヤビツ峠から秦野までは、スリルのあるダウンヒルが楽しめた。バスの通り過ぎた後は、ほこりで目を開けていられず、危い場面が何度かあった。秦野に着いて、しばらくして小川さんと宮崎さんが追いついて来た。町を流れる川の川原でキャンプすることになった。加藤さんが「用事がある」と言って、一日早く東京へ帰っていった。ミーティングでは、いろいろな意見が出た。「下りのスリルがなんとも言えない」とうそぶく者、駄洒落を言う者、様々であった。夜は、みんなで、銭湯へと繰り出した。
明けて翌日、上ったり下ったりの厚木街道は、快調であった。このランは、連休であったせいか車がやたらと多かったが、コースも良く、変化に富んでいてとても楽しかった。サイクリング本来の姿としては、自分で企画し、人生の厳しさを求めて、1人で走り続けるプライベート・ランが本当だと思っていたが、クラブ・ランも別の意味で楽しいことが分かった。また、ただ走るというだけではなく、旧跡などを訪ねながら走るのも、いいのではないだろうか。
山伏峠・正丸峠下見行 – 政治経済学部2年 仲田
山伏峠・正丸峠下見行
政治経済学部2年 仲田
この原稿を編集局から頼まれた時、正直なところ、ちょっと困った。というのは、小生は今までのサイクリングで記録など取ったことがないからである。サイクリング・ノートなるものを、一応一冊持っていることは持っているが、それも去年の合宿の途中までしかまとめておらず、何の役にも立たない。どの位困ったかといえば、まず第1に、いつ行ったのかはっきりしない。手帳を見ても何も書いてないし、必死に考えたあげく、5月10日ではないかと推測した。第2に、日付がその程度であるから、細かい時間などまるっきり覚えちゃいない。だいたいを書くより手がないわけである。それでも、経路とか道路状況など、時間に関すること以外はある程度覚えているので、一応、サイクリング・レポート的なものにまとめることができると思う。
日曜日の朝、9時から10時頃、大原交差点で小川さんと待ち合わせる。勿論デートなどではないから、不景気な顔をしている。だいたい、クラブ・ランの下見なんか、よほどのことがない限りする必要がないと思うのだが、小川さんは1人ででも行くというし、一応小生も責任者に指名されているのだから、1人で行かせるような、非人情かつ無責任なことは絶対できない点、実につらい。
自然、雨でも降らないかとか、小川さんが止めるといい出さないかとか、他力本願なことばかり考えてしまう。しかし、空はあくまでもさえわたって暑いぐらいであり、小川さんは、といえば、とても止めようなどといい出すはずもなく、腹の中はいざ知らず、ニコニコ笑ってついて行かざるを得ない。
大原を出て、青梅街道に入り、そのまま田無へ向かう。田無で、小川さんがガードの金具を買い、その間、小生は店の前のピンク映画のポスターを眺める。所沢街道より飯能までは、周知の通り、何の変化もない、狭くて、しかも交通量の多い道なので、別に書くこともなかろう。
飯能へ着いたのは、12時半頃ではないかと思う。例によって昼になれば、食堂へ入る。ともかくきょうは暑い。初夏の暑さで、日向にいれば、じっとしていても汗が出てくる。その上、所沢街道では、実は小川さんに先を走ってもらったのだが、この人がまた随分と飛ばしたものだから、とてもじゃないが、たまらない。後で聞くと、何でも小生が後から迫ってくるものだから意地になって飛ばしたらしい。こちらはこちらで、離されるのがいやだから必死に追いすがる。すると、また逃げる。こうなるともう悪循環である。こんなことなら、わざとゆっくり走ればよかったと後悔しながら、冷し中華とサイダーを注文した。時間はまるっきり覚えていないのに、こんなつまらないことはよく覚えている。
コースは、市内をまっすぐに抜け天覧山・正丸峠への道を右に見ながら、名栗渓谷沿いに走る道である。5月の渓谷は、天気も良かったせいだろうが、実に気持が良い。ところどころ釣人が見える。
市街地を離れるとすぐ渓谷が始まり、わりと快適な舗装路が続く。地図によると舗装は少ないと思われたのだが、実際は大部分舗装されており、2、3回地道になるだけでこれもすぐ切れ、ごくわずかな上りの道が木陰を縫うように走っていて、左側の名栗川に遊ぶ人達を見るにつけ、我々も一緒に水遊びをしたいという強い欲望にかられがちになる。いつも思うことながら、こういう時に止まって遊ぶというのんびりしたサイクリングに憧れながらも、それができない自分というもの、実に矛盾した生物である。サイクリストというものは、生まれながらに、さすらいの宿命を背負わされているのであろうか。止めてくれるな娘さん、いかざあならねぇ男の涙。2輪にまたがり、ポンプを背負い、あの山目指してさすらいの、男1匹無宿者、流れ流れてどこへ行く、あぁこりゃこりゃ。
このころから小生の足が重くなって、胸が苦しい。3ヶ月ぶりに走り、しかも風邪が治りきっていないためであるが、それでもなんとか小川さんについていく。「どこかで休もう」といい出してくれるのを望みながらも、そこは偉い小生のことであるから、黙ってペダルを踏む。結局、名栗あたりの店で休息したが、苦しいことなどおくびにも出さず、ニヤニヤ笑ってごまかして、その実、足がガクガクして困った。この店で山伏峠の状況を聞いたが、なかなか良い峠らしく、また店の人も親切に教えてくれた。なかでも、小学生くらいの子供が、歩いて行った経験があるとていねいに教えてくれ、おじさん、おばさんがニコニコ笑いながらそれを見ていた。
たずねるのはもっぱら小川さんに任せて、小生はあせってアイスクリームをパクついたが、最後には熱いお茶まで出してくれ、2人はお礼をいってそれを飲んだ。「来週、20人くらい連れて、また店に寄ります」とかなんとかいって出発したが、東京近辺にこんなのどかな田舎じみた所があるとは、思わなかった。なにしろ、『早稲田』といってもびっくりしなかったものだ。店を出て、少々上りもきつくなりだした。といっても相変らず1パーセント以下。聞いたところでは、名郷より約4キロ位、地道で峠まで続いており、その舗装の切れる所より、本格的に坂がきつくなるらしい。ますます細くなる渓流沿いに快適な道をしばらく行くと、部落とおぼしき家並みに入り、これを抜けた所より確かに舗装が切れて、上り出していた。
小生はその手前より本格的にダウンしており、小川さんについて行く!ことができなくなっていたので、そこより頂上までフリー・ランで走ることにして、先に行ってもらった。道は、天気のせいか、ほこりっぽく、白く輝いて暑い。
先にも書いたように、峠路はだいたい4キロ前後、所々きつくなるが、おおむね楽に上れると思う。小川さんの所要時間が2~30分で、小生が押して上っても45分前後であったので、そこからどの程度か推察していただきたい。路面は、砂利も浮いておらず、天気のせいでほこりっぽい以外は、走りやすい。
峠の頂上は、やや空地がある程度で何もない。上ってきた方を振り返ると、わずかに視界が開けていて、下の道が見えるのだが、反対側、つまり正丸峠の方は、ただ、道が下っているだけで何も見えない。東京近辺ではまずまず峠らしい峠だと思うが、まだ現在はわずかにハイカーが来る程度である。しかし、開発がもっと進んで、上り口手前まできている舗装が頂上まで続いた時、この車の往来の少ない、東京では数少ない絶好のサイクリング・コースがどうなるかと考えると、是非1度走ってみた方がいいのではないだろうか。
わずかに下って、正丸峠の下へ出る。左へ下ると秩父、右へ上ると正丸から飯能へ出る。この交差点にある店の道の下にキャンプ場があり、予約さえすれば、無料で貸してくれるとのこと。そばに小川が流れており、水、トイレは店で使わせてもらえ、キャンプ場は小川沿いに長く伸びている。付近に食料店はないので、食料は名栗で買ってくるか、秩父まで行くよりしょうがない。薪はこの店で分けてくれる。
小川さんと小川で水遊びをして、いやいや自転車に乗って出発する。少し上れば、すぐ正丸峠である。東京側の展望は、わりに開けていた。反対側は忘れた。峠の休息所でしばらく休んだ。この上にまだ展望台があるらしいが、歩いて行くのも面倒なのでやめた。さすがに、ここには東京あたりから来たドライバーがウジャウジャいて、店の中で何やら騒いでいた。例によって例の如く、小川さんはいつもの病気が出て、自分の持っている物を持っていない他の人類に、祖先伝来の本能からくる、一種の超音波を送っていたが、なにしろ隣りに小生がいたものだから(と、言いたそうな顔を彼はしていた)ことごとく失敗して、意気消沈してしまった。
正丸峠のこの道は走った人も多いと思うが、舗装されていてダウン・ヒルが結構楽しめる。峠から少し下った所に西武経営のキャンプ場があるが、これは、無論、有料である。予定のクラブ・ランでは、2日目にここを下って途中から左へ、定峰峠の方へ折れるのだが、これがかなりの難所らしい。グリーン・ラインとかいって、車も通れるのだが、かなりきついらしく、きょうは勿論その状況を聞くだけにして帰りを急ぐことにした。
下り、特に帰りを急ぐ時の下りというものは、それがだらだらであればあるほど、長く感じる。この道にしたって、峠から飯能までは距離的にさほどでもないのに、途中でいやになってしまった。そんな時は、余裕を持って風景でも眺めて – 考えてみれば、危険この上ないが – いればいいのだろうが、小生にとって、この下りの風景は何の意味もなかった。「絶景かな!」などという詠嘆のことばは、その時々の気分に左右されやすいものだ。気分によっては、何でもない田舎道の名も知らぬ草花にだって、詠嘆のことばをつけたくなり、気分が変われば、富士山だって、空気ほどにも感じなくなってしまうのである。
飯能に入る前、すでに夕闇が迫っていた。気ばかりせくが、足はいうことを聞かない。ついにたまり切れず、市内の喫茶店で一服することにした。クリーム何とかという、甘いやつを食べて休むそばで、小川さんは地図を調べていた。
つまらぬことを羅列してきたが、とにかく2人は生きて帰れた。家にたどり着いたのは、8時半頃だった。ただ、所沢で道を間違えて、2人でにぎり飯を食べたことを付け加えておく。
早慶親睦サイクリング座談会 – 法学部2年 保泉
早慶親睦サイクリング座談会
法学部2年 保泉
今年度は、早稲田の主催によって、柳沢峠が企画された。今まではポタリング程度のものだったので、あまり興味もわかなかった。よって今年は新しい試みとして、1泊ランが企画された。
日程は、6月7日・8日と決められ、7日は国民宿舎「思源荘」に泊まることになった。参加人数は、慶応側は11名、早稲田は26名に達した。集合地として、荻窪の四面通りが選ばれた。天気が危ぶまれたが、案の定、7日は雨にたたられ、雨中ランになってしまった。しかし、翌日は、からりと晴れわたり、絶好のサイクリング日和になった。解散は塩山駅前で、3時半頃になった。慶応は自転車を分解し、レーサーバッグにつめた。早稲田は次回ランの為、塩山から、河口湖駅まで鉄道輸送した。尚、慶応2人、早稲田側も2人、東京までのナイト・ランを決行した勇士がいたことをつけ加えておく。
このランに関して詳しいことは、この間、早慶各部員による座談会「早慶ランをふりかえって」が催されたので、その時の模様を述べてみたいと思います。両校とも2名づつ出席して貰う。場所は渋谷の某喫茶店で開かれました。時間的にちょっと余裕がもてなかったため、いろいろな話をきかせてもらえなかったのが残念でした。約束の時間、午後3時には4人とも集まって、すぐ話を始めることができました。
「司会」今日はどうも忙しいところを集っていただきありがとうございました。去る6月7・8日に行なわれた、早慶ランについて、皆さんにいろいろと話合ってもらいたいと思って、今日ここにお集り願ったわけです。まあ、気楽になって、いろいろなことを話し合ってください。それでは、まず慶応の方からこのランの感想などを簡単にお願いします。
「慶大A」それよりまず、早稲田の皆さん全員の努力によって無事終ることができたことを感謝ったします。どうもありがとうございました。そうですねぇ、感想といえば、「ただ苦しかった」という印象が強いですねぇ。大きな、荒い石ころが多くて道路状態はあまりよくありませんでしたね。しかし、あの多摩川流に沿った溪谷美は何とも云えない程、野性的ですばらしいですね。峠を越えて、茶店が見えた時ほっとしました。峠からの下りも相変らず、大きな石がごろごろとして、ハンドルを握る手が痛くなりました。やはり早慶合同ランは、普段のランと違って楽しいですね。
「慶大B」早稲田の各部員の方々に感謝の意を表します。最初の日、かなりの雨に降られて、峠にアタックすることができないのではないかと、心配したのですが、あの通り良く晴れたので、とても楽しく2日目は過ごせました。多くのサイクリスト仲間が試みる峠だけあって、スケールが大きく、またダイナミックなところですねぇ。また景色も抜群に良い所があり、サイクリストを楽しませてくれますね。しかし皆んな早稲田の方は強いですね。こちらはいつもマイペース、チンタラムードでやっていますよ。
「司会」話によると、慶応の人達は、既にこの柳沢峠にクラブ・ランで、アタックしたとか聞きましたが・・・
「慶大B」僕は1度走ったことがあります。その時は、塩山から上りました。普通は、塩山から上る方が多い様ですね。そうすると、峠から青梅まで一気に下れるわけですから。
「慶大A」僕はこれが初めてです。もう、あまり行く気はしません
「司会」主催者側としてはどうですか。
「早大A」最初の日、雨に降られたのでガックリきたのですが、翌日晴れたので、助かりました。僕もこの峠は初めてなのですが、大分厳しいところですね。青梅街道といっても、名ばかりで、石はごろごろしてるし、ガードレールはないし、いつ頭上に石は落ちてくるかわからない様な所ばかりでしたね。それだけにまた、ダイナミックであり、スリリングがあるのかも知れませんね。峠の茶屋で出してくれた、あのお茶はうまかったですね。何も買わなかったけれどハハハ・・・とにかく事故もなく、無事に全員が塩山駅に着けたことは、主催者側としてもうれしく思いました。
「早大B」僕はこのランで今年度2回目のランだったんです。自転車にもあまり慣れてなかった上に、この峠ときているのでしょう。まったく死ぬ思いでしたよ。上ってる途中、何んでこんな山の中まで自転車で走るのか、いく度考えたかわかりませんでした。早く峠にたどりつかないかなぁと、そればかり思っていました。しかし、柳沢峠に着き、展望台から眺めた富士山の姿を見てるうちに、いつしか上ってくる時考えたことも忘れ、疲れもいっぺんに吹き飛んでしまいました。早慶戦は、見るだけですが、自分の体を動かして「する」早慶戦は、楽しいですね。僕はまだ1年生なのでこれからも、あと3回出られるわけですね。楽しみにしたいと思います。
「司会」去年は、多摩湖日帰りランでしたね。まぁ今年は、より親睦を深める意味で1泊ランを取り入れたわけですけれども、この点についてどうですか。
「早大A」やはり、1泊ランにした方が楽しいですね。主催者側にしてみれば、そりゃぁいろいろな苦労がありましょうが。僕は今回のランは非常に良かったと思います。同じ釜の飯を食うだけでも、いくらか親近感も増すのじゃあないかな。
「早大A」僕等の方としても、まぁ多少の苦労は覚悟の上でしたけれども、早慶ランとして何か記憶に残る様なランにしたいし、また両校の交わりを深めるためにも、面白かったと思いました。
「慶大B」これからも、ずっと続くでしょうが、今回のランは、人後の早慶ランに於ける発展の布石として画期的なものではないですか。まぁ来年は僕等が企画する訳ですけれど、やはり、できたら1泊ランにしたいですね。来年、もしまた女性の参加がないようでしたら、テントなども面白いでしょうね。
「司会」あのぉ、夕飯を食った後で、早慶対抗の余興演芸会をやるような話をちょっと耳にしたのですが・・
「慶大B」僕等もこれは面白いな、と思いさっそく出し物も考え始めたのですが、とうとう僕らのうまい「隠し芸」も本当に隠されてしまいました。やはり両校が肌で触れ合う機会も出来たら、よりうちとけるのじゃないでしょうか。やってほしかったですね。
「早大A」こちらとしても、今までのなまぬるい様な、変な気分を打ち壊そうとじ一応企画を考えたわけですが、ちょっと時間が足らず、その他の雑用がありまして、出来なかったことは非常に残念でした。やはり、そういう催し物も絶対必要ですね。来年にでも、酒の杯を交わしながら、お互いにやりたいですね。
「早大B」来年あたりは、やってみたいような気がしますが、慶応の方々如何でしょうか。
「慶大A」そうですねぇ。ぜひやりたいですね。
「司会」早慶両校のスクールカラーが違うように、走り方、クラブの活動等に於いてもかなり異なるところがあるように思います。ひとつ、今回のランを例にとってみて、その点どうでしょうか。
「慶大A」そうですねぇ、まあカラーを示しているようなことと言えば、自分がってにマイペースで走る、ということですかねぇ。今回のランにしてもわかると思いますが、足の強い者は、どんどん先に走っていくし、また弱い者はいつもどん尻にひかえて、余裕をみせるようにして走っていきますね。僕達の走る時の服装を見てもらえばわかると思うけど、皆んな、良く言えば個性的ですけれど、悪く言えば、ばらばらなんです。不統一、不調和に於ける統一、調和とでも言いましょうか。またそれで、僕等はいいと思っているし、このままずっと続いていくだろうと思います。早稲田の様に、全員が揃いのユニフォームを着ている姿を見ると、爽快で魅力的ですが・・・
「司会」そう言えば、どうして慶応はユニフォームを作らないのですか。早慶ランのような時には、両校ともそろいのュニフォームを着てさっそうと走ってみたい気もするのですが。
「慶大B」毎年つくろうという意見は出るのですが、どうも発展しないまま、うやむやになってしまうんです。ワッペンだけでもと、一応考えたことがあるのですが、やはり必要でないという意見が多く出て、そのまま役になってしまいました。まぁそんなところですね。
「早大A」僕等の方としても、慶応側に何かしら一見して『ああ、これは慶応の人だな』という程度にわかるものがある。常に都合がいいんですがね。
「司会」今度は1つ、早稲田のカラーというものは如何ですか。
「早大B」僕はまだはっきりつかめないんですが、ただ言えることは、慶応にユニフォームがなくて早稲田に『ある』ということに全てが集約されてきそうな気がするんです。今回のランに出て感じるのですが、早稲田側には、力強さ、ダイナミックな動き、すなわち『男らしさ』があると思うんです。現にこれを証明することとしては、うちのクラブに女性が居ないということでしょう。まぁこの『男らしさ』が新幹線ぐらいのスピードでつっ走ってしまうと、自転車というものが1つの手段となってしまう恐れも出てくると思いますが。それで十分だと言う人も居ると思いますが。でもやはり、この双輪を「手段であり、かつ目的である」というところまで高めたい気もするのです。僕は今回が最初の早慶ランですが、やはり、本当のことを言って、慶応と競争しているような闘争意識が潜在的にありました。早く峠にたどり着きたい、しかも慶応より早くにと。
「司会」問題がちょっと発展し過ぎたようですが、その競争意識ということに関してどうですか。
「早大A」やはり全くない、といったら嘘になってしまいますね。でも今回などはもうそんなことは、どこかに吹っ飛んだ感じです。やはり、早慶親睦ランとして楽しくやりたいですよ。お互いに・・・
「慶大A」そうですよ、第一面白くなかったら僕は出てきませんから。今までそんなことは意識してなかったなぁ。
「慶大B」うん。全然といっていいくらいなかったなぁ。これからはもう、そんな些細なことは忘れて楽しく走ることに精を出そうよ。
「司会」まぁ、これは最初のうちだけだから心配する必要もありませんね。ところで、もうそろそろ時間もなくなってきたので、最後に次回及びこれからの早慶ランについて何かご要望でもありましたら、お願いいたします。
「早大A」そうだなぁ。今、僕がふと考えたんだけれど、ミーティングの時に、両校のペナントでも交換したらいいんじゃないかな。生協に売っている既製のでいいと思うよ。そして、早稲田のペナントには早稲田の参加したメンバーの名前を書き、慶応のには、また慶応のメンバーの名前を書き入れたらいいんじゃないかな。毎回同じペナントだけれども、何か記念にもなるし、クラブの歴史にもつながると思う。
「慶大B」それもいいアイディアだね。まあ、ペナントに限らないんだけれど、両校の特徴というかな、早慶 – 僕等の方じゃ慶早と言うんだけれど – それを表わしている物ならなんでもいいんじゃないかな。
「慶大A」まぁこれからずっと続くと思うけど、このラン以外にも、何か親睦を深めるものもあってもいいね。ちょっと年に1回きりのランだけでは、もう1つしっくりいかない気もするんだが・・・
「早大A」今後はそのようなことも考えてみるべきですね。一緒に考えましょう。
「司会」今日はどうも長い間ありがとうございました。これからも早慶両校手をとり合って楽しいランにしたいものです。秋にはまた、早慶戦で会いましょう。来年は慶応の企画によって行なわれる訳ですね。よろしくおお願いいたします。
「慶大A」こちらこそ。張り切ってやるつもりです。本当に、今年は早稲田の皆さんごくろう様でした。どうもありがとう。
「早大A」どういたしまして。来年はまた、お願いいたします。
富士スバルライン・トライアル – 理工学部1年 土肥
富士スバルライントライアル
理工学部1年 土肥
今年3回目のクラブ・ラン富士スバルライン・トライアルが、6月14・15日の2日にわたって行なわれた。3回目のランにして富士山アタックで、不安もあり、楽しみ、期待もあった。自転車は、先週の早慶親睦ラン<柳沢峠>の解散地である塩山から鉄道便で、直接河口湖まで送ってあり、我々は7時頃の急行で愛車の待っている河口湖駅へ向かった。天気は晴れていて、やや暑い。『しかし、高地だからこれ位が丁度いいだろう。サイクリングには絶好だ』などと思いながら、景色を見たり話をしたり、電車に揺られていた。大月から富士急行の路線に入ると、もう富士山は近い。しかし、なかなかその姿が見えない。さてはでかすぎて視野に入らないのかなとは思わなかったが、天気のことでいやな予感がしてきた。
9時半頃、河口湖に着き、早速自転車を取り出すとやはり痛んでいた。特に僕の愛車は痛めつけられていた。『かわいそうに痛かっただろうなぁ』と修理をしてやっていると、ポツリポツリ雨が降ってきた。出発するまでに、2回ほどジァーと強烈に降った。早目に昼飯を食べて12時近く出発。柳沢峠を下る時に、後部泥よけのバンドを切り、針金でなんとか吊ったままなので、それがどうも気になる。駅から1キロ程走ると、スバルラインの入口に着いた。通行料を払い、出発前の点検をする。バンドと輸送で痛められた箇所を、何とか最良の状態にしようとしているうちに、皆はいなくなってしまった。急いで走り出す。
標高差約1,200m、距離にして30キロ程のスバルライン・トライアルが始まった。最初のうちはトップギァで走れ、それほど辛くもなかった。右や左の景色 – といっても木立や富士スバルランドへの入口 – を見ながら走った。次第に身体が熱くなり、汗をかき始めた。やはり上り坂なのだ。汗はどんどん出て、大きな水玉になってコロコロと顔の上を転げるほどになる。ギアの切り換えを考慮に入れるようになった。すでに数人が僕の後について走る。つまり、僕が先に出た、抜いたわけだ。しかし、まだ2合目どころか、1合目の標識も見えない。これは見落としたかな?まあいいや、走らなければしょうがない。そうこうしているうちに、勾配は急なものが一層急になり、しかもスリップ止めのデコボコがついて、ますます苦しくなる。しかし、さいわいにも晴れていた空が曇り出し、気温も下がってきて救われた。
前を見ると、篠原さん、滝野さん、仲田さんら数人が走っている。『そろそろ1人で走るのをやめて、一緒に走ろうか』と思うが、そのうちにやはり1人で先に出てしまう。バスや乗用車が、排気ガスをブァーブァー出しながら上って行く。『こんなとこ車で上ったってつまんないよな』といい聞かせながらペダルを踏んでいると、どうしたことか、雨が降ってきた。雨といっても、そんじょそこらの雨とはちょっと違う。すごいのなんのザァーザァー降ってくる。おまけに気温もどんどん下がって、吐く息が白く見える程になった。
「ワァー、頭に来ちゃうな」
つぶやいても、怒鳴ってもしょうがない。ペダルを踏む足がおかしい。気温が急に下がったので、つってしまったのだ。しかし、指の方だったので助かった。すぐ自転車を降りて、歩きながら直した。
『こりゃ心細いなあ。1人で走っていて、ふくらはぎでもつったらどうしよう』と思って後を見ると、篠原さんと滝野さんがやって来る。『救われた!一緒に行こう』こうして2人の後から走り始めた。
この頃には、雷がゴロゴロ鳴り出していて、精神的にもやる気が失くなってきた。1年前のニュースで、高校生が山で落雷に遭い、数人が感電死したことを知っていたからだ。しかも雨が電に変わった。ますます寒くなり、落ちてくる雹が、直接皮膚にあたって痛い。前はかすんで数10mしか見えない。『ああ、早く止まって休まないかなぁ』と心の中で願っていると、やっと木立があり、その中で雨宿りならぬ雹宿りをすることになった。短パンとユニホームきりの服装では、あまりにも寒すぎる。身体は全身ずぶ濡れ。歯をガチガチいわせて、雹にあたらないような所を見つけて休んだ。数分すると小雨模様に変わった。しかし、依然として雷様はごきげん斜めである。「雷が危いですよ!」といっても、篠原さんも滝野さんも相手にしてくれない。仕方なく、また自転車に乗って走り出した。
やはり、じっとしているより、何か身体を動かしていた方が暖かい。しかし、6月半ばでこんな天気とは・・・、我々はまだそんなにバテていなかった。特に篠原さんと滝野さんは、まだスイスイ上っていたようだった。もしこのまま走っていられたら、5合目まで行けたかも知れない。しかし、それはだめだった。再び、雹が猛然と襲いかかってきたのだ。また適当な雹よけの場所を捜さねばならなかった。ようやく見つけた林の中で、パンを食べたり、ジュースを飲んだりして、なんとか、生命の火だけは消さないように努めた。待てども待てども、雹も雷も止まなかった。
そのうちに、僕が待ちに待ったことが起きた。篠原さんが引き返すといい出したのだ。全くありがたかった。篠原さんと滝野さんは先に行った連中と連絡を取るので、僕が1人で下ることになった。
雷が恐かったが、『どうせ感電死だ。そしたら苦しまなくてもいいや』と思いながら、下り始めた。しかし、その寒いこと!じっとしていてもガクガク震えが止まらないのに、風を切って下ることは本当に寒かった。ブレーキをかけるのにも、手がかじかんでいうことを聞かない上、濡れているから余計かかりにくい。そのうちに寒くてどうしようもなくなり、道端の洞穴にひとまず雨宿りすることにした。バスが下って来る。ガイド嬢がこっちを見ている。止まって乗せてくれるかなと期待したが、『あの人、何してんのかしら?』というような顔をして通り過ぎてしまった。『ああ、どうしよう。このまま凍え死んじゃうのかなぁ』ボーと道を見ていると、篠原さんと滝野さんがやってきた。思い切ってまた下り出した。そのうち左手に広場が見え、山小屋らしきものがあった。そこを通過しようとした瞬間、「オーイ!」という声がした。
その小屋は道路作業員の休息所で、声の主は我がクラブ員だった。小屋に入ると、すでにストーブが燃え、数人があたっていた。やっと救われた。完全に凍えていた体が、次第に溶けてきた。それと共に、雹も雨も止んで青空が出てきた。着ているものもできるだけ乾かした。そして、スバルラインの出口まで、寒いが快適なダウンヒルを楽しんだ。
途中、1合目を下った所で、自転車が2台置いてあるのを見つけた。よく見ると「SANNOW」の文字。すぐ我がクラブ員のものであることがわかり、2人を捜した。呼べども呼べども返事はなく、『これは死んだのでは・・・』と思おうとした時、1台の車が止まり2人が降りてきた。なんとも人騒がせな2人である。再び皆んなで出口に向かって走る。出口に全員揃うまでの間にも1度雨が降った。
結局、5合目の終点まで上ったのは7人で、1年生では砂子君だけだった。僕は3合目を少し過ぎた所、道のりであと10キロ程を残す地点まで上ったのだった。今、振り返ってみると、残念でならない。近いうちに5合目まで走り、それから頂上まで登ってみたい。
その夜は、河口湖YHに泊まった。キャンプのつもりで来たのだが、本当に助かった。テレビは見れるし、夕飯も落ち着いて、暖かく食べられた。風呂が格別に気持ちよかった。
次の朝、起きてみると快晴であった。富士山が、目の前にくっきりと、その全容を現わしていた。やはり、5分の2は白い雪におおわれていた。すばらしい富士の姿だった。それを背景に記念写真を撮った。YHに別れを告げ、帰路につく。山中湖までは舗装路だったが、そこを過ぎると、あとは砂利道ばかりである。しかし、たいした上りもなく、下りだけだったので、走ることにおいては楽なものである。
ただ、例のバンドの針金が切れて、タイヤが泥よけをするのが、とても気になってしょうがなかった。それに、寒さのためちょっと風邪気味だった。パンクなどの故障が多く、遅れた人が相ついだ。僕も、砂利道の下りは特にスピードを落として、泥よけをタイヤがすらないようにして相当遅かったのだが、それでも皆んな揃うまでに、1時間も待った程であった。
道は悪かったが、逆比例的に景色は抜群だった。まだ田舎的な所ばかりで、川も、林も、田も、畑も、空もきれいだった。晴れていし暖かく、この日こそ真のサイクリング日和というのだろう。舗装路に出たところで昼飯となる。昼飯といっても、パン2、3個とコカ・コーラという非常にさびしいものであった。それからしばらく走ると、新入生歓迎ランの時のコースに出た。今度はあの時とは逆に走るわけだが、ちょっと懐しい気がした。新宿(厚木市)のT字路に、全員が揃ってから東京に向かった。津久井湖も通り過ぎるだけで、ただひた走りに走った。陽の光がだんだん弱くなるように、身体も疲れてきていた。そんな身体にどんどん走らせた。この時期は1年中で最も日の長い頃だったので、暗くならないうちに、解散地の府中に着いた。
それにしても、面白いランだった。いろいろな経験をした。めったに出会わない経験だろう。しかし、ぜひとも富士山に登ってみたい。この気持は今でも変わらずに残っている。今度アタックする時には、どうか晴れていて、雷様が暴れ出しませんように…。
C140のこと – 法学部2年 堺
C140のこと
法学部2年 堺
それはあまりに唐突だったから、誰でもない、この俺が1番面喰らった。
今年で2回目の戸田橋 – 軽井沢タイム・トライアルは、クラブ行事でもユニークなものである。順位を競い、賞も出るとあっては、クラブ員諸君も、一様に張り切る。2回目となれば昨年の記録が参考になるので、「俺は5時間半で行く」と豪語した御仁もいた。関心は上々といったところである。
さて、俺はといえば、表向きはいわゆるサカイスマイルであっても、凡夫の愚かさ、競争ともなれば、やはり心ひそかに『1発かましましょうか』てなアホな気持がフッとおこる。
集合時間ピッタリに戸田橋に着く。橋を渡りきった交番の前の、ちょっとした広場が出発点である。通勤、通学の人達があわただしく行き交う。車が数珠つなぎになって麻痺状態の17号線。8時6分、俺は中山君と組んで4番目にスタート。フロント・バッグの上にキロ数を書き込んだコース略図。『おまえやる気だな』。ひどい混雑。でも1度走ったことのある道は懐かしい。かなり飛ばす。ほとんどの諸君が高崎までのおよそ90キロは、ノンストップ。140キロもの長い距離になると、何かの条件で差が出てくる。仲田君は信号にひっかかった。保泉君は小用でとまった。大堀さんは不運にもパンク。そして渡辺君は、俺のうしろを走っていて、ガードレールにゴッチンコ。
昨年に続き今年も上天気。松井田あたりから、逆光でシルエットになって見える妙義山のスカイラインが怪奇にも美しい。やがて碓氷峠。横川のドライブインからちょっと下って橋を渡り、2つ3つコーナーをまわると1直線の登りが500メートル程も続く。この道に沿って並ぶ家々は、何となくいい。この道に沿う石の排水溝がまたいい。この直線はいい感じ。上りつめて右にカーブ。C-1の立札が見える。
「これからC-184まで上ってもらいます。おまえさんたちも、物好きだね」
C-1は、俺にそう語りかけた。Cとはカーブを意味する。故に、峠まで184個のカーブがあることを意味する。長い!C-1の前で、C-184はほとんど無限と同じだ。しかし、それはC-1のところでの感じであり、184はあくまでも有限。だから、ひとつずつ行けば必ず行きつく。だから行く。その時の感情は、仕方なしにといった風である。実際、行動として、そうするしかないんだ。
俺は敢然と峠に挑む。快調!!スルスルと苦もなく上る。調子のいい時は、峠も楽しく感じられる。苦痛といえば単調さか。時間が相手となる。去年のことを思えば、それは贅沢。C-140を見やり、ニャリと片頬笑ったのは、意識過剰か?人生がひとつのドラマとなれば、それくらいの演技は、むしろ自然だろう。いや俺たちのすべてが演技なのだ。(演出は・・・?)小1時間で峠に着く。ゴールの軽井沢駅はもうすぐだ。終わった。クラブの皆んなは、駅前の食堂にたむろした。ひとつのことをなし終えたあとの、満足と興奮があふれ、話は弾んだ。渡辺君の事故でのロスタイムを引いた、6時間33分、これが俺の今年の記録。ご苦労様でした。
これだけの話?これだけなら当り前のことだ。第1この文題は、どういう事なのか?
そうだ諸君!全くそうなんだ。俺は、さらに1年前にさかのぼらねばならない。そうしたい。去年のことは、去年にすませておけば良かったのにと言うかも知れないが、(そう言われたらちょっと困るが)多分時間を必要としたんだろう。それとも、1人のものにしておきたかったんだろうか。わかんない。いずれにしても躊躇したことは確かだ。
去年の10月31日、クラブ第1回の戸田橋軽井沢タイム・トライアルが行なわれることになった。朝5時半、戸田橋集合は、きつかった。だから、赤羽の渡辺君の下宿に他の連中3人と泊まったそれなのに、そこを出るのが遅れ、遅刻してしまった。戸田橋に着くと、おおかた出発していて、中村さんが1人、コロナと一緒に立っていた。渡辺君、仲田君が出た2分後に俺は遠藤君とペアでスタートした。(そういえば、あいつは2年になってから最初だけ出たきりで、以後クラブには来ない。どうしたんだ、あいつ。俺はまだ続けてる。バカみたいに続けてる。何がやつと違うのか。焦り気味にそう思う)今年より1,2時間も早かったから、道路はめっぽう空いていた。ひんやり冷たく、澄んだ早朝の空気がうまい。直線の道路を走っていると、突然朝日がカッと射してきて、一瞬全身がポッと暖かくなるのを感じた。あの気持のよかったことといったら…
140キロの長い距離を、それもタイム・トライアルと意識してしまうと、ペースなんてどうしていいんだか、さっぱり分からない。きっと下手なマラソン選手のように、ただ長距離なんだからという理由で、かなりゆっくりのペースだったらしい。その証拠に、脚力の差はあったにせよ、俺達より2分あとにスタートした保泉、松本両君が追いついて来たのは、30分としないうちだった。追いつかれてからは、彼らのあとを走ることになった。17号線は、市街地を避けるバイパスでよく整備されている。それと知らず、はじめは、どっちだろうとあわてた。
スタートして1時間程過ぎた頃、前の2人のあとについて行くのが苦しくなって来た。5m離れ、それを3mにしようとしても、全く出来ない。そのうち10m離れた。『向かい風のせいかな』と思った。20m離れるともういけない。前の2人がチラッと振り返った。かなりねばったがだめだった。初めは、前の2人に追いつくスピードが出ないだけかと思っていたが、そのうち前に進むことそれ自体が苦しくなってきた。信じ難いかもしれない。自転車をただ前方に走らせるというあんな易しいことがやっとなんだ。足の筋肉が硬直してきた。やっとの思いで、近くの菓子屋に行き、ジュースをもらい、そこにあったベンチにフラフラッとへんてこな気分で腰かけた。残念だった。心細かった。
「睡眠不足のせいかな。渡辺君のとこじゃ、4畳半に5人もいて寝にくい上に、遅くまで起きていて、4時間しか眠ってなかったなぁ。その前の日も、そういえば4時間くらいしか眠ってないな。絶対睡眠不足だ。でもいつだったか、何かに書いてあった。卓球の選手が世界選手権に出て、決勝の前日、緊張で一睡もしなかったけど、翌日見事に優勝したなんて。そうなると俺、根性ねえのかな」そんな事をボケッとしながら考えていた。
俺が坐っていた時、遅れて来たらしい守谷さんが、特徴のある低い姿勢で快調に目の前を走り去った。15分くらい休むと、どうやら行こうかという気になった。体の調子を試しながら、そろそろと走り出し、そのあとは、文字通りのマイペースだった。熊谷の繁華街の交叉点で、人数のチェックをしていた木村(治実)さんに会う。懐かしいという程大げさではないが、2時間ぶりで知った人に会って、ホッとしたような感じだ。高崎を目指して、再びマイペース。
高崎の手前の道端でパンク修理をしている黄色いユニホームの2人を見つけて、仲間入りした。加藤さんと吉田君だった。やっと先行者に追いついて、そのことより孤独感から解放されて、うれしかった。自転車を降り、道端の草の上に腰をおろして、天気の良いのに改めて気がついた。10分程も雑談しながら、吉田君のパンク直しにつきあった。高崎の鳥川に沿う道の川風が心地よい。高崎をちょっと出たところで昼飯として、パンやリンゴを食う。高崎からは、それまでとかなり趣のちがう風景が道のまわりに広がる。碓氷峠があるからというので、ギアをあまりおとすわけにはいかないから一層感じるのかもしれない。碓氷峠のふもと横川まで結構ダラダラと上っているのだ。
横川のドライブ・インに、誰かいるではないか!!しんがりの方を受け持つクラブ員諸氏は、競争はこの次とばかり、いや、あきらめ半分か?言ってみれば、実に楽しんでいるといった風に悠々と。そばなど食べ、雑談しながらくつろいでいた。俺もそれにならった。小1時間も、ここでゆっくりした。
ブルッと武者震いをして、自転車にまたがる。7人程でそろってドライブインをあとにし、すぐに碓氷峠にかかる。184個のカーブのあることをあらかじめ知らされるのは、実に嫌なものだ。威圧というか、むしろ、「おどし」と言った方が当たる。その上ご親切なことに、カープ毎にCいくつと表示した札がある。
ギア比は、どうしていいのか分んなかったが、すぐにサードでは無理と知り、C-1で止まって、一気にローにおとした。だけどちっとも楽ではなかった。不調というのか、それとも1年の時の実力は、あんなもんだったのか、上りは苦しかった。それでも痩馬の先走りというやつで、初め加藤さんのうしろを上っていた。カーブ数を書いてある札が怨めしい。C-10のところで『あと今までの18倍』などと考えた時の、あのゾッとするような気持は、碓氷峠を経験したサイクリスト以外には分かるまい。
C-10を過ぎたあたりから、どうした訳か、背骨から腰のあたりに鈍い痛みが停滞し始めた。耐えがたい痛さだった。俺は、どうしても降りるのが嫌だったから、我慢して上ることにした。というよりはむしろ、自転車から降りるのが、恐かったのだ。根性なんていうカッコイイものではなくて、峠まで10分の1にも満たないところで降りてしまって、そのあと19の9以上の道程(みちのり)を目指して走り出すことが何よりも嫌だからという、全く意気地のない動機で乗り続けた。腰の痛みは一向にとれなかった。そうなると自然スピードは落ちた。加藤さんは、ずっと先へ行った。篠原さんと小島さんが、俺の横をスーッと追い越して行った。
しばらく行くと、小島さんが足がつったと言って止まっていた。俺は自分のことで手一杯だったから、十分声をかけることもできなかった。その先、ちょっと行くと篠原さんが自転車を投げ出して大の字に寝ていた。そこで俺も休もうかと思った。しかし降りたあとのことを思うと、やはり降りる気にはなれなかった。余程俺のペースは遅かったらしく、そのあと再び篠原さんが抜いて行った。しかし、今1度俺は、大の字に寝ている篠原さんを見つけた。『兎と亀かな』そんな考えがフッと頭の一部でちらついたが、それは、ニヤリと笑うといった性質のものではなかった。非感情的な呟きだった。それからあとは、ずっと1人だった。俺は、腰の痛みをこらえて、自転車を進めることに、かかりきりになった。耐えがたいと言っても、実際には我慢できたんだから、それは正しい表現でないかもしれない。しかし、あの時の痛さ、辛さといったら限度ギリギリのものだったように思う。
『体をこわしてしまったら元も子もない。バカみたいに無理することはない。苦しかったら降りて休めばいいんだ。楽しむべきなんだ』という考えには、俺も賛成する。けれど俺達凡夫は、全く混み入っていて複雑だ。たまには、とことん頑張っちゃってもいいんじゃないか。そういうアホもいたって邪魔者扱いすることは、やはりないと思う。
カーブの数を書いた立札のおどしが恐かったため、しばらく見ないことにして、もうかなり行ったろうと思って見上げ、まだ峠の遠いことを知った時、落胆は大きかった。
ペダルを踏みながら妄想に近いかもしれない、いろいろなことが頭に浮かんだ。これは、ひょっとして無意味な痩せ我慢じゃないのか?
人が、そして俺ができる多くのことの中で、今こんなことに必死になってかかわっている俺は、どうなっているのか。降りたってちっとも構わない。降りるか?クルシイ!バカヤロウ!降りてたまるか!!1度も降りずに峠を上ることがそんなに誇らしいことなのだろうか。誇らしいって他人に対してか?やっぱり自分に対してか。両方とも大した誇りじゃないな。後者の場合だと自己満足だもんな。でも世の中、自己満足以外何がある?キザかな?まあいいや。まあいいなんて曖昧なのは良くないぞ!でも世の中に曖昧でない何がある?下らない?碓氷峠は俺に敵対しているのだろうか。違う。勝手にやって来た自分を棚に上げて、碓氷峠に8つ当りは、筋違いだ。俺は試されてるのか?誰に?俺にか?もうどうにでもなれ!!もしこの生命が全く白けちゃうような現実のものでないなら、この苦痛は、意味を持ち得ず、無視できるはずだ。どうだ痛くなんかないぞ!今意志が肉体を超越できたら、この生命は全く観念的なものだってことが証明されるんだ。
(これは俺が肉体的苦痛に出会った時、よくやる遊びだ。この幻想を持ちきろうと試みる。そして、できるかと思う。しかし、それはいつも俺の負けが結果される。君痛を我慢し、通したにしても、その間の苦痛は、やっぱり生身の実感であり、何よりも、そのあとに全く白けちゃう現実ってものが待ちうけており、それに俺は、再び否応なしにどっぷりと浸るからである)
苦しい時に考えることなんて、どうせしょうもないことに決まってる。半ば狂気かもしれない。まあ苦しまぎれの悪あがき、といったところが妥当な線か?どうしてあの時、意志はあんなに頑固に意志し、そして又肉体は、どうしてあんなにも苦痛に対応できたのか今もって分からない。やはり1種の狂気だったのかもしれない。
1人のアホともみえる行為は続いた。やがてC-140がカチッと目に入った。その時どうした拍子か、腰部に長く続いた、あの忌わしかった激痛が、スーッとひいた。唐突だった。
あの方は、この俺を見ておられたのか。都合の良い時だけあの方をひきあいに出すのは良くないかな。しかし、ありがちだ。第1、あれは、あの方でなくて誰に可能か?
ペダルが軽くなった。『やれるぞ!』そう心で叫んだ。体中の歓喜がそう確信した時、胸から喉へ熱い塊がグッと突き上げて来た。喉が押し上げられて苦しくなった。目からは、液体が溢れ出そうになった。数滴がこぼれちゃった。『畜生!何てこった。この俺が!女々しくもこんなことになっちまうなんて!!』足はクルクル今までの倍以上の速さで動き出した。『何でこんなことになっちまうんだ!!』熱い塊りは、なおも喉を突きあげた。『俺にまだこんなになることがあったのか、畜生!!』と思ったら、また1段と熱く突き上げて来た。喉をゴクゴクさせて『畜生!畜生!』と思い、思い、C-184までは一気に駆け上がってしまった。碓氷峠の標柱が見えた時、大声でバンザイくらい叫ぼうと思って縮みたが、さっぱり、音にはならなかった。
軽井沢駅まで2キロの下りをトップギアで思いきり飛ばして、多分あまりいい様ではなかったであろう顔面を、高原の風でごまかした。10月末は寒かった。
軽井沢で1足先に着いた加藤さんが、
「ノンストップで来たろう」と言った。
やっと「ハイ」とだけ答えた。そばにいた中村さんが、
「結構!結構!」
と言ってくれたのが、ただ、ただ無性にうれしかった。俺が1年生の時のことであった。
今年のことと去年のことを対比できる格好になってしまった。もとより去年より今年の方が情緒的に鈍くなったと否定的に思っているのでもなく、また、去年より今年の方が力強く成長したと肯定的に考えているのでもない。どっちがどうと価値判断するのは、俺の好みじゃない。そうあったという事実に対しては、謙虚にただ受け入れるだけである。
ただ俺の場合だけかも知れないが、峠を上る時の心情といったものに、ある興味を感じるのである。楽々上れた時は、それでよい。それなりに満足する。苦しい時、耐えて上り切った場合、峠では、途中の苦しさや、大げさな議論も忘れ、また充実感と征服の満足感に酔う。そうでなく途中でおりてしまった時、そんなにしょげることもないのに『俺は敗れた』と悔しく思う場合もあるし、悔しいには違いないが、『あんなアホなことやってられるか!楽しめばいいんだ!楽しまなくちゃダメだぜ』などと居直ってしまう場合もある
(これは、とっておきの逃げ道といえるかもしれない)。都合が良いと言えば、全くその通りなのだ。
蛇足が長くなってしまったが、このことを書いてしまった今も、「きまり悪いような感じがある。あんなことは、これからあと決してないだろう。ある意味においては、今までのサイクリングで、或いは、他を含んでも、最高のことだったと言えるかもしれないし、別に大したことじゃないとも言えるだろう。人間の意識、これこそいろいろで、複雑で、不可思議極まりないものはない。そんな数ある人間のうちには、そして数あるサイクリストの中には、こんなアホもいるんだくらいに軽く考えてもらえれば、俺としてもやり易い。
照れ隠しも手伝って、少しことをつき離して書いて来たが、あの時の気持は、やはりちょっとした感激だったと、素直に認めよう。
鎌北湖顔振峠 二年生企画ラン – 政経学部2年 宮崎
鎌北湖顔振峠 二年生企画ラン
政経学部2年 宮崎
心配された雨もあがり、その日、11月16日午前8時、集合場所である川越街道、環7陸橋下には、9人のクラブ員が集まっていた。
少ない。昨夜来の雨のため、勝手に中止と決め込んだ者が多かったと思われる。早速、2、3人に電話をかけ、呼び起こす。主将はすぐに追いかけて来るとのこと、中村さんも来ることになった。それにしても、2年生の参加がわずか3名とは淋しい。いや、はなはだ遺憾である。2年生企画ランの名が泣くではないか!!2年生にそれだけの責任感が欲しかった。
8時40分、中村さんを待つという仲田君を残して、渡辺君の先導で出発。もう空は晴れて、青空の広がる暖かい日となっていた。しかし、雨上がりの国道は水はけが悪く、前途の多難を物語るかのようでもあった。埼玉県に入り、銀杏のきれいな、とある神社で中村さん達を待つことにした。銀杏がとても美しく色づいていた。その色は、キャンパスの銀杏しか見ていない諸君には想像できないものであろう。それは自然の純粋な色であった。あえて書くことは避けよう。書き尽せないジレンマに襲われるだけである。百聞は一見に如かずである。
さて、2人の到着を待って出発。川越まではすぐであった。いさか回り道をして川越市内を通過し、川越線を右に見て走り続ける。1時間も走った頃、再び休憩。例によって、近くの店に駆け込む。
「ファンタ!!」
「牛乳!」
「このアンパンいくら?」
「ソーセージちょうだい!!」
やつぎばやに声が飛ぶ。秋の弱い日をうけ、歩道に座り込み、アンパンにかぶりついた。その時、サイクリストがひとり通って行った。しばらくして、またサイクリストがやって来た。それは、主将だった。荷物も持たずに、中山君の愛車にまたがり、いかにもがむしゃらに走って来たというふうだった。中山君は風邪をひいて来られないとのこと。総勢11名となって出発する。あとは鎌北湖までノン・ストップ。
舗装も切れ、いよいよ山中へ入る。鎌北湖を目の前にし、道は車の行列 – バスの通過にともなう渋滞である。こんな所まで車で来ることはないだろう。サイクリングに限る。得意顔をして追い抜く。予定より1時間遅れ、11時50分鎌北湖に到着。湖自体は、さして感動を呼び起こす程のものではなかった。ここで昼飯となり、皆で椎茸うどんなるものを食べてみることにした。まずい!!まずかった。それでも全部たいらげた。諸君が今度訪れた時には、是非試食をお勧めする。まずいということだけは請け合う。
この店のおやじさんに、顔振峠への道の状態を聞いた。自転車でも充分行けるとの答が返ってきた。1時間の遅れにもめげず、顔振峠チャレンジが決定!!この日は物好きが多かったようである。もっとも、ここで帰ったのでは、この日のランは全くつまらないものとしかならなかったであろう。さて、いよいよハイキング・コースヘ入る。すぐに道は上っている。きょうはハイカーが多い。
「きびしいですよ!!」と女の子の声。
「なんの、これしきぃ!!」と意地で上る。
しかし、やっぱりだめだ。あまりに厳しすぎる。当然降りて押した。視界は上るにつれて広がる。高い所は、やはり、気持がいいものである。なんとか乗れる所へ出た。左に崖を臨み、適度の上り下りの道を走る。紅葉にはちょっと遅いが、落葉を踏みしめてのサイクリングもしゃれている。快適なサイクリング・コースである。ただ、やけに左へハンドルが取られるような気がしてならない。
適度のスリルのあるコースでもある。どれくらい走った頃だったろうか、道を進めるうちに「顔振峠工事中、通行止」の標識を見つけた。とにかく前進あるのみで、どんなかなぁと前進を続ける。果たして通行止になっていた。右へ折れることにした。それは、一本杉峠を経て黒山三滝へ出る近道であった。一本杉峠には、かなりのハイカーが休んでいた。その中へ、ここまで自転車で来たんだぞと誇りを持って乗り込んだ。視界が開けた。ずっと下に、朝、そのそばを通った工場が小さく見える。こんなに高く上ったのかと感心する。
しかし、下りは、上りよりはるかに苦しかった。雨で道は滑り、傾斜もかなりのものだ。転倒者が続出。中村さんも腕に血止めのタオルを巻いての健闘である。ハイカーの姿も見られない。何か不安な道だ。そして、ついに木馬道の登場となった。ここにまで早同交歓会の影響が出るとは、全く恐れ入った。峠からかなり下り、ハイカーの姿も見かけるようになった。それにしても、スカートで登ってくる女の子には驚いた。あの滑りやすい道を、どうやって登るのだろう?滑って転んだらどうするのだろう?要らぬせんさくをする。三時、黒山三滝に到着。
日本のサイクリング史は、ここで輝かしい1ページを迎えた。俺の自転車が、黒山三滝到着その時点で、ついに6,000キロ走破を達成したのだ。それはアメリカ大陸横断にも余りある数字である。この足で走りきった6,000キロだ。多くの苦しみと楽しさを秘めた6,000キロだ。それは、そのまま俺の青春の記録である。その黒山三滝で、中山君の自転車がマシン・トラブルを起こした。おかげでゆっくり滝を見物できたが、何としても寒い。太陽はすでに近くの山影に隠れてしまった。修理もそこそこに帰路につく。そして飯能に着いたのが4時半。休んでいるうちに、あたりは見る見る暗くなり、ついに真っ暗。皆が走る意欲を失くしたようである。
「飯能のユースに泊まって行くか」の冗談も飛ぶ。
しかし、当然のことながら、そうする者は誰もいない。今は、ただ、この日のランを走り抜くだけである。重い腰を上げ、暗闇の中へと出発した。
早く帰りたい一心で、スピードは上がる。後期から入部した市川君にはきついランであっただろうが、その彼もがぜん張り切っている。しかし、ラッシュ時とあって道は混んでいる。たびたび道をさえぎられ、なかなか進めない。6時、ようやく所沢。藤井さんと渡辺君は、川越街道へ向かう。あとは全て田無へと急ぐ。その直後であった。西武線のガードを過ぎた所で検問にぶつかった。数人が止められる。何を隠そう、この私も実は無灯火。小さくなって謝り続けた。諸君に声を大にして叫びたい。壊れているものは早く修理しておけ!この夜は佐藤訪米の前夜とあって、いたるところで検問があり、このあと更に2度もつかまり、「歩いて行け!!」とまで言われた。
それはともかく、田無で解散したのが7時だった。企画の甘さを、大いに反省させられた。しかし、帰路を急ぐ俺の胸のうちには、楽しかったという思いがあるだけであった。たまには、こんな無茶なランがあってもいいだろう。本当にご苦労さまでした。走行距離は138・4キロ。
四年生追い出し 1年生企画ラン – 教育学部1年 砂子
四年生追い出し 1年生企画ラン
教育学部1年 砂子
1年生企画で本年度最後のクラブランは、締めていきたいと思った僕は、命知らずにも公用ノートに無展望なままにその思いつきを記した。どうも僕という人間は不用意なことをしでかして、あとで責任をかぶる傾向があるのである。早同交歓会しかり、最終ランしかり。Whereの選定には4年生の意向を入れて、早稲田祭の期間中の房総半島1周を考えたが、3泊4日となり個人負担がかさんで参加者が少ないことが懸念されたので、気軽で1泊ぐらいですむ所という条件で考えた。東京周辺でさえ不詳の小生は宮崎さんに頼る以外になすすべもなかった。出た答は和田峠、相模湖方面とあいなった。5万分の1地図を見ての所要時間見込み、勾配度などをテキパキと出す宮崎さんは無知蒙昧の僕にとっては驚異であった。
当日は30分遅れて出発、今までみんなにくっついて走るだけであった僕は、この日先頭を走ることになり、道路をまちがえたらどうしようなどと心配で、内心気も狂わんばかりであった。走りながら及川さんが、信号にできるだけひっかからないように、そして一定の速度で走ることなどなど、先頭を走る心得を話してくださったので気が休まった。調布で数人と合流して休憩しているとき、自動車からやおら外人が出てきて英話をまくしたててきたのだが、10数人の大学生がワイワイガヤガヤ15分もかけて、御岳山へ行く道路をようやく教えたというのはお粗末。ここにあらたゆて英語教育の貧困が問題とされなければならないではないか。とくに僕は英語に東北訛があるので混乱をひきおこすであろうというので、発言を許されなかったのは不本意このうえない。ブッブッ・・・。
八王子で昼食、ここで甲州街道をとれて陣馬街道を走る。見れば遠からぬ所でモウモウと真っ黒い煙がわきあがっている。火事にちがいない。「おもしろーい」の声がクラブの皆んなから起こったのだが、他人の不幸を乞い願い、自己の退屈心を一時的にも充たそうとする不心得な輩と、正義をまっとうする小生は一緒に走るわけにはいかない。(ユーモアを解釈しないからやりにくいの声あり)。
さて諸君、陣馬街道をひたすら走って行ったと思いねえ。天気は良し、なだらかな坂で車が少くてまことに快適だ。快適のむこうになにがあるとあなたは思います?それは、絶対自転車に乗れない勾配15%の和田峠なのであります。フリーランにするにあたってはお店の前で一時休憩して、お店のその日の売りあげをあげてやるのがならわし。この日もその通例にもれなかったが、この見るもあさましい買い食いについては、同志社大学のごとく、みやげものを除いて買い食いは一斉禁止してはどうか。経済的にも11月の早同交歓会に僕は買い食い禁止に恩恵を被ったなどの根拠から言うのである。
本日のアトラクションである和田峠にいよいよチャレンジ、「各自自己との闘いに勝利されんことを祈る」と小生は訓示したとかしないとか、しないほうに50円賭ける。生理的もよおしのため、ドン尻に出た僕は、まず1人つかまえ、2人つかまえ、途中休憩して、15%の勾配を上って行ったのだが、自己との闘いに勝利するということは程度問題であることをしみじみ悟った。峠の頂上はあまりに寒いので、あるものないものを燃やして暖をとったが、自転車に乗っているほうが暖いと思い出発した。
峠をおりるについてたわわに実がなっている柿の木が目についてきた。別れ道で後続を待つ間、道路脇の柿を自己の欲望の対象となして目を向けたが、ここで教養ある小生は「王戎不動」の中国故事を思いだした。王戎が子供達と遊んでいたところ、道端に柿がたわわになっているのを見た子供達は「ワーイ」とてんでに柿にむらがったが、ただひとり王戎だけは動かなかった。不審に思った者が「どうして柿をとらないのか」と聞いたところ、王戎は「甘柿なら道を通る人達がとって残ってるはずがないから、残っているあの柿は渋柿にちがいない」と答え、果してその通りであった。のちに竹林の7賢人の1人となった王戎は子供の頃から考え深い子だったらしい。しかし小生はどっちかというと馬鹿だから「プディングの味は食べてみなければわからない」とこじつけた。で、結局農家で干している柿を食べるのが正解だった。私有財産を犯すという以外は。
サイクリングとはずいぶん離れた話になってしまったが、これけ小生がひとえに自己顕示欲が強いことにほかならない。後続が遅いたのは連続してパンクを3回したおひとがいたためらしいが、小はこの1年間いちどもパンクしなかったので、パンク修理の経験なく、この最終ランでパンクしたい、パンクしたいと思っていたで、まったく羨ましいかぎりであった。そして相模湖・ユースホテルと一日は終った。
翌朝、起きてみると屋根に霜が降り敷かれている。いまさらながら晩秋のサイクリングを実感した。朝寝坊と自転車の整員が長びいたため出発が遅れ、薬王院での昼食は無理だろうと判断し、大垂水峠の登口で各自、パンを買うように指示した。しかし、思ったより早く薬王院に着いたため、パンを買ってもらったのが無駄になってしまった。
大垂水峠を相模湖側から初めて上るが、八王子側から上るよりも傾斜が緩やかで長いだけの、比較的つまらない峠であると思う。峠の頂上から横道にそれて高尾山へと走る細道は、ひと気もなく急に山奥へ入った感じ、紅葉限りなく良しといったところ。高尾山頂へ続く最終コースは、自転車をかついで上るわけだが、ふだん世話になっている連れあいの情がこうじて新鮮味あるサイクリングの一形態ではある。現代版畠山重忠(畠山重忠はくだり坂で自転車ならぬ馬を背負うのは小生知っているのであるが、物語進行上勢いこう書いてしまったのである)は霜がとけて多少やわらかくなった道を上って行ったのであるが、あいにくの曇り空で遠方はかすんでよく見えない。
早い昼飯をすませて、薬王院に下り、うっそうとおい茂った杉林の道を下って高尾駅に着いた。野猿街道を通っての帰り道はしんがりを受け持ったが、しんがりは、後方からの自動車とか、皆んなが整然と走っているかどうかを注意しなければならない。このランは夏合宿不参加の小生にとって、たいへん勉強になった。この頃から陽ざしがよくなって、ポカポカと暖かい小春日和の午後に、多摩川べりを走るのは最高の気持ち。途中、土手が切れていたので、ケッまくって・・いやそれほどのことはせずにすんだが、自転車を流れの向う岸へ渡すといったハプニングもあった。
全員が無事に解散地である関戸橋へ着くことができた。ここで4年生を胴上げして、4年生にとって大学生活最後のクラブ・ランは、幕をとじた。これが小生の1年生時の最終ランであります。
ドンキホーテ的主観主義 – 法学部2年 吉田
ドンキホーテ的主観主義
法学部2年 吉田
セルバンテスの「ドンキホーテ」を読んだ人間は、トルストイの「戦争と平和」を読んだ人間同様多くはないだろう。ぼくは、このセルバンテスの小説を大学1年の夏に読んだ。そして感じたことは、この長編小説は、一般に言われているような単なる、間抜けな男の物語などでは決してなく、夢あり恋あり涙あり、それらを集積総合した出傑の1大名作であるということだ。
最後の場面になると、サンチョ・パンサとともに本当に泣き出したくなってしまう。恐らく、その時点でぼくは、「ドンキホーテ・ラ・マンチャ」が自分自身の内面に強く脈打っていることを発見したのだ。あの有名な、風車に向かって突進していく場面で、サンチョ・パンサとともにドンキホーテを引き止めようとしたのは、他ならぬぼく自身であったはずなのに、風車にはね飛ばされ地面に叩きつけられた、騎士の姿をしたおかしな男も、実はぼく自身だったのだ。何故なら、その場面でぼくは、強烈な「痛み」をじかに感じたからだ。そして、厳密な言い方をすれば、それはこの拙文を読んでいる第三者自身でもなかったかということだ。イヤ、冗談はよしてくれ、俺はそんな頓馬じゃない、と言うならば、彼は正に「ドンキホーテ的主観主義」者だ。
柳田謙十郎という哲学者によれば、われわれの人生は3つの「闘い」から成り立っている。1は「自然との」闘い、2は「社会との」闘い、3は「自己との」闘いだ。ぼくなりにそれを解釈していこう。自然との闘いとは、つまり、われわれの生活はどんなに高度に発展しても、基本的にはすべて環境的自然によって規定されているということだ。しかし、自然を開拓しこれを征服しようと、たちむかい始めた時、人間はもはや単なる環境的自然の一環ではなくなった。自然を自己の「対象」としたのだ。
この時以来、人間の存在は「闘う」存在となった。それは、つまり「社会との」闘いであり、つまるところ「自己との」闘いだった。それ故、闘う限り人間は生きている。闘いの止む時は紛れもなく人間の胸の鼓動が止まった時だ。この意味で、よく言われる「生き甲斐」とは、闘う精神の燃焼の中にある。だから、「闘わない」人間、或るいは「闘えない」人間の顔は生彩を欠き、瞳はくもる。サイクリングクラブでの生活1つを取ってみても、「自然」「社会(クラブ)」「自己」という図式通りの3つの闘いを経験せずにはいられない。
その中で、例えば、美幌峠或るいは西吾妻スカイバレーといった峠・坂を上っていく自分の姿を想像してみると良い。炎天下、或るいは土砂降りの雨の中でペダルを踏み、ひたすら峠を目指す自己との闘いの中では、何か、自分が絶対に環境的他者によって左右されることのない「主体的自己」であると感じずにはいられない。それを生真面目な言い方をすれば、自分が真に生きている、「青春」といった甘味な概念の中をひたすら突走っている、と感じられるのだ。この場合、坂に負けて泣き顔を見せた時、他の言葉を使えば、支配的環境に屈服してしまった時には、闘いに敗れ、主体的人間としての生きた生命はない。峠に着いた時に、虚しい気持ちに陥るのがせいぜいだ。少なくとも、ぼく自身そう思える。何故なら、1つの峠を上ろうと思った時、僕は峠という「自然」と、吉田という「自己」に「闘い」を挑んだからであり、その賭けに負けてしまったからだ。
しかし、そういう闘いを挑まなかった人間にとってぼくは、「ドンキホーテ的主観主義」者に早くも陥っている。「峠未発見者の戯作3昧」と言われても仕方がないのだ。けれど、それは「逆もまた真」なのだ。クラブを逸脱したすべての社会生活の個人対個人の関係においても、大概は相手のやっていることは馬鹿らしく見え、自分のしようとすることは「もっともらしく」見えるものだ。そう考えれば、自己を絶対化し、或るいは何者かに絶対者を設定しようとすること自体、滑稽に思える。別の言い方をすれば、価値というものを動かないものと考えたり、歴史を固定した過去の断絶したものと見たりすることは、凡そ意味を持たない。
この場合も、歴史観、価値観を固定したものと見ている側からすれば、そうは見ない側の人間、つまりぼくを「ドンキホーテ的主観主義」者と呼べるはずではないか、そう言えるだろうか。それは言えない。何故なら、観念論つまり唯心論というものが、唯物論に優っていることを論証したものを、ぼく自身読んだことはないし、また事実現われていないからだ。いや、現われていないというのは正しくない。それは寧ろ、永久に現われない過去の消え去っていったものだ、と言ったほうがより適切だろう。主観的真実はどうにでも覆えすことは出来ても、客観的真実は容易に覆えせないのだ。
話がそれてしまった。要するに、ぼくが言いたかったことは次のようなことだ。柳田謙十郎は、人間は3つの「闘い」を通じて即ち人生を生きると言った。それならば、闘う精神の燃焼の中に、われわれは自分が「生きている」という「証」を、つまり「自己の主体性」ということを感じているはずだ。つまり、「人間とはなにか?それは主体である」と。
人間とは主体である以上、われわれの毎日の生活もその積み重ねでなくてはならない。固苦しく考えれば、人生という大げさぶったものも、自分はこう考え、こう生きたのだと言えるものでなくてはならないし、またそうありたい。すると、「棺桶から見た」人生、つまりそれに発する個人的生き方というものが当然生まれてくる。
「棺桶」から眺めた自分の一生というものは、ひどく短いものだ。そして、そこから垣間見た他人の一生も、自分と同様ひどく色彩に欠け、結局は生まれても生まれて来なくとも良かったもののように思えてくる。それならば、今現在、早稲田大学の学生として、或るいはサイクリングクラブの部員として生活し、生を生きている吉田という個人は、「意味」を持たないのだろうか。それを肯定することはひどく寂しい。肯定はしなくとも、疑問を持ち続けることはひどく苦しいものだ。そういう時に、一筋の光明を差してくれるもの(思想)がないだろうか。つまり、自分の一生は決して「予見」されたり、「運命」づけられたりしたものではないのだ、という拠所が。そう考えれば、自然や社会や、特に自己との「闘い」ということの中から(柳田は勿論意識しなかったけれども)、サルトル流の「実存主義」的生き方というものが当然生まれてくる。
サルトルは何も難しい新奇なことを言ったのではない。われわれが、前向きに生真面目に生きようとする時に、実存哲学はわれわれ自身の内部に立派に芽生えていたのだ。つまり、或る人間の生まれる以前の人生は、その人間にとっては無であって、何の価値も持っていない。
その人間の可能性や才能は、その人間の行動の中にしか見い出せず、それらを予測することはできない。人間は主体性を通じて価値観を創造するのであって、それは決して先験的に存在するものではない。われわれの将来は、すべて現在のわれわれの主体的行動によって決まってくるのだ。被害妄想のようでもあるけれど、ぼくのように社会的身分の低い家に生まれ、勿論社会的門地などなく、経済的にも逼迫し、教育も2流の教育を受けつつ現在に到っている2流の人間にとって、実存主義はいわば下剋上の機会を与えてくれようとしている絶好の思想なのだ。何故なら、ニッポンにもベイコクにもエイコクにも確固たる様々な差別(権威主義)が存在しており、矛盾だらけの社会体制にもかかわらずその中で安穏と生活を続けて、社会を一方的に治めていこうとする「大名」が多くいるからだ。
その「大名」や、様々な「偏見」「差別」を下剋上していかなければ、水呑百姓はいつまでも水呑百姓で終ってしまうだろう。以前、ぼくは、このように考えている他人をみて嘲笑したものだ。おまえは純粋すぎるのだ、おまえは単純なのだ、世の中はそれ程甘くないんだよ。と決まり文句のように言ったものだ。しかし、現在では、そう言おうとすると顔が蒼ざめる。ひどい自己嫌悪に陥ってしまうのだ。
この場合、ぼくは2つのことを考えている。そして、その2つの全く方向の違うベクトルは、互いに打ち消し合ってゼロになり、ほく自身を煮え切らないものにしている。ぼくの中にある「現在」という時点はいわば1種の過渡期であり、青年期特有の矛盾との対決の時期なのだ。
「2つのベクトル」とは、共産主義社会を目指していこうとして、現在の権力と闘うことであり、もう一方は、現在の社会体制を肯定した上で、その中でいかに権力を握っていくかということだ。ハーバート・リードは、「理想的存在のあり方を自由に想像させると、人間精神は権威主義への悲惨な傾向を示す」と述べている。驚くべきことに、ぼく自身将にその傾向を持っている。つまり、理想主義はすべての進歩の原理なのだが、それに伴う弊害は極めて大きい。
ぼく自身、不当な搾取のない理想社会と、一方、名誉、地位、経済的豊かさを備えた自分の未来というものを考えていく過程で、どちらにも共通するものとして或る種の「権威」ということを考えざるを得ない。それに向かって、ぼくの主体性を邁進させていこうとするのだ。問題は、どのような方向づけをもって「闘い」を推し進めていくかということだ。勿論、2つのベクトルは正反対に向かっている。ぼくは、このうちどちらかを確実に選択する必要性に迫られている。いわば、「社会」との闘いの渦中に躍り込んだのだ。
サイクリングという、言うならば1種の遊びのクラブの部誌に、このように居直った形で自分の考え方を披露するのは相当滑稽だ。何故なら、われわれの世代というのは、世の中の価値というものが覆えされ、それ自体が多元化されている。その中では、文学サークルならいざ知らず、反教養的に装い、気取らないのが無難になって生真面目に生きようとする姿勢はひどく軽蔑される。ぼく自身、それは12分に心得ている。しかし、ぼくにとって、文章を書くということは相当重要な課題を含んでいる。それを茶化すわけにはいかない。そこに全自分を投入したい欲望を絶ち切ることはできないのだ。
かって、大河内一男は、「傍観は既に1種の罪悪だ」と述べた。ぼくは、その言葉の重みを痛く感じる。世界を様々に解釈する時代は過ぎた。問題は、それを変革することだ。ぼく自身、人目に映えるほど実際は傍観者ではないけれど、極端な利己主義者のため、自己に還元されない行動は内面で制約している。それは、クラブといろ共同生活の場ではタブーだ。以前のぼくのように、犠牲的精神を発揮できるようであれば、ぼく自身、随分気が楽になる。
けれど、自分としては、現在の依恬地な自己を大切にしていきたい。それから派生する、様々な誤解、中傷、寂寥、孤独感というものを、更に深めていきたい気がする。何故なら、自己と今こそ対決してみたいからだ。そこに自己の主体性を見い出していきたいからだ。どん底につき落とされるまで、ぼくはそれを止めない。その時初めてぼくは「俺だ」といえる自分を確立できるのだと思う。「まじめに、しかし、しかつめらしくなく」と言ったアンソニー・バージェスのことばは無視する。つまり、「まじめに、しかも、しかつめらしく」。
だから、そういう「風車」に向かっていこうとするぼくは、まさにドンキホーテ的主観主義」者と呼ばれるに相応しい。
さすらいの青春 – 教育学部3年 星
さすらいの青春
教育学部3年 星
今日もまた走り続ける。旅を行く俺の心にさすらうものは何だろう。思い出の踏襲か、恋人の面影か、または偉大な自然か、それとも温かい人情だろうか。ふと、疲れた心に安らぎを感じさせてくれるものなら、何でもいい。俺はそんなさすらいの青春が欲しいのである。
(1)
異様な感触に目が覚めた。それは羽根のように柔らかく、なま温かく、息づいている。ハッとして飛び起きると、小猫がそばにうずくまっていた。猫のあの眼つきが、とても気味悪く感じられた。黒くすすけた天井を見上げながら、夜の明けたことを知った。なんとなく、かゆみを覚え、目を移すと、手といわず、足といわず、顔にまで赤い発疹ができている。ここはどこだ?瞬間的に、昨日のことが思い出された。
雨が降ったり止んだりしている空を気にしながら、三面川にかかる橋を渡ると、ヒョロヒョロともやしのように伸びた、背の高いサイクリストが声をかけてきた。
「こんちは!!あなたは、今日どこまで行くんですか?」
「僕はねぇ、予定だと村上までだったんだけど、ユースホステルを断わられたもんだから、走れるだけ走ろうと思って、海の見えるあたりまで・・・君は?」
自転車から降りて話し出した。
「僕は北海道に行くんです。今夜はこのバス停に泊まろうとしてたら、この人が泊めてくれるというんです。一緒に泊めてもらいませんか?」
「ええ、、、」
彼の手の方に目をやると、同じ年頃の若者が微笑んでいた。そばにいる2人の子供達は、珍らしそうに、大きな荷物をつけた自転車を見ている。
「どうぞ泊まっていって下さい。別にたいしたことはできませんけど、、、」
「はぁ、ありがとうございます。でも、いいんですか?」
どちらかというと、他人の世話にはなりたくない、と思っている俺ではあるが、またいつ雨になるかも知れない空を見上げて、1晩泊めてもらうことにした。こんなことが現実に自分の身に起きたのは、これが最初であった。そして、また最後であろう。話には何回か聞いていたが、世間は広いようでもあり、狭いようでもある。見も知らぬ他人を泊めてくれるなんて、親切な人がいるものだ、と昔人のことばを思い出した。
すぐ近くの、田舎によくある雑貨屋に案内された。出てきた血色のいい顔をしたおばさんに挨拶をした。このおばさんをはじめとして、この土地の人のなまりがひどいのには全く閉口した。味わいはあるが、テレビを見ながら話す主人のことばがわからない。早口で、しかも東北弁に似たなまりのため、話は半分位しか通じなかった。同じ新潟県でも、こんなに違うのか、と言葉の世界の広さに驚いた。向こうはこちらの話がわかっても、こちらは向こうの話がわからず、顔ではいかにもわかったように笑っているものの、頭の中では何のことか一生懸命考えていたのである。巻町の高校生だという彼も、おそらく同じ気持だったに違いない。
夕飯も遠慮せずに食べ、すすめられるままに、風呂にも入った。こんなに歓待してもらっていいのだろうか、とかえって気味悪く思い、夜中に身ぐるみ全てはがされ追い出される場面を想像して、いささか不安になった。
いつもは使っていないのであろう、ザラザラする畳の上に2人の床がとられていた。旅の話をしながら眠ろうとしたが、夏の夜はまだ暑さを残していた。しかも、どこからともなく押し寄せてくる蚊に悩ませられたのでは、とても眠れるものではなかった。プューンと聞こえていた音が止む。バチッ!!降りたと思われる所に、力をこめて一撃する。暗闇の中にはかない抵抗は続いた。疲れた身体を襲撃されるのは、とても辛いものであった。しかし、いつしかまどろみ、あの爆音も聞こえなくなってしまっていた。朝、起きて驚いた。手、足、腕、顔などあらゆる所に、その爆撃のあとが残っていた。しめて15ヶ所。かき始めるとますますかゆく、どうしようもなかった。しかし、人の親切心を思うと、そんなことは口に出せるものではなかった。
空は、昨日と同じように、どんよりとしていた。朝食後、丁重にお礼を言って、2人はその雑貨屋をあとにした。まるで2人を待っていたかのように、すぐに雨が降り出した。雨が降ると走りが速くなるもので、温海までは一緒に走っていたが、次第に離れてしまったらしい。海が見えなくなって鶴岡に入る手前の峠らしい坂道で、2、30分雨の中に呆然と彼を待ったが、ついに来なかった。どこかで雨宿りをしていたのかも知れない。彼とはそれきりになってしまったが、なぜか会いたい気がする。しかし、今となっては、彼の住所を知る由もない。
この日は、出発してからずっと降られっ放しの一日で、ずぶ濡れになって鶴岡駅に着いた。秋雨前線が居すわっていて、大雨洪水注意報が出ているなどとは、全然知らなかったのである。
「東京 — 新潟 – 青森1人旅」
(2)
俺は自然との対話を求めて旅に出る。それなのに、旅先で知人に遭遇すると、懐かしさからくる安堵感を覚える。知らないものばかりの旅への不安、そこで感じる郷愁がそうさせるのであろうか。
太陽はだいぶ傾きかけていた。佐多岬への道はしつこく、長く感じさせた。人家の少ない山道で、心の中には孤独の寂しさが募っていた。ようやく大泊に着いた時には、落ち着いた淡い光が、周囲の景色を柔らかく包んでいた。九州を走り回ろうというこの旅は、高校時代の友人が一緒だった。彼にとっては、サイクリングというか、長期のツァーは、これが初めてだった。いつもかなりの距離があくが、よくがんばっている。しかし、岬の突端までの有料道路では、さすがに彼は疲れたと見えて、バスに乗って行くと言い出した。俺は、何としてもこの自転車で走りたかったものだから、別行動を取り、岬の公園で会うことにした。さあ走ろう、と料金所に近づくと、どこかで見たような姿の男が目に入ってきた。見たはずである。料金所から出てきたのは、クラブの渡辺君であった。そして、ぞろぞろと仲田、中山、保泉の3名が出てきた。懐かしい気持がした。
「星さんじゃないですか」
「よお、何だ。どうしてここに?」
「時間の余裕がないので、指宿から船で来たんですよ」
「俺達は明日行くんだけど・・・黒くなったなぁ」
「そんな格好で走っているんですか?」
「そうだよ、格好悪い?」
「いやぁ似合ってますよ」
「山なみハイウェイで雪に降られて、まいりましたよ」
「へぇ、きつかった?俺達も福岡のあたりでちょっと雪を見たなあ。まあ計画通りに走っているけど、九州って思ったより寒いんだなぁ。天気とお金だけは、あてがはずれたよ。ハハハ…」
話すことはいっぱいあっても、どういうわけか出てこない。彼等の顔を見ているだけで、様子がわかるのだ。計画では、彼等と俺達とはだいたい逆回りのコースだし、ぶつかる所では、俺達が彼等を追いかけるようになって、会えることはないはずだったのだが、予期せぬ出会いにとてもうれしかった。早速、汚ない5人が顔を並べて写真におさまった。もっと話したかったが、バスの時間がないということで、話もそこそこにしなければならなかった。しかし、彼等に会えたということは、今まで沈んでいた俺の心に少しの明るさを取り戻させた。一緒に走ってみたい気持がした。相棒は岬行の最終バスに乗り込んだ。
佐多岬からの展望は、ぼんやりとかすんでいて、視界はあまりきかなかった。海の向こうに硫黄島の煙がたなびいていた。道路の閉門時間ぎりぎりだったため、駆け足で走り回らざるを得なかった。突端の灯台まで行きたかったのに、これも時間が許さなかった。展望台の崖下の海の水が、底が見えるほど澄んでいた。岩に砕け散る白い波と青緑の海とが、対照的なつりあいをしていた。
帰り道に見た没しようとする淡橙色の大きな太陽の光は、シュロやフェニックスの葉に柔らかく照り映え、俺の影を長くさせていた。こんなに大きな太陽を見たことは、かつてなかった。自然との対話に心がなごんだ。その美しさに酔い、その淡さを悲しみ、その熱情をうらやみつつも、人間と人間、人間と自然との出会いの偶然性を感じていた。
次の日の朝、太陽は顔を見せてくれなかった。東の空の雲が赤く染まっているだけで、日の出を見たさに1度は起きたものの、再び眠ってしまった。雲行きも怪しく、国民宿舎を出発する時にはどんよりとした空だった。そして、昼過ぎには風が出て雨模様となり、佐多 – 山川のフェリーは揺れて気分は悪く、身体は冷えた。2人が頭を寄せて考えたことは、開聞岳に登るのは翌日にして、とにかくジャングル風呂に飛び込もうということだった。天気はままならぬものである。
「30日間九州1周」
(3)
サイクリングをしていると、いろいろなことにぶつかるものである。走っていると話しかけてくる人がいる。知らない土地の、知らない人の、その風土がはぐくんだなまりのある、あのことばが俺は好きだ。
「あんた、どこから来なすったぇ?」
道を尋ねると、その会話のどこかにきまってこんなことばが出てくる。そして、驚嘆のため息が続く。話し好きの人ならば、仕事の手を休めても、老婆心もまじえて親切に教えてくれる。こんな旅をする者に悪い奴はいないと思ってのことか。それとも、まだ俗化されていないのだろうか。そんな人ばかりなら、サイクリングの旅は面白く、楽しいものである。
夕陽がうろこ雲に映え、きれいな夕焼けである。今日は、まだ建設中のキャンプ場にテントを張ることになった。夕暮れの静かな田沢湖の水面にも、夕焼け空があった。山影もその色を濃くしていた。近くの湖岸にもキャンパーの黄色いテントが見え、楽しそうな声が聞こえてくる。そんな光景にうっとりしていると、近くの農家の人であろう、30過ぎの男がホンダのカブでやって来て、遅れた後続隊を待っている俺の前に止まった。日に焼けた、いかにもたくましい男だった。俺の前には、キャンプにはもってこいの薪が積み上げられていた。どうやら、それが盗まれていないか見回りに来たらしい。薪を縛ってある縄の具合を見ながら、そばにいる俺に聞こえるような大きな声で口にした言葉にそれを感じた。
「また減っているなぁ」
疑惑の目つきが俺の方に向けられた。明らかに俺達が盗んだように決めつけている。今までに、かなり盗まれたのであろう。
「今夜、ここにキャンプするんか?」
「そうですよ」
「向こうの方に、キャンプ場があっただろうが・・・・・・?」
「ええ、でも満員なので、そこの、県民の森の工事をしている人が紹介してくれたんです」
「ここはまだできていないんでのぅ。どこから来たんだい?」
「青森から…」
「自転車で?おらぁ青森の出身だけどよぉ、十和田なんかきれいだったろが?」
「ええ、青森から十和田、八幡平を通って・・・今、合宿中なんですよ」
「だって、そんなのをかついで走ったら、重くてしょうがないでしょう」
「ああ、それであんなにいるんか。飯はどうすんだ?」
「自炊ですよ。大きな鍋で2つ炊くんです」
「へぇ、すげぇなぁ。米なんか買いに行くんか?」
「だって、そんなのをかついで走ったら、重くてしょうがないでしょう。」
「一日どれ位走るんかのぅ?」
「そう、70キロ位かな。1人の時は130位だけど・・・」
「大学生か?」
「ええ、早稲田です」
「ふうん」
話していても、何となく気乗りしなかった。できることなら、こんな男となんか話したくなかった。いやな時に先発隊になったものだ。確かに、見たなりはあまりいいものではないが、人のものを盗むほど落ちぶれてはいないつもりである。
日もとっぷり暮れ、星が出た夜空の下での夕食もうまくなかった。風邪がなおらなかったせいもあろうが、あの男の態度がしゃくにさわった。美しい夕映えの静かな湖も、俺の心の中では、濁った泥水が激しく波立ち、姿を変えていた。悪劣キャンパーの馬鹿野郎!声にはならず、心に叫んだ。あとから来たキャンパーが不快になる。そんな旅は、俺はごめんだ。こんなわけで、田沢湖の印象はいいものではなかった。
翌朝、男に対する悔しさもあり、あてつけもあり、わざわざ買ってきて残った薪の数束を、彼の薪の山まで運んだ。その日の夕方、いつものようにやって来たあの男は、こうつぶやいたかも知れない。
「おや、今日は増えている。おかしいなぁ?」
「東北縦断夏期合宿」
(4)
こんな日に限って、どうしてこんなユースホステルを選んだのかなあ、といらだたしさを感じながらペダルを踏んでいた。阿蘇から高千穂までの距離は、初心者ではちょっと無理だと思い、わざわざ近いYHを選んだつもりが、町の名を聞いた感じでは近くても、実際には、そのYHは町のはずれの奥にあり、かえって遠いものだった。机上の計画の甘さをいやでも味わわなければならなかった。
正調「五木の子守唄」を聞かせてくれた、風変わりで好感の持てるペアレントのいる阿蘇YHを出てから、ずっと雨が降り続いている。途中、雪も混じり、手足は冷たかった。おまけに、相棒は道を間違えたらしく、どうしてもその姿をとらえることができない。阿蘇の外輪山を越すような国道265号線は、通る車こそ少なかったが、雨のため、ぬかるんで走りにくかった。
高森からつづら折りの峠を上ると、この道はいかにも山道らしくなった。同じような景色が続き、時間は進んでも自転車は進まず、まるで同じ道を回っているような錯覚さえした。時たま現われる集落も似たようなものであった。小さな、わかりにくい標識しかない218号線との分岐では、道を間違えてしまった。時間と労力が惜しかった。3けたの国道の継子扱い的な例をかいま見た感じがした。せっかく上ったと思えば、今度は下っているというこの道の長いこと!!山また山の地方である。もっとも、九州を横断しようとしているのだから、山の中を走っても不思議ではないのだが、とにかく疲れていた。YHの予約をキャンセルしようという気も、なくはなかった。
馬見原の分岐で、265号線は五ヶ瀬川に沿って続くのである。川の流れとは逆に、これからまだ10キロ程走らなければならなかった。昨夜、地図で予定のコースを見ていると、YHは鞍岡ではなく、もうひとつ奥の本屋敷にあった。確か予約のはがきには鞍岡と書いたはずなのに・・・まあ、何とか行けるだろう、と出発はしたものの、予想以上の山道だった。この疲れている時に、10キロは軽いものではない。いつか着くだろう、という気持でペダルを踏んでいた。近くの山には霧がかかり、みぞれのような雨は止まなかった。流れのせせらぎも、あまり耳に入ってこなかった。バスがやっと通れる幅しかない道を走った。寒い。人気のない、さみしい道である。
ようやく本屋敷の部落にたどり着いたが、YHのような建物は全く見当たらない。わずか数軒しかない部落なのに、まだ奥に入らなければならないのか、と思ったら、ますます寒さを感じ、泣きたくなった。自転車は勿論、ズック、靴下まで泥に汚れていた。近くの店で聞くと、すぐ前の家がそうだという。助かった!しみじみ思った。しかし、あのJYHの看板も何もない。ただの民家である。本当にこれがYHなのか、と疑ってみた。こんな辺鄙な所だから、よほどの物好きしか来ないのだろう、と思いながら、車がはねた泥で汚れた戸を開けてみた。ありふれた民家で、全然ユースホステルなどという感じはしなかった。
可愛いらしい女の子が出てきて、人なつこい笑みを浮かべた。その後からペアレントの奥さんが出てきた。女の子は、シルクハットのような帽子をかぶったり、取ったりしていた。もう外は薄暗く、奥さんと話をしていると、はぐれた小鳩のように相棒がようやく到着した。顔まではねを上げて泥だらけである。やはり出たばかりの宮地で、57号線との分岐を間違えたということだった。女の子はピンキーの真似をして歌っていた。
「わぁたしははだしでぇ・・・・・・」
室にある表紙の変色した落書きノートを、何とはなしに開いて見た。書き初めが1年程前である。それによると、最近泊まったホステラーは2月25日。今日が4月9日だから、半月の間、誰も訪れていないことを示している。こんなYHがあるだろうか。いつも満員で、若い声がうるさいほどに響いているYHしか想像することのできない俺にとっては、まるで信じられないことだった。ノートにはいろいろなことが書かれてあり、家族的な扱いに暖かさを感じたとか、都会の騒音から逃げてきたとか、同宿人がいなくて久し振りにのんびり眠れたとか、意味のない文章の羅列の中に、俺は、何かしら同じような旅をしている、まだ見ぬ若者達の青春の無鉄砲とも思える冒険心、行動に対する無頓着さを感じた。
こんな所にやって来るホステラーは、誰もがそうなのかも知れない。峠を越すと隣村は「ひえつき節」で有名な椎葉村だという。このYHの唯一の宣伝材料であるが、あまり知られてはいないようだ。この俺もそんなことは全く知らない1人だった。
ここの風呂がまた気に入った。山奥にふさわしかった。俗にいう「五右衛門風呂」である。俺は生まれて初めて、こんな風呂に入った。セメントで造った釜の中に入っていると、下から熱せられてくるのを感じる。何となく情趣があり、山の中に来たなあという遙かさを感じた。おそらく、こんな風呂のあるYHは、この松岡ホステルだけであろう。雨で冷たくされた身体の芯まで暖めてくれた。狭い釜の中に身を沈め、今日のコースのきつかったことを思い出していた。風呂から上がると、疲れのためか、相棒と話すこともなく、すぐ眠ってしまった。
道を隔てて流れる川のせせらぎが、やかましいほどに、雨が降っているように聞こえる。夜が明けていた。一瞬、また雨かと思って窓の方に走り寄った。ガラス窓を開けて目に映ったのは、澄みきった青空と緑あざやかな葉であった。すがすがしい山の空気である。土の匂いがした。苦労して来ただけの甲斐のあるYHだ。今度ホスアラーが来るのはいつだろう。またしばらくは誰も訪れないかも知れない。
椎葉越えもしてみたかったが、山道で険しいというし、以前からの計画を変えたくはなかったので、予定通り、高千穂に向かって2人は出発した。こんなYHがまだあるんだなあ、という感慨が心をかすめる。相棒も同じだろう。来てよかった。朝日の中を走る俺の気持は、きょうの空と同じように、昨日とは全く逆の気持だった。
「30日間九州1周」
雨の七夕 東京-青森ひとり旅 – 政経学部2年 宮崎
雨の七夕 東京-青森ひとり旅
政経学部2年 宮崎
眠い目をこすりながら、テントから顔を出した。川は朝もやに包まれ、雨の近いことを知らせている。ここは平大橋の下、夏井川の川原である。東京を出てすでに3日目。俺は、合宿参加のため、青森までのひとり旅に出たのだ。台風一過の東京を立ち、順調にここまで来たが、ついに雨だ。ポツリポツリと降ってきた。さあ、雨との競争だ。休めば追いつかれ、また引き離し、また追いつかれて引き離す。
おまけに、国道6号線もここにきて、厚木街道ばりの上り下りの連続である。そして相馬を過ぎたあたりから、その雨はいよいよ本物となった。もう全身ずぶ濡れだ。こうなれば、休もうなんてことは考えない。一刻も早く仙台に着きたい、と一心にペダルを踏み続ける。雨は激しく顔を打ち、滝のように流れ落ちる。濁った水をいっぱいに集めて流れる阿武隈川。その流れに目をやり、阿武隈橋を渡る。仙台も目の前、仙台バイパスを右に見て旧道へと入った。しかし、バイパスに別れを告げてからも、仙台は遠かった。雨の日は日の暮れるのが早い。6時40分、ようやく仙台駅に到着。七夕の夜だというのに、雨はいっころ止もうとはしない。
明くる8日も雨。仙台駅のテレビは、大雨洪水注意報を知らせている。その雨の中、松島へと向かい、国道45号線に入った。しかし、この道はいたるところ冠水しており、車に泥水を浴びせられながら、水をかきわけ、かきわけ進むありさま、ついに「国道冠水の為、迂回せよ」の掲示。それを無視して直進する。これがそもそも間違いのもとであった。確かに、冠水の状態はそれまで以上にひどく、どちらか一方のペダルは完全に水の中にあった。一瞬、引き返そうかとも思ったが、とにかく行ける所まで行こうとペダルを踏み続ける。そこへ、土地の少年が声をかけてくれた。
「この先、行けませんよ!!」
「こっちへ曲がった方がいいですよ」
それではと、ハンドルを左に向け、曲がろうとしたその時、「アッ!!アッ!!」と少年の声。
すでに遅かった。冠水していてわからなかった道路脇の溝へ前輪を落として転倒。俺は水の中へ放り出された。なんとぶざまな姿よ!!おまけに荷物もみんなずぶ濡れだ。もうどうにでもなれ!
倉庫の軒下を拝借して、張ったテントの中で、荷物を広げてみた。バッグの中の荷物は、まだ半分水につかったままだった。着替えはもちろん、寝袋もみんなずぶ濡れだ。乾いているものは・・・何もない。走る意欲もなく、濡れた衣服を広げ、しばらく眠ることにした。そして、2時間も寝ただろうか、目を覚ましたのは1時過ぎだった。
走ろうという気力もなかったが、こうして震えていてもしょうがない。テントをたたんで、再び雨の中へと飛び出した。日本三景のひとつとまでいわれる松島の海も、ただの濁った海でしかない。4号線へもどるべく間道へと入った。かたわらを流れる川は、満々と水をたたえ、今にも提防を乗り越えんとしている。地元の人は総出で土のうを積み上げ、堤防の補強に追われている。所によっては、その濁った水はすでに堤防を乗り越え、田畑をおおいつくし、あたかも大河の如き景観を呈していた。これが本当に夏なのだろうか?指先は冷たくしびれ、濡れた体は風を受け、寒さに震えあがる。
明日は晴れる、明日は晴れる、そう言い聞かせながら走った。そう思わずには、いられなかった。その夜、神社の軒下に張ったテントの中で、濡れた服を着て、濡れた寝袋に足を入れた。マッチはしけて、ローソクに火はつかない。暗いテントの中で、このまま凍え死ぬのではないだろうかとさえ思われた。眠りについてからも、あまりの寒さに何度目を覚ましたことだろうか。そして、そのたびに生きていることを確かめ直した。
翌朝、冷たい寝袋の中で目を覚ました。雨の音は・・・していない。すぐに外へ飛び出す。太陽だ!雲の多い空ではあったが、その切れ目から太陽が顔を出している。暖かい。本当に暖かい。昨日までの苦しさを柔らかくつつみとり、心の中まで暖めてくれる、そんな太陽だった。濡れた寝袋やユニフォームを境内に広げ、すでに楽しい思い出となってしまった昨日を思い起こす。若さとはすばらしいものだ。昨日の疲れも今はない。午前10時、太陽のエネルギーを充分に吸収し、青森を目指して北上を始めた。また快適な旅が始まった。
そして11日、青森県に入る。その夜、浅虫海岸に張ったテントからは、青森の灯が海を隔ててすぐそこに見える。来たんだな、ついに来たんだなあと、うれしさが込み上げてくる。連絡船の灯がすべるように海面を走る。穏やかな海だ。明日はみんなに会える。もう着いているだろうか?最初になんと言うだろう?心はすでに青森駅へ飛んでいる。
12日、いよいよ青森の町にやってきた。市街に入り、国道も6号線から7号線に変わった。そして、青森駅まで0・5キロの標識が目の前に現われた。東京を出てすでに900キロ、そのひとり旅が、あと500mで終わろうとしているのだ。ペダルのひと踏み、ひと踏みが、俺を栄光へと導いてくれる。そんな気がして、ペダルを踏む足にもつい力がはいる。駅前広場が見えた。いた!2、3人が自転車を組み立てている。さらに次々とクラブ員の姿を見つけた。自転車を降りて、みんなと言葉を交わす。もう、うれしさを隠し切れない。ほこりと日焼けで真っ黒な顔が笑う。黒く汚れたユニフォームが、ひとり旅の全てを物語っているがのようであった。
ひとりで走り切ったこの900キロ。決して栄光を目指して走ったわけではない。しかし、この900キロ、ただ距離メーターの数字が増えただけでもない。走り抜いた自信とあの雨の日の苦しさが、常に俺のかたわらにいて、苦しい時、つらい時、必ず俺を励ましてくれるだろう。俺はそれだけ強くなったのだ。しかし、この旅もこれで終わったわけではない。明日からは35人の1人として、合宿を走り通すのだ。どんな試練が待っているかわからない。また、何の報いも得られないかも知れぬ、これからの道。しかし、今の俺には34人の仲間がいる。そして若さが俺を駆りたてる。この旅が終わっても、また次の旅が俺を待っているだろう。それが俺の青春だ。サイクリングが、俺に教えてくれた青春なのだ。
ハプニング – 法学部3年 小泉
ハプニング
法学部3年 小泉
私は、何もかもに、誰にも彼にも、すべてに対して苛立ちを感じていた。私自身ではなく、私の周囲が、私をそうさせたのであると思うとなおさらであった。
2つの講義をさぼった私は、これから始まる講義も受ける気持は中途半端で、10数分前に教室に入ったのであった。講義に関係のない教科書を、これも半分、それに苛立たしさを感じながら読んでいた。他の連中が、仲間同志で就職のことなどを話し合っていた。それは何か自慢気に話しているように感じられた。そして、それにも私は腹が立った。私は、自分が、ただ本の上の活字を追っているだけであることに気がついた。私は、その活字の中にはいろうという努力をする気にもなれずに、それを続けていた。
「ちょっとすみません!!来てくれませんか?担架を一緒に運んで頂きたいのですが・・・」
突然、小柄な男が私にこう言った。目を覚ましたばかりの時のような感じで、私に彼の顔を見た。そして、
「ええ、いいですよ」
と、合点のいかぬままに、彼のあとに教室を出た。彼はシャツの腕をまくっていた。ちょっと興奮しているようであった。
教室の入口のすぐ向かい側のベンチに、女性が1人横たわっていた。その脇には担架が運ぶために置かれてあり、そばにポツンと1人の女性が立っていた。
「今、救急車に連絡したんだけれど・・・」
彼は誰に向かうともなく、こう言った。
「それじゃ、車が来るまで、ここに、このままにしておいた方がいいんじゃないのかい?」
さっきまで気がつかなかったが、灰色の服を着た2人の用務員のおじさんが、落ち着いた口調で話しかけて来た。何か無責任のような落ち着き方であった。興奮した学生は、
「そうですか」
と、素直にそれを受けて、まくったシャツの腕を、もっと上の方へまくり上げた。用務員が優越したような調子で、
「1人、外に出て救急車を待った方がいいんじゃないのかい?」
と言って、それぞれの仕事のためらしく、そこを離れた。彼は言われるままに外へ出て行った。ベンチで仰向けになった女性と、そのそばにポツンと立った女性、それに私の3人が、そこに残された。
講義を受ける学生達が、私達の方に目をやりながら教室へ入って行った。私は、どうしてよいかわからなくて、そこに黙って立っていた。もう1人の女性も黙って立っていた。ベンチに寝ている女性と、この女性は友達同志ではないようであった。
「貧血なんですか?」
私はそばに立っている女性にたずねた。目と眉のすんなりとした、そして唇のやさしい、色の白い女性であった。『美人ではないけれど、感じのいい人だな』私はそう直感した。
「さあ・・・」
気のない、曖昧な答えが返ってきた。私は、なぜか、恥ずかしさを感じた。そこで、それを打ち消そうとことばを捜した。
「お友達ではないんですか?」
「ええ、御手洗で急にこの人が苦しみ出したんです」
講義に遅れて来る学生が、こちらに目をやりながら、忙しそうに教室へ駆け入った。と、私に手助けを求めた男が、階段をゆっくり上って来た。
「まだ来ないんだよ、救急車。ああ、君、講義に出ても結構ですよ。救急車が来たら、その人達と運びますから」
「いえ、構わないんです。」
私は、この男も、そしてこの女性も、苦しんでいる黒のツーピースの女性とは、全く関係のない人達であると感づいた。そして、私だけがそこから離れてしまうことは、何か義務を怠ってしまうように感じた。それで、私は2人と一緒に救急車を待った。そして、そのサイレンの音がなかなか聞こえてこないのに、焦りというものではなく、ただ漠然とした不思議さを感じた。
「救急車、遅いですねぇ」
時計をのぞき込みながら、女性が小さい声で言った。
「遅いなあ」
彼はそう言って、また、階下へ降りて行った。それとすれ違いに、私の受ける講義の教授がやって来た。
「どうしたんだい?ああ、この15号館には各階に電話がないんだ。診療所へ連れて行ってあげたら」
「はい。でも、救急車の手配を、もうしましたから…」
教授は、言うべきことばを言い終えたかのように、そのまま教室に入って行った。
もう、20分は過ぎていた。ベンチに横になっている女性は、すんなり伸びた足を片方だけ少し曲げて、もう一方に乗せている。顔を右手で覆い、左手は腹のあたりを押さえている。この女性の姿を、男の私は、男の目で見、男の感覚で感じ、そしてセックスを覚えるはずなのに、不思議と、今の私にはそういったものがわいて来ないのであった。そして、時々通り過ぎる学生の好奇の目でその女性を見るのを、私の彼女が見せ物になっているような気がして、嫌らしくさえ感ずるのであった。
「ああ、痛い」
「救急車がすぐ来ますからね」
「救急車が来るんですか?」
「ええ」
苦しんでいる女性は、うめくような声で、
「痛い、痛い」
と、言っていた。
そばに立っていた女性が、階下を見に行った。半袖の白っぽいブラウスに、やはり白っぽいタイト・スカートのその女性は、女らしく整っていた。
「お医者さんは、まだですかぁ?痛い」
「もうすぐ来ますよ」
私は何と言ってよいかわからなかった。私は、自分がどうしようもできないことに、いささか腹立ちを覚えた。
「貧血なんですか?頭―こめかみのあたりが痛いんですか?」
私は彼女に話しかけた。彼女は何年ぶりかに会った友達のように可愛く顔を横に振った。
「痛いって、お腹なんですか?」
「ええ」
「急に痛くなったんですか?」
「ええ。ああ、痛い」
「もうすぐ来ると思いますよ。連絡しておきましたから」
「早く来て下さい。ああ、ああ、痛い」
彼女は唸った。私は、ふと、彼女は妊娠しているのではないかと思った。
私ともう1人の女性は、救急車のサイレンの音を待った。さっきまで見ず知らずの男であった、あの小柄の学生を待った。
「急性盲腸炎かも知れないな」
私は無責任にもこう言った。もう1人の女性は黙っていた。と、困ったような様子をして、例の小柄な学生がやって来た。
「救急車の連絡を取っていないんだって」
「えっ?」
「係の人に聞いたら、してないんだってさ。連絡するっていっていたくせに・・・頭に来ちゃうよ!!」
「それじゃ、診療所へ連れて行きましょうか?」
さっきまで苦しがっていた女性は、今はもう、落ち着いて来たようであった。静かに横になっていた。私とその小柄の学生は、その女性を担架に乗せた。もう1人の女性が、その女性の靴と鞄を持ってあげた。
「どうも、すみません。だいぶ楽になりました」
照れくさそうに、そして、ほとんど聞き取れないくらいに、担架の上の女性は言った。私達は黙っていた。階段の所で係の人らしい2人が来たので、4人で運んだ。毛布を持って来て、下半身にかけてあげた。そんな配慮をした係の人に私は感心した。彼女は毛布をかぶって、顔にハンケチをあてた。外からは、男だか女だか判別できない程であった。私達は、キャンパスの端から診療所まで、他の学生の注目する中を彼女を運んだ。『第2次早大闘争勝利』をスローガンに掲げた全共闘や民青や革マルの集会の中を、私達はアジ演説以上の注目を浴びて、彼女を運んだ。
「どうしたんですか?」
1人の運動家らしい学生が、何が起こったのだという口振りで私にたずねた。
「貧血らしいんです」
私はそれだけ答えた。彼は、
「ああ、そう」
と、興ざめしたように離れていった。
「すみません。どうもありがとう。あの女性の方にお礼を言って下さい。ご迷惑をおかけしました」
彼女はハンカチの下で、声にならない声でこう言った。
「君達は友達かい?」
と、係の人が言った。
「いいえ」
「そうか、全然知らないのか・・・でも、いいやな、同じ仲間だ」
「そうです。同じ早稲田です」
「そう、同じ大学生だ」
私達は診療所に彼女を運んだ。その時の彼女は、ほとんど元気を取り戻していた。いや、運ばれる前に、既に腹痛は直っていたようであった。しかし、その前にあれだけ苦しみ、そして3人の学生に心配をかけたと思った彼女は、その3人のために素直に担架で運ばれなければならなかった。彼女は、その腹痛がせめて診療所で治療してもらうまで続いてくれたらと思っていたかも知れない。そして、私はそうであれと、教室に向かいながら願ったのではあったが・・・
地獄谷峠 – 法学部3年 篠原
地獄谷峠
法学部3年 篠原
今年の夏季合宿が青森集合と決定してから、今年こそは1人で青森まで走ってやろうと思い、合宿が始まる1週間前に大阪を出発した。つまり、1週間かけて大阪から青森まで走ったわけで、このことは後の話と関連があるので強調しておこう。というのも、昨年の北海道合宿の際、青森まで行くのにとても苦労し、それを今年も繰り返すのがイヤでたまらなかったからである。これは、そのブライベート・ラン中に、毎晩、毎晩夢見たものを、ひとつの物語ふうにまとめたもので、いささか記憶が薄れているが、当時の夢を思い出し書いてみようと思う。
8月4日大阪 – 敦賀曇ときどき雨
昼間のうち、降ったり止んだりしていたのが、夜になってから、本格的に降り出した。心細くなり、先程走ってきた道路にモーテルの看板があったので、その方向に行ったが、真暗な田園の中には、農家が点在しているだけで、モーテルらしきものは見当たらない。このままでは全身ずぶ濡れになるだけなので、覚悟を決めて、民家の屋根の下で仮寝することにした。いささか心細いが眠っていると地獄谷峠の夢を見た。
地獄谷峠 – それは人が生まれてすぐに自転車に乗り、それを目指して出発する峠である。地獄谷峠へは、自転車でしか行けなくて、自転車を捨てるということは、畢竟、死を意味する。そして、この峠を目指した者は、未だかって誰1人として帰ってきたことがない。しかも、その峠にたどりつくことができる者はきわめて少ない。
進一郎も生まれてすぐ自転車に飛び乗り、地獄谷峠への旅を始めた。なぜという理由もなく、また、はっきりとした意思もなく、彼は走ることを余儀なくされた。それは、あたかも何かにとりつかれたようであった。そう、彼は1度あの地獄谷峠に上り、その向こうに何があるか知りたいという欲望に取りつかれたのだ。否、彼だけではない。この世に生まれた者はすべて、あの地獄谷峠を目指して走るのだ、ある者はそれを運命だという。また、古今多くの哲学者がなぜ走るのか、なぜ地獄谷峠を上るのか、いろいろと言っている。しかし、それとは関係なく、彼は生まれたことによって走ること、地獄谷峠を志向することを余儀なくされた。
今日から1週間、彼は他の者達大勢と同様に、彼等が生まれる以前から敷かれてあるレールの上を走り出した、彼等とは無関係な大人どもが敷いた安全かつ最上のレールである。誰もがむしゃらに走り出した。何しろ彼等の世代は、戦後のベビー・ブームとやらで、掃いて捨てる程いるのである。
とにかく、彼はその中でもトップクラスで走った。しかし、そんなことはどうでもいいことであった。生きる、いや走ることは、まわりに誰がいようとも常に1人であるからだ。つまり、彼にとってこの1週間は、まったくの孤独な年月、いや時間であった。
8月5日敦賀 – 高岡晴夜中に雨
出発してから2、3時間経って、彼はある友と知り合った。そして、それから一日中その友と一緒に走った。
一日目は、ともかく、ただ動力的に走っただけである。その夜、2人で小さな公園に野宿し、今日一日を振り返ってみた。何の変哲もない、舗装された単調な道であった。しかしながら、特に自分を意識しなかった。意識するには若すぎた。彼は非常に疲れていたのだ。
今日は、ただ惰性的に富山を目指して走った。途中、金沢でもうやめてしまおうかと思ったりしたが、大言壮語した手前もあり、自分の意思に関係なくペタルを踏んだという感じがするだけであった。高岡に着いてから、すぐに宿泊場所を捜した。小学校の校庭が開放されているので、そこに泊まることにし、寝袋に入っていると、遠くで太鼓の音がする。さすがにのどかなものだと思っていたら、2日目からは、徐々に自分を意識し出した。今日も、ほぼ平坦な一日であろうということが予想された。途中、多少の起伏があったが、地獄谷峠に比べると大したことはなかった。昼すぎ頃から、無性に人恋しくなってきた。いわゆる春のめざめというやつか!特に異性に対する自意識は過剰な程で、まじめに自転車に乗るのが馬鹿馬鹿しくなってきた。
しかし、自転車を捨てる勇気もなく、これに乗っていたら、どうにか無事に地獄谷峠まで行けるであろうと思い、ただ単に他の者達と同様に、いや、むしろ恵まれているエリート・コースなる道を走った。世間では大学道路などといわれているが、いわゆるベルトコンベヤー方式の道で、入口で安くもない料金を払うと、それからは、気楽に景色などを薬しみながら、自転車を降りて、寝ていても、終点までは運んでくれるものである。コンベヤーに乗って走る馬鹿もいないでもないが、大半の者は、ごろごろ寝ころんでいる。夜になってもコンベヤーは自動的に動き、朝まで寝ていた・・・
と、夢見ていたら、急に大雨が降り出した。何のことはない。遠くで太鼓が鳴っていると思っていたのは、実は雷だった。急拠、地下道にもぐり込んで、朝になるまで一睡もしなかった。
8月6日高岡 – 柿崎曇のち雨
大阪を出て以来、実に眠ったという気がしない。今日こそ、絶対にぐっすり眠ってやろうと思い、柿崎海岸のソフトな砂地の上で寝ることにした。少し横になっていると、またまた雨が降ってきた。気も狂わんばかりに頭にきて、それが逆に居直る結果となり、用意してきたテントを出して、ポールだけを砂の中に突込み、どうにか雨だけはしのげる状態にした。ウィスキーを買ってきて、ガブガブ飲んだ。そうと、気持よくなってきて…
朝、起きると、もうすぐこの有料道路も終わりかけている。あわてて降りる準備をしたものの、少し寝すぎた感があり、有料道路終点では、幾種類もの道路の出発点となっていた。彼は急いで、楽な舗装道路を走ろうとしたが、その道は定員制で、早くから起きていた連中がすでに走り出していた。いささか泡を食ったが、時はすでに遅かった。どの道を行っても、最後には地獄谷峠へ行けるので、まずは真中の道を走ることにした。彼にとって、走り出してから少しの間は、今まで寝ていたので、非常に苦しかった。走るのが非常な苦痛に感じられた。しかし、昼すぎには、それに慣れてきて、他の者にそれ程遅れずに走ることができたが、後の方を走るのは非常に辛いらしく、絶えず遅れを意識し、心理的に疲れていた。
昼すぎには、前を走っていた連中が、次々と自転車に女を乗せるために止まっている。中には、前に子供を乗せ、後に女房を乗せて走っている奴もいる。彼は自分1人で走るだけでもばてているのに、この上女まで乗せられない。そんな荷物は御免こうむりたいと思い1人で走ることにした。しかしながら、その夜の1人寝はわびしいものであったろう。
8月7日柿崎 – 新潟雨
今日は一日中雨。新潟に着く頃には、まったくの濡れ鼠。駅に行き、ユース・ホステルの場所を聞き、電話で予約して、すぐにユースに行った。久しぶりの風呂に入り、これまた久しぶりで忘れかけた蒲団で寝てみて…。
今朝は早く起きて、荷物をつんでいると、横に寝ていた男が、話しかけてきた。
「あぁ眠てぇなあ君ねぇ、なぜ、そんなに急ぐの?別に急いで走ることもないんじゃないの」。
「なんでゆうても、はよぉ地獄谷峠を見たいからやんか!おまえみたないか?ほんなら、なんで走ってんねん」
「俺も、最初のうちは、あの地獄谷峠を上り、あの向こうに何があるか知りたかったさ。しかし、今はもうどうでもいいよ。そんなに汗を流して上る価値のあるものかどうか疑問だな」
「価値があるかどうか、俺も知らんけどやなあ、皆んなが走るやないか!これが体制ゆうもんとちゃうか!とにかくこの流れに入ってやなぁ、皆んなについて走っとったら、居眠りしとっても地獄谷峠まで行けるで。こんなとこで寝とってもしゃあないやんか!」
「君は単純な奴だなあ。とにかく俺はもう走らないよ。馬鹿馬鹿しくて生きられるか!」
と、その男はいって不貞寝した。
「そうでっか、ほんなら、さいなら」
彼はいささか腹を立てて、その男と別れた。
昼飯を食いながら、フッと出発した時のことを思い出しながら、彼は自分がツァーを始めて、もうすでに4日目になることを改めて知った。もう彼は心身共に大人になったが、いまだに地獄谷峠を目指して、がむしゃらに走っていた。この年になって1人で走っている人間はめずらしい程だ。ほとんどの者が、女房、子供を乗せて、あえぎながら走っている。彼もそろそろ女を拾おうかなとは思ったものの、その度に荷物を満載したあの自転車を見、亭主があえぎながらペダルを踏んでいるのを見ると、とてもじゃないが身が持たないと思うのであった。
夜になると、話す相手もなく、巷に輝くネオン街に行き、酒を浴びる程飲んでは酔いつぶれ、粗末なテントに帰ってきて、例のごとく1人でわびしく寝ていた。彼は常に孤独であり、また、女房をもらい子供ができて、家庭を持つ持ったとしても、孤独なことには変わりないと確信していた。
8月8日新潟 — 鶴岡雨のち曇
今日も一日中、雨だった。鶴岡駅に行き、安い旅館はないかとたずねてみたが、とても俺には泊まれそうもないので、神社に泊まることにした。新潟を出てすぐ、東京の高校生のサイクリストと一緒になり、彼と今晩は野宿することに決め、東北の地酒を3合程飲み、いい気持になって夢うつつ…
この頃になると、彼と同世代の男達は、社会的にも安定した地位を得、高級車に乗っているが、その日暮しの彼は出発した時と同じポロ自転車に乗っている。今日も彼は1人わびしく例のペースでゆっくりゆっくり走っていると、高級車に乗った男が、前方の道端に寝ころんでいる。
「どうかしたんでっか?」
と、彼は話しかけた。
「いや、どうもしない。少し疲れたので休憩しているんです。ところで、話は変わりますが、地獄谷獄へ行く道はこれしかないんでしょうか?」
と、その男はたずねた。
「ええ、地図見たら、この道しかおまへんなあ。前へ進むんでしたら、今晩泊まる所から道が2つに分かれてます。一方はあなたみたいに疲れて、もう上るのをやめた者が行くらしいけど、その道は墓場に通じてるらしいですよ。後退するんなら、昨日泊まった所から横道にそれる道がついてましたけど、あの道は自転車では上れんでしょうな。少しは近道になるらしいけど、急がば廻れですよ」
彼はその男にいった。
「そうですか!それでは仕方ないですね、後退しますか」
「えっ下るんですか?なんでまた、今日まで上ってきた道を下るんですか?失礼ですが、奥さんもお子さんもいるんでしょう?」
「ええ、いることはいますが、私はもう疲れました。走ることに、生きることに疲れましたよ。それに、女房や子供を乗せては、とても上れませんよ」
その男は無気力に投げ捨てるようにいった。
「下ってあの細い道を行くんですか?」
「ええ、そうしょうと思います」
「そやけど、それは自殺行為に等しいことでっせ。つまり、死ぬことですよ」
「それはわかっています。しかし、このまま上り続けても同じことですよ!どうせ地獄谷峠へは行けませんからなぁ」
と、その男はいって、彼とは反対の方向へ下って行った。
「何が疲れたや、馬鹿野郎!女房や子供を乗せて上るのは、何倍も疲れるのに決まってるやんか!誰も皆んな、それでも上ってるんやんか?地獄谷峠を上れんかったら、結婚なんかするな!単に肉体的に生殖能力があるからといって、それだけの理由で結婚し、できた子供を捨てて、さらには女房まで捨てて、自殺するのは勝手すぎるんじゃおまへんか?俺は冷静に自分を見つめて、1人で上るのがやっとこさだから、そんな荷物は持たんことにしとるんや、まったく無責任な野郎やなあ」
彼は激しい憤りを感じ、ペダルを強く踏んだ。汗をタラタラ流しながら上って行くと、上からさっきの男のような連中が、下りてくる。これもまた落伍者かと思い、わびしくなってくる気持に反してペダルを踏む足は力強い。
また、道端には男の死体があり、そのそばで家族が泣きわめいている。夫を亡くした妻は子供を後に乗せて、ペダルを踏んでいる。夕方に近づけば近づく程、そういう光景がしばしば見られた。それを見るにつけても、彼は自分の年齢を感ぜずにはいられなかった。
8月9日鶴岡 – 秋田晴
大阪を出てから初めての晴である。気持よく快調なペースで秋田まで来たが、菅原さんが今日から東京へ出張ということなので、合宿中に横手で再会する約束をして、今日も神社で野宿した。ちょうど、亜細亜大学の事故を知って、とても他人事のようには思えなかった。合宿では、絶対に事故を起こさないようにと思っている
と、また…
今回のツァーも、いよいよ明白で終わりである。地獄谷峠の頂上もそろそろ見えてきた。ふつうの男なら、今日の昼からは、妻や子供というお荷物は捨てて、最も楽な老人用の特殊自転車に乗ることができる。長年の努力が報いられる時である。しかしながら、それには今日に至るまでの蓄積があって初めてできることで、貯蓄などという観念を持たなかった彼は、どうしても、今までと同じあのボロ自転車で上り続けなければならないだろう。さすがに彼も肉体的疲労を隠すことができない。
しかしながら、地獄谷峠の坂は容赦なく彼の前に立ちはだかる。彼と同類の男達は、そのあまりの厳しさにバッタバッタと倒れ出した。彼は、道端で自転車を抱きながら、倒れている死体には見向きもしなかった。今までに、何と多くのそのような死体を見てきたことだろう。彼はもう何とも感ぜず、無意識にペダルを踏み続けた。明日になれば、この坂も終わる。この坂から解放される。あの地獄谷峠の向こうに何があるか、この目で見てやろう。明日までは絶対に死ぬことができない。明日までは! 急ぐことはない。明日で終わる、終わる、終わる・・・
8月10日秋田 – 能代晴
今日は星君と能代駅前で、夕方に待ち合わせをしているので、60キロしか走らなかった。明日は青森まで150キロあるので、先へ行きたいが、彼との約束で、やむを得ず能代で止まる。海水浴場があるので、裸になって日光浴をしながら暇をつぶし、夕方、駅前で待っていたが、サイクリストが5人程やってきただけで、彼は現われなかった。一日早く秋田を出たことは確認できているのに、来ないということは、男鹿半島にいるか、事故を起こしたか、それとも先へ行ったのか、まあどうでもいいと思い、昼間に捜した公園で野宿し、星空をながめていると・・・
ついに最終日がきた。苦しかった、いや、まだ今日一日ある、この坂もついに終わる。彼は感慨深げに今までの道程を思い出した。かって若かった頃に、幾度となくこの地獄谷峠の姿を自分なりに描いていた。峠の上には、立派なレストハウスがあり、そこで柔らかいソファーに横たわりながら、酒の風呂につかり、朝から晩まで酒を飲んで暮らす、それとも、そこにはパラダイスがあって、天使のような美女をまわりにはべらせて、毎日、毎日、快楽のみを追求する世界があるのか、そんな夢ばかり見ていた。しかし、彼は今、目前に地獄谷峠を見て、そういうのはすべて若き日の空想にすぎないと思った。今や峠に何があるのかわかり始めたような気がしてきた。
長かったこの坂を、なぜこんなにして上ってきたのだろうか?誰が俺を上らせたのか?なぜ俺はこんな苦しみの世界に生まれてきたのだろうか?生まれなかったならば、こんなに汗を流して上ることもなかっただろうに!俺は、生涯、家庭を持たなかった。それは、俺がこの世に生まれたことが、いまいましかったからだ。この地獄谷峠を上るのが嫌だったからだ。人は誰も、なぜ、この地獄谷峠を上らなければならないのだろうか?俺に生まれることを拒否する権利があったのなら、絶対に生を拒否しただろう。祖先も子孫もあったものではない、えい、いまいましい!
彼は無性に腹立たしくなりながらも、それは目前に峠があるからであり、何よりもこのツァーが、今、終わろうとしているからであることを知っていた。彼は率直に喜べないのだ。なぜだか、今まで苦労して上ってきたのが馬鹿らしくなったからであった。そう思いつつも老体に鞭打ち、ペダルを踏んだ。
最後のカーブを曲がると、突然、まったく突然、あたりが真暗になった。何も見えない。
と同時に、体が宙に浮いた。彼は一瞬、谷底に落ちているのだろうと思った。しかし、よく考えると、決して落下しているようではなかった。宙に浮いた体は、物体が落下する際に加速度的に速度が増していくのと同様に、地表からどんどん遠ざかって行く。彼は、直感的に、これが死だと思った。地獄谷峠は地球と無の世界との接点であった。
これが今まで苦労して上ってきた報酬か?何のために、俺は7日間、70年もかけて地獄谷峠を上ってきたのだ。なぜ俺は汗を流してまで上ってきたのだ。一体、誰が上らせたのだ!一体、誰が何のために!何のために…
1個の物体が、加速度的に速度を増して宇宙に飛んでいった。つまり、無の世界に!
俺は息苦しくなって目を覚ました。すると、そばに進一郎が立っていた。そして、俺に微笑みかけている。否、夢はすでに終わったのだ。しかし、進一郎は今ここに存在している。そして俺に話しかけてきた。
「君、どこから来たの?」
俺は、まだ夢見ているのかと思った。
「大阪から…」
と、答にならぬ返答をした。
「へえ、大阪から!若いねぇ!」
俺はまわりを見た。そして、もう夜が明けているのを知った。近所の人達が、この公園にラジオ体操をやりに集まってきているのであった。やっと落ち着き、受け答えができた。その人は、やさしくいった。
「家にきて、朝飯を食べて行きなさい。すぐそこだから!」
俺は何か無性にうれしくなり、厚意に甘えることにした。今日中に青森まで行こう。今日が最後、最後…なのだ。
京都レポート – 法学部2年 吉田
京都レポート
法学部2年 吉田
ぼくが保津川にかかるトゲッキョウを最初に渡ってから数時間が過ぎた。トゲッキョウを渡る時の容易さに比べ、戻る時の足取りは鉛のように重かった。しかも、さして戻る気のないぼくにとってそれは一層憂うつだった。トゲッキョウに戻ってそれから何処へ行くのかと聞かれても、阪急嵐山駅へ帰るとしか答えようがなかった。事の発端は、ぼくの内部にトゲッキョウに戻りたいという声があったからにほかならない。しかし、もう一方の声は、ぼくに帰りたくないなとささやいていた。
1人の女がぼくの隣に坐っている。彼女は、ぼくらの目の前を音も波しぶきも立てず流れている透明な保津川の水面を、飽きもせず見入っていた。小魚が群をなして通り過ぎた。ぼくは、やや紅を増してきた嵐山のほうに少し体を傾けながら、ずっと以前に修学旅行で来た時のことを思い出した。その時も、確かにこのような眩しい太陽が保津川に反射していた。その時ぼくはちょうど今坐っている岸の反対側に立っていた。そして、青い空の下で、嵐山が若葉でむんむんしているのを真正面に見ていた。今、青い空だけが見える。
嵐山は、ぼくの目の隅に小さく映っている。ぼくは小石を川面に投げた。魚が四方に散った。女がぼくのほうをちらっと見た。ぼくの顔に、女の髪が触れた。女のタイトスカートがぼくの気分をいらだたせる。投げ出した脚の膝下から足首まで、良く伸びきった形のよい筋肉がはみ出している。透明のストッキングに水面の光が反射しる。タイトスカートに包まれた豊かな腰が、汗ばんで見えた。
トゲッキョウがぼくらの左手に見えている。その橋の上を、中学生のぼくとぼくの仲間が、真新しい学生服姿で渡っている。それを、ぼくと彼女は笑みを浮かべて眺めていた。(11月6日)
ぼくは、キムラ屋の前を何度も行ったり来たりした。すでに12時を5分過ぎていた。パチンコ屋の前で、何本も煙草をもみ消した。見上げると、けばけばしい色の飾りがずっと並び、四条河原町商店街と書かれたアーチの向こうに、デパートの宣伝垂れ幕が見えた。市電が通り過ぎた。腕時計を見やった。12時6分。
<アラ・いややわ>
ぼくの2・3歩手前で女が笑っている。
<いやぁー!来ないと思った>
<いややわ、嘘なぞつかへん>
それから、肩を並べて昨日同志社とのコンパの後ではいった喫茶店へ行った。彼女はよく喋った。ぼくはよく笑った。彼女はそのうち、ぼくの手相を見始めた。
<あなた、運命線あらへん>
<うん。それに生命線もこんなところで切れてしまっている。ぼくシュッセしないね。>
<ううん、大器晩成型とちがう?>
2人は顔を見合わせて笑った。彼女はぼくの手を握っていた。ほくは彼女の目を見つめていた。近眼のせいか、濁りのない薄青い瞳をしていた。唇が、接吻したい位に瑞々しく熟れて形が良かった。
<そっちへ行くと、帰れなくなる>
清水寺の裏山の小道で、彼女はそう言った。あたりは薄暗くなり始めていた。人影はなかった。一方の道は清水寺の舞舞台のほうにむいていた。一方の道は更に山のほうに続いている。ぼくは、山のほうに続く道に歩を進めながら、彼女のほうを振り返った。彼女は口をとがらせ清水寺へ続く坂の途中で待っている。ぼくは彼女の全身に見入った。胸のふくらみが赤いセーターに隆起していた。下半身は豊かでのびやかだった。背丈はぼく程あった。
<少し、こっちへ行ってみよう>
そう言いながら、ぼくは彼女に口づけた。セーターをたくし上げて、ブラジャーの上から乳房をまさぐった。タイトスカートのチャックを緩めて左手を差し込んだ。コルセットなど勿論つけていなかった。腰の肌は滑らかで冷たかった。手は尻から前のほうに回った。両股の交わった意外に低い所で、ぼくの手は烈しく煩悶した。その深い暗闇の中に、ぼく自身がめり込んでいった。ぼくは濡れる自分自身を感じた。
<早くう。わたし1人で行ってしまうわよ>
彼女は、1人で、ずんずん坂を下って行った。ぼくは、目のまわりが桃色に上気しているのを感じた。依然として、山のほうに体を向けながら、顔だけ彼女の後姿を追っていた自分に気がついた。
(11月6日)
ぼくらはトゲッキョウを渡る手前で写真を撮った。彼女は、水中に顔を出しているコンクリートの堤防の上にピョンとはねて、ボーズを作った。それは大層ぼくを驚かせた。彼女の後で、小舟が何隻ものんびりと浮かんでいた。それから、トゲッキョウを渡った。松が保津川沿いにずっと植わっていた。立ち止まっては何度も写真をとった。1度、河原の大石の上に並んで、小学生にシャッターを押してもらった。並ぶと、彼女のほうが背が高くなった。すると彼女は無理と大袈裟に背を屈め、ぼくのほうを見やった。ぼくは、真面目な顔をして彼女をにらんでから、すぐ吹き出してしまった。
保津川の渓谷は目にしみ入るようだっそれから落柿舎のほうに向かうため、少し急な坂を上った。登りつめると、修学旅行の小学生や中学生が休憩していた。ぼくらはそのざわめきの中を肩を並べて歩いた。中学生のぼくが真新しい学生服を着て仲間を追いかけていた。大層嬉しそうで、大声をあげていた。目がキラキラと輝やき、素早かった。ぼくらは笑みを浮かべながらそれを眺めていた。やがて行くと人影もまばらになり、目の覚めるような竹林がぼくらの頭上を覆いはじめた。少し行くと、古びた門があった。その前で彼女は思い出したように立ち止まった。
<ここに夏来たことあるの>
<へえー、誰と?>
<名前は言えないわ。彼が入場料払ってくれてこの庭園見物したのよ。それに善哉食べた>
その庭園は何といったか不思議と思い出せない。ただ、周囲の竹薇と呼応するかのような古びた門だけが目の前に浮かんでいる。
<彼と君とは、どういう関係なんだい?>
<関係なんて、いややわ。ただ、あなたと同じように京都を案内しただけやわ>
<ぼくと同じように?>
そこでぼくは、少し神経質になった。彼女の言葉の節々を聞き洩らすまいと懸命になった。畢竟、ぼくらは白けた。ぼくは、埃っぽい、うねうねと曲りくねった道の小石ばかり見つめて歩いた。時々、その小石を蹴ったりした。彼女は、前より口数が少なくなったとはいえ、依然と恋愛論などぶっている。ぼくはただ<ふんふん>と言い、時々<イヤ、そうじゃないだろう>などと言っていれば良かった。埃っぽい道は、ぼくらの前をうねうねと下っていた。(11月6日)
うねうねした埃っぽい道を汗をかきながら上っていくと、どうやらもう自転車では上れそうもない。空も曇ってきた。ぼくの前の奴が、自転車をとうとう担ぎ始めた。
<オイ、冗談じゃないよ>
疲れているのに、やはりぼくも愛車「サユリ」を担がなければならなくなってしまった。熊笹に覆われた雲ヶ畑でこりごりした自転車担ぎを、今度は木馬道とかいう足場の不安定な道を歩きながらやらなければいけない。
<同志社では、いつもこんな苦しいサイクリングをやっているのかい?>
<まあ、大体そうやな。京都市内を抜けると必然的にこんな山道を通らなくちゃならんからな>
ぼくはもう肩がぶち割れそうだ。腰も痛いし、もしこの木馬道で足をすべらしたら大ケガして泣き面に蜂だ。恨みつらみの縁坂峠520m。しかし、先頭はどうやら峠に着いたらしい。
<オーイッ!!着いたぞ>
神の声。同志社にはいらなくて良かった。サイクリングとは、自転車に乗って山野を駆けめぐるものだ。肩に自転車を担いで、木馬道なんぞを上ることじゃないよ。あああー、終った。やっと平らな道。さあ、これからは下りだ。(11月3日)
埃っぽい道を下り切ると、懐しい田園の風景が開けてきた。稲を刈り取った後の田が黄金色に眩しく映えていた。稲むらは何故かしばらく振りに見たような気がした。稲むらの陰に隠れながら、ただ夢中になって遊んでいたぼくは、今こうして何とはなしに肺を真白にして喘いでいる。その稲むらに寄り添い彼女と並んで、通りがかりの人にシャッターを押してもらう。田園の端の道沿いに、柿の木がある古びた荒屋があった。
<アレが落柿舎よ>
彼女はそう言って指をさした。芭蕉門下十哲の1人、向井去来の住んだ所よ、と国文科の彼女は学のあるところを見せた。「柿ぬしや木ずえは近きあらしやま 去来」と刻まれた碑の前で、ぼくは陽気さを取り戻した笑顔を見せてカメラに収まった。見物客がやけに多かった。それから少し同じ道を戻って暫く歩くと、大きな総門に出食わした。看板に<二尊院〉と大きく墨書されてあった。彼女を門の下に立たせ、ぼくはカメラを構えた。ファインダーの隅に、見物客が坐って善哉を食べている図がはいった。ぼくはそれに大して注意を払わなかった。
<いいかい>
ぼくはファインダーから目を外してちょっと彼女のほうに合図した。その時、歓声が善哉を食べ、或るいは注文して待っていた連中の中からあがった。(11月6日)
<明日、ぼくは嵯峨野のほうへ行こうと思うんだけど>
<本当かよ。オレ達も行くんだぜ>
大堀さんがニヤニヤした。
<ヒョッとすると会うんじゃないか>
小川さんが好奇心に充ちた口調でそう言うと、そばにいた堺もいわくありげな顔をしている。同志社の梯・井上両君の下宿へ、こうして2日も3日も一緒に泊まっている。夜中に屋台の肉がたっぷりはいったラーメンを食べに行ったりもする。大堀さんの経験談や小川さんの意外と生真面目な面を見せつけられ、布団や寝袋にもぐりながら様々なことを話すのは楽しい。下宿の近くの白河という喫茶店へ行くと、小川さんはすぐさまジュークボックスにコインを入れて、体を揺り動かし始める。梯・井上両君は、早同交歓会で早稲田を招待したのだから、少々のことは我慢して早稲田のバカに楽しんでもらおうと必死の態。ぼくは図に乗って3日3晩も泊った。
<オイ吉田、明日会うかも知れんな>
<ヒョッとしてね。何を隠そう、このわ・た・く・し・そんなへマはやらないつもり>
皆でゲラゲラ笑った。実に楽しい。京都に来て良かった。同志社の連中に感謝している。(11月5日)
<いいかい>
ぼくはファインダーから目を外してちょっと彼女のほうに合図した。その時、善哉を食べ、或るいは注文して待っていた連中の中から歓声があがった。
ぼくらは、小1時間もしてから腰を上げた。保津川の清流は相変らず音もなく、柔らかな水面に落葉を浮かべていた。彼女は1人っ子だという。大学1年の夏に、両親に無断で山陰を巡って九州の自宅に帰ったら、ひどく叱られたそうだ。積極的だ。年はぼくと変らない。身体は大きい。プロポーションがいい。左手にトゲッキョウが見えている。背中には紅がかかり始めた嵐山がある。ぼくがちょうど中学3年の春に、この嵐山に修学旅行で来た。そして、仲間とあのトゲッキョウを渡ったものだ。今、当時のぼくと同じ位の中学生の1群が、同じように瞳を輝やかせてトゲッキョウを渡っていく。ぼくはその光景を無表情で見つめている。彼女も黙って見ている。
その時、ぼくの背後からぼくらを覗く者がいた。誰だい?ぼくは目を開けてその男の顔をまじまじと見つめた。何を言っているのかとんと見当がつかない。何かぼくの目の前で言っているらしい。ああ、きみか。何?砂糖?ああ、そこの棚の上にあるからかってに持っていってくれ。うん、後から持ってきてくれればいいよ。えっ?コーヒー~ああ、いいよ。持っていってくれ。それで彼はぼくの目の前から消えた。しかし、何か微かにラジオの声が聞こえているみたいだ。そしてぼくは、ベットに仰向けになっているようなのだ。
<いいかい>
ぼくはファインダーから目を外してちょっと彼女のほうに合図した。その時、善哉を食べ、或るいは注文して待っていた連中の中から歓声があがった。二尊院の内側にある四季庵というところだ。
<オーッ!吉田!!>
そこで大騒ぎになった。まわりの客はただ唖然としている。
<会ったぞ・会ったぞ!!吉田、とうとう会ったぞ!!>
数奇な運命とはまさにこのことだ。彼女は驚くし、まわりの人間は何が起こったんだろうと目を白黒させている。1番驚いたのはこのぼくで、内心へガクッと力が抜けた。悪い連中に出食わしたものだ。彼らと一緒に本堂を見物したが、彼女はひどく機嫌を損ねてしまった。1人ブンとして先へ行ってしまう。ぼくはただオロオロするばかりだ。彼ら、つまり大堀、小川、堺3君は、してやったりと悦にいっている。ほくは、何事もいいところまでいって肝心なところで何時も駄目になる。そうクサリたくもなった。
竹藪の中に古びた門があった。彼女は思い出したようにそこで立ち止まった。周囲の竹藪に呼応するかのような古びた門だけが目の前に浮かんでくる。
<わたし、夏ここに来たわ>
<へエーッ?誰と?>
<ううん、ただちょっと知り会って京都を案内してあげただけ。あなたと同じように>
<ぼくと同じように?>
<ええ。わたし、彼、とっても好きだった、今でも。住友商事の人なの。早稲田の理工出た人よ。わたし、今まであんな人と会ったことあらへん。あの人になら、ついていける>
<ついていけるって?>
<ええ、結婚してもいいわ。理想の人やわ>
二尊院からえんり庵のほうへ抜ける道すがら、彼女は怒った表情を隠さなかった。ぼくも黙って足許の小石を見つめながら歩いた。大した特徴もない場所で、ぼくを撮ってやると彼女はカメラを構えた。ぼくは馬鹿にぎごちないポーズをとった。ぼくらの間には、どうやら目に見えない塀ができてしまっていた。
<今日か明日にでも、彼から電話があるかも知れへんわ>
彼女は、ぼくに当てつけがましくそう言った。その言葉はぼくの胸に痛く突き刺った。彼女は尙も続けた。
<わたしが居ない留守に彼から電話がかかってきたらしいの。そして、今日か明日にでもまたかけてくるって>
<ふーん>
ぼくは自分がおかしくてたまらなかった。とてつもなく大声で笑い出したくもなった。なぜって、無声の風の音をでんぶから発した後で、
<お医者さんが出しなさいって言うの。御免あそばせっていえばいいんでしょう>
そう言って彼女は平然としていたから。ぼくは今まで、一体何を彼女に期待していたというのだ。京都じゃない。恋愛はそうだ。そうだけれど、しかしセックスは鼻につく。ぼくは何も期待してはいけなかった。
<過去はわれわれにとって何の役にも立たないし、未来は不安に満ちている。現在だけが真実なのだ。この場この瞬間だけがね。現在をつかまえなきゃいかんのだ>
このタムキン博士のことばを、ぼくはどう受け止め耐え切ればいいのだろう。これだから<ソウウツ病>患者は困る。定義。ソウの症状は感情的・楽観的で思考障害では誇大妄想に陥り、ウッの症状は絶望感をもち、思考が極度に抑制され、すべてに対する意欲を失う。
考えているうちに、ぼくらは不思議と天竜寺まで来ていて、総門の前で彼女の写真など撮っている。今から思えば、ポーズを作る彼女はいやに傲慢だ。と、ぶつぶつ言っていると、目の前にもうトゲッキョウが見えてきた。ああ、また来てしまった。
ぼくがトゲッキョウを最初に渡ってから数時間が過ぎた。トゲッキョウを渡る時の容易さに比べて、戻る時の足取りは鉛のように重かった。しかも、さして戻る気のないぼくにとってそれは一層憂うつだった。トゲッキョウに戻ってそれから何処へ行くのかと聞かれても、阪急嵐山駅へ帰るとしか答えようがない。事の発端は、ぼくの内部にトゲッキョウに戻りたいという声があったからにほかならない。しかしもう一方の声は、ぼくに帰りたくないなと囁いていた。
もう一方の声は、ぼくに帰りたくないなと囁いていた。<うん>とぼくは答えた。すると、保津川でぼくらの背後から覗いていた男が大声で笑った。
<オイ、吉田、何がウンだよ>
ぼくはまじまじと相手の顔を見た。それは同じ寮に住むKではないか。
<さっき借りた砂糖とコーヒー返しに来たよ。そんな恰好で寝ていると風邪でもひくぞ>
んだ。ぼくは<ハッ>と思い出したように体を起こした。目の前にカーテンが下がっている。壁には絵も張ってある。ラジオもつけっぱなしだ。ああ、なんだ、俺の部屋か、いつの間にか寝てしまっていたんだ。
編集後記 – 滝野
編集後記
夏合宿も終り、早同交歓会も近づいている。当然解放されてもよい仕事に煩わされつづけた1年間だった。「峠」第7号の発行が遅れること半年以上、本当に申しわけないと思っている。ここ2、3年「峠」の発行が遅れ続けていることを気にかけながらも、ここまで延びてしまった。これは私の責任以外のなにものでもない。どこにいても、どんな時にでも「峠」のことが頭のすみに残っていて、この半年間は、気がめいってしようがなかった。何故、こんな厄介な仕事を引き受けたのだろうと自分を責めたりもした。しかも、こうやって仕事をやり終ってみると、なんとも気持ちが良い。これから先、「峠」の編集を担当する者は、おそらく私と同じ気持、又今までに編集に携わった人々が持ったであろうこの気持に出会うであろう。そう思うと、今から「御苦労さま」と言いたくなる。まことに厄介な仕事である。
「峠」第7号は、今までとこれと言って変った特色を持っていない。単に継続しただけのものとなってしまった。このことが心残りである。これは、私の編集に対する力が足りなかったのが原因である。これは後退であると批難される諸氏もおられようが、「峠」第7号が私の最善のものであることで御容赦願いたい。私としては、これからの「峠」の充実を期待して止まない。
編集にあたって、未熟な私に最大の協力を惜しまなかった星君には、お礼の言いようもない。彼なしでは、「峠」第7号の完成も危ぶまれたであろう。又私を心暖く見守ってくれたクラブ員諸氏、広告集めに奔走してくれた関口君、面白い文面で切捨御免のマンネリ化を防いでくれた堺・吉田両君にお礼を申し上げる。
最後に「峠」に対して暖かい援助をさしのべて下さった、高橋、日東、中村、藤田、サンノー、アルプスの各社に対して深く感謝いたします。
(滝野)
第7号峠
1970年10月1日発行
発行 早稲田大学サイクリングクラブ
編集責任者 滝野
Editor’s Note
1969年の出来事。昭和44年。
第11回日本レコード大賞 1969年 いいじゃないの幸せならば 佐良直美
1月。リチャードニクソンが37代大統領に就任。東大安田講堂事件。
3月。「フランシーヌの場合」(新谷のり子)がヒットする。
6月。日本のGNPが世界第2位に。
7月。アポロ11号が月面着陸。
10月。巨人、金田正一投手が400勝達成。
11月。セサミストリート放送開始。
WCC夏合宿は、「 東北地方 : 青森から – 会津若松まで」でした。
=====
こんにちは。WCC OB IT局藤原です。
1970年にJCA – 国鉄の協定が結ばれ、「輪行」が可能となりました。その前年ですので、手荷物として自転車を運搬することは正式には許可されておらず、代わりに「駅間での輸送」が可能だった模様です。詳しいことを覚えておられる方、ご一報ください。
当時の文章をWEB化するにあたり、できるだけ当時の「雰囲気」を尊重するよう心掛けたつもりです。
文章と挿絵はPDF版より抜粋しました。レイアウト変更の都合で、半角英数字、漢数字表記等を変換していますが、全ての誤字脱字の責任は、編集担当の当方にあります。もし誤りありましたら、ご指摘をお願いします。
2025年3月、藤原
Copyright © 2025, WCCOB会