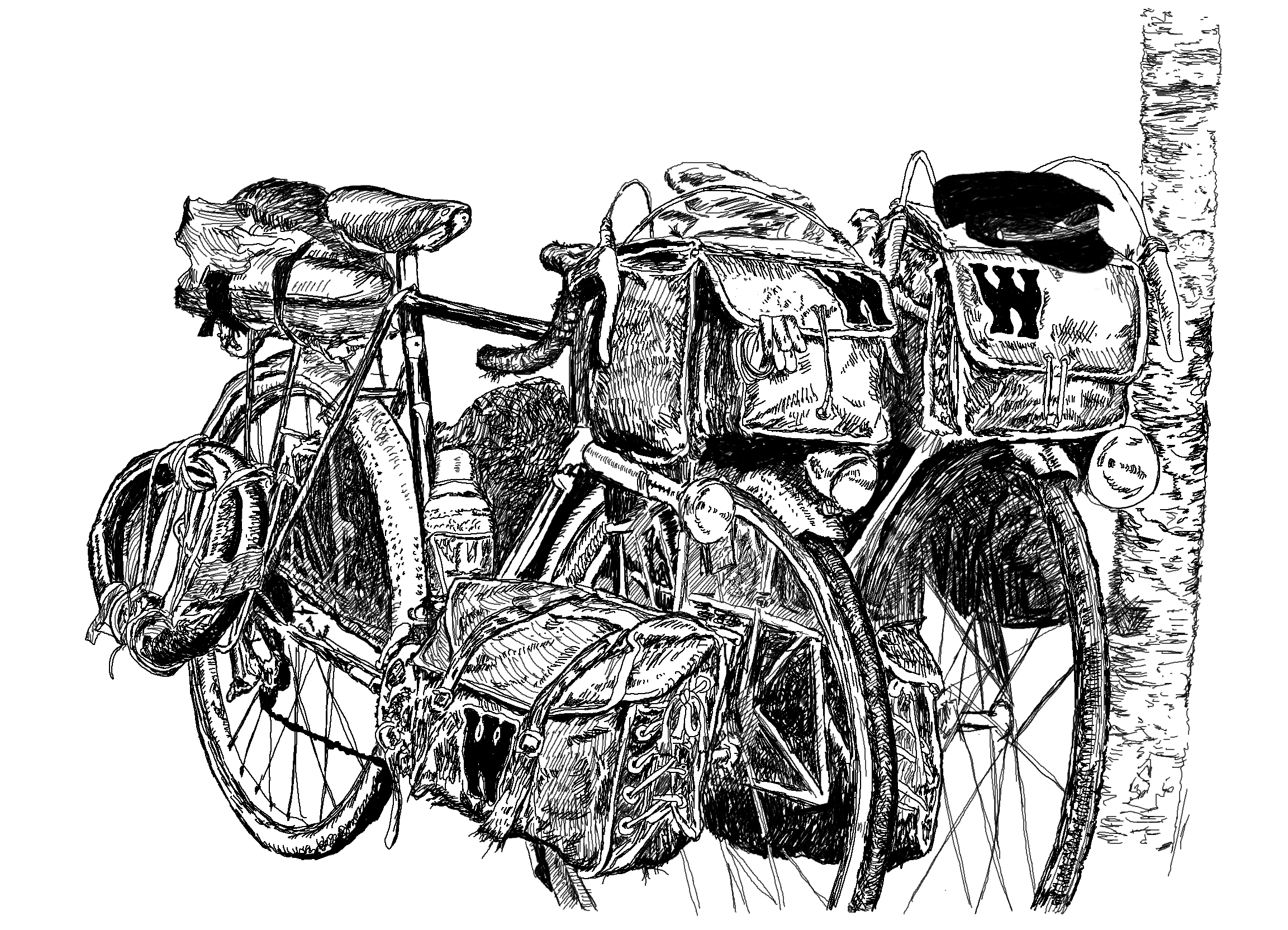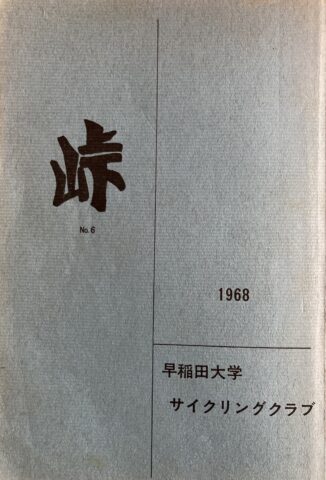
- 峠の詩
- タフ・ガイ雑感 – 文学部教授 清原会長
- 1968年度夏季合宿記録北海道 – 教育学部2年 星
- 想い出 主将の任期を終えて – 商学部3年 加藤
- 資料局の1年間 1968年活動記録 – 法学部2年 篠原
- 新入生歓迎ラン – 商学部1年 高橋
- 南多摩丘陵ラン – 商学部1年 中山
- 宮沢湖ラン – 政治経済学部1年 仲田
- 合同サイクリングに参加して – 日本女子大学 戸部さん
- 北海道のムシ – 法学部2年 小泉
- 第5回早同交歓会報告 – 政治経済学部1年 仲田
- わがサイクリングの視点 – 政治経済学部3年 木村
- 香港・台湾・沖縄サイクリングツアー – 商学部3年 加藤
- 軽井沢-名古屋 hi-lite – 法学部1年 堺
- サイクリング徒然草 – 理工学部2年 木村(治)
- 近眼に関する考察 – 法学部2年 小泉
- 北海道合宿の始ま – 法学部2年 篠原
- ドリル、ペンチ、カナヅチ-まな板の上のトラジディ – 理工学部2年 木村
- 早慶戦観戦記 – 政治経済学部1年 遠藤
- 竹馬の友に捧ぐ – 法学部2年 篠原
- 道 – 理工学部2年 木村
- 編集後記 – 星
- Editor’s Note
峠の詩
峠の詩
果てしなく
遙かに続く道は
僕の未来を
確かめてくれる
峠をきわめて
のどを鳴らす水が
生きる喜びを
教えてくれる
夕映えの雲に向かって
叫んでみても
孤独の涙は
ぬぐいきれない
だけど
そんな自然が
好きなのさ
タフ・ガイ雑感 – 文学部教授 清原会長
タフ・ガイ雑感
文学部教授 清原会長
明らかに何かに憑かれたように活動する人がいる。こういう人は疲れを知らない。興奮状態の精神病者も疲れを知らない。異常者は別として、平凡な我々でも仕事に疲れた後で、スポーツや道楽に熱中して徹宵、疲れを知らないことがある。
タフ・ガイなどと呼ばれる、かっこいい若者がいる。こういう連中はほんとにタフなのか。私はどうも疑問だと思う。タフ・ガイといっても、やり甲斐のあることにタフなのであって、いやなことには意外に懦天(?)ってしまうのではないか。三船敏郎が心理学の講義にダフっている図など、想像としてまことに愉快である。それはそれとして、とにかく疲れを知らない熱中・集中の状態は、誰でもが人生の生甲斐を感じるものであることは確かである。
問題は、どうしたらそんな状態になれるかということだが、常識的には、その仕事に興味や問題を感じるように自分を向けることだと言われている。この常識がちがっているわけではないが、どうも満足できない。このほかに何か知恵はないだろうか。
1つの方法がある。それは、目標を手近なものにすることである。高い山の頂きを、はるか遠くに見ながら登るのはつらい。そこで、あの尾根、あのコブという手近な目標をおいて登ることになる。仕事を沢山ためこんで、一気に片づけるというやり方も、興味ある仕事ならよいが、きらいな仕事ではどうであろうか。無理にやると、そういう時にはすぐ疲れを感じ、ムダな気晴らしがやたらにしたくなる。仕事の要領がいい人は、こうした作戦・計画を立てて、マメに実行する人であろ
自分がタフであるか否か、性格がどうかなどと気にする前に、生活設計や行動デザインを工夫してみてほしいと思う。よい生活のサイクルを作り出してほしいのである。
1968年度夏季合宿記録北海道 – 教育学部2年 星
1968年度夏季合宿記録北海道
教育学部2年 星
8月5日(月)晴 – 1時釧路駅集合
すばらしい青空の北海道合宿初日である。輸送の際にこわれた自転車を修理し、皆がキャンプしている、釧路川原に着いたのが3時頃だった。対岸に十条製紙の工場が見える。川面に水鳥も浮かんでいる。
テント・器材などを運んで、全員が集まったのが4時過ぎ。参加予定者35名のうち、1名だけ不参加という多人数の合宿である。皆がいろいろなコースでやって来た。すでに、こんがり日焼けした顔がある。しかし、木村(治)君が駅からキャンプ地へ戻る途中、踏切で転倒し、右鎖骨を折るという事故を起こした。合宿を断念して翌日飛行機で帰京することになる。初日から事故が起きて残念だけれども、この事故で皆の気持はひきしまったに違いない。また仲田・中山の両君は、自転車が着かず困った様子。結局、仲田君は新車を購入、中山君は木村(治)君の自転車を借りて走ることになった。最終参加者33名。
5時半から自由行動。それぞれ食事に、銭湯にと散って行く。魚の匂いがするのは、魚市場が近くにあるからか。
8時半、再び集合。ミーティングをやって就寝となる。
初日から大きな事故が起きた。
8月6日(火)晴のち曇 釧路 – 阿寒湖74キロ
リーダー和泉・小川・高橋
6時半起床。早速トレーニングをやる。すがすがしい空気である。そのうまさでバンを朝食としたが、量が少ない。昨日の木村(治)君の事故や仲田・中山君のことで、予定より遅れて9時半出発。完全舗装の国道38号線、240号線を快調に走る。
10時半、釧路丹頂鶴自然公園に着く。たった2羽しか姿を見ることができない。出発しようとした時、井上さんの車が大音響と共にパンク。空気を入れすぎて、チューブが裂けていた。これにより炊事班が変更される。
11時に鶴公園を出て、30分程走り阿寒町に着いた。ここで昼食。12時半、阿寒町を出発。汗をかきながら見る牧場もまたよい。上徹別でちょっと休憩し、のどを潤す。このあたりから上りも厳しくなり、走行も乱れてくる。
3時半、水清らかな阿寒湖畔に着いた。キャンプ料金20円也。すぐ食事の準備にとりかかる。献立はカレーライス。腹がへっていたせいかうまかった。6時近く、木村(治)君のことで遅れた中村さん、斉藤君が到着。キャンプ場近くの風呂に行き、今日の汗を流す。星がよく見え、キャンプァイヤーの歌がやかましく聞こえる夜である。
8月7日(水)快晴 50キロ阿寒湖 – 弟子屈
リーダー藤井・星・高原
5時半起床。まぶしい陽の光がテントの中へさし込んでくる。今日も出発がもたつき、9時10分キャンプ場を出た。昨日来た道路を戻ること20分、地道の241号線に入る。どうしたわけか、阿寒湖から黒犬が一緒に走った。野良犬だろうが、我々の脇を一生懸命についてくる。途中ひと休み。
10時45分、双湖台に着く。黒犬はここまで走り続けたが、出発の時には、その姿は見えなかった。ペンケトウ・パンケトウの眺めの美しさに休憩を延長したが、その間に観光バスで来たお姉さまと、うまく写真など撮り合う奴もいた。30分後出発。
上りあり、下りあり、砂利でペタルを踏めなかったり、アブには刺されるし、観光バスには埃をかけられるし、全く走りにくい。双岳台を過ぎ、下りになると、バンク、ネジとび、スポーク折れなどマシントラブルが重なり、前後の連絡がつかなくなった。とにかく弟子屈まで走り、待つことにする。
途中2回休んで、弟子屈町に着いたのが2時近かった。やっと昼食である。加藤さんがディレイラーを折りながらもやってきて、全員集まる。時間も遅いし、湖畔にキャンプはできないということで、摩周湖までの予定を打ち切り、近くの鐺別川原にテントを張る。開発局の土木出張所にお世話になった。
初めての地道でネジとびが多く、今日のコースは楽でなかったが、弟子屈から阿寒に向かうよりは、はるかに下りが長く、助かった。夕方、ちょっとした地震があったが、テントには被害なし。
8月8日(木)曇のち晴 弟子屈 – 屈斜路湖50キロ
リーダー篠原・堀・仲田
5時起床。昨夜は蚊がうるさくて、寝不足気味。雨が降るかなあ。8時出発が8時半になる。まだ予定通りに出発したことがない。弟子屈町で昼食のパンを買い込み、霧の摩周湖へ向かう。
9時過ぎ、陽がさし始める。舗装はしてあるが、だらだら続く上りを、顔に手に足に汗しながらペタルを踏んだ。9時半、第1展望台に到着。自転車を放り出す。見えた!濃藍の水面に浮かぶ小さな神島。摩周岳も湖水に影を映している。何ともいえぬ光景である。
10時15分出発。集合が悪い。第3展望台からの眺めもまたよし。
湖面は3時頃には霧に包まれたという。運がよけりゃ見られるんですね。またここからは、硫黄山、屈斜路湖も遙かに望むことができた。
11時、摩周湖をあとにする。再び地道の下りであるが、昨日に比べて快適である。単調な下りをとばして、川湯に着いたのが12時過ぎ。ここで1時間の休憩。途中の硫黄山まで戻ってみようかなと思ったが、臭いだけだからやめた。パチンコをする奴もいたが、当然負けてすぐ出てきた。
右に湖を見ながら走り、砂湯に1時40分着。みやげ屋のおじさんが、記念写真を撮ってくれたけれど、誰もみやげを買わないので文句言うことしきり。
そこで早々に出発し、地道、舗装道路を走り、2時半頃、バンガローもある和琴半島のキャンプ場に着いた。夕食まで自由行動としたので、ボートに乗る者、泳ぐ者、波の打ちよせる露天風呂に入る者と思い思いに過ごす。ここで見た夕日はきれいであった。
相変らずパンク、ネジとびが多い。明日は美幌峠である。待ってました!!
8月9日(金)雨ときどき曇 屈斜路湖 – 網走63キロ
リーダー小泉・三輪・中山
そろそろ疲労がたまってきているが5時起床。すぐ起きる者は少ない。小雨が降っている。しっとり濡れた草を踏みつけ、トレーニングをする。きびしいなあ。
去年の荒井君の事故を教訓に、今年はまだフリー・ランをしていないが、6日のミーティング以来、フリー・ランを望む意見が強く、昨夜の論議から、今日は美幌峠頂上までフリー・ランとなる。
8時20分出発。と同時に、僕の車のボトムブラケット玉押しが割れる。近くの自転車店に行ったが、部品がないという。ちょうどパンクを修理していたトラックに乗せてもらい、美幌町で取り換える。美幌峠を大型トラックで越えたことは、非常に残念だった?
10時、大部分の者が到着。峠からの眺めは雨と霧に包まれて、屈斜路湖は全然見えない。せっかく泥道を上ってきたのに…
10時30分、峠を下る。国道改良工事中で、水たまりのあばた道路を走った。雨もだんだん小降りになり、12時半、美幌町に着く頃には止んだ。ここで昼食。それにしても道が悪すぎる。
1時15分に美幌町を出発、完全舗装の国道39号線をひたすら走り続ける。また小雨がぱらついてきた。33名の自転車が、ひとつの線となり、雨に濡れた道を走って行く。実にカッコイイものである。この光景に誰が目を向けないでいようか!!
網走湖畔の呼人でキャンプする予定が、雨のため屋根のある所に泊ろうということで、網走市内まで走った。まず網走市立西小学校に願ったがうまく断られ、市の公共施設もだめの返事。一同が思案にくれている間、天の助けか雨もあがり、青空も見えたりしているので、海岸にキャンプすることになる。
夜、たき火を囲んで、野菜サラダの食事。付近の民家でもらった水で洗った野菜は、暗いから全てきれいだと思って食べたものである。食事のあと自由行動となり、早速に夜の街へと出て行く。藤井君が帰る途中、車に追突し前歯をかかし、フレームを曲げる事故を起こした。
すぐ上の国道を走る車の音がやかましい。打ち寄せる波の音を聞きながら、眠りこけて行く。時計は9時を回った。明日は休息日。
8月10日(土)曇ときどき雨 休息日
リーダー加藤・中村
雨にしっとり濡れた砂が、テントの中まで入っている。7時に起床。今日は全て外食をすることになった。砂が入った飯は、あまりうまいものではない。休息日ではあるが、個人的行動は許されず知床半島へ行く者、能取岬へ行く者と網走周辺を回る者との3つに分けて過ごすことになった。
知床半島は霧雨にけむり、非常に寒かった。22トンという小さな船は、オホーツクの荒波に大きく搖れ、気をもませられた。断崖に巣くう海鳥。あくまでも澄んだ濃い緑青色の海。重くたれ下がった鉛色の空。まさに「知の果て」知床は、人を寄せつけない感じであった。船酔いを防ぐため、大声で歌う。
能取岬へは、8名が愛車に乗ってポタリング。40キロを走って、のんびり過ごしたが、疲労のたまった6名は、昼から天都山へ行った。この14名が、呼人にテントを移し、知床探訪組19名を待っていた。ご苦労さん。
それにしても疲れる休息日だなあ。計画を欲張りすぎるのか、日程が短いのか。全く疲れました。合宿は睡眠不足との戦いだとか。
8月11日(日)曇のち晴 呼人 – 温根湯温泉79キロ
リーダー小島・会田・一柳
6時半起床。やっぱり眠たい。トレーニングが終わっても、朝食が食べられない。8時15分、キャンプ場を出発し、呼人駅前でパンを買い、朝食とする。
8時50分、腹ごしらえができたところで美幌町へ向かう。1昨日走ってきた国道39号線を引返しながら、同じ道を走るのはつまらないと思った。見る所なく案内標識を見ていた僕は、前のグループに気づかず追突し転倒、道路に投げ出される羽目になる。9時45分、美幌町に着く。
10時25分、集合が悪く遅れて出発。峠とはいえぬだらだら続く坂を上って行く。この姿はあまり壮観とはいえない。上りきった所ですばらしい眺望が開けた。やはり上ったあとは気持がいい。北見まで21キロ。ずっと下りである。楽な気持で走り出した。
祭りでにぎやかな北見駅に、11時40分着く。ここで昼食。1時間の休憩を取った後、温根湯へ向かう。全くの舗装路。実に単調である。留辺蕊町で小休止。
キャンプ地の温根湯湯泉には、2時過ぎに着いた。テントは、川のせせらぎを聞く土手の上である。銭湯はイオウの匂いがして、気持悪い。土産店で木彫りの実演をしていたが、そのおっさんはバッジを集めることに、異常なる執念を持っていて、バッジと木彫りのペンダントとを交換してくれる。我がクラブ員の中にも、このおっさんに協力した奴がいた。
今日は全く見る所なし。眠たいという声が聞こえる。明日は北海道の屋根といわれる石北峠を越える。
8月12日(月)小雨のち晴 温根湯温泉 – 層雲峡61キロ
リーダー斉藤・遠藤・保泉
朝から小雨がしとしと降っている。初秋を思わせる涼しさである。
5時起床。朝食後、しぼりたての牛乳を飲んだが、中味が濃くてうまかった。しまりがないだらだらとした行動が続く。
8時25分出発。石北峠はきついだろうか。なんとなく気も重い。空も重苦しく雲がはっている。道路わきのハッカ畑の匂いだけが、ちょっと心地よく感じられる。10時10分、イトムカ水銀精錬所に着いた。山肌は緑が少ない。なんとか雨は止んだようだ。
10時半、フリーランの形で、峠頂上1,050mを目指して出発。かなり急な勾配もあったが、額に汗してペタルを踏んだ。つづら折りの道のしつこいこと!4、50分健闘の後、ようやく峠にたどり着く。すぐに自転車を放り出して、ガブガブ飲む水のうまさは格別であった。期待していた眺望も、曇天ではっきりしない。しかし、上りごたえのある峠である。展望台に腰を下ろし、昼食のバンをかじった。しみじみと征服感を味わうのも、この時である。
12時20分、峠を下る。完全舗装で下りとくれば言うことなし!非常に快適なダウンヒルであった。緑濃い原生林を、右左を見ながら風を切って飛ばす。大雪山国立公園を走っている。大阪を過ぎる頃から、切り立った岩、流れ落ちる水、岩にはいつく緑、わずかの空間に青空といった渓谷美が始まる。この美しさに魅せられ、各班の行動がまちまちになってきたため、リーダーは班別の自由行動を許すことになった。走っては写真を撮り、撮っては走るという繰り返し。層雲峡YHからやってきたのであろう数人のポタリングを楽しむ若者がいた。この自然美がいつまでもこわされないであって欲しい。
2時15分、国立層雲峡キャンプ場に到着。国道から脇にそれ、ものすごい勾配の坂道を押して上る。国立とはいえ、藪の中に土の顔を見せた位のもので、特に水の出が悪いのには閉口した。私設キャンプ場とあまり変わりはない。
6時の夕食まで自由行動、食後に各自絵はがきをOBに書くよう指示し、再び自由行動となった。この時に禁酒の約束を破った5人が、主将からお目玉をもらう。団体行動の上においては、規律を守るべし。
10時、疲れながらも、今日の景色のすばらしさを想い出しつつ就寝。星空もまたきれいだ。
8月13日(火)晴 層雲峡 – 旭川66キロ
リーダー篠原・及川・松本
太陽の光が強くテントに入ってくる。10分睡眠をとるため、今日は7時起床。トレーニング後、パンで朝食とする。
9時10分に出発したが、やはり予定より30分遅れた。上川町までずっと下りだが、向い風に悩まされる。自動車の通りも少ないということで、班別の集団追越し方法をとり、走行に変化をつけた。しかし、スピードアップを狙ったこの方法も、不慣れなせいもあつてか、車間距離を10分とっていなかった和泉君と高橋君の接触転倒事故で取り止めとなる。けがはすり傷程度であったが、この事故で各班の間の距離が大きくあいた。踏めども踏めども追いつけなかった。全員がそろったのは、愛別町の石狩川の土手の上で小休止をしていた時である。時は予定よりはるかに遅れて11時半。20分後、旭川に向けて出発。このあたりから、車も多くなってきた。町並みをはずれると、頭をたれる稲穂が目につく。またも単調な舗装路が続く。
1時、旭川駅前に着いた。遅れに遅れたが昼食となる。2時からキャンプ地に行く。2時半、神楽岡公園のキャンプ場に着く。ここで班別にポタリングに出かける。役割のない班は、すぐに走り去った。残った班は、各自の仕事を済ませてから出かけた。5キロ程度のポタリングで、近文アイヌ部落を訪れた。観光化されたものの持つわびしさを感じた。
7時、夕食となる。4人のグルーブで、デンギス汗料理をつつく。なかなか火が燃えず、待ち切れずに生の肉を食べる奴もいた。野外で食べる料理としては、うってつけのもので、うまかった。食後、他のキャンパーと一緒に歌を歌ったりして過ごす。
9時半からミーティングをする。熱のこもったミーティングであった。集団追越しの走行方法についての論議、それから波及して執行部の独裁に対する反論と、異常な雰囲気になっていった。明日の予定を変更したということも、原因のひとつであった。集団追越しについては賛否両論がまちまち、執行部についても意見は平行線をたどった。結論は出ず、そのまま終わってしまう。しかし、33名もの多人数を統べて行くためには、少なからず独裁的にならざるを得ないであろうと思う。
遠くから太鼓の音が聞こえる。盆踊りの太鼓であろう。聞いたことのあるリズムだ。
8月14日(水)晴 旭川 – 砂川79キロ
リーダー板橋·加藤
今日は休息日の予定であったが、明日140キロを走ることは無理なので、ちょっとコースを変えて走り続ける。
5時半、起床の声がする。すぐには誰も起きない。6時からトレーニング朝もやの中にかけ声が響く。映画に撮るということで、45分もしぼられる。7時20分、朝食となる。運動した後だけにうまい。
8時40分にテントをたたんで出発。石狩川に沿って下る。神居古潭で小休止。巨石が流れに逆っている景色を見ていると、カムイコタン(魔神の住む里)の名が出てくるのも無理はないと思った。
10時45分、15分の休息の後またペタルを踏み始めた。国道12号線を1列に走る。少し走ってから左に折れ、国道をそれる。ここから新城峠 – 芦別 – 歌志内 – 砂川という炭鉱町を通るコースも走ることになる。新城峠というものに変化を求めたのであるが、なんなく上れる峠であった。かえって名もない坂道の方がきつく感じられた。新城峠には11時40分上り着く。買ってきたパンで昼をとる。長野県に見られるような風景である。
12時10分、峠を下る。まだ工事中の道路で、地道だったり、舗装路だったりする。ほこりもかなりかぶった。45分位走り、常盤町で休息。このあたりから炭鉱町の特徴が見られる。山腹にならんだ画1的な家。ここにも斜陽化産業の匂いが感じられる。
歌志内市には2時近く到着。腹がへったという者が多いため、再び食事をとった。駅前に盆踊りのやぐらがある。2時半出発。かなり起伏のある舗装路を、砂川市へ向かって走り続けた。
3時過ぎ砂川市に入る。キャンプ地は先発隊の捜した砂川畜産センターだった。こんな所にテントを張るとは思わなかった。4時からパンク修理の講習をやる。たいていの者が軽くやってのけた。しかし、この講習でパンクしていないのを、わざわざパンクさせる奴がいて、笑いを誘った。
7時から夕食。事務所みたいな車庫みたいな建物の中で食べる。屋根の下、電灯の下で食べるのは、何日ぶりだろう。旅先で感じる人の温情も手伝ってか、郷愁にかられた。明日で合宿も終わる。事故のないよう祈りつつ眠る。
8月15日(木)快晴 砂川 – 札幌82キロ
リーダー滝野・堺・宮崎
このところ天気に恵まれ、快適なツーリングを続けている。今日が走る最終日。朝からカラリと晴れ上がった。6時半、起床。朝露をふんで向かいの公園でトレーニング。すぐ近くに石狩川が流れている。8時に朝食をとる。
9時10分出発。すばらしい直線道路が続く。さすがは広大な北海道である。しかし、自転車で走る者にとっては、いささか苦痛である。1時間程走って、美唄市で休憩。10時20分、札幌に向かって走る。畑や水田を見ながら、ただ走るだけである。岩見沢市で小休止をとり、なおも走り続ける。
12時、幌向付近を走っていた我々は、終戦記念日ということで、自転車を降り、1分間の黙とうをする。戦没者の安らかな眠りを祈る。あやまちは2度と繰り返したくない。
山の姿を望むことのできない石狩平野を、33名がどんどん走る。12時半、江別駅前に着く。昼食のため、1時間の休み。それにしても、青空にさえぎるものがなく、とても暑い。
1時半に出発。20分位走ると「札幌市」の標識があった。しかし、札幌市の広いのには驚いた。走っても走っても、中心街に着かない。結局、札幌駅前に着いたのが、3時10分であった。駅前の電光掲示板には、「明日の天気…曇り時々晴れ、只今の温度・・27度」と出ていた。北海道をほぼ横断する形で走ってきた合宿も、まずは終わった。彫像の前で、主将副将らを胴上げし、記念写真に黒く焼けた顔を並べた。この地出身の堺君を中心に3名程が、キャンプ地を捜しに出かけ、残りの者は大通り公園で待つことになる。自由行動が許され、ラーメンやとうもろこしを食べに行く者が多かった。
繁華街をはずれてはいるが、自衛隊の前を通り、車の通りの激しい道路を走ること30分位、札幌市の管理するヒューム管が置いてある空地に、テントを張ることになる。風呂に行って、北海道のあかを全部落した。あとはコンパを待つだけだ。
日もとっぷり暮れ、空に星が輝く頃、すき焼き料理を食べながら、サッポロジャイアンツを飲みながら、コンパが始まった。飲むほどに酔い、酔うほどにいつもの調子になっていった。キャンプファイアも赤く燃え、若人の心そのものだった。空地の向こうでは盆踊りをやっている。こっちでも騒ぎ暴れ回った。夜更けた11時頃、騒ぎ疲れた体を横たえたら、眠くなった。
8月16日(金)晴
最終日ではあるが、6時起床。昨夜のあとかたづけをやる。空いたビールびんを見て驚いた。こんなに飲んだかな?
8時から総合ミーティング。昨夜のファイアを「天よりの水」で消したため、刺激性のある匂いが漂う中で、活発に意見が出た。
・合宿の場所が遠すぎる。合宿が単に足を鍛えるものならば、別に北海道まで来なくてもよい。
・合宿はただ走るだけでなく、比較的暇のある学生のうちに、数多くの見知らぬ土地に行く方がいい。
・小休止をとる毎に、走行順が変わる方が疲れないようだ。
・人数が多すぎると、かなり自由が制限される。集合地は同じでもも、途中から何班かに別れ、別コースをとり、再び合流し、解散地まで走るという方法はどうだろうか。
・休息日は完全な休息日であってほしい。睡眠が10分とれない。
・自由時間が少ない。合宿日数が長くなるかも知れないが、自由時間が多く欲しい。
このような意見が出たが、全体の感想としては、合宿にきてよかったとか、面白かったというのが強かった。来年の合宿は、この意見を参考に、よりよい合宿になることを望む。
ミーティング終了後、器材を札幌駅まで運び、荷造りし発送。11時半頃、今年の夏季合宿は終りをとげ、解散となった。木村(治)君の事故を除けば、大した事故もなく、一応うまくいったのではなかろうか。
厳しさの中にも楽しさがあり、合宿だからこそ知り得た、味わえたという充実感。ついに終ったという虚脱感。ふたつの感じが入り混じる僕は、札幌をあとに、函館へと走り始めていた。
夏季合宿食事献立
8月5日夕外食
8月6日朝パン3種類、タカレーライス 担当渡辺敏明
8月7日朝みそ汁(ワカメ)、トマト、キャベツの塩もみ、タ肉汁
8月8日朝みそ汁、卵、カン詰
8月8日タクリームシチュー、カン詰
8月9日朝みそ汁、梅干し、カン詰、夕野菜サラダ、コロッケ、天ぷら、スープ
8月10日朝外食、夕外食
8月11日朝パン、夕他人丼
8月12日朝みそ汁、梅干し、海苔、カン詰、タケチャップ炒め(玉ねぎ・ピーマン・ソーセージ)、みそ汁(卵とじ)
8月13日朝パン、野菜サラダ、牛乳(2本)、タヂンギス汗料理
8月14日朝みそ汁、たくあん、ソーセージ(マヨネーズ付き)、タハヤシライス
8月15日朝みそ汁、卵、たくあん、納豆、夕すき焼き、ビール
8月16日朝外食
夏季合宿後記 – 主将加藤晃
総勢33名、12日間の北海道合宿も、無事終った。わりあい天気に恵まれ、毎日キャンプできたのは、幸いであった。新入生にとっては、初の長期ランを、あの雄大な北海道で送ったわけであるが、満足できたものと信じて疑わない。
今年は33名もの大合宿で、各々がサイクリングに関しての意見、あるいは疑問を持ち、ミーティングで討論しあえたことは、よい収穫であり、今後役に立って行くものであろう。マシントラブルも多かったが、これも又ある意味ではメカニズムに詳しくなるということで、非常に有意義であった。
今年の合宿で感心したのは、1年生の走行マナーの良さである。簡単なことだが、1列走行を守って、班の走行を乱すことが殆んどなかったのは、後から見ていても気持が良かった。ランにおいて残念なことはただひとつ、峠の厳しさが少なかったということである。班内における行動でも、指名した班長に従って、テント設営、買い出し、食事等をスムースに運んでとても良かった。
何はともあれ、初日の木村(治)君の不運な事故を除いたら、全員無事に釧路―札幌を走破できたのも、執行部及びクラブ員全員が一致団結して、行動してくれたからであり、今後のオーブン・サイクリング、早同交歓会もこの意気で頑張ろうではないか!!
最後に、映画製作担当の辻山、坂本の両君、どうもご苦労さん。
1968年9月17日
想い出 主将の任期を終えて – 商学部3年 加藤
想い出-主将の任期を終えて
商学部3年 加藤
“よし、やってやるぞ!”昨年度最後の総会で第6代主将に選ばれ、品田前主将からバトンタッチをして大いに闘志を燃やしてから、既に1年余。全く月日は夢の様に早く過ぎ去るものである。今この1年を振り返るにつけ、数々の苦しみや楽しかった想い出が、鮮明に心の中に甦ってくる程、主将という責任重大かつ光栄ある役職の経験は、未熟な私にとって非常に厳しくまた価値あるものであったと思っている。今年度の活動が開始される4月前、私はクラブ運営にあたっての私の基本方針を何回も再確認してみた。単なる過去の踏襲は、何ら進歩を生み出す事はできないだろう。
10年前、この早稲田に産声をあげた我がクラブも、現在は総員40名を誇る早稲田大学公認のクラブに昇格し、幼年期から少年期を経て更に成年期へと脱皮を図る過渡期にある現在、我々が為さねばならない事は、クラブ構成単位であるところの自分達をクラブ員として深く自覚し、己を鍛練し全てのクラブ活動に積極的に参加する事である。
そして対外的に更に飛躍的発展を遂げる為には、その基礎となるクラブそのものが、しっかりと組織化されなくてはならない。そう思って今年度の最大目標を”内部組織の強化”に置き、昨年度とは180度違った方向への運営に挑戦してみた。具体的な例を示すと、第1に全てのランに於いて、全員参加を目標とした事である。従来の様に参加者に名前を書かせるというのではなく、不参加者に名前と理由を公用ノートに記入するなり、口頭で私に言うなりして届けさせる様に命じた。
第2に、それまで名ばかりの役職であったトレーニングマネージャーの地位を向上させる事、即ちラン以外に於ける定期的なトレーニングの実施であった。このトレーニングについては、3年生をはじめ諸運営委員の間でも賛否両論があったが、私としては、我がクラブがスポーツ部門に属する以上、トレーニングを実践に移す事は、必要かつ欠くべからざることであると思っていた。なるほど、我がクラブはスポーツ団体ではあるが、その性格上、敵と技や力を競って勝負を決めるということはない。しかし、峠などをアタックする時、言葉では表わせない苦しみの中で自分自身に克つという点では、他のスポーツと相通ずるものがある。結局、サイクリングでも最終的に頼りになるものは、自分自身の脚力及び体力なのである。このトレーニングの実施形態については、有能なトレマネである小泉君に一任し、週最低1回参加を義務づけた。
では今年度の活動記録をひも解きながら、今期の反省と来期以後の抱負を述べていきたい。
今年度の新人募集は、4月中旬までに多数を集める事ができ、まずは上々のスタートを切った。新入生歓迎コンパも盛大に行なわれ、いよいよ第1回のランが相模湖で行なわれた。私はこの時体の調子を悪くしていた為、残念ながら参加できなかったが、好天に恵まれ、事故もなく終わった事を聞いて安心した。以後、多摩丘陵、鎌北湖、鎌倉、丹沢などへのランを行ない、昭和43年度夏季合宿を迎えたのである。6月の運営委員会で、既にコースは北海道の釧路から札幌までと決められ、参加予定者も今までの最高である35名にもなった。合宿形態は、昨年度と同じように班に分け、細かい事は私の指名した班長に全て任せる事にした。
8月5日、釧路には定刻通り34名が集合し、無届けで欠席する者は1人も無く嬉しかった。この日、木村(治)君が事故を起こし東京に戻ったのが、唯一の残念な事だったが、以後33名全て無事に札幌まで走破する事ができた。とりわけ、1年生の走行マナーは非常に良く、1列縦帯の編成を組んで快調に走る様を後から見るのは、とても気持が良かった。この合宿中、私は数々の難問や疑問にぶつかったが、常に自分の信念に基いて統率していったつもりで満足している。各班長並びに諸役員も本当に良く働いてくれて、ここに改めて感謝する次第である。幸い天候にも恵まれ、雄大な北海道の原野で、11泊すべてテント生活ができたことも大きな収穫であった。特に最後の札幌の夜、盆踊りを見ながらの野外コンバは、忘れる事のできない楽しい想い出のひとつである。
合宿終了後、御殿場で我がクラブ主管の下でESCA夏ラリーが行なわれた。このラリーに於いては、我がクラブが誇る名ESCA理事の板橋君の指揮の下で、ラリー初のサイクリング・トロフィーを行ない、各校の絶賛を浴びた。参加人数は各校とも予定者より少なかったが、板橋君の努力により、沈滞気味のESCAに「カツ」を入れた感じであった。中山、寺島両先輩も来て下さり、有意義なラリーとなった。来期以降のESCAの発展を期待する。
さて前期試験の終わった後、10月13日には早慶親睦ランが行なわれ、後期活動が始まった。この時期からトレーニングを休む者が増え始め、1年生もクラブに慣れて来たせいか、少々ダレたムードがあったが、オープンサイクリングを迎えて、再びまとまった感じであった。今年のオープンサイクリングは、運良く新聞に掲載されたため、一般から50名を越える申込者が殺到し、途中で打切った程の盛況であった。しかし亜細亜大と同じ10月20日に重なった為、自転車を集めるのに非常に苦労した。天候こそ良くなかったが、篠原君を筆頭に後輩の努力で狭山湖で楽しい一日を過ごす事ができた。
来期以後のオープンに於いては、各校と連絡をとり日程が重ならないよう注意すべきである。今年度の体験から得たひとつの教訓である。
早稲田祭が開催された期間、我々は2泊3日の秋季合宿を紅葉の美しい軽井沢で行なった。この合宿に今年度からの新しい行事として戸田橋―軽井沢間のタイムトライアルを折り込んでみた。距離が短いとスピードランになり事故の発生率が高くなるので、敢えて長距離にし、自然に走りながら時間を競うという方式を採った。3位までの入賞者にはメダルを与えたが、このトライアルの真の目的は、単にクラブ員同志がそのスピードを競うというものではなく、それまでのランで培われた自分自身の脚力及び精神力の向上というものを、タイムというひとつの有形的結果を対象に知るところにある。来期からも続けていって欲しいものである。
さて時も11月下旬、後期の最大行事である恒例の第5回早同交歓会が、秋晴れの三浦半島で開かれた。今年度は我々が主催したので委員長の落海君も大変だったようだが、両校の親睦をさらに高めた交歓会であったと信じて疑わない。ただひとつ心残りなのは、両校の4年生の参加が少なかった事であった。
以上をもって今年度の活動の殆んどが終了した。4月当初、私が描いたクラブの理想像へ向けての180度転回運営も、残念ながら完全には徹底せず、90度止まりという事になったが、残りの部分を後を引き継ぐ後輩達がきっと成し遂げてくれるものと期待している。そして、諸先輩達から受け継いできたクラブに対する情熱の炎を絶やすことなく、未来に向かって大きく羽ばたいていって欲しいものだ。”自己犠牲の精神を忘れるな!そこに真の人間性―美が存在する”
最後に、折りにふれ激励して下さった諸先輩、ならびに今年度の活動に協力を惜しまなかった諸役員に、心から感謝の意を表しながらこの筆をおくことにする。
資料局の1年間 1968年活動記録 – 法学部2年 篠原
資料局の1年間 1968年活動記録
法学部2年 篠原
今年から新設された資料局。その局長(といってもただ1人であるが)として、この1年間をふり返ってみる。
まずこの資料局ができた意図がはっきりしていなかったために、最初は何をどうやっていいのか戸惑った。が、とにかくクラブ・ランの記録を残すということを専らの仕事とし、それと共に、その写真も残そうということになったが、写真の方は係が一定せず、しかもクラブ・ランに常時参加しなかったりして一貫性を欠き、十分に実現できなかった。それと、ニュー・サイクリング誌を毎月購入するということもうまくいかなかったように思う。この点は来年もう少し検討する余地があると思う。
ではこの1年間の活動状況を、クラブ・ラン中心に述べて行こう。
5月4・5日 新入生歓迎ラン(奥相模湖方面)
参加者15名
今年度最初のクラブ・ランではあるが、主将が病気のため参加できず、副将である小生が代行する羽目になった。3年生の手前、やりにくい感がしないでもなかったが、それにこだわる事なく代行できたのは、3年生諸氏の御好意によるところが大きい。
4日、土曜日で授業と重なる者がいるために、先発隊と後続隊に分けた。先発隊は、板橋・伊藤・落海・新聞・仲田・保泉の6人で、9時に出発した。後続隊は1時に出発した。
道は甲州街道を相模湖まで、おなじみのコース。小生は後続隊だったので、その模様を述べる。まず新入生が6人とかなり多いにもかかわらず、いつもと変らず、いやそれよりも早く走ることができたということは、非常な驚きである。新宿から府中までノン・ストップで1時間、府中から八王子までこれまた1時間。4時前には高尾に着いていた。
高尾から大垂水峠頂上までフリー・ランとする。小生はラストを走ったが、自分個人としては最悪だった。足に力が入らず、かといって腹が減っているわけでもない。坂をエッチラ上っていくと、前方で2人が歩いているのには驚いた。最初の事だし、主将がいない事でもあり、黙っていた。1番遅い者で40分程度で上りきった。
甲州街道からの分岐点に着いた時には、6時になっていた。が、これからが大変な地道で、しかもほとんど上りときている。ここで日も暮れ、3分の1ほどが歩き出した。小島が足をつったといって歩いていたので、小生も一緒に歩くことにした。半ば失神状態で、ただ飯を求めて歩いているといった感じだ。
夕食は新入生歓迎ランということで、先発の3年生が作っていてくれた。1年生はまったくノー・タッチ。食事後、ミーティングをやり、1年生の感想を聞いたが、やはりきつかったといっていた。中には楽しかったという奴もいたが!!打ち解けたところでキャンプファイアーをやり、1年生に各自の故郷の歌を怒鳴ってもらい、上級生は例によって「今月の歌・シリーズ」をとめどもなく歌った。
5日は起床7時。朝食は2年生が作った。今朝はまったくの快晴で、非常に暑そうだ。出発9時半。最初から昨夜の様に上る。道は未舗装であるが、車の少ないのと、天気がいいのとで、サイクリングとしてはまったく最高だった。舗装路に出る手前で和泉が転倒、かなり広く傷を負った。事故第1号である。前と少し離れたので、追いつこうとあせっていたところ、砂利道のカーブでハンドルを切りそこねたのが原因。
舗装路に入って津久井湖へ向う途中、高橋が転倒。傷は大した事がなかったが、ハンドルを大きくまげた。前から車が大きくセンター・ラインをオーバーしてきたので、それをよけようとしてハンドルを切ったが、そのまま端の石にあたり転倒した。
津久井湖で昼食をしてからは順調に進んだ。七国峠、野猿峠もなんなく越して府中に到着、ここで及川と会う。彼は今朝5時に出て奥相模湖まで行ったそうである。まったくご苦労。府中で解散。
5月12日 多摩丘陵ラン
参加者21名
小生参加しなかったため、詳細はわからないが、中山が砂利道の下り坂で事故を起こした。それを本人の文章で載せる。
砂利の坂道にて、スピードは中の上ぐらいでした。砂利の中で自転車がおどりましたので、横の砂利のない所へ出ようとし、ハンドルを切りましたところ、スリップして体は土手の方に1回転。自転車は右へ転倒。怪我はありませんでしたが、クランクがベタルのつけねから折れてしまいました。
5月19日 エスカ新入生歓迎会
参加者17名
エスカ理事校である都立大学で行なわれた。新入生歓迎会ということで、クラブの紹介や、映画を見たり、教授の話を聞いたり楽しく過ごす。また、夏ラリーを我がクラブがすることになった。
5月23日 総会 文学部105教室
参加者36名
1、会計報告
前年度会計担当の田北さんが欠席のため保留。後日改めてすることになる。
2、合宿
北海道に決定。8月一日から2週間以内。集合は現地。詳細は6月の総会に回すことになった。
3、エスカ夏ラリー
我がクラブがやることに決定しているので、特別な理由がない限り強制参加。理由ある者は大堀と堺の2人。
4、早同交歓会
一応クラブ員の希望を聞いた。都内、富士、日光の3コースがあがったがどれも大差なし。同志社に聞いてみてから検討することにする。
5、オープンサイクリング
総務は篠原、コース作成は小島、自転車は小泉が責任を持ってやることに決定。期日は10月10日。これを考慮して、早目に着手する。
6、主将から新入生に対して諸注意
なお、会長の清原教授は、都合が悪く出席されなかった。しかも研究の都合で辞意を表明されているとのこと。これも後日、詳細が明らかになるであろう。
5月26日 鎌北湖ラン
参加者20名
参加者のうち、2年生よりも3年生が多いというのは、まことに遺憾である。
出発8時半。川越街道をただ川越を目指して走るのみ。途中、坂本がどういうわけか、はぐれて遅れた。平林寺を出てすぐに、一柳と松本が衝突、お互いに転倒して傷を負う。交通量の多い川越街道上での出来事なので、注意不足を戒める。この辺で、守谷さんが合流。今年度のランで最初の4年生参加。
川越市の喜多院に向かう途中、リーダーの板橋さんがパンク。その間、小生がリーダーとなる。喜多院に着いてから、後続者を待つのと昼食とで1時間余り。出発は12時半となり鎌北湖へ向かったが、途中、鎌北湖へ行くとすごく遅くなるというので、各自の意思により、近道して宮沢湖へ行く者と、計画通りに鎌北湖に行く者とに分かれる。
小生は宮沢湖へ行き、飯能、入間、所沢、田無と順調に飛ばし、早大学院前で解散。
6月1日 早慶戦コンパ
参加者20名
このコンパは、完全に1年生ペース。今年の1年生はすごいとは上級生の弁。いやまったく同感です。全員銅像前で校歌合唱。馬場まで出て解散。
6月9日 狭山湖合同サイクリング
参加者20名
小生は次回の2年生企画ランの下見のため、房総半島に出かけて参加できなかった。そのため、板橋さんに依頼した報告をここに載せる。
この日、2組のクラブ・ランが行なわれた。しかも同じYWCAから自転車を借り、同じ場所から出発し、同じ目的地へ行くのだ。
ではどうして2組に分れてしまったのだろうか?それは1年生の松本が立案した留学生との交歓サイクリングが、クラブの企画とは全く関係のない経路をとって、計画されたからだ。松本はクラブ・ランのない6月2日(早慶戦)に、そのサイクリングを行なおうとしていた。しかし、これが1週間延期をよぎなくされてしまった。本来なら、合サイのある日に別の合サイを行なうなどということは、認められるべきものではない。クラブのまとまりを重視するならば、強引にその合サイを握りつぶすべきだろう。この留学生交歓サイクリングをどう処理するかは、結果的には私の一存によって決められた。主将の加藤には、決定事項を承認してもらうという形になってしまった。加藤がそのランを知ったのは6日であった。それは加藤と私とが、常に相互に緊密な連絡をとる努力を怠ったことが原因だった。
私のとった処置は、留学生交歓サイクリングを止めるどころか、これを積極的に肯定し、自転車を無料で借りられるように手配してやった。その処置は根本的にはクラブのためを思っての事である。その理由は、第1に、単にクラブの統制に固執することをやめ、WCCのサイクリング活動というものを、より高い立場から考えた場合、外部への能動的行為こそ、重要な要素であると考えたからだ。第2に、松本を含む1年生の自主性を尊重したかった。このサイクリングを許可することにより、1年生と3年生との良好な関係が維持され、かえってクラブのまとまりが強まるだろうと考えた。最後に松本が計画するにあたり、その自主性は常にクラブという組織体を無視したものではなかった事をつけ加えておく。
三鷹駅北口。8時半というクラブ員集合時間に遅れたのは、ほんの2、3人だった。8時45分、中村など4、5人を残して他の者は全員YWCAに向かった。出発前の整備は、ブレーキ点検、チェーンの注油を重点的に行なった。パンク車が2台あり、その修理のため30分以上のロスが生じた。日本女子大の参加者4人がYWCAに着いたのは10時だった。1時間の遅刻だ。それに参加者は半減していた。逆に留学生の方は8人も来てしまった。自転車は13台しかないので、日女大が予定通り来ていれば、3台不足という事態に陥っただろう。
留学生はマレーシア人とはいうものの、日本人と区別がつかなかった。クアラルンプルの華僑だろうというのが、もっぱらの意見だった。早稲田の学生ばかりでなく、お茶の水大、水産大、日本学校の学生も加わっていた。増えた原因は、こうした飛入りがあったためらしい。自転車の配分、サドルの調整にも手間どり、結局、出発は10時45分になってしまった。「合サイ、オープンの整備時間は1時間以上かかると思え」というのが、今日の教訓だった。
小金井公園、小平で休憩。多摩湖の南、滝見橋に12時45分着。20キロを2時間。橋付近の斜面の木陰で昼食。1時半発。狭山湖へ向かう。途中で亜大のオーブン・サイクリングの1隊とあった。顔見知りの人と2、3分立話しできる程、日女大の女性達は遅れていた。わずかの上りで時速15キロのスピードも出せない程疲れていた。2時半、狭山湖の堤防先の草地に着く。小泉の司会で1時間ゲームを楽しむ。3時45分、帰途に着いた。2時間も予定をオーバーしていたので、奥狭山湖コースはカット。
4時前後の青梅街道の混雑は激しかった。特に行楽帰りの観光バスとダンプカーは目立って多かった。青梅街道駅で休憩。ここで思わず微笑をさそわれる光景に出合った。先頭より10分程遅れた加藤は、フラット・ハンドルに乗ってやってきた。よく見ると、後に森田さんという日女大の女性を乗せている。何十回もクラブ・ランに参加しているが、2人乗りというのは初めてみた。狭山湖から5キロ位の所から、ずっと乗せてきたのだそうだ。加藤のたくましさに感心し、随分珍らしいこともあるものだと、腹から笑いがこみ上げてきた。落海は、加藤の自転車を、最後まで2台引きしてもって帰った。2人に心から御苦労様と言いたい。
また、参加者が40人、50人と多くなるオープン・サイクリングのコース作りの難しさを感じずにはいられなかった。小金井公園で休憩。6時、YWCA着。松本達は留学生の下宿に招かれて、コーヒーとお菓子をごちそうになったため、整備には参加できなかった。後でそのことをあやまること限りなし。解散は三鷹の武蔵野YWCA7時。
日女大からの参加者が少なかった原因を考え、今後、女子大との合サイを、続けて行くべきか否かの1資料としたい。
6月15、16日 横浜氷川丸ユースホステル1泊ラン
参加者24名
参加者24名というのは、我がクラブ史上最高人数だそうである。これだけで走れば、さぞかし壮観なものだったろうに!というのは、日曜日の16日が雨のため、その日程が、全面的に中止となったからである。
15日、夕方5時半に氷川丸集合の予定。遠藤を除く全員が時間通りに集合。ユーテルのため、クラブとしてよりも他の宿泊人などとの交歓に力が置かれた点は少し残念だったが、それでもこれだけの人数で1ヶ所に泊まったので、自然発生的なクラブの雰囲気は、非常によかった。4年生の参加がなかったのが残念だったが、2年生が最も多かったのは個人的にも非常にうれしかった。
16日、朝から大雨。朝食後、10時まで待機。しかしながら、雨はやまない。止むを得ず、横浜で解散。24名、全員そろって走るという事はできなかった。結果的にはクラブとして走るということはできず、まったくプライベート・ランの方が多かったようだ。
ともあれ、板橋さんのこの企画は、全員が1ヶ所で寝泊まりしたというだけでも、充分その目的が果たされたと思う。
6月23日 丹沢ラン
参加者15名
小泉と小生は、オーブン・サイクリングの下見で、このランには参加しなかったため、2年生の参加ゼロという不名誉なことになった。遠藤に依頼した報告を、そのまま載せることにする。
9時、二子橋集合。私を含めて、5 – 10分の遅刻者あり。またここで自転車を手入れしたので、出発は9時半頃だった。厚木街道を下る。厚木街道は、なかなか整備されているし、適当な坂があり、サイクリングには面白いと思った。坂を上った後で前方を見ると、道路が直線のため見通しがきき、また坂になっているのが見えるのはなんともいえない気持だった(つまりガッカリする気持と征服する気持の両方がわくこと)。高原君と加藤さんが共にパンクで、2つぐらいの班に分かれて走り、先行隊が30分ばかり待ったこともあった。また、宮崎君が下り坂のカーブでスピードを出しすぎ転倒した。幸い軽いケガだけだったが、くれぐれも注意したい。大山方面へ向かう道の曲り角のところで、全員バンを買ったりして昼食の準備。1山いくらのトマトを買っていた人もいた。
昼食のため、先の曲り角から少し入ったところの左側に、適当な神社があり休む。板橋さんいわく
「昼食の場所としてはいい場所だな。下見もしてないのに、こんな所を見つけられるカンは、素晴らしいもんだぞ」
そうですかネ。私には少し疑問?とはいうものの、板橋さんからもらった弁当はうまかった。卵焼きとおにぎり(コンビーフ入り)。やっぱりサイクリングには、にぎりめしがいい。バンじゃどうも趣がないなと思った。出発。ここまでは舗装道路だった。これから少し行くと、ひどいほこりの泥道とあいなった。まして細い道なのに大型ダンプが数多く通り、そのたびにホコリを浴びるのには閉口した。またラリー中という何台もの自動車と行きあった。道はだんだんと上りになり、どうやら1つ峠を越した。大橋という橋のところで、全員自然的に休む。このへんはキャンプ場があり、またもっと先の橋のところでは、下の急流の所でキャンバーと思われる人がたきびをし、魚をとって焼いていた。なかなかいい所だった。1年生の歓迎にはもってこいだと思ったが・・・
また少し行って本日2つ目の峠、これを越えて(このへんの描写は、あいまいにつき、間違いがあるかもしれません)、鳥尾原というバスの停留所のたんぼ道で休息。落海さんはブレーキがこわれてしまったので、修理しようとしていたが、ネジかなにかがどうしてもなくて、帰りは片方のブレーキで下ることになった。この頃、天気が少しあやしくなり、パラパラと降り出し、また雷も聞えたが、大したことにならなくてよかった。
3時22分出発。下り坂だが道が悪い。スリップ止めのような溝が道にできていて、ガタガタと大変だった。相模川のところに出る。遠くには発電所も見え、なかなか展望のいい所だった。加藤さんの話によると、ここは1度きた所だとか、向こうの台地の所にキャンプしたとか、虫にさされて大変だったとか。先輩のこういう話がきけるのも又いいものだなあと思った。ここで及川君、本日3度目のバンク。なにしろ今回はパンクが多かった。これで道路状況の判断はつくでしょう。また、もっと先の場所だが、道路わきから自転車がニューと出てきて、その後、中山君の白い歯。なんのことはない。ジャリでハンドルを切りそこね、道路わきに落っこったのだそうだ。これも道路状況判断の資料に。そこから橋本まで走って解散。時に4時35分。本日正式のクラブ・ランとしては79・3キロ走った。
6月26日 総会観音寺
参加者36名
合宿に関する、きわめて詳細な日程の発表と、各人の参加の意志に者は32名を数えた。
8月5日 – 16日 夏季合宿《北海道》
参加者34名
これについては、星の合宿記録をもって、それとなす。
10月5日 定例コンパ
参加者21名
合宿の記録映画の試写会を行なった。なかなかのできで、今後クラブの貴重なものとなるだろう。また、1年生がコンパにおいてそれぞれの個性を表わしてきたのが目についた。
10月6日 機械分解講習会
参加者12名
昨日のコンパと、今日の保健の試験とで、参加者は少なかった。対象とすべき1年生の参加が少なかったのは、全く残念であった。この講習会をやる意義が、全然認められなかった。
10月10日 オープン下見
参加者7名
一般参加者が多数になる予想なので、その安全性を確保するためにも、是非とも下見の必要があると思い、わざわざこの日を設けたのではあるが、参加者が極めて少なかったのは、まったく遺憾であった。特に1年生には、交通頻繁な場所で、交通整理をやってもらおうと思っていたのであるが、2名ではどうしようもない。交通整理は、仲田と保泉に任せることにした。さて、コースであるが、これは、多数の自転車が置ける場所という点に拘束され、例年通り、三鷹駅集合、行先は狭山湖という、まったく月並みなコースになってしまった。
これは来年への繰り越し事項ではあるが、コースを決定した際、そのコースにあたる管内の警察署に、道路使用許可を取る必要がある。今度の場合、それに気づいたのが遅すぎたため、できなかったが、許可を取れば、交通頻繁な場所では、巡査が交通整理をしてくれるという利点がある。
10月13日 早慶親睦ラン
参加者6名
昨年、品田さんの発案で始まったこの交歓会も、今年は慶応の担当で川越へいも掘りに行く予定であったが、あいにく朝から雨だっこたため、急拠、行先を狭山湖に変更し、決行された。雨が降ったために、極度にクラブ員の参加が少なくなった。それでも慶応は担当校らしく、15名程きていた。雨のため走ることよりも、お互いに話し合うことに力が置かれた。
この点、交歓会の意義は十分あった様に思う。来年度は両校で計画し、実践しようということになった。
10月20日 オープン・サイクリング
参加者29名一般参加者50名
5月の総会でォーブン・サイクリングの人事が決まって以来、目の上のコブの如き存在だったこのオーブン・サイクリングも、ついにその日がやってきた。
去年は新聞で募集できず、参加人数が少なくて興味半減だったので、今年はその点を考慮して、10月に入ってすぐ新聞に投稿した。その結果、1週間前に、朝日、東京新聞にその旨が掲載された。と同時に、小川宅の電話は朝昼晩鳴りっぱなしであったとか!!
新聞と並行して、自転車の方もJCAと連絡を取り、その確保に努めたが、亜細亜大学のそれとかちあい、彼らの方が少し早く申し込んでいたため、先を越され、10台程しか確保できなかった。
これでは足りぬことおびただしく、その不足を補うため、YWCAその他にあたってみることにした。まず、山手YWCAに行ってみたが、ここにはすでに自転車を置いてなくて、目黒YWCAにあるという。早速そちらと連絡をとってみたが、毎日曜日の午前6時から8時までサイクリングをしているとのこと。オープンの集合は9時だから、1時間で目黒から三鷹まで運べば何とかなると思い、借りることにした。それでもまだ30台位しか確保できなかった。参加希望者は70名にも達しているというのに…
そこで、クラブ員1人1人がコネを使い、手当たり次第に集めることにした。それでどうにか50台は確保できた。これが限界なので、申込みの遅かった人には、来年是非とも参加して下さいということで、残念ではあるが断わることにした。オープン当日までは、まったくあわただしかった。
オープン当日の出来は、決して十分だったとはいえない。一般参加者が50名にもなると、それを統率するのがいかにむづかしいものであるかということを、今更のことのように知らされた。
下見をしていなくてコースを間違えたり、班ごとの連絡が不十分であったり、非難すればきりがないが、2年生を中心に、1年生もよくやってくれたと感謝している。不10分な点は、来年やるであろう1年生が、十分に考慮して、もっと完全なものにすべきである。来年のオープンに期待する。
10月31日・11月1日 秋季合宿《戸田橋 – 軽井沢タイムトライアル≫
参加者24名
軽井沢合宿といっても、これは東京 – 軽井沢140キロを何時間で走るかという、まさにタイム・トライアルそのものである。今年初めての試みであり、来年からも毎年行なわれていくと思う。上位3名には金、銀、銅のメダルが贈られ、その他3名にラッキー賞が授与された。中村さんがこの記録をされたので、そのまま載せる。
天気は晴。戸田橋5時集合。まだ夜があけず、真暗である。非常に寒い。早稲田祭を利用しての秋季合宿である。当初、宿舎は清原教授の別荘を予定していたが、ゼミに使うとのことで、軽井沢友愛山荘YHとなった。結果は以下に記すところだが、予想外の好タイ
ムに驚いた。タイムの差は、脚力の差というよりも、休憩時間のとり方の長短の方にあったようだ。この催しが、WCC内で長く続き、タイムが毎年更新されていくことを望む。
11月10日 鎌倉・横浜ラン
参加者9名
雲ひとつない秋晴れではあったが、サイクリングのもうひとつの障害、風が強く吹き荒れ、小石が体にあたって痛かった。この強風のため、最初は鎌倉へ行く予定であったが、横浜・三溪園止まりとなった。
個人的な話ではあるが、小生はこのコースを走るのは、今年になって3回目である。そしてもう1度、早同交歓会で走るのだから、全くうんざりする。もっと新鮮味が欲しいと思うのは、小生だけだろうか?それが、クラブ員の参加の悪さに影響していると、いえないこともないだろう。夏季合宿以後、クラブ員、特に1年生の参加が、目立って悪くなってきた。いわゆる”中だるみ”というやつか。
企画の板橋さんが引越しし、千葉から2時間半もかかって、なおかつランに参加しているのに!残り少ないクラブ行事に、もっと参加することを望む。
11月17日 中津川溪谷クツキング・ラン
参加者11名
今年度最後のクラブ・ランでもあり、またクッキング・ランというユニークな企画なので参加したかったが、倦怠感が先に立ち、結局参加しなかった。板橋さんには非常にすまなく思っている。これでクラブの行事も、早同交歓会を残すのみとなった。
早同交歓会を前にして、クラブ員、特に1年生の多くが不参加の意志を表わしているのは、どういうことか?確かに、この交歓会が同志社大学の都合に合わせたため、平日の授業と重なって行けないということはよくわかる。それは何も1年生だけではない。全てのクラブ員が同じ条件にある。小生は授業を軽視しろというのではない。クラブが授業に優先するというのでもない。しかし、もう少し考えて結論を出すべきではなかろうか?
1年生諸君、この早同交歓会は諸君たち、いや小生もだが、我々がこのクラブに入る前から、例年行なわれてきた。1年に1度、東の早稲田・西の同志社が同じ所に集まり、サイクリングを通じて生活を共にする。毎年人間は変わるが、そこに集う人の志はひとつだと思う。それが、もはや両校の不動のクラブ行事になったと思う。早同交歓会―実にいいクラブの伝統行事だと思う。小生はまだ1度しか参加したことがないが、そのよさは、十分に理解できているつもりである。授業とはまた違った意義があると思うが、どうであろうか?
11月26日 – 29日 第5回早同交歓会
参加者23名
これについては、一編独立したものを書くことにする。
12月12日 総会文学部105教室
参加者34名
トレーニング効果をめぐって議論がたたかわされたが、結論は持ち越された。退部の項の規約改正をする。その後、来年度の役員選出をした。
以上、この1年間のクラブ行事に関して、資料局としての記録を書いてきたわけだが、最後に、総括的な私個人としての意見を述べたいと思う。
まず、何といっても1番気にかかり、また不満に思ったのが、役・員各自にあまりにも負担がかかりすぎるということである。
主将は役目上やむを得ないとしても(そのために副将がいるのではあるが)、企画、編集、トレーニングなどについては、全くその役員の個人負担となっている。企画の板橋さんの場合、企画するのがただ1人のために、クラブ・ランには毎回出なければならず、編集の星君についても、編集局長とはいうものの、ただ1人である。
今年は特に、エスカ夏ラリー、早同交歓会を我がクラブが担当したため、彼の負担も言語を絶する?ものだったろう。トレーニングの小泉君のことは、小生が述べるまでもなく、クラブ員全員が認めるところである。なぜ、こんなにも役員の負担が大きくなるのだろうか?会則第6条4項には、「各局長の下に本会会員より数名の局員をおく」とあるが、これはどうなっているのだろうか。局長を率先して助けようという積極的な者がいないのか、それができない状態にあるのか、この点もっと考えなければならない時局にきている。
我がクラブができた当初は、サイクリングの好きな者が集って、ただひたすらに走っていたそうである。それが山添さんの時代に、クラブとしての組織ができ上り、鈴村さんの時にその充実、発展がなされ、品田さんに至って、学生の会に加盟でき、ようやく学校公認の団体になった。こうして見ると、クラブは発展してきているが、それを構成するクラブ員は果たしてどうだろうか。クラブ全員が、積極的な自主独立の精神を身につけ、クラブに参加しているだろうか。もしそうであるなら、クラブ役員の負担はこんなにも大きくならないだろう。これは来年度の運営委員に課せられた問題である。
新入生歓迎ラン – 商学部1年 高橋
新入生歓迎ラン
商学部1年 高橋
私は原稿などというものに、このところ全く無縁だったので、原稿を頼まれた時の驚きは、異常なものであった。しかし、頼まれたからには書かねばなるまい。これは、私ばかりでなく、クラブ員全員の心構えであると確信する。そんな私の文に、目を通してもらえれば幸いである。
このランは、4月28、29日に行なうはずであったが、不運にも、天候に恵まれず、次の連休、即ち5月4、5日を利用して行なうこととなった。コースは、早稲田大学—奥相模湖(1泊) – 調布である。
最初は3班に別れて行く予定であった(9時、12時、2時にそれぞれ出発)が、1班はともかくとして、残りの班、特に3班になると、目的地に着くのが夜の8、9時頃になるというので、新入生は、なるべく9時に出発するよう勧められた。土曜日なので、中には授業のあるクラブ員もいて、そう希望通りには行かなかった(これからはこういう点が、クラブが計画をつくる場合のウィークポイントではなかろうか)。私も授業があったので、2時出発を希望していた。しかし、3名足らずで、2年生からの勧めもあって、結局2班と一緒に出発することにした。出発は1時。親爺の銅像前から一勢にペタルを踏んだ。
この日も、どちらかと言えば、上々の天気とは言い難い。出発して1時間程たつと、雨がポツポツ降り始めた。しかし、これは通り雨らしく、そんなにひどくはなかった。途中、府中市役所で15分程休憩をとったが、このへんまでは、新入生といえども、まだまだスタミナは充分ありと見えた。
この日の最初の難関は、何と言っても大垂水峠ではなかったかと思う。先輩達に前から聞かされていたので、覚悟はしていたものの、延々と3キロも続く上り坂は、新入生にとって全く死ぬ思いであった。この坂は、幸いにしてすべり止めなどいろいろ細工がしてあり、上りやすかったのだが、それにしても苦しかった。中には完走した1人もいて、今年の新入生の男意気が感じられた。途中、歯を喰いしばりながら、頂上目指している我々を見て、ドライバー達が「ガンバレ!!」とか「あと一息だ、しっかりしろ!!」など、いろいろ励ましの声援を送ってくれるので、非常に勇気づけられた。苦しくも、こういうことがあるから、サイクリングは楽しい。ホント!悪戦苦闘の末、頂上にたどり着いた時の非常な喜び(征服感)と、同時に内心ホッとした気持ちになったのは私だけだったろうか。
峠であるからには、下り坂もあるはずである。上りが苦しかっただけに、この下りは非常に快適で、下に着いたら、なんだかあっけはく終ってしまったように感じた。ここまで来ると、相模湖は真近に迫ったが、少しずつ疲れが出て、その上、時間も遅かったので、「ここに先発隊がいればよいが・・・」と、かすかな望みをもって走った。しかしながらそこにはいなかった。その時のショック、疲労感は何とも言えない悲痛なものであった。
しかし、そんなことを言ってはいられない。先発隊だって、この困難を乗り越えて、目的地に着いているに違いない。まして、先発隊のメンバーは3年生3人、1年生2人である。2年生のぬけた我々の同僚は、我々以上に苦しかったかもしれない。『さあ皆頑張ろう』と、我々新入生は、心に言いきかせ、再びペダルを踏んだのであった。
けれども、これから先がデコボコ道で、しかもほとんどが上り。予想だにしていなかった大垂水以上の試練に耐え、非常な疲労と困惑の色をますます強くせざるを得なかったのである。途中、連絡のまずさで15分程のタイムをロスしてしまった。太陽が沈まぬうちに、なんとか目的地までの距離を縮めておくべきだったのだが、このようなダメイジは真に痛かった。太陽もすでに西の山中にかくれ、だんだん薄暗くなる。「まだか・・・まだか・・・」と、内心あせりを感じながら、マヒ寸前の足に全身の力をふりしぼり、皆頑張りに頑張った。
そんな時、板橋さんが迎えに来られ、目的地までは、そう遠くないと思い、気持をとりなおして、ペースを上げた。しかし、この頃には、もう皆のエネルギーは、消耗しつくしていたのではなかろうか。トンネルを2つぬける所で、それぞれの自転車のライトは、ギラギラと光り輝き、それが、時には左に、あるいは右に揺れ動いていた。そして下方に点々と見えてきたランブらしい灯。着いた!!着いたのだ!!我々を執拗に苦しめたこの奥相模湖に…
先発隊と顔を合わせた瞬間、胸の底からこみ上げてくる喜びは、何とも言えないものだった。皆が次々に到着。一瞬にして、花が咲いたように、あたりには明かるいムードが一杯だった。先発隊は、すでに夕食を用意しており、肉を焼く匂いが、食欲をさそった。我々はすぐにテントを張り、それが終わるなり、谷川で作った料理を口にした。さすがに普段とはちがって、格別の味がした。
食事のあと、今日の行動の反省会を開いたが、意見としては、やはりこのコースが無理なものであったこと、班に分かれず統一してランをするべきだといろいろと出た。これらの意見を来年からの歓迎ランに生かしたいものだ。反省会が終わってから、たき火を囲んで、合唱をして今日の疲れをやわらげた。
大学へ入って初めての、サイクリングクラブへ入って初めてのこのランが、非常に有意義であり、また楽しいものであったことは言うまでもない。これは皆の顔を見れば、すぐに察知出来た。夜空には、ダイヤモンドのような星が散らばり、それらのひとつひとつが、我々を祝福しているかのように、美しく輝いて見えた。
南多摩丘陵ラン – 商学部1年 中山
南多摩丘陵ラン
商学部1年 中山
僕にとっては、最初のクラブ・ランだった。つまり、サイクリングクラブに入って、初めてクラブの人たちと走ったということである。その日は、朝からすっきりしない空模様で、雨を気づかいながら、集合場所である大学へと走った。全員が揃い、出発したのは定刻を20分位過ぎていた。もうひとつの集合場所である、和泉多摩川駅に向かって走る。途中、小雨がぱらついた。和泉多摩川駅に参加者全員が集まったのは、9時半頃だった。ここで、板橋さんの指示で1年生を2つに分け、1班はここから王禅寺まで、2班は王禅寺から玉川学園までを先行することになった。僕は1班に入れられた。出発は10時を回っていた。
ちょうど多摩川水道橋をわたっている時、またもや雨に降られ、ランは中止になるとさえ思われた。しかし、この雨も局地的なものだったらしく、しばらく走ると、道路も濡れていないほどだった。それからは、雨も降らず、太陽さえ顔をのぞかせた。明治大学・生田校舎の附近の坂道では、かなり疲れた。
この時点では、僕が先行の1班に入っているということは、きれいに忘れていた。というのは、ペダルをこぐだけで精一杯だったから。下り坂では余裕もでき、地図を広げてコースを追って走った。途中、1度コースを間違えたけれど、難なく本コースにもどり、担当終了地点の王禅寺に無事ついた。しかし、王禅寺への道は、かなり細く、また所々ぬかるんでいて、「マムシが出るぞ!」とおどかされるほど、草の生い茂った道だった。自転車をかついで、石段を上る。あちらこちらで「重てぇなあ」という声がした。ここで、水の補給や写真を撮ったりして休んだ後、2班を先に出発となった。
ここから玉川学園までは、時々コースを検討しながら、自転車を押し上げながら、また、イチゴの盗み食いをしながら走った。坂の上で女の子がこっちを見ていたのを、全員が意識していたようだったが、特に小川さんはそれが強かったようだ。そこをいやいや出発し、どんどん走る。僕はここでも相当に疲れた。特に、急な坂を自転車を押しながら上る時は、足が重く、自転車を放り出して、大の字になってその場に倒れたいくらいだった。やっと昼食になる。腹はペコペコ、足はフラフラ。むすび6個にパン2個、それにカステラまで食べたのに、それでも足らなかった。ものすごく、腹が減っていた。
僕としては、もう少し休みたかったけれど、出発の時間だという。走りながら感じたことは、疲れは出てきても、スピードは全然出てこないということである。またしても、上り坂が見えた時には、ゾッとした。しかし、休んでいる時、僕は大発見をした。天の助けか、神の助けか、ギヤーがもうひとつ残っていた!ああ、よかった。それからは、ペダルが嘘のように軽くなった。その坂を上りきった所で、再び休んだ。あとは全て下り坂と思い、快適な気分で走ったが、長くは続かず、途中までだった。
この砂利の坂道は、自転車にまだよく慣れていない僕にとって、大きな落とし穴だった。あれよあれよという間に、砂利にハンドルをとられ、横転してしまった。これだけならまだよかったが、悪いことには、クランクが折れてしまった。「どうしよう」これがその時の心境だった。こんなことは、もちろん初めてで、かなりとまどった。しかし、先輩たちの落ち着いた様子を見て、何となく心が安らいだ。クランクが折れては、自転車はこげない。しかし、幸いなことに、すぐ舗装の道路に出た。加藤キャプテンに押してもらったり、鈴木さんのトゥクリップをつけてもらい、片足でこいだ。どうにか、関戸大橋まで走った。ここで解散。片足でこいだわりには、あまり疲れなかった。吉祥寺まで鈴木さん、及川君と一緒に走る。クランクを直して、2つのペタルで走り出した時は、快適だった。このランは、僕にとってよい経験となった。家に着いたのが7時半、ビールがとてもうまく、次のランが楽しみになった。
宮沢湖ラン – 政治経済学部1年 仲田
宮沢湖ラン
政治経済学部1年 仲田
5月26日、日本女子大との合サイのはずが、どういうわけか鎌北湖・宮沢湖ランということになった。えらい違いだが、しょうがない。ぶつぶつ言いながら8時に大学に集合。家から早稲田までぶっ飛ばしたせいか、あるいは、前日、腹の調子が悪かったせいか、かなりバテ気味 – つまり、全くやる気をなくしていた。
下痢気味の腹をかかえて、8時半過ぎ、早稲田を出発、川越街道へ向かう。ところが、池袋駅から街道へ入る時、ゴチャゴチャした道を通ったため、1年生1名が迷い子になってしまった。止むを得ず、米空軍キャンプ前でしばらく待つことになった。あきらめて出発しようとした寸前、やっと追いついてきて、まず一安心。
キャンプからしばらく走り、予定通り(時間はかなり遅れたが)平林寺で休息。到着が9時45分だから、走り出して1時間と15分。最初の話だとスピードランということだったが、この位のべースだと非常に楽だ。平林寺を見学しようかと思ったが、金をとるというのでやめた。
平林寺を出発してすぐ接触事故があったが大したことなく、快適なバイパスを走る。バイパスの終点で、4年生として今期初めて守谷さんが特別参加。拍手で迎えて、そのまま川越市に入る。途中、今度は板橋さんがパンク。今日は全く事故の多い日だなどと言いながら、喜多院、川越大師に10時58分着。後を走っていた者がかなり遅れたが、それでも全員無事に到着し、そこで昼食となった。
12時18分、川越大師を出発。1時に日高町役場に着く。冷でかなりバテてしまって、役場があと1キロも遠くにあったら、動けなくなったかもしれない – ちょっとオーバーな表現である。
結局、元気な者は鎌北湖へ、そうでない者は宮沢湖へ行くということになる。小生は無論、宮沢湖。リーダーは2年の篠原さんがあたり、町役場を出て、ジャリ道をチンタラと宮沢湖へ向かった。
宮沢湖では2時まで休息のはずが、どこでどうなったのか、2年生3名と1年生1名が女の子4人をひっかけ、いや、女の子とお知り合いになられてポートに乗ったため、3時まで延長。守谷さんと1年の松本君は、アベックならぬオベック(注・オスのアベック)でフンダラモーター(注・踏むと回る)付ボートに乗り、ハントに失敗した残りの者は、指をくわえて見物する。いじけた1年のうち3名ばかりが、守谷さんを誘って宮沢湖1周としゃれた。
というわけで、宮沢湖でかなり時間を食ってしまったが、飯能市から入間市あたりまで快調にぶっ飛ばす。ところが、所沢で雨が降り出し、飯を食う間も止まず、全く元気がなくなってしまった。
上石神井で解散してから、青梅街道を通って一路新宿へと走る。あまりにチンタラと走ったためか、途中で、鎌北湖へ行ったはずの3年生の伊藤さんに追いつかれたのには、マイッタ、マイッタ。
合同サイクリングに参加して – 日本女子大学 戸部さん
合同サイクリングに参加して
日本女子大学 戸部さん
今日は13日木曜日である。早稲田と合同サイクリングに行ってから、もう4日経った今10時、ラジオを聞きながら、これを書いている。頼まれたものの、何を書いていいのかはなはだ困惑している。サイクリングには、前々から1度行ってみたいと思っていた。受験勉強やら何やらで行くチャンスがなかったのだが、長年の望みをおかげでかなえさせてもらった。何しろ初めての経験だった。普通車と違って、たとえフラットといってもハンドルが少しカーブしている自転車。そのサイクリング車をこぐだけで、前かがみになっているだけで、1人「カッコイイなあ」と悦に入っていたのだから、我ながら単細胞だと思う。
私の車との付き合いは、そもそもは乳母車で、もの心つくようになってからも、よくおばあちゃんに乗せてもらって、近所を漫遊して喜んだものである。その次は3輪車で、ある日、前の家の子(この子が私より2つ上で、今流行の肥満児だった)に義理で(私は昔から義理堅かったんだなあ)貸したら、その子が乗った途端、ペシャンコになってしまった。今だに忘れられないところをみると、よっぽど口惜しかったに違いない。
次はいよいよ自転車。小学校の3年ぐらいの時に、子供用の自転車に乗れるようになった。近くの原っぱで、父に後の荷台をおさえてもらい、何とか走れたようだ。走っているうちに手を放されたのも知らず、「うわあ、走れた」と得意の絶頂で後をふり返り、おさえる人が誰もいないとわかった途端、横にバッタリ。そんな苦労を重ねてやっと乗れるようになったが、ある時、近所を乗り回していると、悪童たちに「カッコイイ」などとおだてられ、あせって角を曲ったら、電柱に激突してしまった。人が大勢集まってきた。穴があったら入りたいとは、あの時の私の心境だっただろう。それで半年ぐらい乗らなかったこともある。その頃、小坂一也のサイクリングの歌がはやっていたが、それもサイクリングに憧れる一因だったかも知れない。
ところで最近はマイカー族も増え、また諸々の交通機関が細部にわたって発達して、汗して目的地に達するということが、あまりに少ないのではないか。あの日、ダンプのお兄さんに怒鳴られたり、信号無視をしたりしながらも、懸命に坂をのぼって、狭山湖が見え出した時には、こんな所にこんなきれいな湖があったのかと驚かされた。でも、もしこれが車できたのだったら、きっとそれほど感激しなかったろう。ある目的のものを手に入れるのに、あまり苦労しないと喜びも薄らぐということだろう。交通が発達しすぎるということは、ちっとも人間の為ではなく、全く無意味とさえ思われる。
早稲田の方々はサイクリング普及に務めておられるそうですが、これからも私達のような者のために、いろいろ計画して下さるようお願いいたします。
北海道のムシ – 法学部2年 小泉
北海道のムシ
法学部2年 小泉
私がこれを書いたのは、記録のためではない。恐れながら、あの映画「東京オリンピック」における、市川崑監督の心境で文字を埋めたつもりである。また、この「北海道のムシ」の主人公は、あくまでも、この私であり、あくまでも、この私を中心に、ことは進行しているので、その点を宜しく御了承願いたい。
まず「北海道のムシ」という題について、解説せねばなるまい。たぶん、君にはこの意味が解らないと思うからである。実は、それが私にとっても狙いであり、こういう題なら、さてさて、小泉はどんな作文をしたのだろうと、この文を読み始めてくれるだろうと思ったからである。
この「ムシ」というのは、君をはじめ、誰もが迷わずに想像するような「変なムシ」でも何でもなく、「64」即ち64という数である。つまり車輪の数であり、32台の自転車の意味である。そして、「北海道のムシ」とは、何のことはない、我々WCCの1968年度夏季合宿のことなのである。あの32名の走る有様は、ちょうど、小さい虫のようでもあったから、それをもかけての言葉であるが、我ながら、この題に非常に満足している。
ところで、ここで、君は私にこう反論するであろう。「合宿参加者は33名であった。だから、自転車は33台であり、車の数は66であった」と。それは、私もよく承知している。確かに参加者は33名であり、車輪の数は66であった。しかし、ここでよくお考え願いたい。果たして「66」からよい題名が出てくるであろうか。私が終夜、考えても浮かばないのに、いわんや君をや、ロクなものは出てこまい。そうだろう?それよりも「64」で、「ムシ」のがずっといいではないか。1人ぐらい、まけとけよ。そう堅いことを言わんと!ねっ?
何、我慢できない?そうか。それでは・・・。うん、こういうことにしよう。私をその数から除いてもらうのだ。それならば、33-1=32であり、車輪は32×2=64でよいであろう。実は、私もその方がよいのだ。私が君やその他の者と同じ「ムシ」であってはならないからだ。合宿において、私だけは、あくまでも、1個の人間であったからして、君やその他の者とは別個の存在であったのだ。だから、32名のムシと1名の人間、小泉君から見た32名のムシの行動、「北海道のムシ」こういうことにしよう。これでいい。
8月5日霧のち晴れ
ポキーン!!!
私と滝野と星は、襟裳岬や納沙布岬を汽車やバスで旅行し、午後2時、集合地の釧路に到着した。さあ、合宿だ!
木村が鎖骨骨折で帰京を余儀なくされた。これで私は助かった。なぜなら、もし、木村がカッコよく参加していたなら、実際の参者34名で、私の作文の題名も、そこで、ますます理由付けに苦しくなったであろうからである。
私が釧路駅に着いた時、木村は既に病院へ運ばれていたので、詳細はよくわからない。しかし、集合予定時刻は既に2、3時間を過ぎようとしていたので、寝場所作りにとりかかった。私だけならともかく、クラブ全員でホテルに泊まることはできないので、釧路市の川辺にテントを張った。
そこに、肩から胸、腕を包帯でおおった木村が、さえない顔色で姿を現わした。WCC紳士ゆえであろうか、その包帯姿にもどこか気品があった。なんてことは全然感じられず、遠地での怪我に、やはり、心細そうな様子であった。今晩は旅館に泊まり、明朝、飛行機で帰るそうで、斉藤が空港まで付き添うことになった。
我がクラブは団結力が強く、互助精神に富んでいる。それは、この木村の時にもよく表われていた。特に、斉藤は、こういう時には最適の世話人である。クラブ員の良き女房とでも言えよう。もっとも、斉藤が女になって、実際に妻となったならば、肌白き木村紳士の顔色などは、連日連夜の激戦で蒼白になることは誰も疑うまい。
初日というのは、いろいろとガタつくものである。中山と仲田が、乗るべき連れをあとにおいて、自分ら男2人だけで釧路に来るという、連れには残酷なことをしでかした。つまり、送っておいた自転車が釧路駅に届いていないのである。2人に聞くと、都内のある私鉄駅から送ったそうな。これでは、荷物のリレーに余計の日数と手数がかかることは当然である。日時に制約がある場合などは、なるべく、国鉄の大きい駅、例えば新宿とか汐留とか秋葉原とか小田原などから送るべきである。
結局、2人は今までの伴侶をそっちのけにし、中山は木村のそれにチョッカイを出し、仲田は大胆にも、新しいのに乗り換えた。
古いのは弟にくれてやるそうで、自分でさんざん楽しみながら、古くなったら弟にやるなんて、果たして、弟はそれで満足するであろうか。中山はもっと「立ち」いや「質」が悪い。合宿の間だけ、木村のもので思う存分楽しむのだそうだ。「木村さんは骨折して不具者同然だから、代わりに僕が可愛がってやるんだ」などと、とぼけた口調で話していた。これは後のことであるが、未舗装道路で木村の自転車はよくパンクしていた。きっと中山が可愛がり過ぎたに違いない。しかし、感心したことには、パンクをなおして、また中山を乗せていた木村の自転車のいじらしさであった。
空に星が1つ光った。夏の長い一日ではあるが、それもようやく暮れかけた、川の流れは静かである。1段落ついてから、加藤主将からの諸注意があった。「事故のないように」これが骨子だった。今回は、辻山という、WCCと共にシナリオ研究会にも属している輩が、撮影班として坂本を助手に、8ミリでカラー映画を撮ることになっていたのであるが、主将もそれを意識してか、サングラスと無精ヒゲに、手振り、足振り、体振りで、話をながぁく、ナガァクしていた。釧路の夜は外食であった。
8月6日晴れ
釧路から阿寒湖畔へ向かった。道は果てる所なく直線をなす。両側は背丈50cm位の緑の草が一面に広がる。空は薄い青空。その中を、小川をリーダーに総勢33名がすうっと帯をなして流れていく。後からみていて壮観だった。
33名と述べたが、実は、木村を空港へ送った斉藤、新しい自転車を買う仲田、その世話の中村さんは、2時間ほど阿寒湖畔に遅れて着いた。
8月7日晴れ
阿寒湖畔より弟子屈町へ向かった。予定は摩周湖であったが、予想外のひどいジャリ道と坂道、それにアブに悩まされて、星リーダーの苦心むなしく、弟子屈どまりとあいなった。途中、転倒者が続出し、パンクも中山の他に2、3人を数え、相当好きな奴が多いことがわかり安心した。主将の加藤さんは、やはり他の者と違って男らしい。いや、荒っぽいと言った方がよいかも知れぬ。すごく大事なモノを折ってしまった。ディレーラを折ってしまった。結局、主将はトラックで弟子屈へ行った。
途中に町がなく、10キロ位毎に時々農家が1つ2つ見えるだけ。水もなし、昼食もできず、「これぞ北海道!!!」と少々満足したが、悲しくもあった。
8月8日晴れ
霧の摩周湖も、くっきりとその水面を見ることができた。それまでの上りはかなりきついものであったが、舗装道路と少々の追い風にスイコラ、スイコラ上り切った。
川湯で昼飯を食った。わざわざパチンコをやりに行く奴もいた。伊藤さんのフリーが油ぎれで空回りしなかったり、辻山が前の自転車に追突してハンドルの具合を悪くしたりしたが、ともかく屈斜路湖に到着した。
泳いでいる人もいた。我々は、小波(さざなみ)に運ばれる湖水が音もなく砂の奥底に吸い込まれる、その辺に群がって遊んだ。その水を包んだ砂に、そっと手のひらをあてると、それは温かった。温泉であった。
そこで、我々は、なおも純真な性格をあらわにしてはしゃいだ。
「この水、あたたかいよ」
「そうかい。じゃ、ボクもさわってみよう」ピチャ、ピチャン
「わぁ、あったかい、あったかい」
「本当にあったかいね」
「うん」ピョンピョンピョンピョン
てな調子であった。
砂浜には、縦2m、横1mぐらいの板枠に、温水が湧き留められていた。自然と、我々良い子達は、その回りに集まった。そして、ワイワイ、ガヤガヤと騒いだ。
と、10m位向こうにある土産物店のアンチャンが、ニコニコしながらこちらにやって来た。そして、親切にこう説明してくれた。「この砂浜の温泉は、40・度です。先月、女の人で、この湯の中に、1分手をつけていることができました。それが最高ですよ。皆さんもやってごらんなさい」良い子達は張り切って、湯の中に手をつけた。2分少々つけていた。記録は大幅に更新された。
アンチャンが言った。「ところで、記念写真を撮ってあげましょうか。そこがいいでしょう」店のちょっと手前にある、その店のものであろう、大きな熊の剥製のある所を指さした。良い子達はその熊をとりまき「チーズ」と言って、写真を撮ってもらった。
「サイクリングで、のどがかわいたでしょう。こっちにいらっしゃい。牛乳やコーラがありますよ」アンチャンが言った。良い子達はついていった。アンチャンが続けた。「北海道名物と言ったら何だと思いますか?」良い子達は真剣に答えた。「ハイッ、それはラーメンです」「ビール」「とうもろこし」「チーズ」「オンナ」
アンチャンが言った。
「そういうものもそうですが、マリモがありますね。皆さん、このマリモは、ここにだけしかないものです。どうです、おみやげに?」
良い子達はピーンと感じた。このまま、この店から離れてしまっては、せっかくのアンチャン商法に、傷をつけてしまうのではないかと気づかった。そこで、「牛乳いくら?このマリモ、本物?」と熱心な質問を親切なアンチャンに浴びせた。アンチャンは『うまくひっかけた』と思ったのか、愛想よくそれに答えていた。しかし、それだけであった。誰も何も買わなかった。加藤ガキ大将は良い子達に出発命令を下し、良い子達はそれを理由に、喜んでそこから離れてしまったのであった。かくして、アンチャンの商法は屈斜路湖の彼方へ、くっちゃくっちゃに飛んでいってしまったのであった。
とめてくれるな、アンチャンよ。長い旅路が待ってんだ。俺たちゃ、しがねえ自転車乗りよ。アンチャン、ごめんよ、勘弁な。
キャンプ地、屈斜路湖畔の和琴温泉に到着した。この和琴半島がミンミンゼミの北限地だそうな。
我がD班こと篠原班は買い出しであったため、それが終わると夕飯まで自由時間となった。ボートに乗った。女性が3人で、ボートに乗っている。追いかける。逃げる。追いかける。逃げる。もう1そうボートが来る。これも、我がクラブ員のもの。2そうで追いかける。うまく逃げられる。もう1そう来る。ユニホーム姿の板橋さんを船長とするものだ。3そうで追いかける。はさみ打ちにしようとする。3そうで追いかける。女を乗せたボートは逃げる。接近した時、俺は湖に飛び込む。坂本が飛び込む。篠原が飛び込む。女のボートに乗り込もうとする。しかし、逃げられる。30分位の女狩りは、かくして失敗に終わる。
砂浜の終わるところに天然の浴槽がある。見た目にはどぶのようだが、硫黄のにおいのする露天風呂だ。気持がいい。篠原は、海水パンツ併用の短パンも脱いで、アカを落としていた。向こうから、2、3人の女の子が来てあわててバチャバチャやっていた。
ミーティングでは、フリー・ランの是非が討論された。脚力のある松本から、毎夕、提案されていた上り坂での走行法だ。「自分のペースでどんどん走りたい。前を走る班の遅い人について走らねばならないのは自分も疲れる」彼の主張するところだ。主将が答える。「絶対に坂道でもフリー・ランはしない。団体の中で走ることも大切だ。ただし、最初から峠とわかっているところでは、1度くらいやらせてやる。他ではやってはいかん。明日はちょうど美幌峠がある。明日、実験的にやってみよう。ただし、つまらぬ競争心が湧かぬよう、班毎に時間をおいて出発させる」最良の方法と考える。
8月9日降ったり止んだり
時折、大きな雨粒が落ちる。出発するかどうか、朝食は自炊か外食か、主将の勇断を必要とする。成功すれば当り前、失敗をすれば信頼を失う。不平が出る。この時の主将は孤独であったに違いない。その点、我々は気楽だ。彼の後についていって、いろいろ無責任な言葉を吐いていればよいのだから・・・
自炊決定!出発決定!トレーニングもいつものとおり!!!
国道243号線黒百合国道を少しいったところから、フリーランにする。私は三輪と中山と3人でリーダーなので、1番目に出発の落海班と走る。落海さんが飛ばす。道は今のところ上り、下りがあり、平たい所もある。小さい石がタイヤからブツンとはじける。ジャリ道だ。雨が降る。強く降る。私は落海さんのすぐ後につく。つまらぬことかも知れないが、私は落海さんと競争するつもりである。昨日の加藤主将のことば「つまらぬ競争心」、それを今、私は抱いている。人間本来の心に秘められているもの、私は、今、それを外に表わしている。
私は落海さんの後について走る。時々並行して走る。相当疲れてきたらしい。フロントギアを落としている。私は、あくまでも後についた。カーブがある。私はスッとインコーナーにはいり、そのままとばした。フロントギアを落として、後のギアをローから2つあげた。そのままリズムに乗って走った。30分、後を振り返る。見えない。安心して自分のリズムに乗る。霧が濃い。雨が降る。
10時、頂上に着く。先に出発していた映画班の辻山と坂本が、1人1人を撮る。この美幌峠の展望はすばらしいのだそうだが、残念ながら霧で何も見えない。食堂に入って、皆休んだ。星は、ボトム・ブラケットを割ったため、トラックで先に美幌へ行くそうだ。
美幌で昼食をし、女満別町、網走湖畔の呼人へ向かった。ここでテントを張る予定であったのだが、雨のため、網走へ直行した。前にも言ったが、私だけならともかく、クラブ全員がホテルに泊まることはできないので、学校にお願いしたのであるが断わられ、公民館も悪い返答であった。皆で婦女暴行をして、網走刑務所に泊めてもらおうかと話し合ったが、その真剣な討議中、雨もあがったので砂浜でキャンプをした。大いに砂が入りました。明日は休養日のため、気がゆるんだのか、藤井が、夜遊びの帰り、停まっていた車の後に追突。弁償させられるのだそうな。
8月10日曇りときどき小雨
知床探訪組と居残り組に分かれる。居残り組は強制ポタリングだそうだ。休養日というこ休養日ということになっていたので不満の声がチラホラ。私も少しこの処置には不満があった。
私は知床探訪組で、斜里まで列車で行き、そこから宇登呂までバス、それから岩尾別、硫黄山までを折り返す船に乗った。知床とはアイヌ語で「地の果て」の意だそうで、日本で最も未開発で、最も北海道らしい所だそうだが、小さな船に荒波で、気分が悪くて悪くて、鳥の糞が岩についてまばらになっている光景と、象の形をした大きな岩しか頭に残っていない。私は船内の1番前の席に座った。
それは船の進行方向と逆の向きにすわるようになっており、2番目の席からは、船の進む方向に座席があったので、ちょうど、教室の教壇にいるようなものであった。どうしてそんな所にすわったのかといえば、それは知れたこと。2番目の席に、若い女性がいたからである。と言いたいのだが、実は若い女性と思ったら、中年の古い娘さん達であった。身なりは、高校生や大学生のようなので、後から見た時はわからなかったのである。いざ、1番前の席に座って顔を見たら、気分が悪くなった。船が動く前からこうだったから、荒海での気分は想像を絶するものであったことが想像できよう。とにかく、船中の半数以上が吐いたのだから、ひどい話である。とんだ休養日でした。
テントは居残り組が呼人に設営していた。
8月11日曇り
呼人から美幌町、そして北見市へ向かった。大きな町だった。ここで昼食をする。
私の自転車のクランクピンがゆるんで、ネジ山が馬鹿になっていたので、自転車店へ行った。滝野が一緒に、自転車店を捜してくれた。彼はよく、こういう時、私の面倒をみてくれる。彼とツーリングをした時、何度も、こういうことがあった。ありがたい。
クランクピンは100円だと言う。「へえ、関東では50円だけどなあ」と言うと、「パンク修理代は、こっちの方が安い」と言う。「いくらだ」と聞くと、ちょっと考えて、不安気に「120円だ」と言う。からかって、「へえ、関東は100円だ」と言おうと思ったが、関東では、実際200円だから80円安いことになる。しかし、あいにくパンクは自分で直せるし、それに私にとって必要なのはパンク修理ではなくて、クランクピンであるから、パンク修理代がいくら安かろうと関係ない。だのに文句の1つも出さないで、おまけに自転車油を買ってやったのは、自転車店の大将の気持の良さからか。
2時頃、留辺蕊町温根湯温泉に到着し、公園にキャンプした。銭湯は温泉である。髪をとかすブラシを網走でなくしたので、番台のおばさんに「ブラシを売ってくれ」と言うと、すました顔で「風呂場に持って行くのか」という。はてさて、ここでは、ブラシを風呂場に持っていってはいけないのだろうかと奇妙に思いながらも「いや、持っていかない」と言うと「それじゃ、あとであげる」と言って、週刊誌かなんかの続きを読み始める。買いたいのを買うのだから、今売ってくれたらよいものを、この中年婆ァ、何をへそを曲げているのか!と少し腹が立つ。「とにかく、今下さいよ」と言っても、すました顔で週刊誌を読み続けている。「よそ者には、売れないと言うのか!」と怒鳴ろうかと思っていると「仕方がない美青年だねぇ」というような様子で、3・4個番台のふところから取り出して「これ、忘れ物なんだけど、どれでも1つ取りなさい」値段を聞くと「ここではブラシは売ってないのよ。だからお金はいらないの。あなたにあげるわ。1つとりなさい」
ああ!!!!温根湯の人って親切だなあ。特に、この中年の魅力をいっばいに秘めたおばさんはいい人だなあ。私はつくづくと感じた。
夜の自由時間は、堀のひっかけた女の子、いや、女の人に会いに喫茶店へ入った。当然私は堀のダシだから、コーヒー代は彼が払う。F医大の5年生で、あまりにお姉様だから、あとからノコノコ来た三輪と篠原にバトンタッチして、私は学校時代の恩師と家とある人に絵葉書を書いて、時間を過ごした。
北海道の夜は秋だった。いや、涼しさを通り越して寒い感じがした。焚火をした。落海さんと、及川とテントを同じくしたのであるが、彼らが、私のために、枕もとで面白い童話をしてくれたので、気持よく眠りにはいれた。
そうそう、あまり冷えるので、夜中にテントを出て、星明りの下で、すぐそばの大木に小便をひっかけたっけ。あの木、成長したろうなあ。
8月12日晴れときどき曇り
温根湯から石北峠へ向かった。途中から峠まではフリーランであった。私の脚力は快調そのものであった。
峠で休憩をした。この峠から展望台への半ラセン状の道が、200m位、上っていた。井上さんが皆に向かって言った。「あの展望台まで1分以内で駆け上がった者にコーラを1本やるぞぉ」
1分以内は無理であろうという標準を、どこから割出したのか知らない。しかし、せっかくスポンサーがついたのだから私が走った。
59秒で、辛くもコーラを手にすることができた。皆がやんやの喝采をしたので、観光客の人達が、まるで猿の檻を覗くような目つきで、我々に顔を向けていた。「小泉に走れる位なら俺にもできる」と思ったのであろう。加藤主将も挑戦した。55、6秒であったと思う。得意満面に悠々と、展望台から下りてきた主将ではあるが、井上スポンサーは、彼には何もさし出さなかった。主将はションボリ自前で飲んでいた。
層雲峡へ下る。峡谷美は最高であった。完全舗装道路を、のこぎりで切ったような岩が両側からおおいかぶさっている。青空はその岩の頂から、申しわけ程度に顔を出している。その黄土色の岩肌には、所々にあざやかな緑の小松が生えて、つめたい岩も生きていた。ここで、リーダーの斉藤から、班ごとのフリーランが許可され、思い思いの場所で、汚い顔を並べて写真を撮っていた。
この夜、層雲峡温泉街へ9時までの自由時間があった。街は異様な雰囲気があり、短かい季節的観光に、そのムードをいやが上に盛り上げていた。私はタイツ、三輪は短パンという、考えられない格好の良さで、生バンドのある喫茶店へ入った。その店のサクラらしい女の子達が、最前列の席を占めていた。金を心配しながらコーラを注文して、そこで先輩へ出す絵葉書を書いた。
9時の集合と共に、全員が街の雰囲気そのままにテントに集まった。「全員ここに集まれ!!」いつもと違った調子で、主将が大声をあげた。その声は震えているようでもあった。我々はまだ、ワイワイガヤガヤしていた。
「禁酒を破った者がいる。前へ出ろ!!」
シーンとなった。他のキャンバー達の声がよく聞こえた。
「前へ出ろ!!」5人が頭を垂れて出た。
「合宿の最初の日に酒を禁ずると言っておいたはずだ。それを、お前らは破った!!!」彼は5人を責め戒めた。これも主将としての立場から苦しいところであろう。そのまま笑ってすませばすませたであろう。しかし、彼は怒った。これぞ主将!!何よりも主将らしく感じたのは、私にとってこの時だった。私の今日までの浮わついた気持が吹き飛んだ。皆も引締まったようだった。5人もよく、それに耐えていた。主将の立場をよく解っていた。よく反省していた。彼らは主将にあやまった。これでこそ、大学生のクラブだ。
8月13日晴れ
現在、午前1時である。変な時刻から、この日は書き始めなければならない。ここは層雲峡野営場という、れっきとしたキャンプ場である。我々の他にもテントを張る奴がいる。私の寝ている隣のテントと思う。「ウーン、あついわぁ」「ウフン」「フゥン」何とも表現できない、なまめかしい女の低く柔らかい、かすれた吐息が聞こえる。寝袋のすれる音らしい、ガサガサというのが聞こえる。
「やってるな」そう思うと眠気が覚めて、耳のところでドッキン、ドッキンとしている。私の横には保泉がズデーンと横たわり、その横には板橋さんがチョコンと眠りこけている。隣のテントでは、男と女が仲よく寝ている。いや、重なり合っているかも知れない。偉い違いだ!何かの拍子に、私はこんな時刻に目が覚めたのだった。その原因は当然わからない。私は朝まで、目だけが眠って、頭は半分活動したままであった。
朝、他のキャンパーも、ほとんどテントから出ているのに、例の奴らは出てくる気配がない。『それは疲れていることだろう』と1人で気を回していると、女2人が出てきた。トレーニングに国道を走っている時、その2人と行き違った。我々を1寸見やって下を向いた。キャンプ場に戻ると、男3人がそのテントをたたんで火を燃やしていた。奴らには、その時、確かに晴れ晴れしさがなかった。純真な若々しさというものに欠けていた。少なくも我々合宿をしている者に比べて、そういうものに欠けていた。その奴らの気持は、私にはよく理解できた。そしてその時、私は、その時の自分をうれしく思った。
途中の国道は、例によって直線の舗装道路である。あまりにも単純なコースだからなのであろうか、リーダーの篠原から団体追抜きをしながら進むと指示があった。ABCDEと並んで走り、最後列のE班が及川と松本のサブリーダーに率いられて1番先頭に行く。それを繰り返すというものだ。ひとりがこの走法中転倒し、クランクを折った。即時中止となった。
旭川の郊外、たぶん嵐山公園と思う。だいぶあがった丘がある。上りつめた林の中に、平らな地道がある。サイクリングに、アベックの散歩に最適だ。その1角にキャンプ場があった。そこにテントを設営した。4時頃であった。買い出しの我々篠原班と、炊事の落海班は残って、あとは近文アイヌ部落へ、ポタリングに出かけた。
デンギス汗料理が今晩の食事だ。真中の盛りあがった鍋に、羊肉やピーマンやねぎなどを少しずつ入れて、たれにつけて食う。すき焼きに食べ方は似ている。しかし、味は全然違う。暗闇であったこと、火力が弱かったことなどから、味わいはどんなものか想像できよう。小島などは腹がすいて待ち切れず、半分生の肉を食ったそうな。私も飯ばかり食い過ぎて、料理が食べられる頃には、ほとんど食う気がしなくなっていた。
市内の子供会と思う。明星子供会という団体が一緒にキャンプをしていて、ファイアーを囲んでいたので、途中から仲間に入れてもらった。女性にかけてはたけている小川も、女子中学生には圧倒されていた。「校歌」と「紺碧の空」を歌った。
ミーティングはその後、9時30分より行なわれた。最初のうちは、先のファイアーのなごやかさが混じっていた。しかし、次第にそれは尖鋭なものとなっていった。問題は団体追抜きと、ひとりのクラブ員の事故、それから発する主将の責任、ひいては幹部のあり方であった。
団体追抜きに対しては賛否両論があった。賛成側は、道路が単調で走法を少し変えた方が面白い。うまくいかなかったのは、まだ皆の技術が低いからだ。技術があれば、平均速度も上がってくる。以上が大体の理由である。反対側は、ただ危いという理由からである。この反対意見において、落海さんから加藤主将への責任追求、並びに「餘部は、我々クラブ員の意見も聞かず、独断的に合宿を進めている。明日の大雪山国立公園探訪も、一方的に取り止めてしまっている」と攻撃。
主将から
「今更、団体追抜きが悪かったから、事故が起こった。だから、どうのこうのと言うな!!そんなのは結果論ではないか。男らしくない。確かに俺は篠原に、この走法実施を許可した。それは昨晩のミーティングで、何の反対意見もなかったし、今日の道路の状況からも、良しと判断したからだ。それから、これは主将就任の時、言っておいたはずだ。俺は上からどんどんおさえつけていく。この33名もの意見を、その場その場でいちいち取り上げて、多数決で17対16だから、こうしよう、ああしようなどとしたくない。勿論、1人1人大事な個性を持っている。それまでも、踏みにじる気持は全然ない」
「それは誤っていると思うな。だって…」
主将と落海さんのことばの対決は続く。31名は黙している。ことばが止んだ。子供達の笑い声が、向こうの、暗闇のテントから聞こえた。
板橋さんが、静かに、幹部の考え方を説明する。篠原と私が主将支持の意見を出す。主将が言う。
「俺の1番嫌いなことばがある。『不言実行』だ。何も言わないであることをする。失敗すればそのまま、成功すれば自慢する。そんなのはだらしがない。卑怯だ。それよりも『有言実行」この方がよい。成功するか失敗するか、わからない。しかし、俺はこうしてやるぞ!!と公言し、そして実行する。責任ある態度だ。俺の1番好きなことばだ」
このことが団体追抜き走法における反対者に対して、どうつながるかは、よくわかる。また私も「有言実行」という言葉の方が『不言実行』よりもよいように思う。それは、気の弱い私にはできぬことではあるが・・・また、主将がほぼ独断的に皆をひっぱっていくのにも賛成だ。32名を率いるのに、それより他あるまい。それだけに主将の責任も重いし、勇断を必要とするであろうし、その決断を下す時ほど、孤独なものはなかろう。その主将の気持はよくわかる。それで、私は落海さんの主将攻撃に対して、主将側に変わった。
しかし、「結果論をぶつぶつ言うな!!」という主将の言葉には、団体追抜き走法反対の意見を述べた私は抵抗を感じたし、その時も少しだが反論した。この点においては落海さんに賛成する。同じく、中村さんも星も賛成していたように思われる。4人は各々、ハンドルを握ることを許されている者である。このミーティングにおいて、団体追抜きに反対したのは、結果論をとやかく言ったのではなく、これから先の判断の対象となるべく反省事項として言ったのである。実際、自転車は追い抜きの時、2列になる。そして、自動車はセンターラインをオーバーして走らなければならない。右側を走る車もあったほどであった。交通量が少ないと言っても、都内より少ないだけで、決して安全なものはなかった。サイクリスツが退屈だから勝手気ままに道路を使って、他の車に迷惑をかけてもよいものだろうか。よく言われるが、「道路は、おまえ1人の道路ではない」のだ。サイクリスツだけの道路ではないのだ。車を運転する人ならわかるように、自転車1台が、左端ギリギリを走っていても、運転者は気をつかう。それを33台が並んで走り、しかも、途中2列になるなんて、交通道徳に反するも著しい!!皆の技術が低いからという者がいた。しかし、技術が向上したからとて、それが何になる。
なるほど転倒者はでなくなるだろう。しかし運転者はどうなる。自動車を運転している者はどうなる。通行人はどうなる。「すばらしい!!」と言って車を止めてくれるか。「すてき!!」と言って田んぼのどろ水に、どいてくれるか。
いやしくも公道で、自動車や通行人のいる道ではすべきことではない。やりたければ競輪場でやってもらいたい。サイクリスツは交通道徳に、もっと気を配るべきだ。
8月14日晴れ
大雪山国立公園探訪の予定を変更し、それを中止して、旭川市から神居古潭、砂川まで峠を越えて進んだ。企画の板橋さんのリーダーであったが、手慣れたもので安心して後を走れた。
砂川市の馬の競売場で泊めてもらった。倉庫の中で食事をしたが、久し振りの電燈の下で、おいしいハヤシライスを頂いた。食べ終って聞くところによると、加藤さんを中心に作ったものだそうで、明かるい電燈の下でテーブルについて食べると、まずい料理もこうもおいしく感ずるものか、とは皆の一致した意見であった。
8月15日晴れ
砂川市から、直線が27kmも続く道路を走る。
「北海道の国道は、全て高速道路なり」―とくよし
正午、我々は道路端に自転車を止め、東京に向かって1分間の黙とうをした。敗戦記念日である。
どうせなら、街中の国道で黙とうしたかったと思うのは、ドライであろうか。不純であろうか。なるべく多くの人に、今日は敗戦記念日だ。我々でさえ、そのことをたとえ1分間でも思っているのだと知らせたかった。
札幌に3時半到着。大都会だ。北の東京のイメージそのままだ。
しかし、あと1つ、何か活気がないようにも思われた。地方紙には「東京をまねただけの札幌であってよいものか」とあった。確かに、それは感じられた。
大通り公園で、キャンプ設営地決定まで自由となった。地元の堺が、よく動きまわっていてくれたようだ。我々暇人は早速「すすきの」街へ行った。やはり、ラーメンはうまかった。1番安いしょうゆラーメン、少し高い味噌ラーメン、塩ラーメンなどがあった。しょうゆラーメンを食った。篠原のおごりであった。ぎょうざを三輪がおごった。大阪野郎は気持がでっけえねぇ―。ほんまに、男らしいわぁ。
郊外にあたろうか、大通り公園から30分位自転車で行った所にテントを設営した。今日で実質的にランは終了し、明日、札幌駅で解散である。これからコンパである。
折しも、盆踊りが向こうの空地ではじまった。9時まで踊った。生まれて初めてであったが、楽しかった。曲は北海盆唄。「北海名物ー、かぁずかずこりゃあーれどよ!」女性が多かったのも、楽しかった大きな原因であったとは、後になって真剣に反省してみての結論であった。これは、ほんの冗談。これをまともに受け止めるような君だったら、君は相当に私を馬鹿にしていることになる。冗談だと、すぐにわかっただろうねえ?
コンパは、今までの禁酒が解かれた最初の酒。その勢いたるや、すごいもの。夜の夜中まで騒ぎに騒ぎまくり、テントの入口で小便をする者、吐き出す者、盆踊りのやぐらの上に、わざわざ眠りに行く者、女の子の名前を絶叫する者、1人ぶつぶつ酒がないとか、こん畜生とか怒っている者。
これもまた青春なり。33名、いや34名は、かくして互いに起き、食べ、走り、討論し、寝たのであった。同じメンバーでの合宿はもうあるまい。永久にあるまい。我々は、その最後の晩を、北海道の大地の上で、澄んだ星空の下で、惜しむが故に泥酔し、校歌を歌ったのであった。
「あつまり散じぃてぇ、人はかわれぇど、仰ぐは同じいきい、理想のひぃかり・・・」
第5回早同交歓会報告 – 政治経済学部1年 仲田
第5回早同交歓会報告
政治経済学部1年 仲田
11月26日
本日は、第5回早同交歓会の集合日である。定刻までに同志社の諸氏は、思い、思いに到着され、総数25 – 6名に達した。早稲田は20名近く。ただし、この中には開会式のみ参加する者もいるので、実際に走るのは、もっと少なくなるはずである。
5時過ぎから、宿舎弁天屋旅館にて、開会式を挙行する。両校主将から各クラブ員の紹介、エール交換等がおこなわれた。食事の際など、上級生はさすがに知り合いもいるらしく、旧交を暖め合っていたが、我々1年生は、そばでその話を聞いているだけ。まあ、そのうち慣れるだろう。
本日の事故としては、集合前、我がクラブの渡辺君が車にぶっつけられ、かなりの傷を負ったにもかかわらず、落海さんの助手としし参加した、ということを報告しておく。
なお、就寝前に、我がクラブの某さんが、同志社に襲われて、はやばやとチャックをこわしてしまった。俺もいやな予感がする。
11月27日江の島→城ヶ島
江の島弁天屋旅館を8時半に出発。江の島桟橋をクルリと回って湘南道路に入り、鎌倉大仏へ向かったが、風がかなり強く、いやな感じ。鎌倉大仏から鶴岡八幡宮を経て、長者ヶ崎にて昼食をとる。この頃から風はますます強くなり、砂浜でのバーベキューは、銀メシがジャリメシとなったため、せっかくの企画もだいなしになってしまった。それでも割合に肉が食べられたので、空腹感はさほど覚えない。
12時半長者ヶ崎を出て、すぐ浅間山・大楠山のマウントクライムに入る。押したり、かついだり、悪戦苦闘の末、予定より、2時間近くも早く頂上に着いた。この下りで、我が主将の加藤さんが、派手に転んで手をすりむいてしまった。「下見の時、ノーブレーキで下って、けがをしなかったのに、注意しながらゆっくり下りて転ぶとは不思議だ」とは、加藤さんの弁。
大楠山から芦名へ出て油壺へ向かう。向かい風ではあったが、予定より、1時間も早く油壺へ到着。1時間半位見物してから、本日の宿泊地城ヶ島ユースホステルへ向かったが、Y・H手前の大橋では、強風のため、自転車が進まずストップしてしまう者まで出る始末。後からきた落海さんの自動車が、尻をふっていた。
夕食後、食堂で芸能大会を開催した。将来、夫婦生活に役立つであろうものから、昔なつかしい童謡と踊り、はては早食い競争まで飛び出したが、ペアレントや家族の人達まで見物していたので恥かしかった。この芸能大会の最中、星さんが到着したので、早稲田は17名となった。Y・Hのため、本日はおとなしくお休みなさい。
11月28日城ヶ島→横浜
本日も昨日に続き、風が強い。城ヶ島灯台を眺めてから剣ヶ崎灯台へ。出発を1時間ずらしたため予定より1時間遅れて到着した。記念写真を撮ったあと、そこから三浦海岸を通って武山へ出る。ここで本日最大の呼び物、ヒルクライムを行なう。ちょっとした手違いでなかなか出発できなかったが、12時10分に最初の組がスタート。これを登らないと昼食にありつけないので必死になって登る。
結局、1位は我がクラブの小泉さんでしたが、それより頂上で食った飯のうまかったこと!!!
武山を下って、横須賀で三笠を見物。途中事故のため4名ばかり遅れたが、すぐ追いついた。この頃から風が弱くなってきた。予定されていた猿島は都合によりカットされ、金沢八景から横浜の氷川丸ユースホステルへ向かった。
夜、食事の後ミーティングを開き、各自が感想、意見その他を述べた。やはり、この交歓会そのものの意義、あり方についての意見が多かったようである。
ミーティングの後、予定されていた素人芸能大会を止め、夜の横浜探訪に出かけることになった。両校1年生もグループに分かれて行動したが、皆、喫茶店などに入って、クラブのこと、サイクリングのことその他について話合っていたようだ。
11月29日横浜→東京
本日はいよいよ交歓会の最終日である。氷川丸を出て、三溪園、港の見える丘公園、大棧橋など横浜を見物してから、第2京浜を通って東京へ。さすがに第2京浜は交通量が多く、東京に近づくにつれて、だんだん隊列が乱れ、五反田で、前と後が完全に別れてしまい、止むを得ず、独自にそれぞれ最終地点の皇居に向かった。ここで昼食をとった後、霞ヶ関ビルを見学。その後、一応解散し、同志社の人達は、汐留に行ったり、自転車を分解して早稲田に行き、我々は、各自家へもどって、コンパの用意をすることとなった。
5時半からのコンパでは、種々の行事が行なわれ、教育上よからぬことが行なわれたが、ともかく無事に終わった。小生、ベロンベロンに酔っぱらってしまい、その後何があったかさっぱり覚えておらず、残念である。
とにかく、第5回早同交歓会が無事終了したのは、両校クラブ員の熱意、特に今回の委員長を担当された落海さんの御努力のおかげです。まことに皆様ご苦労さまでした。
わがサイクリングの視点 – 政治経済学部3年 木村
わがサイクリングの視点
政治経済学部3年 木村
序
毎年そうであったように、今年も合宿を無視して、ぼくは1週間の個人ツァーを行なった。(わざわざここで「無視」というような刺激的な言葉を使ったのは、だとえ、ぼくが外的諸事情による不参加の正当性を主張したところで、クラブ員諸氏はことば通りには受けとらないであろうし、かつ又ぼく自身もその正当性をあくまで押し通すことができるとは思っていないからだ。)
それをこれから復元しようというのだけれども、ぼくには記憶力が欠けているし、それを助けるメモも無機的な記録に留まっている。そしてさらに悪いことは、最も美しい自然をくぐり抜けてきたというのに、それを鑑賞する能力を持っていなかったということである。そんなわけで、これから書かれる「旅行記」は、多少創作の加わった記録と、枚数を確保するために気ままになされたサイクリングと余り関係のない無意味な言辞の浪費で埋められるであろう。もし、ぼくに豊富なイマジネーションと文学的才能があるなら、それでも読者を楽しませることができるのだが、あいにくと、それらを持ちあわせていないので、退屈な言葉の羅列ということになってしまうのは目に見えている。
だから、有能な編集者によってつまらない文章であると判断され、削られ、とても載せるに値しないものとされても一向にかまわないし、ぼくもその正当さを認めることであろう。ただ編集者にお願いしたいのは、この文章のできがどうであれ、せめて、この序文だけは載せていただきたいということである。「峠」のために原稿を寄せたという証しのためにだけでも。
さて、最初に述べたように、クラブに入って3年間というもの、1度も合宿に出たことがない。クラブに所属している人間が、その最大の行事の1つである合宿に参加しないというのは、多かれ少なかれ、そのクラブの存在理由に対する挑戦であろう。しかし、我々のクラブはその挑戦に対抗できるほどに強くはないので、結局、しぶしぶながら認めてしまうわけである。それでは、このクラブを強固なものにして、拘束力を増すべきであろうか。断じてそうではない。そうすれば、確かに参加者は増え、全員出席も夢ではなくなるだろう。よくまとまった、結束の非常に強いすばらしいクラブとして称賛されるだろう。
しかし、ぼくはそこに失なわれたサイクリングを感ずる。クラブとしての完成とともに、サイクリングが1点に凝結していくような気がする。だから、ぼくはクラブがこれ以上強くなってはならないと思う(かと言って、弱くなっていいというわけではない。また、断わっておくが、これはクラブの対外的発展とは別問題である)。我々のクラブは、サイクリングを通してあるのではなく、サイクリングとともにあるべきだからである。
何10人の仲間と一緒に走るのも、サイクリングである。気のあった同志数人で出かけるのも、サイクリングである。1人で行くのもまたサイクリングである。舗装道路をひたすらに一日何100キロも走る。郊外を彼女と並んで走る。山道で押したり、かついだりする。テントをつんで何日も行く。日帰りする。いずれもサイクリングである。自転車が何であろうと、服装がどうであろうと、乗車姿勢が悪かろうと、やはりサイクリングである。
それでは、この種々多様なサイクリングの根底に、共通部分を見出すことができるだろうか。つまり「一体、私はなぜサイクリングをするのか」という問いに対して通用する、たった1つの答を見出すことができるだろうか。ある人が「なぜ山に登るのか」と聞かれて、「そこに山があるからだ」と答えた話は誰もが知っている。しかし、これが山男たちの共通の答だとするなら、我々は「そこに道があるからだ」という解答を得るかもしれない。けれども、それが唯一のものかどうかわからない。ただ、ぼくには、あの隊長は「自然が山となって我々に話しかけてくる。自然の恩寵は山となって現われ、私と対等の立場まで降りてきたのだ。それゆえ、山は自然の奇跡だ。だからこそ、そこにある山を求めて登るのだ。私は山を征服することはできない。ただ山に驚嘆するだけなのだ」と言っているように聞こえる。詩人はこう歌っている。
純粋に生まれてきたものは謎だ。
歌にさえこの謎を解くことは許されていない。なぜならば、
あなたははじまった時のままにとどまるだろう。
どんなに困苦と訓育が働きかけようとも。
―ヘルダーリン「ライン」・手塚富雄訳
ここでは自然は川である。では、サイクリングにおける自然は何であろう。ぼくはやはり「道」というものを考えてみた。どうもっくりしない。道は自然の現われなのだろうかという疑問が起こってくる。そうも考えられるし、またそうでないようにも思える。
けれども、ぼく自身「そこに道があるからだ」という答は、なかなかのものだと自画自賛している。なぜなら、自然はまだ知られずにあるのだから。ぼくの前に道はないのだし、道はあるのだ。君たちを見ていると、どうやら、ぼくの答はぼくだけのものでしかなさそうだ。でもまあいいさ。
ぼくは自然を所有しようとするのではない。にらみつけるのでもない。また、それと対話するのでもない。自然が山となり、川となり、海となり、森となり、花となり、鳥となってぼくの前に現われることを、ただ讃美し驚嘆するだけなのだ。もし、人が他のことをなそうとするなら、それは自然を知ろう、この目で確かめようとすることであって、自然はすぐに見抜いてこう言うだろう。
「お前がそうする時、お前はお前自身を私の前で卑小化するつもりでそうするのだとは思っていないだろう。反対に、お前は私より偉大だと感じているのだ」
自然はいつの時にも、やはり未知なものなのだ。
自転車乗りの日記
8月1日
ぼくが旅行に出発したのは、8月1日である。その頃の天気図はというと、日本周辺を4つか5つもの熱帯性低気圧が取り囲んでおり、数日来、どんよりと曇った涼しい夏が続いていた。そして、その日も鉛色の空に変わりはなかった。7時に小金井の自宅を出た。
自転車は、クラブ員諸氏既に御存知の1-1/4インチ。それに前後のキャリアを無理につけて荷物を満載したので、スピード・ラン用のこの自転車は、何ともつり合いの取れぬものになってしまった。この虐げられた自転車を見て、ベスト・サイクリストたちは、一斉に僕を非難するに違いない。「お前は自転車の使い方を誤っている。この自転車はキャンプ用のものではないのだぞ」しかし、「サイクリングには、ルールなんてありはしない」と、ぼくは彼らに答えるだろう。
飯能までの道はポピュラーである。今年のクラブ・ランのコースにもなった、平坦な、舗装された、それゆえ変化のない広い道路である。ここに来るまでに10数台の自転車を追抜いたが、サイクリストはいなかった。でもたった1台、ぼくの印象に残った自転車があった。青いフレームの自転車で、うしろに荷物を結わえつけてあった。20才位の青年がキャラバン・シューズでそれをこいでいたのだ。そして、この青年と翌日一緒に走ることになるのである。
飯能を過ぎると、サイクリストの多く、ドライバーのすべては、右折して正丸峠へ向かうことだろう。なぜなら、そこは舗装されている。しかし、ベスト・サイクリストは直進して、山伏峠のコースを選ぶだろう。なぜなら、そこはほとんど舗装されていない。そしてぼくもその道をとった。なぜなら、そこを上ったことがないからだ。この名栗川沿いの道はやや狭い。そして舗装もやがて終る。車の往来も、平日だから少ない。
しかし、この道はあくまで川に忠実である。流れが堅い巨大な岩壁に突きあたり、方向転換を余儀なくさせられれば、道はそれに従い、堅い岩板にゆるやかな流れを妨げられれば、坂も傾きを増す。涼しい夏といっても8月である。曇った空は汗を発散させることなく、むし暑い。家を出て初めて自転車を降りる。暑さが1度に襲いかかる。河原に出ると流れは豊かである。が、少し濁っている。きっと先日の雨のせいにちがいない。さらに流れに近づく。空気が冷たい。暑さが逃げていく。自分がしばらくここにいなければならないことを感ずる。ここから5キロ程の急坂で峠に導かれるが、それほど荒れた道ではない。いわゆる普通の峠道である。峠は広く、何もない。風すらない。少し砂利道を下り、正丸峠からの道と合流すると、秩父まで舗装された変化に乏しい下り坂になる。秩父市内を左に折れて、しばらく平坦な道を行くと、やがて右手に荒川、左手に奥武蔵の山々を見ることができるようになる。だが何ということだ。山が真白になっている。秩父は昔から石灰が採れ(それゆえ、日原をはじめとする鍾乳洞もあるのだが)、セメント産業が盛んである。そして、それが1つの山全体を根本から食い尽してしまったのだろう。
三峯口に近くなると、自然はそのままの姿で両側に迫ってくる。そしてトンネルも自然であった。この道が足に少し重くなる頃、大滝の分岐点に着いた。1時である。ここで左に曲ると、二瀬ダムまでは荒川を左手に見ながらの上りである。面白くない道だ。下りの快適さのためにだけあるような5キロであった。ダムの手前にはトンネルがある。このトンネルは、おもしろいことに中で2つに分れている。これは何とも奇妙な感じだ。右へ行くと、川又の発電所を経て、秩父往還の最難所、日本3大峠の1つに数えられている雁坂峠へと続く。左が三峯神社までの有料道路である。トンネルを出ると、二瀬ダムの上にいることになる。展望は実によろしくない。大滝の部落はかすみの中に消え、奥秩父の山々はそのおもかげすらない。秩父湖はただ水がせきとめられているだけだ。そして、あと10キロ上らねばならない。
100キロ前後走ったあたりで、疲労のせいか、自転車がいやになることが、ままある。どうやら今それがやってきたらしい。家を出てから98キロである。とにかく動きたくない。そのうちに慣れの中に疲れが消化されてしまうだろう。考えられるのはそれだけだ。先へ進むことへの義務感などというものではない。その期待だけで再び上り始める。右手下方にしばらく秩父湖を見るが、そこに別れを告げると、ゆるやかな山肌をはうように上っていく。完全舗装の道だが1車線の狭いものである。約1時間の後、有料道路の終点、標高1,044mに達した。広い駐車場にあるのは軽自動車だけ。静かである。人影もない。遙かかなたで、木を切っているのであろう、断続的にエンジンの音がかすかに響いてくる。展望はきかない。ささの間に埋もれたゴミだけがやたら目についた。少し下って三峯神社へ行くが、興趣をそそるものはさらにない。この神社は鎌倉時代の初期に修験道によって開山され、江戸時代は霊場として知られていたという。しかし、朱の柱の集まりとしか、ぼくにはそれを見ることができなかった。
ぼくは、もと来た道を引返した。白いアスファルトを見ながら、10分たらずで二瀬ダムに着いた。と、1人の男が立っている。近づいてよく見ると彼ではないか!そう、けさ所沢でみかけた実用車を駆った青年である。話を聞くと、彼は正丸峠を越え、ぼくに遅れること約2時間、たった今ここに着いたのだった。
「今夜は川又あたりに夜の宿をとり、明日雁坂峠を越えて御坂から山中湖へ行くつもりだ。そこにはゴルフ場のキャディのアルバイトが待っている。雁坂峠はどんな峠か知っているか?道路地図を見ると自動車は通行不能となっているが、自転車くらいはきっと行けるだろうと思う」
と彼は言う。
「とんでもない。ぼくもかって、この峠に自転車で挑戦したことがある。その時は塩山側からだったが、とても自転車で行けたものではない。これを見たまえ、完全な登山コースになっている。しかもほくは、この急坂と書いてある手前ですでに引返さざるを得なかったのだ」
と、持参した地図を示した。迷っているようだった。彼の行くべき道は、雁坂越えを強行するか、東京に戻るかの2つしかなかった。そこでぼくは彼に3番目の道を提示した。
「ぼくはこれから大滝まで戻って、三国峠から信州に出るつもりだ。君はそこから韮崎に出ればよい。距離的には遠まわりになるが、時間的にはそういうことはあるまい」そして、彼はぼくと同行することになった。
大滝の分岐点から始まる三国峠への道は、もちろん砂利道である。時刻は4時。日没まで走ろうということになった。一緒に上り始めるが、決して遅いペースではない。彼は変速機のない実用車にもかかわらず、ほぼ、ぼくのペースである。日がだんだん傾くせいもあるだろう、山の奥へ踏み込んでいくのだ、という実感が伝わってくる。流れに沿ったゆるい上り坂は、それほど荒れていない、走りよい道である。約2時間、15キロ程走って少し広くなった川原を見つけ、そこに夜営することになる。幸いに人家もあり、水ももらうことができそうである。テントを張り、夕食の後かたずけを終えると8時であった。見上げると、狭い空には星が静かに現われ、岩に砕ける水音だけがひとり響いていた。明日は晴れるであろう。
8月2日
6時に目が覚めた。朝食は、コンビーフと梅干しである。C大のワンダー・フォーゲル部員である彼は、夕べもそうであったが、食事を作るにも、テントをたたむにもテキパキとしている。まだ1年生の新米部員は、先輩たちにどやされながら造営してきたに違いない。7時過ぎには、すでに出発できる体制にあった。昨日一体どのあたりまで進んだのか見当がつかなかったが、1分も行くと中双里と書かれたバスの停留所があった。確かバスはここまでであったように記憶している。してみると随分と昨日は頑張ったものだ。中双里は、第一日目の計画のマキシマムであったから。(ところでこの「中双里」、一体何と読んでいいのか、未だに解らない。彼は「ナカソリ」を主張し、ぼくは「ナカモロザト」と読んだ。土地の人に聞こうにも人影が全くないのだ。)中津までの5キロは、昨日とほぼ変わらない道を上る。ほとんどの間、左に見る中津川は、川中は次第に細く、岩は次第に大きく、峡谷の様相を呈してくる。
中津の部落をすぎると、林道の開始を示す遮断機に行きあたる。日に焼けた、人の良さそうな老人が「しっかりやれよ」と言いながら、ゆっくりとそれを開けてくれた。「中津川林道起点、19・2キロ」と書いてある。この頃から、晴れていた空が厚い雲におおわれ始める。勾配はややゆるやかな地道となり、川巾も広くなる。しかし、それも長くは続かなかった。彼は少しずつ遅れ始める。あの自転車だから仕方あるまい。どうやら自転車を降りて押しているようだ。そして十文字峠との分岐を過ぎて、ぼくも彼にならうことになったのである。乗ったり降りたりしていたが、悪いことに雨が降り出した。しかも強くなるばかりだ。止みそうにない。やがて見つけた人夫小屋に1時避難する。
雨だけは何とかしのげるが、濡れた体が寒い。30分位遅れて、押しながらやってきた彼は、なおも進み続けるという。ぼくも従わざるを得なかった。100mばかり歩くと、「三国峠4キロ」の指標を見つける。この付近では完全に歩いていたのだが、これを見て勇気100倍、彼をほったらかして再び自転車に乗る。そして30分後の午前11時、ぼくは標高1,754mの三国峠に立つことができたのである。ワンゲル部員氏もさらに30分の後、同じところに到着したのだった。雨は、ほぼ止んでいたが、下界は雲に閉ざされ、視界は狭いものだった。どうも昨日からついてないようである。「三国峠」と書いた看板の前で記念写真。でも、この天気ではカラー写真もさえないであろう。
三国峠は、名前の示す通り、埼玉県、長野県、群馬県の3県の境をなす峠である。奥多摩などにはない、山の気配を深く感じさせる峠であった。
峠をぬけて(というのは、まだ埼玉県側でぼくたちは休んでいたのである)、長野県にはいると、晴れている。雲なんて見当らないのである。道も乾いている。遙かふもとの方に、梓山の部落を眺めることができる。下り坂は、露岩の、荒れた悪路である。けれども、道の両側には様々な高山植物が花を開いて、ぼくたちを楽しませてくれた。悲しいかな、ぼくはその1つさえ名前を知らなかった。その美しさ、可愛いさは、色は何色で形はこうだったと説明したところで、正確に伝えることは不可能である。展望の記憶はない。ぼくの目は下にしか向けられていなかったのだから。これらの高山植物に祝福されて、山を下る気持だった。
梓山林道の起点で、甲武信岳にその源を発する千曲川に合流する。清らかな、しかし幼い流れである。この先は千曲川に沿ってバス道を行くのであって、山々は次第にぼくたちから遠ざかっていく。平坦な砂利道は、信濃川上流まですぐであった。ここで、彼は左へ行き、ぼくは、 千曲川がそうするように右へ、大きく曲がった。ところが、川は山にさえぎられて、もう1度方向転換を余儀なくされたが、ぼくの道はそうではなかった。敢然と山に挑んでいた。そして海ノ口までの数キロは、再び乗ったり押したりの道行きとなったのである。最後の急な石だたみの下りを終えると国道に出る。 千曲川を、ある時は同じ高さから、ある時はかなり高い所から見ながら、やがて松原湖の入口にたどりつく。左へ曲がれば松原湖、まっすぐ行けば、佐久から小諸である。今日の宿泊予定はここからニキロの松原湖、今の時刻は3時過ぎだから、ずいぶん早く着いたものだ。ところが、この2キロがきつい坂なので、またもや押さねばならないはめになってしまった。しかも夕方には、もう1度ここを上ったのである。
パウゼ
ここまでで、最初の2日の様子を述べてきたが、既にかなりの枚数を使ってしまった。この調子で残りの4日間を書き続けるなら、読者に益のない苦痛を強いるだけである。そこでぼくは転調を試みることにした。これからあとは、できるだけ簡潔に記そうと思う。実際のところ、その方がぼくにとっても楽なのだし…
8月3日
6時半に松原湖をあとにした。稲子湯までは、八ヶ岳の裾野を徐々に上る細い7キロ程の砂利道。空気が透明なら、景色の雄大さはすばらしいものにちがいない。稲子湯は僅か1軒の旅館があるだけで、混浴という噂もチラホラ。この先は営林署の車しか通さない林道(道路地図には載っていない)を行く。かなり整備された道である。勾配はそれ程急ではないがやはり歩く。どうせ歩くならもっと歩きがいのある道を、というわけで登山道にも突進。でも、これはよほどの物好き以外には奨められない。麦草峠までは約12キロ。峠は標高2,100m程で、展望はきかない。下りは実にひどい道で、砂利が深いか、岩がゴロゴロ。蓼科湖のすぐ手前から舗装になる。続いてスズラン峠を経て蓼科牧場へ。このコースは絶景である。再び砂利道を白樺湖まで行けば、今日の行程はおしまい。走行距離60キロ。
8月4日
つい1週間前に開通したばかりの霧ヶ峯有料道路は、なだらかな高原を10キロ上り、4キロ下って霧ヶ峯へ至る。普通ならここから茅野に行くのだが、へそまがりサイクリストはそうはしない。ひどい悪路を奥霧ヶ峯へ。途中から、天然記念物の湿原となる。車はここまで。登山道を1キロ程歩けば、八島高原のバス終点に出る。その間、湿原の高山植物が目を楽しませてくれる。ここまで来たサイクリストはそうはいまい。八島高原から中仙道に出る10キロは最悪である。おそらく上ることは不可能だろう。今日はさらに100キロ以上走って、御坂にテントを張った。本来の予定は、南アルプスの広河原へ夜叉神峠、野呂川林道を通って行くつもりだったのだが、自転車は通行不可、変更を余儀なくされた。サイクリング誌のレポートを信用して、計画を立てたのに・・サイクリストの中には、道路標識すら知らない者もいるようだ。
松原湖から中仙道までのコースは、変化に富んだ雄大なサイクリングコースとして、責任をもって推奨できるものである。
8月5日
前日の雷雨でほとんど眠れなかった。有料道路の入口まで5キロ程、そこから未舗装の旧道にはいる。道中は広く、それ程の急坂ではない。6キロでトンネル、それを抜けると河口湖が見える。1軒の茶屋と太宰治の碑が立っている静かな御坂峠である。河口湖、富士吉田から山中湖へ。今日はここまで。昼前に着いてしまった。走行距離44キロ。
8月6日
山中湖を出て山伏峠まではじきだ。ただ砂利が深いので、押さねばならなかった。あとは道志川沿いに東野まで。この間の景色はなかなか良い。富士五湖方面へ行くのなら、甲州街道など通らずにこの道を利用したまえ。道は相当悪いが・・・東野からは新入生歓迎ランと同じコースだからもう書かない。
6日間、550キロの旅を終えて、帰宅したのは3時過ぎ、その間パンク2回、ネジとび2回。落車・けがはなし。使ったお金は3000円。知りあった女の子は皆無?
あとがき
夏のプライベート・ランの記述はこれで終わったけれどかなりの部分を省略せねばならなかった。蓼科高原、霧ヶ峯、八島ヶ池の景色を阿蘇などと比較しながら語りたかったし、峠のよさ―それは展望にあるのではなく、風にある―や、自然と道路との関係舗装道路であるべきか、砂利道であるべきかは環境が左右する―など詳しく述べたいことが残されてしまった。のちの機会に、これらについて書こうと思っている。
香港・台湾・沖縄サイクリングツアー – 商学部3年 加藤
香港・台湾・沖縄サイクリングツアー
商学部3年 加藤
昭和43年2月14日、午後6時30分、加藤、新間、森WCCの3名を乗せた西鹿児島行特急「はやぶさ」号は中村、星その他、俺の友達数名の見送りを受けて東京駅を後にした。我々にとっては初の海外遠征ランである。皆と手を振って別れる時、ふと、もうこれで1ヵ月以上は東京ともお別れだ、と感傷的になったが、それ以上に俺の胸は未来に対するスリルと興奮で高鳴っていた。
「神よ、願わくば我に七難八苦を与え給え」
戦国時代の武将、山中鹿之介の言った俺の好きな言葉である。
列車は一路、鹿児島へ、鹿児島へ…
2月15日雪
朝8時起床。広島附近から雪が降り出し、列車が遅れ始める。下関からみる九州の雪景色が、とても印象的である。前の座席に居た鹿児島に住む西田さん(我が早稲田大学の先輩)という人と知り合い、家に泊まる様に勧めてくれたので、お世話になる事にした。結間『はやぶさ』は約6時間遅れ、午後11時に西鹿児島に到着した。タクシーで西田さんの家に行った。フェニックスのある南国情緒豊な家である。入浴後一杯やりながら御馳走になった、すき焼きのおいしかった事。先輩はありがたきもの!!
2月16日快晴
朝食を御馳走になっている時、テレビのニュースで、東京が十何年来という大雪で、交通マヒになった事を知って驚いた。出発前に西田さんが西郷隆盛の墓と城山公園を案内してくれた。鹿児島港で出発の手続きをしている時、井口さんと再会。面倒だった諸手続をすべて終えて、いよいよ日本としばしの「さようなら」である。ドラが鳴り「ひめゆり丸」と岸壁の距離がしだいに遠くなっていった。湾にいるうちはあまり揺れなかったが、外洋に出てからはかなり搖れる様になった。夜、甲板に出てみたが、意外な程暖かった。あたり一面、見渡す限り海で気持がいい。
2月17日晴10キロ
7時頃起床してみると、皆はもう起きていた。夜明けなのに冷え込みが少ない。素晴しい朝焼けの空を眺めると「いよいよ南国へ来たな」という感が強くなる。9時着の予定が11時になり港がいっぱいとの事で、さらに下船は遅れ、1時半頃になってしまった。とても暖かくて半袖でも平気である。港で自転車を組立て始めると大勢の人が集まって来てビックリ!かなり手間どり4時すべて完了した後、基隆行の手続きを済ませる。約10キロの初ランをやり、春海Y・Hに泊まる事にした。
2月18日雨時々晴60キロ
21歳の誕生日を迎える。10時半Y・Hを出発し、守礼門に向かう。初めて上りにかかる頃から雨が降り始め、少し苦戦。琉球大学の中へ入ると晴れ始め、南国の強い陽光が我々を照らしてきた。
構内の木の緑と、真青な海とが調和する風景は沖縄独特のものであろう。昼食の後「ひめゆりの塔」へ向かうが、雨が激しく降り始め、顔が痛くなる程になったので、サングラスはつけたままである。おまけに途中から舗装路が切れ、アップダウンが多く、全く悪戦苦闘する。南部戦線の跡は昔の面影を偲ばせている。
戦没者の慰霊塔や牛島中将の墓に花を供えて、しばし冥福を祈る。暗くなってきたので「ひめゆりの塔」は明日、行くことにして、そこから糸満へ向かう。遙か西の地平線と、どす黒い雲との間にある僅かな夕焼けがうら寂しく感じられ、現在の沖縄を象徴しているかの様であった。糸満の公民館に到着した時は、すでに真暗になっていた。今日は5回も雨に降られ全身ずぶ濡れ。とんだ誕生日となった。
2月19日曇時々雨30キロ
朝8時起床して、すぐ昨日の雨のため汚れた自転車の整備をした後、再び「ひめゆりの塔」へ向かう。糸満から6 – 7キロのところにあり、塔の前は防空壕になっていた。戦争のはかなさを物語っている様な、何となく寂しい感じのする塔であった。「人間たちはなぜ戦争をしなくてはならないのか?」帰りは強烈な向かい風にあう。
糸満で食事をした後、軍用道路を通って那覇へ向かう。またまた向かい風が激しく、かなりバテる。
那覇へ着いた後、沖縄サイクリング協会長の森さんと知り会い、沖縄ラリー記念バッチを戴き「台湾に行っても、これを付けて元気で走りなさい」と激励された。泊港から出港する台湾行「那覇丸」は、強風の為2時間遅れて午後5時に出港。我々は自転車を甲板の上に括り付け、更に上からテントをかぶせた。その夜、僅か2000トンの「那覇丸」は大搖れに搖れた。
2月20日曇30キロ
朝食を2人分食べて、胃の調子相変わらず快調。12時頃石垣島着。1時から5時まで自由時間。自転車を降ろし、島内を走り始め、大浜前総長の銅像のある八重山高校や総長の生家へ行き、親類の人々と話をする。昨日から船に揺られている為か、上陸後もまだ搖れている感じが残り、足が地につかない。皆が飯を食べている間、1人で西の方へスピード・ラン敢行。西の方へ行くと素朴で沖縄の本当のよさを再確認する事が出来る。海辺もいいし、丘はアメリカ西部へでも来た様に広く感じる。とても快適なサイクリングコースである。時間があれば、この島を1周してみたいと思った。港に帰り新間と木村にこの話をしたら2人共行ってみたいと言い出したので、また灯台の方へスピードをあげて向かった。写真を撮ったり貝を拾ったりしてから5時ジャストに港に戻った。いよいよ明日は台湾である!!
2月21日曇のち雨
6時、目を覚ますが、時差の関係でまだ暗い。8時頃基陸港へ入、諸手続の関係で下船は12時頃になる。自転車は税関に持っていかれ、3時にならないと返してくれないと言うので、明日まで置いておく事にする。井口さんとここで別れタクシーで台北へ。建築物は日本統治時代に建てられたものも多く、さ程大きな変化は見られないが、住民の話す言葉が違う関係上「外国に来たな」という感はある。台湾旅行社へ行き香港行の手続を済ませてから台湾青年社へ行き、旅館の紹介をしてもらい、そこで日本語の話せる林さんという人と知り合う。「華春荘旅社」という旅館(我々の台湾に於けるペースホテルとなる)に泊まる事にした。夕飯の後、1眠りし、6時から林さんが俺と木村を市内見物に連れてってくれた。(新間は風邪気味の為旅館でネンネ)
この晩は、林さんからいろいろな事を多く学び、台湾の情勢をよく知る事ができ、政治経済に対する視野が広まったのは非常に有意義であった。神社へ行ったり、台北の露店でいろいろな物を食べたり・・何しろ食物の安さは日本など問題ではない。ちなみに「おしるこ」僅か1元(日本円約9円)「カキのスープと寿司」(2・5元)「ワンタン」(1・5元)。裏街は赤線地区が非常に多く、売春婦達が異様な目つきで我々を見て誘いの言葉をかけてくる。勿論、中国語だから俺と木村は何を言われているかは解らない。その後、雨の降る中を総督府へ行ったりして午後11時頃旅館に戻る。台湾に来る早々、地元の人に歓迎されて俺達は幸せ者である。
2月22日雨
目を覚ますと又雨が降っていた。台湾では北部はこの1月2月頃は雨季に当り、丁度日本の梅雨に似ている。そう寒くはないが、この旅館の女主人に言わせるとかなり寒いらしい。やはりこれは北国育ちと南国育ちの違いであろうか?昼頃から3人で市内へ出かけ、切手を買い、日本へ絵葉書を送る。博物館へ行ったりメインストリートをしばらく歩いてから台北の第1デパートへ入り、台湾特産品売場で、いろいろな物を見学する。売場では、日本語の少し話せる女の子が我々の相手になってくれて、親切に説明してくれた。旅館に戻り、香港行の仕度をした後、夕方6時、タクシー(基本料金4元で500mごとに2元増)で台北駅へ。そして特急バス(台北ー基隆約30キロ10・5元)に乗り換えて基隆港へ向かった。しかし港に着いて俺達は、どでかいミスをした事に気が付いたのである。税関は5時で、すでに閉ってしまった為、我々が昨日置いておいた自転車を取り出す事が出来なくなったのである。乗船手続きを終えてから、そばにいた係官に頼んでみたが答は「NO!」であった。
頭に来た俺は、自分の荷物の番を新間と木村に任せ、雨の中を税関の建物の方へ向かって走り出し、港の係官らしき人々に英語と日本語で必死に交渉してみたが、結局だめであった。我々はしかたなく、「ANKING」号に乗り込んだ。そこで我々は同じ早大の石川さん、拓殖大学の渡辺君、茨城大学の人達と知り合い、旅を共にする事になった。船客の殆どは中国人である。
2月23日晴
朝方かなり冷えこんだ。朝食を7人掛けのテーブルでとったが、非常にまずかった。(3等であるから余り文句も言えないが…)なにしろおかずの量が少ないし、味も悪く、そのひどさは口では言えない。この為、行きは新間が、帰りには木村がまる一日絶食した。食後甲板に出てみた。空は快晴で、18日以来見る太陽が輝いていたが、海上の風が冷たい為か、それ程暖かくはない。この船も娯楽設備が何もなく退屈なので、甲板で歌を歌ったり、腕立て伏せ、シャドーボクシングをしたりして体を動かして時間をつぶした。夕食後はベッドに横になるが、早すぎて眠れない。仕方なく石川さん達と4人でトランプをして遊んだ。
2月24日小雨のち曇
朝6時、小雨にけむる香港着。夢にまで見た香港!!ナポリ、リオデジャネイロと並び称される世界3大美港の1つ香港!!さすがにその景色は『素晴しい』の一言に尽きる。白亜の高層建築、その背後にある山肌の緑、この人工美と自然美とがうまくミックスされ、香港独特なる美をかもし出しているのであろう。香港は自由港である為、下船の時の荷物検査も非常に簡単に終り、午前10時初めて香港の土を踏む。すぐ 30US$を180HK$に替えてもらってYMCAへ行く。1部屋3人、2日で1人当り16HK$であった。(食事は付かない)
台湾再入国のビザ申請の為、ビクトリア市へ行き手続きをする。船の食事がまずかったので、久しぶりに日本料理かヨーロッパ料理を食べようという事に話が決定。料理店を物色中、我々は街中で1人の中国娘と知り合った。彼女の名前は黄秀芳といい、第1印象は少しシックな感じのする女の子だった。彼女は土曜日だったので仕事を終えた後、我々をある料理店に案内してくれ、一緒に食事をした。次の日、香港を案内してくれる約束をして別れた後、我々は大丸デパートに行き絵葉書を買った。航空便で出す為切手も買ったが、なんとこの代金が1枚25HKD。つまり日本円で15円足らずであり、日本に於ける封書の郵便料と同じなのには、少なからず驚いた。
タクシーで香港の名所の1つ、タイガー・バーム・ガーデンへ行ったが、車から降りるや否や、附近の子供達が、我々に「金をくれ」と寄って来た。我々は、その、子供達を気の毒だと思ったけれど、貧しいからといって人に甘えていてはその子供達のために良くないと思い、結局なにもやらなかった。この庭園は昔、薬を売って大金を得た人の庭園と言われていて、中には様々の人形、原色で彩られた壁などがあって、いかにも中国的感じのする庭であったが、その美は我々日本人にとって多少理解し難いものであった。台湾入国のビザ申請を終えた後、フェリーボートで九龍に戻ってホテルで夕食。
ここで少し香港について説明を加えておこう。香港は面積1,013平方キロ。東京都の約半分。人口約400万人。首都・ビクトリア市。英国直轄植民地。狭い意味での香港はビクトリア市を指すが、実際の香港とは、香港島と中国大陸につながっている九龍半島及び附近の小さな島々から構成されている。次に歴史的変遷をみると、第1次アヘン戦争(1841年)の結果、イギリスは、まず香港島を領有し、その後第2次アヘン戦争(1860年のアロー号事件)で九龍を割譲させ、更に1898年に領土防衛の目的の為、九龍の背後にある新界地(ニューテリトリー)を99ヵ年間清朝政府から租借した。従って、香港は現在もなお英国政府の任命する総督が統治しているのである。
さて夕食後、我々は香港の銀座、九龍の街へ見物に出た。ここはいわゆる香港のショッピング街。目抜き通りのネイザン・ストリートを中心に数々の店が立ち並んでいて、世界各国の商品が本場の国よりも安く買えるのである。実際、香港に於ける商品価格は非常に安く「いったい、この店の卸し価格はいくらなんだろう?」と我々に疑問を抱かせる程であった。皆で、あちこち店を捜しているうちに俺は他の5人と離れてしまった。仕方なく「異国での夜の1人歩きもまたイカしてる」等と思いながら九龍界隈を散歩しているうちに、ある時計店の店員と親しくなり、日本と香港の気候や学校について語り合った。9時を過ぎたので1度YMCAに戻ったが、新間も木村もまだ帰っていなかったので、再び街中に彼等を複しに出かけた。しかし、これが悪く、後で変な女や男につきまとわれたり、人力車のおっさんにしつこく「YMCAまで乗れ」と迫られたりして、香港最初の晩は厄介な事ばかりであった。10時頃ホテルに帰り、日本の友達に絵葉書を送る。
2月25日曇のち小雨
朝9時頃起床してから、久しぶりで風呂へ入る。10時頃渡辺君が来て出発準備完了。たばこを吸って外へ出た時、丁度、昨日の女の子が2人で来た。彼女は昨日のイメージとは、ガラッと変わった服装をしてきたので最初は誰れだかよく解らなかった。連れの女の子は彼女の学生時代のクラスメートだと俺達に紹介してくれた。彼女の名は、厳妙清。瞳がとても魅力的な女性である。我々の最初の行先は香港100万ドルの夜景を1望のもとに見渡せるその名も高き”ビクトリア・ピーク”である。
フェリーで香港島へ渡り、それからケーブルカー(片道料金60HK$)で行った。残念ながらあいにくの曇りで、期待した程の眺めは得られなかったが、なかなかロマンチックなムードにあふれた場所だった。皆で記念撮影。それからバスに乗り換えて漁港として、また水上レストランのある所としても有名な、アバディーンへと向かった。バスの中で彼女(厳小姐)は手帳をとり出し、俺に日本語を教えて欲しいと言ったので、それに書いて少し教えた。彼女は、正確には発音できないながらも熱心に覚えた。とてもその姿が可愛いらしい。アバディーンで円卓を囲んで昼食。
俺達のバスの中での会話は、日本及び香港に関する事が大部分である。政治、言語、気候、映画など。アバディーンから海岸線に沿ってレパレス湾(浅水湾)に到着。ここは映画「慕情」のシーンにも出てくる香港で最も有名な海水浴場で、後には豪華なホテルが立ち並び、白い砂浜が印象的な海水浴場である。ジュークボックスで歌を聞いたが、日本の歌もかなりあった。例えば坂本九の「上を向いて歩こう」「さよなら東京」など。しばらく1人で海の中に石を投げて遊ぶ。夕方近くなってからビクトリア市に戻り、玉屋デパートの中で自由行動。勿論俺達は数多くの日本製品をその中で見る事が出来た。6時頃YMCAに帰り食堂で夕食を皆と共にする。厳小姐は割とおとなしいので口数は少ない方である。黄小姐は彼女とは対照的でよく笑い早口で話す。
彼女達と映画を見に行く事になり、石川さん、木村そして俺と5人でタクシーに乗り、九龍の映画街へ向かった。外は小雨が降り始めていた。新間は渡辺君そして茨城大学の人と一緒にショッピングに行く為、我々とは別行動。(彼はいろいろな物を買って来たが、ついでにナニの方も買って来たんじゃないかという噂もチラホラ・・・)
さて、僕達が映画館の前に着いた時、偶然、黄小姐の兄さんに会い、一緒に「大殺四方」という中国題名のついた西部劇を見る事になった。日本の映画館との違いは、まず第1に料金が安く、この映画館の入場料は2・80HK$である。次に全席が指定席になっている事。最後に大きな違いは上映中にも喫煙が許されている事である。
中に入ると予告編で日本映画”佐々木小次郎”をやっていた。”大殺四方”は俺達にとって字幕の中国語が良く解らないので、英語から判断する以外に手はない。しかし西部劇であるためストーリーは割と簡単なものであり、結構楽しむことが出来た。9時頃映画が終わり、彼女達と別れなければならない時が来て、厳小姐は俺に日本語で「さようなら」を言ってくれた。石川さんと木村は黄小姐と、俺は厳小姐と別れの握手を交した後、雨の中をタクシーに乗り込んだ。YMCAに帰った時、まだ新間は戻って来ていなかった。木村は石川さんと部屋の中で雑談。俺は1人で屋上に行った。
屋上はまだ霧雨が降っていたが、俺はそこから美しい芸術品を見る事が出来た。夜が暗く香港の海と街を包み、その中に無数の宝石をちりばめた様に美しく輝くフェリーや港の灯、街のネオンサイン、そして暗い山並みを縫うハイウェイのイルミネーション。それら全てが俺をファンタジックな夢の世界へと誘う。香港は全ての面で相反する形容詞を所有している場所であるから、そこを訪れる人々をその人々の気持の持ち次第でどの様にでも演出してくれる。さしずめ今日の俺は、楽しい夢物語の主人公!!その晩は香港最後の夜を心ゆくまで味わった。マカオに行けなかったのが残念!!
2月26日晴のち曇
久しぶりに晴れて、香港で初めての太陽を見る事が出来た。中華旅行社へ行き出航手続を済ませたが、出航が午後の2時になったと聞いて非常なるショック!!何しろ予定より3時間も早くなったので、こっちの予定が完全に狂った。土産を買ってなかったので船に荷物を運んだ後、急いで木村と2人で九龍の街へ向かって走り出す。時間に追われているので、じっくり捜している暇などまるでない。時は既に12時半を過ぎている。1軒の店で全ての土産物を買い、あせって船に戻ったのが1時半であった。昨日、彼女達が今日見送りに来てくれると言ってくれたが、急に時間変更になったため、連絡のしようがないので厳小姐に急いで伝言を書き、石川さん(彼はその後しばらく香港に滞在)に彼女に渡してくれるように頼んだ。やがて船は岸を離れ始め、俺達は石川さんと手を振って別れ「早稲田で会おう」と約束した。船は再び基隆へと向かった。
“再見/香港,東洋の真珠!!!
2月27日晴
相変わらずこの船の飯はまずい。3年間世界旅行をして日本に帰る日本人、や台東に住む人と知り合い、雑談したり、トランプをしたりして、時間をつぶす。夜は10時頃就寝。
2月28日晴30キロ
基隆に着いた。船の中で知り合った人々と別れ棧橋へ行く。入国する時は意外と厳しい荷物検査があった。自転車を受け取るため税関が開くまで食事代りに買ってきたバナナを食べていると、2つの新聞社の記者達が俺達にインタビューしてきた。「何処から来たの?」「台湾訪問の目的は?」「滞在日数は?」「どのコースを走るのか?」「日本でのバナナの値段は?」などとおまけに写真まで撮ってくれた。いくら台湾が現在戦時体制下にあるといっても、俺達位の事が記事になる様では、台湾もかなり平和と言おうか暇と言おうか。ようやく自転車を出してもらい整備した後、台北へ向けて初の台湾ランに入る。道路状態は良好であるが、台湾は(沖縄もそうであったが)日本とは違って、車は右側通行のため、どうも調子が狂う。でも我々は快調にとばし、台北の旅館に帰って来た。夜は3人で市内を散歩。
2月29日晴のち曇
朝起きて、昨日の記事が新聞に出ているのを見つける。日本航空へ行き、トランジットビザの事を聞いた結果、延長出来ないとの事で、どうしても13日迄に離合しなくてはならなくなり、12日のジェットで那覇へ向かうことに決める。琉球海運へ行き、船の方をキャンセルし、また、鹿児島行の「おとひめ丸」の予約を済ませる。中華日報社へ行き、記念の新聞を買った後、台北第1デパートで土産物を買った。夜2時頃就寝。明日からは本格的ランである。
3月1日曇のち晴80キロ
全ての整備を終えて台北を12時半に出発。先頭に木村、真中に新間、最後に俺というフォーメーションを組み、1号線を南に向けてひた走る。舗装路であるこの道はとても素晴しく、木村・新間共に快調である。俺の方は、どういう訳か、初めての比較的長い上りでかなりバテるといった不甲斐なさ。普通だったら別に苦にもならない勾配だが、かなりギヤーを落として走った。途中、新聞の写真を見て俺達の事を知っていた新竹に住む林さんという人が話しかけて来て、彼の家へ今晩泊まる様に勧めてくれたので、御世話になる事にする。林さんはバイクなので、それに合わすため、俺達はかなりのハイスピードランを強いられた。
途中、林さんが卓球を教えている新竹県立第1女子中学校へ連れて行かれ、そこの教務主任や先生方に紹介される。校長室に接待されて菓子やお茶まで御馳走になり本当に感激。日本の学校の事などについて話し合う。ここは新竹県1の名門中学との事で校内には優等生の名前と写真が貼ってあった。台湾に於ける義務教育は国民学校(小学校)までとの事。その上に日本と同じ様に中学、高校、大学とあり、6・3・3・4制度をとっているそうだ。来年から中学も義務教育になるが、強制は3年後との事であった。新間が校長室に早稲田のペナントをプレゼント。その後卓球部の練習場に案内され、レギュラーの3年生を相手に俺と木村が汗を流す。さすがにレギュラーだけあって、その腕前は女子中学生としては抜群。4、5人の部員と練習してから、夕暮れせまる学校を後にして林さんの家へ向かう。着いた時は既に真暗であった。
3月2日曇のち雨60キロ
昨日お世話になった林さんに御礼を言って11時スタート。頭分から左に折れて南荘方面へ向かった。山地へ向かうので道はゆっくりとした上り勾配である。獅頭山のふもとに着いてから自転車を降り、20分ほど階段を上って見晴台へ行く。雨が降り出し、とても寒くなったので下へ戻りパンを食べていると、台湾大学の男子学生3人が話しかけて来たので、十分ほど話をする。雨の降り具合をみていたが、止みそうにないので雨の中を走り出す。帰りはかなり早く頭分に戻って来ることが出来た。全身びしょ濡れ。そこから更に走り、後龍という所で旅館に泊まることにしたら、その家の人がやはり俺達の事を知っていて大歓迎してくれた。バナナを20本ほどプレゼントしてくれて「遠慮なく食べなさい」と言ってくれた。外に夕飯を食べに行き、ある小さな店に入っていると、近所の人達が「日本人(ズーペンレン)!!日本人だ」と言いながら入口に集まって来て、我々を好奇の目で見ている。「冗談じゃねえよ全く!!!日本人だって1億いるんだから、3人位台湾にいたからって不思議じゃねえだろー」
久しぶりに風呂に入ってとても気分が良い。女中さんが「洗濯してあげるから何か出しなさい」と言ってくれたので、ユニフォームとタイツを洗ってもらった。新間は下着まで洗ってもらったと言っていた。彼もかなりいい根性してるよ!!!
3月3日快晴85キロ
目を覚ますと空の青さが目にしみた。今日が本当の晴れという感じである。起床して出発の準備をしていると、この旅館のおばさんが1人の娘さんを連れて俺達の部屋に入って来た。彼女は、駅前のある医者の娘で、兄さんが早稲田に貿易学を学ぶため、留学していると言った。俺達を彼女の母に紹介したいからぜひ家に来て欲しいと言ったので、3人で歩いて彼女の家を訪れた。彼女の母や他の医者と雑談。台湾の人は35才以上の人は皆戦前の日本統治時代に日本語教育を受けているため、日本語が達者である。(俺達位の世代の者は全然通じないが・・・)台湾の人は、とても親日感情豊かであるが、余りに歓迎してくれていろいろな人の所へ連れていってくれるので、俺達の出発時間は常に遅れ、今日も昼すぎになってしまった。いざ出発!!最初のうち長い上りで、おまけに向かい風のため少し苦戦したが、後から追い風になったので、道の両側に木が植えてある1号線を時速30キロ以上でふっとばす。途中、海岸へ行き記念撮影。台中に6時20分着。ドロップハンドルとディレーラーが珍しいせいか、通行人がジロジロ俺達を見る。3人で55元の旅館に泊まる。夕食後市内を歩いてみたが、台北に比べるとかなり狭い市であった。
3月4日快晴60キロ
今日もスタートが11時になってしまった。最初は市内にある台中公園へ行く。池がありボートを漕いでいる人もいた。気温は、かなり高く暑いくらいである。南下して省議会へ。南国色豊かでインドネシア的な感じ。そこで知り合った中興大学の男女学生3人が、またバナナをプレゼントしてくれた。この3日間毎日10本以上食べているので少し飽きてきたが、俺はそのお返しにオレンジをあげた。3人共、大学で初等数学を専攻していると言っていた。中を案内してくれた後、大学の方も案内するから来ないかと勧められたが、時間がないので断わった。中興新村、南投を経て集々に入るといよいよ登りにかかり、薄暗くなった道を走る。でも身体の方は快調で殆ど疲れは感じない。完全にあたりが暗くなった7時頃水裡着。1番安い宿に落着き、入浴後傍に住む林さんという人が、彼の妹が日本に嫁ぐから日本の事をいろいろ話してほしいと俺達に頼んで来たの彼の家に行って談笑。午前1時半頃旅館に戻った。
3月5日快晴70キロ
日月潭(海抜850m)に向けて出発。道のり20キロのうち12キロは上り坂である。相変らず体の方は絶好調。木村が前輪のマシントラブルの為か、かなり遅れる。日月潭は台湾で最も美しい湖との評判だったが、この程度の湖なら、日本にはざらにあると思った。昼食後遊覧船で湖をめぐることにした。新間と一緒に日本へ鳥の剥製を買って送る。3時間程滞在してから水裡へ再び向かう。帰りは下りなので時速60キロの爽快なダウンヒルを楽しむ事が出来た。集々を過ぎるともう真暗になった。ともかく竹山までは行こうと思い、夜道を、つり橋を渡ったりして走った。7時過ぎ竹山着。旅館の主人が我々を歓迎してくれてバーに連れて行き、夕食、バナナ、酒等を御馳走してくれた。近所の人々やホステスを含めて10人以上も集まり、ちょっとしたレセプションである。新間の横にいたホステスが城卓矢の「骨まで愛して」を歌った。台湾では現在この歌が流行しているらしい。俺達に何か日本の歌を聞かせてほしいと言ってきたので、御礼代りに俺が流しの人から借りたギターを弾き、新間と木村と3人で「ブルーシャトー」と「世界は2人のために」そして最後に早稲田の校歌「都の西北」を歌った。台湾の人は皆親切で本当にうれしい。
3月6日快晴130キロ
朝9時、昨日のカメラ好きの人や地元の新聞記者達が来て、俺達3人の写真を撮ってくれた。そしてたくさんの爆竹を鳴らしてくれた。台湾では、これを歓迎や祝賀のしるしとしている。皆で徳山寺という尼寺に行った。菓子や台湾のモチをいただく。竹山に戻りパパイヤ(台湾では亡果(モッカ)と呼んでいる)や砂糖きびの汁を御馳走になる。とてもうまい!!台南へ行く途中まで、皆バイクに乗って送ってきてくれた。俺達は皆にお礼を述べた後、再び1号線を南下した。以後、嘉義で20分と途中20分休んだ以外は、ひたすら走った。自動車から手を振ってくれる人には、手を振って応えた。6時20分台南着。さすがに南である。台湾に来て初めて蚊に刺された。夕食は市内の屋台でラーメンを食べた。後輪フリー側のスポークが2本折れているのを発見!!:
3月7日快晴50キロ
昨日気が付いたスポークを直すため、ギヤー及びフリーをはずして30分程かけて新しいスポークに取り換える。市内にある赤嵌楼へ行った。名前の通りの赤い建物で、1650年にオランダ人によって建築された物らしく、中には歴代の文書などが陳列されてあった。韓国の紳士と一緒に記念撮影。台南を出発して高雄へ向かった。とても暑く、途中で冷したパイナップルや氷などを食べる。道行く人々も皆、半袖かノースリーブである。高雄に入る前、道路が工事中のため路が悪くなり、その衝激で再三チェーンが外れる。市内に入った時、早大の先輩の洪さんという人に話しかけられる。彼は日本に留学に来て法学部に在籍していたと言う。ボクシング部にいたためか、腕が太くかなりごつい感じだったが、とても親切な先輩で、我々に夕飯をレストランでおごってくれた。彼は現在、高雄鉄道病院の外科主任医師で、俺達に病院でよかったら泊まりなさいと勧めてくれた。
洪さんの後輩の人に連れられて市内の公衆浴場に行く。台湾に来て初めて公衆浴場を経験したが、日本とはまるで違い、個室になっていて仰向けに寝て湯につかる型のものだった。10時半頃木村と2人で再び市内見物。台北に次ぐ台湾第2の大都市だけの事はある。夜も遅かったが、人通りは結構あった。暑いのでふとんなしで眠ることにした。
3月8日快晴65キロ
連日の快晴続きで顔や手足が日に焼けて真黒。日本を出発してから1度も剃っていない無精ヒゲのため、まるで熊みたいになってきた。8時に起床してから洪さんと朝食を一緒にとる。新間が胃の調子を悪くして下痢をしたため、高雄に残ると言い出した。11日台北で再会する約束をして、木村と俺と2人で一路最南端を目指し高雄をスタート。洪さんの紹介で屏東の中華日報社の林さんの家に寄ったところ、またまた歓迎され、ぜひ今晩は泊まる様言ってくれた。我々は先に進みたかったが、折角の好意を無にするわけにいかず、お世話になる事にする。親類の人が三地門に連れていってくれると言ったので喜んだ。彼はオートバイ、俺達は勿論自転車で行った。三地門はとても景色の良い所で、長いつり橋を渡ったり川におりたりして思う存分楽しんだ。帰りは、かなりふっとばし18キロを30分で戻って来た。彼が俺達をボーリングに誘ったので行ってみると、ここのはセットするのもボールを返すのも全て人間がやっていた。台湾には「婦人の日」という日があり、今日3月8日がこの日にあたる。夜はレストランで林さんの家族や、奥さんの知り合いの人達7人と夕食を共にする。俺も木村もかなり酒を飲まされて参った。林さんの経営するホテルに泊めさせてもらい、久しぶりに風呂で洗濯。蚊がものすごく多い。
3月9日曇1時晴のち雨110キロ
午前9時、最南端の総鑾鼻に向け出発。曇り空ではあるが、コンディションは上々。しばらく行くと、道の両側にバナナ畑のある田園風景が展開される。交通量も非常に少くなったので道路の横で1時間ほど昼寝。枋楓を過ぎ海岸線に沿った道に出ると、地元の人が言ってた通り、風が強く吹き始めた。向かい風になったり横からあおられたりして惨々な目に会う。風の強さは今回のランで最大のもので、前を自転車で走っていた人が吹き倒されたり、木村が1度上った坂を、強風にハンドルをとられて下まで吹き戻されたりして傑作なシーンが相次ぐ。途中、林さんがくれたパンと洪さんからもらったパインの缶詰を食べる。カン切りがないので、ドライバーと石を使って開けた。だんだんと野蛮になってくる。恒春で夜食を買い入れた。
空はどす黒く厚い雲に覆われだし、雨の到来を予告している。鸞鑾鼻に着く9キロ前で舗装路が切れ、道に砂が混じり始める。とても走りにくく何回もタイヤをとられそうになった。遙か左前方に最南端の灯台の灯が見え出した。あそこまで行けばいいと思いながり進むが、なかなか着かない。悪戦苦闘する。6時半頃ようやく到着。既に暗くなり雨が風と交じって強烈に降り出す。でもこれで台湾を縦走した。感激!!最南端でテントを張りたかったが風と雨が激しく、残念ながら断念する。灯台の前にある土産物店の長椅子の上で寝袋に入って寝た。香港の想い出がふと俺の脳裏を過ぎる。
3月10日晴
朝6時起床。自転車を分解して輪行袋につめる。記念にスタンドを最南端の海岸に置いてからバスで台東に向かう。長い間搖られて夜6時半台東着。荷物があるため、木村と交代で夕食を食べに行く。市内で台湾のメキシコ5輪の選手達4人に話しかけられて、しばらくスポーツの話に花を咲かせる。花蓮行の列車が午前0時5分なので待つが、相当長く感じられ再び飯を食べに行き、バナナを20本ほど買い込んだ。
3月11日晴18キロ
列車に乗り込んだ。最後尾に行ったが扉がない。なにも敷かないで床に横になる。風呂に入っていないのでかなり薄汚なくなったが、だんだん感じなくなってきた。まるで浮浪者。この列車はディーゼルカーである。しばらくすると冷え込んできたので、前の車両に移って眠った。5時40分花蓮着。駅の待合室で寝袋に入って眠っていたら、1時間位して警官に起こされてしまった。
観光バスに乗って太魯閣へ向かう。さすがに東西橫貫公路は素晴しく、北海道の層雲峡のスケールを更に大きくした様である。天祥の手前で折り返す時、運転手に頼んで太魯閣まで自転車で走ることにした。組立てには20分もかかってしまった。キャリアー、マッドガードなど余分なものは一切付けていない。快調にバスと競走。ゆっくりした下り坂なので最高のスピードが出せる。後からバスが俺達を追いかける。太魯閣の横貫公路ゲートまでの18キロを平均時速50キロで走破。ゲートに12時15分着。後について来たバスから荷物や輪行袋を受け取り、運転手に礼を言って、すぐ自転車を分解し、12時30分に来た蘇澳行きのバスに危くセーフ。何しろこれに乗り遅れるとヒッチハイクをしない限り、台北に今日戻ることが出来なくなる。必死になって走ったので中で汗がだらだら出始める。
東海岸の蘇花公路は噂通りの切り立った岩壁に沿って走るスリリングな道である。窓から顔を出すと100m以上も下に海岸線を見る事が出来る。もっと日数があれば是非走ってみたかった。蘇澳から観光特急列車に乗る。中にはスチュワーデスがいて待遇はとても良い。お茶を出したり、おしぼり、新聞など。午後7時、10日ぶりに台北に帰ってきた。旅館に戻ると、おばさんと新間が出迎えてくれた。日本の友達から送って来た手紙を読み、楽しい憩いのひとときを過ごす。夜は新間と2人で最後の市内見物に出かけた。木村は眠いといって旅館に残る。
3月12日曇4キロ
いよいよ今日で台湾ともお別れである。荷物の整理をした後、旅館のおばさんに別れの挨拶と御礼を言う。タクシーで台北国際空港へ行き、空港で残ったNT$を使う。銀製の小さな舟を買った。
出発が少し遅れ、午後2時55分日航のコンベア880型ジェット機に搭乗した。シートベルトを締めていよいよ出発。爆音を残して離陸すると家などがみるみるうちに小さくなる。下は曇っていたが雲の上に出ると青い空に太陽が輝き、とてもきれいだった。雲海も印象的。スチュワーデスが紅茶や軽食を運んだりしているうちに、もう「シートベルトを付けて下さい」というアナウンスが機内を流れる。行きには船で2日間もかかった距離を僅か1時間余りで飛ぶのだから全く速い。それから20分位して沖縄那覇空港着。税関の検査を簡単に終えた後、再び自転車を組み立てる。木村はタクシーで先に春海YHへ。新間と2人で走って俺達は15分後に到着。夜は3人で国際通りを散歩した。
3月13日快晴88キロ
最後のランを祝してか全く絶好のサイクリング日和となる。木村はバスで回りたいと言うので、新間と2人で沖縄中部へ向かって走り出す。俺の足の調子は今日が最も良い様に思われる。今日は晴れているので海の色が真青であり、その美しさは、どう表現してよいか解らない程だ。こんなに純粋な青を見たのは生まれて初めてである。沖縄には鉄道がなく、交通機関の重要なウェイトを占めるのがバスであるから、道路には多くのバスが頻繁に走っている。嘉手納米軍基地はとても広く、B52などの戦闘機が黒い機体を横たえている。全く爆音がうるさい!!!基地を右に見ながら進みホワイトビーチへ向かう。砂浜のロマンチックな海水浴場を想像していたが、行ってみると大違い。ここもやはり米軍の軍事基地であった。ふざけるな!!しばらくポタリングをした後、普天間の神社へ行き、そこの鍾乳洞へ入った。中城公園はなかなかイカしていて、城跡からの見晴しはとてもよい。中に動物園があり、しばし彼達(彼女?)と戯れる。5時半頃中城公園を発って那覇へ。これが最後のスピードランと思い時速35キロで力走する。とても苦しく那覇のYHに戻った時は極度にバテていた。夕食をして入浴後、木村と一緒にYHの前にあるボーリング場に行き、ゲームを楽しんだ。
3月14日晴
朝8時起床。那覇港へ行き諸手続きを済ませ、11時頃乗船。今日の乗船者は非常に多い。「おとひめ丸」は今迄のうちで1番素晴しい船である。広くて中もきれいである。12時ジャストに出航。岸壁の見送りの人と船客とを結ぶテープがすごく多い。俺ももらったテープを、3個ばかりドサクサに紛れて、でたらめに投げた。出航後しばらくは甲板にいたが、少々風邪気味のため早く床に就く。
3月15日曇
朝6時起床。すぐ甲板へ出てみると懐しい九州の佐多岬や開聞岳が目の前にあった。思えば1ヶ月ぶりの帰国である。苦しみや楽しみも多く、また我々の視野を大きく拡げてくれた走行距離約1050キロの海外ラン。この有意義だった旅行も、もう終わりを告げようとしている。
帰宅は新間と木村が16日。俺は途中、井原と熱海に寄ったので21日であった。
軽井沢-名古屋 hi-lite – 法学部1年 堺
軽井沢-名古屋 hi-lite
法学部1年 堺
ハイライトといっても、勿論タバコの話ではない。軽井沢から名古屋まで2泊3日で走った。そして、この原稿を書いてみると、随分と長編になってしまった。そこで短縮の手段として、ハイライトとして書こうと思いたったのだ。ハイライトといえば、何といってもやはり第一日目の軽井沢 – 上諏訪だろう。ここのところを重点的に書こう。しかしだ。2日目、3日目もなかなかよかったんだ。ひょっとすると、この策は有効じゃないかもしれない。そんな不安が脳裏をかすめる。とにかくこのコースは、どこをとっても素晴しい景観と紅葉にめぐまれていたのだから・・・
軽井沢合宿のあと、渡辺と僕は名古屋まで走ることにしていた。合宿のあと、どこかにプライベートランをしたい。名古屋に僕の親類が住んでいる。2つの単純な理由であった。
11月2日朝、
合宿は軽井沢友愛山荘YHで解散になった。いよいよ出発。ここで、主将の加藤さんが以前行った白樺湖をまた見たいというので、最初の宿泊地諏訪湖YHまでご一緒することになった。また、2年の木村(治)さんも、夏合宿のケガで自転車には乗ってきていなかったが、同じYHに泊まることになり、ひとまず、木村さんはバスで白樺湖へ行ってそこで3時頃落ち合うことにし、10時半3人は友愛山荘をあとにした。18号線から旧中山道に入る地点で、早くも暑くなり、ユニホームと短パンになる。前日のポタリングコースを逆に走って、佐久市で昼食をとる。入った食堂の昼のテレビニュースが有馬温泉の火事を報じていた。
12時半頃食堂を出て笠取峠まで20キロを目指す。この間の収穫を終えた農村風景は、とてもすばらしかった。盆地部というには少し傾斜があり、山間部のというほどには、深く入った訳でもないちょうどその中間の、ゆるやかな丘陵といった感じのところに、いわゆる畑や水田が広がっていた。『こんなのが、いわゆる日本の農村の情緒かな?』と思う。
峠とまではいかないが、結構手応えのある丘をいくつか越え、下り、また上る。丘にあがると、右手に秋の収穫を終えた水田や畑が黄金色にずっと遠くまで、明るい陽光に映えて広がっている。遠くに近くに、農耕機械を使って農家の人達が気持よさそうに仕事をしている。千曲川の向こうの山並みは白く霞んでいるが、それがまた、ポカポカとしたのどかな雰囲気をかもすのにふさわしい。いかにも平和な図だ。このあたりは、大昔からこんな秋を送り迎えしているのだろう。そんな事を思うと、あまりに、穏やかで、平和で、のんびりとしていて、気が遠くなりそうである。
丘と丘の間には、あまり大きくはないが、街道沿いに、きちんと軒をつらねた、古い建物の多い町があった。「こんな所に、こんな町が!」と思ったほど、小さいけれども、こじんまりと、まとまっていたのが印象的だった。かなり、歴史的に古い町のように思う。中山道ができた、江戸時代からの町かな?この日は土曜日だったので、午前中で授業を終えた中学生か高校生が、そんな町のうちの1つの入口のバス停で、バスを待って大勢並んでいた。他の日本中の多くの生徒と同じように、あたりまえに学生服を着こんですましている彼らと、この町の対照が、どことなく奇妙で、ほほえましく、おかしかった。この生徒達を乗せたバスと僕達は暫くの間前後し合って走った。
このあたりの男子高校生の間では、オートバイを乗り回すのが流行らしく、何台も僕等の後から、あるいは前から、スピードを上げて、追い越して行き、すれちがう。僕らはせいぜい時速20キロである。ゆっくり、着実に、明るい陽を浴びて走る。豊かで、のどかな風景は、都会の雑踏や喧噪がうそのようだ。
笠取峠の手前で、舗装は切れていた。上りは、薄く砂を敷いたような道で走りにくい。かなり汗はかいたが、距離的に短かかったのでなんとか上った。峠には、笠取峠と書いたバス停があったが、切通しになっていて見通しがきかない。とりあえず、出すものを出し、汗をふき、写真を互いに撮って、早々に峠を下りにかかった。50m程下って、パッとひらけた展望に目を奪われた。道は、まるですり鉢の底におりて行くように、急傾斜で下っていた。そして、そのすり鉢状にまわりをとりまいている山々がすっかり美しく紅葉しているのだ。あまり大きくはないが、まっすぐ伸びた木々が密生している。その山々に山吹色から赤褐色までの無数の色彩が展開しており、とにかくきれいなことといったらこの上ない。いかに形容しても形容しきれず、形容の言葉を重ねれば重ねるほど、ある実際の美しい眺望を伝え切れぬ焦燥をおぼえるばかりだ。「10月下旬から11月初めにかけて、笠取峠に行ってごらんなさい」というのが、最も確実だろう。ここでもカメラのためにストップして時間を食った。急な下りをおりるとすぐ長久保に着いた。いよいよ大門峠があるので、長久保でバンを食べて腹ごしらえをする。
午後2時だ。峠まで18キロ。木村さんとの約束は3時である。長久保を出ると舗装で、緩い上りを加藤さんは飛ばし始めた。「ああ、これなら行ける行ける」加藤さんは楽観的見通しでそう言った。けれども、実際はそんな甘いものではなかった。少なくとも渡辺と僕にとっては。それにしてもあんな難行になるとは、夢想だにしなかった。まもなく舗装は切れ、じわじわと上りもきつくなった。まわりの景色はすばらしい。天気もまさにサイクリング日和。しかしそれどころではなくなった。
砂利道で、しかもところどころソロバンになっている。自転車が重い。しかし、加藤さんはそれほどでもないらしく、もりもり上って行く。渡辺と僕は、必死になって、また、それしか仕様がないので、とにかくついて行く。砂利道が恨めしい。「舗装だったら、ちよっとくらい長くても、急でも、何とか上るのだがなあ」「休みたい」「バンクかマシントラブルでもないかなあ」よろしくない考えが頭をかすめる。重いペダルを踏む。ちっとも距離がはかどらないように感じられる。まあ、こうしていればいつかは峠につくだろうが、そしてそれは確かだが、更に続く苦しさのことを考えたら・・・気が重い。
かなり行って、ヘアピンカーブでしかもグッと傾斜がきつくなっているところが見えた。僕は絶望的になった。加藤さんが、20メートル程先でそのヘアピンをもりもり上って行くのが見えた。僕は、渡辺のすぐ後を走っていた。
『渡辺、どうするのかな?降りてくれないかなあ。それとも上ってしまうのかな?それなら仕方がない、ついて行くしかないや』などと思いながら進むと、ヘアピンカーブの手前で、ヒョイと渡辺は降りた。「助かった」とばかり、間髪を入れず、僕もヒョイと自転車を降りた。やっと休めた!!ほっとした。ほっとしたけれど、これは事の全面的解決ではない。先の事を考えると、またすぐ憂うつが僕を重い気分にした。50mほど押して上がると、脇に家があったので、そこで止まり、水をもらうことにした。渡辺と水を飲んでいると、上から来たバスと下から来たバスがすれちがう為に手間どっていたので、それを理由にいましばらくの休憩時間を貪った。バスが行ってから、ふとあたりを見回すと、素敵じゃないか!道の左側に、夏季合宿の時、層雲峡でみたような、露出した岩の絶壁が迫っていて、なかなかの見ものである。それをバックに「撮ろうか」。2人とも上る気をなくしてしまっていた。
それでもなお、僕達のすべき事は、ただ上る事だけだ。義務的に上り始めた。再びいやな砂利が続くが、幾分傾斜は和らいだ感じである。しばらく行くと、観光バスが10台近く続けざまに下って来た。土埃りをいやというほど浴びせられた。いまいましいには違いないのだが、為すスべもなく、サイクリストの悲哀をひしひしと感じつつも、やせ我慢的サイクリストの誇りが僕をして、バスを無言でやり過ごせしめる。さらに砂利道をあえぐ。背中はグッショリ。
『おや傾斜が緩くなった』『あっ平らだ!』普通、平地でも砂利道はいやだけど、この時の何とありがたかったことか。向こうから加藤さんがやって来た。「おや、峠はもうすぐかな」かすかな期待を抱く。「20分待ったけどよう、あんまり来ないから道でも間違えたかと思ってさあ」余裕のある加藤さんの顔が美しかった。峠はまだだった。また、ゆっくり上りはじめる。
峠を越えたらバッと白樺湖が見えるはずだから、道が曲がるたびに、今度は見えぬか、今度こそは、と祈るように期待したけれども、そのたびに空しいものに終った。かなり陽が傾いてきて、少し空気が冷たくなって来た。高度もあるんだっけ。しばらく行くと左側がパッとひらけた。かなりのパノラマだ。道がずうっと1キロ程左にまわり、またそこから蛇行して上っている。すると反対方向から男女20人程の、どこかの大学のワンゲルらしい人達がおりて来た。こっちは背中にWASEDAの文字を背負っている。やはり何となく意識してしまう。あまりバテたような顔も見せたくない。近づく。すれちがう。努めて余裕のありそうな顔をして「こんにちは」と声をかけたが、むこうにはどんな風に見えたことか?そこから2キロ程で峠だったが、最後がまたまたきつい上りで、おまけに砂を敷いたような道で、その上りにくくバテたことと言ったら。2度ほど降りた。
大門峠だ!
来た道をふり返ると、1,442mという高さだけに眺めも雄大だ。上る途中に見上げた山が、下の方に見える。ゲンキンなことに、峠に着いてしまって眺め返すと、上り切った喜びの方が先に立ち、途中の苦労もすっかりどこかに吹き飛び、フッと笑いがこみ上げてきた。「峠っていうのは、いいもんだな」などと。実際、峠に立つとその瞬間、それまでとはガラッと気持が変わってしまうのだから、サイクリングというのは、おかしなものだ。
例によって記念撮影。時計を見ると4時半。あたりは夕闇迫り、日暮れの気配が濃厚だ。18キロを2時間半かかった訳だ。今までで、1番きつい峠だった。全くバテた。それでも加藤さんは、「これくらいなら、1回も休まずに上れるな」などと言っていた。やはり違う。それはそうと、峠からはすぐ白樺湖がある。木村さんが待ちくたびれているはずだ。
白樺湖は、周囲2 – 3キロの小さい湖だった。時間が遅いせいか、シーズン・オフの為か、湖畔は閑散として、女の人が3人チラホラ見える程度だった。加藤さんは、どこに向かっていうでなく、「木村!木村!!」と大声でどなり、あたりを3人で捜すと、湖畔の大きな、観光みやげ屋・レストラン・ホテルのくっついたようなモダンな建物から、木村さんが現われた。かなり待ちくたびれた様子だった。そこで食事をとっている間に、外はすっかり暗くなり、湖をよく見る事はできなかった。残念!
木村さんはバスと電車を乗りついで、僕達3人はナイトランで、再び上諏訪駅でおち合う事にして別れた。渡辺はダイナモがなく、加藤さんは小さい懐中電灯だったので、僕が先頭で白樺湖をあとにした。山の中の夜道で、下りだけとはいえ、道路に電灯などは1つもなく、ちょっと気味が悪かった。暗いとどれくらい進んでいるのか分らず、勝手が悪いものだ。闇の中をかなり飛ばして、上諏訪に着く。さすがに精密機械工業で栄えている町らしく、賑やかな町で予想以上の繁華である。ここで、YHのある場所が分らず、1度下諏訪まで行き、また、戻るなど余計な時間を食い、結局、YHには8時頃たどりついた。諏訪湖YHは、古い昔の建物をホステルに使っており、なかなか趣がある。夕食は出ないので、白樺湖のスパゲティーが、この日の晩飯という事になった。今までで、1番きつい峠を上ってバテているのに、これはまた、ついていない。近くに食堂はない。仕方なく、ペアレントのおばさんがむいてくれた柿やお菓子をガツガツ食べる。入浴し早々に寝る。
11月3日
この日も上天気。これからあとは、全舗装で特に苦しい所もなかった。印象に残った所を書きとめて行く。
諏訪湖YHの朝食は、上々であった。下諏訪駅で、加藤さん、木村さんと別れ、いよいよ、渡辺と2人で名古屋を目指す。
下諏訪を出て、すぐ塩尻峠がある。峠の上り口のドライブインの裏でタイツを脱ぎ、アンダーシャツも脱いで、用意万端整えて、上りにかかったが、15分程で、しかもサードで苦もなく上ってしまった。「こんな上りなら、いくらつづいても楽だな」と語り合う。前日とは全く対照的だった。あいにく、諏訪湖は霞ではっきり見えなかった。峠から塩尻までは、まさに快適なダウンヒルを楽しめ、爽快であった。
塩尻から19号線に入る。きれいに紅葉した山を両方に見て、川に沿って気持良く走る。渡辺と何度も「いいなあ!」「きっれぇだなあ!」と言い合ったが、本当にいくら言っても言いすぎない程素晴しいのだ。同方向に走る高校生らしいサイクリストが2人いた。体は僕等よりずっと大きいのに、何ともない坂を降りて押していた。あまり乗っていないんだなと思い、少々優越感を味わった。
鳥居峠は1,000m以上なので、ちょっと大変かなと思ったが、案ずるより易し、ちょっと上ったと思ったら、目の前に『鳥居トンネル1,045m』の表示が見え「あれ!」と拍子ぬけしてしまった。トンネルができて楽になったらしい。トンネルの中では、工事中らしく一方通行で、片方の入口に並んだ最後の車に、白い直径50センチくらいの輪を持たせて、それを一方の最後尾の車の印として交互にトンネルを通っていた。係の人に聞くと、トンネルの長さは1キロ位ということで、向こう側の入口が暗いオレンジ色に見える。僕の自転車のライトがつくので、僕が前になって最後の白い輪をもった車のうしろについたが、何しろ相手は自動車、だんだん離れる。それでも必死になって走った。トンネルの真中あたりに来た時、あろうことか、頼みのライトが消えてしまった。球が切れたらしい。本当に焦ってしまったが、とにかく、向こう側の車が入って来る前に、トンネルを出なくちゃというわけで、焦りに焦って、ボンヤリ薄暗い、丸い出口へ突っ走る。あと50m位の所で、ヘッドライトをまぶしくつけた大型トラックが入って来てしまった。トンネルの壁にへばりつくように横に寄ると、向こうも気がついたらしく、よけてくれて、なんとか出られた。全く胆を冷やした。
鳥居トンネルを出ると、国道19号線はいよいよ木會川沿いに走る。木曾の棧、寝覚の床、その他「きれいだ!」と思った所で何度も止まり写真を撮ったものだから、すっかり予定より遅くなってしまったけれど、それ程木曾の流域は良いといえる。道路もよく、景色も素晴しいので、気持のよいサイクリングができた。中津川へは6時頃着き、駅の近くの大野屋という旅館に泊る事にしか旅館の風呂は小さいが、なかなか凝っていた。風呂の鏡で、改めて自分の顔がずいぶん陽焼けしているのを見て驚いた。11月の初めにこんなに焼けるなんて!考えてみれば、軽井沢合宿から連日絶好の快晴が続いたもんな。これも日頃の精進が…
11月4日
名古屋まで90キロ余。またまた今日も快晴。恵那峡へ足をのばす。どこかの洋裁学校か何かの女性が、2、3台のバスでワンサと来ていたが、渡辺・堺の両紳士は、そんなものには目もくれず、否、未練がましい一瞥を与えるにとどめ、専ら自然美を堪能した。
恵那市で昼食をとり、一路名古屋へ。このコースは、意外と非常に起伏に富んでおり、また多治見までは向かい風で、進みはあまりはかばかしくない。多治見・名古屋間30キロは、途中、内津峠という小さな峠があったが、1時間15分で走り、今度のランで最も快調に飛ばせた。内津峠は予想していなかったので、ちょっと面くらったが、この峠にかかる所で、僕達の前、50m程を走っていた大型輸送トラックが、路肩からはずれて左側の空地へユラーリと横転した。何か高速度フィルムを見ているようで、一瞬信じられなかったが、運転手が倒れたトラックの窓から飛び出て来て、後から来た車を止め、「無茶な追越しをかけられたんだ。追いかけてくれ!」と血相を変えて、その車に乗って追いかけて行った。
多治見・名古屋間の道路脇には、やたらと「即死事故現場」の立札が多かった。最後を気持よく飛ばし、ともあれ、僕らは無事名古屋へ入った。天気よし、景色よしで最高のランだった。自然の美しさにこんなに魅せられたのも初めてだった。
さてさて、文頭の心配が的中したらしい。短縮しようと努めたけれど、結局、先に書いた原稿と大して長さは変わりない。言ってみれば、やはりこのコース全体がハイライトだったのだろう。
サイクリング徒然草 – 理工学部2年 木村(治)
サイクリング徒然草
理工学部2年 木村(治)
私とサイクリングの出会いはこうだ。高校3年の夏の日に、実家(栃木県)で、何んの意図もなしに普通の実用自転車に乗って遊んでいるうち、ふと何を思ったのか、宇都宮まで行ってみようと思い立った。(宇都宮市と実家のある馬頭町の間は約40キロ)
元来から冒険や旅の好きな性分と、子供の様な好奇心とがそうさせたのだろう。今はやりのハップニングだ。実用車で往復80キロの道のりは、かなり厳しかったが、汗とほこりで真黒になって帰って来た時の沸き上がる征服感が、例えようのない喜びとなった時、これだと内心喝采したものだった。次の瞬間には、すでに自転車旅行という事を考えていた。大学1年の夏休みに、鹿児島から東京まで自転車で旅行しようと決心したのも、実はその時なのだ。
人間誰しも、一定のワクにはまった生活が長びくと、様々な手段を使って、その生活―「生活のサイクル・トランスポーティション」とでもいおうか―から脱出を試みたいと考える。要は、その人の「新しい生活」創造に対する、勇気の有無だろう。創造には、紙一重で、栄光と危険とが共存している。現今、偉人として尊敬されている先人の創造の歴史を、ひも解いてみれば明らかだろう。すなわち、創造への生活行動が、自からをのっぴきならない窮地へ追い込む危険を、常にはらんでいるからだ。
しかし、私はあえてその創造への生活行動を好む故、サイクリングとの出会いは、絶好の材料となった。未来を容易に予測できる様な、サイクル・トランスポーティション的生活次元から、いわば、…彗星の如き行動性によって生活を多次元化する一要素を、サイクリングは我々に提供し、そこからはい出す機会を与えてくれる様に思われたからだ。
42年4月、T大学入学の夢は敗れ、やむなく早稲田の杜に来た時も、本格的ツァーサイクリングの夢は消えなかった。5月半ばの頃だったか、ふたつのサイクリングクラブがあるのを見つけ、入るように事を運ぶことにした。当時、あの薄暗い商学部地下に足を踏み入れて以来、そこにひとつの「島」ができ、今日に至っている。あの時、確か品田、守谷、板橋3先輩がいたと覚えている。品田さんの人柄の良さに、何んとなくとりこになって即刻入部を決意する。私の学生生活にWCCが猛然と割り込んで来た。
合サイ、1泊ラン、オープンサイクリング、奈良・京都で行なわれた早同交歓会など数々印象に残るクラブランを経験してきたが、夏休みにして、前から夢にしていた本格的ツアーサイクリング(鹿児島→東京)が実現し、サイクリングの醍醐味を味わう。
初めてのクラブコンパ(正直いって、第1印象はあまりいいものではなかった)で、木村(淳)さんと意気統合、鹿児島―東京ツァーの計画は万事OKとなる。ところが、あとで他の人に聞いたら、彼はクラブでも1、2の強脚ということで、果たして経験の浅い私がついていけるか心配だった。しかし、どうにか、無事に3,200キ口を25日間無休で走破し、東京に舞い戻ることができた。
鹿児島、長崎鼻、佐多岬、桜鳥、霧島、日南海岸、宮崎、延岡、高千穂、別府、山なみハイウェイ、阿蘇、熊本、天草、雲仙、長崎、佐世保、唐津、福岡、関門トンネル、秋吉台、岩国、広島、呉、松山、高松、鳴門、淡路島、神戸、京都、鈴鹿、伊勢、伊良湖岬、浜松、御前崎、富士宮、山中湖、国道20号線、東京という鹿児島県庁前から都庁までのコースは、計画当初とやや短縮されたが、満足するのに充分なコースだった。全日程中一日だけ雨で、あとは快晴の好条件の下、木村さんの好リードで一日平均120キロのペース。まさにツァーサイクリングそのものを経験した。中でも、九州はサイクリングのメッカともいいたいくらい、格好の場所との印象を強くした。やはり夏がいいだろう。ハイライトは山なみハイウェイだ。雄大な大観美の中を進むハイウェイは、実に愉快にしてくれる。なぜ、もっと早くこんな旅行に遭遇しなかったのだろうと思ったくらいだ。
木村さんに引っぱられながら、止まる所を知らないくらいに、毎日よく走った。霧島登山では人間の限界も知った。おかげで九州を出てからというものは、すべてトップギャーオンリー。無論、鈴鹿峠も大垂水峠もギャーチェンジなしで走破してしまった。慣れとトレーニング如何ではころも強くなるものかと、今考えてみても驚かされる。もちろん、今大垂水まで行って、トップギャーで上ろうとしても、馬鹿らしさも手伝ってやる気はしないだろう。
とにかく、「経験」というものを大事にする私にとって、非常に充実した「経験」をした。今でも地図を見るたびに、その日その日の事が、備忘録の門をはずしてありありと目に浮かんでくる。
いつでもそうであるが、サイクリングでは自分との戦いに終始する。つまり、およそ正反対の性格をもったふたつの「自分」が、常に内部の葛藤を起こし、両者をコントロールする技を、外部の「自分」に要求してくるわけだ。それが特に峠などにかかると、一層その戦いは尖鋭化をみる。より以上の精神力を養成してくれるのも、こんな時と思われる。各々の持つ精神力の限界には、内部の両者間に妥協があってしかるべきだが、それまでに起こる人間本来の「葛藤」という精神行動を通じて得る精神力、根性は大きい。
すなわち、「サイクリングは常に孤独だ」というより、サイクリングによって(ひとつの手段にすぎないが)我々は孤独になり、日常生活の「サイクル・トランスポーティション」から脱し、自己精神修養の場が多かれ少なかれ提供されるということだ。
苦しい山道を、峠を上りつめ、疲労困憊しても、大自然が作る大観美を前にすれば、今までの苦しみは忘れ、征服感、幸福感にひたり、当事者のみしか分らぬ喜びが沸くものだ。だから、もし連れがいた場合、言語はつつしむ。沈黙が最良の「ことば」だ。なぜなら彼もまた、自分と同じ様に征服感、幸福感をかみしめているゆえ、つまらないことばで、それを劈くことを恐れるからだ。そんな時、決して相手のとりこになってしまっては、全てがだいなしになってしまう。
今使っている自転車に乗り始めてから、約8000キロ走破している。実は、今度の北海道合宿後、東北を遊走し、1万キロ走破を目ろんでいたが、不運な事故のおかげで、だめになってしまった。
その間、東京近辺の目ぼしい国道はたいてい走ってみた。1ヵ月に1度は通る20号線(甲州街道)、しつこいばかりに上り下りの多い国道246号線(厚木街道)、それの大型スケールの6号線(水戸街道)、逆にほとんど平らな4号線(奥州街道)、東京湾を囲む環状線の国道16号線、京浜、阪神間の大動脈国道1号線。誰しも経験すると思うが、東海道の名所、由比・蒲原には恐怖を覚える。自転車などひっこんでろといった調子に、実に狭い道路1ぱいに、蟻を踏みつぶさんとする巨象の様に、それこそ10数トンもあろう産業大型車が、自転車をかすめて通って行くからたまらない。サイクリストにとってはまさに生地獄である。いつも思うのだが、これだけの重要産業道路を、せめて3車線位になぜ広げないのだろう。
昨年の日本半縦断の際知ったのだが、もし東海道を走ることがあったら、次のルートを走ってみるのも良いかと思う。国道150号線で、静岡から御前崎を経由して浜松にぬける道路だ。近年全舖裝になったばかりの国道で、東海道を通って静岡 – 浜松を走るより距離はやや長いが、交通量が非常に少なく、安心して走れる利点があるから勧める。入口は例の静岡市内の安倍川にかかる大橋の下からで、南にのびる国道である。
クラブにマージャン風が吹きすさぶ冬に入り、学年末試験の真最中、海外遠征の話はまとまった。ひとつ国を出るのに、こんなにも煩雑な手続きが必要なのかと改めて知る。試験中でもあるので、なんとせわしい毎日であったことか。雪の降る日、青山にある琉球政府のビザ発行所に、午後からある試験を気にしながら行ったのを、今でもはっきり覚えている。パスポート、検疫証、ビザ、チケットと外貨など、外国旅行に必要な書類、手続きが済んだのは、なんと出発当日というあわただしさ。
約1ヵ月の沖縄、台湾、香港への旅行日程は、充分だったとはいえないが、自転車旅行という特殊条件の下でしか得られないと思われる貴重な体験をしてきた。(旅行の詳細は、別記を参照してもらえたらいいが)
1ヵ月ぶりで出発した時と同じ鹿児島港に着いた時、やはり帰国の感動は自分なりにあったが、どういうわけかすぐに虚脱感もあった。慣れない生活環境から解放された安心感が、1度に沸いたに違いない。日本を離れ、異国の中での日本人として、日本を見る機会を得ることができたことは、非常に幸せであった。この旅行で体得した貴重な経験を、将来いかに有効に使うかは、私に課せられた今後の問題だが、前述した様に、サイクリングでしか得られないだろう体験を通しての知識が、国際的感覚、国際的視野を拡大したことも事実に相違ない。
香港で知り合ったS壊から手紙が届くたびに、時の流れに驚きつつ、当時の珍道中が面白おかしく思い出される。
今度のような全治2ヵ月ものケガをしたのは、勿論生まれて初めてのことだが、実に小事が大事を生んだ。悪運にとりつかれた者はみじめである。2度と再びこんな目に会わない事を願うのだが….
私は運命というものを信じる1人である。以前は、真摯な態度で「運命」というものを理論化しようと試みたことさえある。その内容はとてもここでは説明しきれないが、そんな事でうつつをぬかすようになったのも、自分に人より優れた感応力があることを悟ったからだ。勿論、実証はあった。インスピレーション、霊感、予感といった類のものだ。それもどういうわけか、悪い予感が奇妙なくらい的中する。そんなことから、その裏付けとして、運命というものを考え始めたのである。
今になって言っても、真実味はすでにないだろうが、今度の事故の場合も強い予感がした。自転車の事故という予感がしたのだが、果たして自分に災いするとは思わなかった。
自転車が走る場合、その速度によって前の車との間隔をあけなくてはならない。その車間距離の算定式には、A.H.Johnson式、GrcevsField式、A.A.S.H.O式などあるそうだが、
A.A.S.H.O式の算定式によると
L=0.19v+6
(v=km/h,L=m)
というLが必要である。
理論的にそうであっても、実際に身の危険を感じなければ、車間距離にこだわらなくなるものだ。特にスピード・ランの時、車間距離をせばめて空気抵抗を少なくして、前後スイッチしながら、スピードを保つ方法をよくやる。しかし、それもハンドリング、ブレーキングに納得いく技術を持っている者にだけ許されているのであって、自信のない者はさけるべきだ。
サイクリング礼賛の気持は変わらない
大自然に満喫し、赤黒く陽焼けし
疲身にムチ打って、家路に着く
風呂上がりにかたむける、酒杯の味は格別だ
とかく人間疎外の叫ばれる昨今
騒然たる世情のるつぼから飛び出し
新鮮な生命の脈うつ叢に接し
素朴で、強堅な、人間性を見つける
そして、満ち足りた生活が約束される
そこに展開する人生ドラマを
じっくりと噛みしめ
飲欷、憂思し世の雑事に終曲を期し
3つの友にうつつをぬかすもよかろう
大言壮語して、我を誉むるもよかろう
この大海に漕ぎ出るも、またよかろう
近眼に関する考察 – 法学部2年 小泉
近眼に関する考察
法学部2年 小泉
「近眼」とは「限の水晶体の焦点距離が短すぎるか、或は、網膜に至る距離が長すぎるため、眼の調節を行なっても、遠方の物体が網膜より前方に像を結び、そのため鮮明に物を見ることができないこと。これは凹レンズによって矯正される」と『広辞苑』にあります。ところで、あなたは「近眼」を「きんがん」と読みますか。それとも「ちかめ」と読みますか。私は、これを「きんがん」と読みます。というのは、「ちかめ」という言葉には近視を病的な片端扱いにし、馬鹿にしているように感じられるものがあるからです。
かたわ(実際、正常眼ではないということで、片端なのですが・・・また、「片端が何故悪い。外形がどうあろうと、人間たるもの、皆同じに人間だ」などと、ある筋の徳の高い方々からは、お叱りを受けるかも知れません。しかし、皆さん、この「片端」という言葉を、そんなに深く受けとめないで下さい。もっとも、そう受けとめる馬鹿なお人はいないと思いますが・・・)
ところで、我がクラブには、近眼の人が何人いるでしょう。ほんど全ての人がそうではないでしょうか。勿論、私も「近眼」です。中学3年の時、眼鏡を使うようになりました。おかしなもので、その当座は、得意気でした。クラスの皆から、注目されたりしたからでしょう。しかし、5年間近眼をやってきた現在、どちらかというと、それに飽きました。第1、人の顔が判然しないのです―キャンパスを向こうから私の高校時代の美人な先輩がやってきます。私と彼女は、段々と近づきます。彼女は私に、笑みを浮かべます。私はと言うと、私は知らぬ顔で通り過ぎます。彼女は私に憤りを感じます。「なにさっ、すましちゃってさ。もう、あの子の面倒はみてやらないから!可愛い顔してるけど…」
僕は何度このような無礼をしたことでしょう。このようにして、何人もの人達の良き心を傷つけたことでしょう。ああ!私は罪深い人間だ!!眼鏡をすべきだ。こんなことでは、社会に出て、会社に出て、上役に対して、そして未来の妻に対して…
しかし、相変わらず、私は眼鏡をかけておりません。なんとなれば、それは自然でありたいのです。人間が自然によって創られたものである以上、自然であるべきだと考えるのです。眼鏡などといういかにも固い、冷い人工物を、可愛いこの顔に、誰がつけることを許すでしょうか。私はテレビと映画と、見ることを目的とする女を見る他は、絶対に眼鏡をかけたくありません。
しかし、最近、私はサイクリングの時に眼鏡をするようになりました。私は1年生の時、よく自転車事故を起こしました。「おまえは、自転車に向いていないのかも知れない」などと、諸先輩は私にのたまわりました。それを素直に受けとめるような、単純な私ではありませんでした。真剣にその真相究明に努力しました。そして、次のような大結論を導き出すに至りました。
「眼鏡をつけて走らないからである」さらに、小泉(徳)氏の弁は続きます。「私は、乗ることに関しては、何につけてもたけている。それが、何故、たかが自転車などに乗ることに、向いていないと言えようか。そして、私は私の事故の原因は、全て近眼にある。という結論に到達したのです。路上の穴ぼこや石ころ、それは近眼にとってなきも等しいものです。故に、平気でその上を走ろうとします。そこに転倒が待っています。更に、歩道を行き交う女の子、近眼ゆえに目を細めて、じっとみつめなければ、優・良・可・不可の区別がつきません。そこに、よそ見があり、追突が待っています。またトンネル内や暗闇は、近眼にとってめくらも同然。そこにコンクリートの壁があり、いとも清らかな泥川が待っています」
果たして、この研究の結論は正当でありました。2年生になってから、私は事故らしき事故は起こしていないのです。やはり、私は乗ることには、全てにわたって得意であったのでありました。
ところで、先の私の眼鏡をかけたがらない理由に賛同する者が増えたためでしょうか。近頃は、近眼でも眼鏡をかける人が少ないようです。これは、私の気持を世間の人々が理解してくれたものとして、個人としては、実に嬉しいことであります。しかし、世界的立場に立つ時、私はこの傾向に憂慮せざるを得ないのであります。すなわち、近眼は言うまでもなく、遠くの物体を鮮明に見ることができない眼をさすのであります。ですから前述のように、人間の顔付きなどよっぽどの場合でなければ、はっきりとわかりません。
そして、お互い異性の顔付きもよくわからないで、その体つきと顔の輪郭だけで付き合うようになり、付き合っております。そして結婚をします。そして初めて、顔と顔との間隔を互いにゼロ、いやマイナスにした時、ようやく相手の真顔に気づき、いやになります。男は「こんな女のために稼ぐ気はしない」ということになります。女は「こんな男のために尽くす気はしない」ということになります。そして、世界的生産能力は低下し、次代を担う世代は減少し、世界は滅亡へと進んでいくのです。これは、世界的問題です。でありますから、みなさん!私が前述していることは正しいのは当然です。しかし世界の発展のため、近視の人はかけるべき時は、できる限り、眼鏡をかけるようにしようではありませんか。
ところで、次に近視眼の人の持つ特権について述べてみたいと思います。正常の目の人には、近眼がどんな物の見え方をするのか、それがわかりません。しかし、近視の人は、眼鏡をかけたり、はずしたりすることだけで、どちらも体験できるのです。
こういうこともあります―私は彼女とデートしています。静かな雨の中を肩を触れ合い、2人はあのドボルザークの「新世界」の音楽の流れる喫茶店へ吸い込まれます。彼女は、優しく白い手を合わせ、軽くひざの上におきながら、澄んだ瞳で私に語りかけます。
「あなた、いつもはどうして眼鏡をかけていらっしゃらないの?」私は静かに答えます。
「それはね、眼鏡をかけない近眼の世界に、あまりにも魅せられたからさ。何もかもぼんやりと僕の目に映る。決して強くなく、はっきりとした調子ではない。全てが優しく、のどかで柔らかいんだ。ちょうど、霧に包まれたように。椅子のあの堅そうな角も、僕にはしなやかに映り、きつい光のシャンデリアでさえも、淡く光って見えるんだよ」
「まあ!あなたってロマンティストね。素敵だわぁ」正常眼の人よ、こういうセリフを少しでも口に出せるかい?
眼鏡をかけていると、男も女もインテリに見えると言います。特に、男の眼鏡付きの顔はそう見えるようです。確かに、眼鏡をかけている人に極悪人は少ないようです。それは、よく本を読み、よく細かい仕事をし、時間を粗末にしまいと電車内で新聞を読むという人達が、近眼になりやすいからではないでしょうか。しかし、現代において、近眼になる原因はそれだけではありません。テレビの深夜劇場、映画の深夜興行、私の好む薄暗い舞台などといろいろあります。ですから、今日の近眼の人は、その原因から(真性近視は別として)勤勉・勤労家の近眼と、勤遊家のそれと、また両方を合わせもったものに分類できると思います。あなたはどれに属すのでしょうか?
北海道合宿の始ま – 法学部2年 篠原
北海道合宿の始まり
法学部2年 篠原
5月末の総会で、今年の合宿が北海道と決定して以来、遠い未知の土地に胸をふくらませ、かつ、かすかな不安も混じえて、7月中アルバイトに汗を流した。合宿の始まり。それは北海道までの切符を買うことから始まった。時あたかも開道100年記念が行なわれ、それでなくても、夏は旅行者が争って北海道へ出かけるという時に、北海道へ行くには相当の覚悟がいるとは思っていたが!
7月27日
午後9時40分、我が家の電話が高らかに鳴った。この瞬間から北海道への長い苦しい旅が始まった。
俺はきょう一日中、熱い釜の中に入ってハンマーを振っていた。しかも、明日の日曜日も、やらなければならない。半分やけくそで一杯やっていたところだった。ほろ酔い気分で受話器を取り応答した。聞き慣れた三輪のシャガレ声だった。
「今、大阪駅におるからすぐこい!」
「なんでや、もう10時やんけ」
「あほか、おまえ!明日切符買うゆうとったけどなー、俺、近くの駅に行ったらな、駅員が特急券なんか買われへん、いいやがってよ、ほんで大阪駅まできたんや。ほんなら、もう10人程並んどんねん。今から並ばな、明日の切符買われへんどー」
「ほんまかぁ、まいったなあ」
「おまえ、いますぐ寝袋持ってこいよ!」
「しゃーないな、ほんなら今から行くわ!」
俺は和泉(彼とも一緒に行くことになっていたので)にその旨伝えて、早速愛車に飛び乗った。普通なら15分程で大阪駅まで行けるが、あいにく台風4号の影響で、風がまともに吹きつける。酔いも手伝ってか、ペースが非常に遅い。大阪駅に着いてみると、なるほど、暇な奴もいるもので、朝から座っているという。その根性に頭が下ると共に、こうまでもしなければ北海道に行けないのかと思うとゾォーとした。駅員をつかまえて『白鳥』の切符を買えるかと聞いたら、あえない返事。こいつは見込なしと思い、中央案内所へ飛んでいった。
「明日の『白鳥』買えまっしゃろか?」
「さあ無理ちゃうか?切符売り場で聞いてくれ!!」
いささか頭にきたが、大阪駅の構内を馬鹿みたいに走り回る。切符売り場で聞いても
「ようわからんなぁ。多分あかんやろ」
「エッ・・・」シューン
予定が完全に狂って、3人で相談したが、とにかく明日切符が買えるかどうかもわからないのに、朝までこんな所に座っていられないので、明日にでも、各自で交通公社にあたってみるということで一応今日は帰ることにした。帰りの足の重かったことよ!
7月28日
三輪から電話がかかってくる。和泉が交通公社で聞いたところによると、『日本海』という急行がある。それで青森まで行き、函館から『たるまえ』に乗れば、札幌まで行けるということである。最悪の場合は『鈍行』ということも考えていただけに、2つ返事でそれに決めた。ただし、自由席だからかなり早くから並ばなければ、座れそうもないという。これまた後日相談することにした。
8月3日
6時半にガバッと起きて、朝食も食わず大阪駅へ向かう。7時すぎに中央口へ行ってみたが、意外や意外、もう10人程並んでいた。しまったと思ったものの、これならまあ座席は確保できるだろうと思って、早速俺も列の後についた。しばらくすると、三輪がヒィヒィ言いながら、自転車にかつがれてきた。
新聞を広げて寝袋をだし、完全に長期戦のかまえ。この『日本海』は20時40分発である。俺達は、朝の7時からそれに乗るために並んでいるのである。俺達の前の奴等が雀卓を出して、麻雀をやり始めた。その徹底ぶりに感心し、うらめしく見ていたら、その中の1人が高校時代のクラス・メイトだった。早速話してみた。
「オス!お前どこ行ってんねん?」
「オレか?オレ、慶応やんけ」
「ほんまか!」
「お前は?」
「オレ早稲田や」
「ほんまか―、3年か?」
「いや2年や」
彼は現役で慶応に入った。話を聞くと、彼等のグループのうち、3人が俺と同じ高校だそうである。こんな所で、3年ぶりに会うとは!まったく人生とは不可思議なものである。
20時40分、ついに『日本海』に乗る。しかし、大阪駅が始発だというのにもう大阪だけで満員である。これから先はどうなるのかネ。自転車3台が、通路で人間と共にひしめきあっている。非常に混んでいるために、肩身が狭い。乗客全員から非難の目を浴びせられているような気がする。迷惑をかけるとわかってはいるが、自転車を持っていかなければ、何をしに北海道くんだりまで行くのかわからない。心の中で深く頭を下げると共に、これから混雑が予想される時には、絶対に輪行袋を使わないにしようと反省した。
そのうち、乗務員がきて、この自転車を分散しろといってきた。勿論、分散しようと考えていたが、電車に乗るや通路は人また人。トイレにも行けない状態ではないか。しかも自転車の上には、乗客の荷物がつまれている。どうにかしなければと思っているものの、どうしようもなかった。三輪が、人をかきわけ自転車のところまで行ったが、乗務員の態度があまりにもきつかったので、1台だけ通路に置いて、2台を洗面所にほうり込んだ。
彼は気を使って、立つと言い出した。その気持はわからないでもないが、俺達が朝から並んで、やっと獲得したこの席ではないか?手前だけがイイカッコして!!お前が立てば、俺達も交代で立たなければならなくなる。彼にはこれがわかっているのかネ。なるほど、自転車で迷惑をかけているのはわかる。しかし、この電車に乗らなければ、合宿には間に合わない。青森まで23時間も立ち続けるというのか?ここは自我を通さなければならないと言いきかせつつも、朝になったら、代わりに俺が立とうと思って、隣に立っていたおばさんに彼の席を譲った。しかし、2時間もすると、もう辛抱できないといって座りにきた。初めから座っていればいいものを!!!!
5人で座ることもできないので、寝袋を出して座席の下で眠ることにした。これが、意外にも1番楽であることに気づいた。それからは、3人で3時間ずつ交代で寝ることにした。列車は福井、富山と過ぎる。ちょうど、去年の合宿が、この北陸だった。去年は福井駅集合だったので、大阪から自転車で出かけた。あの時はこんなに苦労しなかったし、また楽しかった。それに比べ、今年はどうだ!これなら合宿に参加するだけでも、非常に意義がある。クラブの他の連中もこんなに苦労してるのかなあ、この調子では参加予定者も大分減るのではないかななど考えながら、時間をつぶした。
そのうち、対面のにいちゃん(同志社の1年生)とも大分親しくなった。新潟に着く頃、夜が明けた。新潟に着いてから、混雑は少しましになった。トイレに行って驚いた。なんと、輪行がトイレに入っているではないか!誰が入れたか知らないが、これはひどい。青森に着くまでには、完全ににおいがしみ込んでしまうのではないだろうか?
8月4日
夜が明けてからは、外の景色を見ることができるので、気分も少し和らいだ。日本海とそれに沿って走る国道7号線。サイクリングには格好の道だ。事実、多くのサイクリストを見かけた。ああ早く自転車に乗りたいなあ。自転車の方が楽かもしれないなどと本気で考えた。秋田を過ぎてからは、ようやく空いてきた。と共に、乗客も土地の人が多くなった。窓際に立てかけたウィスキーは、一向に減らない。
7時(つまり、4日午後7時)にやっと青森に着いた。まる一日列車に乗っていた。青函連絡船に乗り換えるための時間は10分間。重い自転車とパニヤ・バッグをかかえて懸命に走った。デッキであろうと、船底であろうと、船に乗れるだけでよい。その時はそう思いながら、人々の後からゆっくりと走った。自分では走っているつもりであるが、普通の人が歩くより遅い。船に乗ると、例の同志社のにいちゃんが手招きする。彼は我等のために座席を確保していてくれた。これも旅ゆえかと思い、ありがたく礼を述べた。函館まで3時間半。列車と違って、船の中はかなりゆったりとしていた。午後10時半、函館着。
8月5日
ついに北海道にきた。待ちに待った北海道!!!「はぁるばるきたぜ函館ぇ――」とまったく大声で歌いたかった。例のように走っていると、駅員が追いかけてきた。何故かなと思っていると「これ、おたくの切符じゃないですか?」ときた。「エッ」あわててポケットを調べたら、ない。切符がない。走っているうちに落としたらしい。瞬間、ゾォーとした。礼を言って列車に飛び乗った。11時半、函館を出て札幌へ。この列車でも、同志社のグループと知り合いになる。彼等もこれから北海道を回るという。車掌に頼んで指定席を取る。座席の下で、寝袋をしいて寝たのはいうまでもない。
6時前に起きて外を見た。これが北海道か!これが!さすがに寒いなあなどと言っているうちに札幌に着いた。ここで釧路行の急行に乗り換えた。ここまで来るとさすがに落着いたものだ。要領も心得て、うまく座れた。輪行も洗面所と通路に置き、迷惑のかからない、いや、できるだけかからないようにした。そうしてるうちに、俺を呼ぶ奴がいる。振り向くと坂本がいた。真黒に焼けて、いかにも遊んでいたという感じだ。事実、休み中毎日海で泳いでいたそうだ。久しぶりに会ってなつかしかった。あと何時間かで皆に会えると思うと気持がはずむ。あいつきてるかなと思いつつ、気持ははやくも釧路に着いていた。
ドリル、ペンチ、カナヅチ-まな板の上のトラジディ – 理工学部2年 木村
ドリル、ペンチ、カナヅチ-まな板の上のトラジディ
理工学部2年 木村
昭和43年8月2日、初めての合宿参加に、意気揚々と出発したものの、何んと不運にも、合宿第一日目にして沈没。全治2ヵ月の鎖骨骨折。悲劇の主人公の如くに、容赦なく悪夢に責めたてられる。
8月5日、午後4時前後だったろう、前日までの東京からの強行軍により睡眠不足だったので、テントで昼寝していた時、ふと目を覚ました。
ちょうど板橋さんが駅に行くところだったので、何気なしに自分も行ってみようと、眼をこすりながら起き出し、自転車にまたがった。辻山君も一緒に行くとのことで、かなり間隔はあったが、3人で駅に向かった。実の所走り出してから、事故までの間のことは良く憶えていない。居眠り運転をしていたのだ。合宿参加者なら知っていると思うが、テント設営地から釧路駅までの間にある引き込み線の2つの踏切りの駅に近い方にさしかかった時、踏切りで路面が凸凹だったため、いつもする様にハンドルを軽く握り、浮き腰で通過しようとしたものの、そうはいかなかった。ハンドルが一瞬とられたので片手運転になってしまった。次の瞬間不安定な自転車は、足を砂利にとられスライディング。ズシンと右肩に激痛を感じた。でも、起き上がってみて、激しい痛みは感じなかったので、なんともないものと思い、肩を2、3回回してみた(よくやる動作だ)。
肩も回る。大したことはないなと思って、肩に左手を回してみたら、無気味な感触があった。とっさに鎖骨が折れたのを自覚した。2つに折れ曲ってつき出ているのが、指先を通じてはっきりと分かる。やんぬるかな、しまったという気持が全身を駆け巡ぐる。
後から、辻山君が来たので、病院を捜しに行ってもらった。1軒目は外科ではなく、2軒目の病院を土地の人に案内してもらって、診断を受ける。無論、完全骨折。当院にはレントゲンが今のところなし無いというので、応急処置だけしてもらい、翌日帰京することにした。
あわれな格好でテント村に戻ったのは、5時頃であったろう。合宿参加者全員集合した中で、突然自転車を奪われた自分が非常にみじめだった。釧路特有の夕霧がかかり、寒さがより以上に感じられた。その夜、斉藤君に付き添ってもらって、市内のホテルに泊ったが、患部が山の様にはれ上って痛くて眠れなかった。
1夜明けて、12時20分発羽田行の飛行機で帰京したのだが、途中、合宿に、こんなことで参加できなかったのが、あきらめきれず、無性に腹が立った。
乗る前に、スチュワーデスに、頼んでおいたので、予想以上に親切に世話してくれた。羽田に4時頃着いた。母と叔母が迎えに来てくれていたが、出てくるやいなや、シャツをまくって腕を確認しようとしていた。無理もない、釧路からはあまりはっきりした状態を知らせていなかったし、右手をスッポリ片腕があたかもない様に、シャツで覆っていたから。早速都内のK病院に急行し、レントゲン検診を受けた。案の定、大きく2つに段違いになって折れている。入院の必要有りというものの、空いているベッドがないというので、国立第2病院を紹介してもらい、そこに入院。
手術が宣せられ、8日手術を受ける。手術台の上に横になるのは、いいものではない。目隠しをされ、周囲に医者、看護婦が集まり、開始となる。まな板のコイだ。「チクッと少し痛いよ」という陰謀に近い言葉と同時に、連続的に、麻酔の注射が患部周辺を攻撃する。メスの切り開く感じが鈍く感じる。手術後、医師から聞いたのだが、骨は大きく2つに折れ、さらに5、6個に小さく、ほとんどめちゃくちゃに砕けていたらしい。自転車で倒れて折ったと言っても、信じられない折れ方らしい。自分でも、それほどとは思っていなかった。
大した痛みを感じることもなく手術が進行するうち、予期しない医師の声を聞いた。「ドリル!」一瞬啞然とした。砕けた骨片を、骨に穴をあけ、針金で巻いて固定するらしい。鈍い痛みと共に、ガリガリとドリルの骨をけずる音が耳元でする。骨髄に達するのだろう、時々激痛がズンとくる。「ペンチ!」まさに残酷ムードたっぷり。約1時間半かかつて手術は終った。
ところがまだ悲劇は続く、翌日のレントゲン写真の結果、針金で巻いたのが、はずれてしまったので、12日に再び手術することになった。悪運はどこまでついてまわるのだろう。当日、又、同じ陰冷な手術室へ。手術前の看護婦の話だと、2度目は痛くないとのことなので、普通の気持で手術台の上に横たわった。ところが、どうだろう、痛くないどころではない、麻酔がどうしたわけか効かず、激痛の連続。叫び通し。なにしろ、何をするにも、鋭い痛みが全身を震わす。あとから麻酔薬を注いでも、血液と一緒に出てしまうらしく、とんと効き目がない。手術の後半は、ほとんど麻酔無しの状態。こんな例えようのない痛さを味わったのは生まれて初めてのことだ。痛さに耐えかねて暴れるので足は縛られ、頭や腕はしっかりおさえられたからたまらない。今度は全身の筋肉がケイレンを起こし、全身の震えは止まらない。失神の1歩手前までいった様だ。全身びっしょり汗をかくし、実に生きた心地がしなかった。
「カナヅチ!」また一瞬、手術を間違えたのではないかと思える様な、言葉を耳元で言っているのが聞えた。小さく砕けた骨片を、骨のすき間に打ち込むためらしい。残酷物語もここまでくると漫画を見ている様だ。「もう少しだ」と医師はいうが、そのもう少しが長い。最後の皮を縫うのにも、麻酔が不十分だから、1針1針が電気を通した如くにビリビリと痛い。
2時間の大奮闘の末、やっと手術は終わった。術後、すぐギプスで固定し、このままで骨がつくまで、約2カ月間辛抱しなければならない。
運命というものは、かくも深刻に迫ってくるものなのか。時々、事故当時を思い出して、あそこでああしなければ、こうしなければと悔いが残って離れない。
早慶戦観戦記 – 政治経済学部1年 遠藤
早慶戦観戦記
政治経済学部1年 遠藤
「カサ買って下さい」「これがないと応援できませんよ」信濃町駅を降りたら、とたんにこれだ。金があるから、ひがさのつもりで1本買った。6月1日土曜日、9時、信濃町駅集合。今日は、クラブの人たちとそろって早慶戦の応援に行く日だ。試合は1時から開始されるのに、9時集合とは、少しばかり早すぎると思いきや、さにあらず。球場の入口のところでは延々長蛇の列。前日の夜から泊り込みで球場にはせさんじ、そのまま寝すぎて開門近くなってもまだ寝てる人のことをけっとばして起こしてやりたかった(この親切な心)が、じっとこらえた。やっと入いれたが、内野席はすでに上の方しか残っていなかった。早く大声を出したかった。バンド合戦なんてのはどうでもいい。バトンガールの可愛い子ちゃんをもっと近くで、たっぷりと眺めていたかったなあ。
そもそも僕は昔から野球が大好きで、早慶戦なら絶対早稲田と思っていたが、どういうわけか、早稲田にはいってしまったので、今日はまさに、命をかけて一生懸命に応援しようと思っていた。
早慶戦も3連投、夜の新宿3連投、おかげで金はなくなるし、大事な美声もだいなしになってしまったが、おれも男だ異存はない。
しかし第1日目は失敗した。僕のまわりはみな男、第2日目からは気をつけて、女性のまわりにすわったが、いつもは純情可憐すぎ、話しもできないこの僕が、この日ばかりは堂々と、肩を組んだり、さわったり。これはイカスぜ、最高だったよ。試合経過はどうでもいい。でもやっぱり早稲田が勝つにこしたことはないな。あの校旗はでかくて実にいい。そして大の男がふんばって持ってくるのも実にいい。僕は旗もちに足をひっかけて、でんぐりがえしてやりたい気になったが(イジワルバアサンに載っていた)、通路のそばじゃなかったのでやめた。それにしても慶応の校歌は長すぎるくらい長い。だけど「若き血」と共になかなかいい歌だ。僕は気に入った。
そう、歌といえば、第2日目負けた日の最後に「故郷」をうたったが、あれは実に胸にジーンときた。僕は感傷的なんだ。それ以来、僕の大好きな歌になった。
さて、これまでじゃ、みんなで早慶戦を見にいった意義が見い出せない。しかしそれは夜の部にあったのだ。「エース」でコンパ。1年生は本性をまさにあらわにした。僕・保泉・中山の3人は、とうとうそれを暴露した。早稲田の学生らしい、高尚かつ独創的な歌を吠えた。実にいい気持ちだった。溜飲が下がる思いがした。コンパ後、大隈侯の銅像の前で、校歌をうたい報告した。大隈さんは角帽をとって笑顔で「よく応援した。それでこそ早稲田マンだ」と言っていた。
全く破廉恥な、ナンセンスな雑文を書きました。早慶戦コンパのあった日に書いたものですから、せっかくの僕の文学的才能も、発揮できませんでした。いや最後までどうも失礼いたしました。
竹馬の友に捧ぐ – 法学部2年 篠原
竹馬の友に捧ぐ
法学部2年 篠原
俺の友達にSというのがいる。いや、いたというべきかな。あいつとはいわゆる竹馬の友で、お互いに生まれてすぐ知り合ったような気がする。3つか4つの頃から近くの保育園に通い出した。あいつが3年間で俺が4年間通った。毎朝連れだって、小さなカバンを肩にかけ、何を話していたのか忘れたが、よくまあ長い間通園したものだ。
性格的には、あいつと俺は正反対だった。あいつは、保育園でもガキ大将でボス的存在だったが、俺はどちらかというと、ひ弱な感じで、むしろ1人でいる方が好きだった。俺があいつにコンプレックスを感じていたのは、あいつにおやじがいるという事だった。俺は生まれてすぐ、おやじと死別した。あいつの家族が4人であるのに対し、俺の家族は、兄を頭に6人も姉がいて、そして俺は末っ子だった。兄は夜間の大学を優秀な成績で卒業し、会社に勤めた。当時、何百倍という日航に合格したというのが、俺の自慢でもある。姉達も自分で働きながら夜学に通った。こんな環境がすでに俺の性質を形成した。
小学校に入学してからは、あいつと俺の性格の相違がきわだってきた。俺達の近所には同級生が10人程いた。いつも遊ぶのは、このグループと決まっていた。道を隔てた向こうの奴等とは、話すらしてた事がなかった。近くに広場があったのと、皆んな俺達と同じ鍵っ子だったので、学校が終わるや、カバンをほったらかしにして集まって遊んだ。教育ママなどというのは、俺達にはまったく無縁のものだった。俺が今、バイトとして家庭教師を絶対にやらないのは、このように育った俺が、羨望にも似た反発を感じるからである。ともあれ、俺達は大いにのびのびと遊んだ。そして、俺達のグループの中心は、いつもあいつだった。
俺達が主に遊んだのは、ソフト・ボールである。当然のことながら、あいつが俺達の監督で3番バッターと決まっている。これはいつも不変であった。あいつは運動神経が発達していて、さすがに群を抜いてうまかった。それだけの実力はあった。俺はどちらかというと鈍い方で、いつもあいつに文句を言われていた。
小学校5年の時、町内でソフト・ボール大会があった。俺達も当然参加した。相手チームはどれも6年生ばかりで敗れても当然だったが、あいつを中心に皆んなで団結して、まったく奇跡的に優勝した。もうこの頃には、俺達はあいつに対して反抗するなどということはできなかった。まったくの独裁であったが、あまり反発も感じなかった。こんなに遊んでいたが、学校の成績はお互いによかった。特にあいつは人気者なので、それがよく目立った。この頃あいつと図書館に通ったりしたこともあった。実際、中学に入る時の試験は俺が1番よかったらしく、新入生の代表として挨拶させられた。
小学校も高学年になると、こんな性質の俺ではあるが、勉強に関しては、誰にも敗けなくなった。成績で競争させられる事自体、俺は好きではなかったし、反発も感じていた。今、大学に入って初めてそれに反発できるようになった。今は、優の多い奴が何も偉いとは絶対思わない。優の数と人間性とは全く無関係だと確信している。
さて話を10年前に戻そう。中学校に入る前に、あいつと俺の、今にして思えば、2人を引き離す事件が起こった。
小学校6年の時、急に、まったく急にあいつのおやじが死んだ。交通事故らしいが、まったく急であった。人気者のあいつだっただけに、葬式には小学校の校長から担任の先生、仲間の生徒も多数参列した。あいつは俺達を見つけると、ニコニコと笑いながら、俺達のそばにやってきた。あいつが作り笑いしているのに、いやな反発を感じた。昨夜あれ程泣いていたのに!それでも立派なものだと思った。俺なら絶対にこんな演技はできないだろう。しかし、俺はこれであいつとやっと対等になったような気がした。そして、俺があいつの笑顔を見たのは、これが最後だった。実際、若いおやじを失くした家庭程みじめなものはない。
俺が独身主義者だ、結婚しないなどと言っているのも、あいつのこの事が影響しているのかもしれない。俺は自分でも長生きできる自信はない。俺の考えによると、あいつの場合をみてもそうではあるが、親となるには、自分の子供が少なくとも成人式を迎えるまでは、生きなくてはならない義務があると思う。俺の場合もそうであるが、残された家族が物質的、精神的に苦労する。俺などは特に、このいまいましい陰うつな性質を持ったのはおやじのせいだと思っている。
あいつはおやじが死んでからは、いままでのような明るさがなくなった。俺達とはつき合わなくなった。皆んなの中心になるのをやめ、1人で飛び出していった。あいつのおふくろさんは必死に働いた。何か商売を始めたらしく、毎日12時過ぎでなければ帰らなくなった。そして、あいつはおふくろさんが帰ってくるまで、ずっと起きて待っていた。炊事等もあいつがやっていたようだ。まったく信じられない変わりようだ。
結局、中学に入ってすぐにあいつは引越した。といっても中学は同じだったので、俺達はあいつとよく会った。しかし、あまり話合わなくなった。お互いの間に割り切れないムードが漂い始めた。中学2年の冬、あいつが久しぶりに俺達の住んでいる所にやってきたことがあった。俺達のグループは散り散りばらばらになり、俺もほんの2、3人としかつき合わなくなった。俺達が話していたのを、あいつは見ながら、俺達に気軽に話しかけなかった。俺も何か話しかけるきっかけをつかめず、その時は、そのままになってしまったが、今でも後味が悪い。本当はあいつ、ひどく内気な奴なんだ。
中学も3年になると、高校進学の事で頭が一杯になる。学校では成績の順位を掲示する。あいつも俺も20番位だった。何しろ800人近くいたのだから、当然、お互いに進学する。有名校に行くことは決まっていたから、あいつも俺も同じ高校を受けた。当然、俺は公立に行かなければならなかった。いや、あいつもそうだったろうに、皮肉にも、俺達の学校からはあいつだけ落ちた。俺は一瞬、あいつが、あの時の作り笑いをうかべているのを想像した。あいつは止むを得ず私立に行く事に決めたらしい。
高校時代、あいつがどんなふうに暮らしたか、俺は知らない。俺にとって高校生活は、まわりの者が、受験勉強ばかりやるので、まったくつまらなかった。俺は兄と同様に、夜間大学に行く事に決めていた。そして、高校を卒業すると同時に就職し、夜学に通い出した。あいつの友達に聞いたところによると、あいつは大学も落ち、1浪して早稲田に入ったらしい。
ともあれ、あいつは、俺にとっては一生忘れる事のできない友である。これから、あいつが如何に生きて行くか、あいつ自身の問題だが、幸多かれと祈らずにはいられない。
道 – 理工学部2年 木村
道
理工学部2年 木村
道―単調にだだ広い草原を真一文字に、地平線の彼方に消えてゆく一本道。我々は、往々にして、そんな単調な道に遭遇することがよくある。しかし、その道もいつか分かれ道にさしかかる。そして、そこに1輪の野菊でもいい、又は石ころしかなくてもいい、まさにその分岐点に立つ時、我々は「生活」を感じる。過去に歩んで来た後方の道をながめながら一息つくのも、そんな分岐点のことがよくある。それがすなわち、無意識のうちに感じている「生活」なのだ。ましてや、峻険な山あいを縫って、うねうねと続く道には、強烈に三界の生活を感知せざるを得まい。我々が街道と呼ぶもの、まさに然りである。
道に刻まれた生活の轍が、雨によって、あるいは風雪に、あるいは新しい轍によって、大地から抹消されてゆくように、道は我々に、容易に万物の流転、時の流れ、生活の変転を連想させてくれる。道に逆らってはいけない。
人間がある基点を設け、既に基点を設けた人間との間に交わりが始まれば、そこに道が生じ、そして初めて相互の生活が始まる。すなわち、道と – ある時は1次元的な道を、また時によっては、2次元、3次元的な道を考えていく時 – 「生活」との間に不可欠なアイデンティティ同一性を見い出せるということだ。つまり「道」は人間生活の場であり、個々の生活空間を連結する空間である。そしてこの公理は、人類がこの地上に姿を現わして以来不変のものであると信じる。
しかし、時と共に、独占欲にたける人間どもの必要が、欲望が知恵を生み、道は常にその形態を変えて来た。人間の両足が方向性を、2次元性を失なわないのに充分であれば足りた細い道は、動物の足が加わり、馬車が牛車が加わり、そして生活が多様化するにつれ、みるみるうちに形を変えていった。更に、自動車の抬頭と共に大きく変貌したことは、言うを待たない。自動車の出現によって、人間は道に一様性を与え、綺麗に飾りたて、大地に巾広いコンクリートの川を作ってしまった。
ここに、社会の複雑化に伴い、特に都会では、道はその代償として、無惨にも個々の生活空間から、取り上げられてしまった。雨が降っても、泥んこ道に悲鳴を上げずに歩けるようにはなったものの、個々の生活空間から隔離されつつあり、この人間を、逆に締出しにかかっているのだ。コミニュケーションの場さえ奪われてしまった。そうしようものなら、まさしく昇天の目に会うだけだ。
「道」はもはや「路」となってしまったのである。「道」は「路」となり、非人間的な権威の示威の場となってしまったのだ。しかし、雑草が覆いかぶさる土や砂や砕石のある道が、何んの興味も沸かない、変哲もない灰色のコンクリートのマントにくるまってしまって、素朴な「道」のイメージが失せてしまっても、我々の心には「道」に対する虚像を忘れられず、心のどこかにしまってあるものだ。
そしていつも実像を求め、探索しているから、ふらっと訪ずれた郊外の雑木林の中などに、人間の手が加えられていない「道」を見つけると実にほっとする。そして、柔らかく弾力のある大地を、10年前の旧友に再会した時のように、何度も歩いてみたい衝動にかられる。また故郷を離れた者が郷愁を覚えるのも、山や川や野というようなものよりも、そこにくねくねと続く素朴な道を前にした時であろう。「道」は赤裸々な個々の生活を正真に教えてくれる。
編集後記 – 星
編集後記
セミの声がやかましいほどに聞こえる、むし暑い日である。ようやく「峠」第6号の編集が終わった。ヤレヤレという感じとは別に、クラブ員、OBの皆さんには、非常にすまない気がしてならない。お許し願いたい。すでに、発刊が4ヶ月も遅れている。責められて、当然のことであろう。反ばくする正当性を、私は持たない。いや、持てない。しかし、これで「編集」ということばが、私の頭を煩わすことがないと思うと、何とも爽快な気分になる。自分で言うのもおかしいが、それほどに厄介な仕事であった。
原稿がなかなか集まらない。毎年繰り返されることである。私としては、クラブ誌であるからには、全員の原稿を載せたいものだと考えていた。少なくとも、その努力は自分なりにやったつもりである。しかし、やはりだめだった。残念でならない。ここに、現代の一面が、顔を見せているようだ。
そこで、いろいろなことが書かれる私用ノートからの抜粋を試みたわけである。ここには、クラブのある面が、顔をのぞかせているからだ。偽らざるクラブの記録であろう。どんな反響が出るか、私は待っている。それによって、私の意図が的中していれば、幸いである。それにしても、4年生の原稿が、1編も手元に届かなかったのは、心残りがする。
誌面は一挙に倍近くになったものの、「厚いだけで内容がない」などと言われそうであるが、一応これで、私の目指すクラブ誌なるものは、不十分ながらも達成されたと思う。やはり、何事も1時に解決はできないもので、徐々に、徐々に解決しなければ、うまく行かないだろう。私が昨年の「峠」を土台にして築いたものを、さらに強く、高く築いていって欲しい。
最後に、日頃の編集活動に協力してくれたクラブ員諸氏、「峠」の作成にあたり、広告集めに飛び回ってくれた三輪君と仲田君、この暑いおり、毎日のようにご指導、ご協力をいただいた中村さん、そして協力、激励を惜しまなかった堺君に心からお礼を申し上げると共に、暖かいご援助の手をさしのべて下さった、高橋·日東·中村・藤田・サンノー・アルプスの各社に対して、深く感謝いたします。(星)
峠 第6号
編集責任者 星
1969年8月1日発行
早稲田大学サイクリングクラブ
Editor’s Note
1968年の出来事。昭和43年。
第10回日本レコード大賞 1968年 天使の誘惑 黛ジュン
1月。 円谷幸吉が自殺
2月。グルノーブルオリンピック大会開幕。
大塚食品がボンカレーを発売。
4月。霞が関ビルが完成。
6月。小笠原諸島が日本に復帰。
7月。郵便番号制度開始。集英社、少年ジャンプを創刊。
9月。タカラ、日本版人生ゲームを発売。
10月。メキシコオリンピック開幕。
川端康成、ノーベル文学賞受賞。
ソニーがトリニトロンカラーTVを発売。
11月。ゴルゴ13連載開始。
12月。府中で三億円強奪事件発生。
映画、2001年宇宙の旅、猿の惑星公開
WCC夏合宿は、「 北海道 : 釧路から – 札幌まで」でした。
=====
こんにちは。WCC OB IT局藤原です。
クラブの体制が整ってはきたものの。事故、メカトラ、走り方で様々な問題が発生した年でした。「フリーラン」が始まった年でもあります。また、初めての海外遠征(沖縄、台湾、香港)の手記が読み応えあります。
当時の文章をWEB化するにあたり、できるだけ当時の「雰囲気」を尊重するよう心掛けたつもりです。
文章と挿絵はPDF版より抜粋しました。レイアウト変更の都合で、半角英数字、漢数字表記等を変換していますが、全ての誤字脱字の責任は、編集担当の当方にあります。もし誤りありましたら、ご指摘をお願いします。
2025年3月、藤原
Copyright © 2025, WCCOB会