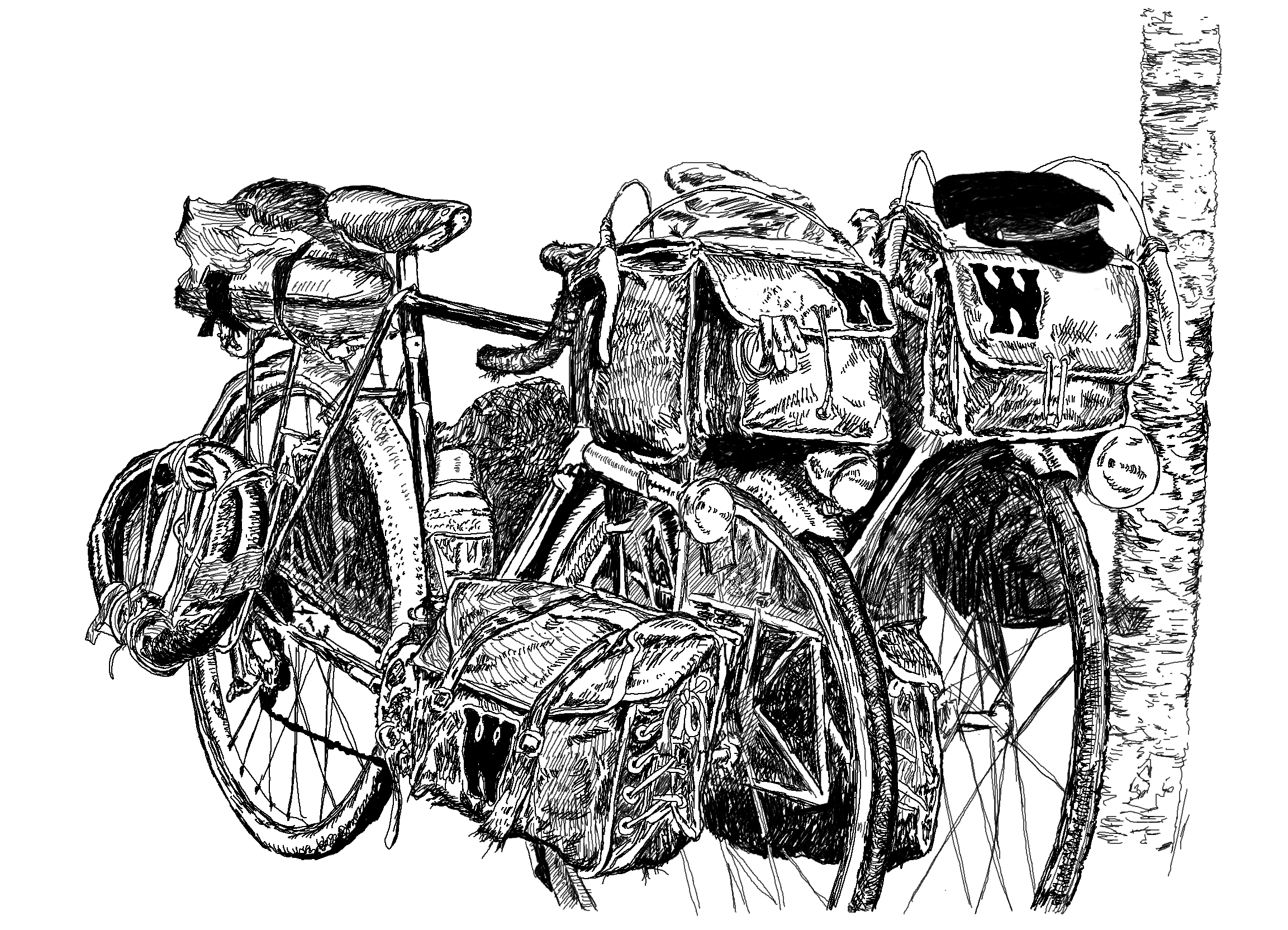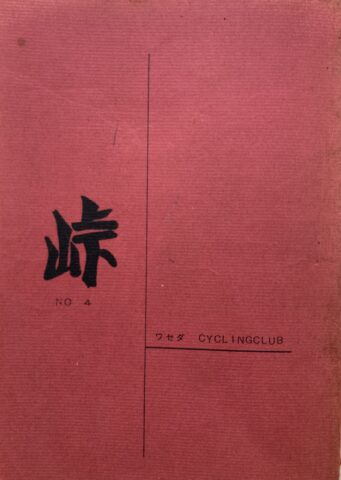
- 峠の詩
- 発刊に際して「峠」随想 – 文学部 清原先生
- 発刊に当って – 主将鈴村
- 合宿記録66年夏季東北 (秋田 – 盛岡 – 山形 – 福島 – 日光)
- 北国の日に – 綿貫
- 台湾旅行前後 – 栗原
- 早同交歓会印象記 – 渡辺
- 早同交歓会の将来 – 藤瀬
- 早慶対抗レース参(?)戦記 – 守谷
- サイクリング・トロフィー奮戦記 – 板橋
- 想輪の記 – 鈴村
- サイクリストとドライバー – 小川
- 1つの提案(こうしたらもっとクラブが活発になるだろう) – 山添
- ペダルを踏んで思うこと – 古川
- 花巻から – 荒井
- 私の履歴書 – 山添
- 自転車専用道路 – 中村
- オープンサイクリング裏話 – 品田
- 編集後記 – 上杉
- Editor’s Note
峠の詩
峠の詩
峠に登って
その思い出の中に
越えた山河を確かめながら
湖を望る旅人は
遠く空往く雲に
何を聴こうというのだろう
秋の空が
その抜けるような青を拡げて
輝く紅葉に映えている中に
一人佇みながら
そっと涙ぐむ旅人は
何が哀しいというのだろう
やがてくる紅の夕焼けに
国境の峠は
明日も晴れるであろうに。
発刊に際して「峠」随想 – 文学部 清原先生
発刊に際して「峠」随想
文学部 清原先生
私の故郷には浅間山と碓氷峠がある。2つともこどもの頃からよくなじんだ山で、私の過去の思い出のいくつかが、そのなかにとじこめられているように思われる。ともに懐しさにかわりはないが、浅間山についてはなにか厳しさの感じが濃くつきまとっている。山のかたちの故かもしれないが、それよりも、自分と山が離れている感じのほうがなにか強い理由のようにも思われる。山へ登りたい、登らなければならない、登ることができた、などという感じがそこにある。
碓氷峠には、なにか浅間山のような距離感がなくて、ごく自然な一体感がある。なぜか、いろいろと考えてみて、そこには「道」という日常なれ親しんでいるものがあることに気づいた。むろん、浅間にも登山道があるわけだが、それは毎日の行動やできごとと、結びついている道とはちがったものである。
峠は毎日の道の延長であり、私の日常生活の延長である。論理的にはつながりがないかもしれないが、たしかな心理の連想がそこにある。
峠道を歩きながら、私は自由に、さまざまなことを考えることができたし、途中で沢の方へそれて、実生(みしょう)の松や楓を掘ることもさしつかえなかった。ふとした想いのままに引きかえしても、それはそれでよかった。
自由のある道、私には峠の道はそういうものだと思われる。旅人にとっては、峠は越えるべき道である。人生という旅でも、そのなかの沢山の峠は、みんな越えなければならないものだ。引き返す自由などとのんきなことはいえないだろう。
しかし、峠はいくつもある。これだけ越えればそれが人生だ、などということはない。だから、それを1つ1つ越えてゆくしかない。1つの山ならば、それを登ることによって目的は果せる。峠はいつ終るともなく、つぎつぎとある。1つの峠道を歩くときに、その果しなさの想いがある。
やはり、「峠」は人生の道と同じもののように思われる。人生には、峠道と同じように、自由さがどうしてもほしいものだ。峠のサイクリングに、ふとしたときに、自由とか、無限とか、一体感などの想いを味ってほしいものである。
1967・3・23
発刊に当って – 主将鈴村
発刊に当って
主将鈴村
本年度は、クラブの活動が従来にも増して断然、活発に行われ、多方面に大きな足跡を残したと思う。それは即ち、諸君のそれぞれが、その責任を果してくれた事、又その団結したファイトによる処であると信ずる。本年は、その意味において我々クラブの1エボックになったと思う。しかしながら、20世紀の人類が何千年の輝かしき過去の土台に存在するごとくに、我々のクラブも先輩が礎いた土台があってこそなのである。そして、更に後輩諸君は、その新しき息吹を持ってサイクリングの発展に寄与してゆかねばならぬ。
この「峠」を通して、もう1度我々の1年間を振り返り、新たに来年度の諸活動の参考となる事を願いたい。
合宿記録66年夏季東北 (秋田 – 盛岡 – 山形 – 福島 – 日光)
合宿記録66年夏季東北
秋田 – 盛岡 – 山形 – 福島 – 日光
8月13日(土)曇ときどき雨
秋田は雨である。11時頃、着いた。街はあまりきれいではない。自転車を市外まで受け取りに行く。全部、無事に着いていた。菅原さんが、駅前に来てくれた。久し振りだ。ヒゲも目立たぬように、よく剃ってある。
8月14日(日)うす曇 秋田市 – 田沢湖
うす曇、微風でサイクリングには絶好の天気。7時50分に、秋田駅前を出発し、すばらしい国道13号の舗装道を楽しむ。坂は6個位、13号線を左へ曲って、46号線に入る。46号線は、砂利道。特に道路工事中の2キロ余りは、大砂利があり下車しなければならなかった。角館から田沢湖町は大きな坂もなく、道も普通の砂利道。
8月15日(月)晴 田沢湖 – 花巻
朝、出発してすぐに仙岩峠へさしかかる。この峠、非常に急で皆歩く。(1年鈴木(光)君のみ歩かないという?彼はトップに頂上到着)峠でバテたものが出たので、その後、計画通り実行できず、国道4号線に入ってからはハイ・スピードにて花巻へ向うも、到着時間は2時間半遅れてしまい夕食が8時頃となる。前半はダラダラしてまとまらず、統卒しずらかったが、後半は、皆そろって走り、その眺め、スタイルは絶景。
8月16日(火)雨 花巻→一関
昨夜来の雨は降り止む気配が全くない。この為、スケジュールを大幅に変更し、中尊寺に寄るほかは、一関まで4号線を突走る事にした。又、雨で炊事ができないので、朝食はバンを購入。ここから水沢市まで3 – 4人のグループに分けてファーストランを行う。
水沢 – 中尊寺は整然と進行。雨もほとんど降らず、ポンチョを脱いで走る。この頃から車の油切れが目立つ。雨の中尊寺はしっとりと静まり、かなり良いムードであった。本堂の辺りで、今東光と記念撮影。その後、一関まで軽く流す。
8月17日(水)曇ときどき小雨 一関→鳴子
昨夜は、畳の上に寝て、皆よく寝られた様子。朝食は、オミオツケ(中味ナスだけ)、ふりかけ、佃煮、トマト、リンゴ。
この日から、4年生の菅間さんが抜け、同じく4年生の新井さんの第一日目が始まる。昨日にひきつづき4号線を走る。コンディションは小雨が降り、むし暑く大変悪い。長崎村よりのフリーランは途中かなり長い坂があり、きつかった。キャンプは降り出した雨のため、予定を変えて鳴子の旅館にとまる。
夕食は、オデン。明日は、90キロ走るとの事。
8月18日(木)晴れ 鳴子 – 山形
今日は、かなりの強行軍の為、起床を早くしたが、食事準備に手間取り出発遅れる。出発点から山刀伐峠頂上まで登りばかりだが皆良く健闘し、だいたい予定通り頂上到着。(渋谷君がギヤの故障にも負けず奮闘)下り坂で先頭を走っていた今日のリーダーの荒井さんは、後続車に気を使いすぎたため転倒、手と足にスリ傷を負う。又、古川さんは、転倒してもカスリ傷1つ負わないという妙技を。人のいない所で披露した。
山形市内を走った時、不注意の為13号線をそれたが、幸いにも、それた道が13号線につながっていたので助かった。
キャンプ地の決定までに役所の許可やら何やらで、以外と手間取った。食事後、当地にて酒宴を開いたが、予算の関係からかビールの本数が足らず気勢が上らなかった。
8月19日(金)晴
山形市内にて一日休養をとる。希望者のみ山寺まで走る。
8月20日(土)晴 山形市 – 檜原湖
4時半に起床したのは初めてであったが、全員協力してくれたお蔭で、朝食、パッキングとも順調にゆき、6時半、2晩世話になった山形市の公園を出発、快調なペースで山形から米沢に到着した。途中から品田君が加わる。船坂峠は全員好調に越え、関町にて休憩をとる。
西吾妻スカイバレー道をとり、白布高湯まで急坂を登る。ラストは大分遅れた。品田君不調。鈴木君、相変らず絶好調。空あくまで青く炎天下を大汗をかいて展望台に着く。最上川源流の標識のある所にて記念撮影。最後の力をふりしぼって1,402mの白布峠に向った。頂上において、バスの乗客より食料をもらう。夜のブタ汁はうまかった。
今日一日痛感した事は峠のある時は充分時間をとって出発するという事。
8月21日(日)快晴 檜原湖→猪苗代町
朝は、霧雨の時々降る空模様、今日一日の天気が危ぶまれたが、梅干しと秋刀魚のカン詰という簡単な朝食をしているうち、除々に好天の徴が見え、狐鷹森キャンプ地を出発する頃は、全くのカンカン照りとなる。
檜原湖は、サンサンたる太陽に映え、湖岸の緑と青い水の色が調和して素晴らしい。五色沼は、その名の如く、水の色が、絵の具を溶かしたようだ。くっきりした山なみを見ながらのダウンヒルは、まさにサイクリングの醍醐味であった。
キャンプ地の小石ヶ浜は、磐梯山の見える絶景の地。ところが、マムシが出るとか出ないとかで一騒動。夕食前の一泳ぎは気持が良かった。
8月22月(月)雨のち曇 猪苗代湖→糸沢村
5時起床。まだ昨晩からの強風が続いていた。音だけ聞いていると雨が降っているのかと思う程、激しい葉づれだった。
7時45分出発。若松市までノンストップ。市と猪苗代湖とは、かなりの落差があり、鶴ヶ城までの17キロの半分は下り坂だった。上三寄のはずれで雨が降りはじめる。ここで、主将から「皆、疲れているだろうが合宿もあと2日だから頑張ろう」と激まされ、全員元気に走った。
田島駅で夕食の材料を買い込み、糸沢村にて、村の寄合所を借りた。10畳2間、8畳1間で合宿の宿泊場所としては、最高の部類に属するものだ。今日はこれから合宿お別れパーティーをする予定。
8月23日(火)晴のち雨 糸沢村 – 日光市
昨日の雨もあがって晴。出発は雨中走行後の自転車整備に時間がかかり、かなり遅れた。村長さんに宿舎を借りた礼を述べてから、出発。山王峠が第1の難所であったが、全員何の苦もなく登る。先頭と最後の頂上到着時間の差は2 – 3分。中三衣より雨がバラつきだす。パンクで遅れた鈴木を除いて、全員そろって川治に到着。ここで昼食をとる。
川治より雨が激しくなり、栗原、品田が先発で日光へ向い、残りは間をあけ、かなりのスピードで今市までとばす。今市にて3年生の荒井さんが別れ、他の者はさらに日光市の旭館まで走った。全員、びしょぬれであった。
北国の日に – 綿貫
北国の日に
綿貫
茜に染まる西空と、黄昏に深く沈む十勝の荒野を残して、今日も北国の陽は果しなく重なる日高の山々に沈むのだろう。銀色の光る地平線はもう海の彼方に没して、吹き抜ける風だけが妙に空しい国境の地。
遠く望む灯もない狩勝の峠に1人茫然と立ちつくす者があるならば、それにひょっとしたら、何でもひどく昔の、自分の姿であるかもしれない。
阿寒の町の夕闇、暮れて行く湖を宿の2階の窓から見ていた者の耳に、どこからともなく聞こえてきたヴァイオリンの調べはメンデルスゾーン。旅人の胸に、思い出の町は美しく、又哀しい。
摩周の霧は尾根伝いの小径にも深かった。流れる様な乳色にカムイヌプリの怪姿はそびえ、カムインシュの島影は消える。ひざまずいたアイヌは胸に結んだ双手はほどこうともせず、なお瞳をこらして何物か凝視し続ける。神か。
網走はさい果の岬に近く、遠い山々を浮べて、ひろびろと拡がった湖。その原生花園には放牧馬が遊ぶ。水辺をさまよう牛に、透き通った陽光を受けて草に座すと、淡い可憐な花の香の上に青空がどこまでも遠かった。
砂丘に登って、オホーツクの目を射る紫紺に対す。北海の渚の灰色の砂丘の向うに秘境知床は横たわり、足元には赤い浜なすの花がただ1つ、潮かおる風に吹かれてゆれいてた。そして今、その淋しげな哀愁の内に、短い北方の日は暮れようとする。
大雪山の連峰は、洋々たる原始林の樹海の向うに残雪を光らせる。北国の旅は次第にせばまる谷の間を、層雪峡に向けて走った。大函、小函の奇観に始まって、銀河、流星の諸滝を配した数100丈の大岩壁が、幾10年の歴史を秘めて黒々と迫る。その寒い様な沈黙。旅人は立ち止り、やがて、そこに深い吐息を残して去った。あとには又石狩の渓流流が1筋、なお黙して行くだけだった。
台湾旅行前後 – 栗原
台湾旅行前後
栗原
先日のニューサイクリングに、やっと我々の台湾旅行記が載せられた。これは高田君の名筆による紀行文で仲々良く書けている。しかし今度の台湾紀行は、栗原が書くのであり、僕の日記に基ずいて、私個人の紀行文として拙い筆を採ることとする。
1966(昭和41)年2月21日、月
午前5時45分、弟におこされた。外はまだ暗い。昨日の夜、スキーバスから帰ってきたばかりで、まだ眠り足りない目をこすりながら朝食をとる。まるで小学生の遠足の時の様にパンがのどを通らない。「いってまいります」のあいさつも多少ぎこちなく、ていねいに頭を下げた。「もしかしたらこれが見納めか」という考えが浮ぶ。外は薄明るくなっている。昨夜の雨のせいか道路はしっとりと濡れて、空気もすがすがしい。少し暖かいせいか、冬の朝の厳しさよりも、春の朝のすがすがしさを感じさせる。
出航は神戸3時だ。それに間に合う様に、東京駅から新幹線に乗り継ぐ。快い振動を背中に感じながら、弟にハガキを書く。受験の最後の追込に入っており、出発前は、色々話すチャンスが無かった為である。
神戸は暖かかった。台湾では必要はあるまいが、日本の寒さが心配で着てきたアノラックも必要が無い位である。高田の自転車が置いてあり、間も無く彼も、日通から僕の自転車に乗ってやってきた。服部さんも山口さんも、山口さんは神戸元町の駅から、箱に入れた自転車を、タクシーも拾わずに、エッチラォッチラ引っぱって来た。御苦労様でした。やがて、まわりの人が、がやがやと1ヶ所に集まり通関手続きが始まった。
船に乗り込むやいなや、階段をズーッと降りて3等船室である。畳の敷いてあるゴロ寝のヘヤである。1角に4人分の席を占めると、階段をかけあがってデッキへ出て、まだ出航まで小1時間もあるというのに、早くもテープを持っている人達をながめる。待つ時間の長いあまり、テープの両方であくびをしている様にならない組もあれば、ハンカチで目を覆って泣いている年寄り組もいる。やはり船の出るのはムードのあるものだ。
飛行機だとこうはいかない。待合室で分かれ、フィンガーまで出たとしても、飛行機の中に入ってしまえば、誰とも分らず、そうこうしているうちに、機体は走りだし、離陸する時には、どの飛行機なのかさっぱり解からないうちに、ジェット音と共に煙の様に消えてしまう。その点テープを持ち合い、岩壁から離れるに従ってテープは伸び、船と岸との海にテープが落ち、人は手を振って別れを惜しむというのは、いかにも人間的に情緒にかなったものである事か!神戸の街の灯は美しかった。もう日も沈んで街は灯りで一杯である。
船室は、エンジンルームのすぐ上なので次第に熱くなってきた。夕食は御飯にうどんだ。
2月22日火、くもり後雨
朝飯は気分が悪くて半分しか食べられない。横になっても気分が悪いのでデッキへ出て、気分を直す。あたり前の事であるが海ばかりで何も見えない。小雨がパラついていて司会もそれ程良くない。
船室には、およそ40人程の人が寝ている。僕の隣りは那覇に帰るという。30前後の姉妹は、ミエコチャンという女の子をつれていて、船旅には馴れている様子である。ミエコチャンは船がゆれてもケロッとしてはしゃいでいる。12才の可愛い女の子だ。休みを利用してきた神戸大の4年生。大阪の高校生。すぐに親しくなれるのも旅ゆえであろう。1人ノンベエのオッサンは、酒を喰らって、赤い鼻をし、足相を見てやるからとそばの若い女の子をからかっている。あまり話題の無い客達は、まわりで、女の子のいやがるのや、しつこいオジサンの光った赤い鼻を見て、楽しんでいる。
夕方、甲板へ出ると、雨上りの北東の空にきれいな虹が見えた。船の位置は、佐多岬沖らしい。少し波も高くなり、風も出てきた。
2月23日水、曇り
朝からひどく揺れる。寝ていても体が上下へズッてゆく程だ。が昨日とはちがって、気分は何ともなく、少し揺れないと物足りない程だ。天気予報によれば、種ヶ島方面には強風波浪注意報が出ているそうだ。我々の船はちょうどそのあたりにいるわけである。朝メシを大急ぎで済ませて、1時間程の寄港を利用して奄美大島の名瀬の街に出る。田舎の街だが、ソテツがあちこちにある所などやはり内地とはちがう。郵便局で大あわてで3枚のハガキを書いて出す。日本だから5円でゆく。船まで強風の中を走って帰った。港を出ると又々揺れだす。ボートデッキに立って、船首を見ていると、大波にぶつかる毎に、白い波が左右に割れ、しぶきが窓に飛んでくる。豪快で1ペンに船酔なんか忘れてしまった。船が1人でこの広い海で苦闘している。そのファイトが、乗っている僕にも満ちてくる様だった。
昼食と夕食は4人とも、船酔いの人の分ももらって2人分ずつ平らげる。しごく快調である。夜は隣りの人の買ってきたウイスキーをコーラで割って飲んだら一杯で例のごとく真赤になって寝てしまった。気がついたら翌日の5時であった。
2月24日木、曇、雨
5時に目を覚すともう他の客は顔を洗っている。デッキに出ると、那覇の街の灯らしきものがズッと見えている。泊(とまり)港沖にもう着いた。親切な事務長さんに下船の手続きを早くすませていただいたので、お礼にクラブのペナントをさしあげてきた。自転車も無事受けとることができた。ところがキールン基隆行きの船はシケで26日でないと出ないときた。しかたがないので2日間島内をまわることに決めて、自転車を組み立てて、昼飯を食べに出かけた。ここで始めてドルを使う。1人35セントの昼飯の味は、どことなく日本とはちがう様が気がして満足であった。
那覇市内は車が多い上、右側通行なので大変気がつかれる。幸いなことに軍用の為道は大変良い。西の海岸づたいに、那覇、北谷(チャタン)、名護を通り、山田で5セントのパンをたべた。雨が降って来たので背良垣(セラガキ)の公民館に泊めてもらうことに決め、このあたりの区長の家へあいさつに行った所、何の風土病か、鼻がテングの様に大きい小父さんが縁側に出て来て、「よし」との許可をくれた。恩納(オンナ)までもどり、公衆浴場へ行き(5セント)土地の人達とわからぬ言葉に苦労しながら話しをした。夕食は30セント、明日の朝食分として、カンヅメやパンも買いこんだ。農協の売店の様な店で、土地の人はみなツケで買っていた。夕飯屋で那覇の平さんと親しくなり、我々の貧乏旅行のことをきいて、困ったら来なさいと名刺を下さった。この平さんといい、途中のパン屋の小母さんといい、沖縄の人達はみな親切だ。
公民館に帰って、アノラックを着たままシュラフにもぐりこんでいると、部落の人達が我々を見にやってきた。言葉の解からないのには閉口したが、話を聞いてみると、この公民館は、昼は幼稚園に使うのだそうだ。公民館の横にある、4本柱の上にカヤぶきの屋根をのっけた3m位の小屋は、何かお祭りの時に使うとの事だ。沖縄第一日の印象は米軍基地と、セコハンの自動車修理工場の様な店の多い事である。内地とちがって食堂なんかどこの町にもあるというのではなく、さがすのに苦労した。
明日は、安富會(アフソ)から東海岸へ出て那覇まで帰る予定だ。
出発してから直ぐに海岸でウンチング。日本を出て初めてである。眼前に開ける青い海と黒い島影をみながらするのは気持の良い事この上無し。さながらパノラマ便所である。
2月25日金、快晴
昨夜は、10時頃まで部落の人と話をしてシュラフに入ったが、明け方の寒さで目がさめてしまった。ここまで来て寒いとは!7時頃朝焼けとともに太陽が出てくる。快晴だ!
安富會から東岸へ出る為に、右へ折れ山の中に入る。山の中にコウキまで、ジープとGIが来ている。東海岸に出た所で、貝や石を拾い、タダの土産とするために、石までナッブザックに入れる始末であった。東海岸のライトブルーの海、青い空、白い雲と、まるで絵葉書そのままの影色が左手に開けている。日秀洞の見物は、ゴキゲンだった。10時からというのを9時から始めてもらい、あまり大きくない所だが、説明には幸喜さんという女の子がついてくれた。沖繩美人という程の色気もないが、健康的な明るいタイプの人だ。中でとった写真を送る約束をして(これは出来てなかったが)別れた。一路那覇に向けて南下し、石川の町までは、GIのオートバイと競走するなど、4人とも大いにハッスルして走る。
古座で昼食。午後は、西沢温泉という所で、「中部製糖」の工場を見学する。あのトウモロコシのような匂いと、砂糖の甘い匂いは独特のものだった。トウキビの収穫は12月から4月の間で、工場もその間だけとても忙がしくあとは機械の手入れ位だそうだ。今はちょうど忙しい時で、24時間のフル運転をしていた。100人程の人が働いており、トラックに山盛りにつまれたトウキビが工場に運び込まれ、大きなツメでどんどん工場の中へ運ばれてゆく。大量のトウキビを食った工場内では、切りきざみ、しぼり出し、煮つめて、黒い、甘いにおいのする液に仕上げ、最後は漂白して、白い砂糖となって出てくるのを、スコップですくいあげて、紙袋につめていた。
中城(ナカガスク)をすぎて南部へ行くに従って、軍用ではないので道路は内地と同じガタガタである。丘を越え、山を越え、道に迷い、やっと、第2次大戦の激戦地マブニの丘についたのは6時であった。
この丘からは南の海が、はるか見渡せ、21年前には、米軍の戦艦が点々と列び、間断ない艦砲射撃が続き、上陸用舟艇が海面をうめたことであろう。今はこの丘には沢山の慰霊塔が林立して公園の様だ。
建児の塔と黎明の塔を見終った時に、陽は、空を真赤に染めて、西の海に沈んだ。あたりは、静かである。我々だけであった。薄暗くなりだした路を一路那覇へ急ぐ。相変らずのデコボコ道の上、明りといえば僕の持っている懐中電灯だけ。対向車のある時だけ点滅して、我々の存在を知らせたが、ひどい振動で持つ手がしびれてくる。左右に持ちかえて、ひたすらに道を急ぐ。ギラギラと光るライトがまぶしい。
左右の草群からは虫の鳴くのがきこえてくる。内地なら、夏の夜というところか。やっと見えた街の明りの下で、ゆるんだヒモをしばり直していると、魚屋の小母さんが、「マアマア」といいながら冷たい牛乳をくれた。明るい灯の下でホッとした気分で飲むその牛乳のうまいこと。他人の親切が身にしみた時であった。那覇の手前の糸満で夕食をとり、10時近くになってやっと市内のエミコチャンの家、平良さんの家につく。何と疲れたことか!
泊る所の決っているありがたさをつくづくと思う。風呂に入り、第2夕食といただいて、平良さんと夜おそくまで話しあった。沖縄の複雑さの一端をうかがい知ることができた。快い疲れで一同やっと床につこうとした時、我々の室の戸を外からたたく女の人がいる。「今日は帰れなくなってしまったので泊めてくれ」というのには我々はびっくり仰天してしまった。
2月26日土晴、雨
夜の2時、我々の室に入って来た若い女の子は、隣りのへやの住人をたずねて来たのだが、わけあってそこへは泊れない。今頃帰ることも出来ないから、泊めてくれというのだ。協議の末、我々がシュラフで寝ている隣の室に入れることにした。我々はといえば、100キロ以上も走ってきた我々に元気の余っているわけがなく、まもなくぐっすりと寝入ってしまった。<汝、疑うなかれ!>
朝、目をさますと隣りもおきたらしい。山口、高田氏はまだ寝ているので、服部さんと、バス停まで小雨の中を送って行く。詳しい話しは色々あるが、マアそれは割愛しよう。何事もなかった様に朝食をすませ、守礼の門と博物館を見学に行った。雨もやんだ明るい太陽の下のそれは、琉球の歴史を忍ばせる様な暗い面を見つけだすことはむずかしい事だった。帰りに、内地からはいてきた、底のバクバクになってしまった靴を直し、荷物をまとめて泊港に行く。今日こそ船は出てくれるだろう。しかし又々、予定が延びて、5時出航となったので、国際通りを見物し、ラーメンをたべ、1ドルのやすいビニールシューズを買って、パクパクの靴とはおさらばした。喫茶店で音楽を聞き、手紙を書いてのんびりと時をすごした。
4時からの通関は、上手に立廻って、自転車はタダで積み込んでもらい、運賃もタダという様に、大変得をした気分だった。3等のゴロ寝船室は学生が多い。早大、青大、拓大、琉球大と、40名位いるだろうか。我々はもう旅馴れたもので場所を決めるやいなや、天井にロープを張って、シャツやタオルやナップサックをぶら下げた。今僕の頭の上には、それらのものがゆれている。沖縄よさらば。
2月27日日曇り、快晴
船の揺れでミソ汁をこぼしてしまった為、まだ、お尻のあたりがつめたい。
正午、石垣島に着く。快晴。海のライトブルーは、沖縄のそれよりも一層美しい。4時までの下船が許可されたので、さっそく自転車をおろして、観光案内所をおとずれて、川平公園に行くことにする。往復約40キロの道のりだ。山口さんは風邪気味で船に残り、3人で、よく晴れた南国の路を走り出す。舗装こそしてないが、良い道だ。右手の山には、キビやパインの畑がずっと見えている。日曜のせいか、子供によく会う。健康そうに日焼けし、よく遊んでいる。ものめずらしそうにながめているのは、我々3人はこの辺ではもうエトランゼであるらしい。
向い風にさからいながら、予定通り1時半に川平公園についた。ここはたいした公園ではないが、その昔琉球王朝へ貢物を積んだ船の出発地であったらしい。海岸は白い砂をしきつめた所で、200m程先の海に島がある。あのかげに船をつけたのだそうだ。茶屋でコーラを飲みながら、若者たちと話す。一見アンチャン風だが、話してみると素朴な好青年達ばかりであった。英雄「満慶山極英」の碑があった。
帰りは崎枝で休み、パイン畑を見物した。親切な小母さんと一緒に写真をとり、時期おくれ(パインの収穫期は7、8月)のパインを1ついただいてきた。大急ぎで巻にもどり、4人で大浜総長の生家をおとずれる。家の方は留守であったが、近所の人が親切に色々と話しをしてくださった。船に帰る前に、石垣市の高校に行き大浜先生の銅像をバックに写真をとった。像の台座に、「生れた所は問題でない云々・・・」の文句が彫んであるのは印象深かった。最後に自転車の手入れをして一日を終る。
旅は、日常とは異る様々な事を、眼の前に展開して見せてくれる。しかしそれを見、それを知るだけでは、旅は何も我々に与えてくれない。旅で得た知識を智慧にしなければならない。そうでなければ、旅の後には何も残らないことになってしまう。智慧とは自分の身についた、自分でそれとは気が付かなくても、自然とにじみだしてくる様なものだ。智慧が智慧とわかる様では本当の智慧とはいえない。旅は後に智慧を残してくれるようなものでなくてはならない。
2月の28日はいよいよ台湾に入る日である。これから先の台湾旅行は、台湾旅行記を見られたい。次に又我々が沖縄に現れるのは3月21日である。僕はそれから日本までの事を続けて書きたいと思う。
3月21日
昨日から基隆に来て出航を待っている。台湾ドルは、てっきり昨日出られるものと思って、土曜日に全部米ドルにかえてしまったので大変困った。70円の泊り代は米ドルを闇で換えてもらってどうにか払う始末である。台湾に着いた日にも寄った港西食堂で、土産にパインを買う。そこの小父さんが親切にもマンゴーやバナナも入れて港まで1かごもってきてくれたので、我々は悔いを残すことなくバナナやマンゴーを食べた。最もバナナは、台北に帰り、ついた17日に10斤、20円で買って来てホテルで食い、高田12本、山口、服部11本、僕は9本まで食べてダウンしてしまったから、バナナに関しては悔いは無いはずである。8時の予定が1時になってやっと出航。台湾役人のスローモーにはあきれた。最も積み荷も多少はあったが。
船は行きと同じ那覇丸、船はこれしかないから行きに乗り合せた連中がみな乗っている。金のないやつらばかりだ(我々もその1人だが)。疲れのせいか、船酔いする。助けてくれ!
3月22日火、晴
夜中に石垣島沖に着き、9時頃上陸、見るものは何もない。週間誌で、羽田と富士山の飛行機事故を知った。富士山の事故の方は、台湾の新聞でおぼろげながら知っていたが。
3月23日水、曇、雨
12時頃那覇に着く。ユースホステルに泊りすぐ帰りの切符を買いに行く。ストで長びいていた期末試験が4月位から始まるらしいので一日も早く帰らなければならない。夜もあまり外へはでなかった。
3月24日木、晴
自転車は又うまくタダで乗せてもらえた。しかし沖縄までの船で潮をあびて、チェーンはボロボロになる程さびてしまった。那覇丸で一緒だった連中の見送りをうけて、那覇港をでる。デッ歯の秋村という女子大生と一緒になったが、つまらない女だ。
3月25日
昼近く、桜島が見えてくる。いよいよ日本だ。鹿児島の税関は聞いていた通り厳しいものだったが、高田の脱税タバコもうまく見つからず、僕の葉巻も5本オーバーしたが関税は払わずに済んだ。荷物をまとめてチッキで送り、切符も買ったが、学割改正でひどく値上りしたのには驚かされた。我々の留守の間に、日本も変ってしまったナ。西鹿児島から19時50分の「城山」で大阪へ向う。東京へ。今夜はこの満員列車では寝られそうもない。
3月26日土、晴
岩国でやっとすわれる。汽車もこう長いとうんざりだ。今汽車は神戸にいる。出発の地だ。マリンタワーもみえている。あと30分で大阪、5時間で東京だ!
了
早同交歓会印象記 – 渡辺
早同交歓会印象記
渡辺
『天城峠』
この詩的な響きを持つ峠。私はその日、11月4日の早同交歓会一日目の日、不安と期待の入りまじったような気分でした。不安はこの峠、細くきついと聞かされていたためで、期待はいつか読んだあの小説の中を実際に走れることができるからであったのでしょう。
伊豆修善寺を出て田園の中を、路傍に赤く熟した柿の実のなる村落を通り過ぎると行手に天城七里をその中に抱く山々がはばむのが見えてきました。天城峠で思いだすのはあの期待に胸をときめかせながら峠をいそいだ青年と、旅情をそそるような絵姿の旅芸人の踊子。あの時のあの青年、あの踊子が越えたこの天城峠をいよいよ我々は越すのだ。
峠にさしか入るとその細い道は、なをなをその道巾をそばめ、いよいよ天城路は上へ上へと線を引き、ますます風景は自然へ自然へと、我々の前に展開していくので、踊子達が越えた日は、秋の山波を乳色にかすませるような雨の降る日でありましたが、我々は小春日和のその山々のいたるところに紅を散らしたような、紅葉が目に入る日に越えようとしているのでした。
私は雨でかすんだであろう山々のつらなりや、右に見える山壁に目をやりながら、白く塗ったような細い峠道を進むうち、私の呼吸は次第にその美しい風景をたのしませることを許さなくなったのです。前かがみの姿勢を更に折り、ただただ白く続く坂道がうしろに去るのを見るばかりで四方を囲む傾斜の急な山波など・・・。
だが相変わらず白い峠道は、黒々と茂る杉並の間を山腹を、ただ腹立たしげなほどに延びるばかりで、更には初めは暖かいと感じた陽ざしも肌に暑く、頭に浮かぶのは頂上のことばかりで、あの愛らしい踊子の姿を描いたあの小説の情景など、いつしかすっかり頭から消えていました。
峠道を登りつめるとトンネルがある。トンネルは長く暗く、私は前方の出口のくっきりと浮かんだ半円形の、貴重な明りにじっと目を凝らしながら進んでいかねばならなかった。出口の外にとびだすと、まったくあのような視界が突然我々の眼前に開けたのです。「峠道が稲妻のように流れていた。」とあるような。
『石廊崎』
若さに溢れた地。我々はすばらしい秋晴れの日の11月5日、この伊豆の最南端の地に着いた。途中で自転車を降り入江を左手にみながら徒歩でその小高い岬の先端に向かった。
進むうち、入江は次第に下方に見えはじめ、上から見ると山間の小さな湖のように静かで、その波のない濃い青緑色の水をたたえている。この入江の両岸を形づくるのは小高い山であり、秋というに、まるで初夏の装いをなし青々とし、更に驚いたことには満開の白い山桜さえまじっているのです。我々が会う人々も若い男女のなんと多いことか。別名この地をアベック岬と言われるそうで、新婚と思われる男女ばかりで我々、山の中を多く走って来た者にはなんともうらやましい限りで目の毒であった。同時に彼女等の着る色とりどりの洋服が我々の心を明かるくし、両校の親しさを増したのは確かであったように思われる。
岬の先端に出ると高い崖をなす岩石のかたまりに、松の密生した青が映え、まるで雄大な景色を描いた日本画のような、すっきりした美しさを感じた。
さてこの地でついに早稲田カラーを示す事件1つ。対岸の崖にいた我らが3年生、1人やをら立つやそのまま勇敢にも海に向かい…。これに返礼するが如く、又もや我らが3年生1人対岸に向かい勇然と立つや・・・。対岸よりの悲鳴と叫び。
『峠』
峠、峠、峠。早同交歓会最後の日、11月6日は名も知らぬ峠ばかり越した。船に乗っていた時間を除けば大部分峠、峠、峠。
早同交歓会の将来 – 藤瀬
早同交歓会の将来
藤瀬
今年の早同交歓会の責任者として、これまでの交歓会の歩みを振り返って見て、そこから今後の交歓会の有り方等について少し私の意見を述べさせていただきます。
今年、早稲田主催で行った交歓会は第3回目でしたが、第1回はやはり早稲田主催で、1昨年三浦半島で行われました。1泊2日で三浦半島を1周し、最後の日東京で盛大なコンパを行い、これが2回3回と慣例のコンパの基をなした歴史に残るコンパでした。コンパはさておき、交歓会の参加者は相方共12-3名であったかと思います。同志社はクラブ創立1周年で、参加者の中に初めてサイクリングをする人もいた程でした。早稲田の者達は、「なんだ同志社大したことないな」と感じたのは偽りの無い所でした。しかしそのお返しは次の年第2回の交歓会で充分にされました。
第2回の交歓会は同志社主催で京都で行れ、その規模、形式等、総ての面で第1回を陵駕し、気楽な気持で参加した我々は、ド肝を抜かれる結果となりました。京都を中心に3泊4日参加者相方25-6名で行われました。1年前とは見違える様に、充実進歩した同志社の見事な企画で秋の京都を存分に楽しむ事ができ、又、当時2年生であった鈴村君や私等は、「同志社に負けてたまるか来年はやるぞ」という気持になりました。同志社独自の規律、密な計画性等多くの事を学ぶ事が出来、真に意義ある交歓会となりました。
第2回に負けない様な交歓会にしようと努力したのが今年伊豆で行った3泊4日の第3回交歓会でした。その評価については、クラブ員それぞれが持っていると思いますので、ここではやめますが、これまでの交歓会の流れの中で新しいものとしては、総勢50名の参加者がッアー形式のサイクリングをした事にあると思います。第2回がベースキャンプ形式で行われ、今年がツアー形式と考えられる2つの形式を行ったわけですが、準備の点等を考えるとベースキャンプ形式の方が良いのではないでしょうか。
3回の交歓会の概略を述べましたが、第4回、第5回と続くこれからの交歓会について次に述べて見ます。
第1回は同志社、第2回は早稲田が、相手校から強い刺激を受け、クラブ発展の為に交歓会を利用し、そこにこの交歓会の意義が有ったと思います。それに対して第3回の交歓会は、両校共実力が伯仲してきて、前2回の様に刺激を与え合う事もなくなり、前2回で親しくなった者達が、1年ぶりに再会し、旧交を暖め合ったという感が強いようでした。それでも1、2年生は、京都にも俺達と同じようにサイクリングをやってる奴がいるという事を知って、サイクリングに対して自信を持ち、又「よし奴等に負けないようにやるぞ」という気持を持ってくれたと思います。
このように交歓会は、1、2、3回と回を重ねる度に、その意義、有り方も変化して来たのですが、これからの交歓会の有り方としては、第3回の様な3、4年生は旧交を暖める楽しい会に、1、2年生には、サイクリングを続け、クラブを発展させようという気持を起させる会になる事が望ましいのではないでしょうか。ただ、この1、2年生と3、4年生の間の交歓会への期待の差をうまく埋める事がこの交歓会を長く続けて行く為に必要な注意すべき点であると思います。楽しさだけを求めても駄目であるし、互のクラブのガの誇示だけの会となっても駄目である。ピリリとした空気と楽しい雰囲気の融合した会となれば早同交歓会は、野球の早慶戦の様に、長く続くと共に、学生サイクリングの中の最高のサイクリング交歓会となると思います。
来年第4回の交歓会は、同志社の主催できっと素晴しい交歓会になると思います。そして次の年は早稲田主催と、主催校が相手校の期待を裏切らない立派な交歓会を行い、この早同交歓会が永久に続く事を願って止みません。
早慶対抗レース参(?)戦記 – 守谷
早慶対抗レース参(?)戦記
守谷
先日、ボクは鈴村さん、木村君と共に平塚競輪場に愛車を駆って、ノコノコ出かけた。
オーブン・サイクリングが無事にしかも盛大に終ってホッとしている鈴村さんに、電話で行キマショウ行キマショウとシッコク迫って、8時半に環7の上馬交差点に集合と決定。金銭的問題から走って行くこととした。
去る9月30日以来、ペダルを全く踏んでおらず、やっとこの間のオープンサイクリングでシッコク再起の道を(?)歩み始めたばかりにもかかわらず、ボクは大胆不敵にも早慶対抗レースにオーブン参加することに決心し、更に図々しくも槐さんにトラックレーサーに乗りたいなどとホザいたのである。しかし、この決心も、環7を走っただけでバテてしまう己の体力の衰えを悟ると、脆くも崩れ、競技参加はおろか、厚木街道を走って平塚へ行く事さえ気後れを感じてしまった。
しかしどうにか無事に到着。(マル秘、鈴村さんは朝メシも食わずに駆けつけ、ハンガーノック気味、その結果厚木街道の昇り坂でバテていた。しかしエサを補給すると、直ちに回復。)
レース内容は、ルールを詳しく知らなかった為、記憶が混乱しているので、プログラムを紹介しよう。
第9回早慶自転車競技定期戦
昭和41年11月27日
平塚市営自転車競技場
1、4000m個人追技競走予選(タイムレース)
2、スクラッチレース予選(鈴村さん出場)
3、スクラッチレース敗者復活戦
4、1000mタイムトライヤル決勝
5、オープン1000mタイムトライヤル
6、タンデムスクラッチ決勝
7、高校1000mタイムトライヤル(これに出場予定)
8、4000m団体追技競走予選
9、10000mポイントレース決勝(インカレ方式の得点方法)
10、スクラッチレース5、6位決定戦
11、4000m個人追技競走5、6位決定戦
12、スクラッチレース準決勝戦
13、4000m個人追技競走3、4位決定戦
14、スクラッチレース3、4位決定戦
15、OBレース
16、4000m個人追技競走決勝戦
17、スクラッチレース決勝戦
18、4000m団体追技競走3、4位決定戦
19、4000m団体追技競走決勝戦
勝敗は新聞で御存知のように早稲田の圧勝であり、個々のレースを見ても優勝を早稲田のチームメート同志で争っていたことも1、2あったと記憶している。
さて、この日ボクの印象に残ったのは、トラックの路面が非常にキレイだということだ。まるで昨日舗装が完成したかの様にシットリと黒いアスファルトトラックは、ボクらの車の様にホコリだらけのタイヤの車が走るとタイヤの跡が付くほどであった。それ故、路面の吸着力は非常に強く、加速が非常に重いかかり、ブレーキもよく利く。走り出す時、思いきり踏みこんで、ハンドルバーを思いきり引くと、前輪がフワッと浮く感じがするほどであった。また最初、鈴村さんや木村君は各自の車でトラックに出ると、すぐ引き返して空気を入れていた。ボクは普断から空気圧を高くしているので、別に何もせずに走った。これは路面の吸着力が強いので、空気圧を高くして走らないと重くてしょうがないからである。
WCCの連中はボクの思う所では、空気圧が低いように思える。ボクラのクラブのようにハイスピードで走るには、もう少し空気圧を上げた方が路面抵抗が小さくなるし、ハンドルや加速も軽くなると思う。それに高い空気圧のタイヤは、小さな石を呼び込まずに弾き返すから、パンク防止にもなる。そこでボクは提唱したい。「舗装路では空気圧を2、3割アップして走ろう、」と。但し砂利道や悪路はハンドルがとられないように空気圧を低くして走ることは言うまでもない。
話がそれたので、トラックの話に戻ろう。バンクであるが、これは普通言われている程恐いものではない。急にハンドルを切ったり、急にブレーキをかけたりしなければ、更には他の車に押されれたりしなければ、落車してコロコロ転がり落ちることなど全然ない。但しバンクに入る際、及びバンクの上部に乗り続ける際には、ペダルを懸命に踏んで、せめてスピードが落ちないように、できれば、加速する余裕が欲しい。そうしないとバンクの下にドンドン落ち込んで行き、遂にはバンクから外れてトラック内部の芝生の上を走るというみっともないことになる。
ボクらは初め自分達の車で試走したが、車体が重くて、タイヤが太くて、従って加速が鈍くて、スピードが上らないので、次にはロードレーサーを借りた。乗るとやはりタイヤが細いのと車体重量の差だけ軽く走れた。しかしボクの好みの乗車姿勢は全くとれなかったので、即ち体にマッチしていなかったので、かなり走り難かった。
またトラックレーサーは鈴村さんが1周しただけであった。ボクも乗りたかったが、空転ができないので戸惑ったこと(無意識にペダルを止めると、後ブレーキを急にしかも強くかけた状態になり、車は一瞬接地力を失い、車体は強烈に振れ、ハンドルは全く利かなくなるのが観察できた)と、試走が昼休みの間を利用したので時間の都合で乗れなかった。鈴村さんの話ではトラックレーサーはロードレーサーより更に軽く走れたそうで、現にボクも鈴村さんの走るのを見てロードレーサーよりもスピードがでているように、更にフォームが安定しているように思えた。
さてオープン参加であるが、ロードレーサーで1000mを走った所、確か木村君が1分36秒5、ボクは全く恥ずかしいが、1分49秒もかかり、2人とも戦意消失して参加は諦めた。
言い訳けがましいが、東京から平塚まで走って来たので、かなり疲労していたことと、昼休みを利用して試走したので、昼メシが食えず、腹が減って力がでなかったこと、更にはロードレーサーのギア比がトラックにマッチしておらず、特にボクなど1000mを走っている間にチェンジレバーを引いたり戻したりして、フロントを上げるのにモタモタしたことなどが原因となって戦意を失ってしまった。
昼休みが終って試走ができなくなったボクらは、急に空腹感を覚えてグッタリし、レースをそっちのけにして昼メンを食いに出かけた。自転車部用意のオリヅメ弁定が足りなくて、ボクらは食いはぐれ、仕方なく町の食堂へ行った。しかし槻さんにはレーシングキャップを200円で買わされたり、タイムの計測やら何やら色々御世話になりました。昼メシを食い、レースに出ないことになってホッとしたボクらは気楽にレースを観賞することができた。
自転車競技は、オートスポーツと同じように、ダイナミックで、スリルとスピードにあふれた男性的なスポーツだと思う。但しオートスポーツのようにダイナミックなエキゾーストノートは聞けず、耳に入るのはタイヤと路面とが摩擦する音とチェーンとギヤの噛み合う、あのシャーッという独特の音だけだが。
ボクは思った。ボクらのクラブの連中もレースを1度見て、実際に走ると良いと。そうすれば、普通の路面で懸命に走る事が、トラックを走る事とは本質的に違うことが判かり、ファーストランに対する認識が変ってくると思う。ボクの考えではサイクリングはやはりジャリ道の、それも峠を懸命に登る時、その本当の楽しさを味わうことができると思う。
こんなことを考えながら、平塚競輪場を後にして、ボクらは、夕日の映える東海道を東京に向って走り去っていったのである。
(レース観戦記としては全くダメな文ですが、マアボクの印象記として受け取り、読んで下されば、ボカァシアワセダナァ)
サイクリング・トロフィー奮戦記 – 板橋
サイクリング・トロフィー奮戦記
板橋
サイクリングトロフィー。耳慣れぬ言葉だ。初めて聞く人も多いだろう。内容をまとめると、サイクリングに関するあらゆる要素、地図の読み方・方角や速度に関する感覚・交通安全・走行中のマナーなどを織りまぜた、総合競技会であると言える。主催者側の話では、その目的は、「サイクリングの紳士を作ること」にあるという。今後、この種の競技会は増々盛んになることであろうから、私達の失敗談をもとに、この日の競技の模様を紹介しよう。
昨年(41年)、中秋のある日、所は多摩丘陵の肩ぐちに当る小田急線・百合ヶ丘で第1回サイクリングトロフィーが開かれた。”第1回”、競技会の歴史のほんの揺濫期だ。早稲田からは、3人が参加した。鈴村さんと久世さんは、先輩のサイクリングマニアである中山さんの招待で、私は、試験で出られなくなった木村(淳)さんのピンチヒッターとして出場した次第である。代打といっても出るからには、少しは試験勉強しようと思いたち、1週間前に、5万分の1の地図と首っびきで王禅寺の辺りを2、30キロ走り回った。この時、都内から10キロと離れていない王禅寺という地に、東北の1寒村を思わせるようなたたずまいを発見して、ずいぶん驚いたものだった。都心から、危なく、糞おもしろくもない国道を通って郊外に出るよりも、近くてこれだけ鄙びた土地があるならば、サイクリングにはもってこいだ。
さて、その日、30分のペーパーテストの後、実走は9時きっかりに始まった。スタートの十分前に、コースを記した5万分の1の地図が渡され、2分間隔で出走する。私は、その地図を見たとたん、1週間前に調べておいたコースが5分の1ほど入っていたので、ワクワクしてスタートした。これならいけると思ったのだ。
しかし、そうは問屋が卸さなかった。地図が細かい上に、2m未満の山道まで通るようになっている。おまけに地形をうまく利用して、非常に起伏の多いコースで、しかも90%が砂利道である。更に、第2のチェックゲートでは、ゲート役員が意地悪く、「ここはどういうゲートでしょうか」と聞くのである。(正解!ゲート手前の電柱に貼ってある紙を読み、そのゲートで番号と名前を申告する。)このようにして、競技者には、心・身の両面から、動揺が与えられる。だから、道1つまがるのも思うようにならない。競技者が、正しく地図を読んでいるか否かの審判は、非常に厳しく、まるで神がかりにでもなったかのように、チュウチョなく正しいコースをとらなければ、そのゲートでの点は与えられない。
従って、良い成績を上げようと思うなら、コースの下見に5・6時間は費やさなければならない。コースを熟知することが、この競技会における最大のポイントである。
4時から成績発表。この時までは、私は相当の所までくいこんだのではないかと思っていた。特に鈴村さんは、ペーパーも良かったし、実走でも、ヒルクライムの途中でギアがトップに入ってしまい、3段階でダウン以外は、かなりの好成績であるように思われた。この日、ゲート役員として応援に来ていた諸先輩も入賞して当然と思っていたでしょう。いよいよ注目の優勝者の発表。
「1位Aさん」早稲田勢ではなかった。少々の失敗はあったから優勝は望んでいなかった。そうだ。もう少し後だろう。「2位Bさん」「3位Cさん」・・。JCA副会長の鳥山さんの重々しい声が流れる・・・。「10位Jさん」。鈴村さん、久世さんはまだか。「15位0さん」。入賞者の発表は終った。鈴村さんも外世さんも、そして私も入賞はしなかった。ざわめく参加者の中で、私は複雑な感情に打たれた。テレくささ、申し訳なさ、腹立たしさ、おかしさ、そんないくつもの気持が、ミックスされたような感情だった。参加前クラブの連絡ノートに書いてあった「参加者は、絶体に賞品を獲るように・・・」といった意気込みからは予想もつかない敗北だった。
まもなく、私達3人は先輩と別れて、駅前の食堂に入った。まちかれていたように、鈴村さんが注文した。「おねえさん、ビール」。鈴村さんは、私とはちがって、先輩からの使命のようなものがあったので、残念の情もひとしお深いのだ。久世さんと私も御相伴にあずかって、良い機嫌になった。この頃は、残念無念というより、おかしくてしょうがなかった。あまりにも徹底的に負けたからだ。
講評、解散のあと私達3人は、4年生の所へ行った。私よりも先輩のほうが、はずかしそうだった。中山さんは言った。「ビックリしたなあ」。ほかの諸先輩もきっと同じような気持だったことでしょう。
夜風にあたると徴かな酔いも吹っ飛んだ。来年はきっと雪辱してやるぞ。そう思ってラッシュアワーの世田谷街道を家路についた。最後に、実走の主なチェック項目をあげておく。
- 注意力テスト(道端の掲示を見逃さないこと)
- スピードジャッジ(1キロを時速18キロで走る)
- ヒルクライム(50m位の坂をどれ位まであがれるか)
- 交通安全(センターラインと一時停止)
などである。
想輪の記 – 鈴村
想輪の記
鈴村
私もやっと回顧を書く身になった。この1年私は自分の出せる力の全てを出して、サイクリングに専心して来たと思う。今この12月の忙しい世の中にあって「ああ1年が終っていったなあ」と言った、唯それだけの感じである。しかしながら、この際に1つ1つこの1年の想い出をアルバムを見ながら考えてみよう。
私が昨年の秋、諸先輩の後を引き受けまして、第4代目の主将をやることになりましたが、此迄の倶楽部はやっとその形を整えたといった感じであった。兎角、無理に無理をしてきたが、再び無理を承知で外部への発展をやらねばならぬと強く感じていた。
最初に私が2年間を通して疑問に思っていた事は、会長さんがもっと我々の倶楽部と接触していただきたいという事であった。
それがヒヨンな事から、現会長倩原先生においで願うことになりました。我々の本年の倶楽部活動が活気に満ちたものになったのも、その因は先生が実に我々の倶楽部のことに気を掛けてくださった事の賜物であると思います。今後とも、共に末長く歩んで戴きたい先生です。
大学の始まる前に、私は九州1周サイクリングを行ないましたが、ここに於て私自身にとって恐らく1つの転期を向えました。単独行により今迄不安と思っていた事が、改めて確められ、又その為後の活動を自信を持って行えるという確信を掴む良い機会を得ました。
そのサイクリング中、私は考えていた。唯単に自転車で走り廻るだけでは、勿論大学生がぶつかってゆくに値するものでない。
重い荷物と時間表を持って出発する事が、既に旅の良さを半減している。家の前より1つペダルを踏めばもうそれが始まりだ。都の雑沓を逃がれて、1人孤独を味わいながら、1踏み1踏み人世を噛みしめて行く。それも未だ晴天好日の時は本当でない。風が吹きまくり、雨の中をドシャドシャになって、又雪の中の寒さを突いて走る時、その時こそ最初の苦痛がいつの間にか「どうにでもなれ」という感じに変わってゆくのが意識出来る。この意識こそが、都会の虚栄、背信の渦巻く生活には必要なものではなかろうか。いづれにしても、物事をゆっくり考えられる中で走るのも実に良いものだった。
未だ早大紛争の未解決状態の中で新人募集が始まった。そして5月のなかばに、今年の新人歓迎コンパが開かれた。部員を前にしての話が始まると、彼等はじっと私の顔を見ていた。彼等は本当に私に附いて来てくれるかなと思った。
第1回のランは、今もはっきり覚えているが、相模湖であった。要領がお互いに掴めず、夕食を始めたのが夜9時過ぎになってしまった。新人の中にはラーメンを食べないと言いだす者がいて弱ったものだ。やがて授業が始まった6月になると、商学部以外の前年度の学年末試験が始まり、その為専ら商学部中心となり、全学の統率がどうしても難しくなり困った状態が続いた。しかしながら、この頃は企画の古川君が猛烈なファイトを見せて、色々な所へどんどんと引張って行ってくれた。今年より始まった土日を利用しての1泊ランは、7月に入りやっと軌道に乗り、気軽にテント生活をやっていった。兎に角合宿に入る前に部員に実力をつけようと、せっせと走った結果、今迄で最高の走行距離に達した。
その頃の私は、主将もへちまもあったものでなく、滅茶苦茶にやっていたなあと思返している。
合宿のメンバーも決まった。夏季学校の為、行けない人が多く残念であったが、秋田に集合する事になった。自分自ら統率して、何とかして無事故で行きたいと思いながらも、一方には何故か沈んだ気持があった。主将の気持というものは、直ちにクラブ全体に響くものである。やはりその気持がすぐに2日目に表われた。
私自身の当時の気持としては、合宿は楽しく適当にブラブラやろうと考えていた。しかしながら、それ以後の合宿は締めに締めたものになった。今合宿では、今迄のばらばらな走行法を改めて、徹底的にまとまって走るように注意してきた。この走行法も、当初は全く慣れずに走りにくいといった不満が多かった。私の気持としては、その走行法について相当自信を失いかけた時もあったが、常にその時に、これで押し通すべきだという考えが離れなかった。
合宿もなかばになって、自分自身に余裕がみえ始めるや否や、サッと目の前が開けるがごとく、これ迄の憂うつな気持が薄らぎ、1人1人の行動が手に取るように見え始めた。
この間にあって、今回の合宿の半分が雨降と、冷夏の東北の為、クラブ員も相当まいらざるをえない情況であった。私としては、それだからこそ?厳しい事を言わねばならなかった。
しかしながら、新人生諸君は只黙々と自転車に乗り、目的地に着くとテントを作り、食事の仕度を文句言わずにやってくれていた事が常に私自信の安堵感を高めていった。
走行中、1人後から、前を隊列を成してきちんと走っていてくれるのを、ぼんやりとしながら見ていると、本当に合宿を今やっているのだという気持がした。又このやり方で誤りがなかったのだと思いながら満足気に後から走っていった。
守谷のふくれた顔、栗原の得意気なパイプスタイル、荒井のカメラスタイル、板橋のチャンチャン帽、渋谷の独特な姿…。
この合宿の思い出が今再びよみがえってくる。3年間の内で私自身にとっては最も苦しい、楽しむ事の少ない合宿であったが、やはりこの合宿で得られた経験は、何事にも換えられないもので、外国旅行等をやらなくて良かったと思いました。
我々は常にまとまって生きて行かねばならぬ程弱い者だ。いくら1人で強がりを言っても、どの道、長途の人生である。1人だけで孤独に耐えられるものではない。時には孤独を味わい、又再び友人知己の社会で一緒に暮すのが我々だ。この巨大な社会を掴むのは1度には到底無理である。やはり自分自身を置ける場を作り、そこで安心して自らを鍛え、社会への基地を作って置いた方が良いと思う。
合宿に続いて行われたESCAラリーは、我々早稲田が当番校を引受けた。現在のESCAの消極さに針を刺す意味で、何事でも積極的に引受けてやろうと言った気持より生じたものでした。日光でのこのラリーは、全く合宿の成果を見せる良い機会であって、我々のスピードの速さは、他の大学の自転車部が舌を巻く程レベルアップしていました。又他の面でも、特に鈴木君の喰いっぷりの物凄さには、宿の女中さんも度肝を抜かれていたようです。もう1つのエピソードを掲げましょう。
ラリー終了後、我々は東大都立大の諸君と、東京迄突走った。最初の頃は、抜いたり抜かれたりであった。私は何かの拍子で、東大、都立大のグループに入ってしまった。流石に自転車部で、走る、走る、4人交代でぶっ飛ばしていた。私もこれが最後の長距離スピード旅行だと思い張切った。そんな走り方をやっている内、わが倶楽部の1人に追付いた。何をしているのかと尋ねたら、早稲田の者達はとっくに先に行ってしまっていると言っていた。それを聞いて彼等は「あいつはトラックに乗っけてもらって行ってしまったのだろう」と言っていた。私は内心やはりやるなと思いました。
秋をまたたく間に向えて、倶楽部全体の雰囲気も一層活気溢れるものになった。この頃になると、3年生諸君は勿論、2年生迄も、これ迄とはぐっと変化を見せ、しだいに後輩への貫録を見せ始めて来ました。
秋のメインエベントは、何と言っても恒例の早稲田同志社両大の交換会でした。
期間中はずうっとスカットした秋晴れで、しかも海と山という素晴らしい変化に富んだコースで行われた為、両校の諸君共に楽しんでいました。この交歓会については、言う迄もなく、藤瀬君が異常なるファイトを示し、その姿には1年生迄も「あれが本当の藤瀬さんの姿ですね」と言わしめた程でした。やはり自己の責任をひしと噛みしめて、全力を尽した結果である。
このようにして1年の行事は、終りましたが、私自身も常に倶楽部のあらゆる行事に首を突込み、自分に納得の行く倶楽部の方向を常に打出して来ました。
今や再び新しい世代がこの倶楽部を受け継ごうとしている。今年1年の所信の如く、専ら外部へ出ていった。又確かに再び無理をして来たが、これも発展への一階梯であると思う。
私があの阿片窟のごとき商学部地下、時には地下の参謀本部のごとき感じがしているが、しかしそこに入るや否や私は、これ迄の憂うつな気持が1度に吹飛び、再び自分自身の取戻す機会を常に与えられていました。
あそこで教わった事は、実に様々である。私が今特に感じていこる事は、皆私の同胞であるという強い意識をはっきり感じさせてくれた事です。この意識を持っていてこそ、自信を持ってクラブ員の行動を信じられたと思います。
我々の倶楽部も菅原先輩より既に7年有余になりました。そこにはそろそろ伝統というものが根差して来たことでしょう。良き伝統は確実に受け継ぎ、常にそれを単なる旧習だけにせずして、生き生きとした発展の中に、それぞれの世代がそれを生かして行って欲しい。
後輩よ!俺達の後をしっかりと固め、常にファイトを忘れず、何の権力にも屈服することなく、否、挑戦の心すらも持って、堂々と限り無き前進を続けて呉れ。
サイクリストとドライバー – 小川
サイクリストとドライバー
小川
徒然なるままに、日ぐらし硯にむかひて、心にうつりゆくよしなしごとをそこはかとなく書きつくれば、兼好の様な名文が書けるのであろうが、私如きが、いくら頭をひねった所で、しょせん・凡人の書く事だから、名文になろうはずがない。そこで思いつくまま、サイクリストとして見たドライバーの事や、ドライバーとして見たサイクリスト(自転車乗り)について書いてみたいと思う。
私が1年生だった頃は、我クラブにおいて交通事故は比較的少なかったし、実際に怪我を負う事などは皆無といってよいと思う。ところが、この1年間に、かなりの部員が、交通事故に会い、怪我を負ったのは、各人の不注意もあろうが、2、3年前に比較し、それだけ交通事情が悪くなったと言えよう。この中には、銀座のど真中で、靴ひもを直そうと歩道から頭だけ出して、タクシーにぶつけられ、怪我したなどという、はなはだ不名誉な部員も居るのだが。増々はげしくなる都会の交通地獄の中を生きぬき走りぬく為には、各人が注意力と反射神経を充分やしなっておく事が必要なのは、言うまでなかろう。
ここで我クラブの交通事故史(死ではない)の様なものを、たぐって見たいと思う。
まずは、私が1年の合宿において。快適な大宮バイパスを過ぎ、道は急に細くなった。それでいて交通量は多く、道のはしが4センチ程低く段違いになっていた為、自転車にとっては、実に走りにくい状態であった。私のすぐ後を走っていたA君、この段違になっていた部分にタイヤをすべらしたからたまらない。バタンと道の内側に倒れてしまった。キーというものすごい音。A君のすぐ後には泣く子も黙るジャリトラが止っていた。突然の事だったからか、又我ながらよくブレーキがふめたわい、とでも思ったのか運ちゃんは別にどならずに行ってしまった。もし、運ちゃんが、ちょっとの間でも、脇見をしていたら、A君は、今頃、本年度クラブラン出席率第1位なんて表彰されなかったであろう。
この事故のちょっと前のだが、車が脇道から顔を出して割り込んで来た。私が車を運転しているのならホーンをけたたましく鳴らしてあげるのだが、なんせ自転車のベルでは分が悪い。接触しそうな所をやっとブレーキをかけて自転車を止めた。むこうの車を見ると、これがバキュームカーであった。これでは相手が悪すぎると一早く退散した。
上高地を通って平湯、乗鞍岳に至る迄は、S君がハデに転倒して、全身すり傷をこさえた位で事故らしい事故はなかった。乗鞍岳からの急な下坂での事だった。下の方からバスが、エッチラオッチラ登ってきた。間をすりぬけるには道が狭ますぎるので、我が身の安全を思ったB君は、自転車からボンと降りた。しかし体が疲れていたのか、足もとがぐらついて、道路の外側に体がはみ出した。気がついて見ると、下は絶壁となっていて、落ちたらそれこそ命はない。バスの運転手もハッとした様だ。それからB君は平湯のキャンプ場に着くなり熱を出して寝こんでしまった。
当時の3年生から聞いた話しだが、自分達が2年生だった時、四国地方の合宿だったが、道路工事の現場で、ぬかるみにはまり、自転車どと倒れて、あやうくブルドーザーの下敷になりそうだった1年生も、その事故の後、キャンプ地に着くと熱を出し寝込でしまったそうだ。人間、誰しも危険に遭遇すると、その反動で、熱を出して寝込んでしまうものらしい。
この様に私が1年の頃は事故にあっても、幸運な事に、負傷したりする事は、無に等しかった。これが1年、2年たつと、ぐっと増えてくる。私はあまり、クラブランに出席しなかったし、事故の現場に居あわせた事は、まれなので、ここから書く事は、すべて、人から聞いた話ばかりであり記憶もあやふやなものがあるので列挙するに、とどまるがお許し願いたい。
- 現場は八王子。坂の下に信号があり、今しも信号が青に変らんとしていた。C君は下坂からの信号の青に変ったのを見て、そのまま加速して通りぬけ様とした。その時、左折車があり、衝突。自身怪我をし、自転車を損壊。よくある事故である。
2、D君は自宅の近くで、自転車に乗っていて、電柱と自動車の間にはさまれ、負傷。
3、E君は、2人並んで走っていて、車にひっかけられ、軽い怪我。
この他本年度の東北合宿の時に、道がせまくなっているのに気がつかず、そのまま真直に走ってガードレールに激突して負傷し、合宿参加を途中でとりやめた先輩と、そのあおりを食って後方車のF君が、追突した二重衝突事故や、2年前の早同交歓会の際、三浦半島で、同志社部員の引起した追突事故など、こう書いていると、自動車事故となんら変りがない様な事故が発生している。
以上、事故発生の日時、場所、内容、経過など、はなはだ不充分な記録であるけれども、一応、我クラブの事故史をつづってみた。もちろん、対自動車による事故ばかりでなく、自分自身による事故も含まれるから、対自動車による事故は、実際は少ないかもしれない。しかし、その事故の大きさ、死に直面すると言った点で、自分自身による事故に比較、数倍も危険であると言えるし、自分自身の不注意と、それが、対自動車との事故と重なったとき、かなりの怪我を覚悟しなければならないと思う。
交通事故は思わぬ所で起るものである。普段から気をつけていても、ちょっとした油断から引起される事は、皆充分知っていると思うが、自転車に乗っていると、例えば、交通事故を引き起しても、自動車の方が絶対的に悪いのだと考えている人が多いのではないだろうか。確かに車の方が悪い。だからと言って、大手を振って、街中を走る手は許されない。又、事故が起きた時、ドライバーは、補償をすれば、それで済むが、負傷した、サイクリストは、一生かかっても、なおらぬ事もありうる。
現在の日本の様に補償制度のあまり発達していない国では、法律的にどんなに車の方が悪くても、負傷した者の方が損する様に出来ているのだ。さらに過失相殺という制度があって、ドライバーが、負傷させた相手方に、少しでも過失があって異議を申し立て、それが認められると、それに見合う分だけ補償をさし引く事が出来るのである。これをサイクリストについて考えてみれば、まず、完壁に迄、正しい走り方をしている者は、少ないと思う。右折、左折する時に、手で合図を、しないで、急にまがったとか、少し自動車の通行帯に入って来ていたとか、サイクリストにとっては、ごくごく当り前に考えられる事が、過失として認められてしまい、過失相殺の対象となるわけである。
こう考えると、サイクリストが道路を走っているだけで、過失相殺の対象になっているみたいだ。確かに歩行者以上に自転車は、車にとって邪魔者だ。私も車を運転していて、そう思う。この間、自転車の正しい走り方の指導が、警察と交通安全協会の指導のもとに行なわれたが、そのうち、自転車も免許制になって、我クラブでも、交通違反でつかまった、なんていうのが出てくるかもしれない・・・。
さて、自転車が対自動車の事故を起した時いかに不利である事が、お解りになったと思う。自転車は、なんといっても、自動車の流れの中に入ってはならぬと思う。交叉点で直進する時も、左折車に対する用心から、必ず、横断歩道を利用すべきだ。自動車の滝の中に入らなければ、例え、穴に落ちて、ころんだって、すり傷程度ですむ。又追突事故もおきないわけだ。
最後に自動車の流れの中に入って、追突事故を起した例を12月10日の新聞からとってみよう。
現場は、横浜市内の交叉点の手前50米であった。先頭を走っていた車が進路変更をせず、突然右に寄った為、2番目の車が追突し、3番目のダンプ・カーがそれを避けようとして急停車したところへ自転車が追突したという四重衝突であった。その結果、先頭の車の運転車はむち打ち症、2番目の車に乗っていた親子4人はウインドーに頭を強打して重傷、ダンプ・カーの運転車は無傷、自転車はダンプ・カーの後輪に前輪をはさまれ、頭を荷台に激突し、頭の1/3がもぎとられてしまった。車の大きさによって弱者の悲しさを見せつけられた気がする。たった1台の車の方向指示違反で四重もの衝突を起こす大事故となったのは、よほど車間距離がつまっており、しかも、自転車を含め、相当のスピードで走っていたに違いない事が相像される。ダンブ・カーの急ブレーキは適切な処置として認められ運転手は第3当事者となったが、問題は急停車ではなく、車間距離確保を怠った点にあるのではなかろうか。故に車間距離に関する落度は自転車にもあてはまる。死者にに鞭うちたくはないが、自転車は車両とはいえ、全く、無防備脆弱なのであるから、自動車の流れの中には入らぬよう、十分自重してて欲しかったと残念に思われてならない。
読み返してみて、随分、くだらぬ事を、ごてごて書いてきたと思われるけれども、クラ部員諸氏が読んで、交通事故には充分気をつけよう、細心の注意を払って、楽しいサイクリングを味わおうと思って下されば、使った脳ミソも、原稿用紙も、インクも、むくわれます。
1つの提案(こうしたらもっとクラブが活発になるだろう) – 山添
1つの提案(こうしたらもっとクラブが活発になるだろう)
山添
新役員が決定し、来年から一頑張り願う訳であるが1つの提案をして卒業したいと思う。
諸君も御存知のように、一国の総理大臣は、正当に選挙された国民の代表者の頂点に立つ人で、その政策には国も選んだ以上協力するという条件が入っている。もちろん総理は責任のある国民の納得のいく、一部の人々より多数の人々の利益になる政策を推し進めるべきで、それには一致協力という紳士協定があるのである。
小さな会にしたって同じである。運営委員会という、総会という国会に当るものがあり、各委員長という内閣組織があり、それらはすべて会則によって運営されるのである。その1つの提案というのは、一致協力をより円滑に運びもっとクラブを活発にさせるにはどうすればよいか、という事の一方法である。一言で言えば、クラブ全員に責任をもたすという事である。
先ず主将はクラブ全体の責任をもつこと。各委員長に対して完全に仕事を分割して、実行させ、会則にはづれぬよう、学生の道にはずれないよう、サイクリングクラブ発展のために各委員長が動くかどうかを観察しているのである。その間各委員長の意思の疎通を図るのをわすれてはいけない。これは主将自らが音頭をとるのである。
次に各委員長は、その仕事全般に対して責任をもつのである。例えば、企画委員長を例にとると、主将を中心とする委員会の意見を参考にするのだが、企画に関する問題は企画委員長は責任をとる事にする。そして、そのやり方は自分とつねに行動できる秘書的役割をしてくれる人を1人そばにおく。これは1年生がよかろう。そして企画に関する命令はすべて委員長から出る形式にし、この対象はクラブ員全員とする。つまり、4月から3月までの企画を各自主将となったつもりで書かせるとか、どこか希望の所を4月の分は誰れと離れがやれ、5月は誰れといった風にどんどん全員の知恵を借りて、全員で盛り上げればいい訳だ。
そしてその集計は先ほど秘書になってくれた人にやらせて、運営委員会にその資料持参で出席、発言するのである。各委員長がすべてこうやるとクラブ全員が全体の仕事に関係する事になり、協力一致体制はますます、盛り上がるであろう。コンパを多くするのも結構だが、こういう点も、もう少し改善したらどうか?
今回の例でも、原稿を出していないのがいるという事実は、すべて主将に責任があるという事になる。しかしそれ以前に出してない人の顔をみたいのが本音である。そういう1つの責任を果せない人は、自分を指導する力がないのだと、私は考える。
ペダルを踏んで思うこと – 古川
ペダルを踏んで思うこと
古川
今年のクラブ活動のうち、特に楽しかったのは、2週間の試験が終ったばかりのときに行った、2泊3日の軽井沢合宿だった。軽井沢は、1年のときの中部地方合宿の際に通ったわけであるが、あのとき泣かされた、あの碓氷峠の仇をとってやろうと、張切って出かけた。
坂らしい坂といえば、大垂峠しか経験の無かった僕には、登れど登れど続く坂道に完全にノックアウトされ、なんでこんな苦しいサイクリングを始めたのかと、本当に死ぬ思いで、今でもあの時の苦しさを覚えている。
妙義山を左に見る横川に、あまり疲れずに着き、そこでガソリンを入れ1休みして「それ行くぞ」と、スタートした。1年のときに非常な急坂だと印象づけられていた為、最初からフロントを落したが、ちょっと走ると、それ程急でないので、すぐ上げた。カーブが183との看板を見て、1つ1つ数えながら登った。この事は登るのに際して随分と力になった。というのは、今どの位登ったか、あとどの位登るのか、が分っているのといないのとでは心理的に非常に違うものだ。1年のときは、熊の平で、もうずいぶん登ったから頂上はすぐだろうと思っていたのに、丁度半分だと聞いたときは、ショックで十分程寝込んだものだった。
実際、この碓氷峠は距離こそかなりあるが、勾配は、箱根などと比べると、ゆるく調子よくホイホイと登れた。1年のときに休んだ場所が次々と現われてくる。「アッここでアメをしゃぶってふてくされたっけ」僕はちょっと微笑えんでヒョイと通り過ぎて登り続ける。日蔭の場所を走るときは冷っとする程で、ほとんど汗もかかずにノンストップで頂上へ着いた。
やはり3年間無駄にペタルを踏んでいなかったわけである。思えば3年間実に良く自転車に乗ったものだ。中部地方の山々をあえぎながらよじ登り、根釧原野の地平線の果てまで続くかと思われる真直ぐな道を、限りなき前進を続け、又あるときは自動車にヒヤヒヤしながら東海道を京へ京へとひた走ったこともあった。
この3年間の体験から僕は僕なりのサイクリングを充分楽しみ、サイクリング観というものも、会得したつもりである。やはりサイクリングを楽しむためには脚力は、強ければ強い程、良いと思う。強ければどんなサイクリングでも、余裕をもって楽しめる。
やっとの思いで目的地にたどりつき、メシも喉を通らないようでは、たんにある地点から他の地点へ移動したにすぎず、移動のためだけならそんなに疲れて、自転車で行くことはない。わざわざ自転車で行くのは、移動の過程において、電車や自動車では得られぬものを得ようとする為だ。このことは皆さんも御承知であると思う。それに周囲の景色も目に入らず、ヘトヘトでかろうじてペタルを踏んでいるような状態では、事故に会う危険も大きいというものである。だからせいぜい足を鍛えて、どんなときでも疲れ切らない体力を養っておきたいものだ。
又、日頃の生活で僕らはよく、そのうち、ヤル気になれば出来るだろうと、難かしい問題に、真正面から取り組まず逃げてしまうこともある。しかし、本当にヤル気になっても出来ない至難な問題もあるものだ。
峠に挑むとき、ヤル気になれば登れるのだが、と少し苦しくなるとすぐに自転車を降りて休んでしまっていては、自分の最高の力を発揮し、更に力をつけてゆくことはできない。実際、苦しくて、もう駄目だと思いながらも、ちくしょうちくしょうと登り続けてゆくことは、大変に難かしいことである。1つの事を成し遂げる困難さを知り、しかしそれを成し遂げ、遂に頂上を極めたときの気持、これも皆さんすでに御存知のことであると思う。
力一杯頑張り抜く、いわゆる根性をもサイクリングは養ってくれると思う。体力的に得た物は勿論、この精神力も、これからの僕の人生において、いつか手助けをしてくれると思っている。
私の高原を走りまわった思い出・・・汗びっしょりになって挑んだ峠の思い出・・・僕は、これらを大事にしたい。
花巻から – 荒井
花巻から
荒井
雨、横なぐりの冷たい雨。「行こう!荒井、先頭。久世、松崎、俺は最後を行く。」路面は白く、ベッタリと光っている。車は少ない。寒い。
足は徐々に、相当なクランク運動をしだした。両腕は堅く、平行にハンドルに続く。まもなく、最前線を行く3人の自転車が気になってきた。「抜いてもかまわないぞ!」鈴村の声である。
ヨシ!
ヤッケの頭がうっとしいので取った。スリルが始まる。無我の境。
20m。
後を見る。いない。もう1度、確かである。
「抜くぞ!」
右手を大きく出す。中央に出た。数秒が過ぎる。左に入る。
1人。1人。そして1人抜いた。緊張は続く。どうかな、自転車は1列である。うまくいった。顔がほころぶ。
雨は少し静かになっていたが、田も、山も、空も、灰色の中にあって、静かであった。足も灰色で疲れていた。
「おさきに失礼!」
さっきの連中だ、春風のごとく、俺様の横を笑顔で通過している。
やったな!
しかしなぜか嬉しかった。
私の履歴書 – 山添
私の履歴書
山添
人の一生は
重荷を負うて
遠き道を行くが如し
大学の4年間を振り返ってみて、私自身、実にいろいろな事をしたものだと感心している。私は毎日、日経新聞の「私の履歴書」欄へ興味深く目を通すのであるが、人の生き方にはいろいろあり、各人がその生き方に対して苦しみ、悩みながら栄光の座についたもの、平凡なる人生を送るもの、又、努力むなしく転落したものもあり実にさまざまである。しかし、結果はどちらでも、その過程は、常にドラマチックで、その人にとっては素晴らしいかけがえのない苦しみ、悩み、努力であったのである。
そこで私は私の23才までの履歴書なるものを書いてみたいと思う。生れは昭和18年5月、当時、日本は戦争中だったらしく私にはまるっきり記憶にはない。記憶にないのは、矢張り「らしい」と書くより仕方がないのである。小さい時は気が弱く、ガキ大将とはならず、家で遊ぶ方が多かった。父母の若い時の長男できびしく育てられた。2人とも滋賀の出身で、父は小さい時からの苦労人でいわゆるお米のありがたさを知っている日本男子。ユーモアに富み、義理と人情に厚いくせに、きびしい人生を送っている。母は育ちの良かったせいか、少しわがままがみられるが、お人好しで日本女性らしいといってもよいタイプである。両人共、余りハイカラな所が見出せないので、その点で私も同じなのは仕方ないと思っている。お客人にはきちんとし、しかも堂々と卑怯なまねはせずという事で、間違えばすぐ横つらを往復ビンタをもらったものだ。
小学校入学当時は、まだ給食もミルクだけで、しかもそれが(当時私は京都、今の京都大学の近くに住んでいた。)進駐軍のものらしく、コップの底にカスが残るのできらいであった。入学して間もない6月に、父の大阪転勤で今の住所へ変った。その時、新入生の挨拶が教室で行われ、初めて人前で1人で喋ったのである。何を喋ったか忘れたが、今から思えば50人の聴衆であったのである。小学校ではまずまず優等賞をもらったり、衛生班長の私自身がハンカチ等々を持たず、廊下に立たされたり、又、ケンカの仲裁に入って一緒にやったりした。しかし何も起らずにすんだ。6年生にもなると、1ぺんに偉くなったようで、いばって歩いたものだ。しかしまだ給食だけは嫌いで、全部食べ終るのに30分以上かかり、昼からの掃除はあまりしなかった。いつも2人いて、もう1人の道畑君は、後日、大阪明星高校野球部の学生監督として評判になった友で、2人で話すといつも話題にのぼるのである。最後のシーズンを飾る運動会には、代表で優勝旗をもらい、学校リレー代表委員で大会に参加したもので、給食を食べなくても、結構いけたものだ。その頃から早稲田大学のファンになり大学生にあこがれを持つようになった。エリートは大学生で、大学で学ばなければ何もできないと思うようになり、角帽をかぶりたいと思った。6大学の全盛時代、長島選手のホームラン新記録達成は、テレビの前で興奮したものである。
中学に入ると、3日目に体育の先生から、校内でボール遊びをしていたため、大ビンタをくらわされ、中学というものは、よっぼどふんどしのひもをしめてかからないとえらい事になると思った。その心配は3ヶ月目にやってきた。1年生のくせに生意気だという訳で上級生からなぐられたのをおぼえている。
2年生の時、女教師を泣かした。というのは教室内で、よその家のカキを食ったというのである。事実、食ったのであるが、果して泣くほどの事であろうか。その時、女というのはつまらんと思った。男と女の違いが段々とわかるようだった。しかし、その結果、2日間程校長室にかんづめにされ、その時から校長先生に挨拶するようになった。彼は私の下手な絵をほめてくれた。しばらくしたら、遠足の時期である。秋の遠足は長野(河内)の観心寺である。私はつくづくいやになった。土地柄、京都、奈良へ行くのが多く、毎回お寺参りばかりである。友と一計を案じ、皆で遠足ボイコットをして、その日一日は、組対抗のソフトボールでもしてのびのびとしょうかという事になり、私が大将となり職員室へかけ合いに行った。「先生、お寺参りばかりいやです。ソフトでもしてのびのびやりましょう。あんな所は、年寄りの行く所や。」
という話だった。そしたら女教師が又、かんかんに怒り、職員室から出られないようにされ、1人1人説得しに廻り、私だけを残し、皆が行くようにしてしまった。折角いい所まで行ったのに皆うまく丸めこまれて、その計画はオジャンになってしまった。そうこうしているうちに、高校受験で、私立へ行かしてくれと頼んだが、家の者はうけつけず今の生野高校へ入った。先ず、クラブを考えた。中学時代ぶらぶらしていたので、3年間みっちりやってやろうという訳だ。
サッカー部は強かった。合宿も、我々の時から遠征形式で、和歌山、兵庫へ行った。ここでは、丸っきりサッカー中心の生活で、アルバムをみてもそればかりである。近畿大会出場、国体予戦準優勝、と輝かしい成績だった。丁度、2年も最後の頃、日本史試験で、組で白紙答案を出すことに決定。1ぺん教師をギャフンといわしたれという訳で(今から思うと、第2反抗期というやつだ。)いざ実行だ。運良く?私は名前まで忘れてしまって、私1人が主犯として呼び出しをかけられ、父兄同伴でみっちりしぼられた。その時の教師は、神主をしていたらしく、私に「それだけ勉強がきらいであるなら神様にみてもらってあげよう。」と家に来るように言った。私は「神さん、そんなバカな。これからの人を導く人が神がかりでどうするか!!」と反論そこで物別れであった。今から思っても、あの教師は本当に神がかりの、かわいそうな犠牲者であった。
このような反抗期があったため、私は浪人生活を送らねばならぬ憂き目にあった。卒業式が終った翌月4月に、1人旅立つ東京の学びの庭は、早稲田の予備校であった。私は、友からの餞別である大きな電気スタンドと、義換を携え大阪駅を発った。早くから早稲田になじむために、戸塚町の時計台の下で下宿するようになり、一生懸命勉強した。1年後の栄冠を目指して、あらゆる外からの誘惑に勝ち勝利を得た。その間に私は真の友を得た。同じ苦しみ、悩みを持ち、お互いに助け合ってゆく友、幡司氏と貞方氏である。
いよいよ角帽をかぶり最初に挨拶をしに行ったのは、新宿のおねえさん方である。当時まだ、早稲田の学生は受けがよく、我々のために祝杯をあげてくれた。入学試験受験当時は、商学部には行きたくないけれども、と思っていた所へ籍をおいているのも何かの因縁かもしれない。
サークルにはいくつも入った。会費は入ってからと思い、出来るだけ様子をみた。一言にしてつまらぬサークルが多かった。その中でサイクリングクラブだけが残ったのは、そこに先輩の方々の人柄に魅力があったからであろう。さてしばらくすると、大阪の連中は何人位いるのかという疑問から稲門会の幹事を引き受けて活動するようになった。しかし800人という大所帯ではまとまりがつかなくなり、生野高校稲門会から手がけ、下から盛り上げ作戦を作った。初代幹事長としての仕事は、母校への早稲田大学への進学指導である。10名の会員中、2人代表として選び第1回を行った。今では大講堂を借りて演説できるようになるまでに育った。10月には思わぬチャンスが舞い込んだ。自民党代議士の応援演説である。私は某政治雑誌学生幹事という事で、福井県で約40日にわたって、現代政治論をぶってきたのである。今は亡き薩摩先生の手足となって働けたのを大なる喜びとしている次第であります。
選挙期間中、キューバ危機などをみごとにさばいて、世界各国の信頼を得たケネディ大統領が暗殺されたのは、はっきりと記憶に残っている。世界は優秀なる政治家を失ったものだ。ジョンソン大統領がそういう点では人気が落ちるのも当り前です。いわゆる、頭がよく、育ちもよく、努力家でもちろん金もあり、そしてスマートであるのは現代政治家の模範とする所であると思います。
当時、私の面倒をよくみてくれたのは、選挙の学生参謀をやっておられた島原氏である。大いに感謝している次第です。その時つくづく感じた結果として、具体的な政志会発足となって今日に至っています。先輩諸君と共に結成に走りまわり、正式に2年生の正月に発足しています。つまり、国民一人々々がつねに政治・経済・文化の動きに目をやり、その時々に的確なる判断を下していかないと現代の政治を良くしようとしてもできない。現在、国会で言われている「黒い霧」の責任の大部分は国民にあるといっても過言ではないでしょう。我々の会もこの点にポイントをおいて行動しています。つまり、政治に関心をもたせる運動です。
当時、私の若さを諸先輩も買って下さったらしく幹事長に推されて、卒業後の私の活動の場ができた訳であります。実質的な活動としては、先ず我々が勉強する事が大切なので、幹事7人を世界各国に派遣して、政治体制はもとより、それを支えている経済、文化、風俗、習慣をも学びとり、現代社会に寄与せんとしています。
その間、2年生の10月にはオリンピック東京大会が開かれ、私もNHKまで直接交渉に出かけ、テレビ取材の仕事をやらせてもらい、アルバイトをしながら(約1200円位)各会場のフリーパスをもらったものだから、仕事の合間に見物させてもらった。つまり無料でオリンピックを見せてもらい、しかも昼食代兼オヤツ代をNHKから支給されたような結果になる訳だ。忘れもしない、閉会式の時、世界の若物が、自己のベストを尽くした、スポーツを純粋に愛している若者達が、女も男も、白人も黒人も、欧州もアジアも、ソ連もアメリカも何の区別もなしに肩を組んで、次のメキシコまでお互いに異国の地で頑張ろうと誓い合った光景。
諸君も御覧になったと思うが、実に素晴らしい事ですね。美しい絵を見たり、たくさんのお金をもらったりして、感動を得るのとスケールの違う素晴らしさでした。当日、私は新聞記者席でカメラの取材に就いていましたが、我を忘れて興奮したものでした。ただぼうぜんとして泣きたいようなうれしさ、喜び、皆もそうであったように・・・。つまりこれは皆が求めている光景です。泣きだしたいような喜びは世界平和の実現です。聖職である国連事務総長も計らずも、私と同じ境地であったに違いないと、今でも思っています。この時から私は、我がサイクリングクラブの1大スローガンは、世界平和と思うようになりました。3年の主将就任の時も話しました。世界平和のために微力ながら協力しようと。我がクラブも全員一致の協力により、盛り上がりをみせる事ができた事に、諸君にも大変感謝しています。特に企画の内藤君は私の片腕となってくれ、実質的な活動は全て彼に任していたくらいです。又、機械の得意な器材管理の中野君、渉外適役の服部君、又鈴村、栗原両君を中心とした下級生の盛り上がりは素晴らしいもので、当時どこのクラブよりも協力一致体制のもとで運営されていたと思います。
いよいよ3年生も終りに近づくと学費値上反対、第2学生会館の管理運営権問題で大学キャンパスは大きく揺れ動き、文学部では危く私もパクられる所でした。しかしその時痛感したのは、学生運動とは、矛盾している限りは、ブルジョアの息子や娘たち、ジャリの遊びに過ぎないということである。本当にもっと真剣に、世の大勢を考えている人々は、じっとこの時を静かに客観的に見つめて、将来に期しているはずだ。その人はどこにいるのかわからない。しかしきっといるはずだ。
諸君もそういう人達と交際を持つことを私は勧めるのであります。私の友人にもジャリの類がいるが、彼につねづね言う。「お前の下宿へ行ったら部屋は汚れている。会に払うべき会費も払わない。そして会の運営は巧くゆかないため、他の人に迷惑がかかる。つまり他人はどうでもよいという考えの人が、どうして一国を治める人になれるか?つまり人の批判をできるのか?自分のことが満足にできないのに、そんな大きな事を考えたって無駄だ。心の中にやる気があるなら、ほんの小さな事から出発せねばならぬ。」と。つまり、身を修め、家を正しく導いてこそ、天下国家を治める事ができるのである。
今までが私の本当の履歴書ですが、これからの履歴書は、私自身が作り出すことです。言いかえれば、人生は創造するのであります。尾崎士郎の人生劇場というのがありますが、人生を劇場におきかえてみますと、自分自分が主役をやり、演出をやり、舞台美術もやり、服装に注意して、立派な劇をみせるのです。その劇は人に喜びと感動を与え、1人何役かの重労働で努力した結果、素晴らしい演技者として認められ、より大きな舞台に出演する事ができるのです。そのうち相手役の良き妻が迎えられ、2人で又素晴らしい劇を作るのです。そのうち又、子役になる人もできるでしょう。自らが全てを知った舞台で、堂々と演技できる、主役になるようにこれからの履歴書を書いてゆきます。
自転車専用道路 – 中村
自転車専用道路
中村
僕が早稲田サイクリング・クラブに入ってから8カ月たった。あまり真面目にランに参加したとは言えないこの僕でさえ、その数少いランからサイクリングの楽しさは、十分過ぎるほど認識できた。特に、キャンプをしながらの泊りがけのサイクリングの楽しさは、抜群であった。僕は、ペダルを踏みながら「欧米では、週末には家族揃ってのオートキャンプが盛んだというが、日本ではまず、サイクルキャンプから普及させたいものだ」と考えた。
しかし、サイクリングを普及させるについては、種々の問題や条件がある。まず、もっとも大きい問題は、自動車の増加に伴う、交通事故の危険である。この点は、先日(12月17・18)の自転車に関する調査の時にも多くの人から指摘されたことと思う。「危いから・・・」の一言を言われると、今の僕達には、どうしようもない。それは、サイクリングをやっている我々が、交通事故のこわさを一番良く知っているからだ。現に、僕がWCCに入ってから、わずか8ヵ月の間に交通事故を起したサイクリストや、起しそうになった人達は、かなりの数にのぼると思う。だから、「いや、安全です」と言い切る自信が僕にはないし、おそらく多くのサイクリング愛好者にもない。
そこで、僕は皆が、もっと安心して気楽にサイクリングを楽しめるようにするために、自転車専用道路の建設を強く訴えたい。41年12月11日付の毎日新聞に、僕と考えを同じくする小林淑谷さんという41才の教員の方の投書が載っていた。小林さんは「自動車専用道路がどんどん作られている半面、歩道や自転車の通る道が次第に狭くなり、消えてゆくが、都市生活の健全化は、自転車専用道路の制定にあるのではないかと思う。未成年者にむゃみと機動車を与えるよりも、サイクリング専用道路を作ってやったら、どれだけ青少年の健全化に役だつであろう。自宅から地方や山岳部へ何の不安もなしに行けたら、子供たちはどんな愉怪な思いをするだろう」と、自転車専用道路建設促進を訴えている。
僕は、これと同じ声を今度の自動車調査でもずいぶん聞いた。「この辺では車が多くてネー。もっと安心して走れるところがあれば体の為にも良いからやらせるんですがネー」「いなかに帰った時は、子供と一緒に自転車を借りて走っているんですよ」等々。
これらの声から察して潜在的サイクリング人口は、かなりあると思われるが、それらの人々の多くが、自転車によってその楽しみを奪われているというのは、なんとも残念なことではないか。
アメリカ・ヨーロッパなどの先進国といわれる国々では、自動車が普及すると同時に自転車も普及し、さらに自転車専用道路が整備されている。現在も、オランダに3万キロ、西ドイツで9千キロが建設されている。自動車が発展しすぎたアメリカでは、逆に自転車熱が高まり、故ケネディー大統領もジョンソン大統領も熱心に自転車を国民に勧め、10年計画で33万キロの自転車専用道路が建設されている。ようやく先進国の仲間入りをしようとしている我が国が、自転車専用道路に無関心であってよいものだろうか。
我が国でも、おくればせながら41年9月20日にようやく自転車道路建設促進協議会が発足し、これから運動を大々的に推進しようとしている。交通事故の危険にさらされ、排気ガスを吸いながら走るのは、もうご免だ。我々早稲田サイクリング・クラブも、ESCAを通じて、あるいは独自ででも、この運動を支持して、我々サイクリストを始め、国民の誰もが安心してサイクリングを楽しめる日が一日も早く来るように、立ちあがろうではないか。
オープンサイクリング裏話 – 品田
オープンサイクリング裏話
品田
11月23日のオープンサイクリングは、46名もの外部参加者を加えて盛大に行われた。こんなに大勢集まるとは予想していなかったので、全く驚いたが、朝日新聞の「読者のひろば」に出したのがてきめんの効果を表わしたようであった。新聞紙上に載る前は10名強しか申し込みがなくて大変苦労したものであるが、今回はその辺の苦労話を詳細かつ多少くずして書いてみようと思う。
まず初日に勧誘に行った学校が、跡見学園、共立女子大などであった。菅間さんの車で行ったのだが、この時、非常に、というより異常に活躍したのが、3年生の高田さんと、2年生のいわゆる「Hグルーブ」と呼ばれる田北、守谷、品田などの人々であった。特にその道に関する限り、圧倒的に他をひき離している田北氏は、強烈なるファイトをもって、くどきにかかっていたが、そのかいもなくついに今上の夢と消え散ってしまったのである。
翌日は、守谷、板橋と一緒に今度はテクシーで女子大めぐりをはじめた。本日の「1番バッター」は、千歳橋を仲人役に、我が校と恋人関係にある「日本女子大」であった。フォークダンスクラブに行って当日踊ってもらえないかと頼んでみたが、「その日はだめよ」とにべもなく断わられた。守谷、板橋、品田の全役員、直ちに校庭に出て、数10秒間にわたる協議の結果、「ドタマにきたから、この学校で勧誘するのはやめよう。」ということに満場一致で決定したので、早々にひきあげた。
次は、渋谷を根城にして、その近辺の女子大を狙うことにしたので、山手線に乗り込んだ。渋谷駅を降りて玉電に乗り、三宿にある「昭和女子大」に向かった。校内をうろつき、女子学生にブリントを配布しようと3人で進んで行くと、ぶったまげたことに、何と逃げようとするではないか。ここにおいてまたまた我ら3名、策を練った結果、機先を制してプリントを渡すことにした。
そうこうしているうちに、用務員のオッサンが出てきたので、自治会のありかを尋ねると、我々に異常な挙動を認めたのであろうか?教務課へ行って教授みたいなのを1人連れてきた。サイクリングの件について誠実に説明したのであるが、「当校にてはそのようなものは1切自治会に扱わせないことになっている。」といって受付けなかった。自治会というものが学校の全く管轄下にある点で、この学校の特徴がよく出ていた。しかし朕ら、ここにおいて人生の大教訓を発見せり。「女子大にて断わらるるは、女性にふられるが如しと。」
さすがの守谷氏もガックリと首をりなだれ、あたかも、己1人が誰かさんにふられたが如き様相を呈していた。3人とも、精神的、肉体的に全く疲労困憊して、しばらく渋谷のハチ公像の前に放心状態でこしかけていた。
もう町のネオンがひときわ目立つ時刻になっていたが、最後の追込みとばかりチンチラカンチラ渋谷の町を歩き出した。目ざすは「実践女子大。」実践のおねえちゃんが横目でにらむと期待していたが、まことに遺憾ながら、さようなことのなかりせば、道ゆく人に尋ねながら何とかたどりついた。実践の自治会は、スムーズに諒承してくれて助かった。
さてさて、オープンサイクリングが翌日に迫った22日、皆で自転車運びをしてから、再び菅間さんの車で2度目のコースの下見をすることになった。乗り込んだ人は運転手の菅間さんと私を除いたほかは、田北と落海であった。再度登場したH路線の要役、田北氏はその名に恥じず、車中で猥歌を歌い、運転手を困らせていたが、三鷹を過ぎてからは発作が止まったようであった。9時頃、狭山湖について下見をしたが、時間も遅かったせいか、落海は頭が痛くなるし、田北は持病がぶりかえすし、菅間さんも運転疲れで、頭ガイコツにガタガタきていた。あまりの惨状を見るに忍びなくなった私は、菅間さんと運転を交代したが、あまりにも遅転がうますぎるとのことで再度の交代を余儀なくされた。
家に帰ったのが11時半を過ぎていて、その後も翌日の企画やゲームを考えたりして、とうとう朝まで、一睡もできなかった。
編集後記 – 上杉
編集後記
上杉
部誌「峠」第4号も無事発刊の運びとなり、編集責任者としてこんなにうれしいことはありません。思えばこの1年、何もわからぬまま、ただ夢中に自分の務めを果してきたように思います。
今ここに最後の仕事が出来上り、ホッと一息ついて今までの事を顧みると、充分にその責任を果したような気もする反面、まだまだ不足であったような気もするというのが、本当の所です。しかし結果はともかくとして、1年間、編集という仕事に従事できたことは、私にとっては非常にプラスであったと思います。たしかに時間的には手間のかかる仕事でしたし、1度に10数枚からの原紙を切り、あるいは原稿を集め、それを構成し、校正することは大変なことでした。それだけに、完成した時のうれしさは例えようもありません。
それに編集という仕事の性質上、その結果が印刷物として手もとに残ることも、他の委員の味わうことのできない喜びではなかろうかと思うのです。それに加えて、今年は編集の仕事に絶対必要である鉄筆、ガリ版を購入し、それに卒業生の記念品として謄写板を寄贈していただいたことの喜びも又、他のクラブの謄写板を遠慮しながら借り、丹精込めて切った原紙が謄写板が古いばっかりに、きれいに刷り上らない無念さを知っている人だけが味わえるものだと思うからです。
このように述べてくると、何か私1人で編集をやったように聞こえますが、御承知の通り、クラブ員諸氏の大なる協力が得られたからこそ、まがいなりにもその責任を果すことができました。皆さんに深く感謝する次第です。同時に、編集という仕事は、諸君の協力なしでは決っしてできるものではないという事を記して、今後も諸君の積極的な助力を願いたいと思います。
最後に、峠の作成に際して忙しい中を御協力いただいた鈴村、小川両先輩、そして板橋君に心からお礼申し上げると共に、暖かく援助の手をさしのべてくださった、東京8社グループの各社、およびアルプス、サンノーの両社に対して、感謝の意を表します。
Editor’s Note
1966年の出来事。昭和41年。
第8回日本レコード大賞 1966年 霧氷 橋幸夫
1月。ウルトラQ放送開始。常磐ハワイアンセンター開業。
2月。
3月。日本の総人口が1億人を突破。
4月。メートル法完全施行。日産サニーが発売。
5月。時代劇『銭形平次』が放送開始。
6月。ビートルズ来日。袴田事件。
7月。都立高校学校群制度開始。ウルトラマン放送開始。
8月。黒い霧事件。上越線の新清水トンネルが貫通。
9月。巨人が2年連続のセ・リーグ優勝(V2)。
10月。江崎グリコが「ポッキー」を発売。
トヨタ自動車がカローラを発表。
12月。核実験成功国に核武装の権利が与えられる。
映画、男と女。
WCC夏合宿は、「 東北地方 : 秋田市から – 栃木県日光市まで」でした。
=====
こんにちは。WCC OB IT局藤原です。
鈴村主将の弁にもありますが、クラブ活動が、従来に増して活発に行われ、多方面に大きな足跡を残した年だったと思います。合宿、早同、オープンなど、この時代に既に完成していたのかと思うと、歴史の積み重ねに驚かされます。
当時の文章をWEB化するにあたり、できるだけ当時の「雰囲気」を尊重するよう心掛けたつもりです。
文章と挿絵はPDF版より抜粋しました。レイアウト変更の都合で、半角英数字、漢数字表記等を変換していますが、全ての誤字脱字の責任は、編集担当の当方にあります。もし誤りありましたら、ご指摘をお願いします。
2025年3月、藤原
Copyright © 2025, WCCOB会