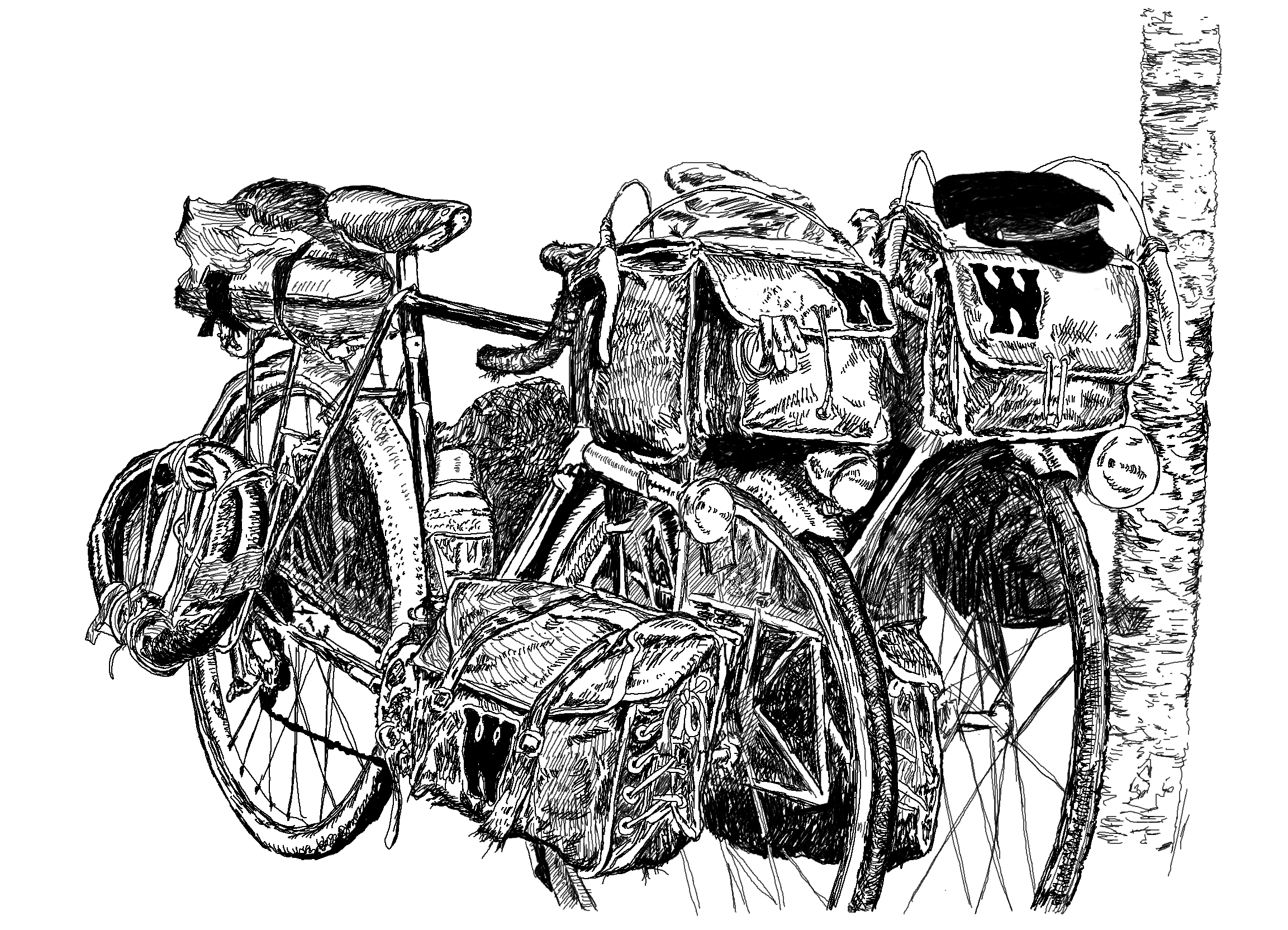待つ – 小林
待つ
商学部3年 小林
ドアの外に、階段を昇り、僕の部屋の方へ歩いてくる足音に気がつく。一体誰だろうか。まさか、あの人じゃあ…。しかし、その足音は、僕の部屋の前を通りすぎ、しばらくして隣の部屋のドアのチャイムが鳴った。
部屋には、電気ストーブが、圧倒的な寒さの中で、か弱く、しかし我慢強く、わずかな暖を送り続けている。ステレオからは、コルトレーンのサックスが、その激しい情熱を抑えつけるかのように、ボリュームを絞って、かすかに僕の耳に入ってくる。幻想世界の漂流。窓の外には、深い闇が、僕以外の全ての存在をかき消そうとするのか、びっしりと厚くはりついている。周囲の窓から漏れている淡い灯りが、まるで黒い海を隔でた、果てしなく遠い街並の灯のように感じられるのは、一体どうしたことだ。苛立ち。この部屋の、この張りつめた空気を破ってくれる人がいるなら、僕はわずかでも心を開いて話すことが出来るだろうし、どんな女でも暖かく抱けるような気もする。
僕は、自分の部屋を出る時、部屋に帰ってくる時、必ずといっていい程、郵便受けを覗(覘)いてみる。もしかしたら、誰かから手紙でも来ているんじゃないかと思いながら、しかし、いつでもそんな心の動きは押し殺し、いかにも自然に、いかにも単なる習慣であるかのように。そして勿論、1通も来ていなくても、その落胆も、失意も、また同じようにすべて否定し平静を装う。自分で自分の演技を意識しながらも、後には、自嘲の笑いが待っているだけだ、ということを認めながらも、演技せざるを得ない。
「待つ」ということが、人間の愚かさ、弱さだ、というような意識が、自分の中にあるのだろうか。これこそ愚かな自尊心じゃないか。そんな内部の葛藤の最中にも、いつも何かを待っている自分。一体、僕は何を待っているのだろう。形も定かでない、もやもやした、漠然とした何か。今の自分の社会にそれ程悲嘆している訳ではないのに、それでも、もっと明るくて、暖ったかくて、華やかで、素晴しいものを、とただ待っている。
じっと待っていることに耐え切れなくなったのだろうか。いつしか、繁華街の雑踏の中で、人々の流れに身を委ねている自分を発見することがある。しかし、いつもそうだ。苦い想いと、空虚な幻影を抱いて、重い足をひきずりながら、また自分の部屋に帰ってくる。むなしいか。わびしいか。いっそピエロにでもなって、「ああ、人生なんて」と嘆いてやろうか。
太宰治の「斜陽」の中で、彼は、かず子に次のように言わせている。「待つ。ああ、人間の生活には、喜んだり怒ったり悲しんだり憎んだり、いろいろの感情があるけれども、けれどもそれは人間生活のほんの1%を占めているだけの感情で、あとの99%は、ただ待って暮しているのではないでしょうか。幸福の足音が、廊下に聞こえるのを今か今かと胸のつぶれる思いで待ってからっぽ。ああ、人間の生活って、あんまりみじめ。生まれて来ないほうがよかったと、みんなが考えているこの現実。そうして毎日、朝から晩まで、はかなく何かを待っている。みじめすぎます。生まれて来てよかったと、ああ、いのちを、人間を、世の中を、よろこんでみとうございます」。
来る当てもない何かを、人間は一生持ち続けているのだろうか。
春の日の独言 – 吉川
春の日の独言
法学部2年 吉川
春が来た、外は春雨。昨日はうぐいすが鳴いた。早稲田合格にいっそう春の日ざしがうれしかった1年前、そしてぬくぬくと暮らす1年後の自分。しかしやはり春が来る。その春の暖かさにつられ、頭もおかしくなってくる。そんな頭をふとよぎるのは、きっとまともな事じゃない。春が人を狂わせ、狂わされた人間は、春が好きだという。こんな頭で、果して何が書けるのか。書いてみなけりゃわかりゃしない。この春の日に狂いながらも考えよう。
ふと心に映る1人の男は、川の流れに身をまかせていた。実に気持ちの良い暖かさがあった。泳いでいる、泳いでいる。自然の流れにはリズムがある。きちんと流れに乗った波のやる事は、手の届く水を如何に消化するかである。そうだ、それでいいのだよ。疲れたら、力を抜き、流れるままに、身を置こう。目に見えぬゆったりとした流れ、だが確かに流れてる。流してくれる。泳ぎたくなったら泳ぐがいい。流れは、そんな気まぐれも包みこんでくれる。
恐る恐る飛びこんだ流れの中、その水はすぐに彼になじんだ。泳ぎを覚えた彼は、ある時は全力で泳ぎまくり、へべれけになり、またある時ははしゃぎ、その水の楽しさに我を忘れた。この流れの中で四季折々の水を味わい、ひとつひとつ思い出を手にした。だんだんふくらんでゆく体験。漠然としていた流れがより密なものになってゆく。もう水は完全に体に浸みこみ、生活の1部となっていた。彼は世界を広げた。確かに1歩、世界を広げた。
しかし、この流れの水の住みやすさ。流れの向きは変えやしない。水から顔を出しもしない。この安定した流れに、ただ乗っていることが次弟に耐え難きものとなる。黙っていても流してくれる。同じ流れるのなら、必死で流れよう。あえて全力で泳ごう。充実感が待っている。大きな流れの中での1人の力など高が知れている。それでもあえぐ。
素適な流れの中に居ながらも、やはり出てくるアマノジャクな心が、考えが…。一定の速度を保ち、定まった溝を流れてく。その流れに、あえて抵抗したくなる。何食わぬ顔で、流れの中だけに居る彼。耐え難き姿と精神。そんな流れに背を向けて…。
僕は、昔から団体競技で育ったクラブ人間だった。そこには具体的目標となるものがあり、ひたすらガッツあるのみ。当然必要な協調性を大切にする。毎日の生活もクラブ中心になる。封建的とも言われるが、より密な縦の関係、力強い流れの中で力一杯手足を動かしていた。きびしさに黙って耐えながら、その情熱に全てをかけていた。
僕のクラブ入部動機は、「それまでのクラブ生活の転換」である。自転車がどうこうという気は、いまだに少しもない。それ故、早くに水に親しんだとしても、それは良きクラブ員であるためのみの条件である。決して良きサイクリストへの道を歩もうとはしなかった。住んでいる土地柄、自転車は必需品、坂を登ることもあたりまえ。そんな僕が高級パーツを云々する気がないのも、当然といえば当然。
頼りになるは、自分の体だけ。自転車を甘くみてる。馬鹿にするな、と人から言われ、がしかし、クラブで乗るまでスポークが折れる話など聞いたこともなかったのである。こんなに面到を物とはつゆ知らず。金をかけたもの程、故障が多い。1人反発して、そんなこともつぶやいた。
峠越え。長年しみついた汗を流すことへの感覚は、ただひたすら。登り切ること、足を動かすこと。ムチを打ち体力の限界への挑戦。始め体力、あと気力。全て体力に勝るものは気力なり、の精神主義。峠の途中、何度か経験した気力の消えかかる時、再び灯をともした。自分に「やったぜ」と万歳をしてしまった。そこには自己満足の陶酔がある。峠越えの真髄かとも思う。
しかし、僕にはきびしさを人に強いることはできない。我がクラブでの自由は個人にある。早大サイクリングクラブという、集団の存在価値がある。様々な目的と理想を持って集まった友達が、ランにおいて行動を共にする。統一された目的はない。それらがクラブを組織、運営してゆくということだけでも大変なことだ。それぞれの個性を尊重する。強制もない。だからこそ、ひとつのランを成しとげる意義も喜びも大きい。
マンモス大学におけるクラブの効用は、一般的にも言われている。そして、それは何よりも身をもって感じ取ったことだ。夢中で過ごした1年目。甘えだけで済んだ1年目。そうして金も出てゆく2年目は、これまでの体験を如何に生かしていくか。力を、そして情熱を燃やすのはこれからだ。けれど、揺ている。
流れ流れて、年々伝統の重みは増してゆく。組織が大きくなる。流れを変えることは困難になる。ひとつの流れの上を適度の力で泳ぐことは楽である。与えられたものをただこなすのもわけはない。責任をもって分担をこなす。集団としての力をたくわえ、その行動も一定のパターンをもって力をつける。年を追って力が増し、その力はは流れを一層堅固にする。
如何に集団としてまとめあげるかである。如何に流れをこなすか。である。そして、如何にその流れを受け継ぎ、受け渡すかである。流れは大切だ。伝統の流れは、足を踏んばり土台を支えている。その流れに身をまかせた1人の自覚と個性で、立派な集団ができあがる。
恐いこと。ただ流れに身をまかせ、あとは野となれ山となれ。それでも流れるたくましさ。人間など弱いもの、「自由だ」といって放り出されりゃそれまでさ。なんだかんだと口走り、気がつきゃどんどん流されてる。一定のリズムを持っていようとも、流れてゆくに違いない。流れ流れて何処へ行く。
1人の男が、常に精神的爆弾をかかえている。しかし、それを爆発させてみろ、クラブは決して成り立たぬ。人間関係のルールがある。もっと流れを大切に。未熟な心が、勝手気ままに口走る。流れに逆う。
しかし忘れちゃいけない、これからだ。流れの中でやるべき事があるのだから。
1年たった春の日に、その暖かさに誘われて、狂いながらも考えよう。我如何に、と…。
当世部室今昔物語 – OB柴田
当世部室今昔物語
法学部OB 柴田
つい先日、4・5年生合同修学旅行、石打スキーツアーから帰ってきたばかりだが、そこへ、酒井(修)前主将、杉本(輝)前副将、正路前出版局長各位から、名誉部員である私にTELがあったり或いはしたりで、これこれしかじか、「10枚位書いてよぉー」、「よかったら書いて貰えますか」、「書いて頂きたいのですが」との要請があり、それこそ1つ返事でOKし、又々文筆の才能を披露してしまうのか、と内心ほくそ笑んだのであります。ところが、一体何を書いていいのやら分らず、しばしば筆も休みがち。今や世を挙げてのロッキードのピーナッツ事件、この事件の論評は色々と事情もある故に、上の様な題目で「峠」を登って行くことにしたのであります。まあ、皆さん、暫らくお付合下さい。
誰が名付けたのか11号館。あの狭い入口をちょっと右寄りに歩み、クリーム色の煙草の煙が漂う階段を降り、進路を左にとるとそこに長屋が展開する。長屋の1丁目1番地が、部室とは程遠い我休息所。用事があろうとなかろうと一日一回は「コンチワー」。
そこに繰り広げられる人間模様、4年分たっぷりとはいかない迄も、別名、西北亭屁臭たる筆者は、一生懸命綴りたいのです。屁臭氏の学生番号は27211528、法学部1972年の入学。これをどこでどう間違えたのか、当時の編集局長、「優取り物語」の主人公平川氏はTEL番号と間違え、「峠」に印刷したこともあるのです。その頃の部屋は、幅は廊下の半分+a、奥行きは部員が縦に2匹寝れば一杯になってしまう位。そこへ昼休みには20人も30人も集まる。然も自転車を置こうものなら、長屋の大家のロ○に叱られて「ゴメン、ゴメン、ゴメン、次からは所場代払います」と言って逃げるのが精一杯でした。そんな時も、隣のアーチェリーの連中は見て見ない素振り、今に見ていろアーチェリー。
集まり散じて人は変われど、仰ぐは同じきサイクリング、否合ハイ。「峠」10号の最後にも合ハイに始まる記事が出ている程。当時何も知らない我々は、立石宰相の号令一下、あっちこっちの女子大を喜んで巡り歩き、何とか話はつけたものの、いざ実践となると餌は、立石氏は全然別としても、他の3年諸氏に食いつくされてしまったのでした。何のことはない、我々は御膳立てをしたに過ぎなかった。
そこで狂った072は、早慶戦を利用して2日に2回続けて内野学生席で合ハイならぬ合観をし、睡眠不足と疲労で結果は言わずと知れたもの。散々な目に合ったことも幾度か。その頃から俄然ウソとイヤラシサの頭角を現わし出したのが理工の072、大岩ウソ太郎。彼は自宅通学にも拘らず、オバサンの家に居候しているとウソを吹き、仕送りも少いのでアルバイトを捜してくれと私に泣きつき、それは気の毒とばかり、私も家庭教師のバイトを捜してやったこともありました。嘗て、関口氏、否、ヌードダンサー関口嬢が
『理工の人物は果して理工でどんな生活をしているのか』
と訝しがっておられたが、渋谷でオカマにひっかかる様な男、大岩は、一体どこで何をやらかすのか分らない。
さてさて暴露記事にし、コンパに目を移すことにしよう。何やらウチのコンパは物凄いと、昔から聞かされてはいたが、最近はかなり大人しくなった様だ。第1に、例の脱がせが全く蔭を秘めてしまい、ベルトに触れようものなら、本気になって腕力を振り、不謹慎な部員が出現し始めた。ターゲットになったら、有難くこれをお受けするのが仁義というものです。然し暴れなくなったと言ったらウソになるでしょう。屁臭氏が1年の時の追こんでは、関口2世の誉高い柴田氏が踊り子さんに祭り上げられ、生贄となってしまったのです。彼女は以後も度々踊らされたとか。(モゥー、絶対にゃらんぞ。あんな事)又、いつぞやは、我々が合宿時に使用しているあの鍋に、酔った部員がクンをしたとか、或いは酔って寝ている部員のナ二の回りに赤チンを塗り、フロ屋に行けずに因った御人が居たとか。流石に最近のコンパ、それがなくなったせいか静かになってきた。音楽、そうムージークで言うならばビートルズからカーペンターズに変化してきた様な感じ。パンツの布キレ飛び交う様は誠に残念なことに見られなくなりつつあるのが現状です。今年の追コンは、大人しい乍らにも結構騒ぎ、畳の上は酒浸しで足の踏場はなく、然もどういう訳か空からソースが降ってきて、やっとコンパらしくなってきた時に、追出されてしまったのでした。
昨年の追コンは面白いと言えば最高に面白い。私1年の時に、我クラブに居たK君が、今はアナ研の幹事とかやらをやっており、コンパ会場が襖1つを隔ててアナ研と同じ場所。K君をひっぱり出してきて飲ませたものの、連中全く不謹慎にも男女席を同じくしており、ヤキモチも半分以上手伝ってその襖を倒すこと数千回。
最後のクライマックスはやはり4年生の脱がせ。電気を消しても良さそうなものを、今回は全く消さず、それどころか喜んで自ら下半身裸になり、そのままの格好で女性の居る隣のアナ研の会場の堺になっている襖目掛けてドスーン。露になった男性の下半身は、はしたなくもウラ若き女性の眼前に晒されたのであります。痴者!と罵られ様と何と言われ様とこんなに面白いコンパ、笑いのコンパは無いのでありました。
然し、全員が全員こんな事をした訳ではないのです。積極的に参加されたのは現5年の岸田氏だったのです。彼は愛犬チャーリーに眼鏡をかけたり、空からソースを降らせたり、本当にコンパの貴重な潤滑油であり、嘗てのコンパ最盛時の片鱗を窺わせる御人なのです。彼は1年の早同で健脚を発揮すると、一躍「メルクス」の異名を欲しいままにしたのですが、それまでは「三木のり平」に似ていると、馬面呼ばわりされていた。何のことはない、彼も元を正せば「桃屋」の佃煮人間だったのでした。
さて、長屋の1丁目1番地はその後どうなったかと言うと、誰が名付けたのか11号館、名称も変わり、11号姦と改まり、新入部員募集のタテ看にも11号姦地下1部室と新入部員の目にとまることになったのでした。人も変わり名称も変わり、変わらないのはサイクリング1筋、女人禁制の掟だけ。然し、そんな中にも我クラブにもアカデミックさはあるのです。
日本国中到る所で出回っている、あの月刊サイクルスポーツに、我クラブの程島、増永、酒井君、それに柴田氏を筆頭に大岩、石沢、吉田君が写真入りで掲載されたこともあるのです。柴田氏なんか昨年の夏、長野県の某所にて、もしかしたらサイスポに出た人じゃないですか、と全く見も知らない学生に声をかけられたことだってあるんだから!一躍スターダムにのし上ったのでした。
今急に、文筆が奮わなくなってしまった。読者諸氏、私に一服させて下さい。さて、一服し終わったところで、程島君就職先のFM東京のジェットストリームも終わりました。一服といえば、私は4年間家にあっては、煙草を喫わない好青年で押し通しました。この苦労並大抵ではありませんでした。夏は扇風機を窓に向けて吹きつけ、部屋に煙がこもらぬ様にし、冬は冬で寒い中を窓から顔だけ出し、冷たい風にあたってもよい様に、手には手袋をして煙を外にフワッーと吐き出すのです。想像してやって下さい。
ちょっと話がそれてしまったので、元に戻すことにしましょう。当世部室今昔物語、長屋の1丁目1番地は確かオイルショックを迎える年の秋だったと思ののですが、部室長屋の大改造を敢行したのでした。幅は昔と全然変わらない乍らも、50人をかかえる大所帯、占領してしまえば廊下は全て我部室。奥行きはというと、隣のアーチェリーとの堺の太い柱の部分を先ず獲得し、そこに何やら乱雑に棚を置き、女人同席のアーチェリーとは完全に遮断され(これはちょっと残念)、反対側はと言えば、クリーム色した煙の立ちこめる階段を降りてきて、すぐ左はもう我WCCの部室となったのでした。
まあ縦に部員が5・6匹は寝られるだけの広さとなりました。然も最近、会計学会だか貿易の会だかから、木製の大きな棚を貰うことになり、部室拡充はイヨヨ増々御発展。でも棚を呉れたところは、その後スチール製のロッカーが入っているのだが…。最近では、おっかない口○も何も言わなくなり、我方勝手放題に「自治」を拡大しているのですが、又々部室の大拡張計画を狙っているのであります。それは例の隣のアーチェリー、ここを何とか占拠して、部員が縦に1・20匹位は寝られる広さにしたいとか。今春の休みが終われば、その計画もかなり具体化することでしょうし、今秋末頃迄には事業も完了していることと思います。第2は館の使用も結構だけど、やはり11号姦地下1丁目1番地が良いのです。多分3年位の先輩諸氏には想像もつかないことかもしれません、この広さ。
先輩諸兄、富永(陽)嬢を覚えていらっしゃるだろうか?多分御本人もここで自分の名が出てくるなどということは夢想だにしていないことでしょうが。そう、1971年度10月23・24の両日、軽井沢でオープンサイクリングを行なった時の、参加者の1人で武蔵野女子短大の女性であります。私が知る由はないのですが、このオープン、色々と問題も多く紆余曲折の末、現在も健在でありますが、こうした行事に参加して下さった方々は今どうしておられるのでしょうか。古い昔はオープンで知り合った女性と御結婚された、我クラブのOBが居らっしゃると聞いておりましたが。
オープンは言うに及ばず、何かにつけて最近は8ミリ映写が当節の流行になっておりますが、この無声映画非常に人気があり、我クラブの「近代化」を示すメルクマールになりつつあるのです。OB総会には是非出席して頂き、OB諸兄に御覧頂きたいものです。
冒頭でも触れたのですが、先日、クラブ史上初めてと思われる、卒業記念4・5年生合同、修学旅行石打スキーツアーに出掛けてきたのですが、僅か2泊3日ではあったのに、大変楽しい想い出を作ることが出来ました。これは野菜作りの名人と言われる伊達君が企画してくれたのでしたが、参加者全員で10名。電車の中で既にサントリーホワイトを2本空にし、麻雀と酒の合間にスキーをしたとは言わないまでも、石川・杉本両君と私は、生まれて初めてのスキーなのに、2日目にして石打のチャンピオンコースをダイナミックに滑走するという大挙を為し遂げたのでした。でも南国鹿児島生まれの新名君は安全パイを握って放さなかったのですが。又残念なことに及川君は捻挫してしまい、大変なお土産品を作ってしまいました。
修学旅行修了後、伊達君と私は、新潟の小野氏宅や奈良の岸田氏宅に御世話になり、最後の「春」を楽しんできたのです。本当に暖いおもてなし、紙面を借りて厚く御礼申し上げます。
さてさて、当世部室今昔物語、如何でしたでしょうか。肝心なサイクリングについては、どういう訳か1つも触れておりませんが、それは他の諸君が書いてくれるものと思うので、そちらに譲ろうと思います。もう予定の枚数は超過してしまっているのですが、なかなか上手に表現出来ないのが残念です。私の新入生当時(リクルート)から、現今の状況迄を詳かにしようとしたのですが、4年間の変化お分り頂けたでしょうか。楽しいこと、苦しかったこと、そして心の底から声をあげて泣いたこと、色々ありました。
時々刻々と変化する社会にあって、我WCCに入部してくる部員も当世風に変わろうとしています。部室の構造も変わればコンパの騒ぎ方も変わり、合ハイ・合コンの相手も変わっていくでしょう(変わらないという声もあるけれど)。先輩諸兄はこの文を読んで、懐しい全盛時代を想い出して下さるでしょうか。そして後輩諸君、我クラブの将来は1にも2にも諸君の双肩にかかっていることを知って貰えただろうか?幸にも我クラブにあっては、黒いピーナッツ事件なるものは聞いたこともない。それが証拠にOB諸兄が古巣へ帰ってきて下さる。そんなWCCをいつまでも作っていこうじゃないか。是非作るのだ。
さぁーて、我輩も今日は大分「私用ノート」を費してしまった。そろそろ引き上げるか。それじゃやはり最後はこの言葉
「失礼しま―す」。
道について – 中山
道について
政経学部4年 中山
私は3年程前の初夏に、奥多摩の風張峠という所を走ったことがある。天気も良く晴れており、道も有料道路になったばかりで走りやすかった。この時のことは、今でも記憶に新しいのだが、忘れられない出来事になった原因がもう1つある。自転車での峠の登りは大変きついものである。誰もが経験していると思うが、登りの厳しさに反比例してノンストップで走る下りは楽しいものとなる。全速力で下っている途中、私はカーブを回った瞬間に「ダメだ」と観念した。狭い山道に外国製のスポーツカーが2台並んでいたのである。
思いきり、路肩に自転車を寄せて通り抜けた時は、思わず「助かった」と叫けんでいた。そして、こらえようのない怒りがムラムラと湧いて来たのである。道路上であのようなルール無視が許されてよいであろうか。私は、落着いてその時の事を考えるにつれ、道路は一体誰の物であるかという疑問を持った。現在の日本は、車社会であると言われている。文字どおり車は道路上の主役である。各地に網の目のように建設されている高速道路、自然をかえりみず能率だけで線引きされているスーパー林道の類は、車優先社会の象徴である。狭い道路の片すみに歩行者や自転車は追いやられ、常にクルマのかげにおびえている。年々何百万台と生産される自動車から出される排気ガスと騒音は、人間の健康を害するばかりでなく、環境破壊という深刻な問題をもたらしているのである。
近年このような車社会を問い直すものとして、各地に歩行者天国、サイクリング・ロード、自然遊歩道などといった、クルマをシャットアウトする施設がつくられている。そして、このような動きは各方面から一応の歓迎をうけている。しかし、私はこの状況に1つの不安を感じる。これらの施設は、あくまでも車が入り込めないような国土の片すみに作られるか、日曜祭日などの車が動かない日に、車の目を盗むようにして作られているからである。
私は車を社会から追い払えなどとは言わない。車は現代の日本の社会において、重要な交通機関である。しかし、人も車も道路において対等な立場でなければならないと思うのである。道は誰のものでもありえない。使う者がルールを守り、安心して通行できるものでなければならないのである。
ドライバー諸君、一度車を捨てて街に出てみてはいかがかな。
オープンサイクリング考 – 藤山
オープンサイクリング考
政経学部5年 藤山
オープン・サイクリングがいつ頃からクラブ行事になり、1泊2日にまで昇格していったかを私は知らない。5・6年前に、クラブ会則の第2条に沿う形で始められたのであろう。だが、この企画が始まった当初、先達によって意欲的な意見が連日闘わされてきたことは容易に想像がつく。
恐らく焦点は、オープンの意義を問い、クラブ行事としてのオープンの在り方やオープン自体の充実、といった極めて前向きの論議であったろう。今にして新聞紙上では「銀輪の復権」とか「バイコロジー」だとか騒ぎ立てているが、当時大学の1サークルが社会に対して働きかけたことは画期的であったように思う。この時期がオープンの発足期とすれば、我々の頃は差し詰め、分散期というか過渡期というか、ともかくそんな時期で、かなり屈折した論議が展開された。オープン廃止論さえ出て来た程である。
意外にも廃止論は当時の執行部で支配的だった。確かにそれなりの理由があったのである。まず48年度からバート・ランがクラブ行事として新たに採用されたことである。(1年生諸君はパート・ランが在るべくして在るかの如く考えているかもしれない。しかし、その採用はクラブ行事全体に大きな影響を与える。当時としては英断であった。この間の事情を知らない向きは1度先輩にでも尋ねたら良いと思う)
執行部としては「パート・ランの回数を出来るだけ増やしたい。10月という最も良い時期にサイクリングであってサイクリングらしからぬオープンは目ざわりだ。日程の変更はできないし、開催に到るまでの労力も馬鹿にならない。故にオープン切るべし」この考えであったようだ。同時に、オープンに臨むクラブ員の態度が云々されてもいた。これは言わずと知れた女性にまつわる問題である。私はオープンに参加した女性をめぐり、クラブ員同志で火花を散らすケースを幾度かみてきた。これもある意味で微笑しいと思いもしたが、合サイ化したオープンに対する建前論からの痛烈な批判の前に再考を迫られることとあいなった。そこで議論百出、ワイ、ワイ!しかし残念なことに感情論が行交い、私も含めてみなさんマトモではなかった。他に金銭的な問題もあったかもしれない。
ともかく、数々の問題点の相乗効果により、廃止論は勢いを増していた。それが案外簡単に開催にこぎつけたのだから不思議である。もともと、オープンは2年生が担当することになっていた。それは期執行部の体制づくりのため、大同団結の必要があり、その機を与えてやろう」という先輩の親心からきたものである。2年生にっては、オープンは腕の見せどころであるわけだ。我々は執行部に対して「ヤラセテクダサイ」と強く働きかけた。これがよかった執行部もいやとは言えず、2年生の泣き落しにあっさり押し出された格好になったわけである。
もっとも、この時点で廃止論も決めてに欠け、我々への心情賛同者が執行部にも、いてくれたのは救いであった。ただ、オープンが末期的症状を呈していたにもかかわらず、論議もほどほどに開催に到った点では、後々まで大きなシコリを残すことになってしまった。開催は本決まりになったものの、場所・宿泊施設の選定、参加者の募集方式、雨天の場合の日程消化策など面倒なことばかりである。このため5月半ばから幾度となく2年生会を開き、検討に次ぐ検討を重ねた。結局、開催地は軽井沢、形式も昨年度を踏襲することで落着いた。多少、事実を歪曲し、増幅した分もあるかもしれないが、48年度オープンの舞台裏はこんなところだろう。
10月6日、どんよりとした曇空、昨年度は雨のため走れず仕舞。今年も..。悪い予感がする。加えて私は必携のシュラフを忘れてしまったのである。オープンの責任者である私自らこの有様では、前途多難を思わずにはいられない。集合所は、第1集合所・上野駅緑の窓口、第2集合所・軽井沢改札口前、第3集合所・友愛山莊YHと、時間をズラし、3つに分けた。参加者の層を配慮したためである。実際、学生・OL・主婦・子供と多岐にわたっていた。
特別な落度もなく、参加者連は無事軽井沢へ到着。宿泊所である友愛山荘YHにほとんど18時までに集合できていた。食事までの30分余りは自由時間。ホールではこの空白の時間に歓談する参加者や、視線を足下に落とし、黙り込んでいる参加者やら様々であったが、食事の準備に忙しく振舞う我々は、いちいち気にしてもいられない。食事を済ませた後、全体ミーティング・班別ミーティングという順序で予定を消化していく。全体ミーティングの際、8ミリ映写をする予定だったが、8ミリ到着がおくれ、とりあえず、班別ミーティングを始めてもらう。ほどなくして8ミリ到着。再びホールに集合し、映写会を行う。参加者には、これが予想通り好評で、翌日のサイクリングへの期待が一層ふくらんだようである。それもそのはず、関口氏の薪割りシーン、雌阿寒御来光シーン、能登合宿打上げコンパの乱行シーン、といった名場面が数多く収められていたからである。クラブ員の卑猥な笑いが、多くの参加者のさわやかな微笑を誘う。
ここにきて、やっとくつろいだ雰囲気ができ、映写後直ちに班別ミーティングの続きをやってもらう。全ての班がミーティングを終えた時には11時をはるかに回っていた。
10月7日、5時頃から雨が降りだした。なんと不運なことか。雨足はかなり激しい。続々と2年生がホールに集まってきた。末だ6時前である。2年生全員が集合したものの、雨天の処理を確認するでもなく、ただ放心したようにすわり込んでいる。うつろ、うつろ…。ラジオから第4次中東戦争勃発のニュースが流れている。中東も大変だろうが、こちらも一大事なのである。雨は止むとは思えない。とりあえず参加者には食事をしてもらう。雨天時の対策は前もって準備してはいた。が、雨が小降りになるのか、激しくなるのか判断に迷い、完璧な対応にはあまりにも不十分である。結局は、軽井沢消遙組、JCB 8ミリ映写観覧組、室内遊戯組のいずれかを選択することによって、その日一日を過してもらうことに決定した。
もちろん班長は班を掌握する必要から、参加者がいずれの組を選ぶのかをチェックしてもらった。参加者のホトンドは班長に引卒され雨の軽井沢へ。15時頃YHに戻ってもらい、記念撮影、その後解散。
皮肉なことに解散時にはほとんど雨はあがっていた。参加者の中の幾人かはサイクリングへの熱情止み難く、クラブ員指導の下、サイクリング・コースを回ったそうである。雨のせいとはいえ、がっかりするやら、申し訳けないやらで言葉もなかった。しかし、1年生は皿洗い、3・4年生は食事の準備、数々のアドバイス、という形での支援や、参加者がその後寄せてくれた何通かの礼状が、我々にとってせめてもの救いであった。
オープン最後の仕事は記念写真郵送とアンケート調査である。このアンケートは、もちろんオープンに対する参加者の卒直な意見や感想を聞き出すためのものであり、参加者全員に答えてもらうことにした。そのうち12・3通が戻ってきた。私の怠慢からこの集計結果をクラブに報告せず、死滅させていたためアンケート調査があったことすら忘れられていると思う。この場を借りて報告させてもらうことにする。
私自身、アンケートの結果がわかる前まで何の期待も抱いていなかったが、鋭い指摘ばかりで恐れ入った。質問事項など吟味すれば、より密度の濃いアンケートを回収できたかもしれない。何しろ思いつくまま9項目を並び立てたものだから、質問自体の重複、欠落も多い。答えにくかったかもしれない。しかし女性特有の小さな字でアンケート用紙一杯埋めつくしたものもあった。予想は裏切られ、手ごたえは確かなものであった。全体を通じて、クラブ員の態度に好印象をもたれたようであり、この種のことが随所に見受けられ、そのトーンは感激で震えているとさえ感じた程である。また「軽井沢でサイクリング」組よりも「サイクリングを通じて」組の方がはるかに多いことを再認識した。以下、質問事項とその反応ぶりを紹介してみる。
1) オープン・サイクリングに参加された動機について記入して下さい。
「運動不足で何だか体を動かしたかったのでよいチャンスと思い参加したのデース。」
「軽井沢に末だ1度も足を踏み入れたことがなかったから。」
「高校卒業以来、自転車に乗る機会がなかったので、新聞記事を見た瞬間どうしようもなく自転車に乗りたくなって」
2) あなたは、この催しを何で知りましたか?毎日新聞(7)、サンケイ新聞(3)、友人(2)、ビラ(0)
3) 軽井沢での開催は適当だったと思われますか。
「電車が混むのは仕方がないから、まあいいとして、軽井沢はサイクリングするにはちょっと狭いような気がした。運賃・乗車時間は適当だったと思う。」
「私自身、軽井沢のサイクリングは、2・3回行っているがいつ来てもあきることなく、場所も景色も十分満喫できる所なので適当だと思う。」
「伊豆諸島なども夜行1泊で十分行けると思う。船旅って素晴らしいですよ。」
4) 1泊2日の形式をどう思われますか。
「ミーティングも8ミリにも時間の余裕があり良かったと思う。」
「目的がただ自転車に乗るというのなら日帰りの方がいいと思う。でもサイクリングを楽しみ、自然に接し、そして人間的交流を多少なりとも望むならやはり1泊2日で余裕を持って参加の甲斐を得たい。1泊2日大賛成。」
5)ミーティングの形式についてお気付の点がありましたら記入して下さい。
「人数が多かったせいか、お互いの交流の場がほしい点では物足りなかったし。」
「…..1時間前位に全員集合してミーティングを行えばいいと思います。」
6) ミーティング前、食後等空白の時間があったと思いますが、この点について御不満な点、お気付の点を記入して下さい。
「自由な時間で良かったと思います。」
「クラブ員と参加者が全然別に固まっているように思えた。もう少し、いろんな人と話せるように工夫したら良いと思う。」
「人によっては別の人と話している人はいましたが、ほとんど一緒の友達との会話が多かったようにおもわれます。ですからミーティングの後など全体でゲームなどやったら、もっとなごやかになったのでは。」
7)集合方法についてお気付の点を記入して下さい。
「人それぞれ学校、仕事と違うし、都合もあるので集合場所、時間等分けたのは良いアイデアだと思います。」
「列車も指定の方が便利だと思います。」
8)参加者確認、パンフレット発送の際、内容・方法等について不満な点があれば記入して下さい。
9)参加費用・宿泊施設・開催時期・クラブ員の態度等についての意見を記入して下さい。
「費用は適当。1年に1回だけでなく、もっと回数を増やして欲しい。普通の人もどんどん仲間に入れるようなサイクリングをもっとたくさんオープンして欲しい。私が1番望むことです。」
「…雨にもかかわらず計画を立てて、色々な所を案内して、気をつかってくれた事を大変うれしく感じました。」
以上が48年度オープンの全貌である。私は3年進級と同時にクラブを去った人間であり、その後のオープンの変遷については小耳にはさむ程度のものである。とはいえ、オープンの扱いについては大分頭を痛めてきたように思える。我々から引き継いだ諸君は、その形式を「オープン・ラリー」という形に変えた。如何なる論議を経てラリーという形式をとったのか知ろうはずもないが、恐らく、オープンの合サイ化、軽井沢様式からくるマンネリ化脱皮を意識してのことだろう。
こうした試行錯誤の段階を経てやっと現在1つの形ができあがろうとしている。それはオープンがオープン局の手に委ねられたことである。この措置は建前論を前面に押し出して、サイクリングクラブと社会との接点としてのオープンを確固たるものにしたように思う。かってオープンの持つ意味が幾度となく問われ、それを2年生の団結云々にまで矮少化してきたことを考えれば、格段の進歩である。もちろん無用の論議の手間が省ける。しかし2,000m級の峠にも挑戦しようという猛者の多い我クラブで、オープンなど軽いお遊びに過ぎないだろう。
参加者が感動していた軽井沢の風景も遠出を重ねているクラブ員諸君にとっては何の感動も呼びはしない。はっきり言って参加者というのはド素人であり、クラブ員は接待にも技術的にも気をつかうばかりである。「転い気持で参加しましたら、みなさん本式で組み立てていらっしゃったりして、びっくりするやら、感心するやらであっけにとられました。」というのが参加者の正直な声なのである。これだけ大きな落差がありながら、この行事を社会的普及だけではとてもやってはゆけまい。これまで以上の覚悟と時間が必要となろう。
私の独断と偏見のみでオープンが語られてきたが、せめて最後はさわやかに決めてみたい。これは参加者から寄せられた礼状である。
「お天気に恵まれなかったサイクリングでした。どんより重い空、それでも雨粒をさけてほんの小1時間ほど念願の自転車に乗りました。ハンドル握る手、ペダル踏む足、風切る頬、ひんやり冷たい空気の中、ポカポカあったかい身体の内、霧の中の静閑としたモミの木材、そしてあのドキッとする下り坂のスピード、自転車でしか味わえなかったあの感覚、これらのすべて、本当にすばらしい思い出になりました。初秋でひろったちっちゃな旅行でした。ちょっぴり余韻を残した楽しい想い出…。」
自転車雑感 – 吉田
自転車雑感
法学部4年 吉田
1、私は、今2台の自転車を所有している。1台は緑色のランドナー。1年生の秋に買ったので、今年で3年目をむかえた事になる。ほとんどのクラブラン、プライベートランに乗っているので大分ボロだが、1番好きな、キマっていると自分では思っている自転車である。
自転車の性格が1番良く表われるのは車輪だと思う。今はハチサン(26 x 1 3/8)をはいているが、3年生の春まではクレメンの42Bをはいていた。クレメンはまるでゴムの固まりで、地道の下りでも良くクッションがきいて、石に乗り上げても不安が無かった。「回転部の軽量は、他の部分の6倍の軽量に相当する」という理論に真向から逆行するが、足まわりの安心と、バンクを防ぐためである。少し極端すぎたのか、ほとんどその重さに愛想が尽き、ナショナルのタイヤに変えてしまった。ハチサンと言ってもシイチ(26 x 1 1/4)に近く、また極端に走ったと言われそうだが、3年の夏合宿もこれでノンバンクである。まったく良く出来たタイヤである。
このタイヤにあわせたホイールが、カンパヌーボのハブとニジのリム。スポークは自分で張ってみた。
チェンジは、前がサンツアーSL、後がサンプレ・プレステージ。サンプレはストロークが短いということと、見た目に後輪がシマると思ったので使っている。日本製の、あの銀色に良く光って、1遍、後にはねかえっている形は好きでない。
歯数は、前47×33、後14×17×21×24×27、とワイドに、低めにしてある。フリーが少しワイドすぎると言われるが、地道の峠ではこのぐらいの差がないと足には感じない。
フレームは、今野製作所の22インチ。色は紺色だったが、自分で深い緑に塗りかえた。エンドは国産用だったが、自分でけずってサンプレを付けている。ディレーラー・レバー台座がユーレーなのが、変っている。ラグレスで、ボルト台座用のネジ穴ぐらいしか特殊工作はない。主3本がクロモリで、あとはハイテン。マファックのカンティにブルックス、プロのサドル、そしてGBのステムに組身のフロント・キャリア。
この自転車で変えたいと思っているのは、かなり狂いの出て来たフレームだけ。金がおしいのではなく、これ以上は望まない。いわば、理想のランドナー像に近いものである。この自転車で山へ行くのである。地道の峠を登るのである。私の仕事は、この自転車を最良の状態にしておくこと。ちょっぴり古風な感じの、中級の我が愛車。いつものように私の心を緑の山道へつれていってくれ。
2、クラブに入るまで、中2の時に親に買ってもらったブリジストンの5段の自転車に乗っていた。一日100キロぐらい走ると、車体のあちこちから音がした。パニヤバッグにロードマップを入れてのサイクリングだった。クラブに入り、赤いサンノーを世話してもらった。この自転車ではずいぶんいたずらや実験(?)をしたが、今は弟が乗っている。輪行も、クラブに入ってから教えてもらった。初めてのクブブランは、初めての輪行で行った麦草峠。初めからバテ通しだったが、すっかりサイクリングのトリコになってしまった。
何がそんなに私の心にアッピールしたかわからないが、バテてしまっても屈辱感は全くなかった。1年の時は、東北合宿までは、ただ、人に遅れまいということしか考えなかった。しかし、今考えて見ると、1番印象に残っている合宿は東北合宿である。ひたすら地面を見つめて登った峠の1コマを、あの木を、太陽を、道をはっきり覚えている。まるで夢のようである。サイクリングには、ただの旅行にはない何かがあると感じた。
3、2台目の自転車はロードレーサー。サンノーで月賦で買った。月賦なのでハブ、ディレーラーがカンパだが、まとまりの良い自転車とは言えない。ロードレーサーをうまくまとめるには、オールカンバにするのが、1番ポピュラーで、うまくまとまる。私もその考えをもってないわけではない。フレームも、イタリアのブロ選手並に立てるのが速く走りそうで良い。そう考えると、この自転車はまるでだめだが、あえて買ったのは、チューブラーによるファーストラン志向ということである。丸タイヤとWOとはまるで異質のタイヤだ。取り扱いも、乗り方も、この自転車を買った目的は、自己の体力、技術、経験を生かしてのファーストランをするためである。ピッチを上げて走る楽しみをあじわうためである。
ライディング・ポジションも、ランドナー以上に前傾を保ち、足の回転を上げやすいように調整してある。その姿勢は、速く走ることを目的としたものでしかない。余談だが、私はロードレーサに乗って、人と車の流れを見るために見た、後ろの景色が好きなのである。わずかだが、ランドナーのそれとはちがう。
4、私の考えるサイクリングとは、自転車に乗る心を持ち、自転車を走らせることである。何も目的はない。走る事自体が目的なのである。峠を征服する事も、ファーストランも、キャンピングも、それぞれ1つのパターンでしかない。どんなに短い距離でも、「ちょっと走ってみようかな」、と思ってサドルにまたがる事がサイクリングなのだと思う。同じ所でも、平地でも、舗装路であっても、ペダルの1こぎ1こぎが楽しみなのであり、サイクリングなのである。私にとって、同じ場所に行っても、2台の自転車は違ったサイクリングを私にさせてくれる。それぞれ、今自分を乗せて走っている自転車のメカニズム、部品の1つ1つが、私のサイクリングに大きく反映する。やはり、サイクリングをつづけて行くには、自転車を愛さなければだめだ。昔、酒井(修)氏が「自転車に『美』を感じるか」と言っていたが、今、私は自分の自転車に『美』を感じる。2、30万円もする自転車も良いが、少しまぶしすぎる。又、今までのサイクリングの思い出が、そう思わせるのかもしれない。それでもいいではないか。この自転車がある限り、私はサイクリングから離れられない。
プレ合宿に想う – 久保
プレ合宿に想う
法学部3年 久保
ある夜遅く、寮(武生郷友会)の電話のベルがけたたましく鳴った。私は『今頃、どこからだろう。』といぶかしげに受話器をとった。それは寮の先輩、増永氏よりのものであった。「実は今、甲州屋(寮の近くの焼鳥屋で私も2・3度行ったことがある。)にいるんだが、こないか。」と云う内容の電話。勿論酒好きの私が断わるはずがない。何の疑いも持たず2つ返事でOKした。しかし、この時から私の不幸は始まっていたのだ。
私はとりあえず、1000円札を2、3枚ポケットに押し込み、部屋の電気を消して、ゲタをはき、甲州屋へ向かった。そこには、増永氏と山田氏(同じく寮の先輩)と、その他に見かけない人が3人程いた。ところが、この3人がくせ者だったのだ。彼らこそWCCが世界に誇るサイクリスト達であった。まず、甲州屋の娘さんらしい女性と、いとも楽しげに歌を歌っていた杉本A氏、それに可成り酒を飲んでいたせいか、グロッキー寸前だった石沢氏、そして1番大人しそうだった(こういうのが1番こわい)石川氏であった。
私はすでに酒の入っている5人に囲まれて唯一人しらふ。まともに話の出来るはずがない。それなのに、彼らはさかずきをそれぞれ私に渡し、「WCCに入れ。」と云う。私もしょうがないから、「はい、はい。」の生返事をしておいたのだった。ところがその後、春(これも寮の近くの飲屋)に行って、(この時、すでに石沢氏はグロッキー状態でしょうがないから、山田氏と増永氏が寮へ連れて帰っていた。)彼らは私にクラブ活動の内容などを説明しだし、ついに増永氏が「来週の月曜日にでも部室に来てみろ。」と云ったのである。酒代も出してもらったことだし、軽く「はい」と、いいかげんに答えておいたのだ。ところが、これが大きな誤りであった。この日を契機に私のバラ色の大学生活は、バラそのもの、イバラのような大学生活へと変っていったのである。
これが、私がクラブに入った直接のきっかけである。いわば酒の為に、いや酒代の為に入った様なものである。私にはもともと体力と名のつくものはないのだ。体力を養成すべき要素は、すべて頭と顔にまわされた様だ。とにかく、体育と名のつく大会の時にはいつも「雨よ降れ降れ!、風よ吹け。」と天に向って祈ったものであった。だから、あの日の前日も、そして当日も私は祈ったのだった。しかし、ついにその祈りは天には通じなかった。晴れてしまったのだ。私はそれでも『東京は晴れてもいいから、向こうは雨が降っています様に』と祈ったのだった。しかし、その祈りもまた、天には通じなかったのだが…。
当日、晴れてしまったので、しょうがないから私は増永氏からお借りした自転車(この時まだ神金の自転車は出来ておらず、増永氏の自転車をお借りしていた。)を輪行し始めた。『フレームでも折れてくれ』と祈りながら…。輪行を終えると、一応持っていく物を確かめて寮を出た。これでこの寮ともお別れかと思うと、何か熱いものがこみ上げて来た。上野に着くとすでに多くの人達が集まっていた。彼らと雑談しているうちに電車がホームに入り、私達は乗り始めた。自転車も入れ終り、しばらくぼやっと座席にすわっているうちに、何事もなくドアはしまり、何事もなく電車は走りだした。私はその時、この電車は何事もなく、時間通りに長野原まで行くものと信じて疑わなかった。
大宮まで可成り混雑していた電車も、大宮を過ぎた頃になって、なんとかすいてきた。私はこの時から空腹を感じ始めていた。前橋まで行けば、と思いながら私は空腹と戦い続けたのである。ところがである。前橋に着くなり、車内のスピーカーはこう告げた。「車輛切り離しの為、1分間停車します。」と。冗談じゃない。1分間で何が出来ると云うのだ。国鉄のクソトンチキ。ところが、もっと思い掛けないことが待っていたのである。何事もなく前橋を出て走っていた電車が長野原を目前にして、火をふき始めたのである。これには驚いた。そしてこの時、私は云い様のない不安を感じたのである。そう、電車の事故こそ、明日のプレ合宿における私を暗示していたのである。電車は結局2時間遅れた上に、長野原まで動けず、1つ手前の中ノ湯に着いた。その夜は、つまりが中ノ湯泊り。
明けてプレ合宿一日目駅に泊まった私は、それまでやわらかい羽根布団の上でしか寝た事がなかったからほとんど眠れず、眠い目をこすりながら体操をする。いよいよ出発。私の前には深津氏、後ろには正木氏(はっきりとは覚えていないが)が走っていた様に思う。それ程勾配はなかったが、私にとっては可成りのスピードでとばしていた為、長野原まで遅れずについて行けるか心配になる。
しかし、そんな心配をしている内に、長野原に着いてしまった。長野原には、幸運にも1つ早い電車に乗った為に、長野原泊まりとなった人々が、我々の到着を待っていた。彼らの泊まった宿に案内されて朝食。ところが、朝食が出されても全く食欲がない。少しでも食べようと、はしをつけるが、口に入れるとすぐはきそうになる。食べなければ走れないだろうし、食べればはきそうだし、どうしょうかと迷っていたが、結局食べずじまい。
そのうちに出発の時間になる。私の班は、班長正木氏、班員高田B氏、清水氏、山村氏そして私の5人。どんどん前の班が出発して行く。いよいよ我々の班の出発だ。緊張の一瞬である。まず高田B氏が、つづいて清水氏、山村氏が、そして私が、最後に正木氏が。走り始めるとすぐ登り。だんだんと山村氏との間隔が広がっていく。勿論、登り始めてすぐ10段に落とす。ふんでも、ふんでも間隔は広がるばかり。この時程、自転車のじょうぶさを感じた事はない。いくらメカトラを起こせと祈っても、歯とび1つしない。しかし、そんな事は云っていられない。踏まなければ。
しかし、みじめ。ついにダウン。休憩をとる。しかし無情にも正木氏がすぐ出発する様にと。CLの高田B氏に告げる。『蓄生、正木のバカ、死ね』と、本気で思う。幾度かそんな事をくり返しながら、ついに草津に到着。まず牛乳を飲む。30分か40分休んで、また走り出すと云う。『この気違いどもが、また走るつもりか。何が楽しみでお前ら走ってるんだ。もう俺はここから輪行したい。』と思う。
草津を出発。いつの間にか我々の班が最後を走っている。つまり、正木氏の後ろに酒井氏がいたのである。2人は私に向かって「よし、いい調子だ。」とか、「休まずゆっくり、自分のペースで走れ。」などと云っている。可愛想にこの2人、私の為に可成りいじけて走っている様だ。『好きな様に走ればいいのに、ほんとに可愛想。』と思う。そり元気づけられて走っているうちに、山ろく駅、に到着。ここからフリーラン。すでに、ほとんどの者が出発していた。私は草津で買ったパンにくらいつく。実にうまい。出来ることならこのままずっと食い続けていたいと思う。
しかし、このサディストの集団が許して呉れるはずがない。すぐ出発。一緒に正路氏、吉田氏、杉本B氏らが走り出す。走っている間中、彼らは何かと元気づけて呉れる。感謝する一方『早く行ってくれ、あんた達が行かないと休めないんだ。』と思いながら走る。だんだんとガスが濃くなり始め、前方が見えにくくなる。何となくロマンティックなムード。しかし、現実はそんなものではない。腹も減り、グロッキー寸前。この時、杉本B氏から救いの手がさしのべられる。「ちょっと休んでメシでも食おうや。」OH、神様!仏様!キリスト様!杉本B氏の後ろに後光がさしている様だった。そこでパンを食ってまた走り始める。
走っているうちに田中氏、野口氏らの姿が見えてくる。彼ら、まだ余裕があるみたい。蓄生と思いながら彼らを追いかける。山ろく駅を出て1時間半。ついにレストハウスが見えてくる。死ぬ気でペダルを踏む。ついに到着。弓池もある。白根山も見える。自分がここまで自転車で走ってきたのが信じられない。白根山を見上げながら煙草をすう。実にうまい。あんなうまい煙草は一生忘れられないだろう。その夜のキャンプ、長野に着いた時の嬉しさ。想い出は尽きる事がなく、ここで書いていると切りがないので、筆を置きたいと思う。ただ最後に、走っている間中、元気づけてくれた先輩各位に厚く感謝すると共に、御迷惑をかけた班員のみなさんに深くおわびします。
坂道 – 杉本
坂道
教育学部4年 杉本
後期試験もどうやら終わって、やっと一息いれることができた。久し振りに自室に転がり、天井をながめながら、マキシムにしようか、それともネスカフェでやめとこかと、必死に考えていた時、もっと大事なことに気がついた。暇になったら、『峠』の原稿を書き上げるつもりでいたのだ。結局、コーヒーはやめ、清酒「大関」で手をうつことにした、その晩は原稿を書き始めることになった。
今、目の前には、薔薇の花が数本…。それは、それは、見事な花をつけている。これを読まれる部員諸兄には誠に気の毒という他はないが、この花は、1月17日の小生にとって22回目の誕生日に、或る女性から戴いたものであります。
このあいだ、かぞえてみたら、小生がWCCに首をつっこんでから、これまでに走ったランは、クラブランだけで20数回になっていた。果して、この数が多いか少いか私は知らない。ただ本意とは裏腹に、行けずに終わってしまったランもいくつかあったことは事実だ。例えば、いまでも酒の肴として、たびたび我々3年生同志の話題になるものに、1年生だった時分の5月におこなわれた「麦草峠ラン」がある。聞くところに依ると、相当な地獄だったらしい。この私は怪我をしていて、とうとう参加できなかった…。
それから、その年の「追い出しラン」。そもそも、この追い出しランというのは、本来はっきりした”納会“というものを持たない今の我がクラブにあって、実質的にその役割を果してきたものなのである。あの年の追い出しランは、極寒の中、凍りつく思いで山中湖あたりを走りまわったということだ。残念ながら、あれも走っていない…。
このようにしてみると、何かの事情で走れなかったランというのは意外なほど後々まで覚えているものである。
これまでに、色々なクラブランが企画された。さまざまなプライペートランにも行った。そのたびに、あちこちの駅で輪行が繰返された。それらの駅は、もしサイクリングに手をそめていなかったら、おそらく永遠に自分を迎えることはなかったのだ。そう思うと、なんとも不思議な気がする…。そのあいだには、周囲の顔ぶれの方も確実に変わっていった。まるで、忙し気に駅頭で輪行する私の目の前を、無言の表情で通り過ぎて行った人々のように…。
3年前の4月14日。『芳葉』にて。例の悪名高き、WCC式の新入生歓迎法でむかえられ、アルコールの洗礼を受けた我々・・・。
その我々の代も、あの新歓コンパからずっと一緒という者は、今ではもう少ない。たとえばあの時、先輩から差し出された、タッター杯の盃さえ、ただもう首を水平に振って、「イェ・・あのウ・・ボク、飲めませんから・・・」と、いみじくも、のたもうておられた酒井君。そして、一見は謹厳居士然としているものの、アニハカランヤ、出された酒は片端から片付け、それでも物足りず、先輩諸氏の方をうらめしそうな顔で見つめておられた正木君。その生来の初々しい容姿でコンパの席に着くや否や、早くもかの○氏あたりの熱い視線をあびていた戸田君。順応性の早さにおいて非凡なる資質を示し、コンパの始まった頃には、早くも2年生かと思わせるほどの貫祿を見せ、コンパが終わった時分には、既に執行部の風格さえ漂わせていた中山君。いま、あの時からずっと一緒の者は自分をふくめて、この5人となってしまった。
我がWCCにいる限り、コンパとランの数に不自由するという事は考えられない。だが、それらの中で、後々まで思い出深いものをあげるとすれば、やはり新歓コンパであり、そして「新歓ラン」であろう。残念なことに、今年はその初端の「新歓ラン」から、雨に降りこめられてしまった。その時点で多少の経緯はあったものの、結果的には『中止』という形をとることとなり、妙に後味の悪さを我々に残した。
あらためて言うまでもなく、執行部として、希望と意欲に燃えて入って来た新入生諸君に、走ってもらいたいという気持には並み並みならぬものがある。このことは、毎年の執行部に共通した心情であろう。また、翻って、執行部自身にとっても、このランが1年間の活動を占う試金石としての役割をもつものであれば、その意気込みもうかがえようというものだ。そこであらためて我々のサークルを考えてみた時、雨だからといって、物理的にみて走れない理由は見当らない。少々オーバーに言うならば、自転車さえあれば、それでもう走れる訳だ。こういったとらえ方も、今のクラブにあって、ひとつのコンテンションとして、一定の説得力をもつ。
もし、その考え方が単なるアンチテーゼ以上の意味をもたないとしても、それなりの意義はある訳だ。たしかに、雨天時のランというのは、執行部にとって処置に苦しむ問題である。だが、ひとつだけ言えることは、執行する立場にいる場合と、そうでない場合において、非常に視点の食い違いをはらむ問題であるということだ。これはクラブを運営していて、実際のクラブランや夏合宿の時など幾度か遭遇し、また実感したことである。
いずれにしろ、雨の問題は執行部がその早い時期に明確にしておきたい問題である。
雨といえば、私は今でも思い出すことがある。長崎の雨だ。いまから、2年前の春に、2週間ほど1人で走った九州一周ツアーでのこと。もう旅も終わりに近づき、かねてから憧れていた長崎に辿り着いたとたん「ザーッ」。(あの時はもう、情ないやら口惜しいゃら…。)いま思えば、あの雨は、ツアーの途中で高千穂の大和屋YHに投宿した折り、隣の女風呂をのぞいたのが災いしたのではあるまいか。さもなくば、鹿児島の堀宅へ、一宿一飯の世話にあずかるべく立ち寄った際、(それも、異臭悪臭、百花乱舞といったいでたちで…。)なんと!おそるべき偶然であろうか!その翌日が、彼の姉上のはじめての結婚式であったのだ。晴れがましい式の、その前夜の、本来おごそかであるはずの雰囲気を、一気にブチ壊した小生への天誅がくだったのかも知れない。(ここまで書くとさすがに気がひけるが、)
もうひとつ考えられる理由は、あれではないか。霧島YHを出る朝、小生寝呆けまなこでパッキングしていて、ついウカウカと、スリーピングシーツをタオルとまちがえて、サイドバックの底の方にほうり込んだまま、出発してしまったのである。だから、あのYHのペアレントの怨念が長崎の地で、雨となって小生の頭上に降りそそいできたのかも知れない。しかしマア、理由はいずれにしろ、あの雨は思い出に残るものとして、いまでも心の中に残っている。あの時は、見た誰もが朽ち果てるのは時間の問題と思うに違いない長崎大学の寮に2泊ほど厄介になり、そこから長崎の街におりて行っては、束の間のエトランゼを味わったりした。グラバー邸の庭からは人の傘の向こうに見える長崎港。薄暗い冷気の中で見上げた、大浦天主堂のステンドグラス。小生をして、石畳というものに惚れさせた、活水女子短大裏手のオランダ坂。どれもこれも、いまとなっては、ただ懐しいばかり…。『長崎は今日も雨だった』のである。
大学に入ってからの3年間。WCCの、おせじにもすわり心地のいいとはいえない椅子に、なぜかくも居座わり続けたのであろうか。今となっては、この素朴な疑問だけが残る。入部間もない頃は、まさかこれほど居座わろうとは思いもしなかった。ということは、自分にとって椅子のかたちとは無関係に、このサークルが居心地のよい場所だったということであろう。そして今思うことは、サークルにとって、1番大事なこと、必要なことは何であったのかということである。3年間もこのサークルに棲息し、副将という立場で執行部を経験し終えた現在でも、ある明確な答えを見い出せずにいる。
だが、はたして自分だけがそうであったのか。昨年の牛田氏や新名氏、その前の酒井氏、小野氏はどのように考えておられたのであろうか。しかし、その事自体にはさして悲観はしていない。なぜなら、クラブ員1人1人が、それぞれの異なった価値観とクラブ観とをもっている以上、サークルにとって何が1番大事であり、必要であるかということは、一概に言えることではないと思うからである。3年前の主将であられた立石氏の妙に印象的な言葉を思い出す。
「我々のクラブには、明確な統一目標というものは存在しない。なにかの選手権をとるといった・・・」まさにそれなのだ。クラブ員の入部動機をみても、ただもうサイクリングがやりたくて入った者。あるいは、メカをふくめて、自転車という動物に魅せられた者。とにかく、何かのサークルに入りたくて、そのひとつの手段として、サイクリングをえらんだ者。その入部の動機同様、サイクリングに対する興味志向の程度も1人1人異なっている。このようにみてくれば、我々のクラブにとって、クラブランで一緒に走ること、そのこと自体が、すでに我々にとって共通した目的であることに、クラブ員であれば、早晩気がつくはずである。
ひとたびサイクリングに出ると、そこには自然がある。果てしない(本当にそう思う時がある)自然が広がり、訪れた我々を迎えてくれる。重たい輪行袋をかついで降りたった駅の改札口をぬけ出た、その時から・・・。つい前夜まで、眠たい目をこすりながら分厚い本のページをめくっては、少さな文字の行列を追っていたものが」。今思えば、これまでに旅やサイクリングでひろった風景や自然というものは、私にとって妙に印象が薄かったような気がする。海の色とか山のかたち、あるいは、それぞれの場面は確かに覚えているし、山の端に夕日が沈む光景を思い出すことはできる。だが、あらためて「印象は」となると、そのとたん、やけに弱々しいものになってしまう。極言すれば、自分にとって旅先で見る景観などは、それ自体どうでもよいものであった。平庭高原の白樺は、確かに美しい。8月の高原はもう秋であった。木々を渡っていく風は、「…目にはさやかに見えねども」なるほど、「風の音にぞ驚かれぬる」のであった。
だが、それがどうしたというのか。記念写真のバックになるのがせいぜいである。奥丹後半島の経ヶ岬から見る日本海の姿は、見る者をひきつけずにはおかない。しかし、2時間もそこにいれば、あきあきするものだし、蒜山や大山の山容がすばらしいといっても、そこに3日も逗留すれば気がめいってくる。自転車を引っぱり出し、力一杯ペダルを踏み込む。力を込めれば、その分だけ確実に自転車は前に進む。まわりの景色が全て後ろに流れていき、その時、つめたい風が顔に当たれば、たしかにそれもひとつの自然なのである。だから、私にとって景色がよくても、あるいは悪くても、大した問題ではない。走ること、1本の道を走り終え、さらに走りつづけること。この、なんとも素朴極まりないムーブメントだが、自然のもつ無責任な相対美にむかってカメラを向けることより、なんとあてになることか。
野麦峠に登る手前の部落で会った人の顔を、かって東北の街で見たような気がした時、そういえば「どこを切っても金太郎」の顔があらわれる、あの金太郎アメを我々はずっとなめつづけてきたような気がする。だから見知らぬ土地を走っていて、ふといつか見たよりな風景にぶつかることは現にあったのだし、さっき渡った橋を、かつて渡ったような気がしたのは確かなのだ。そのような場面に出会うたびに、我々は小さな眩畳を感じ、確かにふたつのものが存在し、別々の自分がそれぞれに出会ったのではないかと思ったりする。驚きは一瞬だけのものであるが、その不思議さを単純に納得した時、きまって、ふたつの自分を意識していたことに気がつく。それはまるで、椎名麟三のものを読んで、それでは自分は一体、安太なのか、銀次郎なのかと思い悩む気持に似ている。
5月17日、18日の「パートラン」は、その前の「新歓ラン」が中止となった結果、今年度最初のクラブランということになった。コースはあらかじめ企画局によって企画されたもので、我々はそれに従って思う存分走ることになっていた。パートランは、我々が執行部を引き継ぐにあたって、念頭においたいくつかの目標のうち、ある意味でその中核をなすものであった。そして、いよいよそれを実現したのである。我々が少人数によるパートランを積極的に推進した理由は、いくつかあったが、とにかく我々としては、ランにおいては楽しい雰囲気(ラクをする意にあらず)を重視したのであった。
ひとたび峠を前にすれば、苦しさと対峙するのは目に見えていたが、ランそのものは、和気愛々の中でもっていきたかったのである。しかし、それには当然、逆の見方もでてこよう。すなわち、少人数で走るパートランに求められるものが、全体ランというものの中で止揚できないはずがないといった…。だが、実際問題として我々は、6~7人と30人以上という、数の違いに目をつぶって、まったく同じ尺度でそれらをとらえることができるであろうか。数人で走るバートランでは、集合したその時から始まって、走行中はもちろんのこと、休憩、食事、そして解散するまで、同じ班の者と顔を付き合わせ、言葉を交わす訳である。やはり、そこに我々はある種のまとまりの良さを認めないわけにはいかない。
そして、なによりも少人数の場合、自分達○○人で走っているという、共通した意識が生まれ、案外に、このもつ意味が大きいのではないだろうか。我々としては、大勢で走る全体ランが、多くの利点をもっていることも認めない訳にはいかない。だが、それと同時に、我々のクラブが何よりも人と人とのつながりを重視していることを考えた時、全体ランというのは、あまりにも走る楽しさ以外に費される労力が大きすぎるような気がしてくるのである。
このようにして行なわれたパートランであったが、我々としては、ひとつのパターンを呈示したのに過ぎず、果して、我々が求めたものが結実したかどうかは、参加したクラブ員1人1人の判断をまたねばならない。企画局からは、(小諸・田口峠 – 下仁田)(白河 – 八溝山 – 黒磯)(後閑 – 切久保峠 – 新前橋)(上田 – 地蔵峠 – 風越峠 – 松本)の以上、4コースが出され、班割りはWCCに属するなるべく多くの者と、走る機会がもてるようにということで、年間を通してこの私がやらせてもらうことになった。
6月に入ると、7、8日の両日にかけて、今年度最初の「オープンサイクリング」が行なわれた。昨年度までとちがって、年2回開催という全く新しい形式への挑戦であり、6月のそれが第1回目であった。前々年までの、「オープンは10月の軽井沢」といった半ば慣例化していたものを、打ち破るものだっただけに、執行部としても開催までに何度となく話し合いがもたれた。そして、年2回開催ということについては、多少の異論も聞かれたが、我々の執行部がめざしたもののひとつが、対外的な面の重視であったから、その帰結としての年2回のオープンなのであった。
それに我々としては、春と秋のオープンにそれぞれ異なるものを求めていた訳である。我々が役員改選を経て、執行部を形成する段階で、新たにオープン局を新設したのも、ともすれば実行委員長ひとりが、東奔西走していたこれまでの弊害をあらためるためであり、さらにオープンというものの存り方を明確にするための方策であった。従来つづいてきた紅葉の軽井沢から、初夏の房総へと、時期も場所もまるで異なったスタイルでのオープンだっただけに、局長の斉藤君をはじめ、局員諸君の苦労は、さぞ大変だったことと思われる。だが幸運にもその努力は報いられ、お断わりしきれないほど、一般参加者からの申し込みを受けた。今年は、いくつかの大新聞の他に、『ノンノ』や『アンフン』といった雑誌が、募集広告を掲載してくれたことが効を奏したようである。当日は雨の心配もされたが、運よく好天に恵まれ、この事も我々を喜こばせた。
今年のオープンの新しい趣向として、「サイクルオリエンテーリング」が取り入れられ、それは参加者との親睦を深めるうえで大いに役に立ったようだ。果して、我々のめざしたオープンが次の執行部に引き継がれるか、あるいは新しい企画によるオープンが登場するのか解らないが、必らずしもそのことに固執しないでほしいと思う。常に摸索し、その中で最良と思えるものを見つけ、あとは皆の力によって盛り上げていけばよいのである。
6月も後半を迎かえると、部室にも少しづつ夏合宿の雰囲気が高まる。我々にとってその前哨戦ともいうべき「プレ合宿」が、21日から22日にかけて渋峠をめざして行なわれた。できれば、それには全員の参加が望まれたが、やはりそれは無理なようである。当日は、吾妻線の長野原駅に牛前7時集合の予定であったが、列車故障で部員の半分近くが遅れるという、WCC史に残る珍事に見舞われ、出発も若干遅れることになった。いざ出発してみると、2,000Mを優に越す渋峠はさすがにきつく、本番への足ならしとしては、10分すぎるほどの歯ごたえであった。当初、薄日もさしていた天候であったが、時間と高度の経過につれて次弟に怪しくなり、草津温泉を過ぎる頃には本降りとなってしまった。それは6月という時期を考えれば、不思議とも思えない天候であったが、「ブレ合宿」ということを考えれば、やはり真夏日を思わせるような気象条件であってほしかった。
新入生には、合宿のつもりで大いに汗を流して、苦しんでもらいたかったのである。キャンプ場に到着すると、さっそくテント設営の要領などが上級生から新入生へ教えられた。翌日も強い雨足で目をさました我々は、これからの予定について協議せざるを得なかった。いちばん警戒したのは事故である。列車故障という不測の事態や、前夜の雨などによる睡眠不足、そして、久しぶりに2,000M級の峠を走破したことや、慣れぬ重装備による疲労。さらに降り続ける雨の中を今日も走らねばならないこと。色々な条件を考慮した結果、当初の解散予定地である上越線の石打駅をあきらめることにし、長野駅ということになった。「ブレ合宿」としては、いささか涼しいそれとなってしまったが、コースのきつさ、標高差、その他の条件を加味した時、我々としては一定の満足感は得られたのである。
8月16日の夜。気持ちよく冷えたビールの泡沫の中に、12日間にわたる「合宿」の苦労をふり返り、全員が無事に合宿を終えることができた事を感謝した。だが、今年の「合宿」の幕あけは、実に波乱に富んだものだったのである。金沢を出発した第一日目からして、夜半に雷雨に見舞われ、近くの体育館に避難する有様だった。最所の3日間など、予定どうりに進むことができず、パンフに刷られたキャンプに辿り着くことは、それこそ夢のまた夢のように思えた。我々が焦せったのは、言うまでもない。
その上、2日目は早くも集中豪雨を思わせる大雨にぶつかり、2つの班が山中で立往生を余儀なくされるという事態に見舞われた。辛うじて通りかかった営林署のクルマに救助はされたものの、部員の疲労は日を追って増していくのが感じられる程であった。学年別ミーティングでは、毎回のように対応策が検討されたが、自然現象に対する方策など見つかろうはずもなく、とにかく睡眠だけは十分とり、走れなくなるようなことがないようにという事が確認された。又、この頃には会計局の方から、金がかかり過ぎるという意味の注文が出され、この事も我々を悩ませた。確かにその通りなのだ。自炊のつもりが、外食に変わり、キャンプするはずが、営利を目的とした宿泊施設に泊まるのであるから、出費が、かさまないはずがない。我々の執行部がめざしたもののひとつに、少人数によるランがあったが、これは年間を通じてのバックボーンとなりえるものであったし、この合宿においても実践され、おおむね満足のいくものであった。
この合宿では、石沢君の発案により2回の班別パートランが盛り込まれた。(うち1回は、諸種の事情により全体ランに変更。)おそらく、これは合宿における初めての試みではないだろうか。また、今合宿で特筆すべきことは、8月11日、合宿の7日目に、1人の落伍者もなく、全員が乗鞍岳の畳平まで登ぼったことであろう。それは、今回の合宿の企画が始動をはじめた頃からの、我々にとってのいわば夢でもあった。個人的には、おととしの夏、1度登ってはいたが、皆と合宿の一環として再度登れるのは嬉しかった。
8月10日。乗鞍高原中腹の国民休暇村で、高山市で別れたB班と合流。いざ乗鞍の勇姿を前にした時、はやる心をおさえ、もう1度冷静になることに努めた。前日、主将の酒井君らと、畳平アタックについて協議した結果、とにかく安全第一でやろうという事に決まった。荷は全部はずして行くが、工具、防寒具、予備食料は最低各自で持って行くという事が、朝のミーティングで伝えられた。その結果、出発間際には、部員の間でキャリヤ、電装、果てはマッドガードにいたるまで、異常とも思える軽量化作戦が展開されたのである。また、もう1つの決定事項として、疲労している者や、体調の悪い者には、止むを得ないが残ってもらうことにしていた。(幸運にも該当者なし。)我々は「乗鞍ラン」をやっているのではなく、あくまでも「合宿」を行なっているのである。細心の注意と最大の用心を払ったのは、当然といえるだろう。さらに、一応の備えとして、この時だけは、主将の酒井君と私が最後尾につくことにし、他の者は最初から、「オール・フリー」ということにした。1年ぶりの乗鞍。それは、いくぶん去年より残雪が少ないように思えた。
たしかに、合宿にあまり目新しい要素を求めることは、難かしい事に違いないが、かといって、今まで通りのものをそのまま踏襲する必要もこれまたないのである。常に問われるのは、参加する我々自身の姿勢であろう。
9月。合宿を乗り越えた後の一種の虚脱感が皆の中に感じられたのも、またこの頃である。とは言っても、まだ年間行事のやっと半分を終えただけであり、マラソンでいうところの折り返し地点が見えただけのことなのである。この時期に、我々は何度か運営委員会や、3年生会をもった。どうしても、ここで後期の重要性を認識し、それと共に気分を引き締めておく必要があったからだ。だが、この沈滞ムードはその後もしばらくつづくことになる。
このような雰囲気のなかで、9月28日には「1年生企画ラン」が奥多摩方面で行なわれた。例年、前記のような事情で参加者の少なさが指摘される「1年生企画ラン」であったが、私はあえてこのランに期待することにした。とにかく、走ることによって沈滞ムードを払拭し、部員の「走り虫」を呼び起こそうと思ったからである。当のランは、1年生諸君の努力によって、無事、五日市で解散することができた。2年ぶりに復活した「1年生企画ラン」であったが、我々が1年生に望んだものは、実際にランを企画・運営する手立てを学びとってもらうことであり、そして、ひとつのランを全員の協力によって成就するなかで、学年内部がまとまる一助になればと思った訳である。結局、参加者は22名ということで、1年生企画ランとしては、例年並みといえたが、3年生の参加が5名だったのは、なんとも淋しかった・・・。
10月に入ると、11日から12日にかけて、秋の「オープンサイクリング」が催された。今回は、霧ヶ峰にその地を求め、下諏訪(集合) – 和田峠 – 白樺湖 – 大門峠 – 小諸(解散)というコースがとられた。秋のオープンは、全面的に2年生の手に任された訳であったが、日高君や萩原君を中心によくまとまった力を見せてくれた。
当日は、昨年度も一般参加された松本氏や堀越氏などの姿も見え、我々を大いに感激させた。考えてみれば、一般サイクリストを招いての、この形式のオープンは春のそれと異なり、いくつかの難しい問題をかかえている。そのうちでも、人集めが、その最大のものである。この問題は、昨年度も指摘されたことであり、今年担当された日高、萩原両君もさぞ痛感されたことであろう。だが、それがそのまま、この形式でのオープンを否定することになるであろうか。我々は、自分達のやっているサイクリングが、すべてであるとは思っていない。もっと違った形のサイクリングが存在するはずだし、それを実際にやっている人達もいることを知っている。我々としては、その人達と一緒に走ってみたいし、話してみたいとも思う。我々の代が、昨年度において、それまで続いてきた軽井沢でのオープンに代わって、一般サイクリストを招いてのオープンを実施したのは、そういった最大公約数的な点での一致を見たからであった。
10月18日、19日に予定されていた「パートラン」は、前日来の雨のために、実際に走ったのが2班だけという結果に終わってしまった。日光方面へ向かった班と、小生が参加した三国峠をめざした班である。ここでもまた、雨天の場合のランという問題が浮揚されたのであった。
第12回目を迎かえた今年の「早同交歓会」は、同志社側の主管によって、11月1日〜4日まで、秋の気配深まりゆく古都奈良をめぐるなかで行なわれた。全日程を通じて、そこかしこに石仏や、古社寺をちりばめたコースが用意され、例年とは一味違がったアカデミックな雰囲気の中で行なわれたのである。天武・持統天皇陵 – 高松塚古墳 – 石舞台 – 室生寺。走るほどに、走るほどに、はるかな古代へ帰っていくような錯覚にとらわれた。惜しむらくは、就職試験と重なって、両校の4年生の姿がほとんど見られなかったことである。それはまた、来年も当然予想されることであり、大きな課題として今後に残された。
なお、恒例の”タイムトライアル“は、同志社側の熱い要望によって、なんと2度も挙行されることになった。そして、その結果は、『1年間、この日のためにのみ』夜の大特訓を重ねてきた、主将酒井君の精進が大きな花を咲かせ、見事1位を取ったこともあって、大いに盛りあがった。ちなみに、彼はあの優勝カップを、トレーニングの相手に見せてあげたのかしら…。ネエ、酒井君。その他、このタイムトライアルでは、早稲田の1年生の活躍が目立った。
日一日、一日と寒さを増していく中で、今年度の「走りおさめ」ともいうべき、「追い出しラン」がもたれた。11月23日、4日、コースは小金井公園に牛前9時に集合した後、入間 – 越生を通り、二本木峠 – 釜伏峠を軽く越え、寄居までというもので、それは明らかに4年生5年生の体力と血圧を考慮してのものであった。だが、それにもかかわらず、峠を登る時の諸氏の走りっぷりたるや、みじめそのものであった…。その体たらくぶりを見るにつけ、『自分だけは、4年生になっても、アアはなるマイ。』と思ったのだったが、その半面、『もしも・・・』といった不安もぬぐいきれなかった。途中、後続の班が道をまちがえ、真暗になっても宿に到着しないという失態を演じ、宿で待つ私を大いにあわてさせた。それでも、「追い出し」という、和気愛々のランにあって、追求の手もアッサリゆるめられたようである。宿に着いてからのコンパは、予想されたこととはいえ、「追い出し」にふさわしい、ソレであった。
酒が意外と出たこともあって、先輩諸氏のボルテージも上りっぱなしだったようである。おまけに、岸田氏や吉川君の新曲発表が、それに輪をかけたようである。小生など、『出るか、出るか』と思っていた、柴田氏のアレが遂に見られなかったので、いささか拍子ぬけしたものであったが、4年生の歌う、『北帰行』や、『惜別の歌』などを聞いているうちに、妙にわびしさを感じて、胸がいっぱいになってしまった・・・。予定をだいぶオーバーして終わった宴会であったが、卒業される4年生、5年生はもちろん、我々にとっても、十分満足のいったことでしょう。宴会が終わって、おもてに出た時、身を切るような寒さと裏腹に、妙に暖かなものを感じた。4年生5年生どうも御苦労さま。
だれかが登り坂と言い/だれかが下り坂と言う/僕には/どちらか/わからない/僕にはわからない…。
社会・青年・私 – 田中
社会・青年・私
文学部3年 田中
支離滅裂な筆者の書いた
支離滅裂な文章を
支離滅裂な読者に捧ぐ。
司会者挨拶
現代の社会が、人間を除外し機械に犯された文明により、若者に与える影響は深刻です。若者は淘太の世界から必死に生きようとしています。しかし、そんな世界に残れずにいる者もいます。彼らはそこから逃れ、自分の生活の場所を求めなければなりません。或る者は、そのあるべき本来の社会を求めはするものの、結局は1部の倫理を失った者達の内に埋づまることでその生活の場を求め、そこに安らぎを見い出している。そこには全く別の世界がある。まるで一般の人間社会に戦いを挑むかの様に反逆的なものもあれば、また薬物により閉鎖された、他の人間の入り込もうとする事のない所に自分を置こうとするものもあります。そこは全く閉鎖されていて、他との関係をひたすら拒否しています。彼らは快楽に体を包まれている。否、自ら快楽、一時の興奮と言う鎧をまとっているのです。
果たして彼らには「生」はあるのでしょうか。勿論、積極的な意味においてですが。彼らは一体どういう風にして、そう言った状態に陥ったのでしょう?そして他の、少なくともこういう生活とは呼べない世界に逃避することのなかった若者達は、現代のような社会をどう考えているのか。それでは、少なくともこういう、生活とは呼べない世界に逃避することのなかった若者の1人であると自負している、田中君の場合を1つの例として、皆様の前に御紹介することに致しましょう。これは、彼がある日の夜、翌日の語学の予習も全て終えた後、徒然なるままに思い浮かべた事を文章に置き換えたものです。では皆様、御静粛に願います。
幕が開く
他に何もする事がない人、でなかったらどうする事も出来ない程暇な人は、この文章でも読んで時間をつぶして下さい。大学と言う所は入学する前からそう思っていたのですが、お金を出して時間を買うようなもので、何でも好きな事をして暮らしておられる場所のようでありまして、私もそういう点から起こる弊害をなくす為に、このWCCに入部したような次第なのです。勿論自転車が好きだったと言う事もありますが、いわば、E・フロム言うところの「自由からの逃走」というところでしょうか。と言いましても、これから先の内容はクラブとは全く関係のないことですから、そのつもりで。
これから皆様に読んで致きたいのはとてもつまらない事です。これは筆者自身が言うのですから、全く正しい事なのです。ですから、ほんとうに暇な人以外は別の週刊誌でも読んでいて下さった方が本人の為なのです。くどい様ですが、それだけは先ず申し上げておきます。
以前よく考え、また現在でも時々考える事なのですけれど、一体日本人と云うのは、何故こうも空しい人種となってきたのでしょう。高校の時の歴史の先生の言葉ではないが、全くバイタリティをなくしてしまっている。例えば、テレビでの街頭インタビューがその良い例を示している。インタビュアー「あなたの未来の夢は何ですか。」解答者「そりねェ・・、別にないネ。」
これだけ聞いただけで、もうその後は聞きたくなくなるのです。期待して聞いていても続いて出てくる筈が、僕らを失望させるだけだと高を括っているからであります。最もこれらの解答者はそのほとんどが中年過ぎのオジサン達で、我々のような若者ではないと言う反論も起こってくるでしょうが、しかし、それだからと言って黙っていられるでしょうか。
日本全体の風潮としてそういうところはないでしょうか。確かに「俺には関係ない」と言ってしまえばそれだけの事だが、それでいいのか。ほんとうに関係なく、自分自身ではっきりとした生き方を持っているのなら、それらの人達には、こんな事を馬鹿みたいに考えている人間も、確実に1人はいるのだと言う事を知って致きたい。
しかし、どうせ書くのだから、暇のついでに一諸に考えてもらえたらと思っている。正直なところはそういうことなのであります。ここまで書いて来て、やっと自分自身がその問題となっている日本人であると言う事を実感しました。それが日本人の最も顕著な特徴となっている。本音と建て前を、自分自身否定していながら、分けて使っている事に気付いた為です。
ここまで読んでしまった人、残りはあとわずかですから頑張って読んで下さい。読む人も実にかったるいと思いますが、書いている人も、きっとかったるいのです。それに、これも筆者自身語った事ですが、「自転車クラブの機関誌にこんな論文めいたものを載せたのでは、返って他の記事に障りがあるのではないか」とのことで、読者の事を気使っております。けど、ほんとにここまで読んできてしまったのだから、もり一気に最後まで読んでしまって致きたい。そうすれば、軽い坂道を息をつかずに一気に上りきった後の様に、さっぱりした気分になれる事は受け合いなのですから。
文章と言うものは、少なくとも読破してしまえば、それだけで十分な満足は得られるものですから、先ず読むだけでも読んで下さい。
(第1章)今の社会、どうなってんの
「人間は社会によって作られる」と言う言葉は、ほぼ完全とした意味を持っていると言える。誰が言ったかは定かでない。暇な輩は、現在日本国内で出版されている書籍を全て捜してみたらいかがであろうか。今のところ、この正解を知っているのは僕のみであろう。参考の為に、また暇がなくどうしても真理を知りたい人の為に最後の方で記しておくことにする。
と最初は思っていたのだが、清書をしているうちに、そんな事を言っていたのでは忘れてしまうだろう事に気付いたので、今この場で明かしておく事にします。多分この文章を読む方なら誰でも知っているだろうと思います。それは何を隠そう、この原稿に一当最初、名前の出てくる人なのであります。
さて、この言葉の示す通り人間は、既に、社会に影響されている。と同時に、社会は人間によって築かれている事も、明らかな事実である。これはちょうど、日本政府高官がロッキード社から賄賂を受け取っているのと同じだけの信憑性を持っている
(10年後、この雑誌を読んだ時、現在起こっている様な事件を知ったら、その時この埋もれていこうとする一文章は、どの様な重要な内容を含むことになろうか。そして、立花隆はと言えば、改めて脱帽せずにはいられないだろう。今この場に、インク消しが無いと言う事は、今後のクラブ内での私の立場をどの様なものにするか危まれる)。
のみならず、社会は文明を構築していくものであると言えるだろう。と言うよりは、社会と文明をほぼ同様のものとみなす事ができよう。よって、文明とその中にいる人間とは、社会においてと同じように相互関係を持っている。簡単に考えて、文明は人間の生活を良い方にもたらすと考えられるのだが、それは事実に則してみても当てはまらない事が理解る。当てはまっているのは、極く一部の人間達だけであろう。文明が人間を左右していくのは判然としている。
人間が文化(精神的なもの)、文明(物質的なもの)を持つようになってから、今日は第2の文明変革の時と言われている。第1の文明変革と言うのは、知る人ぞ知る18世紀イギリスに起こった産業革命である。これにより、従来の手工業的工業技術から工場制工業への変革が成され、経済的には生産力の偉大な発展を見ることとなったが、社会的には資本家と労働者との階級対立と言う重大な問題を引き起こしている。
階級対立の問題は、現在でも引き継がれているから考えから除外しても良いが、しかしこれを、社会文明と言う問題にしぼった場合、どういった点に相違があるのだろうか。今、問題の中心となっているのは文明についてである。現在のそれは、時代と共に、否、時代を追い越して急速な発展をとげている。(これは中部合宿の時、B班が美女峠に向かった際、4班が他班を返り見ずに飛ばして行ったのに似ている。あの時のCLは私でありました。5・6班の皆さん、ゴメンなさいであります。)がしかし、人間は社会科学上の問題として、それに追いつき発展することができない。産業革命当時のそれはどうだろう。社会が発展したことにより、それと同様のものと考えられる文明は、当然発展したであろう。
しかし、人間を無視して、機械のみが急発展すると言う事はまだ起こってはいない。また、人口と言う面から考えても、少なくとも人間が優位にあったことは相像するに難くない。
人間は機械文明を発達させ、現代は一名「機械の時代」とも言われている。人間の持つべき文明を、機械が取って換わって持とうとする現代は、人間は機械に動かされるの感を持たざるを得ない。常盤線沿線の天王台駅そばにある三ツ矢サイダーの工場など、一目見ただけで、人間の少なさ、人間が機械に動かされている悲劇を良く示してくれる。この様な光景を見て喜んでいられるのは、社会を考える事のない中学生ぐらいの子供達であろう。わずかでも人間、社会、エトセトラについて思う人なら、必ず現代の社会をのろわしく思うに違いない。
こういった文明機構が人類にもたらすものを考えてみると、
〇経営者に巨満の富
〇ホワイトカラーに精神的重圧
〇他の部門への労働力提供(つまり、オートメカ)
等々がある。
あっさり考えただけでもこれだけの事が挙げられる。この内で最も恐しいのは最後のものであり、現代社会の悪化へ寄与している1つの原因とも言える。
人口の爆発現象と社会の人間選択は、動物界で見られる自然淘太に似た現象を生み出している。『淘太』である。人間が淘太されていく。自然界で行われている淘太とは文字通りの意味では違っていても、これは大変な問題を生み出しているのである。動物界で見られる淘太では、あぶれた者は自然、死へと至らしめられるのだが、人間界では彼らは一体どこに行けば良いのだろうか。ここでは触れないことにするが、教育問題にも同じことが言える。最もこれも文明に巻き込まれて動かされているのであるが、ここでも淘太が行なわれている事は誰でもが知っている事実である。
機械文明の持つ冷たさと、人間の教育と言うものの中で見られる御太の冷たさは、そうした人々を不信の孤独の世界へと連れていく。孤独の内に置かれた人間の寂しさ、辛さ、遣る瀬なさは、その内に入ったことのある者にしか解らないものである。
(第2章)急ぎ過ぎた若者の論理
人間は元来、1人1人が全くわずかな弱い力しか持っていない。そして孤独であることに耐える事ができず、いつでもびくびく、そわそわとしている。それ故、人間は自分の存在を他の何らかの集団 – 例えばクラブであり、政治党派であり、暴走族である – に委ねることにより、強固にしようとする。そこでは集団所属意識が働らいて、自分の存在を足場のあるものとして定着出来るのである。
集団所属意識を持てない人間は不幸である。そういう人は、あらゆる事を自分1人の身に持ち、蓄積し、発散できずにいる。悩み、悩み、そして悩み疲れてしまう。彼らの思考の順路を簡単に示してみよう。
〇人間は一体何の為に生まれてくるのか。何故俺はこうして悩んでいるのだろう。
〇俺は生まれる事を欲しなかったではないか。生まれて、生きている事に苦悩の種がある。俺の誕生と共に、苦誕も誕生した。
〇人間、否、動物の行き尽く点は死である。その間の過程は、一体俺に何を与えると言うのだ。全ては俺の肉体の滅亡と共に消滅するのではないか。
〇生きる事の究極の目的は死にある。それならば1足飛びに目的に飛びついてやろう。
斯くして、急を過ぎた若者の到達するところには、ブロバリン、ハイミナール、電気、絶壁等が用意される。彼らは満足できない集団所属意識を、自ら持ち得ないようにすることで、その願望を成就させてしまう。つまり、その精神を宿しているところの肉体を滅却させることにより、苦悩から逃れるのである。
ここで考えねばならない事は、彼ら自殺者の持つ思考過程の誤りはどこにあるか、と言う事に凝縮されるであろう。この問題の解答は明らかである。それは論理の出発点にある。人に生まれて来た目的を示す事は、それ自体無意味と言わねばならない。目的を証明できる者がいるとするならば、それは神のみであろう。しかし、神の存在を否定する私としては、この意見もたいした意味を持たない。ただ単なる仮定の話、それだけのことだ。人間には本来、生まれてくるべき目的など有りはしないのである。
それはサルトル言うところの実存主義が明らかにしている。人はそれぞれ生まれる時、否、受精の際に各々の事情をその生命に持っている。或る者はほんの戯れによってであろうし、或る者は荻野氏式避任法を逆に利用することで、計画的に制作されたであろうし、また、たまたま薬局が休業であった為等、その理由は多岐に渡るであろう。が、しかし、理由はいかなるものであろうと、親となるべき者は果たして子供を制作するに当たって、目的など持たせたであろうか。それが個人に関するものについてである。全ての人間については理解らないが、僕自身はそうでないと思われるし、また他の多くの人も多分僕と同じであろう。そうであるならば、彼ら生きる事を急ぎ過ぎた人間の誤りは、どのように訂正されるべきなのだろう。次に提示される問題がこれである。
思考の誤りがどの点にあるか明示された以上、これをどのように改めるかによって問題の解答は与えられるであろう。人間1人1人には元来、生まれて持ってくるべき理由などない。そうだ、ほとんど多くの人間にとって、全く無いと言っても過言ではあるまい。有ると仮定して考えたならば、答はどこまで行っても否定の連なりであって、最後には自己の否定にもつながるのは当然の帰結である。
人間はその問題とするところは、「いかに生きるべきなのか?」と言う事にあるのである。勿論この考えには、目的と言うものが備わっているであろう。例えば、大学と言うものを目指して高校生が猛勉強する如くの。また、有名商社と呼ばれる会社に入って多くの金を得る為に、大学を利用する人間もいるであろう。それらも、それぞれの時点においての小さな目標ではある。だが、しかし、それだけの目的で生きている人間はそう多くはいないだろう。それだけのものであるなら、その人々は吝嗇家(りんしょくか)として一生を終えるだけである。別に、そういう人を責めているのではない。僕に言わせれば、空しい一生であるのではないか、と言うことだ。人は誰でも、ある時点時点で、その時に応じた小さな目的を持って活動しているが、それが究極の目標ではないであろう。これら小さな目的はどれをとっても、究極のそれに近づく為の条件として用いられているのではないだろうか。
ほぼ普通の人の一生を簡単に追ってみよう。幼稚園→小学校→中学校→高校→(大学→)入社→金銭→幸福。それぞれの時点での小目的は、現代社会においては(他の時代でもそう違ってはいなかったろう)金に凝縮され、最終の目的は幸福で落ち着いた生活へと連なっている。そして、これら一連の流れはこういう上記の様な生活を求める人にとっては、いかに生きるかと言う命題で始まっているのである。ここまでは極く一般の人でさえも、考え得られる人の生活の経路であり、自分なりの幸福の為に、その到達方法(いかに生きるか)に重要なポイントを置いていることがうかがわれる。
(第3章)私の場合
それでは、最後に私自身はどのような考えを持っているのか簡単にお話します。論理的には今まで説明したように割り切ることができたとしても、それらの問題解決の道は、結局この訳のわからない生の中にある故、生と言うものを明確につかめない限りは、正しい方向が見定められない様にも思えるし、また僕個人の経験からも判然としている。もっと具体的に問題を考え直してみよう。
問題の分岐点は、何故生きるかと言う事と、いかに生きるかと言う事に拡張している。そして1つの(私としては全く正しい解決の道と考えるのだが、この他にも別の考えがあるとすればそれも又1つの意見である。)解決の道すじとして後者をとり、そしてその中における最終の目的と言うものを個々人の幸福へとつなげた。一見これが最も一般的な人生の道であるのだが、先ほども言ったように、私個人の経験として、すっぱりと割り切れるものではないのである。
「君個人の性格、人生への方向性(すなわち、これからの一生に対しての明瞭な目的)がない為にそういう思考経路に落ち入るのだろう」との反論も有るだろうとも思われますが、それに対しては僕は何とも反駁する事はできません。人間の性格を責める事は、それ自体意味のある事とは思われません。ここでは何故割り切った物の考え方が持てないのだろうと、その事のみに注目して致きたいのです。何故、割り切って考えられないか。それは、前にくどくどと述べて来たことの繰り返しになりますが、個々人の究極の目的であると述べた幸福が、全て有限の人間の生の内にある為に過ぎないのです。
「人生、幸せであればそれでいいではないか。一体何をそんなに深刻に考え込んでいるのか。」と言う。これを読んでいる諸氏の口から漏れる言葉がはっきりと私の耳にも達しているのですが、しかし頭悩で消化され、思考の養分と成らずに老廃物として蒸発して行ってしまっている事も、又実感できるのです。この問題は即答できるものでもないでしょう。ただ、慌てずに考えていられる自分がそこに生きているだけましなのかも知れない。そして、これからも訳の理解らない事を考え続けて行くのでしょう。
結局、誰かから「人生って何なのでしょうネ。」と聞かれたら、「良く理解らない。でも今は、それが何かを考える事が私の人生のような気もする。」としか答えられないでしょう。
人生が何かなどと言う事、理解るにはまだ若過ぎる。人生を考えるには、先ず生きていなければならないのである。これだけが、僕の言える最も確実なことなのです。
白い壁 – 日高
白い壁
教育学部3年 日高
栂坂峠。私はこの峠の名を一生忘れることはできないでしょう。奈良で行なわれた第12回早同交歓会の風景を折り込みながら、その峠での出来事をお話しします。
同志社大学主催による今交歓会に参加した私は第2班に加えられました。この班はユニークな人格が多く、走っている間でも会話がとぎれることなく交され、楽しい雰囲気に満ちていました。11月2日の、明日香村石舞台から談山神社までのタイムトライアルの後、我班の吉川君が駐車していた車と喧嘩し、自転車の1部を損傷するというハプニングが起こりました。しかし、大した事もなく全員無事に吉野山に到着しました。
翌日、私にあのような運命が待ち受けているなどとは夢にも思わず、ユニークな人格に囲まれ和気靄々とした中で、吉野山のユースホステルを後にしたのでありました。この日は班別の行動で、我班は吉野山を下った後、伊勢街道を今夜の宿泊地である名張へ向かって走っておりました。道は平担で走り易く、時間が許せば、赤目四十八滝でも見に行こうか、などと話合っておりました。
高見峠の手前で伊勢街道より分かれ、滝野、開路を経て、いよいよ本日唯一の峠である栂坂峠目ざし、意気込み挑戦しましたが、何の事はない、峠とは名ばかりのものでミニサイクルのアベックでさえ楽に登ってゆける峠でありました。それでも峠だというので休憩を取り、後から来たミニサイクルのアペックと記念写真を撮ったりしたのです。その後、峠を下るところを8ミリで撮ろりということになり、同志社のA君が1人先に峠を下り、撮影の準備をすることになったのです。
数分後、我々は峠を下り始めました。8ミリの前を皆が大胆なポーズを付けながら通り過ぎるのを見て、私も8ミリに出演するにあたり、短時間のアップにするか、長時間の点景として写されるか、いろいろ迷った挙句、前者を選び、ハンドルを8ミリを取っているA君のいる反対車線へ切ったのです。いかに美しく写されるかという一心で、8ミリの方へ視点を注ぎ微笑みかけたのです。さあ、これで私の出番は終った、と前方を見ると、なんとそこが左カーブであったことに初めて気がつき、すぐにブレーキをかけたのですが、加速を押さえただけで、自転車は止まる気配もありません。「曲がり切れない!」と直感した私は、前方のガードレールの合間に小さな草地があるのを発見し、ガードレールに激突するよりは増しだろうと、その草地へ時速30km位のスピードで突入したのです。
頭から転落したものの意識はしっかりしており、私はすぐに立上り、横に自転車があるだろうと辺りを見渡すと、何と自転車は数メートル独走しており、崖へ転落していました。どうして私だけが草地に落ちたのか合点がいきませんでしたが、よく助かったものだと感心していると、次第に左肩が熱くなってくるのを感じたのでした
「救求車はすぐ来る!」はずでしたが、何しろ田舎のこと、その救急車がどこかへ行ってしまったということで、救急車の運転手が白ならぬ黒の自家用車で、約1時間後に私を迎えに来てくれました。私が運ばれた先は町立病院でありながら、藪医者でありました。愛想も悪く、レントゲンも撮らずに左鎖骨骨折と診断を下した後、やおら棚より、回りが茶色に変色した医者のあんちょこを取り出し、ああでもない、こうでもないと楽しそうに私の横にいる看護婦と話しながら、私を巨大な絆創膏で巻き付けて診察を終えました。
その医者の提言により、私は2班の班長である同志社の二木さんと吉川君に新大阪駅まで見送られ、体操服のまま新幹線に乗り込み、帰京したのでありました。
これを振り返ってみますと、私はサイクリングというスポーツをやっていたにも拘らず、全神経を自転車に向げず、8ミリを気にしていたあの数秒間の怠惰、すなわち、サイクリングをしているからには、そのサイクリングの時間を1秒1秒真摯に充ち取ってゆかねばならないことを怠った結果、起こるべくして起こった事件(過失)ではなかったかと、この頃反省しております。…
帰京して2日後、私は近所の病院へ入院しました。私の病室は白い天井と壁の窓外の風景とに囲まれた虚しい空間でありました。その空間の中央にポツンと私が横たわっているベッドがあります。満足に動く事のできなかった私は、毎日白い壁の1点を見詰めながら、様々な想念に捉われていたのです。しかし、この優雅な時も手術までであり、手術後は薬などの副作用のせいか、気分が悪く、何も考えることができなくなったのです。
そんなある日、暗雲の道中を彷徨っている私を、見舞に来てくれたクラブ員の面々を白い壁の前に見た時、空虚な白壁が希望の白壁に見え、心の暗雲の中に1条の光を見出したように思ったのです。
峠を求めて – OB程島
峠を求めて
性春の悶 – どっこいオレは生きてるぜ
商学部OB 程島
私は出発前夜、1枚の写真を見つめていた。あれは、忘れもしない1973年8月14日の非常に暑い日の事であった。私は東北合宿を終えてから、入部以来の輪友、柴田オナラの介とベッドではなく列車を共にして、直江津の駅で数日後の乗鞍岳での再会を祈って、しばしの別れをしたのであった。
それから数時間後、私は長野をあとにし、「おうーおうー。この峠はきついぜ!おっ、あの車いっちょまえに女なんか乗せおって。にゃーろー、自転車じゃいきがってもさまにならねーよなー。おうーきついぜ!」といったような伊達ブツブツの介ではないが、1人言が思わず何の気なしに、屁をこくのともろ同様といった感じで出て来るぐらいの、きつーい峠をヒコヒコ走っていたのだ。が、しかし、その1人言はうそで、オレは1こぎするたびに「あっもう峠か。しょうがねえなあ。近頃骨のある峠が無くなっちまったよな。もう1丁越えるか。」ってな調子で、四十八曲峠、修那羅峠、豆石峠、保福寺峠と昼メシ前に4丁の峠を4回ペダルをこいだだけで料理したのよ。距離にして70キロ、標高差1,770mを走破したのであった。
私は自己の限界に挑戦しようともくろんでいたのである。しかし、ちまたでちょっと騒がれていたらしいエディメルクス(彼はどういう訳かオレとの勝負をきらった。負けを恐れていたからだ。その証拠にメルクスはオレの居る日本に1度も来なかった。)なんつう奴なんかシッポ巻いて逃げ出す程の地獄林道が次におひかえしておったのである。
この完全岩石道路の蝶ヶ原林道には、さすがの根性1本どっこサイクリストたるオレも考え、アグネスちゃんちゃんつうー感じだったのよ。オレがこうだから、よく1人言を言う分身の方はどうだったかと言うと、「あーあ水を飲み過ぎたしな。メシも食ってねえしな。なんだこの道は。通行止めじゃんか。通行止めじゃ行かれねえよな。しゃあないわ。こりゃ。」てな調子で、てんで弱きそのものよ。それでオレはどうしたかっつうと、もうこれを読んでいる先天的単純明快的救助船も転覆する事まちがいなし的、ヒマ人の方々の中には、ひょっとしたらオレとオレの分身との関係が、どうなっとるのかに気づいた人がいるのか、いない事はないのか、わからないが、その答えは、分身はグチを言ったり心にもない事を言ったり、うそをついたり、とにかく、くっちゃべるエネルギーは待っているが、行動するエネルギーは与えられていないわけよ。後者のエネルギーはオレが持っているわけよ。
だからオレは、敢然とその林道に突入して行ったのである。それは正に完全岩石道路であった。左手の尾根から石っころなんつー甘いもんでなく、岩っころがこれでもかこれでもか、という位に道の上にあったんだ。それも本当に岩っころがこんなに転がってるのかなって疑いたくなる程転がってたんだ。だからオレはホッペをつねってから改めて道を見たんだ。しかし、やっぱり転がってたんだ。正に岩っころまた岩っころ、そして、もひとつおまけにハイ!岩っころじゃんという感じだったんだ。
それは客観的に見るも主観的に見るもなんて及びでない道で、WCC入部以来走破して来た経験の集体成を要求するものであった。私はこの道に絶対に屈服したくなかった。私は10段にせざるを得なかったが、そんな事は、その道で私が屈服した事にはならなかった。私は勾配も15%マッツァオの道、それも左側の尾根からくずれ落ちた岩石に占領されわずか10数センチ程しかないその道本来の路面を、正にロデオ張りに乗りこなしていった。
「ざまあみろ!こんなとこを走れるのはオレぐれーのもんよ。ケッケッケッ。おっとっと。この憎たらしい岩っころめ。この石っころも憎いぜ。だがよ、いくら転がっていたってオレにはへのカッパよ。岩っころメ、もっと転がってみろ。」といったように、分身もいつになく鼻いきが荒い。分身がそう言っている時はオレは疲れているのだ。
しかしだ。分身とオレがかかる関係にある、いや陥いった時こそが、私の求めるものを生み出す時なのだ。私は走りながら、余裕にも屈服ならぬ一服していた。私は屈服していなかった。なぜなら私はその時「 オレは走っている。」と確信し、そして両腕の毛が強裂に逆立つのを感じていたからである。オレはトリ肌から生まれるというトリが1せいに飛び出さんばかりに毛を逆立てて、それを乗り切った。距離110キロ、標高差2,500m、長野から四十八峠、修那羅峠、豆石峠、保福寺峠、そして蝶ヶ原を経て松本までの記録である。(いきがった割にゃーたいした事ないよな。この記録はよし。でもよし、本番の記録はまだこれからの事よ。期待してろ。)
なお、この蝶ヶ原林道では、針と糸がこんなにも貴重なものかと痛感した。それは、やっと峠を乗り切った時である。緊張がとけてションペンの方も気がゆるみ、祝走破放出をやってみるかってんでヒョイと手を第3の分身をつかむために短パンのジッパーにやったのであるが、しかし、オヨヨ、不思議く、オレの手には第3分身が即飛び込んで来たのであります。そう、あまりの激闘に私のグレーのカルダン製の短パンはもうだらしなく破れていたのですね、これはまぎれもなく。「おーおーあぶねえ、あぶねえ、車輛通行止めで良かったぜ。」オレは短パンを脱ぐというよりはずすといった感じではぎとり、バンツ1丁にランニングというB・C・アダムスにかなり迫る格好で道端にすわり込み、なお、裁縫をしたのであります。WCC諸氏よ。裁縫道具は持って行った方がいいぞい。
話はコロッと変わって、私は例によって相変わらず例の如く、その夜松本駅前に寝転がり、オレの方をものめずらしそうに通り過ぎる人達(もちろん目が疲れるのを避けて若い女だけに焦点を絞っていた事はあたりまえ。)の反応を楽しんでいたが、そんな事は本来好きではなかったので、それにいいかげん3時間ぐらいでもう飽きて、私はふと空を見上げた。そして、オレは、ただ1点を見つめていた。そう。北斗の星を見つめていたのだ。オレは、その夜、何か自分の中に強いものが入り込んだような気がした。これこそが、これまで私が思っていた”大自然との接点”たる峠から得る何かなのではないだろうか。正に、この岩石だらけの道の中に立つ愛車の姿は、それを訴えているといえるのだ。
私は、この写真を見るたびに、あたかも渡りの季節の渡り鳥のように、何か押さえ難い熱情が湧き起こるのを感じざるを得ないのである。そう、それは峠が私を呼んでいるからだ。
峠は過酷だ。それは、それが偽りの無い自然の中にあるからだ。峠越えには甘えは許されない。だが峠には何かがあるのである。だから私は走る。そして私は、いつの時も常に自己の限界で峠を訪れたいと思うのである。
オレは写真を見つめたまま、これまで訪れた峠に、又明日から訪れる峠に思いをはせていたのであった。オレは走るぞ!今、この時に! オレは心の中でそう強く叫んで、ベッドの上でペタルフミフミ運動をしながら、1人でいきがっていた。
我が愛せし早同の記録 – 野口
我が愛せし早同の記録
教育学部2年 野口
PART1 そこに男がいた
10月29日、いつものように池袋で輪行を済ませた私は、丸の内線を駆って一向東京駅へ急いだ。やっとの思いで東海道線の改札口へたどりついた時のことだった。「君、1年生?」という声がしたので一瞬たじろぐと、好青年が、「どこへ行くの?」と更に問うのだった。すかさず私は、「早同があるので、ブライベートも兼ねて若狭・奥丹後を汚してこようかと思ってるんですが・・・、ところで先輩は?」
X氏曰く、「いやあ、僕ネ、岡田君達と同期の陶山だよ」エッそれでは大先輩ではないかと恐れおののく。ほんの1、2分立話して別れ際に、せん別でもいただけるかと甘い空想に耽っていたがやっぱり、当然のごとく、「じゃ、気を付けてネ、失敬」先輩と話してて感じたのだが、あのカンチョーマンスタイルは幾つになっても懐しいのだなぁとWCCの強烈さを改めて見直す。
PART2 列車番号347
階段を登るとそこは9番線だった。今夜は僕の初体験の日である。あの恐怖の大垣行に乗れるのだ。いつも新幹線の自由席にしか乗ったことがないのに、18の心はその余りの転落に感激した。少し、否、長ーい時が過ぎていよいよ入線だ。優雅にあさましく、良い席ばとらにゃいかんば、と思い輪行袋を抱きしめてドアに突っ込む。終電に乗り遅れた酔っぱらいで、徐々に車内は混んでくる。知らないおじ様が横にすわる。でもローカル線ていうか、各停っていうのは旅情をいやが応でもかきたててくれるのだ。また今夜も旅に出るのだナ、という感情に耽る。静かにといいたいところだが、飛び込み乗車もいると見え、「わっ、いてえ、何やこのじじい」とかの罵声の中で発車する。後に残るのは、一日の勤めを終えて閑散としたホームとゲロの固まり、それに美しい流線形のひかり号だった。
PART3 白馬童子よどこへ行く(その1)
ここは大垣、1度はおいでという歌があるかどうかは不明だが、新快速に乗り換えることにする。まだ学校は休みでないと見え、途中の無人駅からセーラー服が乗ってくる。米原で北陸線各停に乗り次ぎ。長浜の地を過ぎる頃、豊臣秀吉の封地であった事を思い出し、彼のことをしのぶ。またまた乗り換えなのだ。ここ敦賀は深井少年と夏のブライベートの一歩を記したところである。敦賀から小浜行きの若狭2号に乗車。なんと単線で、途中、五木ひろし君の生れた所を通る。やっとこさ小浜に着いたのが午前10時過ぎ。座り過ぎでケツも痛い。早速愛車の組み立てにかかる。いつもながらいとしい車よと感激し、道中の苦労を考え1人涙す。WCCにこれだけナイーブな面を持った人が居れば、中野君の様な悲劇は起こらなかったであろう。合宿を想起してほしいよ、これについては。
PART4 白馬童子よどこへ行く(その2)
小浜から天の橋立まで行くことにする。即、日和って海岸コースだ。コース的にはなんてことない道だ。ただ雨だけが気に掛る。舞鶴で休憩をとる。ここは海上自衛隊の基地がある。路上、軍用トラックが追い越していく。中からナッパ服きた水兵さんが僕を注視している。一瞬赤面する。これこそWCCの面目躍如の時と思い、カモシカの様な脚でスパートする。見る見るトラックは遅れる。なんのことはない、駐屯地のゲートをくぐるためにブレーキングしたのだ。しかし、軍艦というのは優美だ。美の極限を感じる。一見、灰色の鉄の塊まり風だが、機能的なことこの上ない。舞鶴付近から雨が降ってくる。強行するが、雨足は強くなるばかり、ついにあと120円区間まできて断念する。天の橋立駅で降りる。YHに行くまでが大変だった。風雨にさいなまれながら山を登る。地獄だった。全く。
PART5 嵐ヶ丘
YHはちょうど小高い丘の上にある。ずぶ濡れの服をしぼりつつ、ホッとする。明日はいよいよ奥丹後だと思い、決意を新たにして、女の子達と興ずる。2人ともヨーコだったが高校生は可愛いいのう。一夜明け、雨は収まったが湿りがちである。一同の声援を背にカンチョーマンスタイルで出発。天の橋立の中で、2人のヨーコに追いつく。「あの早稲田のサイクリングって素適ですネ」と言い寄ってくる。2人と別れて今日のコースを検討してみる。軟弱にも、強風波浪注意報を盾にとって奥丹後はやめる。野獣死すとかなったら困るもんネ。
即、福知山を目指す。なに、昼前にはつくと思い安心する。楽勝と思いきや、ダラダラ上りが続き、おまけに雨まで降ってきた。切り通しの頂きに立ち、さァ下りだと軽快に行くと、なんとまた上り。甘かった。後日、DCCの連中に聞くと、この峠も割合よくいくとのこと。しかしだ、日本海側はさすがに寒々としている。あながち雨のせい、季節のせいにもできないと思う。太平洋ベルト地帯に比べて立ち遅れが目立つ。福知山からまた輪行。うまい具合に京都行きがあったので飛びのる。コーラとあんぱんの昼食。
PART6 同志社にて
京都での寝ぐらを捜すために同志社へと向かう。同志社って校舎が離れてて面倒臭い。やっとの思いでBOXを訪れる。「あの、ワセダの者ですが」とおずおず言うと、「なに、もうきたのか、ま、座れ」と、やたら、せわしい。でも初対面の彼等から歓待を受けて、本当に嬉しかった。でも俺、同志社、落ちたもんネ。早速、サ店に行き、落ち着いてきたので1卓交えることにする。その晩はとりあえず梶山君の下宿に泊まることにする。彼はその容貌どおり、ざっくばらんないい奴だ。でも、自分の下宿を忘れたのには参った。さすが同志社、西の雄。ここで負けては男早稲田の名がすたる。地でいこうと決意する。結局、梶山氏宅に2泊した訳だが、体調もおもわしくなく、満足に酒をくみ交わすこともできずに済まなく思っている。
PART7 集合
新谷君と連れ立って近鉄に乗る。1昨日位から腹の調子が悪い。出るものが出ないのだ。痛む腹をさすりながら、橿原神宮駅で組み立てを始める。しばらく待つと、来るわ来るわ、黄色い群れが、懐しい顔ばかりだ。まだ同志社とはお互い初対面なので、初夜の床の花嫁の様に恥じらっている。全員集合したところで、班別にYHへ向かう。我が5班はWCC側から、杉本氏、深津氏、私、DCC側から内田氏、西尾氏、比垣君、太田君だ。ところが、ここに1人阿呆なのがいた。私の口から言うのは恥ずかしいが、姫路の女殺し深井少年だ。彼は、何と集合時間を午前9時と間違えて、待ちくたびれて姫路へ帰ったという。やっぱり保護者同伴でないといけないかた。深井君、この汚点のために第2回のTTでは黄金の脚もお目に掛けることができなかった様だ。
YHでは待望の メシにありつけた。なにかと同志社の3大必殺技のひとつである早メシについて噂されていたのだが、早さでは私も決して劣らなかった自負している。だが、あのクソにたかる銀蠅以上の、骨までしゃぶるおひつの底の根性は認めて悔いなし。梶山君、君には参った。つつましやかにしょう油で、2杯くってから本菜にとり組むのだから。その晩は合宿以来絶えて聞くことのなかった某氏の歯ぎしりを子守歌に、やすらかた眠りの世界についたのだった。
PART8 押しとかつぎの多武峰TT
タイムキーパーの大役を負った僕は、早くから眼が覚めていたのだが、皆の安らかな寝顔をくずすのもものとせず、一喝。即、門杉トレマネ氏の地獄が待っていた。ワセダサイドから苦痛の声がもれる。小生、合宿と同じく、池田氏とともにトリ。魔太郎君並に、この恨みはらさでおくべきかと、コンパの日のために体力温存、TTの手抜きを講ずる。
初日は、飛鳥村見学後、予定外のTTがあった。さすがに全員緊張の色を隠しえない。と思いきや、何のことはない、修学旅行のおネーチャン達の品定めに余念がない。男の性は争えぬ。5分間隔で次々と発送することになった。ちょっと自転車に乗ったかと思うと、もう押し。狭い山林を登る。汗はかくし、足許は泥だらけ、誰もいないので、つい力が抜ける。と、後ろから猿の様な、身のこなしの快男児登場。これが1回目TTの覇者、日向建児鳥越日吉丸だった。次の組なのに、さすがですネェ、山奥育ちは。
やっと道に出る。渋谷さんがにやにやして見てる。私は痔が痛む門杉さんと共に、メシのくえるであろうゴールにとびこんだ。一服してると、中山さんと同志社の中山さん、つまり中井さんが「俺がブービーじゃ」とか醜くく言い争いしてやってくるのが見えたのだった。上には上がいるものだとひとしきり感心する。昼飯は下ったところにある神社でくったのだが、小生、蜂に手を刺されて、はれあがったので、佐々木君の注告に従い、小便ぶっかけて、メンソレータム塗って済ませた。この頃は既に早同両校の1年共は、まるで10年来の旧知であるかの様に振るまっていたのだ。
この後、吉野山へ向うのであるが、下りで吉川船場太郎君がアクシデントを起こしてしまった。現場に居た訳でないからはっきりしないが、車とじゃれあってしまったとのこと。フリー側のエンドが曲がっている。下りではとにかく気を付けよう。注意一秒怪我一生である。そんな吉川君の事故にもめげず、我々は立ち上がり歩を吉野山へと進めた。ところがである。トンネルを抜けても行けるというのに、内田さんがわざわざ獣道を通ろうなどとわめきはじめ、結局トンネルの上を越えて行くことになってしまった。
とにかくひどいところだった。草や苔で足はすべるし、道は崖崩れで細くなってるし、悪戦苦闘。今思い出しても吐気がする。でも楽しかったようでもある。悪魔の道を抜けてしばらく行くと、なんと、後発したはずの中山さんたちが、国道の方から走ってくるではないか。ムムッ計られた。時すでに遅し。しかし、これからが大変だった。全班集合して吉野山のYHへ向かったのだが、登りばかり。しまいには、また押しになってしまった。でも、吉野山からの眺望は絶景であった。
PART9 班別フリー
今日は楽しいフリーラン。昨夕、恥ずかし気に参加した深井も一夜明けると、もとのもくあみの姿になっていた。我が5班は、北垣、太田両氏の企画の同志社結社100周年記念コースを行くことになる。
いかめしい名称だが、楽勝とのこと。天候にも恵れて秋の吉野を満喫できて本当によかったと思う。栂坂峠等も越えたし、青連赤川に沿った香落溪は抜群だった。ちょっと車が多かったけど。これを読まれる方々、あの感激をもう1度思い起して下さい。
我が5班は楽勝コースの名に恥じず、赤目ハイツには1番のり、風呂もアカ浮かぬ前に入れて本当によかった。北垣君有難う。ところが、この時、事件は起ったのだ。内田さんが何やらつぶやいていたので聞くと、今、電話で早稲田の人が事故で重傷らしいと連絡があったと言われる。一瞬、全身の血が逆流するのを覚えた。その後、後続の班の到着と共にわかったことだが、日高氏が栂坂峠の下りで転倒、崖下に落ちて、鎖骨骨折との話。日高氏は付近の病院で手当の後、即、帰京された。とにかく大事に至らずに済んでよかった。この時、日高氏の班のCLは新谷君だったのだが、人づてに聞いたが、誠に沈着冷静で適切な事後処理をしたらしく、感服した。今度の事故は、日高氏だけのものではなく、我々全員への警鐘として受け取るべきであろう。
今夜の宿泊所の赤目ハイツは民宿で メシも豪華でみんな満足していた。この晩は学年別ミーティングが行なわれた。お互い両校の印象や早同について話しあったが、惜しむらくは、もう少し時間が欲しかった。なんとなく改まった場所になるとみんな遠慮がちになってしまっていた。酒でもくみ交しながら話したいな、もう1度。
この日、内村氏が新鋭ロードをひっさげて、小林B氏が、白鳥号に乗って参加された。
PART10 ハイライト
第2回目のTTの日はやってきた。笠間峠を越え、津越から水間峠まで5.5km、標高差285mへのチャレンジである。さすがに、今日は緊張する。老雄、酒井主将など、秘かに覇者たらんと望んでいるらしく、アディダス ランドリア レーシングチームの僚友石沢氏のマッサージをうけている。かと思えば、民家の渋柿をとって遊んでいる中山、中井両氏のブービー狙いの組の姿も見えた。コースは最初に急坂があり、後はだらだら坂である。いよいよスタートである。私めはたまたま酒井氏と一緒であった。勝利の女神よ、主将のもとに輝きあれ、と秘かに祈っていた私であった。コース的には楽であったが、最初のメカトラで意気消沈してしまい、また、緊張のためか、やはり長く感じられた。もっとトレーニングせにゃいかんばいと思ったのだ。結果、オリーブの冠を授けられたのは酒井主将、2位鳥越、3位高橋、4位吉川と早稲田側に凱歌はあがったのである。戦いすんで日が暮れてではないが、神社でメシをほうばり終ると、奈良への下りが待っていた。快適を下りで、眼下に広がる古都奈良と紅葉の錦は早同最後のコースにふさわしいものであった。
全員、鹿のたむろす公園に集い、整理体操をして、解散、祇園でのコンパ会場に集合することにする。京都まで走ってゆく組や、輪行する組、どの顔にもランの時と違った笑みがりかんでいた。私は走って入京、BOXに落ち着いたあと、入浴、番号の女の子、可愛かったなあ。
PART11 酒は涙か溜息か
田淵さん待望のコンバなのだ。久々に美酒で喉を潤せると思うと楽しい。テーブルの上にはすき焼の用意がある。もうたまらん。
乾杯の音頭のあと、いろいろ話がでたが、一応割愛する。宴も半ばの頃、学年芸能会が始まる。早稲田側1年も、武藤君の脚本までできていたのだが、訳がわからなくなり、結局歌を歌って、騒いでおしまい。その後はもう無礼講、コッブ酒をあおる者も居る。そら始まった。早稲田得意のコンバットマーチが。伊藤さんが、内田さんが、門杉さんが、板東さんたちが次々と宙に舞う。宴も終りに近い。校歌、応援歌の交換。私は、否、私だけではないと思うが、同志社しょうよう歌の時には、不覚にも泣きだしてしまった。門杉さんを始めとして、次々と握手を求め、涙はとどめもなくでてとまらない。至る所でこんな風景が見られた。皆、心の底から早同を愛している。そう思う。何も言うことがない。事実、これを書いている今、あの感動が体中を駆け回っているのだ。
1次会の次は、2次会だ。皆、放歌高吟しながら街の明りの中へ消えていったのだった。
思い出してくれ – 石沢
思い出してくれ 石沢
私は2ヶ月前に袋の中に入って以来
バラバラの体をその中に横たえている
走ることを忘れてしまいそうだ
天城峠はよかったなあ
北海道 信州 九州 東北。
全くよく走ったもんだ。
峠路に残した厳も数知れず。
思い出も尽きない。
私も歳を取ったもんだ。
でもまだ走れる。
袋の中から主人に言った。
「暮坂はよかったね。」
「武道峠へ又行こう。」
「渋峠にも行きたいね。」
でも主人には聞こえない?!!
もう私のことなど忘れたのだろうか。
さびしいですね。
表紙のことば – 小林
表紙のことば – 信州峠にて
政経学部4年 小林
昨夜の東京の雨は、この辺りでは雪であったようだ。信濃川上から、数年前とはうって変わった鉄製の標識に従って峠への道をゆけば、それでも右手に雪をかぶった八ガ岳が美しい。残雪が、やわらかな春の陽に照らされ、雪溶け水となって道に小さなせせらぎを作っていた。遅い春の訪れを聞きながら、足先が濡れるのに任せて、トボトボと歩いてゆけば、形ばかりの九十九折を経て、やがて峠に着く。振り返り、やがて消されるであろう雪についた足跡と轍に、1人苦笑いし、数年前と何1つ変わらない、峠の風情の1つ1つを確認してみたりする。登りがいがあるわけではなく、又決して眺望も良いわけではないが、私はこの峠がたまらなく好きだ。
編集後記
編集後記
一仕事、終えたあとの一服のタバコ、満たされたあとの空虚と何か相通じるところがあるのではないだろうか。(清水)
ここに、われわれ意を同じくする者たちの3年間の結晶がある。この中には、何のまじり気もない、われわれ1人1人の喜び、怒り、哀しみ、楽しみが、純粋な形でつくり上げられている。来年は、今年の経験を生かして、より一層のものを目指していきたい。(田中)
峠編集にかかった時、僕はコートを着ていた。今、編集後記を書く僕は、コートを脱ぎ、セーター姿で居る。この雑誌が世に出る時、僕は半ソデのシャツ姿で居るだろう。(小林)
昨年度のブロントバッグ前刊号に、「峠」問題始末記、と題する小文を載せた。そこで、われわれは、「峠」11号というものを、「年間の記録を主とするもの」として位置づけた。これに対して、フロントバッグは、より即自的なコミュニケーションの場をクラブ員に提供するということであったわけである。しかし、われわれは、『峠』11号を編集するに当たって、単に事務的に文章を羅列することは避けたつもりである。そして、われわれは極力、クラブ員から提出された原文を改変することのないように務めた。これが、言わばこの雑誌の、唯一の編集方針である。
2年間のブランクをのり越えて、今回出ることになった『峠』11号は、必然的に、3年間に渡る、わがクラブのクラブ意識というものの変遷をとどめていると思う。それをクラブ員諸氏がどのように受け止めるのか、最早われわれの関知する問題ではない。それは、なによりもまず、君たち自身の問題なのである。この雑誌が、そのことを考えるに当たって、いくらかの示唆ともなってくれれば、編集に従事した者として、いくらかの満足(もちろん自己満足だが)とはなる。
最後に、労力を惜しまず、原稿を書いてくれた諸氏に、せん越ながら、感謝の意を表します。また、広告を提供して下さった山王、神金、沢田屋、オギワラの各社に御礼を言うとともに、われわれの陰となり日向となり、この雑誌をバックアップしてくれた各氏の労をここにねぎらいたいと思います。(正路)
峠 第11号
1976年6月11日発行
編集人 正路 小林
発行所 WCC出版局
Copyright © 2025, WCCOB会