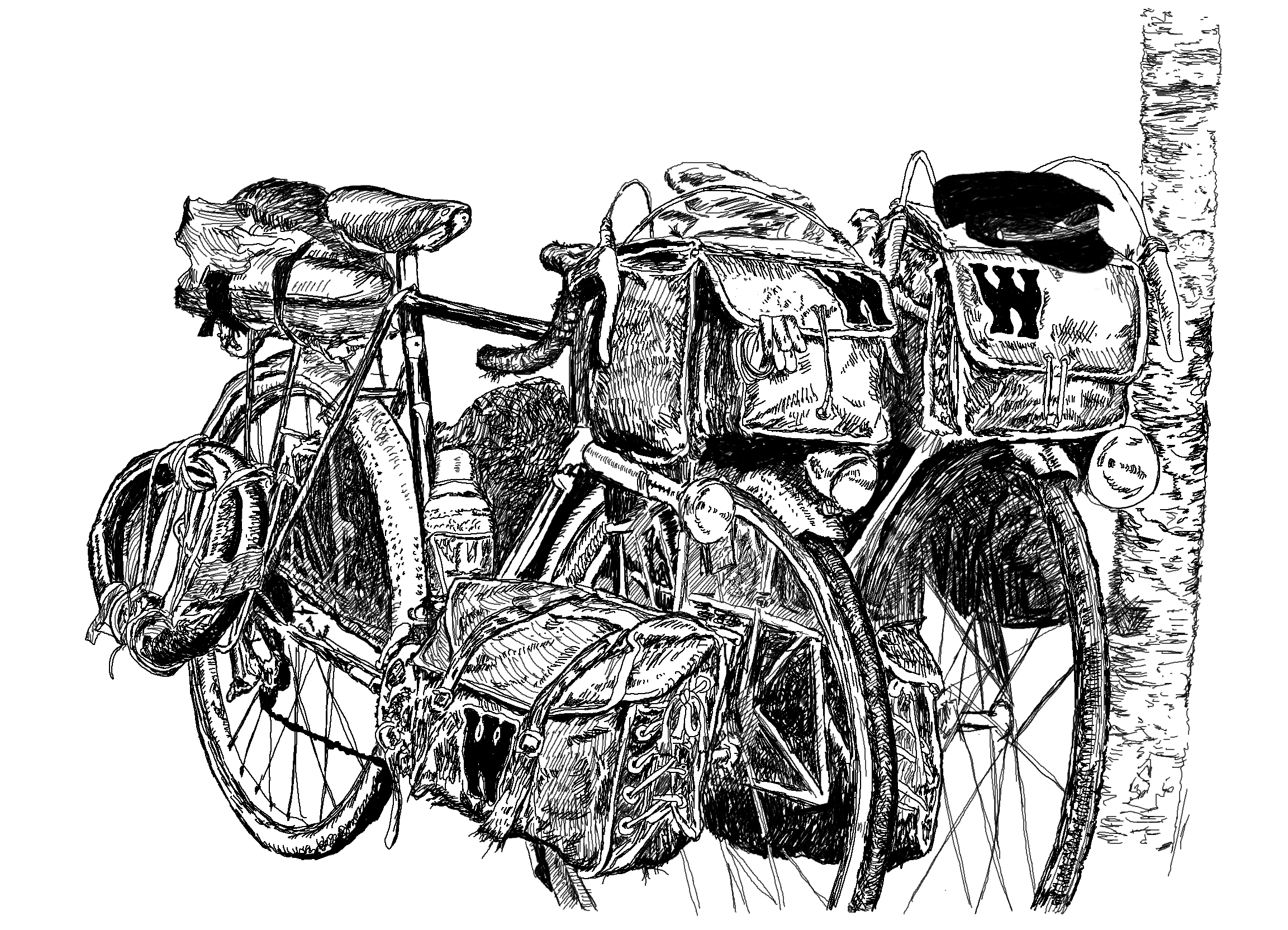この文章は、21期永井氏により寄贈された物です。文集「峠」としての出版には至りませんでしたが、きちんとした原稿が集まっていたことがわかります。1983年の夏合宿は「飛騨地方」でした。
「1983年中部夏合宿A班日誌」23期荒川
■「1983年中部夏合宿A班日誌」23期荒川
(1986年執筆)
もう3年前のできごとになってしまった夏合宿。そんなに時間がたっていることが不思議なくらい強い印象が残っている。
ボロボロになった飛騨合宿のパンフを、この文を書くために本棚の奥から引き出し、ページをめくってみると、1つ発見した。なんとA班の記録係は私じゃなくて後藤(23期)ではないか。しかし彼がモロッコへ旅立ってしまった今、私がこの記録を書くほかなさそうである。
大学に入ってからサイクリングを始めた私にとって、飛騨合宿は最初の長期ランであり、私のサイクリング観を決定づけるようなものとなった。
<7月31日>
初日である。全部舗装のコースであったが初心者である私は登り坂でギヤチェンジできず、何度も足をついていた。揖斐川沿いに上って横山ダムに近いキャンプ場泊。今日は足慣らしである、というようなことを聞いていたので、前途が多難であることを感じた。
<8月1日>
天気が悪かった。雨の中、地道の冠山をフリーランで越えた。とてもつらくて合宿から逃げ出したくなってしまった。しかし、先輩たちは峠でびしょ濡れになりながら元気に騒いでいるので感心した。
この冠山の峠を下る途中に事件が起こった。俗にいう「村井のガケ落ち」である。
私の所属していた3班は、阿部さん、私、村井、永井さん、川島さんの順で(中本さんがどこに入っていたか忘れてしまった)、濃霧の中を下っていた。
カーブがじゃりで滑るのであぶないなあ、と思いつつ下っていると、突然「ストーップ!」という永井さんの絶叫が聞こえた。何だろうと思って戻ってみると村井がボーっと立っていた。そして震えながら「ガケから落ちた」ということを話してくれた。はるかガケの下では川島さんと永井さんが村井の自転車を引っ張り上げていた。あんな下まで落ちたら、と思うと私は全身がひきつるような恐怖を感じた。
「村井君が死なずにすんでよかったです」というのが、その日の私の一人一言だったが、本当に死んでもおかしくないような事故だったのである。村井はこの時の怪我でしばらくの間、戦線離脱。村井が食当だったので、以後1人食当になってしまった。植木の苦労が始まる。この日のキャンプ場ではWCCのOBである地元の方にたいへんお世話になった。
<8月2日>
B,C班と別れて走り出す。急に人数が少なくなり気楽になる。舗装の峠を1つ越えて越前大野の町へ入る。この町での買いだしで豆腐を買ってしまったため、大きな発砲スチロールの箱に詰めて川島さんがキャリアに積んで運んだ。まるで豆腐屋のようだった。キャンプ場は山の上にあり、そこまでとてもきつい登りだったが早く到着したので洗濯をすることができた。
<8月3日>
キャンプ場を下ってから九頭竜川沿いに走る。九頭竜湖へは向かわず桧峠への道を通る。この峠までの登りで男同志のペアランが行われた。私は門田さんと組んで峠へ上った。キャンプ場は蛭ガ野高原にあった。ここは日本海と太平洋の分水嶺になっている場所である。林間学校がキャンプしているような広いキャンプ場だった。
<8月4日>
1年生の私がCLを初めて任された。阿部さんが教えてくれたCLの走り方について気をつけながら走った。CLは風を受けるので疲れるということがよくわかった。
合掌造りの家、御母衣ダムなど見ながら走り、国道を途中で折れて地道を上りきるとキャンプ場であった。この日も早く着いた。近くに白水の滝という大きな滝があり、それを背景にして班写真を撮ったが、そのときに近藤さんが高所恐怖症であることが判明した。
また、温泉もあるということなので明るいうちに温泉宿を確認しに行った。宿はキャンプ場からガケを下ったところにあった。夜、食事が終わってから風呂のため真っ暗な中、ガケを下るのは非常にスリルがあった。
<8月5日>
この日は白川郷から天生峠を超える予定だったが、道路工事のためなんと通行禁止であった。しかたなく迂回して天生峠の北にある牛首峠を越えることになった。牛首峠への登りは急勾配の地道でとてもつらかった。私の前を走る中本さんは、その日、手を負傷していたため坂道でハンドルを引き上げることができず、見ていて気の毒であった。
その中本さんが峠の下りでは「飛んで」しまった。つづら折りの道の1段下まで飛び落ちてしまったのだ。中本さんがこの合宿で(ウルトラ)セブンと呼ばれるようになった理由の1つとなった。
牛首越えで苦戦したため買い出し地点の飛騨古川ですでに日が暮れ、四十八滝のキャンプ場では暗い中での炊事、食事となった。メニューは酢豚であった。この暗い中での夕食が、翌日私と守田さんに悲惨な結果をもたらすことになる。
<8月6日>
あまりに腹が痛いので起床時間前に起きてトイレに走った。
せっかくの高山での休息日だというのに、私は守田さんとともに食中毒にかかってしまったのだ。
守田さんは高山駅でゲロを吐いて倒れ、私はこの炎天下だというのに寒くて震えがとまらない。タクシーで病院へ連れていってもらい、点滴を打った。
熱は39度以上、食中毒と診断された。松広さんが医者に、自転車に乗っても大丈夫かどうかたずねると、平気である、というような返事。私はもうこれで完璧に家へ帰れると思っていたので、
その医者の言葉が信じられなかった。
しかし、松広さんが一生懸命、私がリタイヤしないように頑張ってくれたおかげで、今こうしてWCCの合宿について語ることができるわけで、もしこの高山での食中毒でリタイヤしていたら
以後のクラブランでも私はずっと同じような弱気な行動を取り続けることになってしまっただろう。無理にでも私をつれていこうとしてくれた松広さんには今、本当に感謝しています。
松広さんたちは私と守田さんの診断が終わると、すでにキャンプ場へ向かっていた班員たちを追いかけて出発した。高山に残ったのは班員の川島さん、守田さん、私の3人で、晩は高山駅前にマットを敷いて寝た。数時間前に病院で点滴を受けていた人間がなんでこんなところで寝なきゃならんのだ、と思った。この日、後藤がA班に合流したが、キャンプ場までの登りで、慣れていないせいか、いきなり死んだそうだ。
<8月7日>
守田さんと私は班と別行動だったので班員の人たちがどのように動いていたかわからないが、川島さんは高山の朝市を見物し、私と守田さんはバスで輪行して、キャンプ場の上高地へと向かった。
途中、平湯温泉で武田さん、石井に会う。石井も昨晩、食中毒の症状が出たため、班と別れて上高地の診療所に行くということであった。上高地診療所はいいかげんなところで、石井に飲み薬を与えただけで済ましてしまった。
上高地は有名な観光地だけあってキャンプ場は盛況、マキの自動販売機まであった。また、キャンプ場から見えた大きな穂高岳の姿は強く印象に残っている。
<8月8日>
合流日である。上高地からの下りで、幽霊の噂のある釜トンネルという急勾配の狭いトンネルを通った。このトンネルの前で信号待ちしている時、私の前にいた後藤が突然、自転車にまたがったままドタッと横倒しにぶったおれたので、幽霊のたたりにあったのかと思った。岡本さんがここで顔にケガをした。
梓川沿いにトンネルの多い道を通り、白樺峠へと向かう。この上りで永井さんの自転車のギアが折れてしまった。白樺峠から乗鞍岳の偉容が見渡せた。いわれてみれば馬の鞍のようにも見える。明日、あの山の上までいくのかと考えると不思議な気がした。
乗鞍高原のキャンプ場でB、C班の仲間たちに再会する。炊事の時間はみな自分たちの班の様子を他班の連中に話したくてしょうがない、といった雰囲気の会話で盛り上がっていた。上田さん、近藤さんたちは尻を出して写真を撮り合っている。3班合同でのメシつぎ競争でA班は惨敗。晩には雨が降り、年次会ミーティングが開かれた。
<8月9日>
乗鞍大フリーラン大会のその日、朝のランニングはやけに長かった。15km1200mアップのフリーランはさすがにきつかったが、自分としては満足できる結果であった。しかし名和さんの速さはすごい。まるでオートバイのようだった。
山の上の人と車の多さには驚いたが、そこに自転車を置いてみんなで乗鞍の最高峰、剣が峰へ登った。(浜梶さんのように自転車を頂上まで持っていった人もいたが)。
3026mの山頂で全体写真・校歌。WCCだなあ、と強く感じる。雲がかかり山頂からの眺めは良くなかったが、山腹でスキーをやっている人たちがいるのを見ると高い山へ来たのだとと実感できた。前日と同じキャンプ場泊。
<8月10日>
再び3班は別れる。A班は奈川村を通り境峠から木曽へ入った。境峠は楽勝の峠だったが、後藤は前日の疲れからかCLで先頭を走りながらバテバテになっていた。
木曽福島の町で買い出し。特殊機材(エロ本)を購入している先輩がいたような気がする。近藤さんの体の具合が悪いらしい。この日あたりから合宿の疲労がみんなの体に現れ始めたようだ。木曽駒高原キャンプ場はスノコの上にテントを張る方式で、そのスノコが傾いていたため、寝る時松広さんがのしかかって重かった。
キャンプ場の近くに温泉があり、夕食後みんなで入浴した。湯が赤錆色をしていた。先輩たちも疲労してきたのか、一人一言では活気のない1年会をしかる人が多かった。
<8月11日>
御岳の田ノ原までフリーランで上る予定だったが天候が悪いためフリーランのコースを翌日にまわすことにする。御岳中腹のキャンプ場までの上りは、御岳が山岳信仰を集める山であるため、
道端にのぼりが立っていたりして独特のムードであった。
いつ合流されたか忘れてしまったが、この日、宇野さんがいたことは確かである。
<8月12日>
朝、キャンプ場からの出発が遅れ、ボスの松広さんが、ダラダラしている班員たちにみかねたのか、みんなを激しくしかった。私には松広さんの言っている博多弁がよくわからなかったが、
しっかりしなくては、という気持ちにさせるような熱意が強く感じられた。そのためか御岳でのフリーランも気合が入った。
フリーラン後、上ってきた道を王滝まで下ったが、下る途中で会ったサイクリストが、
「早稲田のサイクリングクラブの人が王滝のバス停にいましたよ」
といってくれたので私は反町が合流しに来たのだと思った。
王滝のバス停にそれらしい人物は見当たらず、森林鉄道の線路跡を通って3浦貯水池へ向かった。松広さんが三浦ダムのエレベーターに乗ってダムの上まで行ってしまうというようなこともあった。
三浦貯水池はひとけがなく、水面に流木が浮いていたりする神秘的な湖であった。私にとってこの合宿中、1番印象に残った場所だった。
そこから地道を上ると鞍掛峠である。辻さんたちの班はこの上りで道を間違えて標高を少しかせいだ。峠からの下りはゴリゴリの地道で、私がパンクして迷惑をかけてしまった。
宿泊地はキャンプ場ではなく、旅館の庭であった。そこへ村井が突然登場した。王滝のバス停にいたのは村井だったのだ。村井の復帰で活気づいたA班であった。テントを張っている最中に夕立にあい、テントは内も外もびちょびちょになってしまい、しかたなく、その晩は旅館の廊下で寝ることになった。
炊事もなしで、夕食は1人パン1斤(キャベツ・魚の缶詰付)と下呂牛乳だった。夕食後、食当疲れでノイローゼぎみの植木が石川とケンカした。
<8月13日>
下呂の町から線路沿いに飛騨萩原へ。そこから日和田峠を越え下ったところにある馬瀬村役場で休憩する。役場はとても立派な建物だった。
金山湖から合宿最後の峠、小川峠へ向かった。ワセダファイトの掛け声で上り切り、もうこれで上り坂がないのだと思うとホっとした。峠で、インフレーターを発射台としてロケット花火が何発も打ち上げられた。峠を下って郡上八幡の町に着くとB、C班の仲間と再会できた。この町で後藤は、当たればもう1本もらえるジュースを2本連続して当てていた。
キャンプ場は、合宿パンフには「河原キャンプ場」と書いてあったので河原という地名の場所にあるキャンプ場かと思っていたら、なんと長良川の河原を勝手に使うだけのものだった。
河原の石でかまどを作り、1年生だけで炊事を行う。水は、川の水が衛生的でないので近所のガソリンスタンドでもらった。夕食後、有名な郡上八幡の徹夜踊りに参加した。にぎやかな盆踊りで、明日はゴールだと思うと自然と陽気になってくる。2曲ほど踊り方をマスターしたころに就寝時間のためテントに戻った。
<8月14日>
河原キャンプ場を出て、全クラブ員は長良川沿いに岐阜の町をめざして走る。
今晩宿泊する予定の超豪華岐阜ワシントンホテルの前を通り無事岐阜駅へ。2週間前にこの同じ場所から出発した時と全く違った気持ちでWCCを考えられるようになった自分を発見する。紺碧の空、校歌。夏合宿最高の瞬間であった。
晩の柳ケ瀬での打ち上げコンパ後、ある1年生は朝まで道端で倒れていたそうで、豪華なホテルに宿泊できなかったことをくやしがっていた。
おわり
「1983年中部夏合宿C班日誌」23期村田
■「1983年中部夏合宿C班日誌」23期村田
(1986年執筆)
<7月30日(集合前日)>
前日から名和氏の実家にお世話になる。
昼間は、プライベートを共にした1年生と世良川で水遊びをする。川の水に浸りながら、明日から始まる夏合宿のことを考える。やはり不安を真っ先に感じる。
夜、名和氏に集合した大勢の3年生と一緒に夕食をごちそうになる。「とても夏合宿前夜とは思えん」と3年某氏がいうように和やかな雰囲気である。ただ、長良川の花火大会は雨のため中止となり、見られず残念。さて明日からどのようなドラマが展開されようとしているのだろうか。
<7月31日>
(岐阜→北方→揖斐川町→横山ダム)57km200m
名和宅から集合地の岐阜駅に向かう。そこにはなつかしい顔が勢揃いしている。プライベートで真っ黒に日焼けした者、(ただし永岡氏の手足火脹れはやり過ぎである)、
真っ白な顔をしている者、サーファーパンツをはいた者、わけのわからない傘をもった者。(彼らはお代官様に直訴でもするつもりか)。
午前10時、メモ帳を脇にかかえた鳥渕副将の「集合」という声で83年夏合宿は始まった。午前11時出発、岐阜の市街地をぬけ、郊外の大型スーパーで昼食をとるため休憩する。ここで買った食べ物をそのまま店内で食べる。
純心無垢な私は、まわりの視線が気になり恥ずかしさを感じたが、「みんなでやれば恐くない」というわけでこの恥ずかしさが快感に変わる。これで1人前のWCC部員?
濃尾平野を離れて山間部に近づくと胸が高鳴る。川沿いの道をだらだらと登り、キャンプ場に到着する。ここで私はある事件を目撃する。それは、植田氏の額にペグが刺さり、そこから血を流していたが、それを目の前で見ていたK氏は何の手当てもせずに黙って立ち去ってしまったという事件であった。
夕食の時に雷が鳴り雨が降り出す。悲惨な夏合宿の初日らしい天気である。
<8月1日>
(徳山村→冠山→志津原)48km800m
予定していたコースが通行不能となり、A、B班と一緒に走る。この合宿初のフリーランを冠山で行う。相変わらず純心無垢な私は、「全舗装」というデマにだまされる。すぐに地道が始まる。しかも路面はボコボコで、豪雨(私にはそう思えた)のため、道は川と化している。
マットガードに泥が詰まり、四苦八苦する。
やっと峠に着いて昼食にありつこうとしても雨ざらしの中コッフェルを開けると、あっという間にお茶漬けに変わってしまう。
この下りで村井がガケから落ちる。残念ながらこのとき負った傷のため、リタイヤすることになる。
一人一言で名和氏が、途中寄った徳山村は近年ダム建設のため水没するという話を聞き、感慨深くなる。
<8月2日>
(寺島→大野→九頭竜湖→油坂峠→ひるがの高原)
114km1000m
この日、A、B班と別れる。前日のコース変更のため、かなり長い距離を走らなくてはならない。
途中の味見駐在所の前で徳味さんが記念写真を撮る。
九頭竜湖のまわりの景気は針葉樹林が一面に広がっており、まるで北欧の湖と森を見るようである。油坂峠で、福井県から再び岐阜県に入る。誰からともなく「また岐阜か」という声が出る。以後C班は岐阜県と他県を行ったり来たりするコースをとることになる。キャンプ場到着時間は5:30であった。
<8月3日>
(御母衣湖→上洞→白水湖)34km600m
本日は楽勝日。御母衣ダムの展示館に寄り、ダムの構造を勉強する。こういうアカデミックなことはWCC夏合宿によく似合う?
白水湖までの10km400mの登りは班別フリーである。途中、川で水遊びをしようとするが、流れが速く、しかも水が冷たいのであきらめて、日光浴を楽しむ。
さて、1休みして本格的に班別フリーが始まる。この日はタイムテーブルに余裕があるため1年生にCLが任されている。しかもこの時はわたしがCLを担当したのだが、なにぶん初めての経験のためペースがわからず班員に迷惑をかける。他班ではCLが班員をぶっちぎり2年生が死んだそうだ。
途中見上げると、万年雪をいただいた白山をのぞむことができた。
キャンプ場には3時半には到着する。近くの山小屋に風呂があったので汗にまみれた体を洗うことができた。ボスの鳥渕氏は自分で決めた集合時間に間に合うため、風呂に入ったあと、急坂の登山道を自転車を担いで登り、たっぷりと汗をかいたそうだ。
<8月4日>
(白川村→牛首峠→松ケ平)59km960m
前日登ったコースをピストンして下る。路面は簡易舗装されているが、カーブには砂が浮いている。みんなで誰かが転倒するぞと言い合っていたが、やはり約2名の犠牲者を出した。
白川村の合掌集落はタイムテーブルに余裕がなく満足に見られなかった。そのわけは、のちに50000図でも実線のゴリゴリ地道、牛首峠が待っているからである。フリーラン地点に向かう途中の登りで蒲本氏がパンクする。氏のパワーがタイヤの空気圧に勝ったのである。
フリーランの最中、私は大失敗を犯す。コースの途中に分岐があるため、全体CLが道標として置いたイエロージャージを私は落とし物だと勘違いして拾っていってしまったのだ。このため数名の上級生が道を間違えて行方不明となる。
2発目の峠の下りは、途中からガンガンに飛ばせる舗装路であった。途中、地図にないダムがあり、ここで三橋が「ダムのため道がない」と言い、企画の高橋Jr氏を慌てさせる。
ここでやっと長い一日が終わるかと思うと、キャンプ場は小高い丘の上にある。到着時間は5時30分であった。
<8月5日>
(谷折峠→八尾町→岩峅寺→立川)70km1150m
本日は休息日のはずが、企画の判断で称名の滝を見ることになり、起床は4:30になる。八尾→立川間は、この合宿で初めてフラットな田園地帯を走る。ここで中野は前走者に接触し、水田に飛び込む。この事件を契機として9班はメカトラを続出させるのである。
キャンプ場に12時30分に到着。ここでサイドバックをはずし、称名の滝までの4km400mをフリーランで登る。ボスの
「A班は安房峠、B班はブナオ峠、我々も今日はプレ乗鞍だ」
という言葉に緊張する。(1部の者はムッとする)。
夕食の準備が1段落した頃、西の空が東京では見られない美しい茜色に染まっていた。
<8月6日>
(有峰湖→大多和峠→船津→流葉)65km1400m
この頃になると、朝の炊事の仕事が軌道に乗り、いつもより30分近く早い7時30分に出発する。
今日は大きなピークをもたないが、いくつものアップダウンを超える容易じゃないコースである。
有峰湖から立山をのぞむことができずに残念。
この日も9班はメカトラが続出し、浜梶氏は「9班には休憩時間はいらない」、と捨て台詞を吐く。
キャンプ場には私たちの他に小学生の団体がいた。夜、彼らが踊るフォークダンスを私たちはジュースを飲みながらぼんやりと眺めていた。
<8月7日>
(神岡→栃尾→新穂高温泉)42km720m
本日は峠なしの休息日である。この日も朝の炊事が順調にすすみ7時30分にキャンプ場を出発する。
我が班のCL三橋は前日あたりから腹をこわし絶不調。このころ疲れのピークを迎えた者もいて、他に数名が体をこわしている。
途中、穂高連峰が突然目の前に現れて大いに感動する。
キャンプ場には12時に到着。そして町営浴場の浴槽で多勢の登山者と一緒にいもを洗うように体を洗う。一緒に入った山屋さんたちと比べても、いかに自分たちが汚いかがわかる。
夕食後、もう1度旅館の風呂に入る。その後ロビーでジュースを飲みながらテレビを見て、久しぶりに寛いだ雰囲気を味わうことができた。
<8月8日>
(平湯→安房峠→乗鞍スーパー林道)50km1670m
朝から快晴。というわけで企画の英断から出発を遅らせてロープウェイで西穂高口へ登ることになる。ロープウェイの終点の標高は2156m。穂高連峰の山々が目の前に迫ってくる。
目を転じてみると、焼岳の奥に乗鞍岳がはっきりと見える。高いお金を出してロープウェイで登ってきた場所よりも1000m近く高いところに自分が明日自分の足だけを頼りにして行くことが信じられない。それほど乗鞍岳は大きく高い山に思えた。
それからが大変。出発はいつもより2時間遅れの9時30分。やっと休憩地点に到着してもすぐに「8班出発準備」という無念の声。昼食も30分で済ませ、とにかく全員がタイムテーブルを縮めることに必死である。
安房峠ではA班の残した「C班ファイト」の書き置きを見て感激する。キャンプ場ではなつかしい顔が待ち構えていた。「いざ乗鞍へ」という高ぶる気持ちを抑えて、おやすみなさい。
<8月9日>
「起床!!」という声がかかる。疲労した体を起こしてテントを出る。いつもとは違う緊迫した雰囲気に満ちている。それにしても、武田の野郎、トレーニングであんなに長い距離を走らせやがって。
いよいよフリーラン開始。全長15km、標高差1200mを一気に登る。
全体CL、1年、2年、3年の順でスタート。1年が出発する際の上級生の声援はものすごく、いやがうえに気分が高まる。
ペダルを踏み続ければいつかは終わる。長い15kmの道のりを終えればそこは標高2700m。山頂までもうすぐなのだが、登山道を登る足は疲労のため重い。
山頂では校歌、紺碧をみんなで歌う。気分は最高。しかし、まだ今日という日は終わらない。夕食の買い出しのため、キャンプ場からスーパーまで200m以上下る。帰り(登り)はどしゃ降り。ああ無情。
<8月10日>
(白樺峠→奈川村→月夜沢峠→開田村)59km1050m
毎年恒例のことだが、合流日の朝は大混乱、出発は8時50分となる。
白樺峠で最後の穂高を拝む。この日もメインイベントは月夜沢峠。地道でしかもわだちが深くゴリゴリ。大フリーランが終わってもまだまだ夏合宿は終わらないのである。
フリーランのスタート地点は野麦峠との分岐点。ここでS氏が月夜沢峠へ向かわず、ものすごい勢いで野麦峠へかっ飛んでいった。はじめはギヤチェンジのためかと思われたが、単に氏は道を間違えたのである。氏のみこの日は3発の峠を越えたのである。
この日午前中は青空がのぞいていたが、月夜沢峠に大半の者が到着したころから突然雨が降り出した。全員そろうまで出発するわけにはいかず、しかし峠には雨宿りができる場所はなく、みんなは雨ガッパを着て(約1名傘をさして)ただ茫然と立ち尽くしていた。その雨も夜までにはあがり、美しい星空を満喫することができた。
<8月11日>
(長峰峠→濁河温泉)30km830m
本日はタイムテーブルに余裕があるため、CLは1年生。8班のCL、Mが班員に声をかける。「8班コッフェル準備!」一同大爆笑。
この日は「タイムレース」という初めての試みが行われた。
優勝は筒井氏、ゴール前でみんなの顔色をうかがいながら巧みにゴールするタイミングを読んだ。2位は鍵本氏、ゴール前で故意に?こけたことが勝利につながったのだろう。3位は沢田氏。氏はまさに人間サイクルコンピューターである。なお、1位の筒井氏には後日エロ雑誌とフリーランの全体CLという賞品が贈られた。
キャンプ場には2時前に到着したのだが、それから大変なことが起きる。キャンプ場まで自転車が入れず、しかも水が出ない。親切そうなおじさんが場所を提供してくれたのだが荷物を降ろした後で、追い出されてしまった。
結局、お寺の敷地を、合流したB班とともに借りることになる。一人一言で氏本は「責任はテントより重い」と発言する。またこの日、鳥渕氏がコッフェルを川に流したことも付け加えておく。
<8月12日>
(岳見岳→美女峠→高山市)48km250m
水の便が悪く、出発が8時30分に遅れる。軽く峠を2発越えて高山市に12時に到着する。私は1年生数名と一緒に昔の町並みを訪ねたり、みたらしだんごを食べたりして大いに楽しむ。
特によかったことは最後に訪ねた飛騨民族村で見たミニスカートである。これが並みの短さではないのだ。街の喫茶店で先輩方がくつろいでいると外を同じショートパンツをはいた、恋人気分の2人が通り過ぎた。なんとそれは蒲本氏と氏本であった。ペアルックで歩く2人の姿は高山の街にとてもマッチしていた。
この日はC班最後の夜である。眼下に高山の街の灯が見える。久しぶりに見る街の灯である。
<8月13日>
(一ノ宮→坂本峠→郡上八幡)75km880m
7時十分キャンプ場を出発。高山市に戻り朝市に寄る。そして夏合宿最後のフリーランを行う。峠の上から見える景色は今までの高く険しい山並みではなく、低くなだらかに連なった山々である。
このことからでも私はゴールに近づきつつあることを感じる。3時20分郡上八幡に到着する。なんと、キャンプ場は何にもない河原。水はガソリンスタンドの水道がただ1本あるだけである。食当を任された1年生は大混乱する。
<8月14日>
(美濃市→岐阜市)55km
長良川沿いの国道56号線を下れば、そこは岐阜の街。駅前で歌う校歌、紺碧は最高、WCC夏合宿バンザイ。
(あとがき)
今回の夏合宿は、ガケから転落する者、風邪をひく者、食中毒など、リタイヤする者が目立ったが、わがC班では最初から最後まで18名のメンバーは変わらなかった。このことがC班最大の勲章だと思う。
おわり
「とりVの説教じみたぼやき」21期鳥渕
■「とりVの説教じみたぼやき」21期鳥渕
(1985年執筆)
WCC?
初めて聞いた時、WCにションベンのCでも余分にくっついているんだろうか、と思った。そのサークルに俺は4年間どっぷり染まり、そして卒業した。”我が大学生活に悔いなし”、俺は胸を張って言いたい。
授業にはろくすっぽ出ず、きたない部室でたむろし、土・日になればあまり整備もしていない、うす汚れたちゃりんこを、うす汚れた輪行袋に押し込んで峠を目指し、生活費のほとんどがメシ代と酒代、4畳半1間にこつこつ買い集めた電化製品とほこりにうもれて過ごした4年間。(この下宿にいったい何人の人間が入り、何人の人間が泊まっていっただろうか・・・)。
短小軽薄が喜ばれ、外見だけで中味のない人間が大量生産されている現代に、まわりからは冷やかな目で見られながらも反抗しつづけた4年間。
なんでも器用にやってしまうものだから、何1つ本当の喜びを体験できずにいる今の学生と違って、不器用だからこそ、サイクリングという時代の流れに逆行するようなものたった1つにのめり込み、多くの友を得、多くの感動を得ることができた4年間。
社会人となった俺のおおきな自信であり、心の支えでもある。WCCからは本当に多くのことを学ぶことができたと思う。
フリーランで自分の持てる力の全部を出し切ったあとのあの満足感。文字どおり同じ釜の飯を食い、苦楽を共にする夏合宿でのあの喜び。まったく異なる価値観を持った人間がサイクリング観やクラブ観、そして人生観をさかなに酒を飲み、そして激論を闘わせるあの楽しさ。
旅の先々で地元の人が何気なくしてくれた親切、そこから芽生えた思いやりの心、そして、1年生、2年生と先輩の大きな恩に育てられた自分達が、3年生となり、執行部を取り、クラブを実際に運営し、そして夏合宿を成し遂げた時の喜びと自信。
個人主義がはびこり、人間関係がますます疎遠になっていきている日本社会のなかでオアシスとも言えるWCCを、後輩へ後輩へと至急に伝承していってほしい。
3年生が1年生を育て、2年生がそれを吟味して次に生かす。この繰り返しの中で、WCCもまた成長していくのだと思う。
この伝統重視のクラブ方針にたいして、独自のサイクリング観を確立している者からは、閉鎖的であるとか、封建的であるとかいった批判などもよく聞かれる。確かにそんなところもあるが、ただもう頭ごなしに反発するのではなく、
「先輩たちはなぜこんなふうにやってきたのだろうか」
「伝統的なものにはそれなりに良い面があるから今までつづいてきたのであり、それはどんなところなんだろうか」
なんてところまで突っ込んで考えてみてほしい。
そうすればクラブが新しい時代に対応して変化を遂げていったとしても、伝統的なWCC精神、WCC魂だけは引き継がれていくのであろうから・・。
ちょっと堅苦しい話になってしまった。どうも俺は肩のこる話しかできない損な性格らしい。
でもこんな人間も1人くらいいいるほうが、バカばっかりやってる集団の中で少しでもまとまりがつくんじゃないかと思って4年間がんばったわけだ。
WCCという大きな器の中で、どうすれば自分を1番いかせるか。どうすれば1番目立てるか。どこに活躍の場を見出せるか。1人1人がうまくそれを為し得た時に最高の執行部そして最高のクラブができてくるのだと思う。
後輩諸君、せっかくWCCとめぐり会えたのだからこの中で大いに暴れまわってほしい。そして、都の西北と紺碧の空を声高らかに歌えるこのクラブで何か1つ光って見えるものを見つけ、それを自信としてほしい。
最後に我が下宿に来たことのある者なら1度は目にしたであろう、俺の座右の銘ならぬ、冷蔵庫の上の黒板の銘を諸君に送る。
「人に甘えるな、自分に負けるな、そして翔べ」
おしまい。
「今しかできないことを徹底的に」21期辻
■「今しかできないことを徹底的に」21期辻
(1985年執筆)
私は、このWCCに入り自転車を初めてから、ある考え方をもつようになった。それは、「今しかできないことを徹底的にやれ」ということである。
こう考え始めたのは、いつ頃からであったろうか。
あまりはっきりはしないが、1年の夏合宿(’81年)頃からこの考え方は芽生えてきたようだ。
それ以前私は、フリーランのたびに、私の横を瞬時に通り過ぎるバイクを見ては
「どうして俺はこんなに苦労して峠を登っているのだろう」
という疑問を抱いていた。
ところが、夏合宿も終わりに近づくと次のように変わった。
「彼らはどうしてバイクで峠を登るのだろう。もったいないな。」
つまり、
「バイクはオジンになっても乗れる。しかし、自転車で峠を登れるときは今しかない。」
と考え始めていたのである。
ここに、「今しかできないことを徹底的にやれ」という考え方の
芽生えがみられたのである。
この考え方はうちのクラブに強く根づいているようである。
地道を好んで走ること、合宿中に黄緑色に変色したジャージを着て誇らしげに街中を闊歩すること等にもよく現れている。
私はこの考えはうちのクラブに影響されたものであろう。夏合宿でこう考えはじめて以来、私は、春合宿・夏合宿の前後には必ず1ヶ月近くは走ることにした。
ノルマを一日100キロ以上と決め、原則としてY・H等には泊まらず駅・テントで済ませ、自分のヒゲ面・きたなさを誇りに思った。
そして、学生時代にしかできないこういう旅(少なくとも家庭をもってからはできない)をしたおかげで多くのことを得ることができた。
とくに、旅先の土地の人々の親切は本当にうれしかった。駅長さん1人しかいない田舎の駅に宿を求めたら朝コーヒーを入れてくれ、おまけにボトルに熱いお茶まで入れてくれたこと。
稚内で、他のサイクリスト2人と堀さんというおじいさんの家でお世話になったこと。
裏磐梯小学校の教員宿舎に泊めてくれた英語教師の森合さんなど数え上げたらきりがない。
そして現在も私は、
「今しかできないことを徹底的に」の精神をもっているつもりである。
そして社会に出ても、多くの制約はあるだろうが、できるだけこの精神を生かし、常に向上心をもっていたい。
以上
「鉄路or道路?」21期永岡
■「鉄路or道路?」21期永岡
(1985年執筆)
田舎が九州という遥か彼方にあるのにも拘わらず、飛行機で帰省したことがない。いや、したくない方が正解かな。将来、旅行社に勤めたいと思っているのに、飛行機に乗りたくない。たとえ生き残ってもマスコミの取材を受け、フライデーか何かに載るのが落ちだ。
その点、鉄道はよろしい。足が地に着いているぶんだけ安心できる。しかし、居眠り運転のトラックが雲悪く踏切りに突っ込んで来て、たまたま自分のいる座席にぶち当たることも考えられるが。万に1つの確立、即ち、隕石がてめえの頭に当たるぐらいのものだ。
また、その昔、カサンドラクロスという映画があったが、鉄橋が落ちることもあるまい。仮に「あさかぜ4号」が伝染病に侵されたとしても、日本政府が自衛隊員を乗せて、余部鉄橋(日本1の高さ、山陰線)まで持っていって、ダイナマイトで橋を爆破するわけもない。そこまで考えると、おちおち夜も寝られないので、話を先にすすませていただくことにしよう。
大学2年のときのことである。合宿終了後、ESCAラリーに出るべく、広島から大阪まで国道2号をひたすら東進した。国道2号と山陽線・山陽新幹線は、地図上では組んずほぐれつしながら東西を結んでいる。特に、尾道、相生、明石近辺では、まさに隣あわせになっている。
根っからの列車好きで、目を悪くしたのも時刻表の見過ぎという経歴の持ち主なので、いまだ通学途中の西武線の中でも車体番号やスピードメーターに目を配るほどだ。幼稚と言えばそれまでだが、常人にはわからんでしょうな。
話が脱線してしまった。ちなみに国鉄の隠語では「ゲタを脱ぐ」と言う。修学旅行専用電車のことは「ジャリ電」、ブルトレは「青大将」、キセル乗車を「薩摩守(その昔、薩摩守忠度(ただのりと読む。ただ乗りとシャレたわけ))、鉄道自殺の轢死体のことを「マグロ」と言う。
話がゲタを脱いでしまった。話にゲタを履かせよう。(復旧させること)。
博多まで帰るのに、広島あたりまで鈍行を乗り継ぐことがある。(単に金がないので、新幹線や寝台に乗れないだけなのだが)
昼間を列車の中で過ごせる。朝のラッシュ、朝日を浴びながらの通勤、通学の人々。特にセーラー服の女子高生はよろしい。お買い物のオバサン達。前に座ったおっさんの寝顔。
ふと窓の外に目を向ける。あれ、どこかで見た風景だ。そうだ、たしかここは、自転車で走ったところだ。ちょうど今くらいの時刻だった。ここはあの時自転車で・・・。単行本に向かっていた目も窓の外に釘付けだ。
そうそう、ここが峠の入口。何回足着いたっけなあ。昼飯食ったドライブインだ。ビールひっかけながら走ってて、白バイのポリさんに並ばれて「頑張れよ」って声かけられた所だ。ただただ申し訳なかったことだけが思い出される。
しかし、列車じゃ、あまりに早く駆け抜けてしまう。
時速20キロ。ペダルを踏む度に、新しい風景が目に飛び込んできた。「旅」を肌で感じていた。「旅行」じゃないんだ。本物の「旅」を肌で感じていた。本物の「旅」をやっていたんだ。自分の足で・・・。
今そうやって、車窓からの風景を見ていると、数時間で日本中を結ぶ鉄路を見ていると、空しさすら感じてしまう。ただ目的地に早く着けばよい。トンネルを突っ切り、あっと言うまに鉄橋を渡ってしまう。東京~博多、わずか6時間40分。
木洩れ日を見ることなく、鳥のさえずりを、川のせせらぎを聞くことなく、ただ単調なレールの響きだけ。自分の足こそが「旅」を造れるんだ。時刻表をながめつつも、遠く、レールの響きに思いをはせる。しかし、隣を走り抜けていく列車を見送りながらも、こうつぶやくのだ。「くそっ、輪行すりゃよかった!!」
参考までに。
東京~博多、学割9680円。新幹線だとプラス指定7900円。
寝台はプラス9000円。(当時)
ちなみに、私は寝台の方が好きです。新幹線では腰が痛くなるし、食堂車からの富士山の眺めは最高です。しかし、食堂車で朝食を食ってる時、通勤客で一杯のホームに止まった時は、視線のやり場に困ります。あの1分間のとまどいがたまりません。
以上
「ビルマにて」21期松広
■「ビルマにて」21期松広
(1986年執筆)
<その1>
ビルマは、ほんとうに理解に苦しむ国だ。日本のように物質文明が栄えた国から見れば、とくにそうかもしれない。とにかく物がない。50年くらい前から何もつくっていないのでは、と思うくらいである。家も車も机も本も、すべて骨董品のような代物だ。
したがって、ビルマでの1週間の旅は、難民船や復員列車を使ってのそれを想像してくれればいい。ボロ、ほんとうにボロの列車や船に、汚い食器や布切れをいっぱいに詰めた荷物をもち、ほこりまみれの黒い顔をしたビルマ人があふれている。足の踏み場もない混みようだ。その中に、1群の外国人旅行者がほうり込まれる。
ビルマでは、観光客はお客様ではなく、現地の人と同じ扱いを受けることを覚悟しなければならない。(もっとも、これが正常なのだろうが・・・。)
やっとのことでたどり着いた田舎町には、車などほとんどなく、あるのは馬車と自転車タクシーだけ。こんなところが日本の近くにあったなんて信じられない。物質的尺度でいくと、タイなんかまだましなほうだ。
この物のなさは、社会主義体制下の鎖国政策に原因があるのだろうが、一方でヤミ経済が堂々と栄えているのはどうしたことか。「ジョニ赤」、「555」という英国製タバコ、ドルはヤミで公式レートの4倍くらいで交換できる。YMCAの掲示板にはヤミドルの交換場所が書いてあったり、役人自らヤミビジネスをもちかけてきたりもする。
それでも、いちおうは取り締まりというものがあって、不法な露天商を捕まえようと警察らしき人たちがトラックに乗って駆けつけたとき、露天商が品物を載せた風呂敷をパっとたたんで、逃げ出そうとする光景を何度か見かけた。だが、おおかたの取り締まりはザルのようなもので、むしろ統制に比例してヤミやコネが横行しているように思えた。
ビルマ人の男性は、ロンジンという布を腰に巻き付け、スカートのようにはいている。顔つきは素朴そのもので、どことなくサンダーバードの人形に似ている人もいる。
列車に乗ると、駅に着くたびにおびただしい数の物売りを見かける。女の物売りは、タナッカーという化粧の1種を無造作に顔に塗り、果物や飯をのせたザルを頭の上に置き、へんな叫び声をあげている。ちょっと目が合うと、とろけるような眼差しでこちらをみつめてくる。
社会主義経済とヤミ経済、ロンジンとタナッカー。ビルマ人のやっていることは、私には到底理解しがたい不思議なものばかりである。子供のお遊びを大人がまじめにやっている気さえしてくる。
でも、ビルマ人の仏教に対する信仰の深さ、そして、おそらくそのことに起因するのだろうが、
彼らの仏様のように純粋で幸せそうな顔を見ていると、日本でのストレスに満ちた生活があほらしく感じられてくる。物なんかなくても、幸せに生きることはできるのではないか。そんなことを重いながらビルマを旅するうち、私はどことなくビルマが好きになってきた。
<その2>
そのアメリカ人とスイス人とは、ビルマに入って以来、ほとんど行動をともにしている。ビルマは7日間しか滞在が許されない上、交通手段が限られているので、おのずと行動が一緒になってしまう。
アメリカ人は60すぎのカリフォルニアの農夫で、古き良きアメリカの代表選手のようなおっさんだ。スイス人は30歳くらいの庭師で、少々あくの強いところがある。
私が嬉しいのは、この2人が、他に多くの白人旅行者がいるにもかかわらず、
私たち(もう1人日本人と一緒だった)日本人と行動をともにしてくれたことだ。
英語もろくに話せず、どちらかというと内にこもりがちな日本人を、彼らはほんとうによく誘ってくれた。彼らがけっして無理をしているのではないことを私は知っている。彼らはあくまでマイペースなのだ。もちろん、私たちだって同じだ。それでいて、ほとんど行動が一緒になってしまう。全くのくされ縁。これほどいい関係もないのではないのではないか。
日本人を欧米人が理解するのは難しいことだと言う人がいる。実際、スイス人のにいちゃんは、日本に来た時、日本人が「へえ、そうですか」と相づちばかりうつのを見て、わからなくなったと言った。
しかし、日本人が欧米人を理解するのもまた難しいことだと思う。彼らは、ほんとうに思ったことをストレートに言う。スイス人のにいちゃんなんか、あんまり生意気なので、思わずムッときて別れたくなった時もあった。でも、彼らはほんとうにいい奴等なんだ。
ビルマ6日目、タジという駅で夜行列車を待った時、スイス人「オレはもう先に行くぜ。ひとりで行きたいのさ」荷物をもって行こうとする。
アメリカ人「本当にひとりで行ってしまいたいのか」
沈黙
スイス人「冗談さ」
実際、私たち4人は極度に疲れていた。ひとりになりたいのもやまやまだった。しかし、このあとも私たちは一緒に旅をした。
ビルマ7日目、ラングーンに戻ってレストランで夕食をとりながら、
スイス人「アメリカ人のやつ、宿で寝てやがる。きのうの夜行列車でも口あけてぐっすり寝てたぜ。やつは疲れているんだ。オレは明日飛行機に乗れなくなってよかったと思うぜ。だって、やつは少し休んだ方がいいんだ。」
ラングーンに着いて、バンコクへの飛行機のリコンファームをするが、オーバーブッキングでビルマに足止めを食らう。早くて1週間後に出国。ほとんどの外国人がビルマにとどまることを余儀なくされた。
スイス人とアメリカ人、そして日本人が2人。お互い理解しがたい部分を持ちながら、一緒に旅を続けた。そして、なんとなく、お互いのことが好きになっていったのだった。
<その3>
改選で、
「うちのクラブをそこらのおばさんに説明するとしたら、あなたはどう言うか」と質問した。
ある主将候補はこう答えた。
「なんかわけがわからないけど、バカやってるクラブですよ」。
わけのわからないクラブ・・WCC。たしかにうちのクラブには傍目では理解しがたい部分が多い。でも、私はこのクラブが大好きだ。深くつきあえばつきあうほど。
だから、私が今唯一言えることは、多くの人にこのクラブと深くつきあってほしいということだ。
はじめはわけがわからなくても、なにかのきっかけでWCCを知ったのなら、とにかく身をおいてみてほしい。
そうやっていくうちに、理解しがたい部分を残しながらもだんだんと好きになっていくのではなかろうか、このWCCというものが。
そして、WCCと深くつきあうやつがどんどんふくらんでいけばこのクラブはますます、人を深くひきつける魅力あるものとなるのではなかろうか。
2週間に延びたビルマの旅で、人と人があゆみよることの素晴らしさを強く感じた。私自身、これからも、ビルマを、欧米人を、クラブを、会社を、我が祖国日本を、そして我が人生を、悩みつつ、だんだん好きになっていきたいと思っている。
そのために、完全燃焼あるのみだ。
1986年2月22日ラングーンスウェダゴンパゴダにて。